
福祉の枠組みの外の世界
障がい者福祉事業所に勤めて半年余りの私が書くことではないのかもしれませんが、さらに半年後、あるいは1年後の自分が読み返したときにどう感じるのか…という今の私に見えている世界について書いてみようと思います。
お恥ずかしい話ですが、私は今の仕事に就くまで福祉業界について何も知りませんでしたし、知ろうとも思いませんでした。
特に障がい者福祉は過去の法制度の建付け上、社会から隔絶された入所施設から端を発した経緯から、家族や友人に障がいを抱える方がいない限りは触れることのない世界でもありました。
私の幼少期には、まだ義務教育機関に「特殊学級」と呼ばれるクラスがあり、同じ校舎で知的障がいなどの軽度から中度の障がいを抱える方と一緒に登下校することがありました。
今は特別支援学級という名称になっていますし、なにより障がいを抱える児童向けの特別支援学校という、障がいを抱える児童を擁する教育機関も確立されつつあります。
…あ、すでに本文を始めちゃっていますが、今回は仕事を通して感じたことについて書いていきます。
最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー
賢明な皆さまのことですから、半年前の私と違って障がいを抱える方が職に就くことなく生活できている理由を明確にご存知ですよね?
……。
正解は税金です。
私たちが納めている税金の一部は、障がいを抱える方の生活を支えるために使われています。
この事実をどのように感じるかは人それぞれだと思いますが、多くの障がいを抱える方々は、この事実に憂いているか、事実を理解できていないかのどちらかであって、決して税金の上にあぐらをかいているワケではありません。
「事実を理解できていない」という部分を少し補足しますが、「知的障がい者」とは専門的な用語を完全に取り払い、誤解を恐れずに申し上げるなら、知能指数(IQ)が75~65を下回る水準の方を指します。
障がい者福祉には「9歳の壁」という言葉があり、小学校3年生レベルの学力が一つのボーダーとされています。
現在は、何度となく法制度を整えてきたことで「精神障がい」という区分がありますが、それ以前には、いわゆる「発達障がい」も「知的障がい」として捉えられてきました。
ですから、類似する特性であっても、療育手帳と精神保健福祉手帳という異なる障がい者手帳を持っている方がいるのはそのためです。
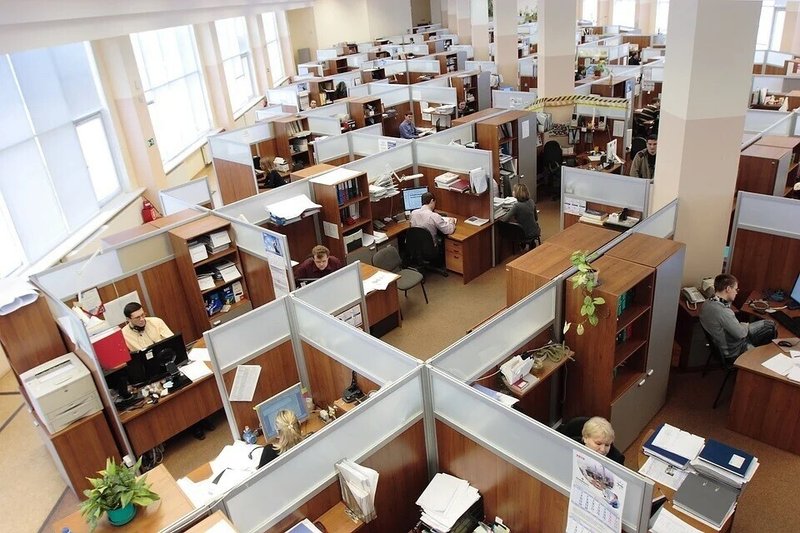
ーーーーーーーーーー
私たちのように、社会で働くことが当たり前だと思っていると、働くことで得ている恩恵を忘れてしまいがちです。
…お給料のことではありませんよ?
私もよく記事にするテーマですが、人間は他人に認められたい生き物です。
他人に褒められたい・認められたいという欲求を得るためのもっとも効果的な行為は、社会に貢献することです。
私たちは、叱られたり注意を受けることばかりに意識が向いてしまいますが、他人に認められることも、実は働かなければ、なかなか得ることは出来ません。
障がいを抱える方すべてが、社会に守られるだけの存在ではありません。
彼らにも自我があり、誰かのために生き、喜んでもらいたいという欲求があるのです。
昨今、障がい者の社会参加を推進する動きが加速しています。
急に現実的な話になりますが、税金で支援している障がい者の一部でも企業に就労することができるのなら、「税金で暮らす人」から「税金を納める人」となり、立派な経済の担い手として活躍することが出来ます。
そのお手伝いをするのが、障がい者福祉の中でも「就労支援」と呼ばれるジャンルで働いている私たちの使命です。

ーーーーーーーーーー
一方で、障がいを抱える方を支える機関というのは、国や自治体などが統括しています。
つまり、こちらの運営も税金だということです。
私も働いてみて気づいたのですが、一般的な企業に比べ、税金で賄っている以上、多くの制度やルールが存在します。
分かりやすい例では、むやみやたらな残業など以ての外です。
税金ですから。
この制度やルールは納税をしている国民に示すものですが、支援対象は障がい者です。
ここにねじれが生じます。
例えば、障がいを抱える方が夜勤者の場合、何らかのトラブルが生じ、企業が行政機関に支援を要求した場合、どうなるのでしょうか?
一人の夜勤者のために、行政は動きません。
しかし、企業は一人の従業員のために損失を被ることになるのです。
…この図式を考えれば、企業が障がい者を雇用するには、あまりにリスクが大きすぎると言わざるを得ないのだと思います。

ーーーーーーーーーー
ではどうするのか?
行政機関の支援に準ずる働きを民間で請け負う企業があればよい、というのが、現在の私が働いている事業となります。
行政機関の支援は、税金で賄われているので基本的には費用が発生しませんが、その分、企業が求めるスピード感での解決は難しいケースがあります。
他にも、地域によっては個別で多くの課題を抱えたまま、身動きの取れない企業も多くあります。
そもそも、急成長した企業に、ある日突然「障がい者法定雇用率」というものがのしかかり、一定規模以上の企業には障がい者を法定雇用率以上受け入れなければならないという義務があります。
福祉に関する情報がない状態で、障がいを抱える方を雇い入れることは、企業だけでなく障がいを抱える方にとってもリスクが大きすぎます。
あまり適した例ではありませんが、ある日突然、言葉も通じない外国で働くことになった場合、あなたは何のストレスもなくその職場に定着することが出来ますか?

ーーーーーーーーーー
ここまでいろいろ書いてきましたが、どんなことにも限界はあります。
一つのやり方がすべてをカバーすることなど、どの分野でもあり得ないことでしょう。
だからこそ、違う道を進む必要があり、そこを事業機会と捉えることがビジネスなのだと思うのです。
福祉に従事する方の中には、福祉とビジネスを繋げることを由としない方もいます。
しかし、理念やマインドにしっかりとした福祉の精神を灯すことで、利益追求ではなく、社会貢献や地域貢献に特化したビジネスが根付くでしょうし、そんな企業を目指したいと思います。
かなり中途半端になってしまいましたが、今の私に書けることはこのくらいだと思います。
ーーーーーーーーーー
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の投稿は以上です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
