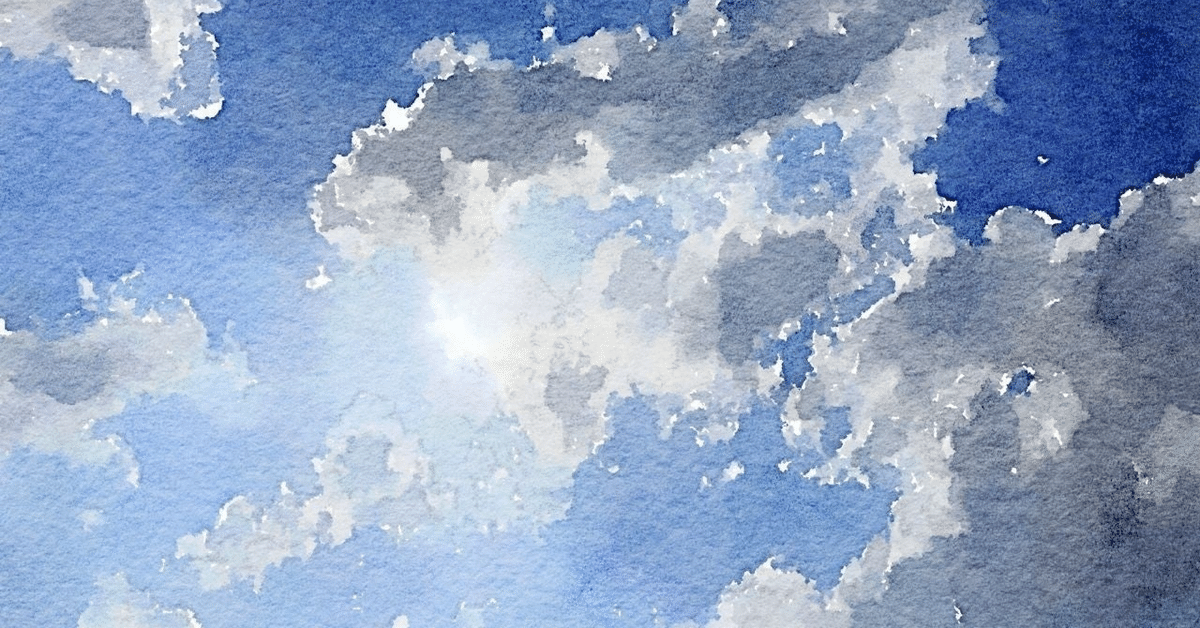
[ちょっとしたエッセイ] 忘れられない空
気がつけば、当然のように12月も半ばが過ぎた。終わりのないように思えた仕事も、途中であっても時が待たず、終わらせるしか選択肢がなくなり、そんな中でも気持ちだけは年末モードになる。そして、あらゆることが年末という言葉に浄化あるいは免罪化されているように見える。すると、それを目的とする勢力も笑顔で現れ、会社の中がカオスと化す。
まあ、そんないつもの年の瀬の風物詩に呆れ果てながら、会社の屋上へ出て、晴れ渡る冬の空を眺めていると、ふと向こうの方に飛行機雲がひと筋浮かんでいた。
手に持っていたスマホで、その雲をパシャっと撮ってみたものの、目で見るより薄くて細くて、結局なんなんだかわからなかった。地平線の方へ目をやると、富士山が予想よりも近く大きく見えて、これも写真に収めてみたが、結局写真の中の富士は、その存在感が8割くらい失われていた。
僕の祖父は、写真が好きな人だった。写真が好きとは言ったものの、こだわりなんかはゼロで、林家のパーのごとく片手に持っては、さっとシャッターを切るような人で、カメラも近所のカメラ屋で買った、安いキャノンのカメラだった。10円玉が何枚も入るなつかしいフィルムケース。フィルムを不器用ながらもていねいにカメラにセットする姿を今でも覚えている。
当然、そんな写真の撮り方なので、アルバムに残せるような写真は1つのフィルム24枚中2〜3枚。あとは見切れていたり、ブレた何方かの残像だけが写るので、おおむね処分された。それでも、多少のブレがありつつも顔や風景などが視認できる、残された写真がアルバムに収まっている。そんな適当写真家のアルバムの冊数から思うに、いったいいくらくらい現象にお金をかけていたのか、想像するだけでおそろしい。
そんなアルバムをパラパラとめくるたび、なぜか空の写真が差し込まれていた。その写真は建物などはまったく写っておらず、ただ空の写真だった。しかも青空ばかり。時折、雲のかたまりが静かに漂っている。写真を抜き出してみると、裏面に日付と、誰とどこにいたかが記されていた。
昭和51年 お母さんと上海
昭和62年 〇〇と桜田門
平成2年 〇〇入学式
こんな感じの簡素なメモだ。でもそれらの青い写真は、どれも空の写真だけで、それがどこなのか判断はできない。メモがあったところで、本当にその場所かもわかるはずはない。けれども、祖父は、その空の写真を意図的に残していたのだ。それに、ブレもせずちゃんと撮影している。
僕がそんな祖父の数ある空写真の中で、唯一記憶にある1枚があった。中学の入学式の日のものだ。寄宿舎住まいとなる僕、家族にとって不安のある日でもあった。そんな日の1枚だった。後にも先にも、これほど記憶に残る別れはない。
「がんばるんだよ」
祖父はそう言ったと記憶している。生真面目で結構堅物ではあったけど、笑顔が多かった祖父。そんな祖父でも、この日だけは少し心配そうな顔をしていた。
その日の空なのだ。鳥は大空をかけ、雲はゆるやかに流れていく。その春の日。記憶の視界が広がった。
「なんか、古い写真見つけたんだけど〜」
そう僕のデスクの横の人が言った。たぶん30年くらい前の写真だろうか。誰も決めていないし、誰も頼んでもいない。でも、みんな仕事の合間合間に、自分の縄張りの片づけをしている。写真は、過去の記録だ。そしてそこには撮った人のかすかな記憶や思いが残像している。
「〇〇さん、めっちゃ若くてかわいかったんですね」
そう僕が言うと、
「君さ、もう少し言い方あるんじゃないの?」
「今と全然変わらないっす」
「でしょ? ああ、なつかしい」
写真があると、会話がはずみ、花が咲く。その時代の名残が鮮明に残っている。
年末モードの社内は、あらゆることが年末という言葉に、浄化され、あるいは免罪符を渡されたかのように、みんなの顔が少し晴れやかになっていく。僕は屋上に行き、冬の空を一望する。雲は風に押されるようにゆるやかに流れ、頬を刺す風は、冬のそれである。
まもなく終わる2022年に、さらりと想いに耽ってみた。そして、空の写真を1枚。スマホにカメラロールに残る空の写真たち。どれもまったくもって感慨深くも、思い出深くもないのだが、なんとなく消せずに、同じようなものが並んでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
