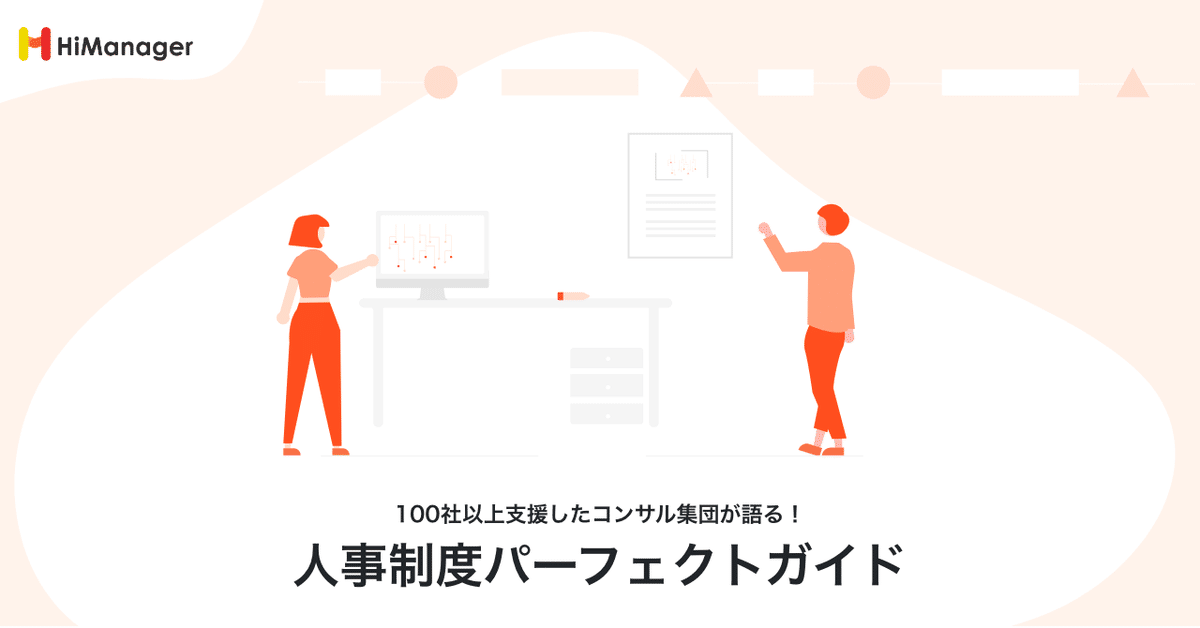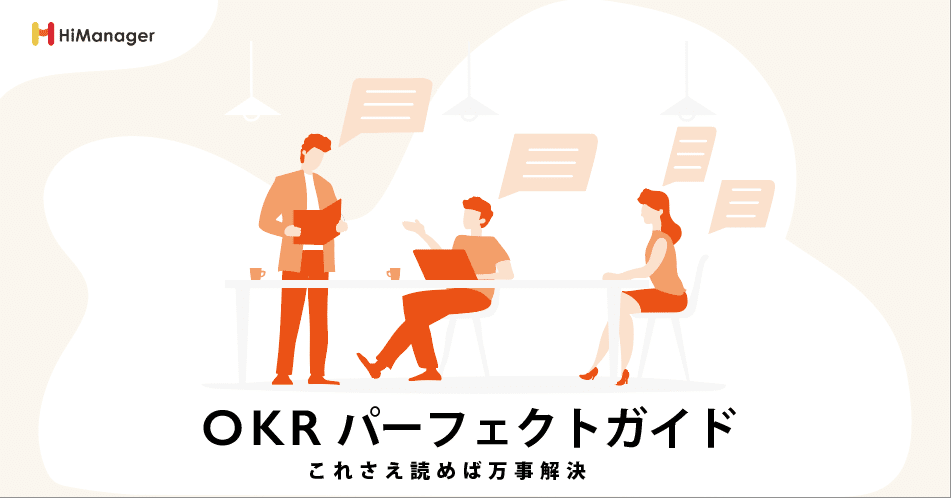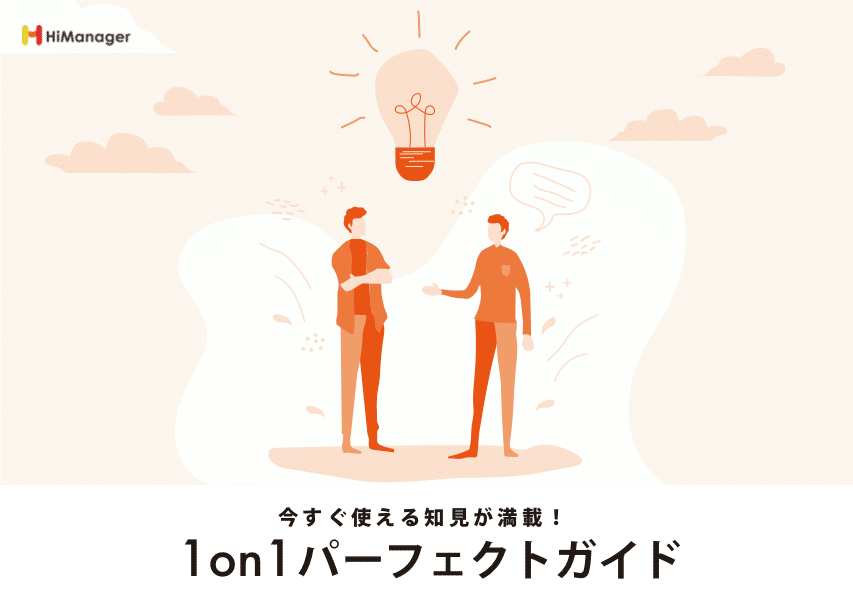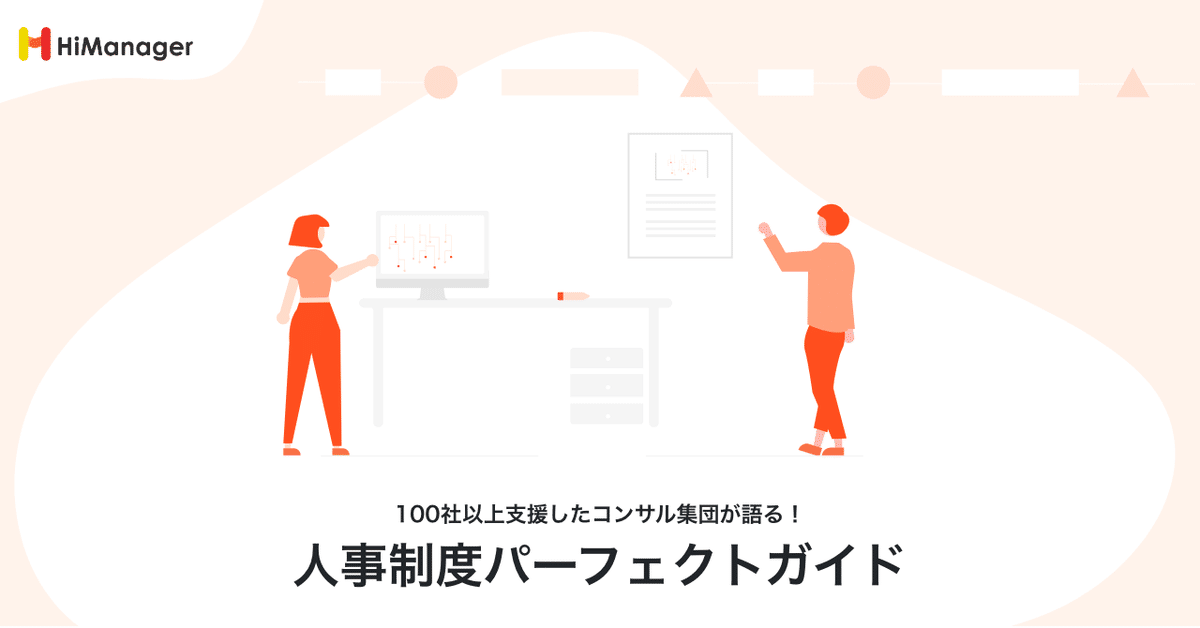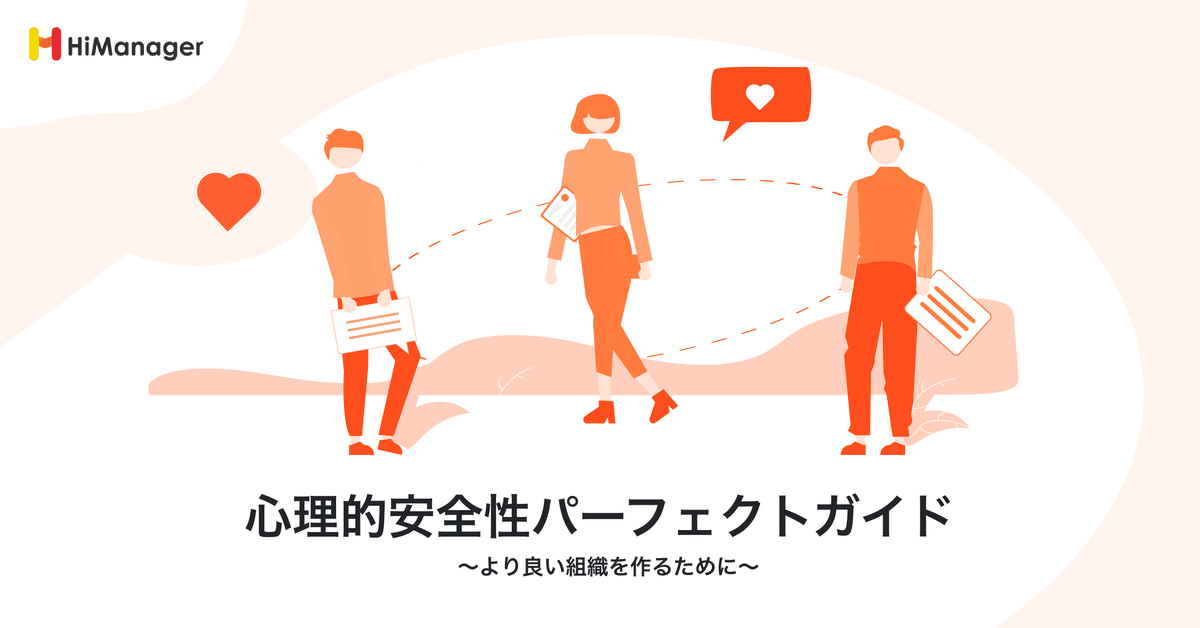【必読1万字】これさえ読めば、明日からパフォーマンス・マネジメントの実現ができる。パフォーマンス・マネジメントパーフェクトガイド。
ハイマネージャー株式会社CEOの森です。
OKRや1on1、リアルタイムフィードバック、人事評価等などを実現することのできるSaasを提供していますが、そんな中でも特に「パフォーマンス・マネジメント」に関するご相談は多くいただき、実際にここ数年で導入された企業も増えております。
一方で、パフォーマンス・マネジメントについてはまだまだ認知が広がっていないことや、基礎知識はあれど実践まで落とし込むことが難しいという実態があります。
そこで今回は、パフォーマンス・マネジメントの導入を100社以上支援してきた私たちハイマネージャー株式会社だからこそわかる、導入・推進をしていきたい方向けの、パフォーマンス・マネジメントパーフェクトガイドを作成しました。
これさえ読めば、パフォーマンス・マネジメントに関しては一通り理解できるような構成になっています。
少し長いですが、ぜひ最後まで目を通して頂き、パフォーマンス・マネジメントを導入する際の参考になりますと幸いです。
パフォーマンス・マネジメントの理解を深めたい方はこちら
パフォーマンス・マネジメントの基礎知識から、「実践」するために必要な情報を全てまとめた資料です。
以下のリンクからダウンロードください!
1.パフォーマンス・マネジメントとは

パフォーマンス・マネジメントとは、従業員一人一人の目標達成に向け適切な「行動」を考え、その結果に対して定期的な評価やフィードバックを行う、リアルタイムフィードバックを基にした、アジャイル型のマネジメント手法のことです。
パフォーマンス・マネジメントは、従来の年間評価を軸としたPDCAの少ないマネジメントとは異なり、リアルタイムで細かくフィードバックを行い、これにより従業員の「生産性向上」「エンゲージメント向上」を実現します。
また、後ほど細かく後述していきますが、パフォーマンス・マネジメントの構成要素としては「OKR」「1on1」「フィードバック」「称賛」「人事評価」などがあり、中でも「1on1」「フィードバック」「称賛」についてはリアルタイムで行っていきます。
パフォーマンス・マネジメントの必要性が高まってきている理由として、現在多くの企業で導入されている「MBO(目標管理制度)」では、変化スピードが早い現代のビジネス市場においては対応が難しくなってきていることが挙げられます。
MBOは、半年もしくは1年に1回評価をするのが一般的な流れであり、これでは現代のビジネス市場には追いついていけなくなってしまうのです。
パフォーマンス・マネジメントは、より現代に適したマネジメント手法と言えるでしょう。
2.近年のパフォーマンス・マネジメントの状況

パフォーマンス・マネジメントは、昨今特に注目されておりますが、
その背景には、現在多くの企業で導入されている「MBO(目標管理制度)」では、
① 変化スピードが早い現代のビジネス市場において対応が難しくなってきていること。
② ビジネスでの主力である、若手世代・ミレニアル世代に適していないこと。
が理由に挙げられます。
特に②については、若手世代・ミレニアル世代は、従業員エンゲージメントを高めるのに
以下の4つの価値を満たす必要があると言われています。
そんな中、パフォーマンス・マネジメントでは以下の通り、それぞれ求める価値をしっかり提供することができるのです。
以上の通り、若手世代・ミレニアル世代に、より適したマネジメント手法として
近年パフォーマンス・マネジメントが普及し始めているのです。
3.パフォーマンス・マネジメントでやるべきこと
ここからは、パフォーマンス・マネジメントで行うべきことを、「OKR」「1on1」「フィードバック」「称賛」「人事評価」の要素別に解説していきます。
3-1.やるべきこと①|OKR
3-1-1. OKRとは
OKRとは、英語でいう「Objectives and Key Results」の頭文字を取った略称であり、目標 管理指標の一つです。
Objectives and Key Resultsは、日本語では「目標と主要な結果」と いう意味になります。
OKR=
1. 定性的な目標を設定し
2. 定性目標を達成するために必要な定量目標を設定
以上の2つの要素からなる目標設定手法だと考えると理解しやすいです。
OKRは、Objectives(目標)1つに対して、Key Results(主要な結果)を3つ前後設定します。
また、Objectives(目標)は定性的なもの、Key Results(主要な結果)は定量的なものに設定します。

3-1-2. OKRの実施方法
<初期導入のポイント>
・導入6週間前|社員の意見を参考にしつつ、自社のOとKRを特定する
⇨匿名のアンケートを行うか、各部門のマネージャーが社員の意見を吸い上げて経営層に提出するといった方法が推奨されます。
・導入5週間前|OKRを可視化し、追跡するためのツールを決める
⇨もちろんツールを使わずにOKRを実行することもできますが、現在のOKRの進捗や過去の振り返りを全社的に行うのは、ツールなしでは一苦労です。
・導入4週間前|各部署のマネージャーと協力して、部署単位での目標を作成する
⇨会社のKRと、部署・部門のOが紐づくように作成するのがポイントです。
・導入3週間前|OKRを会社全体に周知する
⇨会社のKRと、部署・部門のOが紐づくように作成するのがポイントです。
・導入2週間前|各マネージャーが社員と話し合い、各社員のOKRを作成する
⇨OKRは独特な概念のため、違和感を覚える社員も多いかもしれません。各種資料を準備し、丁寧に説明する機会を設けましょう。
・導入1週間前|一旦、全社でOKRを組んでみて、適宜修正を加える
⇨ここで一度、全社のOKRをまとめます。違和感があった場合には、適宜修正を加え、全体 を整えていきます。
・導入1週間前|全社会議で経営層がOKRについて再度周知する
⇨最後にもう一度、全社会議で経営層がOKRについて周知します。
<導入後のポイント>
・ポイント①|毎週チェックインを行い、必要に応じてOKRを修正する
⇨チェックインとは、毎週のはじめに行う小さな報告会のようなものです。チェックインでは、各社員が今週やることをOKRに沿って発表していきます。
・ポイント②|毎週ウィンセッションを行い、達成したことを評価
⇨ウィンセッションとは、今週達成できたことを各社員がOKRに沿って発表しあう報告会のことです。チェックインとウィンセッションを毎週行っていくことで、各社員にOKRへの意識づけができ、生産性の向上へと繋がります。
3-1-3. OKRについてさらに知りたい方はこちら
OKRについてさらに知りたい方は、詳細に解説しているこちらの資料をご覧ください。
3-2.やるべきこと②|1on1
3-2-1. 1on1とは

1on1とは、マネージャーと部下が定期的に行う、1対1のミーティングのことです。1on1は、組織としての結果に焦点が当たる一般的な面談とは異なり、主に部下のための時間として用いられます。
1on1は当初、画期的なマネジメント手法としてアメリカのシリコンバレーを中心に話題となりました。日本でも、ヤフーが導入したことをきっかけに普及が進み、現在では全国各地の企業が導入を進めています。
1on1の5つの特徴と、通常の面談との比較は以下の通りです。
3-2-2. 1on1の実施方法
<1on1における2つのフェーズ>
フェーズ①|部下との信頼関係の構築
⇨話す内容:「相互理解」「体調管理」「モチベーションUP」
⇨1on1で最も大事だといえるのが、部下との信頼関係の構築です。
フェーズ②|部下の課題克服、キャリア支援
⇨話す内容:「課題改善」「目標設定・評価」「戦略/方針の伝達」「キャリア支援」
⇨部下との信頼関係が構築できてきたなと感じたら、いよいよ課題克服とキャリア支援に入ります。
<1on1におけるコミュニケーションの原則>
原則①|傾聴
傾聴を行うことによって、部下への理解が深まり、部下との人間関係の構築につながります。また、部下の自己肯定感の向上や思考の整理になるなど、部下側にもメリットがあります。傾聴を行うことによって、安心感・信頼感を醸成することができるのです。
原則②|質問
質問には大きく分けて2つの種類があります。相手が自由に回答できるような質問を行うオープンクエスチョンと、「はい」か「いいえ」で回答できるような質問を行うクローズドクエスチョンです。このうち、1on1ではオープンクエスチョンを多用すると効果的です。部下が自由に回答できるため、部下の幅広い考えを引き出すことができます。
原則③|承認
部下が心を開いてくれるようにするためには、まずはこちらから部下のことを承認することが重要となってきます。部下を承認していることを示すためには、肯定的な相槌を行うと効果的です。まずは部下の考えを受け入れることで、部下は「このマネージャーは自分のことを認めてくれている」と感じるようになります。
3-2-3. 1on1についてさらに知りたい方はこちら
1on1についてさらに知りたい方は、詳細に解説しているこちらの資料をご覧ください。
3-3.やるべきこと③|フィードバック
3-3-1. フィードバックとは

そもそもフィードバックとはどういった意味なのでしょうか?
フィードバックは様々なビジネスシーンで活用されている普遍的な手法ですが、曖昧に使用されることが多い概念でもあります。
そこで、まず最初にハイマネージャー社での定義をお伝えしておきます。
フィードバックとは、目標達成に向けて過去の活動や業務に対する評価や提案を行い、その評価を次回以降の活動や業務に反映させるための管理手法です。
経営層からマネージャーに対して、あるいはマネージャーから部下に対して行われることが多いです。
業務に対する評価に加えて、フィードバックを通じて社員の会社における役割を伝えたり、会社の方針を伝達する場合もあります。
フィードバックは英語でfeedback(FB)と表記し、直訳では「帰還」と訳されます。
少し耳慣れない言葉が出てきましたが、これはフィードバックがもともと、制御工学の分野で使用される用語であったためです。
制御工学におけるフィードバックとは、入力と出力があるシステムで、出力された結果を入力側に戻すことによって、出力される結果を制御するという意味になります。
そこから転じて、ビジネスシーンにおいても活用されるようになっていきました。
3-3-2. フィードバックの実施方法

フィードバックは、社員のタイプに応じて内容を使い分けると、さらに効果的なものになり ます。
今回は、社員のタイプの分類法としてDiSC理論をご紹介し、それぞれのタイプに応じたフィードバックについて見ていきます。
DiSC理論とは、人間の行動パターンを4つに分類したものです。
直感的で決断の早い主導型(Dominance)、楽観的で社交的な感化型(Influence)、思いやりがあり協力的な安定型(Steadiness)、緻密で正確な慎重型(Compliance)の4つのタイプに分類されます。
DiSC理論は一種のコミュニケーションツールであり、相手のタイプを予め知っておくことで、良好なコミュニケーションを取ることができます。
もちろん、「あの人は主導型だから仕方ない」といったように、タイプによって相手を決めつけすぎるのは危険な考え方ですが、適度なコミュニケーションツールとして活用するには有効な理論です。
参考:https://www.hrd-inc.co.jp/whatsdisc/
この章では、DiSC理論のタイプ別に応じた、フィードバックの方法をご紹介していきます。
<主導型(Dominance)に対するフィードバック>
1つ目のタイプは、主導型です。このタイプは、意思が強く、行動的でチャレンジ精神に富む、細かく指示されることを嫌う、プレッシャーに打ち勝つ強いメンタルを持つといった特徴があります。起業家やリーダーに多いタイプです。対人関係においては、行動的なため挑戦を受けて立つ、困難に立ち向かおうと権限を求める、指示を受けることを嫌うため自分で仕切る、といった傾向があります。
主導型に対するフィードバックのポイントは、内省や気づきを促す問いを与え、最終的に自分で納得させることです。主導型は指示を嫌うため、とにかく自分で考えさせる方向に持っていくことが重要となります。
<感化型(Influence)に対するフィードバック>
2つ目のタイプは、感化型です。感化型は、明るく社交的な性格で人と接するのを好み、感情表現が豊かで物事を肯定的に捉えるが、粘り強さや緻密性には欠けるという特徴がありま す。このタイプは営業マンに多いとされています。対人関係においては、自分から積極的に人と関わろうとする、明るいムードメーカー的存在である、自ら援助を申し立てて人を喜ばせるといった傾向があります。
感化型に対するフィードバックのポイントは、より積極的に取り組めるように、前向きな言葉を中心にすることです。積極的であるという感化型の特性を、より伸ばすようにフィードバックしていくと効果的です。
<安定型(Steadiness)に対するフィードバック>
3つ目のタイプは、安定型です。安定型は、コツコツと努力する粘り強さがある、協調性があり協力的である、安定した状況を好み変化を嫌うという特徴があります。事務職やカスタマーサクセスにこのタイプが多いとされています。対人関係においては、相手からの感謝や承認を重視する、言われたことを言われた通りに実行する、相手の立場に立って話しを聞くことが得意な傾向にあります。
安定型に対するフィードバックのポイントは、寄り添う姿勢を意識し、少しずつ改善できるように行うことです。着実性が安定型の強みなので、そこを活かせるようなフィードバックにしましょう。
<慎重型(Compliance)に対するフィードバック>
最後のタイプは慎重型です。慎重型は、データや数値を駆使して合理性を求める、長短を検討した上で慎重に結論を出す、質問が多く納得しないと動かないという特徴があります。アクセス解析の担当者やプログラマーに多いタイプとされています。対人関係においては、妥協や人を介して人との衝突を回避する、状況に対して一貫性のあるアプローチを取る、賛成反対両者の意見を聞き結論を出す、といった傾向があります。
慎重型に対するフィードバックは、適切な根拠を示し、より納得感のあるものにすることが重要です。客観的なデータで示すことも一つの作戦だといえます。
3-3-3. フィードバックについてさらに知りたい方はこちら
フィードバックについてさらに知りたい方は、詳細に解説しているこちらの資料をご覧ください。
3-4.やるべきこと④|称賛
3-4-1. 称賛とは

称賛とは、各社員の努力や実績を認識し、讃えることです。
一般に、社員の満足度を高める方法は、金銭的報酬と非金銭的報酬に分かれます。
金銭的報 酬はとてもわかりやすい方法ではありますが、社員が得られる満足感は一時的なものに留まります。
一方、評価や承認、称賛などの非金銭的報酬は、一見効果は薄いように感じますが、正確に実施することによって社員は継続的な満足感を得られることがわかっています。
社員に対して称賛を行うことによって、会社は2つのメリットを得ることができます。
1つ目のメリットは、社員のエンゲージメントの向上です。
特に昨今においては、転職市場 の活況も相まって各社で離職率が上昇する傾向にあり、企業は社員をいかに定着させるか、 頭を悩ませています。
称賛を受けた社員は満足度が上昇して会社への帰属意識が高まるた め、社員の離職率低下の手段の一つとしても、称賛は役立ちます。
2つ目のメリットは、社員のパフォーマンスの最大化です。称賛によって、社員は継続的な 満足感を得ることができます。
その満足感が日常業務への意欲の向上をもたらし、社員のパ フォーマンスを加速させます。
3-4-2. 称賛の実施方法
<称賛を行うと良い5つのタイミング>
・タイミング①|社員が採用されたとき、入社したとき
社員が採用されたときや入社したときは、称賛にうってつけのタイミングです。
例)入社してくれてありがとう。チームの即戦力になってくれることを期待しています。
・タイミング②|社員が昇進したとき
社員が昇進したときも、称賛のチャンスです。まずは昇進を祝い、今後も積極的にサポート していくことを伝えましょう。
例)昇進おめでとう。責任も生じて大変だと思うけど、わからないことがあったらすぐに助けるから遠慮なく聞いてね。共に頑張りましょう。
・タイミング③|社員が新しいことに挑戦しているとき
社員が新しいことに挑戦しているときは、それ自体が会社にとっても、本人にとっても喜ば しいことです。
例)新しいプロジェクトへの挑戦は、とても素晴らしいことだよ。どんどん積極的にチャレンジしていこう。辛くなったら相談に乗るから、頑張ってね。
・タイミング④|社員が関わっているプロジェクトの終了後
大きなプロジェクトが終了した ときは、その反動で社員に大きなストレスがかかる傾向にあります。
例)お疲れ様。あなたのおかげで、今回のプロジェクトはとてもうまくいったよ。疲れているだろうから、まずはゆっくり休んでね。
・タイミング⑤|誕生日や入社後の節目など、記念日のとき
記念日は、会社全体で祝ってあげましょう。誕生日や入社してちょうど1年の日などが適し ています
例)誕生日おめでとう!今年も〇〇さんにとってよい1年になるよう、祈っています。これからも一緒に頑張ろう。
3-4-3. 称賛についてさらに知りたい方はこちら
称賛についてさらに知りたい方は、詳細に解説しているこちらの資料をご覧ください。
3-5.やるべきこと⑤|人事評価
3-5-1. 人事評価とは

人事評価・制度とは、基幹となる等級制度、評価制度、等級制度を活用しながら、従業員の能力や会社への貢献度について評価を行い、適切な処遇を決定する仕組みです。
人事制度の導入目的は様々ありますが、企業として業績(成果)向上に最適なマネジメント を行うこと=経営戦略を実行すること、社員がモチベーション・エンゲージメント高く働け るようにすることの2点が重要だと考えています。
特にスタートアップの方は人事制度をいつ作り始めるか悩まれると思いますが、これまで 様々な企業の人事制度設計・運用に携わってきた中で、20人以上の規模になったタイミン グが1つの目安だと考えています。
20人を超え始めると、組織構造が少なくとも3階層になり自分と全く関わらない人 が出てきたり、社長・経営陣が直接関与が少ない従業員が出てき始めるため、上司に評価を 移譲する必要が出てきます。
そのため、これまで阿吽で通じていた企業のコアな価値観も少しずつ薄れてくるタイミングとなるため、企業理念や価値観を浸透させる意味でも人事制度が必要になってきます。
3-5-2. 人事評価の実施方法

人事評価・制度設計に取り掛かろうとする際、具体的に何から考え始め、設計していけばよいのかイメージが沸かない方も多いかと思いますが、人事制度設計・導入の一般的な段取りは上記の通りです。
詳細は以下の通り、ステップごとに解説していきます。
<人事評価・制度作成のプロセス>
ステップ①②|目指す姿 (MVV) の設計と人事ポリシーの作成
人事制度の目的を果たすためには、以下図のように人事制度は単発のものではなく、企業の目指す姿(MVV)から経営戦略など全て繋がりを持って設計する必要があります。
人事制度ポリシー(人事制度)はとても重要で、会社の目指す姿を踏まえて人事制度は何を目的としていくかを明確に定義しておく必要があります。
人事制度ポリシーが明確だと、後段の等級・評価・報酬を設計する上でも人事制度ポリシーがベースポイント(立ち戻れる場所)となり、メッセージをぶらさずに設計することができます。
ステップ③|等級制度作成
等級制度は人事制度の骨格となり、等級により後段の評価・報酬制度も大きく変わります。また、等級が設定されると社員の方が会社の中でどのようなキャリアパスを描けるかが決まるため、エンゲージメントにも大きく影響する要素です。例えば上記のような観点で等級制度を選択します。
ステップ④|評価制度作成
評価制度を作成する上では、人事制度ポリシーや等級制度の内容を踏まえて、適切な評価項目を選択していくことが重要です。例えば、上記などが評価で使われる観点となります。評価制度・目標管理制度を設計する上では、評価が処遇の決定のためだけのものにならないようにすることが重要です。
ステップ⑤|報酬制度作成
報酬制度は従業員にとっても関心が高く、メッセージが伝わりやすい部分でもあります。報酬と聞くと基本給・手当・賞与といったお金をイメージしますが、トータルリワードという考えがあり実は金銭報酬だけでなく、表彰ややりがいのある仕事の提供といった”非金銭報酬”もあります。
ステップ⑥|評価シミュレーション実施
評価シミュレーションでは、設計した等級・評価・報酬を現在の従業員に当てはめて仮評価や報酬決定を行うことを指します。事前にどのような動きになるかを想定しておくことで、検討漏れや個別論点となる部分をあらかじめ見つけておきます。
ステップ⑦|人事制度説明・人事制度運用開始
人事制度の設計ができたら、いよいよ従業員の方に説明が必要です。単発的な説明だけでなく、従業員の方がいつでも見返せるように、従業員説明資料やマニュアルを作成し、公開しておきましょう。
特に評価者となる管理職層に対しては評価の目線がぶれないよう、評価者研修やデモを行うことも効果的でしょう。管理職が理解しないと人事制度が浸透しなくなってしまうため、丁寧に説明・サポートしていくことが必要です。
また、前述の通りスタートアップにおいては状況変化に応じてチューニングが必要になってくることが多いため、導入後も定期的にフィードバックを受けてブラッシュアップすることを心がけましょう。
3-5-3. 人事評価についてさらに知りたい方はこちら
人事評価についてさらに知りたい方は、詳細に解説しているこちらの資料をご覧ください。
最後に
いかがだったでしょうか。
パフォーマンス・マネジメントのパーフェクトガイドはこれにて以上となります。
パフォーマンス・マネジメントを始めとして、OKRや1on1・人事制度などに関するご相談があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!
ハイマネージャーの提供する、6つのお役立ち資料はこちら
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。