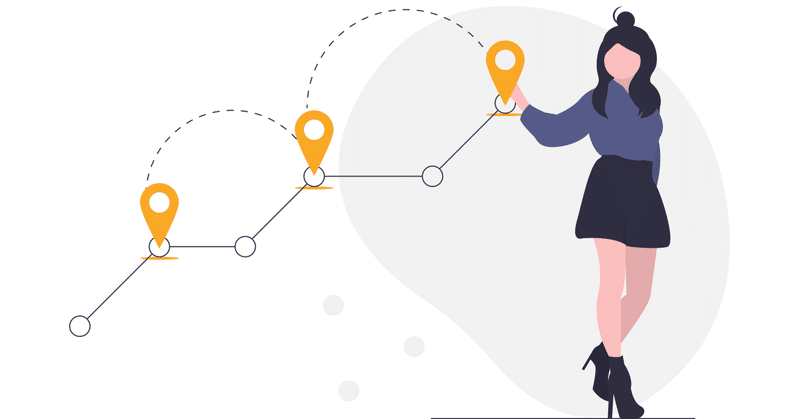
パフォーマンスマネジメントの歴史的変遷
いつの時代もマネージャーや経営陣の悩みとして挙がるのが、「メンバーのパフォーマンスをいかに向上させるか」ということ。
「なんとなく従来のやり方を続けているが、メンバーのパフォーマンスが安定しない」、「いまいちメンバーの考えていることが把握できない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで昨今注目されているのが、「パフォーマンスマネジメント」。
実際にパフォーマンスマネジメントの領域では、日夜研究が進んでおり、これまでにも様々な手法や概念が生まれ、時代と共に変化を遂げてきました。
今回はパフォーマンスマネジメントのトレンドと歴史的な変遷、その背景をまとめました。
自社のパフォーマンス管理に悩まれている方の参考になれば幸いです。
1. パフォーマンスマネジメントとは
「パフォーマンスマネジメント(Performance Management)」とは、従業員一人一人の目標達成に向け適切な「行動」を考え、その結果に対して定期的な「フィードバック」を行い、「パフォーマンス向上」や「成果」に繋がる行動を身に付けてもらうマネジメント手法のことです。
パフォーマンスマネジメントは、従業員一人一人が主体的に行動し、成果を上げるということが根本的な目的になります。ここでは「自主的な行動」ということが重要であるため、プロセスに注目します。
あくまで管理職や人事部の方はサポート・コーチングをする役割であり、従業員には目標達成に向け主体的に行動していくという姿勢が求められます。
詳細を知りたい方は以下の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご覧ください。
2. パフォーマンスマネジメントとトレンド手法
昨今、パフォーマンスマネジメントが注目されてきた背景には、現在多くの企業で導入されている「MBO(Management By Objectives/目標管理制度)」では、変化スピードが早い現代のビジネス市場において対応が難しくなってきているということがあります。
そして、そんなパフォーマンスマネジメントを推進するうえでの手法としては、
・OKRによる目標管理
・1on1によるリアルタイムでのフィードバック
といったものが昨今のトレンドとして挙げられます。
元来、特に日本企業においては、職務遂行能力に基づいて等級を定め格付けし賃金管理を行う「職能資格制度」が人事制度の主流でした。この「職能資格制度」では成果だけでなく従業員個々のスキル、職務態度、行動を評価していました。
しかし日本経済が低迷する中で、日本企業はコストダウンに迫られ、人件費をかけずに業績を向上させることが求められるようになりました。
そこで、成果を出す従業員に高い報酬を支払うことで従業員が納得感を得やすくし生産性を高める成果主義に着目。
従業員の成果を評価するためのツールとして、MBOを運用することとなったことから現在のトレンドに繋がります。
3. 歴史から見るマネジメント手法の変遷
ここまでで、パフォーマンスマネジメントのトレンドについてまとめました。
それではここからは、具体的にどのような変遷を遂げて今日のパフォーマンスマネジメントに至るのかを見ていきましょう。
以下の表に大まかな変遷を記載しました。

表から、徐々に変化のスピードが早まっている様子が見て取れるかと思います。
この100年ほどで、マネジメント手法は大きな変化を遂げたことがわかりますが、その起源は第二次産業革命まで遡ります。

第二次産業革命による変化(1800-1900年代初頭)
第二次産業革命期には、新しい機械の発明により、生産速度が向上し、1890年から1958年の間に、アメリカでは労働時間当たりの製造業における生産高が約5倍になりました。
1800年代後半から1900年代前半にかけて確立され、急速な発展を支えた大量生産方式においては、より多くの従業員とマネージャーが必要になりました。
なぜなら、この時代に経営者が追い求めたことは、「徹底的な標準化」と「いかに労働を強制させるか」ということだったからです。
つまり、「仕事を誰にでもできるようにすること」と「誰でもいいから労働者の数を確保すること」がマネージャーに求められる仕事でもあったため、個人の能力を引き出すといった考え方はほとんどありませんでした。
ただし、やはり経営者側にとって都合の良い論理でしかなかったという背景もあり、1900年代初頭には、労働者による集団的権利を確保するための組合活動が盛んになりました。
また、劣悪な労働環境に起因する大規模な工場火災なども発生する中で、まず、「労働環境を整える」ことがパフォーマンスに直結するという認識がアメリカを中心に普及しました。
パフォーマンスマネジメントの始まり(1920年代)
1920年代に入り、徐々に個人のパフォーマンス向上と組織が果たす役割に焦点が当たり始めました。
その契機となったのが、アメリカ・Hawthorne Works社での実験です。
Hawthorne Works社はまず初めに、標準化が進んでおり、単純作業を行っている部門を2つのグループに分け、5分間の休憩や1日の労働時間の短縮を導入するなどの実験を行いました。
しかし、これらの実験ではパフォーマンスへの関係性が確認できなかったため、次に心理学者のイーロン・メイヨー氏を招聘しました。
イーロン・メイヨー氏は工場を訪れ、労働者に対してのインタビューを敢行することで、マネージャーのスタイルと従業員の士気や生産性との間に関連性があることを発見し、「個人がチームとなることで、自発的に協力するようになり、生産性の向上に寄与した」と結論づけたのです。

政府も巻き込んだ変化(1940-60年代)
メイヨー氏の研究結果は、1940年代から50年代にかけての職場の変化のきっかけとなり、マネージャーのあり方に変化をもたらしました。
マネージャーは「従業員に仕事を割り振る」役職というより、「従業員と親身に話をするカウンセラー」のような役職に近くなっていったのです。
加えて、1962年の連邦給与改革法により、政府が業績評価制度やインセンティブ制度を導入するなど大きな変化が生まれます。
これは、報酬を業績に連動させるという評価制度の最初の例となり、評価も主観的なものから、より具体的な指標を用いる手法に移行する契機になったとされています。
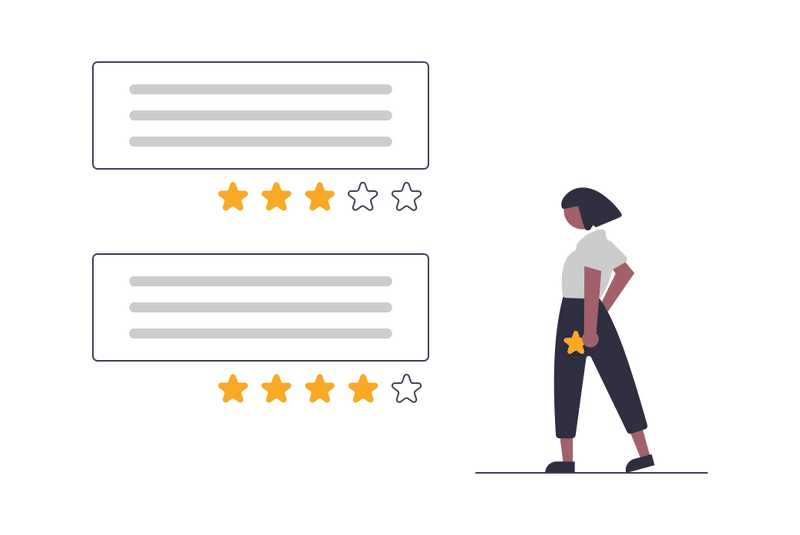
成果主義型評価手法の確立(1980-90年代)
まず1980年代に入ると、ヒューレット・パッカード社などが「MBO」を用い、業績向上に繋げました。
これまでは経営者が一方的にノルマを設定するような手法だったところが、経営者と社員が一緒になって目標を設定し、達成するという方向性への変化が生まれ始めたのです。
現代的なパフォーマンスマネジメントの興りと言えるでしょう。
そして、1980年代から1990年代にかけては、ゼネラル・エレクトリック社のCEOであった、ジャック・ウェルチ流の評価手法が一世を風靡しました。
彼は、毎年の業績評価に基づいて社員を評価・ランク付けする厳格なシステムを提唱しました。
社員は「スタック・ランキング」「ランク・アンド・ヤンク」と呼ばれるランキングシステムで評価され、A(上位20%)、B(中位70%)、C(下位10%)に分けられるのです。
そして何十年もの間、数値による順位付けが行われ、成績下位10%の社員は解雇されました。
ただし、これは経営者目線では合理的な手法であったため流行しましたが、マネージャーやメンバーを問わず、スタック・ランキングと年に一度のレビュー自体は不評だったようです。

旧的な評価制度の停滞(1990年代-2015年)
1990年代から2010年代にかけて、評価制度は一つの大きな局面を迎えます。この時期には、マネージャーやメンバーだけでなく、企業も旧的な評価手法を無駄だと考えるようになったのです。1992年には、自社の評価手法に満足している企業はわずか20%ほどとなりました。
そして2010年代に入ると、ソーシャルメディアの台頭もあり、個人が容易に評価を行える立場ともなったことで、トップダウンの画一的な評価制度がマッチしなくなり始めました。
実際にマイクロソフト社では、チームメンバーが協力し合うのではなく、互いに競争していることを見て、2013年にスタック・ランキング制度を廃止しました。
スタック・ランキングに代表される旧的な手法においては、革新的なアイデアがすぐに潰され、社員の評価が下がるようなものは隠されるという文化を生み出してしまったのです。
結果的には、リアルタイムで業績をトラッキングできるようなテクノロジーの普及もあり、このような形式的な業績管理は、徐々にその姿を消しつつあります。
移り変わりの激しいビジネス環境の中で、「年に1回のフィードバックだけでは明らかに不足している」という現状が露わになった時代とも言えるでしょう。
実際に2015年末までに、フォーチュン500社のうち少なくとも30社が評価制度を大幅に見直しました。
Googleの元執行役員 ラスズロ・ボック氏は、「ほとんどの組織で行われているパフォーマンス管理は、ルールベースの官僚的なプロセスになっており、実際にパフォーマンスを向上させるというよりは、それ自体が目的になっています」と述べています。
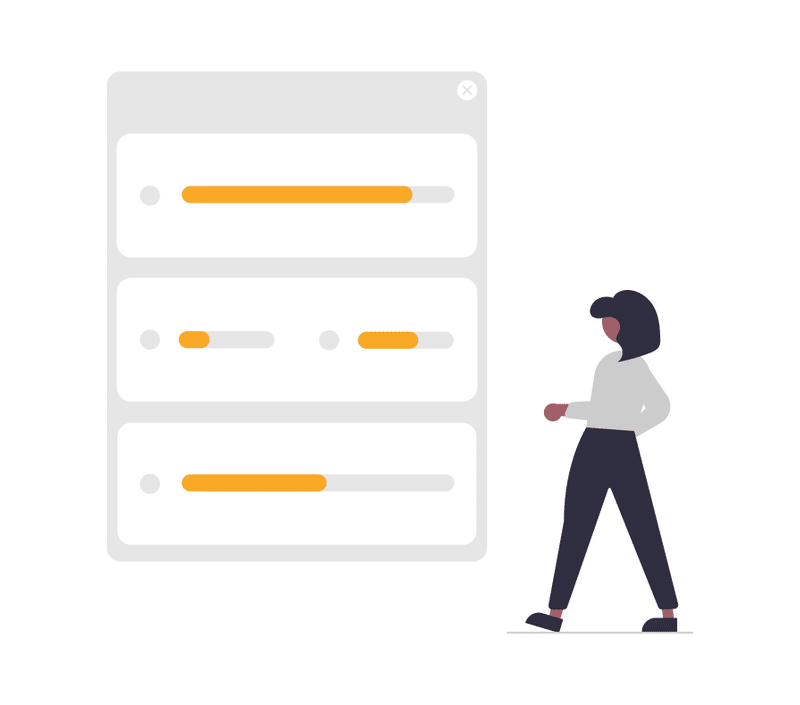
継続的パフォーマンスマネジメントの導入(2010年代〜現在)
実際にミレニアル世代は、親や教師などと即座にコミュニケーションを取れるようなデジタル環境で育ったため、より頻度の高いフィードバックを求めています。
例えば2012年、アドビ社は年1回のレビューから、少なくとも隔月に行われるチェックインに移行し、マネージャーと従業員の対話を促進しました。
TriNet社とWakefield Research社の調査によると、18~34歳のフルタイムワーカーの60%が、現在の業績評価には欠陥があると感じています。
さらに74%が、マネージャーや同僚が自分の業績をどのように考えているか、掴みかねていると回答しています。
つまり、業績評価制度を刷新していくことと、マネージャーとメンバーとのコミュニケーションを促進していくことはあらゆる企業に求められていると言えるでしょう。
最終的な目的としては、従業員がどのようにスキルを伸ばし、会社に利益をもたらすかについて明確な方向性を示し、従業員の利益となるように導くのです。
従業員が自ら目標を設定し、業績を向上させていくためのスキルセットを持たせられるようなマネジメントが重要です。
そんなマネジメントを既に成功させている企業の事例としてはフェイスブック社の事例が挙げられます。
フェイスブック社では、同僚に評価を書いてもらい、ほとんどの場合、上司だけでなく、同僚同士にもオープンに共有するようにしました。
マネージャーは、それらの評価を元に個人的な意見を最小限にしつつ、評価について話しあいます。そして、最終的な評価に偏りがないかどうかを分析チームが検証し、報酬に反映させるという手法を採用しています。
フェイスブック社の人事部長であるLori Goler氏は、「重要なことは成長を認め、それに報いる文化を構築すること」と述べています。
つまり、従業員の育成に焦点を当てるために、マネージャーは目標設定についてオープンに伝え、透明性を確保する必要があるということです。
優秀なマネージャーは、チームに対して明確な方向性を示し、明確なフィードバックを提供します。
昨今では単に年1回の業績評価だけでなく、継続的な管理システムを通じて行われるようになっています。
4. まとめ
いかがでしたでしょうか。
もしかするとあなたの会社での評価手法は100年ほど使われているものかもしれません。
一度自社の評価手法を見直してみるのも良いでしょう。
その上で、今ある評価手法も変遷とその背景を知れば、社内での導入が進めやすくなるのではないでしょうか。
ぜひ各社の事例やこれまでの歴史を参考に、自社にとって最適な手法を考えてもらうきっかけになれば幸いです。
OKRの理解を深めたい方はこちら
OKRの概念的な理解から具体的な手法までを網羅した全35ページのパーフェクトブックです。以下のリンクからダウンロードください!
・・・
ハイマネージャー
OKRや1on1、フィードバック、人事評価などハイブリッドワークのマネジメントに必要な機能が全て揃ったピープルマネジメント・プラットフォーム「HiManager」の提供、及びマネジメント・人事評価に関するコンサルティングを行っています。
マネジメントに活きる知見を発信しています。フォローをお待ちしています。


