
地方自治体のデジタル化は、若い人が町を変えていけるチャンス
4月から65歳以上、15歳以下の約2,000世帯にタブレットを配布する都農町。町民IDを蓄積、子どもたちも町にどんどん意見を言える双方向型のポータルサイト「都農ページ」もスタート。
若い人がデジタル化を活用、都農町で暮らし、働けるためのポイント3つ。①ICTリテラシー ②コミュニケーション力 ③事業企画力
1. デジタル・フレンドリーの先にあるもの
そもそもなんで都農町がデジタルするかといえば、人手不足解消のための効率化、高齢化加速による医療・交通の課題解決、有事対応のため。
ただ、個人的には「未来のチャンス創出」が本質だ思っています。10年後、20年後に人口は激減、高齢化と若者流出が同時加速、若者が地元に残って働くことは、いま以上に厳しくなることは容易に想像がつきます。
「都農町デジタル・フレンドリー」は、10代、20代の人たちが将来も都農町で食べていけるためのインフラづくりだと思っています。
2. 高齢者には、次世代のため協力してほしい
毎日、44自治会をまわっているんですが、デジタルにすぐシャッターをおろそうとする高齢者の方々に、タブレットを使うことが個人にとってどんなメリットがあって、慣れたら絶対できるから、とやや洗脳口調(笑)になりながら根気強く説明ナウ。(果てしない道w)

もうひとつ、高齢者がタブレットを使えるようになって、情報収集や交流が増え、健康で自立した生活を1日でも長く過ごせるようになれば、それが一番、子どもたちや孫たちのためになるって思いません?って話もトライ中。(もちろん、人と言葉を慎重に選びつつ)。
要は次世代のための協力だと思って、デジタル、おねがいします!
3. デジタル文明開化を目指して
町のデジタル化を活用して、若い人たちが新規事業や起業を実現、町に残ったり、帰ってこれるようになることがスーパー理想形です。
理想論で終わらせないよう、先週から僕らのチームの20代メンバーが、町の若い人たちに声をかけ、自主的な会合をはじめました。
これまでに累計30人近い、若い人たちが夜な夜な、新しくできて開業をまつ「文明|BUNMEI」に集まり、まさに文明開化前夜。

ひとつの趣旨は、僕らと一緒に、孫世代として高齢者にタブレットや都農ページの使い方を伝えていきましょう!という「デジタル・サポート・チーム」へのお誘い。
もうひとつの趣旨(こちらのほうが大事)が、デジタル化されてきた町で、データやアプリを活用して、何を起こせるか、起こしたいかのディスカッション。「ここからが未来を賭けた挑戦!チャンス!」
4. 教えることは最大の学び
「教えることは最大の学び」なので、まずは高齢者の方々の質問にやさしく答えられるよう、自らのICTリテラシーを高めていきます。
これは、僕もいま高齢者訪問していて実感中。「タブレットで電話はできるのか?」とか、「Wi-fiってなんだ?」「ガラケーでできて、タブレットでできることは?」「1GBってどんぐらいだ?」とか、率直な質問に、どういう言葉とどういう言い方で話せば腹に落ちるのか、日々壮大な実験中。
本当に最高のコミュニケーション訓練になってます。
これだけでも、若い人たちのコミュニケーション力アップは間違いないですね。いまのところ、最強の研修になると確信。
さて、基礎的なICTリテラシーと、コミュニケーション力は身についていくとして、課題は、なにかを事業化する力です。
5. 最大の課題は事業企画力
収益性重視か社会性重視化は別に、アイデアで終わらせず、具体的なアクションにどう落とし込めるか、継続したアクションになる仕組みをつくれるかが勝負かと。
地域活性化や地域経済振興策で必ず出てくる「起業支援」。
町の中で、どれだけの人が起業したことがあるのか?いや、県内見渡したって、数えられる程度。僕も20年近く経営に携わっているけど、まともにこれが起業だぜ、って手応えなんてほぼない。
あまりにハードルが高いな、って思います。
といって、だからできませんではすまず、ちょっとヒントになるのが最近、本や動画でとりあげられることが多いように思う社内起業。
主に大企業にいながら、社内の新規事業として起案、社内決裁を得て資金を調達、子会社設立、うまくいけば上場というパターン。
リクルートが伝統的に新規事業、社内起業の実績を多数つくっています。最近ではサイバー・エージェントの社内起業マクアケが上場して話題になってました。
そういえば、僕のキャリアも社内起業からスタートしてたっけ。
新卒で入社したポーラ、配属は新規事業開発部。商品とチャネルともに、新しい市場を開拓することがミッションでした。
商品は化粧品から菓子・食品へ、チャネルは訪問販売から駅売店・コンビニ・量販店へ、というチャレンジ。キャンディーをゼロから立ち上げ、ヒット商品では「MINTIA」をうみだしました。
その後、ポーラからアサヒグループ食品に事業譲渡、今でも順調に食品事業を展開しています。いわゆる社内起業の成功例といっていいと思います。
いま、自分で起業していて思いますが、ポーラ在籍当時の経験が財産。本体の化粧品で実績をあげていたオジサンたちよりも、僕ら20代のほうがアイデア出せたり、キャンディー詳しかったりして、やたらフラットで楽しかった思い出多数。
いま思い出しても重大な責任を持たせてくれ、若手に好きにやらせてくれた社内起業家の前田さんのおかげ。いまでも尊敬し続けるロールモデル。(仕事は大変だったけどやりがいしかなかった)
ゼロからリスクをかけて起業するのも尊いことですが、この際、起業の美学よりも、町の中で、お金がまわり、雇用をうむ事業をつくれれば良いので、手段は選ばず。
町内の既存企業の社員が新規事業を企画する力をつけるほうが早いかなと。
都農町の企業の社長さんには、ぜひ「新規事業の実践論」とか社員さんたちに読んでもらってほしいです。勉強会やってもいいし。
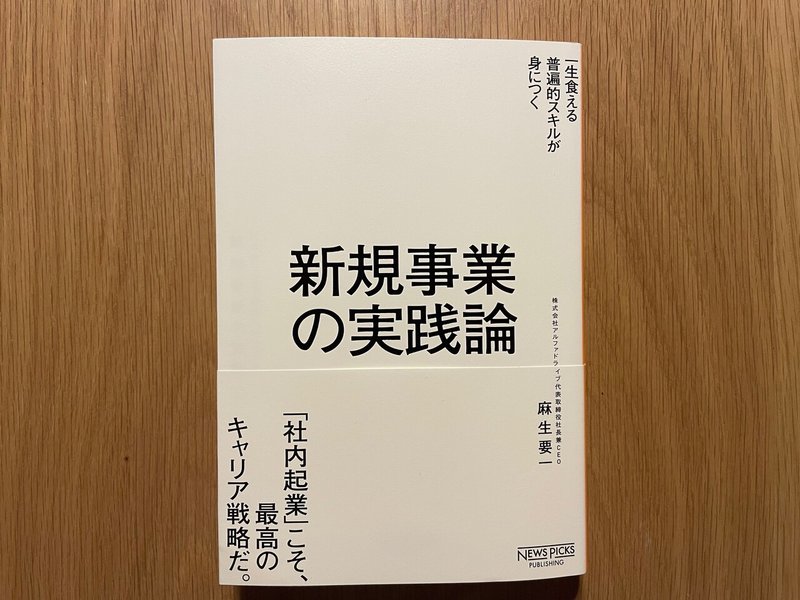
また、社内起業とともに、もうひとつの選択肢が「兼業」「副業」
都農町からも受講者を送らせてもらってお世話になっているコンパクト農ライフ塾の校長、井本喜久さんの「ビジネスパーソンのための新兼業農家論」なども参考になるところ多いのでは。
1万人の町で、1.7億円投資して、2,000世帯にタブレット配布したり、町民のIDを蓄積できるホームページ開発するからには、そこで可能になったコミュニケーションチャネルやビッグデータをどう活用するか、若い人にとっては大きなチャンスだと思います。
①ICTリテラシー ②コミュニケーション力 ③事業企画力、この3つを育成できれば、デジタル化した1万人の町で、自分らしく、仕事や暮らしを楽しむことができるのではないかと思い、引き続き、全面バックアップ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
