
問題解決で大切なこと
大切なのは問題解決力?
問題解決で大切なことは何でしょうか?
問題を解決する能力(問題解決力)も大切ですが、まずは次の点を見定めることが大切です。
何が問題か?
解決すべき問題は何か?
これらの点を見定めて、解決すべき問題を定めることを問題の設定と呼びます。
問題の設定をきちんと行ったうえで、問題の解決アイデアを考えることが大切です。
そうしないと、せっかく考えたアイデアが的外れになる可能性があります。
その理由を説明します。
問題の原因は1つとは限らない
次の問題を考えます。
自動車の乗り心地が悪い
解決アイデアを考えるために、問題の原因を分析します。
問題の原因を分析するときは、「なぜ?→なぜ?」を繰り返すと、より本質的な原因を見つけることができます。
まず1回目の「なぜ?」では、「自動車の乗り心地が悪い」原因は、座席の座り心地が悪いことだと考えました。
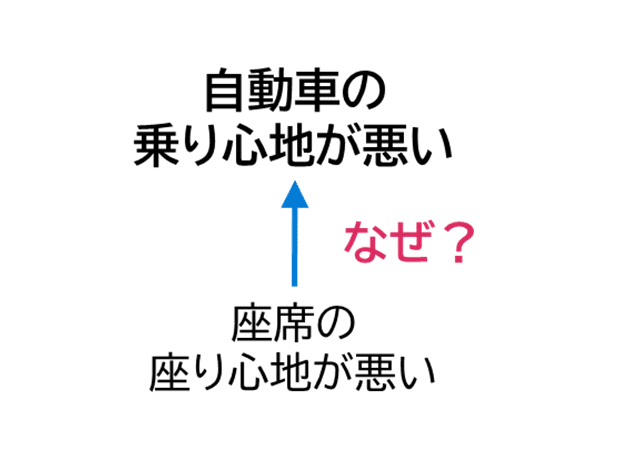
もう一度「なぜ?」を繰り返します。

2回目の「なぜ?」の結果、座席シートが硬いことがより本質的な原因だと考えました。
本質的な原因が見つかれば、改善アイデアを考えます。

ここまでの流れは、問題解決の流れとしては良いように見えます。
しかし、問題の原因は1つとは限りません。
「自動車の乗り心地が悪い」原因は、次の図に示すように、他にもあります。

「自動車の乗り心地が悪い」原因として、①「座席の座り心地が悪い」以外に、②「自動車の振動が大きい」③「路面がデコボコである」などが考えられます。
②と③についても「なぜ?→なぜ?」分析を進めると、次の図のようになります。

それぞれの本質的な原因がわかれば、その改善アイデアを考えることができます。

上図のように、問題の原因が異なれば、全く異なる改善アイデアにつながります。
「問題の設定」は大切
ここで、「自動車の乗り心地が悪い」と言っている顧客の困りごとを考えてみましょう。
もし顧客の実際の困りごとが、②「自動車の振動が大きい」場合は、残念ながら「座席シートの改善アイデア」は的外れになってしまいます。

また顧客の実際の困りごとが③「路面がデコボコである」場合は、自社では対応不可になってしまいます。

頑張ってアイデアを考えた後で、上記のような状況になると困りますね。
ここでは、わかりやすくするために極端な例をあげましたが、似たようなケースが他の製品開発でも生じる可能性があります。
考えたアイデアが的外れにならないようにするためには、アイデアを考える前に次の点を見定めることが大切です。
何が問題か?
解決すべき問題は何か?
問題の設定をきちんと行ったうえで、問題の解決アイデアを考えることが大切です。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
