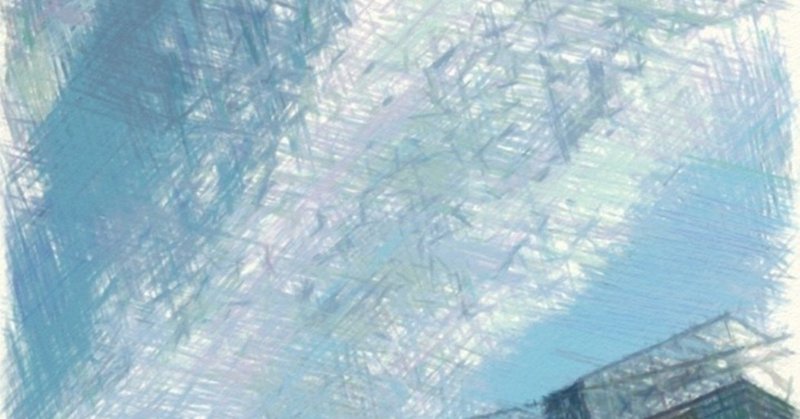
失われた共感覚
ユーザーネームの由来の話をしよう。
「風埜いろは(かぜのいろは)」は中学生の時にラジオネームとして使ってから、高校・大学時代は創作ネームとして使っていた。社会人になってからは創作活動を全くしていないので休眠していたが、noteを始めるにあたり復活した。
何故この名前になったのか。それは幼稚園時代に遡る。転勤が多かった私は、3つの幼稚園に通ったのだが、それぞれの園でそれぞれのこだわりがあったらしい。
1つ目の園はキリスト教保育の幼稚園だった。ここでは、手を洗うことが好きだったらしく、親が迎えに来てもずっと手を洗っていたらしい。
2つ目の園は普通の幼稚園。絵を描くことに夢中になり、特にスクラッチがお気に入りだった。スクラッチ(ひっかき絵)は、画用紙にあらかじめ隙間のないようクレヨンなどで色を塗り、その上から黒いクレヨンやアクリル絵の具で上塗ってから、竹串などでひっかきながら描く技法なのだが、これは今でも覚えている。(今度やろうかな)
3つ目の園は神社が併設されている仏教系の園だった。このころになると、お友達と遊ぶということが少なくなったらしい。これはお友達を拒絶するというわけではない。自分がしたいと思ったことに忠実で、仲の良い子が違う遊びをしていても別に構わないといった風だったらしい。しかし、友達の誘いを断ってしていた遊びは「木登り」だった。
外遊びになると真っ先にお気に入りの木に登り、ぼーっとしていたという。先生が遊びに誘っても全く乗り気にならないので、何が楽しいのか聞くと「風の色を見ているのが楽しい」と。
×××
そもそも、私は幼少期の記憶がほとんどない。これらの話も親や兄弟から聞いたことなので、まったく覚えていないのだが、風に色があって、言葉には味があって、味には形があった…ということはぼんやりと覚えている。
学校の先生にその話をしたら、それは「共感覚」だと言われた。
辞書によると共感覚とは「音を聞くと色が見えるというように、一つの刺激が、それによって本来起こる感覚だけでなく、他の領域の感覚をも引き起こすこと。」らしい。
現象には個人差がある。
数字や文字に色が見える場合や、音に形がある場合など、人によって異なる。そんな想像もできない世界が見えている人たちがいるらしい。特に生活に大きな支障もなく、実際はみんなにも同様に見えているものだと思って、特別に思っていない人もいる。
驚くべきは歴史上の芸術家、作家、詩人、さらには音楽家、数学者の多くはこの共感覚を持っていたとのこと。日本人では宮沢賢治が共感覚保持者だったらしい。
×××
今の私にはもう何も見えない。全く。
そして、失われたことがとても惜しい。…本当に共感覚だったのかは定かではないが。
しかし、一度見えていたものだとしたら、いつかまた見えるかもしれない。そんな願いを込めて。
「風の色は?」
今後も有料記事を書くつもりはありません。いただきましたサポートは、創作活動(絵本・書道など)の費用に使用させていただきます。
