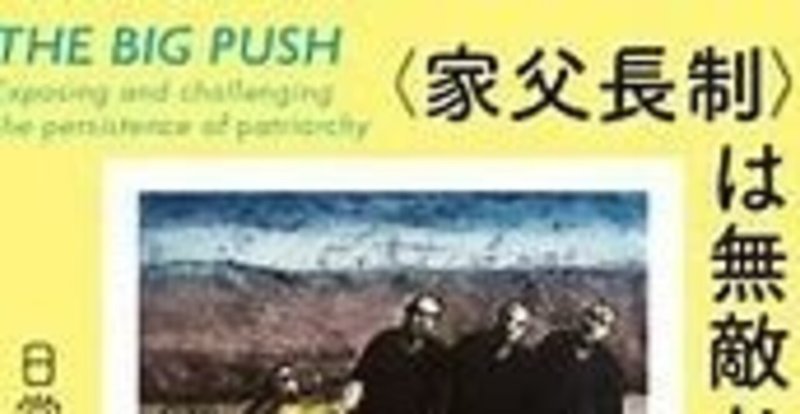
「〈家父長制〉は無敵じゃない」を読んで
こんにちは
かわうそちゃんです
今回は、「〈家父長制〉は無敵じゃない 日常から探るフェミニストの国際政治」(シンシア・エンロー著)を読んだ感想を書きたいと思います。
この本に出会ったきっかけは、大学の授業で紹介されていたことです。
私の通っている大学は共学なのですが、女子大の講義に参加する機会があり、その講義を行っていた先生が紹介していた本です。(まだ授業は1回目しか終えていないのですが)
女性の社会参加は今、大きな話題になっています。
フェミニストやフェミニズムなどという言葉を聞いたことがある人がいるかもしれません。
Twitterなどでは、女性に対する批判的な意味でとらえられる事が多くありますが、実際は今まで私たちが当たり前として受け入れられてきたおかしなことや理不尽、疑問を声に出している人々なのです。(勿論一部過激な人もいますので、一概には言えないことは事実です)
今、男女平等は多く叫ばれていますが、私の考える男女平等は「女性の社会的地位を上げる」ことではなく「男性も女性も性別に囚われることなく、個人として生きていくことが出来ること」であると考えています。
「女性の社会的地位を上げること」は男女平等のゴールではなく通過点であるという考えです。
しかし、今回は女性にとって理不尽なこと、不自由に感じることに疑問視するフェミニストの視点を想像しながら感想を述べていきたいと思います。
当たり前になっている「家父長制」を題材に疑問を問いかけるように書かれたこの本は、自分が今まで当たり前に受け入れてきた物事や理不尽、概念について考えさせられました。
以下、この本のネタバレ等が含まれている可能性があります。
この本では冒頭で女性の社会運動について多く取り上げられているのですが、女性の社会運動は実は昔からあり、多くのフェミニストが声を上げてきました。
私は法学部在学中なので、法律について書かれていると目に留まり、考えさせされるのですが、日本の法律のみならず、海外の法律にも女性にとって理不尽な法律は多く存在します。
この本ではアイルランドの憲法に書かれている妊娠中絶の禁止に反対する運動が行われていたと記されています。
確かに、妊娠中絶を禁止された場合に誰に影響があるのでしょうか。
子供を産める体を持っている方です。
子供を産むという事は、その方の人生を大きく左右します。
子供を産むことがゴールではなく、その先にあるのはその子を育て、共に生活していくことです。
しかし、望まない妊娠をし、産みたくないと希望する方もいます。
アイルランドのこの憲法では、望まない妊娠をし、産まないという選択は出来ません。
妊娠したら産むがセットです。
この法律は、子供を産める体を持っている人にしか影響がありません。
子供を産めない体を持っている、体が男性の方には特に影響がないのです。
そうなると、この法律について、考える人が減ります。
産まない人にとっては関係のない法律ですので。
そうするとこのような問題に関して考え、発言することが減ってきてしまうのです。
このような問題に疑問を持ち、声を上げる事はいけないことなのでしょうか。
家父長制について考える中で、誰がこの概念を維持し続けているかは非常に問題として考えてもよいと思います。
本の中ではドナルド・トランプなどが度々登場するが(なぜトランプが出てきているのかはぜひ本を読んでみてください☺)、トランプが一人でその体制を続けていてもなかなか続かないのが現実でしょう。
トランプは権威や影響力が大きい人です。
しかし、トランプを大統領にしたのは誰ですか?
アメリカ国民です。
周りに支持者がいることによって、成り立っているのです。
これは家父長制にも同じことが言えます。
支持を表明しているわけではなくとも、それが当たり前だと思っている。
それが「普通」であると思っている。
このような考え方が家父長制を現代まで持続させているのです。
ここまでで2000字近くあるのですが、感想を書いているのは最初の40ページ程です…
今資格の勉強や、大学の勉強に追われて感想を書いている時間があまり取れないので、一旦公開にしますが随時更新していくつもりです。
Twitterで更新情報を挙げていきますので、気になった方はTwitterを参照してください。
この本の感想を共有したい方や、一度話してみたいという方も大歓迎です!
それではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
