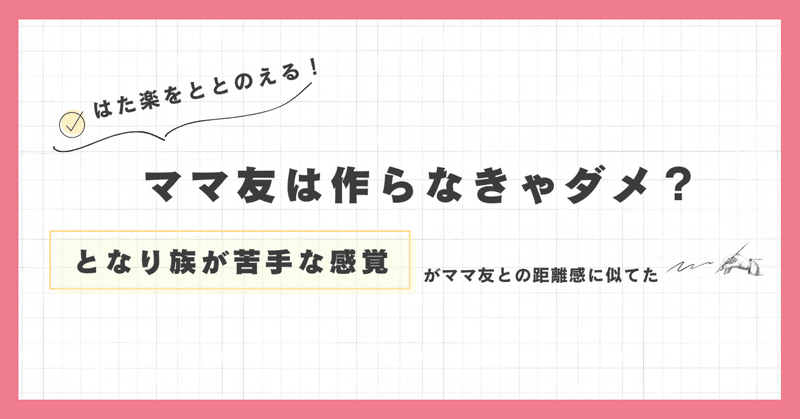
「となり族が苦手」な感覚が、ママ友の距離感のとり方と似てた話
なんでこんなこと書くのか、というと、
先日会社の新米ママの後輩から
「働いてるとママ友ってなかなかできないんですけど、作らなきゃだめですか?」と聞かれて。
うーんわかる・・。
私もちょっと悩んだことがあるんですよね。
10年ほどフルタイムのワーママとしてやってきて、最近この感情にうまいこと言葉をきせられることができるようになった気がします。
それが、「となり族が苦手」という感情に、
ママ友との距離感のとり方が似てるということ。
なんのこと?と思う人もいると思いますが、
以前ダウンタウンの松ちゃんが同じことを言ってたことがあって「あーわかる人はわかる感覚なんだな」と思ったので書いてみます。
少しだけ、自己紹介しますと、
広告畑で20年以上のキャリアを持ち、
SNSやブログ、noteで
発信しているカツママと申します。
▶️フィジカルは「体温」
▶️メンタルは「言葉」
心身両方の軸のアプローチで働く日々をラクにする『はた楽』をととのえるをコンセプトにnoteでは発信をしています。
この記事を読むと、子育てしながら人間関係で悩むことがちょこっと減るかと思いますので、最後までお付き合いいただけたらと思います。
「となり族が苦手」な感覚が、ママ友との距離感に似てた。
昔から「となり族」が苦手。
となり族って言葉が存在してるのか不明だけど、
最近よく聞く「心理的安全性」的なことにも通じる気がしてます。
「心理的安全性」とは、「サイコロジカル・セーフティ(psychological safety)」を日本語に訳した心理学用語で、どのような言動をとっても拒絶されない状態のことを指します。米Google社が自社の生産性向上のために調査する過程で再発見した言葉であり、注目を集めています。
「心理的安全性」って、組織の中で自分の気持ちや考えを安心して話しやすい環境を作れるような状態を作ること、でキャリアデザインのあり方や職場づくりでもてはやされることが多い気もしますが、
働くお母さんがふえた今、ママ同志の関係にも
一部通じるものがあると思ってます。
と前置きはさておいて、めちゃくちゃ個人的な違和感「となり族から苦手」から、私が感じた”心理的安全性INママ友”をお話しします。
例えば
空いているジムのロッカー、
自分が使っている隣にわざわざ陣取る人。
30個以上ロッカーがあるのに「なぜここ?」
銭湯のロッカー、人が裸んぼうで着替えてる隣にわざわざ陣取る人。なに?他にもロッカーあるけど、ここなの?と、扉ちょっと閉め気味にこちらが気を使ったり。
平日のガラガラの電車、後から乗ってきた人が私の隣に座る。スリなの?それともあれか?チカンとか?お向かいもきちんと席ありますけど・・・
変なマイナスの期待のソワソワ感とは反して、意外にも、ただただ「となり族」は平然と隣に座ってる、だけ。
千と千尋の顔なし、、ばりに。こちらは先に座ってたのにモゾモゾする。。

とにかく「となり族」が昔から苦手💦
そういえば、小学生女子だった頃から「いっしょにトイレ行く女子」が同じ女子のはず・・なのに理解できなかった。
なんでトイレに連れ立って行くの?一緒に行ったら単純に混むからゆっくりできないじゃん。
トイレの感覚ってみんな違うよね、、など、おそらくいっしょに行きたい女子からすれば、なんでそこにこだわるの?って話。
野生の勘とか、生理的にイヤ、としか言いようがない。
母になってから気づいたのが、
この感覚がママ友にも当てはまるということ。
ドンづめに距離を狭めてくこられると逃げたくなる。ちなみに私HSP気質でもなんでもなく、どちらかといえば”あけすけタイプ”。
あんまりいろんなこと気にならないんですが、
「となり族苦手・撲滅委員会」を立ち上げてもいいほど、苦手。
異文化交流を楽しむ感覚で過ごすと、見えること。
保育園までは、保育園そのものが基本、「働いてるママが利用する」前提なので、比較的同じような人が集まってるし、それぞれ忙しいから朝晩顔を合わせるレベルでしか関わらないのだけど、
就学後って特に子供が同じクラス、同じ学年であると言うだけで、今まで話したこともないようなタイプの人もごちゃ混ぜになる
フツーに大人やってたら、まさに味わえない異文化交流。
ニンゲン観察的にはとても面白い。
中には会社のやり方をそのまま保護者会で流用しようとして、総スカン食らっちゃうママもいたりして(これは別の機会にお話ししたい)今までのキャリアややってきたこと関係なく
子供が同じ学校に通ってるだけ、で集められた集団なのです。
会社や、同窓会的なことでも出会ったことなかったようなタイプの人もいて、会って数分後に急にLINE交換して〜!と距離を縮めてくる人もいる。
子供が仲良しだとむげに断るわけにもいかなくて・・・。ましてや小学校低学年のうちは親の交流が子供の交流のカナメ、みたいになるところもある。
息子が小学2年の頃、息子の学校では「校外で遊ぶ時にあの子のママとLINE交換するのが必須なのよー」と驚愕の話を聞いたことさえある。もちろん私は聞かなかったことにして、そーっとその場を離れた。
まあ知らないふりを決めこもうするような親(私)の子も、鈍感力が人一倍強いのか、それとも男子だったからなのか、
うちの子は一向に困る気配を見せなかった、(もしくは私が気づいてないだけ、なのかもだけど)困ってたんだったら悪いことした・・。
話を元に戻すと、となり族をやってのける人って、グイグイ感で父兄関係もやりのけるんだろな、と勝手な想像というか、体感値。
グイグイくる…だけど、私はやっぱりとなり族が苦手。
世の中のママたちはどうなの?と思ったら、
面白い調査があったのでご紹介しますと、
株式会社しんげんが運営する主婦向けの情報メディア「SHUFUFU」は、「信頼できるママ友」に関するアンケート調査を実施↓

信頼できるママ友はいますか?の問いに対して最も多かったのが「いる(1人)(37.5%)」でした。 次いで「いる(3人以上)(27%)」「いない(18.5%)」という結果に。
ママ友なんて1人いればめっけもん!の現実。
案外自分の感覚もずれてない!と確信。
私は「つかず離れず、で続く人だけ、世にいう「ママ友」としてお付き合いいただけてる感じ」がとても居心地いい
だから、冒頭の後輩ママにもこう答えた。
つづく人とは、いつ仲良くなったかわからんけどつづいてる。
ママ友作らなきゃ、なんて焦らなくても大丈夫、仲良くなる人とは自然と仲良くなる。だって友達を戦略的に作ったりしたこと、ほとんどの人が経験ないですよね。
この感覚わかる人、いますかね?
職場での心理的安全性なんて言葉も取り沙汰されている今、ママ友との関係においても心理的安全性をどう気づくかって、当事者にとってはビミョーな問題ですよね。
SNSが前提だと、考えが近い人に出会える
と言うわけで、「ママ友って作らなきゃダメ」に対して、自分の肌感覚で感じてた、となり族から考える「ママ友問題」の話をしてみたのですが、
それでもどうしてもママ友が欲しい!自分の気持ちと共鳴できる人が欲しい!と感じる人は、ネットで発信する側になることがおすすめです。
オフライン世界では思いを共有することって、
じつはほとんどないですよね。
よく顔を見ることはあるし、挨拶や立ち話をすることはあっても、その人が根本の部分で何を考えているか、わからなかったりしませんか?
この文章を奇跡的に読んでいただけているあなたに「いま私が心の底から思っていること」をこのようにお伝えすることはできても、いわゆる学校関係で出会った”ママ友”にここまで深い話をすることはありません。
じつは私、数年前までネットなんて怪しいと思ってましたが、
こうして自分の思いを発信するようになると、そこから広がる出会いに随分と助けられたことがあります。
2023年にはSNSを通して出会った人とリアルで話したりする機会を持つことにしたら、気づいたことがあります。
文字だけの考えで共鳴できる人とリアルで話すと、初めから心理的安全性的な距離感の保ち方が近しい人と出会うことが多いということ。
おそらく事前に考え方をシェアすること、から始まっているから、だと思います。
子供を持ったり、年齢を重ねると、どうしても人間関係は膠着しがち。
だけど、誰でもオンラインで繋がれる時代に、あえてオフラインの自分の周りの人間関係だけにこだわっていても広がりは限られます。
友達は作るもの、じゃなく、
あなたがあなたらしくいれば自然とできるもの。
これは大人になっても変わりません。
働く毎日や子育ての人間関係の悩む人のみかたでありたい!と言う思いから
▼心身両方からのアプローチで働く日々を楽にする「はた楽」をコンセプトに発信しています▼
今後も記事を展開していきます。
となり族は苦手、ですが、
考えに共鳴いただける方とはどこまでも仲良くしたい所存!
ですので、いいねやフォローをいただけますと素直に嬉しいです❤️
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
