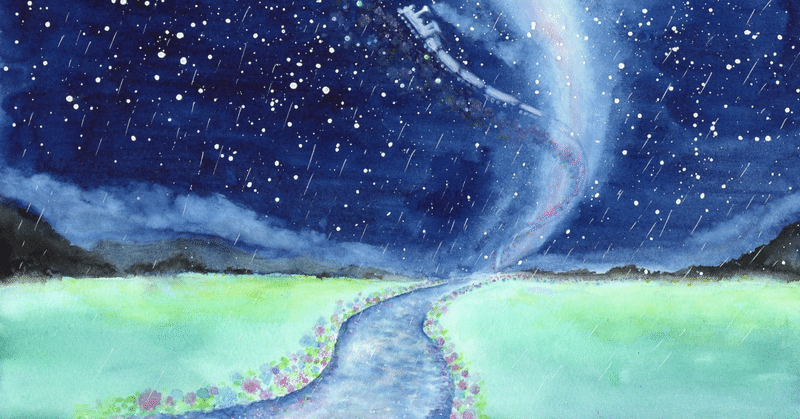
感情の地形図と意識の流れ:価値のコンパスと意志の力
これまでの記事では、主に無意識での判断や行動と、意識的な思考について考えてきました。
無意識な状態での知性は、人工知能に見られるニューラルネットワークの性質を手がかりに分析ができました。また、意識的な思考については、システム的に要素と構造を紐解いていくことで分析を進めることができました。
一方で、まだ、感情については考えてきていませんでした。感情は、捉えどころがないのではないかという印象があったため、後回しにしていたのだと思います。
ただ、これまでの思考の分析で、おそらく意識的な思考は固体のような境界が明確で、その固体の相互作用を考えるニュートン力学のようなものであるという気づきがありました。それと同時に、感情は、もしかすると液体のようなものかもしれないというインスピレーションがありました。
そうなると、物理の世界でも、ニュートン力学ではなく流体力学のようなアプローチに切り替えた方が扱いやすいように、感情を分析する際には、何かこれまでとは別のアプローチが必要になるかもしれません。
この記事では、感情についてそうした視点を持ちつつ、まずは思いつくままに、考えてみることにします。
■ポジティブな感情とネガティブな感情
喜びや楽しさ、満足感、達成感など、感情にはポジティブなものがあります。一方で、悲しみや怒り、不満、虚無感など、感情にはネガティブなものもあります。
私たちは基本的に、ポジティブな感情を得ようとし、ネガティブな感情を避けようとします。
■結果への感情、過程へのして感情
喜びや悲しみや虚しさは、自分が達成や到達をした、人から何かをされた、などの結果対して抱く感情です。
一方で、楽しさは、自分が何か好きなことをしている時や、他者が何かをしているのを見ている時、などの過程に対して抱く感情です。
また、怒りも、進行中の過程が存在することを前提とした感情です。進行中の過程があればこそ、怒りはどうにかして、そこにアクティブに介入するように仕向けようとします。
恐怖も同様でしょう。進行中の過があるからこそ抱く感情だと思います。こちらは、怒りとは反対に、消極的な反応を促します。この他、寂しさも、進行中過程の中で感じる感情でしょう。
■対象への感情、状況への感情
喜びや悲しみ、怒りや恐怖、満足感や不満、楽しさや退屈感は、対象を伴う感情です。感情の向けられている先に具体的な対象があります。
一方、安心感、不安、虚しさ、寂しさは、対象は漠然としています。これは状況が引き起こしている感情です。
対象がある感情は、その対象と感情を紐づけて学習することができます。これによりポジティブな感情であれば、その対象との関係を繰り返し再生しようと考えるでしょう。一方でネガティブな感情であれば、その対象を避けるように行動するでしょう。
状況による感情は、具体的な対象がないため、学習や行動を伴いません。ではこれらは全く意味がないかというと、そうではありません。これらの感情は、意識と無意識の切り替えに作用します。
私たちは慣れている状況では意識的に思考せず、無意識に判断して行動することができます。そして、慣れていない状況に遭遇した時に、無意識から意識にバトンタッチされ、意識的に思考して行動を決定するように促されます。
状況に対するネガティブな感情は、慣れている環境であっても、意識を呼び起こす作用を持ちます。そして、考えるように促すのです。反対に、状況に対するポジティブな感情は、意識を落ち着かせて無意識に移行させます。私たちは安心できる家を求めますが、眠るためには無意識への意向が必要だからかもしれません。
■感情の効用
結果に対する感情は、次回、類似の状況が訪れたときのための学習効果があります。
過程に対する感情は、第一義的には現在進行中の過程や状況に対しての意思決定に影響を及ぼします。一方で、副次的に、次回の類似の状況に対する学習効果があります。
漠然とした状況に対する感情は、無意識と意識の切り替えに作用します。これにより無意識に行動していたことに対して再考を促したり、意識を休ませて癒したりエネルギーを節約したりします。
こうして考えると、感情は、学習への作用と、意志決定への作用、そして意識と無意識の切り替え、の三つの役割があります。感情は、より生存率を上げるために、生物に仕掛けられた仕組みだと考えられます。
■感情の地形と意識の流れのイメージ
個人の意識が水のように高いところから低いところに向かう性質があるというイメージをすると分かりやすいでしょう。
私たちの意識が認識する感性の世界は、はじめフラットな平地に見えます。そこにネガティブな感情を引き起こすものが現れると、そこは丘のように盛り上がります。私たちの意識は、その丘を避ける方向に向かおうとします。
反対にポジティブな感情を引き起こすものが現れると、そこは窪みになります。私たちの意識は、その窪みに向かうように流れていきます。
こうして認識した丘や窪みを、私たちは学習します。やがて、また、類似の対象や状況に近づく機会がきます。学習した感性の世界の地形に沿って、私たちの意識は流れていきます。学習をしているので、少し手前の段階から、丘を避けたり、窪みに向かう事もできます。
■意志の役割
一方で、私たちの意識は単に感情に流されているだけではありません。あえて丘に登る勇気を持つ事ができます。窪みの誘惑を我慢する事もできます。これは意志の力です。
目の前の小さなネガティブな感情を避け、ポジティブな感情を得られる方に流れるのが、意識の自然な姿と考えることができるでしょう。しかしそれでは、その先にあるより大きなネガティブを避けることや、大きなポジティブを得ることができないかもしれません。
また、感情とは別にして、何かどうしても守りたい価値や、手に入れたい価値がある場合もあるでしょう。
目の前の感情の地形把握するだけでなく、私たちは、広い感情の地図と、価値のコンパスを持つこともできます。この地図とコンパスを持っていても、意識という水の流れをコントロールすることは簡単ではありません。
しかし、不可能ではありません。地図とコンパスに従って、意識の流れをコントロールする能力が、自由意志です。
■感情の伝播
集団では感情が伝播する。これにより、一人が感じた感情であっても、それを集団の学習につなげることができます。
また、過程に対する感情の場合は、感情の伝播により、集団で対応できるようにもする作用があります。
生物は、この伝播を目的に共感能力を身につけたのかもしれません。
■何が感情のトリガーになるのか?
脳が何かの概念を知覚する時、そこにはパターンの認識があります。共通のパターンがあれば、それを同じ概念として認識します。
しかし感情は、こうした概念の認識には当てはまりません。パターンを認識しているわけではないようです。
また、脳は既に覚えた概念同士の関連から連想したり、メカニズムを把握してシミュレーションすることもありますが、それらにも感情の発生には当てはまりません。
もちろん、過去に感情を経験した時に学習をして活用する際には、パターン認識、連想、シミュレーションを使います。しかしそれらは感情そのものの認識ではなく、経験の認識にすぎません。
そう考えると、もしかすると、逆に捉える必要があるのかもしれません。
私達は感情を知覚しているのではなく、その反対に何かが認識できなくなると、感情が出てくるのかもしれません。例えば、突然目が見えなくなったら、恐怖を感じるでしょう。そうした形で、何かが認識できなくなることで感情が出てくると仮定してみます。
その仮定が正しいのであれば、感情を抑えている何かについて考えると答えが見えてくるかもしれません。
■さいごに
これまで人間の知能についていろいろ記事を書いてきました。その中で、まだ取り上げていなかった感情について、考え始めました。まだ、分析に着手したばかりですので、結論や大きな発見があるわけではありません。
私たちの頭の中で起きる感情は、捉えどころのないような現象にも思えます。けれど、今までの記事で、意識や無意識、自由意志といったものを掘り下げていたことが役に立ちそうです。感情以外の部分の外堀が埋まってきたことで、感情についてもある程度考えをまとめられるかもしれません。今回の記事を書く中で、そうした感触を持つことができました。
特に、感情のトリガーについての謎は、今後の大きな検討課題です。このトリガーと感情が発生するメカニズムに、説得力のある仮説を立てることが、まずは目標です。それができれば、感情についての理解を大きく深めることができると思います。
サポートも大変ありがたいですし、コメントや引用、ツイッターでのリポストをいただくことでも、大変励みになります。よろしくおねがいします!
