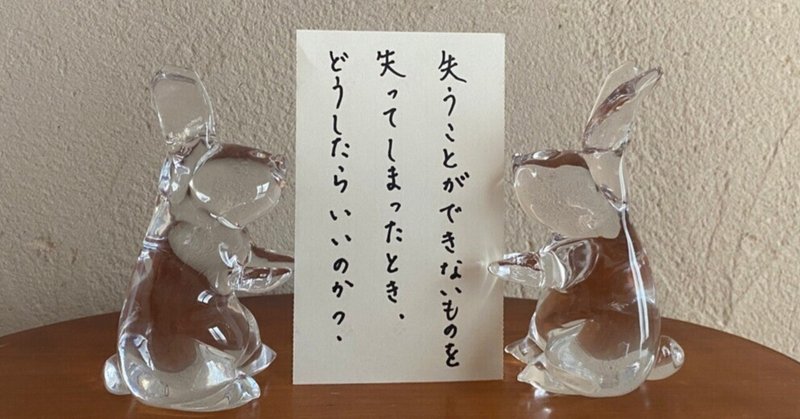
失うことができないものを失ってしまったとき、どうしたらいいのか?
エッセイ連載の第22回目です。
(連載は「何を見ても何かを思い出す」というマガジンにまとめてあります)
7月3日はカフカの誕生日で、生誕140年でした!
ということで、今回はカフカの有名な「人形のエピソード」について。
失うことができない大切なもの
人生で「これだけは失いたくない」という大切なものが、誰でもあるだろう。
愛する人がいれば、失いたくないだろう。打ち込んでいる仕事があれば、失いたくないだろう。宝物も持っていたら、失いたくないだろう。
そんなたいそうなものは何もないという人でも、たとえば、手や足を失えば、それがどんなに自分にとって失いたくないものだったか、気づかされてしまうだろう。ピアノやヴァイオリンを弾いている人だったり、ランナーだったりすれば、なおさらだ。
「お願いですから、これだけは自分から奪わないでください!」と、神に祈りたくなるものが、誰にでもあるものだ。
それを人生の最後まで失わずにすむこともある。とても素晴らしいことだ。
しかし、人生の途中でそれを失ってしまうこともある。
問題はそういうときだ。
失うことができないものを失ってしまったとき、いったいどうしたらいいのか?
カフカと少女と人形の有名なエピソード
カフカに、人形と少女と手紙にまつわる有名なエピソードがある。
『変身』などの小説を書いた、フランツ・カフカのことだ。
あらましは、こんなお話だ。
ある日、カフカが恋人のドーラといっしょに公園を散歩していると、ひとりの少女が人形をなくして泣いていました。カフカは少女に声をかけます。「お人形はね、ちょっと旅行に出ただけなんだよ」
次の日からカフカは、人形が旅先から送ってくる手紙を書いて、毎日、少女に渡しました。
当時のカフカはもう病状が重くなってきていて、残された時間は一年もありませんでした。
しかし、ドーラによると、小説を書くのと同じ真剣さで、カフカは手紙を書いていたそうです。
人形は旅先でさまざまな冒険をします。手紙は三週間続きました。どういう結末にするか、カフカはかなり悩んだようです。人形は成長し、いろんな人たちと出会い、ついに遠い国で幸せな結婚をします。
少女はもう人形と会えないことを受け入れました。
これは私が書いたのものだが、元にしているのは、カフカの恋人のドーラの証言だ。『回想のなかのカフカ 三十七人の証言』という本に載っている。邦訳も出ている(吉田仙太郎訳、平凡社)。
エピソードは変化するのがあたりまえ
これを読んで、「あれ? 自分が知っている話と少しちがうぞ?」と思った人もいるだろう。
そう、このエピソードは、少し変化したかたちで広く伝わっている。
まあ、有名人のエピソードというのは、たいていそんなものだ。口から口、人から人に伝わっていくうちに変化していく。面白くなっていくことも多いし、その人物の本質をより伝えるものになっていくことも少なくない。
たとえば、江戸時代に池大雅(いけのたいが)という画家がいて、この人が描いた龍が、絵を抜け出して、家の天井を突き破って天に昇ったという有名なエピソードがある。
これは実際には、龍の絵を描いたら、大きすぎて、家から出せなくなってしまって、天井の一部を破って、そこから出したのだそうだ。
でも、龍が天井を突き破ったという話のほうが、「池大雅は、描いた龍が絵を抜け出したと噂されるほどの絵の名人であった」ということを伝えてくれている。事実のほうは、絵描きだったということしかわからない。事実よりも、変化した話のほうが、より真実を伝えているとも言える。
だから、「伝わっている有名なエピソードは、事実とはちがう!」と目くじらを立てることは──研究者の人にとってはもちろん大切なことだろうが──一般人にとってはあまり意味のないことだと、私は思っている。
小さいけど、決定的なちがい
だが、このカフカのエピソードに関しては、ちょっと残念だなと思っている。なぜなら、変化したものより、元の事実のほうが、いいからだ。少なくとも私はそう思う。
どう変化したのかというと、一般的に広まっているエピソードでは、最後にカフカが別の人形を渡したことになっている。冒険の旅から戻って来たとして。そして、少女が「私の人形とはちがう」と言うと、「旅をしているあいだに、少し変わったんだよ」と説明したことになっている。
「なんだ、それだけのちがいか」と思うかもしれない。
でも、私はこれは決定的なちがいだと思うのだ。
少女にとって人形は生きていくために欠かせないものだった──と言うと、大げさに感じられるかもしれないが、子どもにとってはそういうこともあるし、少なくとも、少女の世界の大切な一部だったはずだ。
だから、泣いていた。
人形をなくしたことで、少女の世界には欠落が生じ、それが少女の世界全体をゆるがせた。大黒柱がゆれだした家には住んでいられないように、そんな人生を生きていくことは難しい。
人形をなくしたということは、少女にとって、現実を受け入れられなくなったということだ。
カフカはそのことを感じたのだろう。自分自身がすぐに世界がゆらいでしまう人だったから。
世界がゆらいだとき、どうしたらいいのか?
失えないものを失って混乱してしまった世界に
大きな助けとなってくれるのが、文学だ。
人は誰でも物語を生きている。世界がゆらぐということは、これまでの物語では生きていけなくなったということだ。新しい物語が必要なのだ。それを作らなければならない。
そのためには、まずは他の物語を読むことだ。そうすることで、自分の物語を書き直せるようになる。他の子どもが遊んでいるのを見て、自分も遊びを考え出せるようになるように。
カフカは少女に、人形が旅をしている物語を書いて読ませた。それは人形がいなくなったことの言い訳でもあったが、それ以上に、物語を読むということが少女を少しずつ救っていったはずだ。
そして、ある程度の時間をかけて、ついに人形が戻ってこないという結末を書く。
そのとき少女は、自分の世界を、人形がいない世界として、新たに書き直すことができるようになっていたのだ。
これこそが肝心なことではないかと思う。
ドーラはこう語っている。
フランツは、ひとりの子供の小さな葛藤を芸術の技法によって解決したのだった──彼が世界に秩序をもたらすために、みずから用いたもっとも有効な手段によって。
失えないものを失って混乱してしまった世界に秩序をもたらす、それこそが文学の力だと思う。
失ったものを戻せば、たしかに解決だけど……
私もじつは、この少女とまったく同じように、カフカの文学に助けられた。だから、つい、このエピソードには思い入れが深い。
二十歳で突然、難病になったとき、私は「健康」や「普通」という、人生で失うことができないものを失ってしまった。私の世界は大混乱し、どう生きていっていいかわからなかった。こんなのは自分の人生ではない、こんな人生はいやだ、こんな現実はとても受け入れられない、というふうにしか思えなかった。
そんなときに、カフカの文学を読んだ。おかげでずいぶん救われた。とても感謝している。少女も同じだったのではないかと思う。
だから、最後に人形を渡すというのでは、だいなしだと思うのだ。それだと、私で言えば、最後に健康を戻してもらったことになる。
失ったものを戻してもらえれば、それがいちばんの解決なのはもちろんだが、現実には、失ったものは、もう戻ってこないこともある。そのときどうしたらいいのかということこそ、大問題なのだ。
だからこそ、カフカは残された貴重な時間にもかかわらず、少女のために手紙を、物語を書いたのではないだろうか。
あとで人形を戻すのだったら、手紙はたんに、もとの人形と少しちがっていることの言い訳にすぎてなくなってしまう。
ブロートのうっかり
どうして話がこんなふうに変わってしまったのか?
私は人の口から口への変化を信じている。先の池大雅の場合のように、事実とはちがってしまっても、より真実を伝えるものになっていくものだ。
それなのに、このカフカのエピソードの場合は、どうしてこんなことに?
じつは、理由がある。
これは人から人に伝わるうちにだんだん変化したわけではないのだ。
ドーラからこのエピソードを聞いた、カフカの親友のマックス・ブロートが、まちがって本に書いたのだ。
それは『フランツ・カフカの作品における絶望と救済』という本で、邦訳は出ていないのだが、幸いなことに、先の『回想のなかのカフカ 三十七人の証言』に一部が収録されていて、そこに人形の話が出ている。ブロートはこう書いている。
しめくくりに彼は(中略)子供に人形をひとつ残してゆくことを、そしてそれが古いなくした人形なのだと証明することを、忘れなかった。人形は遠い国々でのあらゆる体験を経ているうちに、多少の変貌をとげたにすぎないということにしたのである。
まさに、今、一般的に広まっている話そのものだ。みんなは、ブロートの話を忠実に伝えていたにすぎないのだ。
カフカのことは、みんな、ブロートを通じて知った。だから、親亀こけたら皆こけるで、みんながまちがえるのも無理はない。
ブロートは、私はとても素晴らしい人だと思っている。非難する人も多いが、私はちがう。「ブロート礼讃」という文章も書いたことがあるくらいだ(『草獅子 特集カフカ』双子のライオン堂出版部)。
しかし、ブロートは思い込みが激しく、勘違いが多い。市川崑監督版の金田一耕助映画で、ポンと手を打ち「よしっ、わかった!」と早合点する等々力警部のようなところがある。
ブロートはこの人形のエピソードを「ドーラ・ディアマントが話してくれた」と書いている。おそらく、いちばん最初にドーラから話を聞いたのがブロートだっただろう。その最初の時点で、もう勘違いしてしまったのだ。
ブロートは、いい人なので、その勘違いは許していただくとして、カフカ生誕140年のこの機会に、本当はこういう話だったということを、知っておいていただけると嬉しいなあと思う。
なお、ポール・オースターは小説『ブルックリン・フォーリーズ』で、このカフカの人形のエピソードを紹介しているが、ちゃんと本来の話をしている。最後に別の人形を渡したりしていない。さすがだ。
立ち直れたわけではない
ねんのため、もう少し書いておくと、「少女はもう人形と会えないことを受け入れました」というのは、人形を失っても平気になったということではない。
少女はその後も、悲しくてさみしくて、泣いたかもしれない。ずっと忘れられなかったかもしれない。
しかし、ともかくも、人形がいない現実を生きていけるようになった。苦しみながらだとしても。
大ゆれにゆれた家が、元通りになったわけではなく、傾いたまま、なんとか住み続けられるようになったということだ。
私の場合も同じだ。カフカによって救われたというのは、病気でも平気になったとか、いわゆる「病気を受け入れる」ということができたわけでも、まして「病気になってよかった」と思えるようになったわけでもない。
今でも、病気は受け入れられないし、こんな人生はいやだし、嘆きつづけている。しかし、ともかくも、生きている。立ち直ってはいないが、倒れたままで生きている。
そのことで、ずっとカフカに感謝している。
カフカの唯一の童話が発見されることを願って
だからこそ、私はこの少女への手紙が読みたくてたまらない。
それは少女が持っていたはずで、きっと捨てたりはしなかっただろう。
もしかすると、どこかの家の屋根裏とかに、箱に入った古い手紙が眠りつづけているかもしれない。
ベルリンの新聞が、呼びかけたことがあるが、いまだに見つかっていない。
カフカの唯一の童話だ。いつか、ぜひ読んでみたいものだ。
もしおもしろいと思っていただけたらお願いいたします。 励みになりますので。 でも、くれぐれも、ご無理はなさらないでください。 無料掲載ですから。
