
書くことは生きること その3
私には何の才能もない。ただこれまで何かを書くことでピンチをすり抜け、生きてきた。誰にでもできる書くという作業が私にとっては生きることなのだ。『書くことは生きること』の実体験を連載する。
母に習った文章の基本
小学校一年生の時に母から作文の基本を教えてもらった。まとめてみると次の通りだ。
●5W1H
いつ
どこで
だれが
なにを
なぜ
どのように
●自分の気持ちを書く
●情景の描写
これらは私の心の奥底に染み込み、一生の財産となった。しかし、そこから読書量が増えたとか、何かを創作してみようという路線には行かなかったのだ。
一つの原因として、小学2年生の担任と出会ったことが大きい。
私は栄養失調で背も小さくガリガリの女の子だった。
そこに担任としてやってきたのは若くて綺麗な高橋先生。体育大学を出たばかりのスポーツマンだった。先生のおかげで、大嫌いだった体育が大好きになった。
自分でも知らなかった持ち前の負けん気を引き出してくれて、10秒を切るまで何度も50メートルを走らせた。10秒を切った時には私を抱きしめて喜んでくれた。
それから私は運動のほうに興味を向けてしまったのである。本を読むのはかったるい。外で身体を鍛えている時間のほうが楽しくなってしまった。
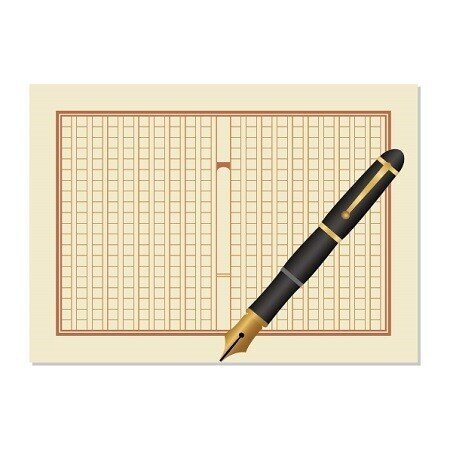
雑誌に投稿する
再び書く喜びを見出したのは24歳になった時である。
中央公論社『婦人公論』に投稿したのだ。21歳の時に体験した悪徳商法の舞台裏を描いてみようと思った。レーザーディスクの英会話教材を販売する会社で、徹底的にマニュアルを暗記させられて、電話で獲物を釣る。
ローンを組ませてとんでもない高額な教材セットを購入させるのである。中に入っていた人間でしか知りえない恐ろしい従業員への洗脳方法を書き進めて行った。
当時はワープロさえなく、原稿用紙にシャーペンで手書きである。一行書き始めたら止まらない。気が付いたら外ですずめがチュンチュン鳴いていた。完成した原稿は30枚を超えていた。
雑誌に掲載、そして電話
投稿したことで専業主婦の私は十分満足だった。一カ月過ぎた頃、中央公論社の編集部の方から電話をいただいた。携帯電話もない時代だからもちろん家電だ。その人は開口一番にこう言った。
「あなたは文章を書いて食べていく人です」
次の言葉が出てこなかった。母から文章の基礎を習ったとはいえ、これまで自発的に何も書いてこなかった。
今は専業主婦で2番目の赤ちゃんがお腹に入っている。夫は上場企業の営業マンなので生活にはゆとりがあった。なにも文章を書いて生活費を稼ぐ必要はなかった。
「すみません。今は妊娠中なので……」
と言うと、
「すぐにとは言いませんが、書かないのはもったいないですよ。あなたの文章には一気に読ませる力があります。その力は誰もが持っているものじゃないんです。原稿ですが次号で掲載させていただきますね」
信じられないお言葉をいただいたが、私にそんな能力があるなんてまだ実感が湧かなかった。
本当に次の号に私の書いた文章が掲載され、印税4万円が振り込まれた。よく印税生活という夢のような言葉を聞くけど、私にとってこの4万円は額縁に入れて飾っておきたいほど嬉しかったことを覚えている。
その4へつづく
よろしければサポートをお願いいたします。取材などの経費として大事に使用させていただきます。
