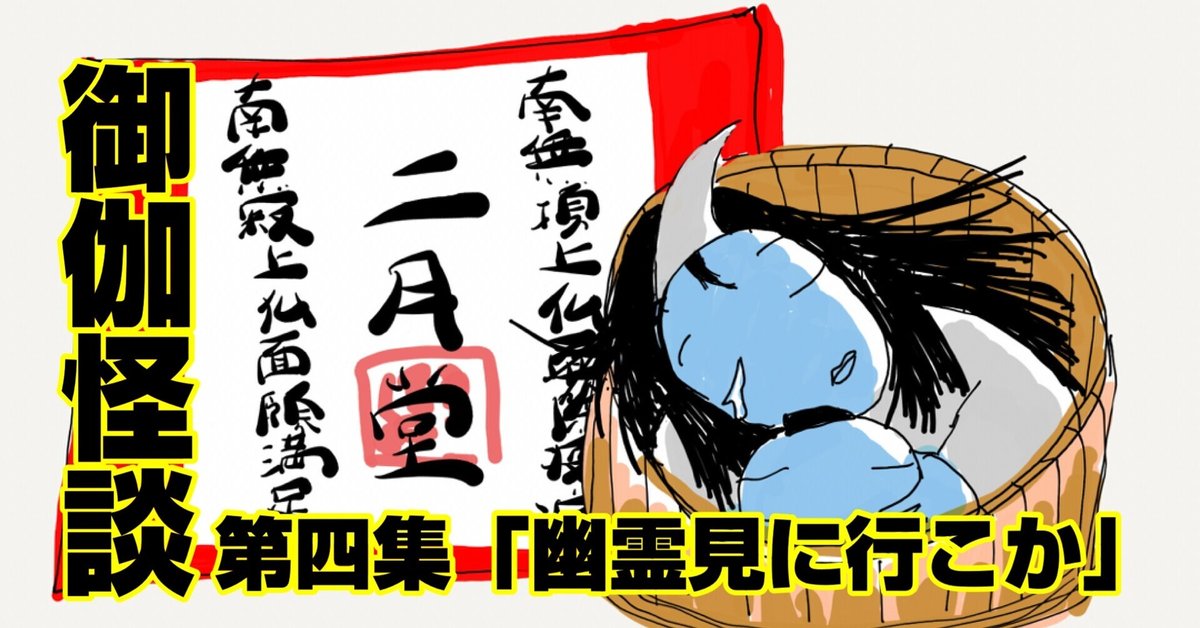
御伽怪談第四集・第五話「牛王を怖れる」
一
延宝五年(1677)の七月のこと、
——七條ケ原あたりに、誰とも知れぬ死人の塚があって幽霊が出る……。
と噂が広まった。毎晩、人魂が漂っては、すすり泣く女の声が響くと言う。特に雨のシトシト降る夜は、人魂がゆらゆらして、怖ろしさ満点であった。
友人からまた聞きした者の話によると、
「人恋しや。人恋しや……と、確かに聞こえたんや」
真実かどうかは分からなかった。悲しげな声は凄まじく、聞く人は肝を潰し誰もが逃げたと言う。皆、逃げてしまうため、どんな幽霊が出るのか見届けた者もなかった。ただ噂ばかりが囁かれていたのである。
巷でほ、
——何年か前、あの墓場の奥で化け物《もん》に骨を抜かれた奴がおる……。
とか、
——見に行った奴らは、皆、行方知れずとなり、ひとりとして帰らんかったそうや。
確かにこのあたりに化け物に骨を抜かれた者はいた。しかし、考えたら妙な話である。誰ひとり帰らなかった場所で見聞きした物事を、いったい誰が伝えたのであろう。
そんなある日のこと、恐い物見たさの若者三人が頭を寄せ合って話し合っていた。町人の半兵衛、関七、権左衛門である。
半兵衛は怖がりだが威勢が良く、何でも茶化す性格であった。
関七は真面目な怖がりであった。ふたりとも、いかにも京男と言った感じの、イチビリでシワい男たちであった。イチビリとは調子乗りのことで、シワいとはケチ臭い奴らのことである。
最後の権左衛門は怖がりではなかった。しかし頭が鈍かった。鈍いから怖がらないのか、それとも剛の者だからなのかはハッキリしなかった。三人は幼馴染みで気心も知れた友人であり、時々、肝試しと称して、当たり障りのない場所ばかりをさまよっていた。
今回も、半兵衛が噂を聞いて言い出した。
「今度こそ、幽霊、見よう」
「またかいな」
「関七……お前、怖いんか?」
「いやいや」
「権左衛門は、どない思う?」
「さぁ、わいには分からんけど、いっそ、見つけて退治したらよかろう」
「怖いこと言いなさんな」
などと、いつものように盛り上がっていた。この手のことはその内に立ち消えるものである。盛り上がるだけ盛り上がったら、それで飽きてしまうが今回は違っていた。
半兵衛が両手を合わせ頼み込んだ。
「なぁ、後生やから、今度こそほんまもんの幽霊、見に行こや……」
関七が呆れて言った。
「なんべん、後生や言いますのん」
半兵衛が苦笑いした。
「今度こそ、心底、幽霊やで。肝試しと洒落こもか」
「前のんは、ひどかったさかいなぁ」
「ハハハ、あれは、もう言わんといて……」
「権左衛門は、どないする?」
「わいは、怖いと思ったことないからなぁ」
「お前は気楽で、ええなぁ」
何やかんやでその日の夕方、連れ立って七條ケ原の墓場へ赴くことになった。途中で提灯を手に入れて、暗くなるを待ち、河原へ向かった。明日は七夕。あちこちに七夕飾りが出されていた。特に子供のいる家には、つたない願い事の短冊が、いくつも風に揺れていた。その中に〈お化けにあいませんように〉と書かれた短冊もあった。
ニ
七條ケ原に行くためには、五條大橋を渡って川沿いを南下する。先頭を歩く半兵衛が、提灯を揺らしながらブラブラ歩くと、関七は怖わ怖わついて行った。少し遅れて権左衛門がのんびり歩いていた。河原に首切り場が見えて、なかなか不気味な景色であった。七月六日の夜だった。明日は七夕。提灯がなくてもまわりは見えたが、やはり明かりは必要だった。トラツグミが鳴く不吉な夜であった。
半兵衛がいつものようにイチビって関七をおちょくった。
「どうするぅ……悪いことしたら、お前、あそこで、首、晒されるんやでぇ」
「ええって」
提灯が半兵衛の笑いで大きく揺れた。
幽霊の噂はいつでも行ける場所にある。これが遠すぎたら、無理して行く者などいない。行けるから、つい、行く者が出てしまう。しかし、多くの噂は空振りで、大したことのない体験をして、必要以上に怖れては逃げ惑い、おかしくなるのがオチである。
墓場に着くとせせらぎが聞こえた。星がまたたいて天の川がハッキリと見えた。幽霊のことを忘れるほどの見事な雰囲気であった。河原へ視線を落とすと、幸いなことに処刑はなく、獄門台に首はなかった。
土手をくだる処刑場。左に折れると墓場の入り口である。近くにコンモリした土饅頭があった。半兵衛はそれを見て首を傾げた。
「これが塚なのか?」
関七が、ぼんやりとつぶやいた。
「土の饅頭みたいやなぁ」
「あたりまえや、土饅頭って言うんやで。ビビッて忘れたんかい?」
「いや、そ、そないなことは……」
遅れて到着した権左衛門が、
「やれやれ、やっと着いたんかいな?」
「あぁ、権左衛門、遅かったな。ビビッて、もう来んのか思ってたわ」
「何をビビるんや?」
と、ちょうど良い大きさの、コンモリとした固い塚に腰を降ろした。
その時、関七がアッと叫んだ。しかし、権左衛門は何のことかも分からず首を傾げた。あろうことか塚に腰掛けていたのである。案の定、塚の中から嘆き悲しむ声がした。
「人恋しや、人恋しや……」
そう、聞こえたかと思うと、氷のように冷たい手が、後ろから権左衛門の腰をむんずと掴んだ。権左衛門は少しも騒がず、二人にゆっくりと申した。
「何ぞ、腰を掴む者がおる。ちょっと見てくれへんか」
半兵衛がアクビをしながら、権左衛門に答えた。
「なんや、腰やて? 気のせいやろ……」
提灯で照らした半兵衛は、そのまま黙ってガタガタと震え出した。
関七が、ふと、首を傾げた。
「半兵衛、また、怖いふりして……引っかかるかいな」
近づくと、塚から透き通った白い手が、権左衛門の腰をしっかり掴んでいた。関七もアッと息を飲んだまま、跡も見ず、ふたりしてスタコラサッサと逃げてしまった。
「お前ら、どこ、ゆくんや?」
さて、ひとりぼっちになった権左衛門は、腰に妙な違和感を感じた。
「誰や、腰を掴むんは? 寒いやないか」
塚の中から驚く声がした。
「さてさて、今まで御辺ほどの武辺の者もないわいなぁ」
武辺と言うより単に鈍いだけなのだが……塚の下から声が続いた。
三
「わらわは、三條室町に住む刀鍛冶の女房であったが、卑怯な女に毒殺されて、今は、粗末な塚に住む者ぞ……」
権左衛門は、尻から声がするのでムズムズした。立ち上がって塚の前に座り直すと、また、声がした。
「……あまつさえ、三七日も経たぬのに、わが夫を誑し込み、夫婦となって思いのままの振る舞い……許すまじ」
権左衛門も同情した。
「それは、ひどい話やのぉ。恨みを晴らそうとは、せんかったんかいな?」
「思えば無念さに、夜な夜な門まで参ってみたが……」
「ほぉ、それで」
「二月堂の牛王霊符が門にあって、もう、怖ろしゅうて、怖ろしゅうて、入ることも出来やせん」
「それは残念」
「魂魄、この世に留まりて、恨みはあれども晴らす術もなし。願わくば、鍛冶屋の霊符を剥がしてくれろ……」
言葉が泣き声に変わっていった。シクシクと泣きじゃくる声に、権左衛門も亡霊を不憫に思い、
「よっしゃ、わいが行って、剥がしたるわ」
と、安請け合いして、鍛冶屋の家に行くことになった。
刀鍛冶の住む三條室町は、二條城の南東にあった。七條ヶ原からだと、土手沿いの道を五條まで上がって大橋を渡り、烏丸《からすま》通りを過ぎて、もう少し先のあたりである。夜の京都は通る人もなく静まりかえっていた。そろそろ気の早い鈴虫が鳴きはじめ、コオロギの声もした。盆には早い七夕の夕暮れ時、家々の軒先には七夕飾りが出されていた。七夕は一夜飾り。今夜、外に飾り、明日は川に流すのである。
権左衛門は、詳しく聞かなったことを後悔していた。行けば分かると思っていたが、何件もの鍛冶屋があったのだ。いつくかの門を眺めると、ひとつの館に霊符が貼られていた。牛王の物だとハッキリ分かった訳ではなかった。ただ、霊符の真ん中に〈二月堂〉と書かれていたのである。
南無頂上仏面除疫病
二 月 堂
南無寂上仏面願満足
霊符の端に爪を掛けると、風にあおられ、端がペラペラした。一気に引き剥がすと、古い紙のように粉々に飛び散った。その時、物音がしたので、権左衛門は驚いて物陰に隠れてしまった。
見上げると、遠い空に黒雲が巻き起こり、鍛冶屋の屋根に降りて来た。雲の中に青白い人魂が見え、その人魂が、鍛冶屋の館に飛び入るように見えた。すると、館から、わっと叫ぶ声がした。
権左衛門がハッと息を飲んで目を凝らすと、刀鍛冶夫婦の首を携えた怨霊か姿をあらわした。怨霊はゾッとするほど美しかった。透き通る白い肌は、かすかに青白く輝いていた。右の小脇に男の首を抱え、もうひとつの生首は、解いた髪の端を銜え、乾ききらない血潮がポタポタと地面に落ちた。怨霊はニヤリと微笑むと、権左衛門に向かって言葉を発した。
「さてさて、長年の恨みも、お陰さまで晴らすことが出来申した。かたじけなく思いまするぞ」
しかし、口は生首を銜えたまま、少しも動いていなかった。
四
怨霊は左手をそっと着物の懐に入れ、袋を取り出した。
「これは感謝のしるし。ありがたや」
と、頭を少し下げると、その場で蝋燭が消えるように失せてしまった。怨霊の手を離れて袋が宙を舞った。権左衛門があわてて受け取ると、ずっしりとした重みを感じ、権左衛門は首を傾げて袋を開けた。何とも言えない嫌な臭いがした。死臭である。中を見ると、そこには小判で十両入っていた。
「どっから持って来たんや? 不吉やが、銭は銭か?」
権左衛門は袋を懐に入れようとした。だが、何とも嫌な臭いが鼻についた。袋を摘んだ手の先をめいっぱい伸ばして、汚い物を持ち帰るような感じで家に帰った。
翌七夕、三條室町は大騒ぎになっていた。下働きの者が、主人が起きて来ないのを不審に思い、首の千切れた死体を見つけたのである。門の近くに血が落ちていた。首は見つからなかった。
権左衛門はそんなことなど知る由もなかった。昨夜は一晩中悩んで、銭の使い道を考えていたのである。不吉だとしても銭は銭。十両と言えば大金である。盗んだだけで首が飛ぶ価値があった。
悩んだ末に半分を懐に入れ、申し訳程度に塚を移し変え、供養することにした。
——塚と言えば聞こえは良いが、処刑場の端の仮埋め。あれでは寂しかろう。
と、思ってのことでもあった。
墓場近くの寺に行き、もちろん、詳しいことは語らなかったが、移し替えて供養することを願い出た。
僧侶や墓掘りたちにくっついて塚へ着くと、近くに女の首が転がっている。寺男が悲鳴をあげた。僧侶が命じて寺男のひとりを奉行所へ走らせた。
生首は、獣やカラスに啄まれ、ずたずたに朽ち果てて、哀れな姿を晒していた。男の首らしき物はなかった。すべて食べ尽くされたのか、獣に持ち去られたものか、権左衛門には分からなかった。
読経がはじまると、権左衛門も手伝って塚を掘った。しばらくすると、棺の蓋が割れて怨霊の死骸が現れた。
寺男が壊れた蓋をどけると、突然、両手を合わせて、
「なんまいだ、なんまいだ……」
と大声で祈り出した。
僧侶が首を傾げて、
「なにを、そないな大きい声出して」
寺男を嗜めたが、声は止まなかった。
権左衛門も首を傾げ、
「なんや、どないしたん? これかいな?」
と、棺桶を覗いた。すると、中の死骸は、愛しい夫の生首を抱きしめたまま死んでいたのである。まるで生きているかと思うほど、艶かしい骸であった。
権左衛門は目にいっぱいの涙を溜めて、残りのお金も僧侶に手渡した。
「この首も、一緒に弔ってくれろ」
その後はこの塚に、何の不思議も出なくなったと言う。
人を殺すと必ず報いがあると言う。〈報い〉と言うのは警察などに捕まり、罪を償うことではない。そちらも必ず起こることであるが、霊的な因果応報により、償わされることを意味する。時には何世代にも渡って報いがあると言う。
そのため、殺人事件の犯人が、被害者の亡霊を見ておかしくなる話が枚挙に遑もない。『諸国百物語』より。〈了〉
* * *
