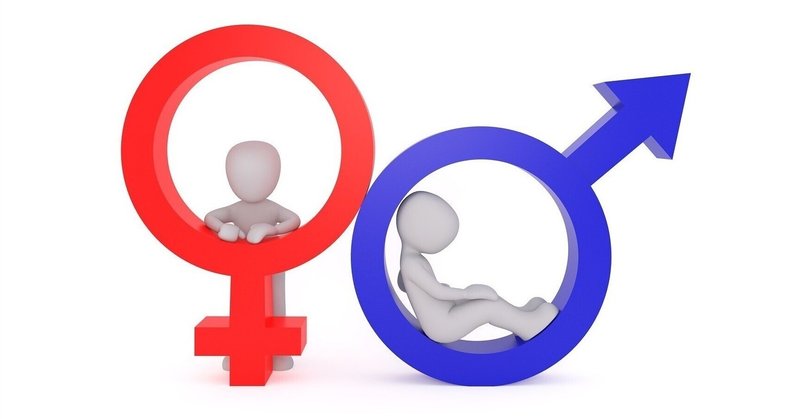
”属性”依存の自己肯定/男性のホモフォビアとモテ
いまだに、淫夢ネタみたいな狭い村での共通言語を反復することで安心を得ようとする輩が多いことにゾッとした。
ホモを男性がさげすみ笑う理由については前回も読んだ上野千鶴子さんが納得いく解釈を書いている。
ちなみに僕は新宿二丁目の男性同性愛者のための店で短期間働いていたこともあり、ホモセクシャルを現実的じゃない珍獣かのように見る考え方はしていない。
その前に題名の「”属性”依存の自己肯定」について書こうと思う。
人間は誰しも属性を持って生まれてくる。
「男性」「女性」という身体的な性別という属性、
「黒人」「白人」「黄色人種」など人種的な属性、
「名字」というのも属性を表すもののひとつ。
そして生まれた後も様々な”属性”を身につけていく。
「〇〇大学卒」というのは学歴という属性、
「〇〇の社員」というのは所属会社という属性、
もっと広く見れば「飲食業」「建設業」など所属業種も属性になる、
細かいところでは「〇〇コンテスト優勝」とか「〇〇と付き合っている」なんてのも属性になり得る。
ここからは自分の体験と観察をもとに書く。
自立(Independent)していない人は、自己(Self-image)をこの”属性”に依存させる傾向が強い。
わかりやすくいえば、自分に自信がないと、属性を隙間なく身につけることによって、変装・武装するようになるということ。
例えば「モテない男性」の話。
男性社会では、男性としての自信を持つために「女性にモテること」が必要な場合がある。
山田詠美の小説『ぼくは勉強ができない』は男性にとってモテることがいかに重要かがひとつのテーマになってる。
その過酷な「モテ」競争に破れたものの中には「男性」としての自信を失ってしまう人もいる。
そういう人は、
[モテる男性 > モテない男性]
という階級構造に取り込まれ、自分が劣位の存在だと思わされてしまうことになる。
もちろんそんなものは「モテるかモテないか」というだけの話であって、「泳ぎが上手いか下手か」くらいの話。
人間としての価値とかそんなものに直結する話ではない。
ただそう考えられない人もいる。
そういう人は「モテない → モテる」へのランクアップを求めて奔走する。
これは「モテる人」という”属性”を身につけ、それを自信の拠り所にしようとしていると解釈できる。
(すべての場合がそうだとはいえないので、単純な性欲以外の動機があると考えた場合の話にはなるが)
これと似たことが有名大学に固執する意識にもいえる。
[Sランク大学 > Fランク大学]という階級構造がある中で、
より高い階級に属するための資格を得ようとする。
つまり自己肯定の根拠として”属性”(モテる/所属大学)を求める構図が通じている。
少し話を戻して「男性にとってモテることがなぜ重要なのか」ということについて書く。
ここは前の記事で触れたBeauvoirの『第二の性』の解釈にもとづいて書く。
少し哲学的な話になってしまうけれど。
一般的に、男性というのは主体的な存在である。
これをBeauvoirは「Transcendenceな存在」と表現している。
では”主体的”とはなんなのか。
それは”客体的でないこと”として捉えられる。
これは英語のPassive文(受身の文)で考えるとわかりやすくて、
ある男性がリンゴを見るとき、
その男性はリンゴを”見ている”ため主体的で、
リンゴはその人物に”見られている”ため客体的だといえる。
つまり「見る側・行動を起こす側」が主体で、
「見られる側・行動の対象」が客体ということになる。
Beauvoirのいう”Transcendence”もこれと似ているけど、
この場合は「自然」(ヒトとしての肉体や本能も含む)に対して、
主体的であるか、客体的であるか、といった意味合いで使われている。
まぁそれは余談なので置いておいて、
じゃあ「男性は主体的である」というのは「どういう対象に対して」なのかというと、そこで「女性」という存在が現れる。
つまり、
「男性は女性を見る主体」⇔「女性は男性に見られる客体」
「男性は女性に行動を起こす主体」⇔「女性は男性の行動の対象となる客体」
という対置が前提になっている。
逆にいうと、もし女性という客体的な「対象」がなかった場合、
男性は「見る対象、行動を起こす対象」を無くしてしまうため、「主体的な存在」であることもできなくなってしまうということ。
これは「上司」という役職が「部下」という人間がいなければなんの意味も持たないことに似ていて。
上司であることを実感できるのは、自分の指示に従う部下がいるから。
もし部下が1人もいなければ、命令を出す相手もおらず、自分が”上司”であるということすらできなくなるでしょう。
長くなってきたので、ここから「男性にとってのモテることの重要性」に話を戻して、
最後に「男性がホモをさげすみ笑う理由」に繋げようと思います。
端的にいえば男性にとってモテることとは「男性であること=主体的な存在であること」を認められることだから重要なのです。
よく女性を「お持ち帰りする」とか「ゲットする」とか「俺の物にする」なんて表現があるけど、どれも女性を物として客体化している表現です。
そんな風に「自分の好きなようにできる対象がいる = 自分が主体であり物事を動かしている」という実感がないと、男性は不安になってしまうのです。厄介な生き物です。
それではなぜ「ホモ」は男性にとってさげすみの対象になるのでしょうか。
ここからは上野千鶴子の解釈ですが、
1.男性は、自分が女性を”ゲットする”、”ものにする”、という構図によって、女性を客体化し、自分の主体性を確立する。
2.ホモの男性を認めてしまうと、自分が”ゲットされる”、”ものにされる”、という客体的な存在になる可能性が生まれてしまう。
3.つまり「男性(主体) > 女性(客体)」という階級構造が変質して、
「ホモの男性(主体) > その対象となる男性(客体)」という構図が生まれてしまう。
これを最初の属性の話とつなげると、
男性というのは、生まれながらに持った「男性」という属性によって、
「女性」という属性に対して「主体的」に振る舞うことができます。
その人がたとえ上司にこきつかわれる「客体的」な男性だったとしても、生まれながらに「女性という客体」が用意されているから、それを逃げ道にできる。
つまり”男性”という属性に頼ることで、自分の主体性を「女性よりは上だ」と自己肯定しているのです。
そうした古典的なジェンダー規範を拠り所とする男性にとって、
ホモの出現は”男性”という属性を変質させてしまう危険なものです。
そうなるともはや”男性”は、主体的でも客体的でもありえる。
男性同士の恋愛やセックスは、主体であるはずの男性が、客体にもなっている。
それを「ありえないものだ」と感じてやたらに嘲笑するのは、
それを「ありえないものにしておきたい」という心理からです。
それがありえてしまえば、自分が寄りかかっている「男性=主体的」という柱が崩れてしまうからです。
ーーーーーーーーーーーーーーー
※以下に記載したのはあくまで参考にした著書であり、
上記文章の最終的な責任はわたし猪股紘樹に帰属します。
参考:
Simone de Beauvoir(シモーヌ・ド・ボーヴォワール)『第二の性(決定版)』
山田詠美『ぼくは勉強ができない』
二村ヒトシ『すべてはモテるためである』
上野千鶴子『女ぎらい ニッポンのミソジニー』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
