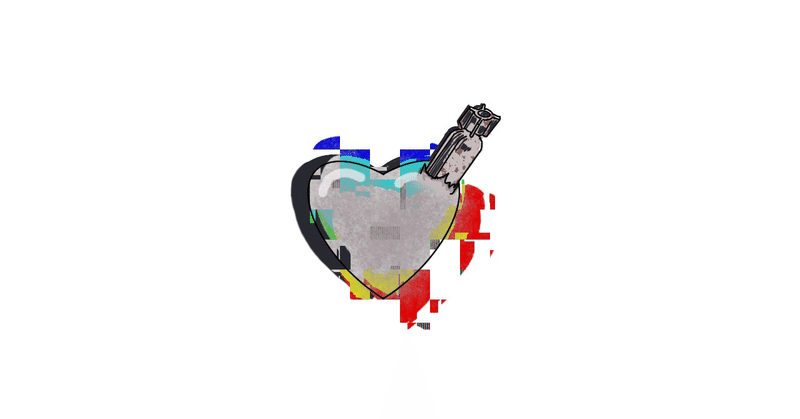
いつか読もうと思っていた本/明日の私に残すnote
ぬこです。
ずっと読みたいなあと思いながら、
仕事が忙しい
読む時間が確保できない
といった言い訳を使い続け、購入に至っていなかった本がありました。
それが、家庭向けの雑誌を発行されている暮しの手帖社さんの『戦争中の暮しの記録』。
暮しの手帖社さんは、その前身、衣裳研究所から始まります。
戦後まもない、物の無い時代でもおしゃれに美しく暮らしたいと願う女性への、服飾の提案雑誌から今のスタイルへ変遷していきました。
その根底に、あの戦争を2度と繰り返すまいという思いがあり、戦後20年あまり経った昭和44年8月15日に刊行されたのがこの本です。
戦場は戦地だけか
この本は、読者投稿総数1736編という応募数のなかから、入選作135編が掲載されています。
ただだだ、その壮絶さ、言語に絶するほどの苛烈さに、向き合うのに大変なパワーがいるものでした。
B5版290頁、そのすべてにびっしりと文字、文字、文字。
魂がこもっていると感じました。
冒頭、暮しの手帖創刊者であり、編集者・花森氏の「戦場」という10頁に渡る詩の、
空襲の跡を単に焼け跡と呼んでいいのか、家を焼かれ、命を奪われたひとびとを「罹災者」で片付けていいのか。
ここは紛れもなく戦場ではないのか、
という一文に、確かにそうではないかと感じ、また、テレビで観るウクライナの人々の姿を思いました。
あの場所も戦場と化しているのだと。
ささやかな贅沢品もない悲哀
私がはっとさせられたのは、勝矢武男さんという方が、戦時中に書いておられた絵日記でした。
段々と、食料に窮するようになる日々が綴られていました。
中でも、
サイパン陥落す。
暑中休暇なれど、夕刻より校庭に緊急父兄会。
校長より、四学年以上学童集団疎開の説明あり。
戦果の巷となる東京に置くよりも、かの地に送るが瑠美子を愛する所以なるを思い、集団疎開に参加を決断す。
日日の歌/勝矢武男
という一文から始まる1日には、思わず息が止まるような思いでした。
まさに、戦況が日に日に悪化している頃なのです。
勝矢さんは、夏休み中の学校で開かれた父兄会に参加し、自身の娘さん、瑠美子さんを東京から疎開させる決断をしました。
疎開というのは、空襲の多い都市部に住む子供や高齢者、女性たちを田舎に分散させることでした。
勝矢さんも、いつ東京が大規模空襲に見舞われるかわからないから、娘さんを少しでも被害の少ないであろう地域に逃がそうと考えたわけです。
そして出発を明後日に控えたある日、せめて今日くらいは贅沢をさせてあげたい、もしかしたらこれが今生の別になるかもしれないからと、瑠美子さんをつれて日本橋から銀座までを歩いて行くのですが、何も、娘さんに買ってあげられるようなものはない。
パン屋一軒すらもなかったのでした。
時代は違っても、たまには子に贅沢をさせてやりたいという親心は変わらないのに、食を奪われ、娯楽を奪われ、文化や芸術を奪われ、何もない、という事実に、何とも言えない気持ちになりました。
生活から彩りが奪われていくのです。
彩というのはすなわち、私たちの精神を豊かにしてくれる芸術・文化をさし、目に映る色をさします。
この彩りというものが生活圏から消えたのがこの戦争で、私はずっと、戦時中の写真は白黒だから、当時は生活自体もモノクロと化してしまっていたのだと思いました。
だけど実のところ、ちょっとだけ違っていました。
色はあった。
でも、色が姿を変えたのだと思いました。
「赤」と聞けば、私は美しい朝焼けの赤や椿の赤を思い起こしますが、戦時中にはこれらの美しい赤を思い起こすような余裕もなかったでしょうし、実際、燃える赤を目にする機会の方がうんと多かったのではないかと思います。
まとめ・3日間読んでいるけれど読み終わらない
読みながら、手が止まります。
まさしく言語に絶する記録の数々です。
空襲に逃げ惑いながら、食糧に窮しながら、日々を戦っていた人たち。
この方たちに、戦後、心安らぐようなことがあっただろうか、あるといいのだけれど、と思いながらひとつひとつ読み進めます。
なんだか世界情勢が不安定になっている昨今、改めて大事に読み進めていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
