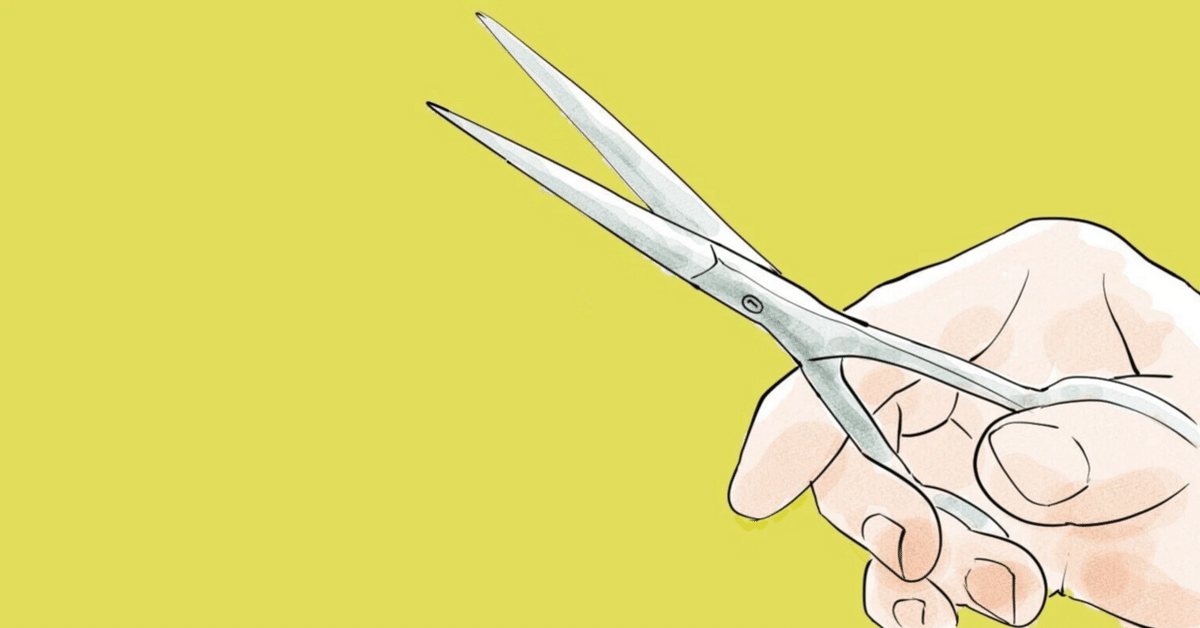
小説:髪を切る理由
軽快なEDMが流れるヘアサロンに居た。
「急なのにありがとうございます」
「ううん、時間はあったから大丈夫。こちらこそありがとうね」
後輩の裕太くんは若い美容師のアシスタントで、前にも一度毛先を整える程度に髪を切り染めてもらった。今日来店できるカットモデルを探しているとSNSで見かけて連絡をしたのだ。
「今日はどうします?」
「特に決めてないのよね。前みたいなのでもばっさりいっちゃっても、裕太くんが似合うと思うように好きにしてくれていいよ」
「え、ショートとかでもいいんですか?髪伸ばしてるって言ってませんでしたっけ」
「…短くてもミディアムでも何でもいいの。暑くなってきたしね。もうTUBEがすぐそこでスタンバってるんじゃない?」
私は笑いながらそう言った。
裕太くんは懸命にいろんな提案をしてくれてミントアッシュのボブに髪型は決まった。絶対にその方が可愛いと言う裕太くんは嬉しそうだった。
「元々ボブの人を切り揃えたりはするんですけど、実は僕ウィッグ以外でこんなに長さを切らせてもらうのは初めてなんです。楽しみだなあ。じゃあ、いきますよ」
ジャキンと耳元で音が響いた。
「駄目だ、暑すぎる。髪切ろうか悩んでるんだけどどう思う?」
数年前の夏、下着とキャミソール姿の私は隣に寝そべる男に尋ねた。
「切るな。ロングのまま」
「何でまた。いつも途中で自分の髪で窒息しそうになるんだけど」
「…好きにしたらいいけど、ロング」
あっそ、と言いながら私はスマホでゲームをする男の肩に顔を埋めた。綻んでしまう顔を見せるのは癪に触る気がしたからだった。
「どこか出る?今日、とても良いお天気」
「出ない」
「やだ、お散歩したい」
「勝手に行ってこい」
その言葉に私は顔を埋めたまま拗ねたように言った。
「1人じゃ出れないから言ってるのに」
男は変わらずスマホで麻雀をしているようだ。
そのまま眠ってしまった私は陽が落ちる頃に起こされて、少し遠回りして一緒に歩いてテイクアウトのコーヒーを買いに行った。信号の横のグラウンドカバーの立性ローズマリーが芳香と共に風に揺れていた。
また男の家に戻り、私が帰宅したのは風が少し冷たい深夜近くだった。
裕太くんは話しかければ笑顔で会話をしてくれるが髪を切る眼差しは真剣そのものだった。途中からは静かにその姿を鏡越しに眺めた。
彼はまだアシスタントなので最後に上司の指導と手直しが加わる。専門用語こそ私には分からないが上司の男性は説明が上手く、黙って聞いている私にも理屈はよく理解できた。裕太くんはズバズバと指摘された点をしっかりと頭に叩き込んでいる様子だった。
髪を切って良かったと思った。若い彼の実践という貴重な学びの機会となるのだ。勤勉な裕太くんはきっとこのまま学び続ければ腕の良い美容師になれるだろう。私の髪でさえ役立つのならば好きにしてくれれば良い。
去年の真夏の夜。
動画を回しながら私はケーキの蝋燭に火を灯した。
「お誕生日おめでとう」
「はい、どうも」
約束したわけではないけれど毎年この動画が増えていった。男が大抵一発で吹き消せない姿を私はいつもケラケラと笑った。
その日の帰り道は自転車を漕ぎながらいつも同じことを考える。
“今年も祝えた。来年は分からないけれど、今年は祝って同じ時を過ごしたのだ”と。
男が私の誕生日を祝うことは一度もなかったが、私は誕生日に良い思い出は少ないのでそれで良かった。元よりこの男に良い思い出で塗り替えてもらえるなんて期待はしていなかった。
ショートヘアにしたことはほんの数回で人生の殆どをロングヘアで過ごしてきた。そんな私が最後にショートヘアにした時に一目惚れをしたという青年がいた。
「ロングもきっと綺麗だけどこの可愛い顔がよく見えてすごく良い」
そう言いながら青年は私の髪を手ですかした。私は髪を切ったことを少し後悔した。
「こういう髪型は本当はもっと小顔で目鼻立ちのしっかりした子の方が似合うのよ」
まあだいぶ傷んじゃったからばっさり切ったけど、という私に青年は言った。
「俺が良いと思うからいいの」
私には青年の言う意味が分からなかった。
いつも側にいたショートヘアのあの子たちはとても可愛かった。私には眩しくて、いつも背中を向けて守ろうとした。
「私たちはセリーナとブレアみたいだね。あなたがセリーナ、私はブレア」
私はあの頃のその言葉がどうしようもなく嬉しかった。
未来の私は過去と同じくして改めて、変わらない素朴さから素直であることの美しさを教わった。それを貫くことは強さだと知った。私の何倍も彼女らは強かった。
「お誕生日おめでとう。まだちょっと早いけれど」
私がそう言って手渡したのは少し大ぶりのドライフラワーのスワッグだった。彼の誕生日を知った後に自宅で干して手作りしたものだ。
以前に彼の家を訪れた時に、整然としたこの部屋にはユーカリのようなシルバーリーフが似合うと思った。白と青を基調とした柔らかいけれど何かを秘めたような凛々しさのあるものが良い。
ドライフラワーにできる青い花はそう多くないので選ぶのには少し難儀したが、白い薔薇と少しのカスミソウ、青みがかった刺々しいエリンジュームなどを纏めた。
手作りのものなどどう映るか少しばかり心配だったが予想以上に喜んでくれた。
彼は私をしっかりと抱きしめて言った。
「ありがとう。すごく嬉しい」
「ゴッホの白い薔薇、好きだって言ってたでしょう?」
「覚えててくれたんだ。本当に、綺麗」
彼の言葉は至極シンプルだった。しかし私はこれほどまでに言葉と行動で気持ちが伝わってくるものなのかと少し驚いてしまった。私は湯船に包まれたように温かく満たされた。
「この瓶に入れたいな」
彼が手にしたイタリア語の酒瓶にはまだそれなりの量の酒が残っていた。
「ラベルの色と字体がよく似合うわ。でも口が狭くて入らないかも」
そう言いつつも酒はあっという間に2人で飲み干してしまった。そして彼が徐ろに持ってきたのは紙袋とトンカチだった。
バリン、と真夜中に不似合いな小気味良い音が響く。割れた酒瓶に入れられたスワッグは白いスピーカーの隣に飾られた。暖色のライトに照らされたその光景を私たちは暫く黙って見つめていた。
「でも本当に良かったんですか?僕としてはありがたいですけど、こんなに切っちゃって」
店内にはカラー剤を塗る彼と私の2人きりだった。
「いいのよ。私癖毛だからやりづらかったでしょう?でもそれが裕太くんの経験になるなら光栄だわ」
「…何か、あったっすか。切った理由」
そうね、と言いながら私は少し黙った。
連絡が途絶えて察した私はさて今回はどれ程持つかなと思った。4ヶ月、半年ちょっとか。長ければ8ヶ月か1年2ヶ月。
そうすればまた連絡が来るのだろう。当たり前のように変わりのない私は戻ってくると思うのだろう。
私は連絡一つ寄越されればまたきっと会いに行く、かもしれない。私は塗り替えられ、当人の知らないうちに私が塗り替えたことを今になって本人も自覚している頃だろう。私たちは利害と恩と哀れみも含めた息で太く繋がっていた。
でも、今年の誕生日はきっと祝えない気がする。
今までと違って、もう連絡が来ることはないかもしれない。そんなことは出会った頃から何ら変わりのないことだった。
私はいつか会うかもしれない日に変わらない姿を見せるのがどうにも癪だったのだ。染め上げられた衣を纏った私だって日々他の色を吸収しているのだ。
私が髪を切った理由なんて、そんなくだらない負け惜しみだ。フラストレーションを晴らしたかっただけだった。私が髪を伸ばしていた理由はそんな時にスカッとした気持ちになれる為の保険や貯金のようなものだった。
「夏の始まりをいつまでも嫌いでいたくなかった、そんなとこよ」
これ以上何も言う気はない私はにっこりと裕太くんに微笑んだ。
ドライヤーをして髪を丁寧にセットしてもらい、私は軽やかな足取りで店を後にして1人で飲みに行った。柔らかなグリーンを帯びたグラデーションの髪は私も大層気に入った。
夜風が髪を抜けてゆく。何だか強くなったような気分だった。
「お姉さんはどういう人がタイプ?」
先ほどまでは常連客だという中年夫婦と楽しく飲んでいたのだが入れ替わるように入ってきた若い男が先ほどからやたらと距離が近い。
「人間への理想なんて挙げたらキリが無いから考えないです」
私は前を向いたまま答えて酒を飲んだ。
「キリが無いなら俺だって一つぐらい当てはまるところあるかもしれないじゃん。俺、一目惚れしちゃったかも」
白々しく腰に手を回されたので私は男の方に向き直ってその手を外した。
「死んだようなアーモンド型の二重の目で逆まつげ、髭が生えてて結べる程のロン毛の男」
若い男はたじろいだようにもごもごと何か言っている。
「筋肉が綺麗で思慮深くて色に自分の拘りがあって寂しい時に私で埋めようとする人」
私の口は止まらない。
「優しくて、狂気的で、私には無いものを教えてくれて、自分の知らないことを私から学んでくれて、言葉を大切にしていて、風景を愛して、美しいものを美しいと言えて、知識を互いに分かち合えて、一緒に馬鹿なことをして、善く在る為に弱さを開示する勇気を出せて、時々突飛もないものを見せてくれて、何も話さずに居られて、一緒に過ごす間は私のことを大切にしてくれる人」
「えっと、誠実な人が好きってこと?」
「いいえ、屑な人が好きよ。安心できるじゃない」
「ちょっと難しいなあ。随分具体的だけど、誰かのこと?」
「言ったでしょう?理想や好みなんてイエスかノーで答えられるものも含めたら無数にあるの。何も異性に限ったことではないわ。完璧な恋愛対象も、完璧な友人も、完璧な都合の良い人間も、完璧な自分も居ない。折り合いを付けるの。
だから、考えない。考えるのはどこまで受け入れられるかどうかだけよ」
若い男はヘラヘラと笑っている。
「難しいこといっぱい考えているみたいだけどさ、優しい人も好きなんでしょ?俺、優しいよ」
「それだけ?」
「あとは何が必要なの?」
そうね…と私はグラスの中身を飲み干した。
「花瓶が無ければ真夜中に酒瓶を割るような豪快な思い切りの良さ」
今日も今までと違う色になった私はじゃあね、と笑って1人で店を出た。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
