
『舞踏会』芥川龍之介 「全部が優雅だ」と、物憂げに
○はじめに
このnoteは、本の内容をまだその本を読んでない人に対してカッコよく語っている設定で書いています。なのでこの文章のままあなたも、お友達、後輩、恋人に語れます。 ぜひ文学をダシにしてカッコよく生きてください。
『舞踏会』芥川龍之介
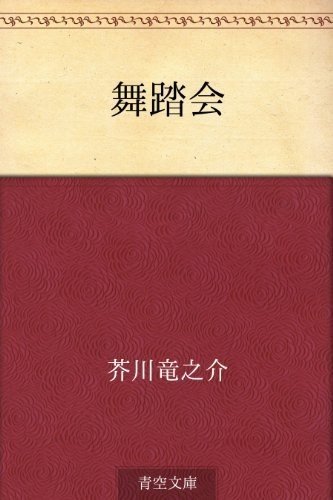
【芥川龍之介を語る上でのポイント】
①『芥川』と呼ぶ
②芥川賞と直木賞の違いを語る
③完璧な文章だと賞賛する
の3点です。
①に関して、どの分野でも通の人は名称を省略して呼びます。文学でもしかり。「芥川」と呼び捨てで語ることで、文学青年感1割り増しです。
②に関しては、芥川賞は純文学、直木賞は大衆文学に贈られる賞です。それ以上はよくわかりません。
③に関しては、芥川はその性格上完璧を求めるが故に短編が多いです。僕個人短くて凝ってる文章が好きなので、まさに芥川の文章は僕の理想です。
○以下会話
■優雅で上品な小説
「優雅な小説か。そうだな、芥川龍之介の『舞踏会』がオススメかな。『舞踏会』は芥川が28の時に書いた小説で、芥川中期の代表作と呼ばれているんだ。内容は、明治19年に鹿鳴館の舞踏会に招待された娘が、フランス人海軍将校に踊りを申し込まれる恋の話なんだ。構成としては、その舞踏会の32年後に、老婦人になった主人公があの頃を思い出すという構成なんだ。文章は優雅で上品で、18世紀のロココ様式のような雰囲気で書かれているんだよ。
■17歳の明子とフランス海軍将校
『舞踏会』は、17歳の明子が父親と一緒に鹿鳴館の階段を登るシーンから始まるんだ。初めての舞踏会に明子は「愉快なる不安」を抱えて、話しかけてくる父親の声にも上の空で対応していたんだ。「ほとんど人工に近い」菊の花が美しく並ぶ階段を登りきり、会場の扉を開けるんだよ。すると、既に会場にいた人たちは、薔薇色のドレスを身にまとった明子を見て、皆その美しさに一瞬驚いて、ため息をつくんだよ。明子は皆の反応を見るうちに段々と緊張が溶けていくんだ。会場を歩いているうちに、あるフランスの海軍将校に踊りを申し込まれるんだよ。
明子は申し込みを承諾し、二人はしばらく優雅に踊るんだよ。その後、腕を組みながら下の階にある広い部屋に入ったんだ。明子は、海軍将校がじっと明子のことを見つめているのを知って、気恥ずかしさから近くにいたドイツ人を見ながら「西洋の方は美しいですね」と言ったんだ。海軍将校は首を振りながら「日本の方も美しいです。特にあなたは美しい。アントワーヌ・ヴァトーの絵のお姫様のようです。」と言うんだ。明子は、アントワーヌ・ヴァトーを知らなかったから、海軍将校が喩えた美しい幻想は名残なく消えていくんだよ。
そして二人はテラスに出て夜空を眺めるんだ。すると、美しい花火が一つぽんっと上がったんだよ。それまでざわめいていた会場も、一瞬静かになって、口から感心したため息が漏れたんだ。花火が消えても夜空をじっと見つめる海軍将校に、明子は「お国のことを思っているのですか」と聞くんだよ。海軍将校は子供のように首を振るんだよ。明子は「でも何か考えてるようでした」と言うと、「なんだか当ててごらんなさい」と言われるんだよ。するとまた、会場の声が一瞬止まったんだ。二人は話をやめて、夜空を見ると、赤と青の花火がすーっと広がって、消えていったんだ。明子はその花火を、悲しい気持ちになるほど美しく思ったんだ。
海軍将校は「私は花火のことを考えていました。私たちの生命のような花火のことを」と言って、明子を優しく見つめるんだ。
そしてそれから32年後、大正7年の秋。老婦人になった明子は、汽車に乗っていたんだ。同じ席に座った、菊の花を持った小説家の青年に「菊を見ると思い出す話がある」と言って、舞踏会の話を聞かせるんだよ。青年は何気なく「そのフランスの海軍将校はなんというお名前ですか」と聞くんだよ。明子は「ジュリアン・ヴィオという方です」と言ったんだ。すると青年は興奮気味に「ではその方は『お菊さん』を書いたピエール・ロティだったのですね」と言うんだよ。そして明子は「いえ、ロティではありません。ジュリアン・ヴィオという方ですよ」と言うんだ。これでお話は終わり。
■誰にも邪魔されない恋
最後の部分がちょっとわかりにくいよね。当時、本名が「ジュリアン・ヴィオ」で、ペンネームが「ピエール・ロティ」で、活躍していたフランスの作家がいるんだよ。ロティは日本に来たことがあって、『お菊さん』とかを書いたんだ。明子と踊った海軍将校は、このピエール・ロティだったんだ。
ピエール・ロティの本名を知らない明子は、青年に言われても意味が理解できず、「ロティさんじゃないですよ。ジュリアン・ヴィオという人ですよ」と言ってしまうという終わり方なんだ。
この終わり方は、舞踏会での二人の夜を「無名の二人の幻想的な思い出」にする効果があるんだよ。17歳の明子は、不安とウキウキがごちゃ混ぜになった感情で、初めての舞踏会を経験したんだ。そこで出会った海軍将校は、17歳の思い出として誰にも邪魔できないものなんだよ。きっとその舞踏会以来、二人は再会していないんだよね。その思い出の海軍将校は、ピエール・ロティという有名な作家ではなく、ジュリアン・ヴィオという一人のフランス人の青年であることに意味があるんだ。「有名な人の恋物語」よりも「無名な人の恋物語」の方が淡い気がするでしょ。名のない二人の若者が、花火のような美しく儚い恋をしたんだよ。
同じように、海軍将校が「アントワーヌ・ヴァトーの絵のお姫様のように美しい」と言った時に、明子がアントワーヌを知らなかったのにも意味があるんだ。アントワーヌはロココ調を代表する画家なんだけど、この「世間」の事例を明子が「わからない」、つまり否定することで、より二人の世界が世間とは離れた、花火のように上空に打ち上がった幻想的な思い出になるんだよ。

『シテール島の巡礼』アントワーヌ・ヴァトー
■三島「芥川の長所ばかりの出たもの」
この小説を三島由紀夫は「芥川の長所ばかりの出たもの」と絶賛してるんだ。実際に作品解説で、「青春の只中に自然に洩れる死の溜息のやうなもの」があるのが良いって言ってるんだよ。確かに三島が『舞踏会』を好むのはめちゃくちゃ分かるんだ。『金閣寺』にもまさにその美意識が反映されていて、三島は「究極な美」が好きなんだよ。もし僕が三島と知り合いだったら、「三島さん絶対好きですよ」ってオススメするくらい。まさに三島が目指す「美」の世界だなって思う。
完璧主義の芥川らしい、一言一句が全て美しい小説になってるから、是非読んでみて。」
この記事が参加している募集
お賽銭入れる感覚で気楽にサポートお願いします!

