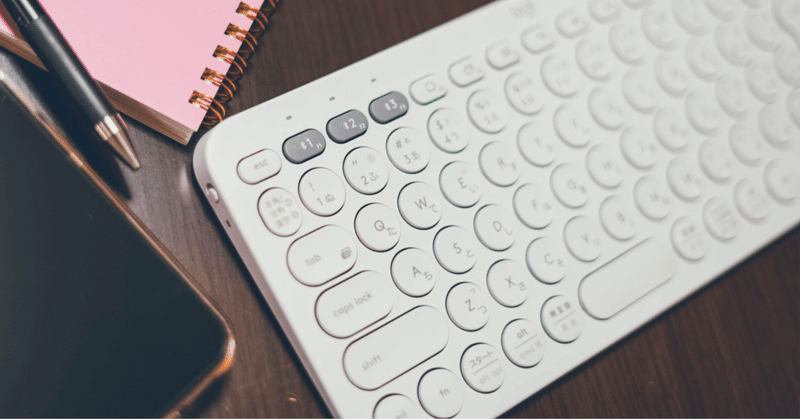
面接
面接官の眼鏡が光った気がした。照明に反射しているのだろうけれど、画面越しじゃ現実味がなくて、漫画の一コマみたいだった。
私の瞳もハート形に光っているのだろうか、とパソコンに取り付けた小さなライトを盗み見る。雑誌の付録だったハート形のライトがこんなところで役に立つとは、人生何があるかわからない。
そもそも面接をオンラインでやっていることも、私がスーツを着て髪を黒く染めていることも、真面目に働く未来を選んだことも、何もかも予想外のことだ。しっかり未来予想図を描いたことはないけれど、もっと違った道だってあるはずなのに、世間的な正しさに飲み込まれようとしている。悪いことじゃない、でもどこか寂しい。画面越しじゃわからないだろうと、半袖のシャツに羽織ったスーツの裏地が冷たい。
「すみません、もう一度お願いします。回線がちょっと」
精一杯申し訳なさそうな顔で言った。聞き逃したことを電波のせいにできるから、オンラインの面接は楽だ。まだ口馴染みのないセリフは、パソコンに立てかけたカンペが補ってくれる。ついでに書いた背筋伸ばす、の文字は毎回忘れられていて、今日も猫背は全開だ。
「貴方がこのアルバイト先を選んだ理由はなんですか」
面接官は電波が悪いならしょうがないね、という風に質問を繰り返した。さっきまでとは違う話題だった。手元のアンケート用紙を眺めているのだろう。
都心にある飲食店で二年間働いていた。アルバイトと言っても、小遣い稼ぎくらいの出勤頻度だった。実はついこの間辞めたけれど、辞めたことを言えば理由をセットにしなきゃいけないし、心象が悪そうだから言わない。
面接は駆け引きだと思う。どれだけ相手に有益な情報を渡せるか、それはひっくり返せば、不利益な情報をどれだけ隠せるか、だ。そのためには多少のごまかしは許されると思っている。どうせばれやしないし、舐めてかかるくらいが私にはちょうどいい。余裕があるひとのほうが魅力的にみえるってこと、この数年間で思い知らされてきたんだ。
どこまで言おうか逡巡して口を開いた。
「消極的に聞こえたら嫌なんですけど」
正しい敬語は使えないままだった。ですます調だけしっかりしていれば十分だろうと高をくくっている。言葉遣いが原因で落とすようなところは、入っても窮屈なだけだ。ちょっと緩いくらいがいちばん居心地がよくて、私のいるべき場所だと思える。
「髪色が自由だったからです」
駅から近いとか、時給がいいとか、お洒落ができるとか、そういう条件の積み重ねで決めたのだ。飲食店を選びたかったのではなくて、条件で厳選したらそこになって、受けてみたらその場で採用されたというだけ。だから強いて言うなら、理由は髪色の自由さだった。
「そういうことできるのって大学生のうちじゃないですか」
何歳になっても、どんな仕事をしていても、髪色で遊べたらいいんだけど。
「だから選びました」
「へぇ」
面接官は曖昧な相槌を打ちながら次の言葉を探していた。もっとしっかりした理由が来るとでも思っていたのだろうか。だとしたら、貴方の学生時代はどうだったんですか、と質問を返したいけれど。
変に間が開くのが嫌で、エピソードを追加することにする。
「去年は全部青とか、緑とかにしてました」
「すごいね」
「一度やってみたかったので」
興味があるんだかないんだか、気の抜けた返事に感じた。電波に乗せることで感情は伝わりにくくなるから、もっと大きく反応すればいいのにと思う。選ぶ側と選ばれる側にきっぱり分かれているようにみえるけど、こちらにも選ぶ権利はあるんだから、お互い様なんだよ。
「何か変わりましたか?」
変わりたいとか、そんな大義名分を背負って髪を染めたつもりは全くない。しかし何か理由がないと、髪色を変えることは理解しがたいとでも言うような問いだった。
地味な服装をした面接官が急につまらなくみえた。つまらなくみえたせいで、興味が湧いた。このひとたちは学生時代、どんな格好でどんな毎日を過ごしていたのだろう。どんな勉強をしてどんな遊びをして、ひとには言えない秘密を抱えたりしたのだろうか。それが青春だったと言えるようなきらめきで満ちていたのだとしたら、その美しさを損なわずに生きてほしいと願う。私も、それを損なわずに生きていく。面接という短時間の一期一会でわかるくらい、いつだって輝いていたい。
面接官を笑わせたくなった。この時間が楽しかったと思ってほしくなった。だから少しのユーモアを添えて。
「人混みでぶつかられる回数が減りました」
この話を面接でできることが、収穫のひとつかもしれなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
