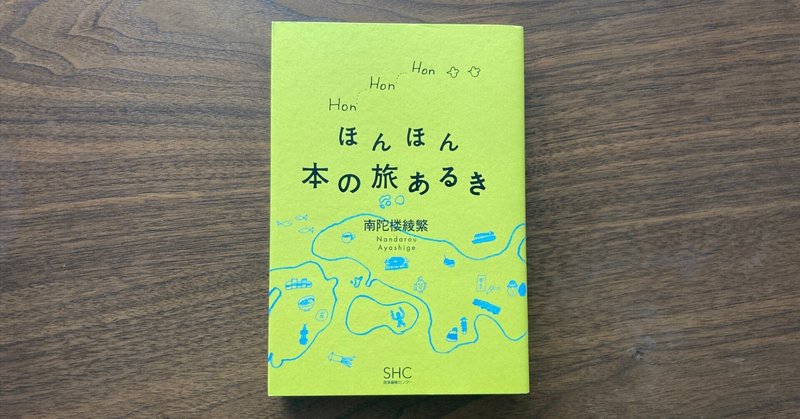
書店で本が多すぎて選べない問題
先日、友達がこんなことを言っていた。
「本屋に行くんだけど、本が多すぎて選べない。目が滑ってしまう」
確かに、最近の本屋は売り場の大型化が進み、その中から自分好みの一冊を選ぶとなると途方に暮れてしまう。
ただ、私も書店員の端くれ。
その友人には、「エッセイの棚から興味のある本を選ぶ」という方法を提案しておいた。
本屋が広すぎて選べないなら、自分で見る棚の範囲を限定すればいいのだ。
「この棚から1冊は買うぞ」
そういう心持ちで見れば、記号にしか見えなかった背表紙の文字も、ようやく頭に入ってくる。
ただ、小説を選ぶのは難しい。
タイトルから内容が推測しづらいからである。
例えば、私が最近読んで面白かった小説に『夏の庭』という本がある。
このタイトルから得られる情報といえば、「まあ季節は夏で、庭に関する話なんだろう」くらいである。
正直、買うには至らない。
実際、自分がこの本を買ったのも、好きなマンガの作中で紹介されていたからである(読んでみたらめっちゃ面白かった)
それに比べてエッセイである。
例えば私の手元にはこんな本がある。
『貧乏大好き~ビンボー恐るるに足らず』
『やりたいことは二度寝だけ』
『電車の中で本を読む』
エッセイのタイトルは、頭にスッと入ってくるので、選びやすい。
実際、これらの本はタイトルに惹かれて買ったものばかりである。
思うに、小説のタイトルは読んでから深みを持って理解できるのに対し、エッセイのタイトルはその内容を説明するものになっているのではないか。
だから、エッセイの棚はなんだか親近感が湧く。
そこでなら、自分にあった一冊を選ぶことができるだろう。
ただ、お気に入りの一冊を見つけても尻込みしてしまうことがある。
「買ったあとでもしもこの本が面白くなかったら、お金がもったいない」と思ってしまうのだ。
これについてはこう言いたい。
それでも買うのだ、と。
自分が選んだ本が、実際読んでみたら面白くなかったなんてことは、正直ざらにある。
ただ、それを繰り返していくうちに、自分の中で本を選ぶ基盤ができていく。
そうなってから初めて、本屋の中を自分の足で歩けるようになる。
気になっている一冊をお金のために買わないというのは、読書の習慣自体から遠ざかることを意味する。
買わないという選択をすれば当然家に帰っても読む本はないし、「本屋で本を選べなかった」という思いは、今後本屋に行く足を鈍らせる。
たった1000円のために、人生を豊かにする読書から遠ざかってしまうのはもったいないことだと思う。
だから、本屋で本を選ぶときに必要なのは、「とにかく一冊買うぞ」という気概である。
そうして買った本が面白くなかったら、読むのをやめて次の本を買いにまた書店に行けばいいのだ。
そこで重要なのは、間違いなく面白い本を選ぶことではない。
面白い本でなくてもいいから、自分で本を選んだという経験なのである。
それを続けていくことで、本屋に体が馴染んでいく。
アウェーだったはずなのに、いつのまにか本屋に行くと落ち着くようになる。
そして気がつくと、本屋の広さは本を選ぶのに不自由な広さではなく、自分の興味関心が動き回るのに不自由のない広さになっているのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
