
異業種と情報を共有することが、新たなイノベーションには不可欠
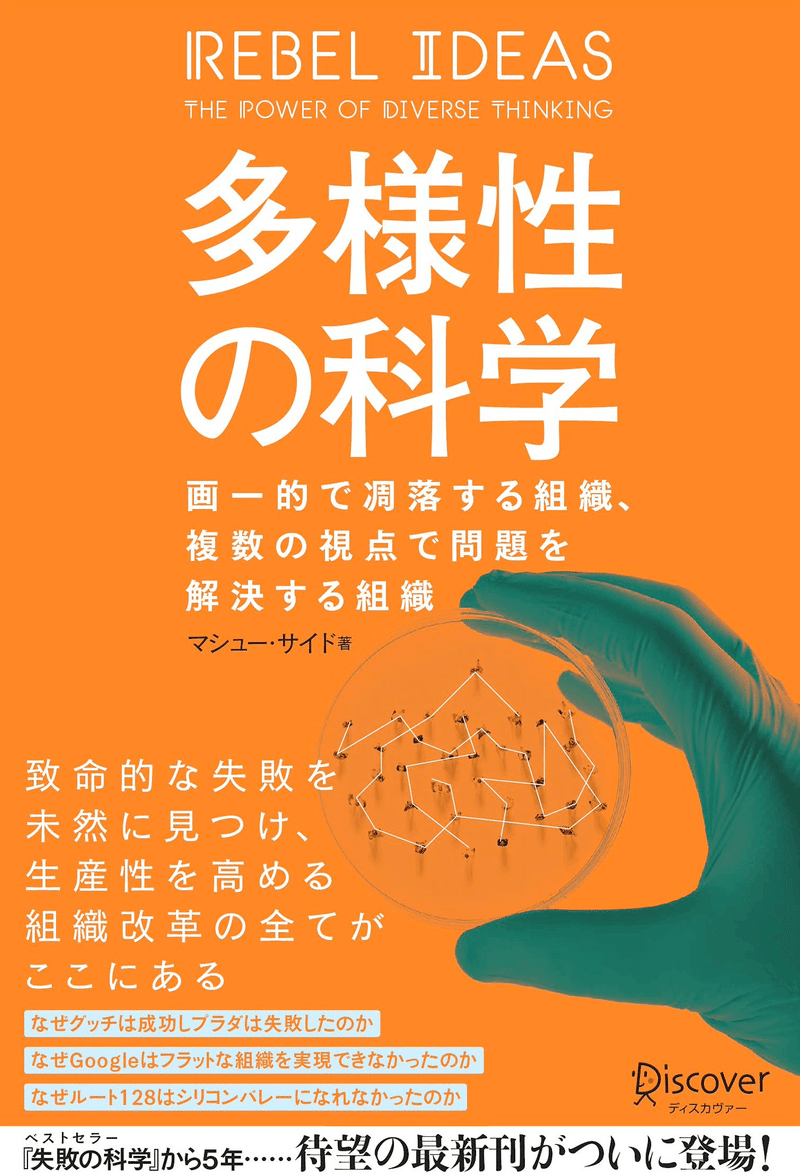
多様性って難しい。
最近ではセクシャルマイノリティな人を差別することはいけませんとか、女性の社会進出をもっと促進しましょうとか、その他いろいろな面で多様性を重んじる風潮が根付いてきている。
人間は誰一人として同じ人はなく、性別も体質も思想も文化も価値観も人の数だけ存在する。
誰一人として排除されることなく受け入れられなければならない、それぞれの人を尊重しつつうまく社会を回していきましょう、というのを簡単に言えば「多様性」ということになるんだろうか。
たしかにそれは大事なことではあるけれど、「多様性」という便利な言葉を盾に、自分の主義主張を押し通そうとするのはまた違うんじゃないかと思うのだ。
世間のことはよくわからないけれども、「多様性」とは強いるものではなく、各人それぞれが自分とは違う者を受け入れようとする「受容力」みたいなものじゃないかと思う。
「多様性」によって人類は新たなステージ、より一歩高いステージに進化するために必要な考え方だと思う。
この本で言うところの多様性とは、色んなバックグラウンドや知識や専門性がある人とコラボレーションすることで、自分 1人では気づかなかった、発想できなかった考え方ができるようになり、より柔軟に物事を思考できるようになる、その結果今までになかった新しいイノベーションが生まれる、ということ。
自分と同じような思想や専門性を持ったスペシャリストが集まったって、結局は同じフィルターで見ているのでそこに大した違いはない。
でも、全く別の分野の専門の人が加わることによって、違った分野の掛け合わせが突飛な発想を誘発し、考えても見なかったようなものが生み出される可能性が高まる。
かのスティーブ・ジョブズだって、「新しいアイデアは既存のものの組み合わせで生まれる」と言ってたけど、その既存のものが違う分野であればあるほど、一見関係なさそうなものであればあるほど、新しい突破口が生まれやすくなる、ということらしい。
そしてさらに大事なことは、自分の知識を出し惜しみせず、同じチームの人たちと情報を「共有すること」が不可欠ということ。
解決すべき問題に、それぞれが持っている情報を共有して全体像を浮かび上がらせなければ、どこに問題があるのか、何に対処しなければいけないのかが見えなくなってしまう。
情報を共有するためには、各人同士の「信頼感」や「受容力」も必要になってくる。
いくら情報を伝えたところで、それを受け入れようとしなかったり聞き入れようとしなければ、正しく物事を冷静に判断することができなくなる。
多様性には年功序列や先輩後輩などの立場は必要なく、フラットに話せるような環境でなければ効果を発揮しない。
どんなに突拍子のないことだとしても、どんなに些細なことだとしても、それを思い切って言葉にして問題提起できるような環境が整っている必要がある。
それが「心理的安全性」につながってくる。
「多様性」とはただ単に色んな人を受け入れなきゃだめだよね〜、みたいな生半可で優しいものではない。
本気で多様性をとり入れようとすると、自分と違った意見の人の話も聞くことになる。
自分が行った意見に反論しようとしたり、批判される場合だってあるかもしれない。
そんなときに感情的にならずに冷静に話し合うことができるだろうか?
自分が攻撃された! と牙を向いて相手に食ってかかろうとしないだろうか?
そんなことになれば、人類は進化ではなく退化することになってしまう。
最近は SNSやインターネットによって情報化社会になっているけれど、情報があればあるだけ自分の思想や信念と同じようなものを探しやすくなる。
自分と似た考えの人たちで集まると自分たちの考えが正しいように感じられ、視野が狭くなり、その他の意見を受け入れられなくなるか、または排除しようとするようになる。
「情報」の取扱たかたを間違えれば争いの火種となり、人間は狩猟採集民の時代に巻き戻り、異質なものを排除しようとするだろう、と書いてあった。
つまり多様性は大事なことだけど、簡単に言うほど取り扱いは簡単ではないよ、ということ。
多様な意見を取り入れ、まとめ、決断を下すということは並大抵のことではない。
人々がお互いに協力し、それぞれが納得できるところまで落とし込み、時には妥協しながら解決を目指す。
多様性は何でも受け入れられる、という魔法の言葉じゃない。
受け入れられるのではなく、受け入れる度量の広さを各人が求められている、という気がしている。
多様性は人間性の進化を測る物差しになるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
