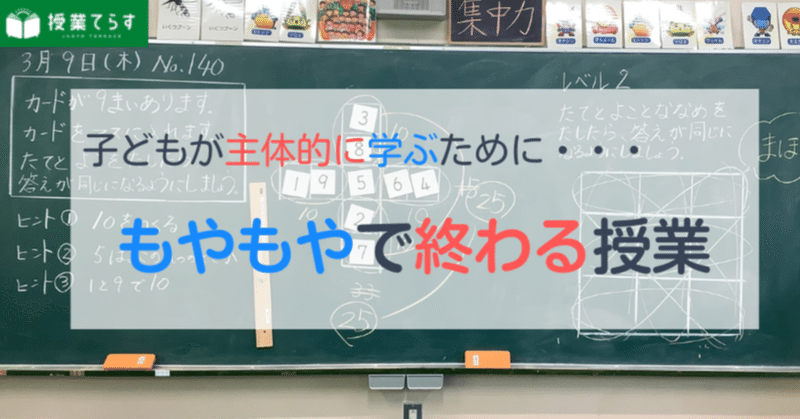
もやもやで終わる授業
1、はじめに
算数といえば、問題解決型の授業というイメージがありませんか?
「問題提示→課題提示→自力解決→集団検討→まとめ→適応問題→振り返り」という流れで算数の授業を行なっている先生方が多いのではないでしょうか?
しかし、決まった流れの型通りの授業をしていれば良いのでしょうか?そんな疑問を私はもち、授業改善を行ってきました。
2、「めあて」っているの?
まず私が、はじめに行った授業改善は、「めあて」の提示をやめたことです。「めあて」は本時の学習のゴールであるから提示するべきというご指導をいただいたこともあります。しかし、学習のゴールを知っているのは教師であり、ゴールを一方的に教師から示すのは、教師主導の授業であると私は考えています。
では、「めあて」とは何なのでしょう?
私は、「めあて=子どもの問い」という言葉が一番良いと考えています。教師からめあてを与えるのではなく、子どもの素朴な問いからめあてをつくっていく授業の方が私はすてきだと思っています。
子どもから「自然な問い」を生み出すのは教師の授業力だと考えています。教材の工夫をしたり、教師の言葉を考えたりすることで子どもたちから「問い」と引き出すことができます。
子どもが「あれ?」「なんで?」と考えたくなる教材。授業のポイントに迫っていく発問。他にも「問い」を生み出すには、様々な要因があると思います。私は、現在上記の2点に絞り、日々の授業実践を行っています。
3、しかし問題が、、、
子どもの「問い」を引き出す授業を意識して、授業を行っていました。
しかし、大まかな流れは問題解決型の学習と変わりはなかったのです。
「教師からの問題提示→問いの共有→自力解決→集団検討→新たな問いの共有→自力解決→集団検討→解決」という流れが私の授業でした。
この授業の流れだと、子どもは本当に主体的に動いているか疑問をもちました。授業の中では、子どもたちは、生き生きと考え議論を行います。しかし、それは教師の与えた土俵の上で考えているだけなのです。
私が、違和感を感じる理由の中に、「きれいに授業を完結している。」ということを考えました。1時間の最後に答えが共有された後、子どもたちは「スッキリ」「なるほど」「ふーん」「終わった」などの感想をもつのではないでしょうか。授業で答えが分かってしまうため、それ以上を考えないのです。授業中しか学ぼうとしない子どもたちは、果たして主体的なのでしょうか?
私は、子どもが教師に与えられた課題だけをやっているのは、主体的ではないと考えています。自分から、「学びたい」と思えることが大切なのだと思います。
つまり、答えを最後に共有してしまうことで、主体的に学習に向かえない子どもたちが育ってしまうのではないかと考えています。そこには、子ども一人一人の問題ではなく、教師の授業力が大きく関係するのだと考えます。
4、もやもやで終わる授業
上記の問題を解決するために、私が至ったのは、「もやもやで終わる授業」でした。これは、現在考えていることなので、また考えが変わるかもしれません、、、。
ある日の算数授業のことです。時間が足りず、授業の最後に答えの共有をしないで終わりにしてみました。すると、子どもたちからは、「答えを教えて欲しい。」という声が聞こえました。答えを求めることにこだわっている子どもがいると反省しました。子どもたちの声は聞こえていましたが、答えは共有しませんでした。
すると、どうでしょう。授業が終わった後に、ノートに向き合う子どもや友達同士で考えを話し合う子どもなど、学び続けようとする子どもたちの姿が見られました。学校だけでは、答えが求められず、家に帰ってから家族と考える子どももいました。すてきな姿だと私は思いました。
授業の最後に答えを共有しない、「もやもやで終わる」だけで、子どもたちが主体的に学んだのです。私は、「続きをやりましょう。」とは言っていません。子どもたち自らが動き出したのです。
次の日の学習は、前時のもやもやを解消するところからのスタートです。その際に、家で問題に取り組み、正解を導き出した子どもにスポットを当てました。頑張った子どもがヒントを出す場面をつくることで、すすんで学習することの良さを学級全体に価値付けました。
「もやもやの解決→新たな問題→問いの共有→自力解決→集団検討→もやもや」とすることで、より問題が子どもの方に近づいたと感じています。しかし、更なる新しい問題を教師から与えてしまっているところなど課題はまだ多くありそうです。
もやもやを解消する過程で、発展的に問題をつくろうとする姿が見られることもありました。問題を子どもたちに近づけることができた結果だと思います。子どもたちは、問題を自分ごととして捉えることができたのだと思います。しかし、全ての時間で子どもたちが発展的に考えることができたわけではありません。今後、子どもが毎時間、新たな問題設定をできるような実践ができたら良いと考えています。
5、おわりに
授業展開を少し変えることで、子どもが動き出すことを改めて学びました。まだまだ、私が知らないことが多い世界だと感じています。よりよい授業を目指し、今後も精進していこうと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。
かずや_鈴木一矢@東京
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
