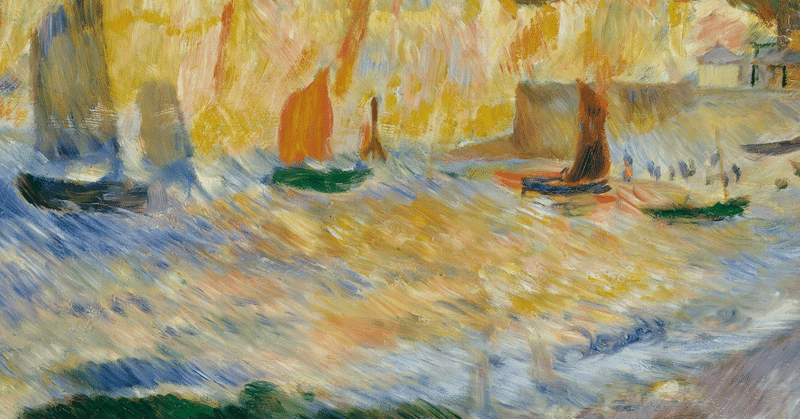
003:トキメキ二重奏【ユーメと命がけの夢想家】
前回
目次
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
「二人組、できたかなー?」
教官の一言が、死刑執行の合図のように聞こえてしまって、マルサイは情けなさと屈辱でいっぱいになった。
「きょーかぁん、ここらへんにまだの人がいます」
すかさず、ひょうきん者のレイトロが手をあげる。そして、おどけた調子でマルサイの付近を見渡すのだ。
「あれえ、どっこだあ、見えないなあ」
教室はくすくすと笑い声がにじむ。
……だからイヤなんだ。
7才のマルサイは、ことあるごとにチビで出来損ないと嗤われた。チビで出来損ないであることが、まるでクラスの結束を固める重要な要素であるとで言いたげなほどだった。
クラスが結束を固めるたびに、マルサイは拳を震えさせるのだった。
「このクラスはまだ欠員を出してないから、余ることはないんだけど……」
「教官」
挙手がなされた。しかし、その挙手するさまを見る者は、教壇に立つ先生のほか、誰ひとりとしていなかった。
比較的前方の席で、腰から右手中指のつま先にいたるまで、ぴんと伸びる姿であるにも関わらず、である。
「わたしが残っています」
先ほどまで騒がしい空気が一変、静寂が突如として訪れた。拳を震えさせていたマルサイはしかし、安堵の情など抱くはずもなく、今度は全身をがたがた震えさせるのであった。
「ミス・アナン。そうでしたか。それではミスター・マルサイ、〈二重奏〉の主体学習では、ミス・アナンと組みましょうか」
「はい、教官」
マルサイは快い返事をした。教官の命令は遵守せよというのがこの学院の規則なのだ。
それに、ここで渋るような態度を見せるのは、彼からすれば格好わるいことだと思えた。もちろん、心中曇天模様であることは疑いない事実であるのだが。
アナン。
同い年の女の子とは思えないバケモノ。
〈学院〉きっての〈能力〉の持ち主。
それがマルサイの抱く印象であり、それは〈学院〉、すなわちサイトU92・スチャキレンコ235区の院生の共通認識であった。
「やったなマルサイ! 〈ドアノブ〉に触れるときは、気を付けるんだぞ!」
ひょうきん者のレイトロが軽口を放った。マルサイは起立し、再びざわつく教室を歩く。そして、自身の席で腕を組んだままのアナンの横に立つ。
彼女の釣り上がった視線が向けられると、マルサイの頬にパチパチと静電気が奔った。
「アナン、また、よろしく」
静電気につられて、自ずと彼の顔は引きつった。
「いい加減、顔を見るのも飽き飽き」
期待の欠片もないアナンの顔は、すぐに真正面を向いた。
「〈二重奏〉なんて、あなたできるの?」
「やるしかないだろ。俺だって〈熱い湖〉に埋められたくはないんだから」
ふたりはあまりもの仲間で、組になれば必ず一緒にはなるものの、傷を舐め合うような間柄ではなかった。
二人の挨拶を確認して、教壇の先生はパチンと手を叩いた。
「それじゃあ改めて、主体学習をはじめますね。教えたとおりに〈能力〉を引きだしてみて」
指示に対して、アナンは少しも動じる様子はない。
「教官の命令は遵守、だぞ」
そう耳打ちしようと顔を近づけると、バチ、と強烈な電撃がマルサイを襲う。
「順守するのはあなたよ、出来損ない」
アナンは言い放った。
「だって、わたしはとっくに〈能力〉を引き出してるもの」
そう口にするあいだも、マルサイの脳裏では、パチ、パチと白い火花のようなものが弾けていた。
アナンの〈能力〉によるもので、そのぷちぷちとした痺れに、マルサイは一歩引かざるをえなかった。
みんな分かってない。こいつは〈ドアノブ〉どころじゃない、鞭使いだ! マルサイは心のなかで叫んだ。
アナンの〈能力〉値は他の有能者を遥かに凌駕する。
それは自らの器に収まらないほどで、彼女は常時〈能力〉を垂れ流さないといけないほどなのだった。高濃度の〈能力〉に触れれば、当然電気が流れるような感覚を抱く。
故にアナンは、乾燥した冬に触れると静電気を起こす〈ドアノブ〉と呼ばれ、誰も近寄ろうとはしないのだ。
一方マルサイは、第2学年に進級してもなお、〈能力〉開花の兆候は見られずにいた。
能力を引きだすと言われても、三本目の腕を動かせと言われてるみたいで、どこに力を入れればいいのか、分からないのだ。
〈能力〉を持つ者と、持たざる者がいる――と、ここで読者諸賢に話を振るのはいささか唐突であることは承知の上、あえて申し上げよう。
しかし、先の一言は、この世界で暮らす諸賢からすれば、スチャキレンコの管理時計なみに正しく自明な認識かもしれない。
だが〈能力〉を持つ院生の生活というものは、あまりに知られていないこともまた事実である。長きにわたり秘匿されていた歴史ゆえ、致し方ないことではあるものの。
スチャキレンコに収容された子どもたちにとって〈二重奏〉は、あらゆる意味で今後の将来を決定づける、特別な授業であった。
〈能力〉を正しく用いるための、初歩的な訓練。ふたりで組となって、思念だけで互いの意思を疎通させる。はじめは至近距離から。それからどんどん距離を離して、やがて距離の概念がなくなるまで。
『能力』に嫌悪的な風潮がはびこる現代社会において、その第1段階が有能者同士の交流と聞くと、驚かれるかもしれない。
〈二重奏〉を扱うことは、人が火を扱うことと同じくらい、初歩的で重要なことなのだ。
しかし盲導犬が本格的な訓練の前に、パピーウォーカーのもとで愛情に包まれて育まれることとを考えれば、彼らが『能力』で意思疏通を図ることも、ある意味当然のことと言えるだろう。
「それじゃあここまで」
ベルが鳴ったところで教官が手を叩いた。
「〈二重奏〉できた組が大勢いて、びっくりです。みんな優秀ですね。でも、上手にできなかったみんなも安心して。主体学習はあと2回あります。座学で学んだことを振り返って、コツさえつかめばできるからね」
無論、マルサイの組はできずじまいであった。「みんな優秀ですね」の一言に、悔しくて泣きそうになる。
俺は優秀じゃないのか。こんなに頑張ってるのに、他の奴らとはなにが違うんだ。
そんなこと言ってもどうしようもないことは、とうの前から気づいている。
今日の講義はこれでおしまい。院生はぞろぞろと寄宿塔へ向かう。アナンは真っ先に教室から出ていってしまった。
「マルサイ、〈二重奏〉は決められたか?」
連れを大勢従えたレイトロが、追い抜きざまに小さな背中をバチンと叩く。
「痛えな。なにすんだよ」
「悪ィ悪ィ。〈ドアノブ〉の静電気と、どっちが痛かった?」
レイトロの連れがクスクス笑った。
「『二重奏』決めると、最ッ高に気持ちがいいんだぜ」
気持ちいい?
「耳元よりももっと近いところから囁いてくるんだ。ありゃあゾクゾクするね」
すると、連れのなかにいた女の子がひとり、顔を赤くしてレイトロの肩を叩いた。レイトロは、にた、と脂っこい笑みを一瞬浮かべ、マルサイの頭を乱暴になでた。
「知らないのか? 知らないんだな? マルサイはまだお子さまだな!」
「うるさい。俺だってやればできるんだ!」
「はは、意気地になっちゃって。わざわざ意気込んでやるもんじゃねえんだぜ。な、お子ちゃま」
せいぜい〈熱い湖〉に埋められないよう足掻いてくれや。そう言い残し、レイトロ一行は去っていった。
その後ろ姿は、踏み越えた者だけが醸しだせる余裕がはっきりと見てとれた。
寄宿塔の小さい窓から〈熱い湖〉を眺める。
スチャキレンコの高台からならどこからでも見える。というのも、この都市は湖に浮かぶ島であるためで、正面の鉄橋を渡ることを除けば、船を出さなければ対岸には辿り着けないのだった。
〈熱い湖〉が大きいのか小さいのかは、マルサイは比較対象を知らないのでよく分からない。
そもそも、ここから見えるのは、この湖と、遥か先まで続く荒涼の大地と、さらに遠方に見える白い山塊の稜線だけであった。
マルサイは、気がついたときには、232区〈児童舎〉で遊んでいた。それ以前はどうしていたのか。教官を含め、年長者は教えてくれなかった。
1年と4ヶ月前に〈学院〉へ移り、今に至る。〈学院〉での生活を終えたあと、どうなるのか。それも教えてはくれない。
そんな疑問も、自分がおちこぼれだということに気づいてからは、どうでもよくなった。
おちこぼれの院生は、ある日突然姿をくらます。どこへ行ったのか知ろうにも、彼らの痕跡は跡形もなく消えてしまう。
つい数時間前まで〈二重奏〉できていたはずなのにそれもできなくなる。だから調べようにも、どうすることもできないのだ。
そして、まことしやかに、こんな噂がささやかれるのだ。
おちこぼれの院生は〈熱い湖〉に埋められるのだ。
だから湖は赤い色をしていて、夜になると、ぼんやり青白く発光しているのだ、と。
景色を眺めていると、ドアが開く音がした。マルサイは振りむく気になれなかった。
「今日はどんな空模様だい」
声変わりしたばかりの、低い声。それから間もなく、2段ベッドにカバンを置く音。
「雲が、多いよ」
「そっ、か」
ふたつあるうちの、出入口側の机から、椅子を引く音。
ぎしぃ。
何世代もの積み重なりをへた、軋み。
「つらいことがあったんだね」
その一言に、マルサイは背中をまるめ、窓枠に乗せた腕を枕にした。
「イジョーも〈二重奏〉できるんだ。僕の心を読んだんだ」
「〈能力〉といっても誰でも気軽に読めるもんじゃないよ」
「知ってるよ。じゃあなんで俺の気持ちが分かったんだ」
「君が窓を眺めてるときは、いつもそうだから」
マルサイは、ちら、とイジョーのほうを向いた。脚を組み、机に突いた肘で頬杖してほほえんでいた。
その瞬間だけを切り取れば、書物の時代にありがちな人物画のようだった。当然、マルサイにそんな知識があるはずもないのだが、しかし、心の隅に留めていたいと思える笑みであることに変わりなかった。
「夕ご飯は?」
「いらない」
「そうだねえ、食べたくなくなるときだってあるよな。ただ、それしちゃうと、消灯したあとに後悔するんだよね」
イジョーはくしゃりと笑い、白い歯を見せた。
「そうだ、ちょっとだけ付き合ってくれないか」
「もう日が暮れるんだけど」
「大丈夫だよ。抜け道を知ってるんだ」
「イジョーって、存外不良だな」
「それじゃあ君は、不良のルームメイトだ」
そのジョークに、マルサイは〈学院〉規則に記される「連帯責任」の字を浮かべた。
また、品行方正といえども出来損ないである自らを思った。どうせ〈熱い湖〉に埋められるかもしれない身なのだ。すこしくらい不良になったところで、教官や管理官の評価は変わるまい。
マルサイは立ち上がり、窓から離れるのだった。
イジョーは、〈学院〉の第8学年だ。マルサイにとって、もっとも身近な大人だった。
〈児童舎〉での生活を終えたマルサイは、他の子と同様〈学院〉に隣接する寄宿塔へ移された。院生は上級生と相部屋になって生活することが規約に定まれている。
マルサイは、イジョーの部屋に選ばれた。物腰やわらかな口調で、自分とはまったく別の世界のことを考えてるようだった。彼とはとても親密になることができたとマルサイは考えているが、その一方で絶対的に越えられない線が引かれていることも重々理解できた。
だから、イジョーと共に過ごした一年間は、安らぎと不安の双方が絡みあっていて、それは今も続いている。
……はしごをのぼっている。
歩きどおしだった水路の音が、少しずつ遠のく。
手すりは錆びついてささくれだっていて、マルサイのやわらかい両の手に喰いこむ。
こぉん、こぉん、こぉん……1段のぼるたび、歩きどおしだった地下水路に音が木霊した。
「ちょっと待って」
先にのぼるイジョーがささやく。光を灯した指先を天井に、なぞった。
ぱちん、と音がしたのを確認すると、イジョーは力を込めて天井を押し上げる。マルサイは目を細めた、夜でも光がまぶしかったのだ。
「誰もいない。今のうちだ」
天井とは、マンホールだった。ごりょりょ、と深く鈍い音を出してマンホールは動いた。
人ひとり分の隙間だけ開けて、イジョーが先に出る。それから手が伸びる。マルサイはその手を握りしめて、白い息とともに地上へ出た。
そこは、知らない場所だった。
針葉樹の連なる道路に、崩れかけの建物が、月光を浴びて青白く染まっている。
そして、星と月とすじ雲が空にあった。イジョーは道を離れ、針葉樹の木立の先で手招きしている。幾本かの樹幹の脇をすり抜けると、視界は一気に開けた。
「〈熱い湖〉のほとりだよ」
夢の世界に迷い込んでしまったような光景だった。湖畔沿いの水面はうっすらと光を帯びて、しんとしている。
地平のほうへ視線を向けると、徐々に湖面は夜空を反射させ、月がおぼろげに浮かんでいる。
「すごい……」
思わずため息を洩らすと、その白い息はゆったりと上方へたちのぼる。
「ここは旧地区らしい。リビルドを待ってるようだけど、ご覧のとおり、まだまだ先の話さ」
よく見ると、道路の先は鉄柵で封鎖されていた。針葉樹は不格好に枝が伸び、幹から折れたものもある。地面には葉がうずたかく積もっている。
こんな場所を知ってるのは、第2学年でマルサイだけなのではないだろうか。
そんな、優越感にも似た充足感が足の先から全身へと駆け巡った。
お調子者のレイトロも、奴の周囲に寄っておこぼれを頂戴する輩どもも、そのほかマルサイを小ばかにする諸々全員、地下水路の先に未知の世界があるなんて知る由もなく、今頃寄宿塔のかび臭い大食堂で〈食物〉を胃袋に流し込んでいるに違いない。
俺のことを嗤いたけりゃ嗤え。俺は心のなかで嗤ってやる。お前ら全員、箱のなかの土人形だ。特別なのはお前らじゃない。この俺だ……!
「ほら」
根元で折れた樹木に腰かけたイジョーが、なにかを投げてよこした。手に取ると、それは銀包装の〈食物〉だった。
「いつの間にかちょろまかしたのか」
「人聞き悪い。今晩は君と食べると、ジルサンに言っただけさ。とりあえず僕は今食べてしまうけど、お腹いっぱいだったら部屋で食べればいい」
そう言いながら、イジョーはズボンで手を拭き、包装を破った。
穏やかな物腰と違って、イジョーのやることは大胆すぎる。
ため息が洩れそうになるが、彼の隣に座って、同じように手を拭き、包装を破るのだった。
ぶよぶよと弾力のある〈食物〉を奥歯で引きちぎる。多層的な生地をすりつぶす。何度も顎を動かしていると、ふと、奇妙な感覚に襲われた。
「いつもと違うものを食べてるみたいだ」
食事とは、〈食物〉を口に含んで歯を動かして唾液と混ぜ合わせ、適度にほぐれてきたら水と共に流し込む作業だと思っていた。
包装に入ったこの固形物に対して、それ以上の感想を抱くことはないものだと思ってた。
でも、ここで食べると、舌がじんわり溶けてしまうような感覚を抱くのだ。
「だろう? まるで星を食べてるみたいだ」
イジョーは、かじりかけの〈食物〉を掲げた。星が落ちてくるのを待ってるみたいだった。
「これ以外に食えるものがあるもんか」
「分からないよ。世界は、僕らが教えられてきたよりも、もっと広がりがあるのかもしれない」
イジョーの冗談に、思わず笑う。
スチャキレンコには、世界のすべてがつまっている。世界が際限なく広がっているのだとしたら、人は地面にあふれているだろう。
人だけではない。荒涼とした大地のすべてが、建物にあふれているはずだ。でも、現実はそうではない。地平の山の先になにもないからこそ、スチャキレンコのほかにはなにもないのだ。
「いいや、僕は大真面目さ」
しかしイジョーは真剣そのものだった。
「遥か彼方に見える山の先にはなにもないと言うけれど、空に浮かぶ雲は、山の向こうから流れてくる。なにもないのだとしたら、雲が流れてくることはないはずだ。雲だけじゃない。星も、月も、太陽だって。みんなあの山の向こうから現れるじゃないか」
マルサイは不思議だった。まるで実際に世界の果てを見てきたみたいに言うのだ。
イジョーはどうして、そんなふうに考えを巡らせることができるのだろうか。
俺の悩みなんて、つゆほども抱えることもないんだろうな。そう思うと、心細さを抱いた。
「でも山の向こう側なんて見えないし、辿り着けるはずもない。確かめようがない」
「できるさ。僕らは有能者なんだから」
有能者。そのなかにマルサイ自身が含まれているなんて、考えることができなかった。
「……俺は落ちこぼれだ。みんなみたいに、未来はなんでもできる気がするはずもねえ。〈二重奏〉の主体学習があって、みんな〈能力〉を発揮できたけど、俺は……」
果たして本当に〈能力〉を使うことができるのだろうか。最近思うのは、そればかりだった。
「『二重奏』の授業か。懐かしいな」
白い息を吐いて、イジョーはぼさぼさの針葉樹を見上げた。その大人びた横顔に、マルサイのなかの不安が膨らんだ。
「パートナーも、俺のことを拒絶してさ。アナンのやつ、〈能力〉の値がひとより少しあるだけで高飛車になりやがって。まるで世界が違うとでも言いたげな態度で。そんなのと〈二重奏〉なんて、できっこねえっつうの」
言いたいことは山ほどあった。ぐにゃぐにゃの〈食物〉を重いっきり噛みしめて、なにもかもをぶちまけた。
「チビなのがそんなに面白いか! 好きでチビやってんじゃねーんだよ、こちとら!」
くだらない愚痴を、イジョーは時折相槌を挟みつつ、うなづきながら耳を傾けていた。
はじめのうちは、思うままにまくしたてていたマルサイであるが、徐々に気分が沈んでいった。
俺の想いは、伝わっているだろうか。イジョーはやさしいから、話を聞いてはくれるだろう。
でも、俺の苦しみは、哀しみは、孤独は、寂しさは、悔しさは、つらさは、痛みは、どれだけ分かってくれるのだろう。
ああ、イジョーと〈二重奏〉ができたとしたら……煩わしい思いをすることもないのに。
語気は衰え、マルサイは幾分かの沈黙をした。それから、指先から鉛筆が転がり落ちるように、ぽろ、と言葉が洩れた。
「〈二重奏〉ができるようになると、なにもかも変わっちまうのかな」
「変わる?」
〈二重奏〉を決めたレイトロの後ろ姿。一歩踏み越えた者の背。
特別。
それと、心細さ。
言葉はあらゆるものがまじりあって、生み落とされるものなのだろう。
「悩みとか悔しさとかつらさとかさ。そういうのって誰にも分かってくれないものだろ? 中途半端に同情してくれてもさ、お前に分かるわけねえだろ、なんて思うんだ」
〈二重奏〉がどんなものなのか、マルサイは知らない。ただ、それを知ることで、見えるもののすべてが変革する予感がする。それが楽しみであるのか、おそろしいのか、あるいは両方なのか。
「孤独を感じる一方で、この気持ちは特別なものなんだ、とも思うんだ。でも〈二重奏〉できるようになると、感情も伝えられるんだろ? それって安らぎかもしれないけど、俺の特別は、特別じゃなくなっちまうのかなって……」
そんな話をしたいわけではない気がする。主体学習中やそのあとでレイトロにいじられたときに抱いた気持ちは、もっと素直な嫉妬や羨望で、自分が惨めで仕方がなかった。
特別でもなんでもない。強いて言うならば異端であり仲間はずれだ。
でも、あのとき抱いた心地と、今抱く不安感は、また異なっていた。
「マルサイ」
イジョーは、その握りこぶしを、マルサイの胸に当てた。
「君は今、とても大切な気持ちを、抱いている」
「こんなの、今すぐにでも捨て去りたい」
「ああ、つらいもんな」
イジョーは静かにうなづき、続ける。
「でも、人と安易につながるとね、捨て去ろうなんて思うまでもなく、いつの間にか忘れてしまうんだ。ちゃんとそこにあるのに、見失ってしまうんだ」
「そんなの分かるわけがない。イジョーは『能力』を使えるけど、俺とは思念を交わせないじゃないか」
「だけど、かつては僕だって君と同じだったんだ」
「かつてはかつてだろ! 俺の今を知ってくれる人なんて、誰もいないんだ。誰も……!」
そんな返答を求めてなどいなかった。
イジョーなら、地下水路より入り組んだ〈どうしようもなさ〉を解消する導きをもたらしてくれると、信じていたのに。
裏切られた気分だった。
勝手に期待したのは、マルサイ自身であることも自覚したうえで、しかし、この不条理をどうすればいいのか分からないまま、イジョーにぶつけていた。
「違うんだ、マルサイ。君を傷つける気はなくって……ひとりぼっちにさせたいわけでもなくて……」
うろたえるイジョーを見て、マルサイは泣きたくなった。
俺だって別に、こんなふうにしたいわけじゃないんだ。ただ、つらいだけなんだ。どうすることもできないつらさを、俺は周囲にぶちまけることしかできないでいるんだ……。
間があった。マルサイは拳をぎゅっと丸めて、太腿に押しつけた。歯を喰いしばって、涙が風にさらされないようこらえた。イジョーは、半身が欠けた月を仰ぎ見て、白い息を吹きかけていた。
それから、ズボンのポケットから、小さな筒状のなにかを取り出した。
人差し指と親指でつまんで、また月を見る。
「あの人なら、なんて言うんだろう」
イジョーのつぶやきには、今までとは異なる揺らぎがあった。
マルサイは思わずその横顔を見た。視線に気づいたイジョーは、力ない笑みを浮かべてみせた。
「あの人から聞いた、昔話を思い出したんだ」
「……あの人?」
「君が来る前にいた、ルームメイトさ。僕が君と同じ第2学年のとき、第8学年だったんだ。大切なことは全部、あの人から教わったんだよ。月と雲の昔話も、あの人から」
「月と、雲?」
マルサイが問うのとほとんど同じ折に、薄い雲が月の下を流れた。夜空は白に染まった。
「遥か昔のお話だ……」
遥か昔のお話だ。
雲と月は、〈二重奏〉をする同士だった。
口にせずとも言葉を交わし、思索をともにし、月の喜びはふたりで喜び、雲の悲しみはふたりで半分にして慰めあう仲だった。
ところがある日、月は大切だった星のひとつぶを失ってしまった。
月は悲しんだ。
〈二重奏〉の相方たる雲もまた、その悲しみに浸った。
しかし、雲の心は折れることなく、月を支えようと考えた。
大丈夫、君の悲しみは、僕が受け止める。
だが、どれだけ説こうが、雲にとってその星は、無数にある星のうちのひとつぶにすぎなかった。
月にとっては、決して欠けてはならないひとつぶであり、特別だった。
悲しみがいつまでも続くので、雲は自らの一部をちぎって、その星と同じ場所に、同じ色のかがやきをもたらした。
月はその思いやりに、少しだけかがやきを取りもどすことができた。
「でも、決して月の隙間を埋めるものにはならなかった。だから月は、ひと月のうち、たった1日を除いて、その身が欠けてしまっているんだ。結局、悲しみを分かち合ったところで、月の傷は癒えることはない。雲はそれでも分かち合おうと、その身をちぎりつづけている……」
イジョーは、そう物語を締めくくった。
美しくも、寂しさの薄い膜に包まれている。
それは、世界のことわりを描く物語であった。
コンクリート片の上は、相変わらず冷たい風が吹きすさぶが、身体の芯は火照っていた。不思議な心地だったのだ。
月と雲の物語は、マルサイの心に驚くほど深く浸透していった。
まばゆいほどの視線をイジョーに向けると、彼は頬を赤らめて視線を逸らした。
「つまり……」
そして、まるで言い訳でもするかのように、言葉を放つのだった。
「〈二重奏〉できるからといって、特別は特別なままなんだと思う。〈能力〉が使えるからといって、すべてが思いのままであるわけではないんだ」
月も雲も、互いのことは分かり合ってるはずなのだ。
「僕は僕で、君は君なんだ。決して、溶けあえるわけじゃない。孤独なふたりが、孤独なまま、寄り添うってことなのかもしれない」
「うん」
「だからこそ、〈二重奏〉だけじゃどうしようもできない孤独さを知る人は、強いんだ」
「うん」
マルサイは強く頷いた。
羨望の眼差しが強まるごとに、イジョーの表情に影ができる。苦々しげに唇を噛んだ。
「ごめん」
と、しぼるように、イジョーはつぶやいた。
「僕は、先輩失格かもしれない」
「そんな……!」
マルサイは首を横に振る。
「イジョーはすごいやつだ。悩んでるとき、いつだって導いてくれる。俺の周りにいるやつのなかで、イジョーだけがまっすぐ遠い先を見つめてる。俺はあんたに付いていきたい。そう思わせるだけの器があるんだ」
「そうか、それは……光栄、だと受け取っとくよ」
イジョーの横顔は、相変わらず月の光をまとっていて、ほほえみがあった。
「ただ、もし君が僕を見て憧れるのだとしたら、その要素は全部、あの人から学んだことなんだよ」
彼は、手の平にある円筒状のものを軽く転がした。
「君が来るまで、同じ部屋で暮らした先輩からもらったんだ。万華鏡、というものらしい。ここから筒のなかを覗くと、いろんな模様が見えるんだ」
マルサイは万華鏡を受け取った。覗き穴を見ると、月明かりに照らされた粒が、麗しい模様を形づくっていた。
「あの人が確かにいたってことの証で、これを見てると、ここにいてもいいんだって思えるんだ。何にも代えがたい特別なんだ」
「特別」
このちっぽけな筒は、なかの模様を見る以上のものではないし、そんなもの、〈学院〉ではつゆほどの役にも立たないものだった。
しかし、この穴から見えるものは、マルサイが今まで見てきたもののなかからでは、決して見つけられないものだと思った。
そしておそらく、イジョーにとっては、さらに特別なものに違いないと思えた。代々伝えられているという実感、それと、〈あの人〉との思い出……。
「でも、そうだな、よかったら、君が預かっててくれないか」
「そんな、受け取れねえって」
「いいんだ」
イジョーは、マルサイの右手を取ると、その手のひらに万華鏡を置いた。
「どうか預かってくれ。そうすれば、君が僕の特別になる気がするから」
マルサイの心臓が、高く脈打った。これほど心強い言葉を、マルサイは知らなかった。
「さあマルサイ、起立だ」
万華鏡を握りしめたのを確認したイジョーは、すっと立ち上がった。マルサイも、少し遅れて立ち上がる。
「君が今すべきなのは、分かるね?」
マルサイは頷いた。
「主体学習はあと何回?」
「2回、だな」
「そしたら、ちゃんとパートナーと寄り添っていかないとね」
そうなのだ。やるべきことは、みんなやる必要がある。
〈熱い湖〉に埋められるのはごめんだ。大切なことを教わった。簡単には手離したくはない。
「大丈夫、マルサイならできるよ。僕のルームメイトなんだから」
マルサイは全身を震わした。あらゆる活力がみなぎるようだった。
冷えてきたね。その姿を見たイジョーが、軽く笑んだ。
「帰ろうか」
その一言に、マルサイはうなづくのだった。
イジョーは憧れだ。でも、憧れだけではどうしようもない。
やるぞ。俺はやるぞ。
アナンと、〈二重奏〉を決めてやるんだ……!
「あなたとなんて、したくない」
2回目の主体学習早々、アナンは言い放った。ついでに教本も顔面にヒットする。
「ってえ、いい加減わきまえろよな!」
ついにマルサイの我慢も限界だった。無理やりその腕を取り、額に念を込める。
「したくないって、言ってるでしょ!」
バチ、とこめかみと視界が白くなる。
それから浮遊感。
気がついたときには、いくつかの机をなぎ倒し、マルサイは埋もれるようにして大の字になっていた。
アナンが〈能力〉を使ったのだ。座学で習った覚えのないわざだし、なんの予備動作もなく駆使するところから見て、ただの空咳みたいなものなのかもしれない。
くすくす笑い声が聞こえる。組になればマルサイはアナンに吹き飛ばされる。クラスの風物詩であった。
「〈二重奏〉ができなかったら、俺たち〈熱い湖〉に埋まっちまうかもしれないんだぞ!」
打ち付けた腰や背中をさすりながら、マルサイは立ち上がった。
一方、アナンはつまらなそうに教本を拾い上げ、ぺらぺらとめくるのだった。
「どのみち埋められるでしょ。あなた、出来損ないなんだし」
「それは……そうかもしれねえけど、だからってお前まで埋められるのはおかしいだろ」
マルサイの言い分に、アナンはばつが悪そうに顔をしかめた。
そんな言い分、飽き飽きしてるとでも言いたげな表情を浮かべ、枝毛になった髪をぼさぼさ掻いた。
「知らない。どうだっていい」
どうだっていいわけないだろ、とマルサイは心中でぼやいた。
天才の考えることはよく分からない。
「どうしてそんなに〈二重奏〉したいの?」
どうしてと言われても困る。
有能者にとって〈二重奏〉は〈能力〉を駆使するための入門のわざであり、これを行うのが当然のことだということは、〈学院〉に通うものなら必ず教わるものだし、そうでなくても当然の事項としてわきまえている。
加えて、〈二重奏〉を決めることは、気持ちがいいものらしい。その気持ちよさを、一度でいいから味わってみたいとも思う。
「んだよ、お前はしたくないのか?」
とにかく、〈二重奏〉したいかどうかなんて疑問を抱くまでもない。成長したら通過するものなのだというのが、マルサイの認識なのだった。
「質問に答えて」
「やけに突っかかるな」
「みんな、少しずつ上達していくのに、わたしたちはその入口にすら立てずにいる。その焦りが気持ち悪いんだ」
アナンは勝手な推測を口にした。
前回の主体学習で〈二重奏〉を決めた組は、少しずつ距離をとる段階に入っていた。
〈二重奏〉は理論上どこからでも交信が可能であるが、人間には思い込みというものがある。
どんなに心のなかで相手の名を叫んでも、振り向きすらしてくれない。それは、思念は伝播せず、自らの内側で完結するからだ。
そのため、〈二重奏〉を初めておこなう場合は、思念を相手に伝えるイメージを掴むために、手を握ったり、額を触れあわせたりすることが推奨される。
そこから、手を離したり1歩下がってみたりドア越しにしてみたりと、徐々に〈二重奏〉の感覚を掴んでいくのだ。
「それとも、レイトロたちの嘲笑に耐えられないから?」
レイトロの組は、すでに教室を離れ、〈学院〉の至るところで交信する段階に入っていた。
ここまでできれば、もう習得できたと言って間違いない。講義中であろうがなかろうが、存分に互いを求めあうことだろう。
「愚かね。やつらのなにがいい? 湖の内側しか知らないくせに、どうしてそこまで偉そうにできるのか」
悪態をつくアナンに、マルサイは不思議と興味を抱いた。
「……湖の、内側?」
「そうでしょ。湖と荒野と高原が見えるけど、見えてるだけで、その足で立ったことはない。全部、湖の内側で手に入る情報だけ。湖も荒野も高原も、そして〈二重奏〉や〈能力〉のことも、全部この場所でこさえられたものを見聞きしただけで、すべてを知った気になってる。正しいと信じて疑わない。いえ、正しいとさえ思ってないかもしれない。ただそこに、あるだけ。水があれば手をすすぎ、〈食物〉を見つければ口に含む。〈能力〉があれば使う。主体学習で〈二重奏〉を扱うからする。そこに正しさなんてない。あなただって同類でしょ」
冷めきった言葉の羅列を並べ立てる。
マルサイは心臓をどきりとさせて、慎重に息を吸った。
この俺が、レイトロと同じ? そんな屈辱あってたまるものか。
そう考えて間もなく、マルサイの判断基準はレイトロと少しも変わることがないように思えてくるのだった。
当たり前はあっても、正しさはなかった。どれもこれも、周りに流された結果なのではないか。
レイトロを見て、悔しいから歯向かう。ああはなりたくない。
イジョーを見て、憧れているから、月と雲の物語に感動する。ああなりたい。
アナンの指摘は、図星だ。間違いなく図星で、マルサイは否定する術を持っていない。
それでも。
「お前自身は……そうじゃないって、言えるのかよ」
足が震えても踏ん張り、言葉がつっかえても気丈に、視線を逸らしたくても真っすぐに。マルサイはアナンと対峙することを選んだ。
「ええ、わたしは違う。与えられたものだけが世界のすべてではないってことくらい、理解しているもの」
「そうだとして、結局は湖の内側。俺もお前も、同じじゃないか」
「貧相な想像力しか抱けない人と同類にしないでくれる? わたしは特別なの。誰もが、わたしを特別な者だと見て扱う」
「……世界に果てがあるのなら、雲も星も月も、ありはしない」
「なに、それ」
アナンは、マルサイの突拍子もない一言に戸惑いの表情を見せた。その表情は、マルサイの待ち望んだものであった。
「お前は、自分のことを特別だと考えてるかもしれねえ。〈能力〉は誰よりも優れてるし、俺たちなんてガキにしか見えねえかもだけど。でも、間違ってんだ。俺にとって特別は、俺だけだ。〈能力〉も引き出せない。背は小さい。みんなからバカにされる……。それが俺にとっての特別で、お前なんか特別でもなんでもねえ。ただの人間だ」
「だから、なに」
「だから……」
マルサイは息継ぎした。
「特別は、たったひとつだけのもので、なにものにも代えがたい。それと同時に、ひとつでもふたつでも、心に留めおけるものだと思う」
イジョーからの受け売りだ。
でも、それでいい、とマルサイは考えるのだ。
「分かるか? つまり俺にとっての特別とお前にとっての特別は、どちらも代えがたいもので、どちらも自分の特別として両立できるということなんだ」
「ふざけ、ないで!」
アナンは声を上げた。
同時に、空気がぴりぴりと震え、目の裏側がちかちかする。
「ワケの分からないことを。わたしのことなんて、理解できるはずもない。安易に〈二重奏〉でもすれば話は別でしょうけど。そこまでわたしを覗き込みたいの? 気味が悪い。わたしは特別を教えたくなんてないし、あなたの特別とやらも知りたくない。もうやめて」
それが、果たして拒絶なのか、拒絶の言葉を用いた別の吐露であるのか、そんなものは分かるはずもなかった。
しかし、マルサイは確かに、アナンからなにか叫びのようなものを受け取ったように思えた。
アナンの孤独を分かち合うことはできない。でも、アナンをアナンとして、その特別ごと包みたいと願った。
手を伸ばす。近づくにつれて、指先から肘の先まで痺れが増幅していく。白くなる。吹きとんでなくなってしまってもおかしくないくらい、熱い。
「俺は、お前をひとりにさせたくないだけなんだ」
「嘘つきだ。そういう人間は、みんなわたしを裏切ってきた」
それでも、アナンはマルサイを見つめる。
怯えたような、寂しそうな、苦しそうな顔をしている。
そのどれもが、マルサイのなかにもある感情と連動する。
アナンの特別と、マルサイの特別は、まったく異なるものだ。だけれども、こうして表に出てくるものは、どれも言葉や、表情筋を介したものになる。
だから、人は勘違いするのだ。安易に同情してしまうのだ。
人の真の苦しみや喜びは、他人が想像するより遥かに複雑で繊細で、彩り豊かで、決して伝わるものではないのだ。
「俺が嘘つきかどうか。そんなの、こうすれば分かることなのに!」
その肌に触れる。骨の感触が直接伝わるような、細い手首だった。
マルサイは念じた。
伝われ――強く、感覚の遠のく指先に。
指紋を密着させ、薄い皮膚を介して、アナンの毛細血管と交わるように。重ねた。
〈二重奏〉自体の描写は、実に容易い。
いうなれば映像化された心情描写を脳髄で読み取るような感覚である。
伝達内容も、送信者のイマジネーションをそのままに伝えるため、「熱い」だの「好き」だの「抱きしめたい」だの、そういった心情を心情のまま受け手も感じとる。
無論、ひとりの語り手として、マルサイ少年の念を、〈能力〉萌芽の瞬間を、〈二重奏〉の旋律を、こと細やかに描写する義務があることはいうまでもない。
しかし殊この〈二重奏〉に限っていえば、言葉にすることすら難解なほどに、あまりにシンプルな願いだった。
あえて文字に起こすのであれば、それは「合一」という熟語に集約されるのだろうが、その二文字すら希釈されるほどに、マルサイの祈りはまっすぐアナンに注ぎこまれた。
その一方で、アナンの思いもまた、マルサイに届けられた。
あまりに膨れあがった寂しさの情に、彼は立っていることさえ忘れ、深い穴に落ちていくような感覚に襲われた。
アナンは死にたがりであった。
優遇と期待を抱く大人たちと、嫉妬と羨望の眼差しを向ける子どもたち。アナンの〈能力〉はあまりに膨大で、常に垂れ流されていた。
ゆえに、空気を介して、世界をめぐった。
世界は、イジョーが示唆したとおり、山のさらに向こう側まで続いていた。
雪化粧した美しき山麓の先に、多くの人が呼吸をし、数多の骸が腐臭をあげていた。人はその上に営みを設け、それもやがて灰燼と帰す。
世界はそうして成り立つのであり、我々の当然であり、〈能力〉を持つ者とは異物的人間を肉塊にする役割を負う者であった。
それ以上の、例えば我々のように、大切な人を養うだとか、突き抜けるほどの青い空に思いをはせるだとか、香草の添えられたムニエルに舌鼓を打つだとか、そういった役目は負うこともなく、いやむしろ我々がそうした平凡のなかで過ごせるよう、彼らは自らが戦場で肉塊となるその日まで、異物の排除をつづけるのだ。
……そして、マルサイはアナンの繊細なやさしさを感じた。
「ずっと、夢を見ていたかったのに」
アナンはぽつんと言って、唇を噛んだ。
「わたしたちは殺人兵器なの。機械となり、〈能力〉を駆使して、ひとりでも多くの敵を殺すだけ」
「まさか、こんな……」
「それだけなら、まだ世界を受け容れることはできたと思う。わたしだってそのくらいの覚悟、できる。でも、どうして〈能力〉を用いた初めての主体学習が、〈二重奏〉なの?」
〈二重奏〉は、〈能力〉を持つ者が最初に教わるわざだ。
互いの思いや感情を共にする。互いの感覚をつなげることで、戦場で効率よく敵を炙りだし、排除が可能となる。
「マルサイ、この意味が分かる? わたしたちは思いを共有する。片方が死ねば、一方は相方が最期に叫ぶ呪いをその身に刻みながら、人間を殺さなければならないってこと」
〈学院〉では、第9学年で〈敵〉の概要を教わることになる。
〈敵〉は肉塊の集合物であり、有能者は〈敵〉を元の状態に戻すことが務めである、と。
「わたしだって、そう信じたかった。特別はわたしだけだってことにしておきたかった。〈敵〉も教官もクラスメイトも、それからマルサイだって、感情を抱いたり、思いを巡らすような『素振り』だけ見せる、ただの肉塊だって納得したままでいたかった。〈二重奏〉さえしなければ、信じたままでいられたのに……」
夢を見ていたかった。
アナンは繰り返した。
アナンは夢を見ることはなくなるだろう。
永遠にだ。仮に夢のようなものを抱いたとしても、それは現実の先にある目標でしかない。
少女は大人になった。
マルサイがそうさせたのだ。
その事実に打ちひしがれて、呼吸が荒くなる。
彼の胃袋が収縮し、朝に摂取した〈食物〉がせり上がる。力が入らなくなり、ついに膝を床についた。
焦点が定まらなくなる。全身から汗が噴き出て鳥肌が立ち、体温が奪われる。
白。
白。
嘔吐でもすれば、なにもかも赦される。思考が、都合のいい甘言をぼやく。
薄れゆく意識を手離そうとした、そのときだった。
――助けて。
はたと、遥か彼方から旋律が奏でられた。
違う。
違うんだ、そうじゃない。
俺は後悔するために〈二重奏〉をしたわけではない。
たしかに、世界はあまりに身勝手で、俺たちは単なる道具にすぎないのかもしれない。
それは事実だ。
事実からは、抗えない。
それならばなにに抗えばいい?
俺はどうしたい?
俺のおこないは、すべてムダなことだった?
違う。
俺には、まだひとつだけ、残された意志がある。
……アナンをひとりに、させてやるものか。
世界の事実を知ったからって、それは変わらない。
アナンの悲しみを分かち合えたとしても、その孤独を埋めることはできないし、おそらくマルサイがどれだけ奮闘しようが、彼女の絶望は癒えることはできないだろう。
それでも、マルサイは〈雲〉になることを決心した。
月の欠けた痛みはどうすることもできないが、共にいることはできる。誰かがそばにいることの心強さを、マルサイは知っていた。
腕はひりつき、頭は破裂しそうなのを気力で抑えて、アナンの腕を取る。そして、告げる。
――今晩、寄宿塔の正面ロビーに来てほしい。
そこから、俺なりの覚悟を見せてやる……。
暖炉が焚かれていて、燭台には上級生の当番が繰り出した灯し火はゆらめいている。
ソファではディパーキと呼ばれるカードゲームに興じる院生が一喜一憂している。マルサイは観葉植物のとなりに腰掛け、教本を眺めていた。
眺めているだけで、なにひとつとして語句の意味を理解しようとは思わなかった。
文字はもはや文字ではなく、ただの模様だった。
「よう、マルサイ」
誰も話しかけんな、と心から念じていた。
それなのに、調子のいい声が飛んでくる。
「お前、〈ドアノブ〉と決めたんだってな」
教本で顔を覆っても、レイトロは決して躊躇しなかった。
「驚いたぜ。泣きべそかいて〈熱い湖〉に埋められるもんだと思ってたが、やるときゃやるんだな。その話を聞いたとき、見直したんだぜ」
マルサイはちらと顔を上げた。
レイトロはひとりだけで、連れはひとりもいなかった。珍しいこともあるもんだなと、ぼんやり思うのだった。
「なあ〈ドアノブ〉ってさ、どんなこと、考えてた?」
「は」
マルサイは思わず声を洩らした。
「ほらあいつ、高慢で矜持の塊みたいなところ、あるだろ。でもそれだけじゃない、はずじゃないか。あいつだって人間だし。人間らしい部分だって、きっと……」
「どうだかな」
視線を教本に落とす。
レイトロのことがあわれに思えた。
〈学院〉に通う人々のこれからを教えてやったら、どんなふうに思うのか、すこしだけ興味を抱いた。
しかしこれは呪いだ。いたずら半分で流布するものではない。
地下食堂へつながる階段から、待ち人がのぼってくるさまを見つけた。マルサイは本を閉じ、立ち上がった。
「お前らに、しあわせがくれば、それでいいんだ」
「おい、待てよ」
話の途中だからか、レイトロはその背中を呼び止める。
「教えろよ。マルサイ。しあわせってなんだ。なんなんだよ、それ――」
――これから見つけにいくんだ。
そのひとことが伝わったかは、どうでもよかった。マルサイの関心はアナンに移っていたからだ。
「来ないのかと思った」
「わたしたちに、そんな冗談は通用しない。でしょ?」
二人は文字通り以心伝心とも言える関係性なのであるが、マルサイは会ってどうするのかは伝えずにいた。ただ、「覚悟を見せる」と。
――しあわせ、見つけに行くんだ。
アナンはマルサイの手から教本を取り上げた。くるりと後ろを向いて、2歩進む。
――こう見えてわたし、結構楽しみにしてるんだけど。
マルサイの脳裏に、そんな声が響く。
はっとなって見ると、アナンは口元を教本で隠して、ちら、とマルサイを見るのだった。
ふたりの、小さな旅がはじまった。
目的地は、〈熱い湖〉のほとりだった。
暗い地下水路を歩き、何度かの分岐を経て、マンホールのふたを開けた。
湖は、この前に見たときと同じように、白い光をたたえ、遠くは鏡面のように雲と星と月を映していた。
マルサイは安堵した。安堵したと同時に、初めてこの風景を見たときに抱いた感動が静まっている自分に驚きを抱いた。
驚きなのか、寂しさなのか、いまいちぴんと来なかった。
――今の感覚を教えてくれないか。
だから、マルサイはアナンの手を握った。
そこには、ほくほくとした視線の移り変わりがあった。
ほのかに照る水際をくまなく見渡し、その際に沿って地平へと向かい、揺れる月明かりの辺りで空を見上げる。冷え込んだ夜の空を大きく吸い込むと、鼻の奥がツンと痛い。
それすらも、思わず笑ってしまうほど新鮮で、おかしくて、気持ちがよかった。
それが、アナンの心情だった。
――万華鏡って、知ってる?
――なにそれ。
マルサイは、ズボンのポケットから小さな筒を取りだして、アナンの手のひらにのせた。
――覗いてごらん。ときどき回してみて。
アナンは口を小さく開けて、そのなかをじっと見つめた。
片方の手でマルサイに触れ、思念を送った。
だから、マルサイもまた、万華鏡の変わりゆく模様を眺めている。
粒の集まりが模様を変える。月の光も、筒を介して眺めている。世界のすべてが、万華鏡のなかに集約しているように思えた。
赤い色をした〈熱い湖〉は、なおも青白い光を浮かべている。マルサイは軽く目を閉じた。
まぶたの裏側で、また万華鏡の模様が変化した。
アナンは、決して特別なんかじゃない。
きっと、大勢の人たちが、自らの未来を知って哀しんだのだ。
赤いのは、世界を知ってしまった人々が底で眠るから。
青白い光を放つのは、月の涙をたたえているから。
ふたりは孤独だった。
孤独を抱いたまま、寄り添うことができた。
いずれ月が慰めてくれるだろう。
きっと、マルサイのことも、アナンのことも。
そう願うことが、ふたりのさいわいだった。
マルサイとアナンというふたりの〈能力〉持ちがこのあとどうなったのか。
それは、誠に遺憾ながら、散逸した資料からはこれ以上辿れない。
〈熱い湖〉に埋められることになったのか。
自ら月の涙となったのか。
あるいは〈学院〉を終え、山嶺を越えた先で肉塊となったのか。
しかし、これがひとつの物語として描くのであれば、事実を羅列するのではなく、読者諸賢の頭のなかで思い描くのが、もっともよい締めくくりだろう。
あわよくば諸賢の物語を〈二重奏〉できればと思うが、無能者ゆえに、潔くここで筆をおく。
マルサイとアナン、そしてスチャキレンコの子らに、幸あれ。
テーマ:トキメキ二重奏
「お題.com」(https://xn--t8jz542a.com/)より
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
次回
目次
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
