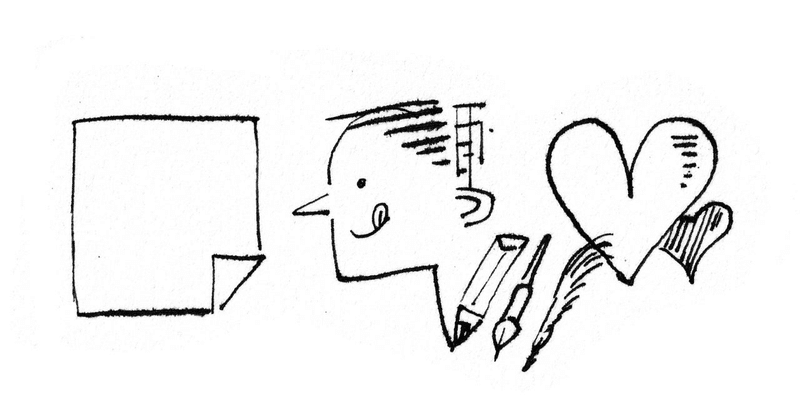
小説が書けるとき・書けない時【自己分析】
私はプロではないが、作家になりたいので小説を書いて、noteで連載したり、公募に応募したりしている会社員だ。
こういう生活は今年2023年1月から始めた。しかし、よくプロの方が言う「最後まで書きましょう」が、なかなかできない。
できるものもあるが、できなくて眠っている書きかけも結構多い。
そこでこの二日ぐらい、書きかけの作品のプロットを改めて作り直したり、ネットでプロットが行き詰まったときについて言及されている作家さんのnote記事を読んだりして分析していた。
▼参考にさせていただいた記事
その結果、わかったことがいくつかったので、書き記そうと思う。
私が書けない時は「面白い」と思えるポイントがゼロで始まっていることが多かった。
例えば今noteで連載している小説「トイレ世界漂流記」のおもしろポイントは
受験生の一郎が、受験の日にトイレに吸い込まれて異国へ流されてしまう
というものだ。
これは書くのは辛くない。正直楽しい。もともと国際的なところは得意分野だからというのもある。
ただ、いろんな国のトイレや文化を調べすぎて、海外旅行へ行って帰ってきたかのような疲労感はある(笑)
今まで最後まで書けた小説はこういうふうに30文字以内で「どういう物語か」という特徴を述べられるものだった。
私の場合は、そういった特徴に応じて想像が膨らむタイプのようで、その場合は一気にストーリーが思い浮かぶ。
実際に「トイレ世界漂流記」は構想に一ヶ月くらいかかったイメージだったが、実は第一話を考え始めてから書き終えて公開するまで、わずか5日だった。
そのぐらい頭の中にワサワサ書きたいことが降りてきていた。その時、ちょうどこんなことをメモしていた。
逆に、書き上げられずお蔵入りしているものは、特徴がなかった。
あと、上記note記事を引用すると、夫と酒を飲みながら打ち合わせという儀式を挟んでいないのも共通しているw
伝えたいメッセージやキーワード・テーマになるものはある。
でもそれだけの装備で物語を書き出しても「どんでん返し」も「オチ」も「伏線」を創造するのが難しいことがわかった。
さらに、なぜそうなるのかと言うと、これは私が作家になりたい理由が読者の「生きづらさに寄り添いたい」というものがあるからのように考えた。
この気持ちが強いと、「面白い」とか「物語のダイナミックな動き」より、「登場人物たちの心の動き」ばかり細かく考えてしまいがちなのだ。
そういったところをポイントにしつつ、ダイナミックな動きがなくても面白い映画や小説は、すごく憧れる。
でも残念ながら、今の自分にはまだそういった技術はないようだ。
ここまで分析してわかったこと。
物語の特徴となる、核心部分を1番に考える
それを夫に酒を飲みながら話してみる
人の感情やディテールは、一番最後に創る
私の場合はここを押さえるだけでも、プロット作りが詰まることが減るように思った。
私は9月末の公募にできれば応募したい。
それに向けて今書いていたプロットを修正するか、一度引き出しに入れてゼロベースから他のものを創るか悩む。
今日は9月3日。もう少々検討して、今後の方向性を決めたいと思う。う……がんばろう!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
