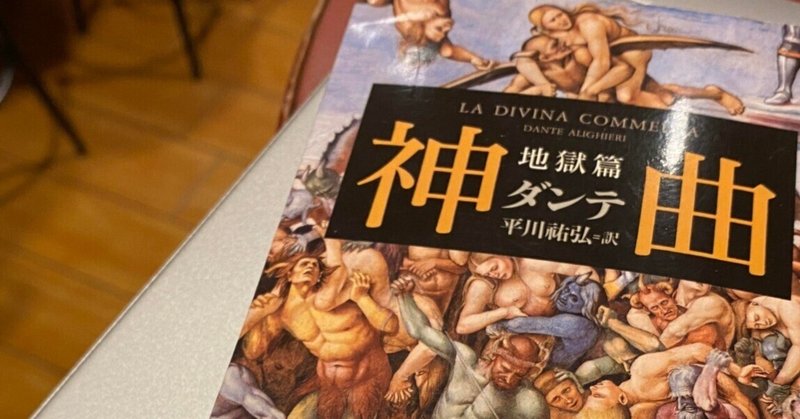
『神曲 地獄篇』 読後の違和感とその正体とは。
いろんな本を読み漁っていると、どうしてもダンテの『神曲』やゲーテの『ファウスト』の引用が目につく。無学で何も知らない私は、少しはその手の古典に触れておいたほうが良いのではと手にしたのだが、全くと言っていいほど興が乗らなかった。欧米圏では文学史上最高傑作と評されることもしばしばある『神曲』だが、世界史音痴で浅学なうえ、当時のフェレンツェの歴史を知らない。そもそも西洋の言葉で書かれた詩句を日本語に直すこと自体、無理があるではと思ってしまう。いくら読んでもわたしにはこれが詩のようには感じられないでいた。原書は、ダンテが広く読まれることを狙ってラテン語ではなくトスカーナ方言で書いている。訳者の平川 祐弘氏はそれに照らし合わせ、文語調を取り払い、なるべく平易な言葉で綴るようにしているのだが、わたしにはどうにもあっさり感が否めないでいた。たしかに文語調で晦渋な辞句ばかり並んでいては、苦しい読書を強いられることになるだろうが。
さらにキリスト教の文化や価値観もわたしにとっては興味の埒外であり、それも手伝ってか、読んでいて熱というものを一切感じることができず、夥しいほどの注釈を追いかけることに焦燥しながら、結局読了までに随分と時間を要したのであった。同じ古典でも詩ではなく小説という形態で、時代もずっと最近のものになるが、1720年頃に書かれた『ガリバー旅行記』を読んだときは、その普遍的な世界感と現在の政治的状況に通底するアイロニーに強烈な熱情を覚えたものだが、今回はそのような感情はついぞ一度も訪れることがなかった。その証拠に付箋魔のわたしが、これほどまでに付箋をつけなかった本はない。通常の本の1/10ぐらいしか付箋はつけられていない。
私が、今回読んだのは地獄編のみ。現生において悪事を働いたきたものたちへの恐ろしい制裁が、その罪状に合わせ9つの谷の中で繰り広げられるという構成になっている。その罪状がなかなかに興味深い。アリストテレスの『倫理』を下敷きに、キリスト教に照らし合わせ、さらにダンテの考えた倫理観を反映されているようだ。それぞれの谷で永劫に続く刑罰を受けているのは、当時の世俗の人々、暴君や政治家、聖職者など実在の人物たちである。政敵によってフェレンツェを追われたダンテは、自身の憤怒をぶつけるようにして、この地獄篇を描いたのだろう。
最初の谷は、洗礼を受けなかったものが罰を受けている。2つ目の谷は、愛欲に溺れた人間たちが罰を受けている。3つ目は、なんと大食による罪である。大食も罪になるのか。これを読みながら、わたしも勝手にいろんな顔を次から次へと思い浮かべていた。情欲に溺れ不倫ばかりを繰り返し女性の心を弄んでは捨てるという行為を繰り返していた彼奴は、此の谷で鬼たちに苦しめられることになるのかとか。貪欲な大食漢で、俺を著しく割り勘負けさせるあいつは、かわいそうなことに、3つの口を持つケロベロスという怪物に喰われてしまうのかとか。当初はそういうことを想像しながら読んでいた。
4つ目の谷にいくと、そこは吝嗇と浪費の罪人たちの集まる地獄であった。吝嗇も罪になるのか。俺のことかと焦る。吝嗇と浪費を対にする発想がなかなか面白い。その欲望の根源は同一線上にあるということなのだろうか。次の5つ目の谷は憤怒者の地獄である。これこそ俺のことだなと焦る。7つめの谷は、異端者の地獄ではある。ここでは、ムハンマドがエラいことになっている。滅多斬りにされ身体を真っ二つにされるのだ。これはさすがにというか当然ながら、いまだにアラビア語圏では訳さることがないらしい。7つ目の谷は、暴力者の地獄である。これは分かりやすい。そのなかには自分への暴力も含まれる。つまりキリスト教だから自殺も罪になるということらしい。
8つ目の谷は、この地獄篇の半分近くを占めるほどにダンテが力を注いで書いた部分である。ダンテにとって最も腹立たしい人間たちがここに集められているのだろう。ここは悪意者の地獄と呼ばれており、汚職者や、謀略者、詐欺師、偽善者などが集められ、惨憺なほとに厳しい罰が執行されている。長いこと政権についていることをいいことに、あらゆる利権を手中に収め、友人ばかりを依怙贔屓し、格差を拡大させ市民を苦しめ続けている此の国の政治家とその取り巻きの上流国民たちも、きっとこの8つめの谷において、焼かれるような苦しみを永劫に受けることになるのだろう。
9つ目の谷は、裏切り者の罪人が集めらている。キリストを裏切ったユダと、カエサルを裏切ったブルートゥスとカッシウスが、巨大な魔王の口で引きちぎられようにしているというところで、物語は終わる。
最初は、敬虔な信者であるダンテと先達の詩人ウィリギリスの視点にたって読み進めていった。最初のほうでは愛欲にかられてしまったがために地獄に送られた女性の話を聞いて、その気の毒な女性に心を寄せて卒倒してしまうダンテの姿が描かれている。また男色の罪で地獄に送られた恩師を見つけたダンテは、その寂しげな恩師の姿に憐憫の情を隠せないでいる。そのように前半部分では、地獄に送られてしまった人々への不幸に心を寄せる優しいダンテの心情が描かれていたのだが、段々谷を進んでいくに従い、苛烈な地獄絵が展開されていき、主人公のダンテも、彼らに対して容赦なく憤怒をぶつけるようになっていく。
当初は訳注を確認しながら読み進めていた。ダンテやウィリギリスの良心を信じて、その気持ちに沿いながら読み進めていたのであり、当然、地獄で苦しむ人たちは因果応報であろうと考えていたのだが、それがなかなか不思議なことに痛快には響いてこないのであった。むしろ物語が進行するに従い、だんだんとわたしの心は離れていくようであった。
わたしが文学に魅了されるのは、不可視なものに光を当てるという文学の行為に価値を感じるからだ。人々の心のなかには、人それぞれの文学が流れている。罪人のなかにも文学は伏流しているのだ。文学には、ひとつだけの答えに収斂することのない両義性がある。ひとつの価値に固定することがなく、揺れ動きながら常に多面的で深遠な世界を映し出してくれるのが文学ではないかと思うのだ。自身の正義が必ずしも正しいと断定できない、そこにに含みを持たせるのが文学ではないか。ニーチェではないが、"知的良心"に裏打ちされているのが文学の世界ではないだろうかと思うのである。
しかしここで描かれているのは、そうした文学の世界とは切り離された世界に思えてならないのだ。一神教であるキリスト教からみた一方的な断罪であったり(たとえば異教者や男色者が断罪されている)、ダンテが抱えた私怨をそのままに断罪しているかと感じてしまうのである。文学が放射する多面的な価値観とその柔軟性からは遠い世界のように思い、後半からこの物語を読み進めるのがしんどくなってまったのだ。訳が分からないままに読了したものの、判然としないので訳者の後書きを読み進めてようとすると、驚くことにあとがきのタイトルは『ダンテが良心的な詩人か』となっていた。 平川 祐弘氏は、ダンテ研究の第一人者である。そんな大御所が、わたしが漠然と感じていていた違和感をテーマにあとがきを記していたのである。
「地獄篇では多くの男女を処罰する際、ダンテは声高に正義を主張した。しかし本当は地獄・煉獄・天国というフィクションを語ることで、時には自分の嫌いな奴は地獄に堕とし、好きな人は天国行きとし、一見謙遜ではあるが、作者ダンテは自己主張もし、詩的表現を楽しんでいたのではないだろうか。」
平川氏はそうした疑念を呈しつつ、ボッカチオの『デカメロン』と対比させて記述を進める。デカメロンは、生真面目な『神曲』とは対照的で、つねに諧謔的で、卑猥で破廉恥である。そもそもこのふたりの出自は全くの対照をなしている。貴族出の気位いの高いダンテと、商人の父と外国婦人との間に私生児として生まれたボッカチオである。未読であるが、わたしの趣味は、断然、反権威的でユーモアセンスの溢れるボッカチオ、デカメロンだなと思った。
「ボッカチオは市民階級者としての常識に富む。そればかりか現世的欲望を楽しみ、聖職者も笑いものにし、はははだ不謹慎である。しかし地中海世界でキリスト者以外とも交易の体験のあったらしいボッカチオは無闇に対決的な言辞を弄することがない。いかにも散文的である。ただしボッカチオを良心的と呼ぶ人はまず見当たらないだろう。」
こんなことが書かれているとますます興味が沸き上がってくる。
ちなみに余談だが、わたしは未読であるものの高校生か大学生の頃から『デカメロン』に並々ならぬ興味を示していたのであった。というのも当時深夜放送でパオロ・パゾリーニ監督の映画『デカメロン』が放送されており、たまたまチャンネルを動かしているときに、そのあまりにも卑猥極まりない映像を垣間見てしまったからだ。身体中、とくに下腹部に、かつて経験したことがないほどの旋律が走ったのであった。この映画を映画館で最初からちゃんと観てみたいなと思って、ぐっと我慢をしテレビを消したのであったが、その後30年以上、この映画が劇場でかかったことを知らず未見のままである。それ以来、わたしは、歴史の教科書に必ず出てくる「デカメロン」という言葉の語感に、勝手に卑猥なものを当てはめて想像を逞しくするのであった。
閑話休題。
では平川 祐弘氏は、「ダンテは良心的な詩人なのか?」という自身の問いにどのような結論を与えたのであろうか。
「わたしの答えはこうである。作中人物ダンテが良心に誓って地獄を見た、というのは大嘘だ。嘘を言いながら「良心だけが私の支えだ」などとぬけぬけというのは厚かましいにもほどがある。しかし嘘の世界が面白い。そしてその嘘というかフィクションをこれほど見事に描き切ったダンテの詩的推敲の努力、それはまことに見上げたものである。ー 中略 ー ダンテは芸術家としてはまことに「良心的な詩人」であった、と申して本解説の仮の結論といたしたい。」
この前半部分の仮借なき批判を読んで、わたしの読後の感触は決して見当違いのものでなかったようだと感じた。。
訳者のあとがきのあとに、別の評論も記載されていた。それを読むと、煉獄篇は、地獄篇とはうってかわって温和な感情がみなぎって、訳者の詩心が一気に解き放たれたかのようで極めて流麗、詩情豊かな世界が展開されていると称揚していて、なんとも興味がそそられる。煉獄とは天国に召されるまえに、苦罰によって罪を清めらる場所である。地獄にいくものと、煉獄へ行くものを分かつ理由は、己を悔い改める自省の念、自戒の念を持ち合わせているかどうかであるらしい。いつまでも悔悟することのない悪者は未来永劫、焼けるような罰を受け続けなくてはならない。なんとも気持ち良い話ではないか。ちまみにプロテスタントは煉獄の存在を否定しているとか。
もう辛い読書はこりごりだなと食指が動かないものの、せっかく『地獄篇』を読んだのだから『煉獄篇』を読まない手はないのではないかと思いが揺れている。読書計画に加えてみる方向で検討したいが、しかしそのまえにやはり『デカメロン』を読むことになることだろう(笑)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
