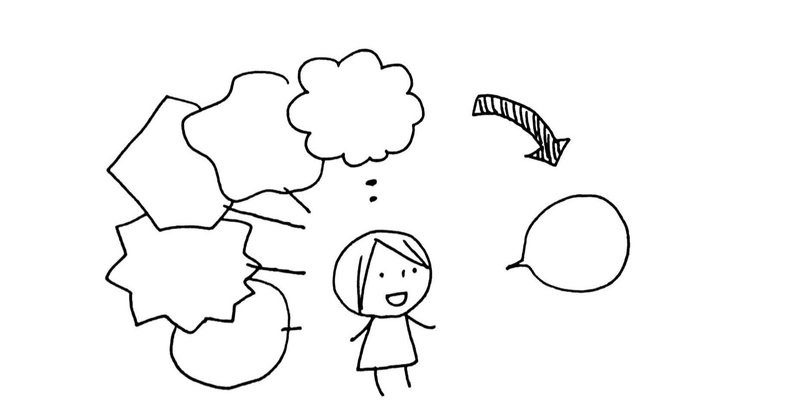
私たちが「何気なく使う」レベルに普及している言葉はすごい
言葉って、たくさんあります。「コップ」「牛乳」「YouTube」「カレンダー」「スニーカー」「メモ」。その言葉の一つひとつは、何気ないもので、当たり前にそこにあるように感じます。
でも実は、当たり前じゃないんだなあと、思いました。
世の中には、消えてしまった言葉が、星の数ほどある
世の中には、消えてしまった言葉が、星の数ほどあります。
例えば、「Keeloun」って知っていますか?
知りませんよね。ぼくも知りませんでした。これは、エスキモーの太鼓の名前だそうです。
それでは、「Keeloun」という言葉が、月に何回検索されるか、分かりますか?
答えは…0です。
※正確には、ぼくが検索したので2回くらいです。
対して、「ギター」の検索数は、月に何回くらいか分かりますか?
答えは…なんと、日本だけで平均13万5千回もあります。
この違いは何なのでしょうか?
各所からの要請で、言葉は広がっていく
言葉は、なんとなく広まっていく訳ではないと思います。
広まるのは、プロモーションのお陰だったりします。
例えば、「プリウス」は月間平均検索回数が24万回もあります。
しかし、発売の1997年以前には存在しなかった言葉です。
また、広まるのは、政治からの要請だったりもします。
例えば、「ソーシャル ディスタンス」は月間平均検索ボリュームが7万あります。
しかし、2019年以前には存在しなかった言葉です。
その言葉には、パイオニアとして人生を捧げた人がいる
どの言葉も、かつては世の中に存在しなかったと思うと、驚いてしまいます。
「プリウス」の検索回数が0だったなんて、信じられません。
そこには、0から数十万まで育てた誰かがいます。
例えば、「ギター」が言葉として使われているのも、ギターに人生をかけて、商業的に大きく成功した人が大勢いたからです。エルヴィス、ジミヘン…いろんな人が思い浮かびますよね。
もし彼らがいなかったら、みんなギターじゃなくて、バンジョーを弾いていたかもしれません。知らないですが。
私たちが何気なく使うレベルに普及している言葉はすごい
言葉を、私たちが何気なく使うレベルに普及させるのは、途方も無い偉業だと思います。
どうやってそんなレベルに達するのか、少し考えてみました。
ぼくが思うに、言葉には、ざっくり3つの広がり方があります。
①協賛する人が多く、文化的に受け入れられる
②商業的に軌道に乗っている
③国に認められている
そして、何気なく使うレベルに普及している言葉は、3つの広がり方を網羅していることが多いように思います。
①協賛する人が多く、文化的に受け入れられる
言葉が何気なく使われるためには、まず、お互いに知っていること。利用シーンが多いことが前提です。
協賛する人が多く、文化的に受け入れられている、ということになると思います。
②商業的に軌道に乗っている
言葉の利用シーンが多いということは、多くの人が必要にかられているということなので、大きな市場ができることが多いように思います。
数十億円以上の市場が形成され、何万人の顧客がいて、ビジネスや雇用を生みます。何社ものプロモーションが走っています。
つまり、商業的に軌道に乗っています。
③国に認められている
①②のように、多くの関係者を巻き込むには、制度やガイドラインも必要です。業界団体があり、政策提言や自主規制などロビイングをしています。
また、何気なく使うレベルの言葉は、公的な文書でも使われる、公共性のある言葉だったりします。
つまり、国に認められているのです。
①から③まで見ましたが、例えば、「自動車」「スピーカー」「LEDライト」「万年筆」など。日常で使いますし、根強いファンもいます。それぞれに関連する会社や業界団体もあります。
田端信太郎さんは『MEDIA MAKERS』の中で、あるジャンルが業界として成立する条件として、「それでメシを食ってる関係者の有無」と、「専門誌の存在」を上げています。
競技スポーツと同様、「プロ」と呼ばれるかどうかは別にしても、それでメシを食っている関係者がその周辺に少なからず存在しているわけです。業界が存在するとは、つまりはそういうことです。
私が指摘したいのは、広告主となる業者、取材対象となりコンテンツを供給する専門家の集合体としての「業界」の有無です。ゴルフやサーフィン、スケボー、盆栽、茶道にあって、缶けりにないものとは「業界」なのです。あるジャンルが「業界」として成立するかどうか、とそこに専門誌が存在するかどうか、は鶏が先か卵が先かの関係にあると私は思っています。
「業界」とは、それに関連する「言葉」とも読み替えられると思います。
何気ない言葉でも、ぼくのような素人が「ぱっと思いつけてしまう」というのは、すごいことだと思いました。
終わり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
