
螺旋状の視界 ベルンハルト・ラングと鈴木治行について幾つか
ベルンハルト・ラングのとあるCDを初めて再生したときのこと。筆者はあまりのポップな響きに驚き、ロックの音盤が間違って梱包されていたのかと疑った。フリージャズやプログレシヴ・ロックなど、先鋭的なポップミュージックからの影響を受けた現代音楽作品は数多い。しかしながら、そのまま他ジャンルで通用し得る響きが飛び出すことは希だろう。
クラシック至上主義に代表される、音楽ジャンル間のヒエラルキーに囚われないこと。それがラングの音楽の第一の特徴なのだ。このことは彼の経歴を一瞥すればよくわかる。1957年、オーストリアのリンツに生まれたラングは、当地のブルックナー音楽院という、いかにもクラシックの殿堂然とした教育機関に学んだが、程なくしてジャズの音楽家として活動を開始した。「現代音楽」の作曲家となってからも、自作にターンテーブルを大胆に導入し、erikmとDJユニットを組みもするラングは、経験豊かなDJとしての評価を確立している。そう、DJとはまさに、どのような音楽/ジャンルも、音盤上の情報として等価に扱える立場ではなかったか。この立ち位置ゆえに、ラングがベートーヴェンを素材としたとしても、その表現の在り方は、クラシックの伝統主義に立脚する作曲家、たとえばイェルク・ヴィトマンとは根本的に異なるものとなる。
鈴木治行の音楽は、ラングのそれに似ているとしばしばいわれる。それはまず、鈴木もまた、音楽ジャンル間のヒエラルキーを意識しない/させない作曲家だからに違いない。筆者はかつて、リモート授業で大学生相手に熱心に昭和歌謡を講ずる鈴木の姿を垣間見た。芸術一般に対する雑食性は鈴木生来の性分だろうが、これを大きく育んだのが映画音楽での仕事であることは疑いない。映画音楽の現場においては、作曲技術の粋を凝らした六声のフーガより、子供の鼻歌の方がシーンに相応しいということがしばしばある。実用本位の視点から音楽の機能を取捨選択することが、旧来のヒエラルキーを無効化してしまうのである。
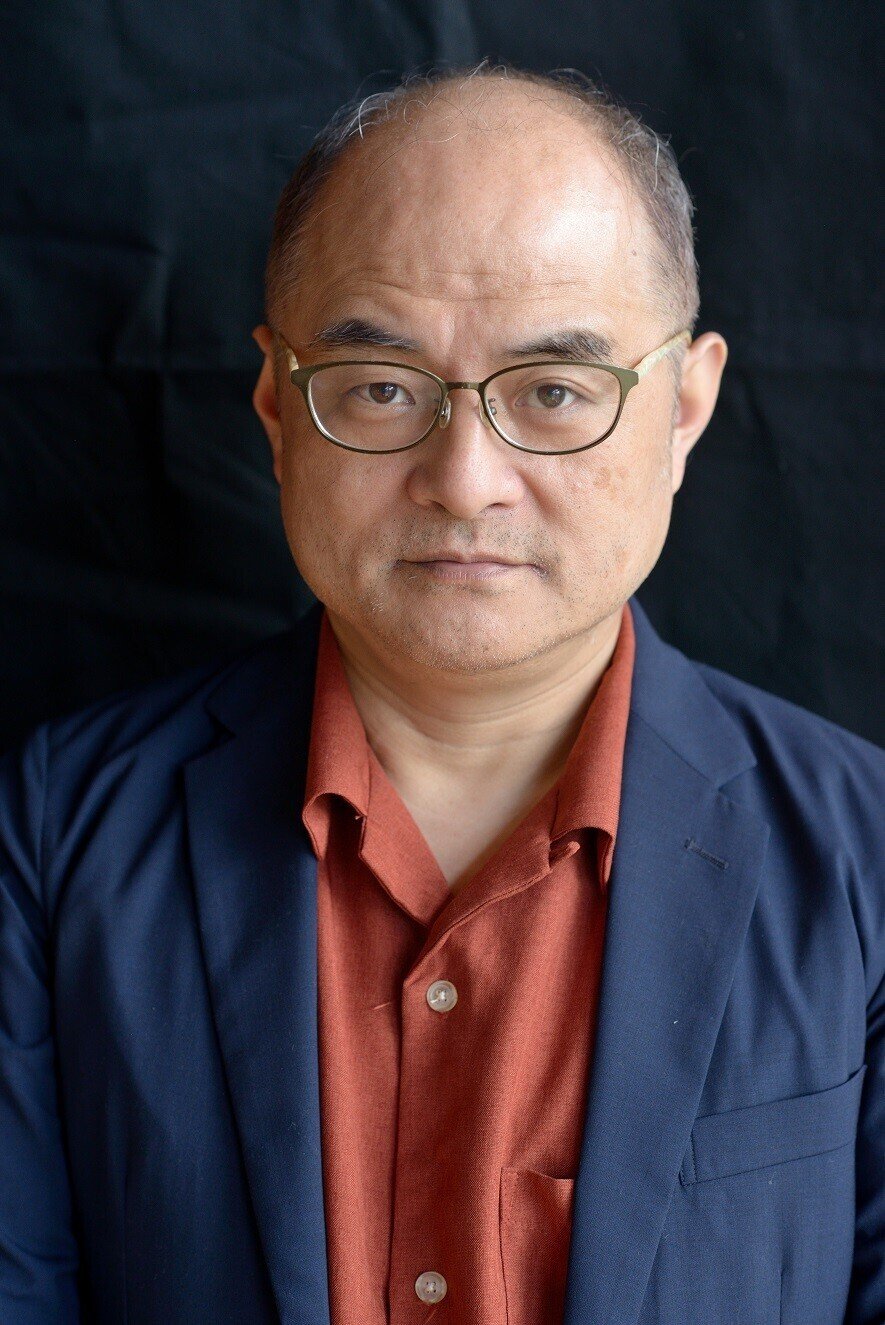
ただ、鈴木の現代音楽分野の作品を他ジャンルの作品と誤認することは、まずない。よって、その点で鈴木の音楽はラングのそれとは随分異なっている。ポップミュージックに対する態度は、鈴木の創作においては、些か内在化している。ならば、聴覚的に理解できる共通点は何か。すると鈴木もラングも、(疑似)反復語法を創作の中核に据えていることに気付く。
筆者は昨年、鈴木治行にとっての音楽の時間構造とは、「作曲家の意図が聴き手の認識に確と刻み込まれる仕掛けを含んだ、音楽形式の工夫」と書いた。この工夫の一例を比喩的に説明にするなら、このような感じになるだろうか。もし、あなたが柔道の試合に出て、相手に大外刈りをかけようとしたとする。だが、相手の脚だけをいかに執拗に狙ったとしても、技がかかることはない。力任せに一点を狙っても上手くいかず、たとえば、相手の袖を何度となく引くことで重心を崩しつつ、自己の攻撃パターンを相手に予想させ、その裏をかくように足をはらう。鈴木の音楽における(疑似)反復とは、この袖を何度も引くという動作に似ていなくもない。よって、オスティナート的に反復そのものの高揚を聴かせるより、次なる展開への仕掛けとしての性格を強く持つ。
対するラングもまた、反復の作曲家であることは、その作品を聴けば明らかである。そもそも、ラングは≪差異と反復≫という題名を冠した(言うまでもなく、この題名はジル・ドゥルーズの著書に拠っている)作品を、30作近く作曲していたではないか。ただ、ラングの反復もまた、鈴木とは別の意味でオスティナート的高揚からは程遠い。驚くほどにぶっきらぼうで、反復の回数すら、相当に適当に決めていると聞く。そうした中、ラングの作品においては、ある素材Aの反復が、全く相関しない素材Bへと移り変わる局面が多々存在する。ぶっきらぼうに素材を投げだしているような身振りが、その切断の鋭利さを際立たせる。
ラングと鈴木の差異は、各々の偶然性に対するスタンスを反映しているように筆者に見受けられる。ここで別稿の曲目解説を参照頂きたい。そもそもバロウズは、そしてラングは、なぜ「暗殺教団の開祖」ハサン・サッバーフにああまで肩入れしたのだろう?大シリアの山岳地帯にドラッグ・カルチャーを根付かせたから?なるほど、バロウズの場合はそうなのかもしれない。ただ、評論家/翻訳家の山形浩生はこう解説する。「かれがなぜバロウズのアイドルかというと、かれがカットアップの祖だったからだ。カットアップは、本のページを適当に切って切りつなぎ、新しい文章を作る手法だ。ハッサン・イ・サッバー(引用者注:サッバーフのこと)は、ある国の要人だったのだが、政敵の陰謀で、王の前で発表すべき文章を切り刻まれてしまい、それをそのまま読んだところでたらめな文章になってしまった。それでかれは失脚し、その恨みを晴らすべき暗殺教団を作ったのだ」。
ラングが≪モナドロジー≫で行っていることは、このカットアップの手法に近いものだ。アルゴリズムによって素材を用意しても、セル・オートマトン的な数理アルゴリズムが出力する素材は、複雑化するほどに予測不可能性を増し、入力する人間が想定する範疇にはまず収まらない。これは、旧来の美学に拠って立つならば「期待外れ」のものしか出力しないことを意味する。よって、そうした自らの期待を裏切る/超越する素材をとにかく拾い上げる行為は、かつてケージが行ったような偶然性の音楽に漸近する。ラングの作品で時に見られるぶっきらぼうさは、この素材の「偶然性」を作品に取り込もうとするラングの態度に起因するものであったのだ。
対して、鈴木治行は作品に偶然性を生のまま取り込むことはない。鈴木にとって重要なのは、あくまで音と音、音響と音響の関係性であり、偶然性を取り込むことはあっても、それが作品のフォルムを壊して暴走する可能性は注意深く排除されている(よって、作曲者の想定を大きく超えるような事態は起こりにくいともいえる)。鈴木のスタンスは、ケージやフェルドマンに代表されるアメリカ実験音楽を深くリスペクトしながらも、自らの方法論に基づき(初期作品を例外として)確定的な譜面を書き続けている近藤譲に近いように思う。
かのように、ベルンハルト・ラングと鈴木治行の音楽は、良く似たところを持ちつつも決定的に異なっている。各々の作品は互いに相補的な関係をもち、ならばこそ、二重螺旋状に屹立し、ポストモダンの音楽を切り拓くことができるのだ。
引用元
山形浩生:山の老人の絶望と孤独。 https://cruel.org/cut/cut200304.html
川村恵里佳ピアノ・リサイタル ~反復のOrient-Occident~
2021年9月30日 於:杉並公会堂
プログラム解説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
