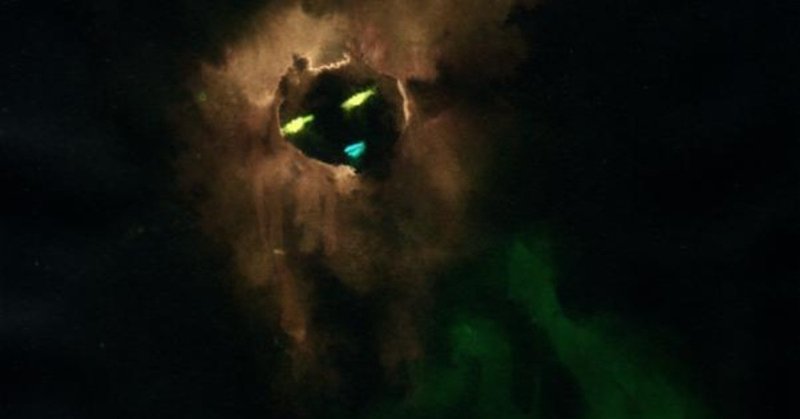
ドストエフスキー『地下室の手記』で人間の最奥に触れ、そして震える
フランクル『夜と霧』とか『アンネの日記』的な話かとずっと思っていたが、全然違った。
その地下室は、主人公である小役人の脳内にある、自意識渦巻く精神が逃げ込む堅牢な地下室であるという話。そしてそれは、不可侵な安寧の場ではなく、自分自身を縛り閉じ込め、グヂャグヂャに切り裂く拷問器具のような地下牢であるという話。
全編を通じて、主人公の独白形式でぐわーーっと話が進み、ほとんど事件らしい事件やダイナミックな展開は起こらないのだが、それでも、その内面がグロい、きつい。
「そう喋りながらも、自身が本当にはそれを信じておらず、むしろそうした言動を蔑んでさえいると気づいていた。だからといって、止めることはできない。引っ込みがつかないのだから。」
彼の語り口は、一事が万事上のような調子である。
自己肯定と虚栄心、周囲への憤りや蔑み、それら感情がほとばしる最中にあって、しかし常にそのすぐ裏側で虚偽を悟り、虚しさを自認しながら、自己否定、嘲笑、etcetcを重ね、それが何かに昇華することは決してない。そういった精神の在り方が彼の現実の認識を歪ませ、血の涙を流しながらも非合理で痛みを伴う振る舞いを続けさせる。
一縷の望みになるかと思われた愛の力も彼を救わず、幾度となく象徴的に使われる決闘-死という切り札も、ついぞ実行に至らない。
外見にはさざ波ぐらいしか立たない幕中での、異様に絡まりこんがらかった自意識の暴走に身震いしながら読み進めるが、しかし本当の恐怖は、自分の中にもこれと同根の精神のもつれ/絡まりをいとも容易に見つけることができること。
これは、著者がただただ想像の遊戯として脳内で結んだ架空の像では決してなく、僕ら人間に埋め込まれた、とてつもなくリアルでとてつもなく重い、醜悪な性、その写し鏡なのである。
この、どんなに平凡な人間の心中にもごく普通に潜むカオスを、心理学や人文知の枠組みで捉え、定式化することは難しい。唯一、小説というフォーマットだけが、吐き気がするほどの手触りを以ってこれらを抉り出す事ができる。
そして、そういった人間精神のエグ味を捉える解像度において、やはり人と社会の悲哀がぎっしり詰まった近代ロシア文学が随一だなぁと感嘆するし、ドストエフスキーがその圧倒的頂点に鎮座するということを、今回改めて認識した。
今後自分は「本書の通読を抜きにして、真に人の気持ちを理解することなぞできない」と言うだろう。ただしきっと、苦虫を噛み潰したような顔で。
いったい理性は利害の判断を誤ることがないのか?..(中略)..人間が苦痛をも同程度に愛することだって、ありうるわけだ。
..(中略)..
自意識は、僕の考えでは、人間にとって最大の不幸だ、などと説いたが、しかしぼくは、人間がそれを愛しており、いかなる満足にもそれを見変えないだろうことを知っている。
自意識は、たとえば、二二が四などよりは、限りなく高尚なものである。二二が四ときたら、むろんのこと、後には何も残らない。
頂いたサポートは、今後紹介する本の購入代金と、記事作成のやる気のガソリンとして使わせていただきます。
