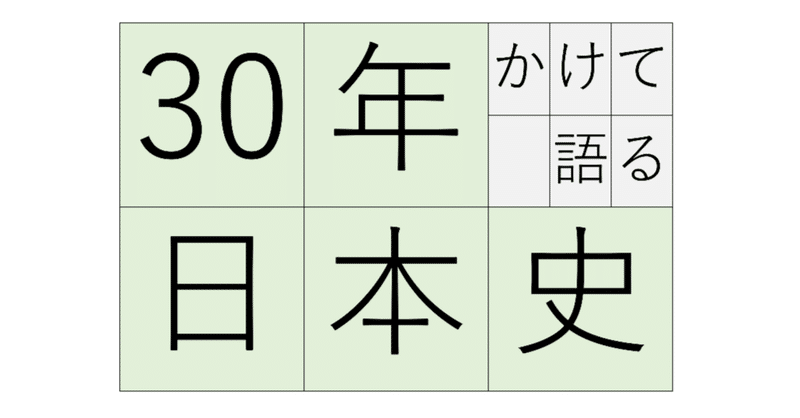
30年日本史00756【鎌倉末期】護良親王の逃避行 芋瀬の庄司
尊雲法親王改め護良親王は十津川で再起の機会を窺っていましたが、彼の十津川滞在はやがて熊野別当定遍の知るところとなってしまいます。
定遍は、今すぐ十津川に攻め込んだとしても勝ち目がないと考え、一計を案じました。あちこちに
「大塔宮を討った者には銭6万貫を与える」
との高札を立てたのです。いかな勤皇の精神にすぐれた十津川の住人たちといえども、こんな大金には目がくらんでしまうかもしれません。
事実、護良親王に住宅を提供している竹原八郎の息子までもが、裏切りを考え始めてしまいました。これを聞いた一行は、もはや十津川にはいられないと考え、竹原八郎の引き留めを振り切って十津川を脱出することとしました。
一行はとりあえず高野山(和歌山県高野町)へと向かうこととしました。
最初に通った難所は芋瀬(いもせ)という場所です。ここは現在の奈良県十津川村五百瀬(いおせ)に当たります。
芋瀬を治める庄司(しょうじ:荘園を管理する役人)は
「熊野別当から命令をいただいている以上、ただで通すわけに行きません。合戦をしたというふりをするためにも、熊野に報告したいのでお供を1、2名引き渡すか、あるいは紋章入りの旗を渡すかしていただけませんか」
と言ってきました。
何ともずるい態度ですね。護良親王の味方になってくれるでもなく、しかし合戦して傷を負うのも嫌がっているわけで、保身の塊のように見えます。
ここで名乗り出たのは側近の赤松則祐(あかまつそくゆう:1314~1372)でした。主君を救うために自分が捕虜になるというのです。
しかし平賀国綱(ひらがくにつな)がこれに反対しました。
「この艱難の中で御供をしている者は一人といえども貴重であり、手放すべきではありません。むしろ簡単に渡せるのは旗ではありませんか」
護良親王はこの意見を容れ、錦の御旗を芋背の庄司に渡すことで無事に通ることができました。
旗を渡すという行為はひどく屈辱的なことに思えますが、護良親王はあくまで合理主義者でした。側近を失うよりも旗を失う方がはるかに受け入れやすかったのでしょう。
ちなみに平賀国綱はあの江戸時代の博物学者・平賀源内の祖先といわれていますが、事実かどうか定かではありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
