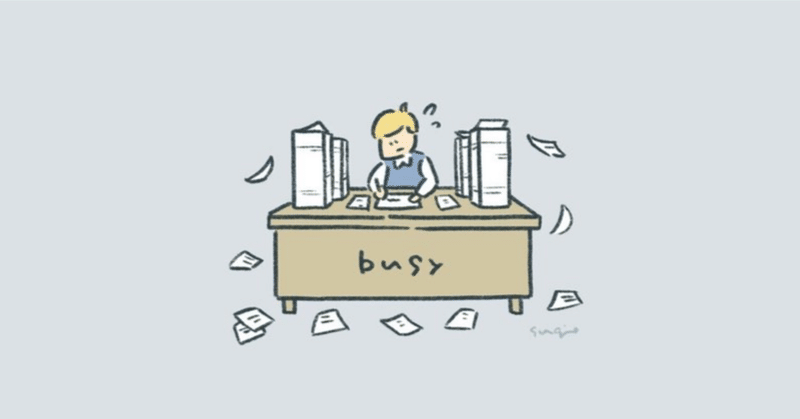
自分の中での生業の捉え方を変えてみようと思う
日本の終身雇用を崩そう、という動きが出てきたことで、転職エージェントや転職者が増えていき、ジョブ志向、そして適職・天職を求めていく時代に移り、終身雇用を求めている求職者は、もう少数派でないだろうか。
こうした雇用形態の変化とともに、「仕事」というものをどのように捉えるかの考え方がより変化してきている。生きるためにどんなことでもやる、「仕方なくやる事」と書いて、「仕事」と読む、という言葉も以前は聞いたことある。今の管理職以上の年代の人からは、特にやりたくない仕事も多くある、という大前提がある。それが時代の変化とともに、「適職・天職」志向として、仕事が「自己実現の手段」、「やりたい仕事」を目指していく人が増えている。そのある意味過剰性として、Z世代新卒社員の早期退職も問題視されている。(個人的には、大企業に入る以上、就活時にある程度いわゆる「上司ガチャ」がある事自体、わかることだから、大博打に出過ぎているような気もしなくないが、、、同じZ世代でも少し理解に苦しむ、、、)
とはいえども、日本の労働内容の自動化・機械化などが遅いこともあいまっているが、「嫌だけど誰かがやらなければいけない」仕事は未だ多くあり、そこには経済的な付加価値が発生しづらく、「エッセンシャルワーカー」問題として社会問題となっている。一部の人達に負担が偏り、それがほぼ貧富の格差と相まって固定化してしまうのである。世間には無視して生活している人がかなり多いが、個人的にはどうにかならないもんか、と思っている。(と言いつつも、何もできずSEのポジションに甘んじてしまっているが…)
これからあらゆるエッセンシャルな仕事が自動化させられていくのか、はたまた違う形になっていくのか、わからないが、嫌なことでも誰かがやらなければいけないし、そうでなくても、そもそも人生というのは理不尽なことはたくさんある。嫌なことでも生きていくためにやっていかなくてはいけなくなってしまうこともある。全てを思い通りに進めることは、神様ではないので無理なのである。
そんな中で、私は、よく調べていたように、好きなことから天職を探していくことを単純に目指していたが、動機があまりよくなかったように思う。「やりたくないこと、嫌なこと」から逃げることばかり考えていたように思う。理不尽な世の中では、逃げようとしてもあらゆる苦手分野が襲ってくるものである。もちろん、無理して苦手を伸ばさないといけないわけではない。しかし、完全に逃れられる、と思っていることが大きな間違いであった。
「やりたくないこと、苦手なこと、やらなければいけないこと」を上手く勧めていくためには、自分で乗り越える、の他に、他の人に頼る、あるいは自分が乗り越えられるように他の人に助けてもらうという手段もある。当たり前だけどすっかり忘れていた。だからこそ、苦手な人間関係は、全てをシャットアウトしてしまうのは良くないのかも知れない。その塩梅は難しいと思うが、人助けをして置くことで、思いもよらないところから助けてもらえるかも知れない。そこは、修行である。一見苦手な人でも、自分のスタンスが悪かっただけで、自分が変わればいい関係を築ける様になることもある。
そして、「天職」志向が出てきて、自分の「天職」を見つける・作ることに成功しても、そこはゴールではなく、結局のところ、「天職」であっても、人生の目的のための一手段であることは変わりないのではないだろうか。
自分がなぜその「天職」を求めているのか、職業で何をなしたいのか、どういう価値を発揮したいのか、目に見える形よりも大事な要素があるのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
