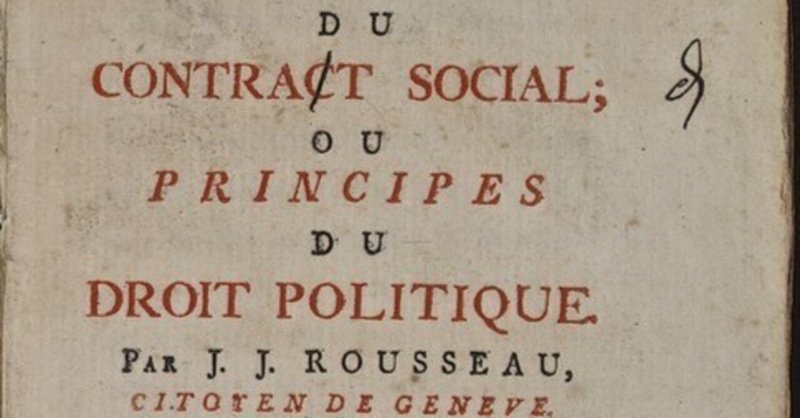
ルソー『社会契約論』を読む(14)
さて、今回からは第四篇。『社会契約論』もいよいよラストスパートです。さっそく読んでいきましょう。
一般意志は破壊できない
多数の人間が結合して、自分たちを一体であると考えているかぎり、彼らは共同体の保存と全体の福祉とにかかわるただ一つの意志しか持っていない。〔注1〕
ここで言われる意志、それは「一般意志」です。この点はもう大丈夫でしょう。ここまでルソーを読んできた人なら、わかるはずです。
一般意志だけが支配する国家。そこでは、国家のあらゆる原動力は活気に満ちて単純で、国家の格率は明快であり、光り輝いています。そこに利害の対立や矛盾はまったくありません。こうした国家では、ごくわずかの法律しか必要とされません。さらに、新しい法律を公布する必要が迫ってくるにつれて、その必要が誰にも見えてくるので、立法の提案者は、すべての人々がすでに感じていたことを口に出した、というただそれだけです。
意外かもしれませんが、法律は「少なければ少ないほど」良い国家だ、とルソーは(もちろん条件つきですが・・・)考えています。その条件が、先ほど引用に挙げた箇所です。たくさんの法律が必要、ということは要するにそれだけ国家に「マズい」人々が多く、「マズい」状況に国家が直面している、ということの裏返しなわけです。
例を挙げましょう。「たばこのポイ捨てはやめましょう」とか「万引き注意」とか、そんなポスターや看板がたくさん貼ってある街と、そんなものは一切存在しない街。どちらが清潔で治安が良い街でしょうか。警告があるということは、それだけその地域には、たばこを道に捨てる人や万引き被害が多いということです。だから、国家も同じで、法律は少なければ少ないほど、うまく統治されている、ということが言えるのです。
さて、そうはいっても、社会の結び目がゆるみ始め、国家が衰え始めたとき、また、特殊な利益が意識に上り始め、いくつかの小社会(徒党)が大社会に影響を及ぼし始めるときには、当初見られたような共同の利益は実質を失い、それに敵対する「マズい」人や状況が出てくる、といいます。そうすると、
投票においても、もはや全員一致が支配することはなく、一般意志はもはや全体の意志ではなくなる。対立や論争が起こり、どんなに立派な意見でも、論争なしには通らなくなる。(p.213)
そして、国家はやがて滅亡に近づき、もはや欺瞞的で空虚な形でしか存続しなくなり、社会のきずながすべての人々の心のなかで断ち切られ、もっとも卑しい利害さえもが厚かましくも公共の福祉という神聖な名で身を装うようになる、といいます。そこに至り、「一般意志は口をきけなくなってしま」(p.213)い、特殊な利益しか目的としない不正な命令が、法律という名のもとに誤って可決されてしまうことになるのです。
しかし、そうあってもなお、一般意志は生き続けます。
一般意志はつねに健在であり、不変で、純粋である。だが、一般意志は、それに打ち勝つ他の意志に従属せしめられている。(p.214)
ルソーは、一般意志への希望を持ち続け、あくまでも議論を続けようとします。
だからこそ、前回までで大事だと言われてきた「集会」で公の秩序を守るためには、「その集会において一般意志を維持することよりも、むしろ一般意志がつねに意見を求められ、つねに答えるように仕向けること」(p.214)が欠かせない、とルソーは主張します。
つまり、ここから先考察すべきことは、「主権の行為そのものとしての投票という単純な権利、すなわち何びとといえども市民から奪うことのできないこの権利について、また、自分の意見を表明し、提案し、議事を分割し、討議する権利、すなわち政府がつねに細心の注意を払って、政府の構成員にしか認めまいとしている権利について」(p.214)である、と述べ、議論をさらに深めていきます。
投票について
集会において、調和が支配していればいるほど、すなわち、意見が満場一致に近づけば近づくほど、一般意志もまた、それだけ優勢である。これに反して、長い討論や紛糾や喧騒は、特殊な利益の台頭と国家の衰退を告げている。(p.215)
ルソーは、一般意志を実現するために、できるだけ満場一致であることが望ましい、と考えます。そして、その「全員一致」について次のように語り始めます。
全員一致の同意を成立にあたって必要とする法は、その本性からいって、ただ一つしかない。それは社会契約である。(p.215-216)
もちろんあらゆる法律、政策を全員一致で進めていこう、というのはとてもじゃないけれど無理だ、ということはルソーは重々承知しています。しかし、それは全員一致が必要ない、ということを言っているのではありませんし、「必ず全員一致でなければならないものが、ただ一つだけある」というのです。それが、「社会契約」です。その理由は、いかなる人間も生まれながらにして自由であり、自己自身の主人であるから、何びとも、彼の同意なしには、どんな口実のもとでも彼を服従させることはできないからです。
他方、ルソーは、この原初の契約以外は、最多数者の意志が他の人々を拘束する、という多数決の原理を採用します(ここは私たちの常識とも一致する見解ですね)。
では、その話し合いの場面では「何が」話し合われているのでしょうか。それは、「彼らが提案を承認するか拒絶するかということではなくて、それが人民の意志たる一般意志に合致しているかいないか、ということなのである」(p.216-217)とルソーは説明しています。
つまり、議会で提案されている議案が「一般意志と合致するか否か」について、各人は投票を通じてこれについてのみずからの意見を表明します。私の意見と反対の意見がもし勝った場合は、つまりそれは、「私が思い違いをしていた」ということなのであって、「一般意志ではないということではない」のです。
しかし、多数意見が無条件に一般意志というわけでももちろんありません。その比率に応じて一般意志であるか否かを判断する必要があります。
①討議が重要で深刻なものであればあるほど、勝を占める意見は、全員一致に近づかなければならないということ。
②検討されている問題が迅速な決定を迫っているものであればあるほど、賛否の取り方についてあらかじめ定められている差をいっそう狭めなければならないということ。(p.217-218の要約)
そして、「これらの格率のうち、第一のものは、法律を定める場合にいっそう適しており、第二のものは、政務を決める場合にいっそう適しているように思われる」(p.218)と続けます。
選挙について
統治者および行政官を選出する方法は、二つ存在します。一つは選挙、もう一つは抽選です。ルソーは、「抽選」が望ましいと考えます。
なぜでしょうか。それは、行政官という職は、(私たちの常識的な理解に反して)、利益ではなく重荷だからです。また、全員が政治的原則や財産に関して、さらに品性や才能に関して平等な世の中ならば、選択はほとんどどうでもよいこととなるからです。
つまり、真の民主政にとって、統治者および行政官を選出する方法は、わざわざ選挙という複雑な方法を採る必要などなく、抽選でいっこうにかまわないのだ、とルソーは考えているのです。しかし、何でもかんでも抽選でよい、と考えているわけでもありません。
前者(=選挙)は軍務のような特別な才能を必要とする地位を満たすのに使われるべきであり、後者(=抽選)は司法官職のような、良識、正義、潔白だけで十分な地位に適している。(p.219-220)
護民府について
さて、以上の議論のあとで、ルソーは「護民府について」と題して新たな議論を始めます。ここも、『社会契約論』の中でとても重要な箇所です。では、護民府とは何でしょうか。少なくとも現代の日本では聞き慣れないこの団体をルソーがどのように定義しているか、まずは見てみます。
他の官職と一体をなすことなく、各項をその正しい比例関係に置き直し、あるいは統治者と人民のあいだの、あるいは統治者と主権者のあいだの、もしくは必要とあれば同時にこの二組の比のあいだの、連絡役あるいは中間項となるもの(p.232)
ルソーは上記の引用に続いて、護民府とは、「法律と立法権の維持者」(p.232)であり、それはローマの護民官のように、政府に対して主権者を保護したり、ヴェネツィアの十人評議会のように、人民に対して政府を支持したり、スパルタの監督官のように、両者の均衡を維持することに役立ったりする存在だ、といいます。
この護民府の大きな特徴として、立法権、執行権をほんの一部でも、決して分かち持ってはならない、という点が挙げられます。なぜなら、法律と立法権を維持するためには、みずからは何もなしえないことになっているからこそ、すべてを阻止することが許される存在であり得るからです。法の守護者としての資格において、法を執行する統治者や、法を制定する主権者よりも、いっそう神聖であり、いっそう尊敬される。そんな存在が、護民府なのです。
しかし、護民府は、ほんの少しでも力を持ちすぎるとこれまで議論されてきたことすべてを覆してしまいます。つまり、護民府が力を持ちすぎたとき、その政治はかならず僭主政治に堕するのです。護民府は執行権の調停者にすぎないのに、この執行権を簒奪することが起こり得る。あるいは、法律を保護するだけでとどまらねばならないのに、法律を授けようと望むことがあり得る。これこそ、護民府による簒奪行為であり、彼らが簒奪した権力は、かつては自由のためにつくられた法律に助けられて、けっきょくは、自由を破壊する皇帝の擁護に役立つに至るのです。
ならば、護民府の権力簒奪を予防する方法はないのでしょうか。ある、とルソーは言います。それは、この団体を常設のものとせず、間隔を定めて、その間はこれを廃止しておくこと、です。彼らの任期はできるだけ短い方が良いし、必要とあれば特別委員会が人気を短縮することも必要だ、と主張するのです。
では、なぜ「護民府」が大切なのでしょうか。ルソーは、今更(最終篇にもなって)何を言い出すのでしょうか。
その理由は、現実の政治においては、有事のときに、政治的判断で超法規的な措置を取ることがある、ということをルソーが洞察していたことと関係しているように思えます。もちろん、その超法規的判断が本当に正しい判断なのかどうかは、後の時代に検証されることです。しかし、そうした「政治的判断」はなぜ可能なのでしょうか。言い換えれば、通常の民主主義的なプロセスを経ずに、どうしてトップダウン式に意思決定することが違法ではないのでしょうか。ルソーは、こんな風に言います。
危機が深刻で、身を守るのに法律という装置が障害になるような場合には、すべての法律を沈黙させ、主権を一時停止するような最高の首長一人を選んで、任期をごく短い期間に限り、けっして延長できないようにすることによって、独裁制を敷くことが必要だ。(p.234-237を要約)
民主主義者ルソーともあろう人が、独裁制を容認しているかに見えるのです。意外ではありませんか。民主主義を愛したルソーが、その対極にある独裁を必要だと考えているように見えるなんて。でも、これにはいくつか制限があります。
その制限とはまず、立法権の停止はけっして立法権の廃止ではなく、立法権を沈黙させるこの行政官は、それを語らせることはできない、ということです。つまり、彼はそれを支配しはするが、代表することはできない。彼はあらゆることをなしうるが、法をつくることだけはできない、という制限がないと、全体主義のような悲惨な政治になってしまう、と考えているのです。
また、もう一つ制限があります。それは、「任期をごく短い期間に限り、けっして延長できないようにすること」(p.237)という条件です。あまりにも任期が長いと、僭主政治に堕落してしまうことは言うまでもありません。さし迫った必要が満たされてしまうと、あとはやりたい放題。しかし、もちろんのこと、僭主政治に堕するリスクだけを考えていては、国家が滅亡してしまうかもしれません。だからこそ、その危機に対応するためだけの任期をただ一人に与えて、その人はその問題にとにかく必死になって対処させる、そして、その人は問題を対処したらすんなりと辞めてしまう、ということが、現実的に最も妥当な対応策だ、とルソーは考えているのです。
江戸時代に「大老」という役職があったことを思い出されると、イメージが付きやすいかもしれませんね(井伊直弼が有名でしょうか、まあごく短い任期だったか、と言われれば違う気もしますが・・・)。
あるいは、現在問題になっているウクライナ侵攻を例に考えると、ゼレンスキー大統領は、「いまだけは」独裁制のように政治をすることは許容される、ということが言えそうです。なぜならば、
独裁官は、彼が選ばれるにいたった必要に対処する時間しか持たなかった。彼には、他の計画を考えたりする時間の余裕はなかったのである。(p.237)
次回予告
以上の議論は、決してオマケとして論じられていることでは決してないということを、賢明な皆さんならばきっと理解されることでしょう。ルソーはまた、「世論の腐敗を防ぎ、賢明な実施によって世論の正しさを保ち、ときには世論がまだ定まらない場合にこれを固めさえして、習俗を維持する」(p.238)ために監察制度を設ける必要がある、という主張もしています。ここは、世論の重要性、あるいは世論の役割について述べている箇所で、専門的にルソーを研究される方にとっては、政治哲学的な文脈においてとても重要なポイントのようです。と言いながらここでは詳しく立ち入ることはしません。『社会契約論』を読み終えるべく、次回は「最終章」を読んでいくことにします。
それでは、お楽しみに!
ーーーーーーーーーー
本文中に〔 〕で示した脚注を、以下に列挙します。
〔注1〕『ルソー全集 第五巻』作田啓一訳、白水社、1979年、212頁。以下、本記事において、特に断りなく頁数だけが示されている場合は、ここにあげた白水社版『ルソー全集 第五巻』の頁数を示しているものとします。
ーーーーーーーーーー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
