
【一気読み・長編小説】「あっとほーむ ~幸せに続く道~」第三部
こちらは「あっとほーむ~幸せに続く道~」第三部(全12話)を通しで読めるようにまとめた記事です(一部、加筆修正してあります)。
AIで生成したイラストも挿絵として使用しています。また、番外編として投稿した『ワライバでのとある一日』も挿入してあります。冒頭には、第一部・第二部のあらすじも再掲していますので、初めての方でも本記事から楽しんでただけます。長編ですが、お時間がある方、通しで読みたい!という方はぜひご覧下さい🥰
第一部・第二部あらすじ
第一部
父親の急逝で体調を崩した鈴宮悠斗。それをみた野上彰博、映璃夫妻は、彼に「家族にならないか」と申し出る。彼らの養子であるめぐと将来的に結婚して欲しいという意味だ。しかし戸惑う悠斗の前に、めぐの従兄・野上翼が現れて「俺にもめぐちゃんと結婚する資格がある」と言い始める。二人は互いをライバルと認め、めぐを振り向かせるために試行錯誤を繰り返す。
一方のめぐは一度に二人も恋人ができたことで舞い上がる。が、どちらにも「あなたが一番」というそぶりを見せたことで二人の、とりわけ悠斗の機嫌を損ねさせてしまう。結果、「高校生の恋愛ごっこには付き合えないから」と、しばらく会ってもらえなくなる。
ただ好きなだけではダメなのだと気づいためぐは悩みに悩んだ末、二人を平等に愛することを決意する。想いを伝えると二人はあっさり受け容れてくれた。聞けば二人はめぐがそのような決断をするだろうと予想し、それがめぐの幸せに繋がるなら喜んで受け容れようと話していたのだという。
三人の望みは、三人で暮らすこと。しかしめぐの父親である彰博は首を縦には振らなかった。そのかわり、しばらくの間五人暮らしをするのはどうかと提案する。一緒にいることが目的である三人はその提案を受け容れる。
野上家の人たちと関わる中で、心を病んでいた悠斗と翼はそれぞれに傷を癒やしていく。そして互いの絆をより強固なものにしていく。
第二部
その日、めぐは十八歳の誕生日を迎えた。三人は、めぐが高校を卒業したら今度こそ三人暮らしの許可を得ようと密かにその準備を進めている。しかしめぐには一つ気になることがあった。悠斗と翼の仲があまりにも良すぎる点だ。もしかしたら、男同士で愛を確かめ合っているのでは? そんな疑念を抱いためぐは二人の寝室に押し入る。しかし目にしたのは、めぐの身体を奪い合わないために自制している二人の姿だった。
またもや稚拙な行動を取ってしまっためぐは、いよいよ自己成長が必要だと感じてアルバイトを始める。そんなめぐをみた悠斗も自分探しをするため、娘を亡くした沖縄の海を訪れる。その間、翼も実家に戻り、父との和解を果たす。 成長し、三人のこれからについてそれぞれの解を見つけた彼らは野上家で再会する。
悠斗は、めぐと翼の結婚こそが自分の幸せに繋がるという答えを出した。
翼は、めぐへの思いを強くし、再びプロポーズをした。
そしてめぐは、翼の深い愛情を知って彼との結婚を決めた。
すべてが丸く収まったことで満足した悠斗は、三人暮らしをする予定で手入れをしていた実家に一人、戻ることを告げる。が、二人がそれを許さなかった。二人は、自分たちの暮らしには悠斗が不可欠だと考えていたからだ。引き留められた格好にはなったが、悠斗は二人の思いに感謝し、引き続き一緒に暮らすことを決める。
彰博の許可も下り、三人は予定より早く三人暮らしをすることとなった。 しかし、新生活が始まったのもつかの間、めぐと翼の祖父が倒れた。婚約はしたが結婚は先、と考えていた二人は、祖父の余命を思って結婚を前倒しすることを決める。
翼が二十九歳の誕生日を迎えたその日、二人は神と親族に祝福されて結婚する。そしてその晩、二人ははじめて互いの身体を知ったのだった。
翼とめぐの結婚式を終えた日の晩、悠斗の元に亡き娘の魂がやってきて「もうすぐ会える」と語りかけた。そしてめぐの前にも同様に現れて「あなたが望めばわたしがあなたの赤ちゃんになる」と告げる。しかし新しい命は身近な人の命と引き換え――。そう告げられて戸惑うめぐであった。
一 共同生活
<悠斗>
オジイとオバア、そしてめぐと翼。鈴宮家なのに、野上姓ばかりのいるこの家の、なんとも不思議な暮らしは想像していた以上に充実している。そう感じるのは、おれ自身がすでに両親を亡くしていて老齢の親と暮らさなかったこともあるだろうし、若い夫婦を見守ることが使命感になっているせいでもあるだろう。
共同生活を始めて三ヶ月。九十代の老夫婦の世話をするのは正直しんどい。しかし、おれが両親に返せなかったぶんの恩を返せるとしたらこれしかない、という気持ちで日々過ごしている。その甲斐あってか、オジイもオバアも比較的元気でいるし、めぐと翼も祖父母と暮らせることを喜んでくれている。そんな彼らの笑顔がおれを幸せにする。自分が五十歳にさしかかっていることも忘れてしまうほどに。
「家族とはいえ、悠斗さんに身の回りの世話をしてもらって申し訳ないね」
オジイはいつもそう言って頭を下げる。息子たちが世話をするのと違い、わがままも通せないからだろうか。
「いえ。申し訳なさを感じる必要なんてないですよ。おれにだって、言いたいことは何でも言って下さい」
「……なら一つ、聞いてほしいことがある」
「はい、なんでしょう?」
「……長年住んできた家を処分しようと思ってるんだが、売れたらその資金を受け取ってはくれないだろうか」
「……え?」
何でも言ってくれとは言ったが、さすがに驚きを隠せなかった。
「いや……。売る手続きをして欲しいと言うならやりますが、売れたお金をおれが受け取るわけには……」
「うむ、実はこの話には続きがあってな。家が売れた暁にはそのお金で鈴宮家を修繕するのはどうかと思っているんだよ。もちろん、じいちゃんたちが住むためにするんじゃない。君たちがこの家でこれから家庭を築いていくと言うなら、手入れは必要なんじゃないかと思うわけだ。まぁ、高い値がつくとは到底思えないが、修繕費くらいにはなるだろう。こうして世話をしてくれるお礼と思って受け取ってはくれまいか?」
確かにこの家はおれがまだ幼かった頃に両親が購入したもので、築四十年以上が経っている。めぐや翼たちと暮らすにあたり、傷んだ床や畳は交換したものの、外壁や屋根などは両親が二十年ほど前に修繕したきり。オジイが気に病むのは至極もっともなことだ。
「彰博には……息子さんたちには話しているんですか?」
「言っておらん。常識的に考えれば、家の売却益は息子に分配するのが筋なんだろうが、じいちゃんは悠斗さんに受け取ってもらいたいんだよ」
「…………」
仮に家が売れれば、かなりの金額になるだろう。それに、おれが受け取るとなれば法的な手続きだってきっと必要になる。簡単に「受け取ります」と言ってしまえるような話じゃないはずだ。
「……オジイの気持ちは分かりました。でも、まずは彰博たちに相談させて下さい。彼らがいいと言ったら、その時は前向きに検討します」
「ああ、頼んだよ」
◇◇◇
その週末、両親の様子を見に来た彰博に、オジイからもらい受けた話を伝えた。案の定、彼は寝耳に水といった様子で驚いた。
「……昔から突拍子もない思いつきをする父だったけど、最後の最後にそんな提案を君に持ちかけるとは」
「おれも驚いてる。だからこその相談だ。お前の率直な意見を聞きたい」
「……僕はもうあの家を出て久しいし、父がそう言っているなら家をたたんでもいいと思う。もちろん、これは僕の意見であって、母や兄貴の考えも聞かなきゃいけないと思うけど。家が売れたときのお金をどうするかについても」
「そうだよな……」
「相談してくれてありがとう。早速このあと両親と話し合ってみるよ。兄貴にも声をかけてみて、時間がありそうなら鈴宮家に来てもらおう。構わないかな?」
「ああ。むしろ、そうしてくれると助かる」
「ありがとう」
そう言うと、彰博は早速スマホを取り出して電話をかけ始めた。
「悠くん? パパと何を話していたの?」
玄関で立ち話をしていたら、めぐがそばにやってきた。
「今、家をたたむって聞こえたんだけど……。もしかして、古くなったこの家を……?」
「そうじゃないんだ。……そうだな、めぐや翼も話に加わった方がいいかもしれないな」
「なになに? 一体どうしたんだよ?」
妙な空気を感じ取ったのか、翼もそわそわした様子で現れた。そこへ、電話を終えたらしい彰博が輪に加わる。
「兄貴はすぐに来てくれるそうだ。……あの様子じゃ、今日は大変な一日になりそうだな」
彰博がため息をついた理由はその後、すぐに判明することとなる。
*
十二月だというのに、彰博の兄は汗だくでやってきた。どうやらここまで走ってきたらしい。そしてやってくるなり靴を脱ぎ捨て、居間に飛び込んだかと思うと「どういうことだよ、親父!」と大声でまくし立てた。
「父さん、そんな大声を出すなよ。外にまで聞こえるだろ?」
翼が慌てて制するが、彼は聞く耳を持たない。
「お前は黙ってろ! おれは今、親父に聞いてるんだ。実家を手放す話はまぁ、いい。だけど……ここにいる鈴宮君に売れたお金をあげたいって話は納得できねえ!」
怒り狂った彼は、ツバを飛ばす勢いで語った。が、オジイは車椅子に座ったまま泰然としている。
「路教のそういう態度に嫌気がさしてる、と言えば分かるか?」
静かな語り口調だった。にもかかわらず、場が一瞬にして凍り付く。彰博の兄が拳を握りしめたのが分かった。オジイは続ける。
「路教はじいちゃんやばあちゃんのことを、厄介者のお荷物だと思っている。それが言葉の端々から感じられるんだよ。退院後の同居話を持ち出されたときに断ったのもそういう理由だ。お前にやいのやいのと言われながら暮らすくらいなら、親身に世話をしてくれる悠斗さんや孫たちと一緒に暮らす方がずっといい。……悠斗さんは本当に優しいよ。お礼がしたいと思うのはごく自然なことじゃないか」
「…………」
「路教。わたしもおじいさんと同じ考えよ」
オバアも話に加わる。
「かつてのように自由に動けないのはわたしたちが一番分かってること。その悔しい気持ちに、悠斗君はそっと寄り添って下さるの。ゆっくりでいいですよって言って下さるの。日々、仕事に追われているあなたにそれが出来る?」
「…………」
「あなたが悠斗君に負い目を感じているのも分かっているつもり。でも、忙しいあなたに代わって悠斗君がわたしたちの世話をしてくれるのよ? その礼金を、自宅が売れた分で支払うと思ってもらえないかしら?」
「つまり、おれでは母さんたちの役には立てない、と。それを金で解決しろ、と」
彼は不満そうな顔のままおれに問いかける。
「……鈴宮君はどうしてそこまでおれの両親のために尽くしてくれるんだ?」
「親孝行がしたいんです。自分の親は急逝してしまって、恩を返せなかったので」
「自分の親に出来なかった親孝行を、他人の親に出来るものなのか……」
その目がおれを疑っているのが分かった。ひょっとしたら、おれがオジイに金の無心をしたと思っているのかもしれない。それならば、あの剣幕も理解できる。
おれを睨み付ける彼をなだめるように、彰博が言う。
「兄貴。悠は裏表のない人間だ。……別の言い方をすれば馬鹿正直に生きてる、とも言えるけど、今の言葉は決して下心から出たものじゃない。そして普段からそういう人間性がにじみ出るような話し方をするから、父さんと母さんも安心感を抱いているんだと思うよ」
彰博の言葉を受けて、彼の兄を除く全員がうなずいた。ちょっぴりこそばゆかったが、彰博はじめ、ここにいる家族がおれを信頼してくれていることが誇らしくも思えた。彰博がなおも言う。
「兄貴はもう分かってると思ってたんだけどな。悠の素晴らしさを。もし分かってなかったんだとしたら……いや、腑に落ちていないんだとしたら、一度しっかり語り合ってみたらいい。彼の本懐を知れば兄貴だってきっと……」
「わかってるよ。鈴宮君がいい人だってことは。ただ……このまま鈴宮君に最後まで頼ってしまったら後悔するのは目に見えてる。……おれは後悔したくない。おれに出来ることがあるならやりたい。ただ、それだけのことなんだ」
「それなら、おれも同じ思いです。いや……。後悔したからこそ、今必死に取り返していると言えるかもしれません。……もし、お兄さんが反対ならお金は受け取りません。オジイが心配するような修繕が必要になった場合は自分で工面すればいいだけの話ですから」
「…………」
「あのー……わたしから提案なんですけど、いいですか?」
その時、めぐが遠慮がちに手を挙げた。視線を一手に引き受けためぐは恥ずかしそうにもじもじしながらも発言する。
「もし……もしですけど。伯父さんさえ良ければ、週末だけでもここに寝泊まりするって言うのはどうでしょうか。平日は仕事がメインで無理だとしても、休みの日だったら、少しは心に余裕を持った状態で、おじいちゃんとおばあちゃんのお世話が出来るんじゃないかなって……」
「えっ? いや、だけどそれはさすがに迷惑じゃ……」
「ああ、俺もその意見に賛成」
めぐの発言を受けて同意したのは翼だ。
「父さん、じいちゃんとばあちゃんのことが気がかりなんだろ? 悠斗に任せっぱなしも嫌なんだろ? だったら、父さんに出来る範囲でやったらいいじゃん。俺たちは別に構わないからさ」
「しかし、鈴宮君がいいと言うかどうか……」
困惑する彰博の兄に、おれは深くうなずく。
「手伝って頂けるならおれとしても有り難いです。こういうことはやっぱり、実の息子がやるのが一番だとおれだって思ってますよ。彰博のお兄さんがいてくれたら、オジイだってもうちょっとわがままが言えるでしょう」
「……ふっ。もう充分わがままを言ってるような気もするけどな」
彼はようやく笑った。
「わかった。鈴宮君がそう言うなら、早速この週末から、今日から始めよう。そしてきちんと話し合っておこう。家のことや、その先のことを……。親父、母さん、それでいい?」
「……路教は頑固者だからな。そう決めたなら、こっちがなんと言おうと意見を曲げないことくらい知っているよ。ああ、路教の好きなようにすればいい」
「そうねぇ。『後悔したくない』は、あなたの口癖だもの。気の済むようにしてちょうだい」
オジイとオバアはそう言ってゆっくりとうなずいた。
*
「おれの家族が信頼を寄せている理由がやっと分かったよ。確かに鈴宮君は、一緒にいたいと思わせる何かを持っている」
週末をこの家で過ごす用の荷物をまとめ、再びやってきた彰博の兄は、荷ほどきをしながらぽつりと呟いた。それから「あー、そうそう。呼び方のことだけど」と話を続ける。
「ここで世話になる間は好きに呼んでくれ。ただし、家族っぽい感じで頼むぜ。よそよそしいのは嫌なんだ」
それを聞いて、オバアとした会話を思い出し、笑いそうになる。やはり親子なのだな、と思ったからだ。
「そうですね……。じゃあ、ニイニイはどうでしょう? 母の出身地の沖縄方言で『お兄さん』という意味なのですが。おれは兄弟がいないんで、彰博が兄貴って呼んでるのが実は羨ましくて」
「おう。実の兄だと思って慕ってくれよ。おれも、素直な弟分なら大歓迎だ。彰博は反論が多くて面倒だからなぁ」
ニイニイはそう言いながら豪快に笑った。
*
本当の家族になって欲しい――。
彰博たちに打診された数年前のおれは、めぐと結婚し、名実ともに彼らと「家族」になりたいと思っていた。しかし、めぐとは結婚しなかったにもかかわらず、どういうわけか息子や娘、オジイやオバア、そしてニイニイと……。次から次へ野上家の人たちと家族みたいに関わり合っていくおれがいる。
これはもはや、おれが思っていたとおりの未来と言っても良かった。父が急逝したときは天涯孤独の身になってしまったと落ち込み、生きる気力さえ失ったが、おれは今、再び幸せの只中にいる。
(親父、お袋。この幸せが一秒でも長く続くように祈っていてくれ。新しい家族との日々を、少しでも長く楽しみたいんだ……。)
一人になったタイミングを見計らい、仏壇に向かって手を合わせる。
――生きている限り、素直でいる限り、助けてくれる人が集まってくる。だから悠斗は、決してひとりぼっちにはならないんだよ。これからも、ありのままの悠斗でいれば大丈夫……。
どこからともなく、そんな声が聞こえた気がした。

<めぐ>
翼くんと結婚してもわたしの暮らしは変わらない。卒業までは高校にも通うし、朝は相変わらず悠くんがバイクで送ってくれる。しいて挙げるとするなら、住所が変わったことくらいだろうか。
クラスメイトが必死になって受験勉強に励む中、わたしは比較的のんびりと残りの学校生活を送っている。というのも、卒業後は進学しないと決めたからだ。その代わり、いま働いている喫茶店「ワライバ」で引き続き雇ってもらう予定になっている。翼くんが社会勉強は必要だと言っているし、わたしも「ワライバ」で働くことが楽しいと感じ始めている。料理の腕も少しずつ上がってきているから、このまま修業を続けていこうというわけだ。
友人の木乃香はわたしのことを大層うらやましがっていて「あたしも早く結婚したい!」と口では言っているものの、父親の後を継いで菓子職人になるべく目下、受験勉強に励んでいる。ときどき巫女さんの仕事をしていたから、てっきり神社の後を継ぐのかと思っていたが、わたしの結婚式で悠くんに口の悪さを指摘され、向いていないことが分かったのだとか。
*
在学中は週に四日ほどアルバイトをしている。基本、年中無休の店だが、「新婚さんの夫婦生活を応援したいから」というオーナーの計らいで、土曜は必ず休めるよう、シフトを組んでもらっている。おかげさまで今日も朝から翼くんのために手料理を作ることが出来る。
「めぐちゃん、最近料理がうまくなったよね。バリエーションも増えたし。マジうまー!」
朝ご飯に覚えたてのオムレツを作ったら翼くんが褒めてくれた。
「でしょう! 我ながら上手に出来たと思う!」
「ねぇ、ねぇ、めぐちゃんも食べてごらんよ。ホントにおいしいから。さぁ、口を開けて。俺が食べさせてあ・げ・る♡」
ニコニコ笑顔の翼くんが、スプーンを差し出して待っている。
「んもぅ! 一口だけだよ?」
照れながらも差し出されたオムレツを頬張る。
「んー、おいしぃ♡」
「だろ? 俺が食べさせてあげたから、うまさも倍増さ」

こんなわたしたちの様子をジト目で見ているのは悠くんである。
「……お前ら。結婚したからってイチャイチャしすぎだろ。それとも何か? おれに見せつけてんのか? ……まぁ、仲が良いに越したことはないんだけど」
「妬いてるの? しゃーないなぁ。悠斗にも食べさせてやるよ。ほら、あーん」
「……遠慮する」
悠くんはため息をつくと、自身の食事に集中し始めた。
呆れているように見える悠くんだが、実は仲良くしているわたしたちの姿を見ることに幸せを感じているのは知っている。だからわたしたちも、彼と三人でいるときは結婚前と同様に振る舞うようにしている。さすがに、祖父母の世話をするため週末泊まりでやってくる伯父やパパの前では、恥ずかしくて出来ないけれど。
今週末の当番はパパだ。パパはいつも、わたしたちが朝食を終え、一休みした頃にやってくる。
「今日は大事な話があるんだ。全員、居間に集まってくれるかな」
パパはやってくるなりそう言った。
祖父を車椅子に乗せる手伝いをし、居間まで連れて行く。全員が揃ったところでパパが報告する。
「実家を手放す件だけど、不動産屋に相談したところ、すぐに買い手を見つけたいなら更地にした方がいいだろうという話だった。近隣にもそういった方法で手放した人がいるらしい。まぁ、予想はしていたけど、取り壊すとなればもうあの家とは本当にさよならをすることになる。そこで父さんや母さん、それからみんなの意見を聞かせてほしいんだ」
「おじいちゃんとおばあちゃんの家を壊しちゃうの……?」
取り壊されるイメージが浮かび、切なくなる。
「思い出がなくなっちゃうってことだよね……? わたしは寂しいな……」
「めぐちゃん。そう言ってくれるのはありがたいけど、あの古い家に住みたいという人が現れるとは思えない。上物は壊してしまって、あの土地が気に入った人に新しい家を建ててもらうのがいいと、おばあちゃんは思うわ」
「うむ。じいちゃんも同じ考えだ。……世代交代というやつだ。仕方がない。そうやって命も家も巡っていくんだから」
「…………」
淡々と語る祖父母の言葉に納得がいかなかった。まるで祖父母たちも家と一緒に寿命を迎えてしまうように感じたからだ。
黙り込むわたしを見て、翼くんが肩を抱いてくれた。
「……俺から一つ、提案があるんだけどさ」
彼は一同を見回してから言う。
「家を壊しちゃうのは仕方がないのかもしれないけど、せめて、ばあちゃんが育ててきた庭木だけは救えないかな。このうちでも、アキ兄んちでも、俺の実家でもいい。思い出を、残したいんだ」
「それは名案だな」
悠くんが同意する。
「生きてる庭木を家ごと潰すなんて、考えただけで心苦しいぜ。一本だけでももらい受けよう。移植を嫌わない木なら、新しい環境でも育つだろうさ」
悠くんと翼くんはうなずき合った。そしてわたしと目が合うとウインクをした。
「庭木を受け継いでくれるなんて素敵な話ね。ぜひそうしてくれると嬉しいわ。わたしたちがこの世を去っても、わたしたちと共に生きてきた木が残ればあなたたちも寂しくないでしょう」
祖母は子どものように喜んだ。祖父もうなずいている。それを見たパパも納得した様子だ。
「それじゃあ、家を取り壊す話は進めていくとして、その前に庭木を保護する方向で動こうか。僕んちの庭は狭いけど、一本くらいなら場所を確保して引き取るよ。兄貴んちでも引き取ってもらえるかどうか、早速打診してみよう」
パパはすぐに電話をかけ始めた。それを見てほっとしていると、翼くんが顔を寄せてきた。
「大丈夫さ、めぐちゃん。思い出はちゃんと残る。だから心配しないで」
「ありがとう。翼くんがナイスな提案をしてくれたおかげだよ」
「ううん。俺だって、一つでも思い出が残る方がいいもん。……そうだ。家の中のものも、思い出になりそうな品があったら引き取ろうよ。ああ言うのって、こっちの思い出なんて知りもしない人たちが重機で一気に壊しちゃうイメージがあるじゃん?」
「そうだね。そうしよう」
「おれは梅の木がいいなぁ」
悠くんが早速もらい受けたい木の候補を挙げる。
「何年か前の正月、野上家で新年会をしたときオバアが飲ませてくれた自家製梅酒をうちでも作ってみたいもんだ」
「おっ、それいいな! 俺も梅の木がいい!」
「じゃあわたしは梅ジャムを作ろうかな」
談笑しているわたしたちを見て祖母が微笑む。
「いいわねぇ。木一本からこんなにも会話が弾むんですもの。家をたたんだってちっとも寂しくないじゃない? ねぇ、おじいさん?」
「そうだなぁ。どうせなら一本と言わず、庭ごと持って行ってくれてもいいぞ?」
祖父の言葉を聞いたわたしたちは大笑いをした。
◇◇◇
年が明けた冬のある日。庭師によって祖父母の家の庭木が掘り起こされ、梅の木は無事、鈴宮家へと移された。移植後、長ければ数年は花をつけないという話だったが、鈴宮家での生活を満喫しながら、花が咲く日を楽しみに待つことにしよう。
庭木がすっかりなくなった祖父母の家の庭。そこに立ったとき、急に幼い頃の記憶がよみがえってきて切なくなった。やっぱり女の子の孫はかわいいと言って、庭の片隅に咲くシロツメクサで花かんむりを作ってくれた祖母と、それを嬉しそうに見ていた祖父はもう、自由に動き回れないほど老齢になってしまった。今日だって、祖父母だけ鈴宮家で留守番をしている。
「家を取り壊す前に、親族で記念写真を撮る予定。だから、そんな顔をしないで」
パパがうつむくわたしの隣に立つ。眼鏡の奥の表情をうかがい知ることは出来なかったが、その声は少し震えていたような気がした。
「……ありがとう。おれたちの育った家。長い間、ご苦労さん」
家の壁をいたわるように伯父が言う。
「……よく、この壁に向かって投げたり打ったりしたもんだ。ほら、少し球の跡がついているだろう? あの頃はひたすら野球してたっけなぁ。懐かしいよ……」
伯父は元高校球児。今でも暇さえあればバットを振っているらしい。それを聞いてパパは当時のことを思い出したようだ。
「あの頃は壁が壊れるんじゃないかと、いつもヒヤヒヤしていたよ。いや、一度ひび割れたことがあったような……?」
「それは壁じゃなくて窓ガラスだ。バッティング練習の球が逸れて割ったことがある」
「ああ、そうだった。窓ガラスが割れる音を聞いたのは、あの時が最初で最後だよ。母さんが顔を真っ赤にして怒る姿を見たのもね」
「……まぁ、昔のことだ」
伯父はちょっと居心地が悪そうに肩をすくめた。
「……なにはともあれ、だ。良かったことも悪かったこともおれたちの記憶の中にある。つまり、おれたちが生きている限り残り続ける。何も寂しがることはないんだよ、めぐちゃん」
「そうですね……」
伯父の言葉には重みがあった。きっと、わたしよりも伯父やパパの方がずっとこの家に愛着を持っていて別れを惜しんでいるからに違いない。
「せっかくですから、聞かせて頂けませんか? ここでの思い出を。この場所で」
わたしはパパと伯父に提案した。
「もちろん」
「おれたちが喧嘩した話しかないけど、それでも良ければ」
二人はそう言って早速家の中に入る。わたしたちもそれに続く。
懐かしい匂いに出迎えられ、夏休みに何度も泊まりに来た記憶がよみがえる。当時はまだ白かった壁がすっかり日に焼けて変色しているのを見て、年月の経過を嫌でも感じる。
「そういえば、学校から帰るなり玄関先にランドセルを放り投げては、そのまま遊びに行ってたっけなぁ」
「兄貴はいつも外遊びしてたよね。僕はチェスばかりしてたけど」
家の中を歩き回りながら、二人は懐かしそうに語り始める。
傾斜の急な階段から何度も転げ落ちたこと。パパが幼い頃は、居間で一緒にチェスをしていたこと(伯父とパパとは六歳離れている)。食事の支度をする祖母の後ろ姿を見ながら、お腹を空かせて待っていたこと。ほんの一時だったが、パパと祖父母、そして伯父夫婦の五人で暮らした時期があったこと。そして奇しくもそれがきっかけでパパの人生に転機が訪れたこと。また、家の前で翼くんが生まれた記念写真を撮るとき、それぞれが一回ずつ抱いて撮影したので最後には赤ちゃんの翼くんを大泣きさせたことなど……。
次から次へといろいろな話が出て来る。悠くんはもちろん、翼くんも初めて聞く話が多かったようだ。わたしたちはいつまでもパパたち兄弟の話を聞いていた。
「意外と仲良くやってたのかな、おれたち。結局、喧嘩したことは思い出せなかったな」
「それだけの年月が流れたんだよ。喧嘩した思い出が美化されるほどに」
「そうかもな……」
伯父とパパはしみじみと語り合い、続いて家の中の物品の整理をはじめた。
「捨てなきゃいけないなんて、何だかもったいない気もするけど……」
未使用のタオルや食器類を見て呟くと、悠くんが首を横に振る。
「めぐ、こういう時こそ思い切りが必要だ。おれは両親の所有物を処分したことがあるから分かる。親の所有物は親のもの。おれたちが引き受けない方がいいんだ」
「なるほど。鈴宮君の言うとおりかもしれないな。よし、それじゃあ本当に必要なものだけ残して、後は処分するくらいのつもりで仕分けるか」
伯父はそう言って気合いを入れ、タンスの中身の整理に着手したのだった。
*
直感的に作業していったおかげで、手元に残すものはずいぶんと少なくて済んだ。それを持ち帰って祖父母に見せたところ、二人は懐かしそうに微笑んだ。
「このブローチはおじいさんと結婚した頃にプレゼントされたものよ」
「へぇ! 素敵!」
「もし気に入ったならめぐちゃんにあげる。わたしにはもう必要ないから」
「うん。ありがとう。それならお言葉に甘えて」
「翼にはこれをあげよう。じいちゃんが退職するまで毎日身につけていた腕時計だ。今は電池が切れているから止まっているが、おそらくはまだ使えるだろう」
「えっ、いいの? こういうのは父さんかアキ兄にあげた方が……」
「実は路教にも彰博にも、結婚するときに腕時計をプレゼントしていてな。有り難いことに今も大事に使ってくれているようだから心配はいらないよ。翼には、じいちゃんのお古で申し訳ないが、結婚祝いの品だと思って受け取って欲しい」
翼くんの隣に寄り添って祖父が差し出した腕時計を見てみると、スイスの有名な時計メーカーのロゴが入っていた。皮バンドは傷んでいるものの、文字盤には傷一つ見当たらない。
「本当に? じいちゃん、ありがとう。……おぉ。なんか急に大人の男になった気分だ」
翼くんは早速腕時計を身につけて笑みを浮かべた。
「済まんね。悠斗さんにはこれと言ってあげられるものがなくて」
祖父がちょっと申し訳なさそうに呟いた。が、悠くんは首を横に振る。
「いえ。自分はオジイやオバアと一緒に暮らす時間があれば充分です。それに、立派な梅の木をもらってますから」
それを聞いた祖父母は顔を見合わせて満足そうにうなずいたのだった。
◇◇◇
祖父母の家の片付けをすべて終えたのは三月上旬のこと。以前から、売却前には親族全員で最後の時間を過ごそうと話していたのだが、いよいよその日を決める段になったとき「どうせなら、めぐちゃんの卒業と一緒にしちゃおうよ」と提案してきたのは翼くんだった。
わたしも家も「卒業」。一同が会するのにはぴったりの日だと全員が賛同し、卒業式を終えた日の午後、わたしたちは祖父母の家に集合したのだった。
午前中に涙の卒業式を終えたばかりのわたしは、まだその時の気持ちを引きずっていたこともあって黙り込んでいた。そのせいか室内が重苦しく感じる。食卓にずらりと並ぶ酒や寿司、オードブルの豪華さとは対照的である。
しかしその空気を吹き飛ばしたのは祖父だった。祖父はビールを各人のグラスに注ぐよう指示すると、自らもビールがなみなみと注がれたグラスを手に取った。
「しみったれるのは無しだ。今日はいつもの調子で盛大に飲んで騒ごう! それじゃあ、乾杯! めぐ、卒業おめでとう!」
祖父が乾杯の音頭を取った瞬間「今日で最後」という雰囲気はなくなり、全員が破顔した。これでこそ野上家だ。宴会が進むにつれ、家中に笑い声も響く。
「ほら、高校を卒業したんだし、形だけでも付き合いなさい。家の中なら構うことはない」
ジュースをつぎ足そうとしていたら、陽気になった祖父がビール瓶を差し出してきた。そこへすかさずパパがやってくる。
「父さん、飲酒年齢は二十歳だよ。めぐはまだ十八……」
「彰博は真面目すぎる! じいちゃんがいいと言ったらいいんだ! 本当は彰博だって娘と飲みたいんじゃないのか?」
「えぇっ……?」
戸惑うパパにわたしが追い打ちをかけるように言う。
「パパ。ちょっとだけ飲んでみていい? 一度、おじいちゃんと飲みたいと思ってたんだよね」
「めぐ……!」
「わっはっは! めぐの方がずっと分かってるじゃないか!」
祖父は口を大きく開けて笑い、新しいグラスにビールを注いでくれた。
「改めて、卒業おめでとう。乾杯!」
「かんぱーい!」
泡だらけのグラスに口をつける。苦くてとてもおいしいとは思えなかったが、祖父が満面の笑みを浮かべているからこっちも笑顔でいようと決める。そこへ翼くんと悠くんもやってくる。
「おっ? めぐちゃん、ビールデビュー? んじゃ、俺とも乾杯しようぜ」
「オジイから飲酒解禁令が出たのか? それならおれも混ぜてくれよ」
「えー、いいのかなぁ……? どうなっても知らないよ?」
思わずぼやくと、その場にいた全員が大笑いをしたのだった。
*
日が傾きかけたころ。宴会を終えたわたしたちは上機嫌で外に出た。いよいよ最後の写真を撮る時間がやってきたのだ。
車椅子に乗った祖父と背中を丸めた祖母が最前列。二人を囲むようにわたしたちが並ぶ。
「よーし、それじゃあ撮るぜ!」
デジタルカメラのタイマーをセットした伯父がシャッターボタンを押し、急いでこっちに回り込む。
「イエーイ!」
お酒が入っているから全員赤ら顔。そしてやたらとテンションが高い。いい年のおじさんたちはピースサインを出したり、肩を組んだりしているが、真面目くさった顔で写るよりこっちの方が我が家らしくていいのかもしれない。
撮れた写真を確認すると、全員が最高にいい笑顔で写っている。特に祖父母の笑顔が素敵だ。
「ありがとう。みんな、ありがとう。じいちゃんは本当に幸せ者だよ。これでもう思い残すことはない」
祖父はみんなと握手を交わし、何度も何度も礼を言った。
「何言ってるの、じいちゃん。この家がなくなっても俺たちの暮らしは続いていく。明日もあさっても。……さぁ、帰ろう、鈴宮家に」
翼くんが祖父の肩に手を置いて帰宅を促す。祖父は小さく微笑んだ。
◇◇◇
それから二週間が経ち、とうとう家の解体日を迎えた。
今日は「ワライバ」の仕事は休み。現場に足を向けることも出来るが、わたしは祖父母と共に鈴宮家で過ごすことにした。
窓から柔らかな春の陽が差し込んでいる。庭に目を移せば色鮮やかに咲く春の花々や蝶の姿。それを見ていたら、小学生の頃の記憶がよみがえってきた。
「あぁ……。春休みには良く、おばあちゃんとあの家の縁側でサンドイッチを食べたよね。お庭に咲いていた桜や花壇に植わった花々を見ながら、花見団子を食べたこともあったっけ……」
しかし、それはもう出来ない……。深いため息をつくと祖母が言う。
「あの家は大きな役目を果たし終えたのよ。だから、これでよかったのよ……」
そう言いながらも祖母は目に涙を浮かべていた。わたしはその手を取って微笑んだが、自分の目からも涙がこぼれ落ちてしまった。祖母がわたしの手を握り返す。
「変ね……。思い出は確かに胸の中にしまってあるのに、どうして涙が出てくるのかしら……。めぐちゃんを悲しませてしまったからかしら……?」
「それは、あの場所と思い出が一緒になっているからだよ……」
祖父が呟く。
「泣けてくるのは、それだけ長く住んだ証拠だとじいちゃんは思うよ……。しかし、もう礼は言った。思い出の品も継承した。だから、涙を流すのもきっとこれで最後だ……」
「そうね……。親友と最期のお別れをするときは悲しいけれど、ちゃんとお別れした後は気持ちも落ち着いてくるものね……」
祖父母は互いに見つめ合い、うなずき合った。まるで二人だけにしか分からない想いを確かめ合うかのように。
「……そうだ、二人においしい緑茶を淹れてあげる」
わたしは返事も待たずに台所へ向かった。胸がざわつき、再び涙が込み上げてきたからだ。
祖父母にはもう、人生のゴールが見えているとしか思えなかった。二人は今、人生を振り返ってひとつひとつ向き合い、命を終える準備をしているとしか……。
目から温かいものがポタポタとこぼれ落ちる。お茶を淹れると言ったのに、涙のせいでまったく作業が進まない。その時だ。
――いつになったら願ってくれるの? わたしは早く会いたいよ……――
頭の中に聞こえて来たのは、半年ほど前に見た夢で聞いた悠くんの亡くなった娘、愛菜ちゃんの魂の声だった。直接在りし日の姿を見たわけではないが、悠くんが同じ日に同じ夢を見たと言っていたのだから間違いない。
あのとき彼女はこう言った。私はあなたの赤ちゃん候補の一人。あなたが望めば、誰かの命と引き換えに、あなたのもとに生まれることが出来る、と。
あれ以来、夢を見ることも声を聞くこともなかったが、白昼堂々、再び語りかけてきたと言うことは、声の主は焦っているのか……。それとも誰かの死が迫っていることを暗に伝えようとしているのか……。いずれにしても、今は望みを叶えてやるときではない。
(わたしにはまだ、別れを告げられない人がいる。たとえあなたが誕生を待ち望んでいるとしても……!)
――じゃあ、もう少しだけ待つね……――
毅然とした態度で言い返すと、それきり声は聞こえなくなった。
<翼>
仕事を終えてすぐ、祖父母の家に立ち寄った。が、そこにあったはずの家はもはや原形を留めていなかった。分かっていたことだが、酷く空しくなる。胸の痛みに耐えきれず、急ぎバイクを走らせて家路につく。
「おかえりなさい、翼くん……」
彼女は俺の帰宅を知って玄関先まで出てきたかと思うと、目をうるませながら抱きついてきた。よく見れば、その顔には涙の跡がついている。仕事だったとはいえ、彼女が最も辛かったであろう時間帯に一緒にいてあげられなかったのが悔やまれる。
靴を脱ぎ、すぐに俺たちの部屋にいく。二人きりになった途端、彼女は堰を切ったように泣き出した。そして涙ながらに語る。
「思い出の家がなくなっちゃったからかな……。同じ家に住んでるはずのおじいちゃんとおばあちゃんが急に遠く感じられて怖いの……。いよいよさよならの時が近づいてきたように思えて苦しいの……」
今朝の時点で、めぐちゃんは解体現場を見に行かないと言っていたが、もしかしたら見てきたのかもしれない。俺がまさに胸を痛めて帰ってきたのだから、心優しいめぐちゃんがそう感じたとしても不思議ではない。
いつものように「大丈夫」と慰めてやることが出来なかった。実際、祖父母の死期は着実に迫っているし、俺の力でどうにか出来る問題でもないからだ。
寄り添うことしか出来ない俺の隣で、少しずつ落ち着きを取り戻しはじめた彼女がぽつりと呟く。
「本当は分かってるんだ。おじいちゃんおばあちゃんとはもう、子どもの頃のように接することは出来ないって。今は一日のうちでも、一緒に食事をしたり、つかの間のおしゃべりを楽しんだりする時間しかとれない。なのに、二人にはこの先もずっと生きていて欲しいと願ってるわたしは、わがままだよね……」
「ううん。俺だってめぐちゃんと同じだよ。いつまでも心の支えでいてくれたらと願わない日はない。……だけどね。そう願ったっていいと俺は思うよ。俺の父さんじゃないけど、後で悔やむくらいなら、めぐちゃんに出来ることを出来る範囲でやればいいし、言えばいいと思う」
「翼くん……」
「俺がじいちゃんに鈴宮家で暮らすことを提案したのは、後悔したくなかったからだよ。アキ兄に、俺にもめぐちゃんと結婚する権利があると異議申し立てたのだってそうだ。……苦しくなって、動けない瞬間は誰にだってある。だけど、今のめぐちゃんなら、自分の想いを行動に移せると信じてる」
めぐちゃんは小さくうなずいた。そして少しだけ笑みを浮かべた。
「……わたし、うまく笑えてるかな? おじいちゃんたちの前ではいつでも笑顔でいようと決めてるのに、今日は気分が落ち込んでたせいで何度か泣いちゃった……」
「無理して笑う必要はないと思うけど、そうだな……」
俺は思案し、それから彼女に顔を寄せた。
「……晩ご飯が済んだら二人で夜桜を見に行こう。確か、川沿いで遅くまで桜のライトアップをしてるはず」
「夜桜! いいね! ……でも、二人だけで行くのは後ろめたいかな」
その言葉からは、祖父母や悠斗とも一緒に観たいという思いが感じ取れた。
彼女は本当に優しい心の持ち主だ。しかし、その優しさが向けられる先に嫉妬したくなるときもある。俺は彼女を力強く抱きしめた。
「……今日は俺のわがままを聞いてほしい気分。だから夜桜見物は二人で行こう。めぐちゃんを独占したいんだ。俺の心を癒やせるのはめぐちゃんだけ。じいちゃんたちでも、悠斗でも、咲き誇る桜でもない」
そこまで言って、俺にとっても祖父母の家の解体が心に傷を負わせる出来事だったのだと知る。だけど、永遠に変わらないものなんてこの世には存在しない。たとえあの家が解体されず運よく人手に渡ったとしても、年月と共に家は朽ちる。そのたびに手が加えられれば、最終的には思い出のかけらすら残らないだろう。
俺は続けて言う。
「めぐちゃんの気持ちは分かるよ。ただ、言い方は悪いけどじいちゃんたちの子育て期と孫育て期は終わったんだ。つまり俺たちの、孫としての役目も。……一緒に過ごす時間はもちろん大切だと思う。だけど、元気な姿や夫婦で仲睦まじく過ごす姿を見せるのでも、二人を喜ばせることは出来るんじゃないかな」
「…………」
「じいちゃんばあちゃんと過ごした日々は、思い返せば楽しく、美しいものばかりかもしれない。だけど、過去なんだ。二度と戻ってこない日々なんだ。俺はそこにしがみついて生きていたくない。……俺はめぐちゃんと二人で生きる道に新しい足跡をつけていきたい。前を向いて歩いていきたいんだ」
「……翼くんの気持ちは分かった。少し、考えさせて」
めぐちゃんはそう言って立ち上がり、部屋を出て行った。
*
祖父母を交えた夕食は静かなものだった。少しでも明るい話題を提供しなければと思えば思うほど言葉が出てこない。そのうちに悠斗が仕事から帰ってきた。俺が事情を話すと、彼は何か思うところがあるかのように表情を変え、それから快く家のことを引き受けてくれた。
市内でも有数の桜の名所に行くつもりでバイクの鍵を持つ。ところが家を出た途端、ポツポツと雨が降ってきた。出鼻をくじかれた格好。もたもたしているうち、屋根のない駐車場に置いてあるバイクが濡れていく。
「……降って来ちゃったね。お花見は延期にする?」
めぐちゃんが空を見上げながら言った。
「……近所で桜が見られる場所、知ってる?」
デートを諦めたくなかった俺はめぐちゃんに問うた。彼女は「それなら、やっぱりあそこかな」と言って傘を手に持ち、開く。歩き出した彼女の後を黙ってついていく。
*
十五分ほど歩いただろうか。ついた場所は近所の神社――結婚式を執り行ってくれた宮司のいる春日部神社――だった。
「観光スポットではないけど、ここの桜も立派でしょ?」
振り返っためぐちゃんが空いている方の手を差し出した。その手をとって隣を歩き出す。
雨のせいか、夜桜を楽しもうとする人の姿はない。しかしめぐちゃんの言うとおり、数本ある桜の巨木は満開で、その下に立てば空も足もとも桜の花びらで一杯だった。今日ばかりは、境内に設置されている夜間灯でさえ、夜の桜を美しく見せるための照明に思えてくる。
「こんなに綺麗な桜を二人きりで見られるなんて。雨には感謝しないとな」
「そうだね」
めぐちゃんが握った手に力を込めた。
「……さっきはごめんね。翼くんの気持ちをうまく受け止められなくて。でもそれにはちゃんと理由があるの」
「理由?」
彼女は表情を曇らせながらも話し出す。
「実は今日、またあの声を聞いたの。悠くんの娘さんの声を」
「……夢に出てきたって言うあの声のこと?」
「うん。その声が言ったの。早く会いたいって。……もちろん拒んだよ? だけど、なぜ急に声が聞こえたのか気になってしまって……。もしかしたら……」
「誰かが……じいちゃんが死ぬかもしれない?」
「うん。それが怖くて……」
なるほど。それならさっき、少しでも長く祖父母と過ごしたいと言ったのもうなずける。しかし、納得は出来なかった。
「……やっぱりめぐちゃんは俺よりじいちゃんのことが好きなんだな。顔も出さない幽霊の言葉を真に受けるくらいだもん」
「そ、そんなことは……」
「ほんとに? その夢の話を聞いてると、まるでめぐちゃんの気持ち一つでじいちゃんが死んでしまうみたいに思えてならない。でも、そんなのはあり得ないよ」
「そうですよ」
背後から声がして振り返る。そこにいたのはこの神社の宮司、高野凜さんだった。彼女は微笑みをたたえながらやってくる。
「お久しぶりです。ご夫婦で夜桜見物なんて素敵ですね」
「ご無沙汰してます。……高野さんも桜を見に?」
「いいえ、ご神木さまの声に導かれてここへ」
「……本当に神様と繋がっているんですね?」
「声が聞こえない時期もあったのですが、樹木の生長と共に再び言葉を交わすことが可能になりました」
「それで、神様はなんとおっしゃったんです?」
気になって問うてみると、彼女はゆっくりとした口調で言う。
「凜の言葉を待ってる人がいる、だから助けてあげて、と。一体誰が待っているんだろうと出てきてみたら野上さんたちがいて、何やら深刻そうな話をしていた……。それで声をかけたというわけです」
「木乃香のお母さん、実はわたし……」
めぐちゃんが口を開きかけたが、宮司の高野さんはすべてを知っているかのようにうなずいてから話し始める。
「私も信じていたのよ。ご神木さまの言葉を十七年間も。だけど大切な人に……夫に言われてようやく分かったの。目に見えない神様の言葉よりも、目の前にいる『この人』と過ごす時間や言葉の方がずっと大切だってことが。……神様や精霊、人の魂といった目に見えない存在は、それ故に不思議な力を持っているかのように錯覚しがちだけど、彼らの言葉は彼らの世界でしか効力を発揮しない。つまり神の力をもってしても、人の命を自由に操ることは出来ないのよ」
「えっ。それじゃあ例えば、わたしの子どもになりたいと望む命のかけらが語りかけてきたとしても、その声の主には何の力もないってこと?」
めぐちゃんの問いに彼女はうなずく。
「彼らはうらやましがっているのよ。肉体を持つ私たちのことを。……かくいう私のもとにも、木乃香を授かる前には何人もの赤ちゃんが名乗りを上げては誘惑してきたわ。だけど、一切耳を貸さなかった。自分たちの意志で子どもを持つと決めるまでは。大丈夫よ。あなたには頼りになる旦那様がいるのだから」
めぐちゃんが俺の顔を見上げた。その、ちょっぴり不安げな顔を見て思う。彼女がこんな顔をするのは俺が頼りないからかもしれないって……。いや、違う……。俺が不安な顔をしているから、彼女も同じ顔をしているのだ。
結婚するときに誓ったはずだ。俺がめぐちゃんを幸せにするのだと。祖父にも言われたではないか。翼が笑顔でいることを忘れるな、と。
俺は彼女の傘に入った。そして顔を近づけて精一杯笑った。

「こんなふうに笑えるのは他でもない、めぐちゃんがそばで笑っていてくれるからなんだよ。……正直に言おう。俺はそんなに強くない。幽霊をはねのける力だってない。めぐちゃんから毎日毎日笑顔を分けてもらわなきゃ、生きていくことも出来ないくらい、柔な男だ。だけど……。こんな俺でもいいと言ってくれたなら、一生一緒にいたいと決めてくれたなら信じて欲しいんだ。俺の言葉を。俺の行動を」
「……わたしが笑顔でいられるのは、翼くんや家族が愛情を与えてくれるからだよ。なのにわたしと来たら、目の前の人ではなく、見えもしない魂の言葉や、まだ起きていないことばかりに注目しては不安になってた……。そりゃあ翼くんが『独占したい』って言うわけだよね。よそ見ばかりしているんだもんね」
「そうそう。こんなに近くにいるんだから、今は俺だけを見ててほしいな」
「うん。ちゃんと見る。そして、ちゃんと笑う」
その顔はいつものめぐちゃんだった。俺たちのやりとりを聞いていた高野さんが一歩近づく。
「めぐちゃん。神の言葉は、見えない世界に住む存在の言葉は、自分を映す鏡なのよ。鏡である以上、鏡の中の存在が自発的に行動を起こすことはない。変化があるとすればそれは……」
「自分の行動が変わるとき……」
「そう。すべては『私』から始まるの。きっかけそのものは誰かから与えられたとしても、動くのは『私』自身なのよ。……逆に、何の行動も思考もしなければあちらの世界に引っ張られ、心も体も支配されてしまうことになる。……あなた方は誰の言葉を信じる? パートナー? それとも……?」
『もちろん……』
俺とめぐちゃんは互いに見つめ合い、うなずいた。高野さんもうなずく。
「……困ったことがあったらいつでもここを訪れて下さい。神様はあなた方を見守り、導いて下さいます。そう、神様の言葉は道しるべ。その先の道を歩くのはあくまでも『人』だと言うことを忘れないで」
『はい』
「それでは、私はこれで。……夫婦水入らずでお花見を楽しんでいって下さいね」
高野さんはゆっくりと一礼をし、帰って行った。その後、二人きりの花見を満喫した俺たちも遅くならないうちに帰路についた。
*
「おかえり。オジイとオバアは今し方、寝付いたところだ」
帰宅すると、居間から出てきた悠斗に出迎えられる格好になった。ただいまの代わりに「お疲れさま」と声をかける。悠斗はそれには答えず、こちらの様子を聞いてくる。
「雨、降ってるんだろ? どこまで行ってきたんだ?」
「春日部神社。あそこの桜もなかなか見応えがあったぜ。雨で貸し切り状態だったのも良かった」
「うん。桜の花びらで埋め尽くされた雨空が、まるで満天の星空みたいに見えて綺麗だったよ!」
「……その顔を見る限り、めぐは元気を取り戻したみたいだな」
悠斗はめぐちゃんの顔をのぞき込んで、ほっとしたように頭を撫でた。
「安心しろ、オジイもオバアも今の今までしゃべってたくらい元気いっぱいだ。やれやれ、おれを心配して欲しいくらいだ。さすがに疲れたぜ……」
彼はちょっと大げさに肩を揉む仕草をした。
「ありがとう、悠くん。……ごめんね、心配かけて」
「そりゃあ心配もするよ。おれが解体現場を見て帰ってきても、話題にしないどころか口数も少ないし、すっと居なくなっては、こっそり泣いてたみたいだし。オジイとオバアも気にしてたぜ?」
「何度も泣き顔を見せるわけにはいかないと思って……。でも、余計に心配させちゃったのかな?」
「そういうこと。いいんだよ、我慢しなくっても。泣きたいときは泣いていい。それを許してくれるのが家族だって、おれは思ってるから」
「そう言ってくれるのは嬉しい。でも、もう大丈夫だから。翼くんとお花見してきたらこの通り、いつもの笑顔でしょ?」
めぐちゃんはニコリと笑った。ちょっと無理してるかなとも思ったが、悠斗を納得させるには充分だったようだ。彼は深くうなずいた。
「……オジイとオバアだけじゃない。おれも、めぐや翼とは喜怒哀楽を感じながら暮らしたいって思ってる。それが今一番の幸せだから。……これ以上を望むつもりは毛頭ない。ないんだけど、どうしてかな……。最近になってまた夢を見るんだ。生前の娘と……愛菜と一緒に遊んでる夢を。愛菜はきっと生まれ変わりを切望してるんだろうなって思う。夢という形で、おれにそれを知らせようとしてるんだろうなって。だけど……」
そこまで聞いためぐちゃんは、目を丸くして悠斗に迫った。
「実は今日、彼女がわたしに語りかけてきたの。早く会いたいって……」
「やっぱりそうか……。今日、めぐの様子がおかしかった理由はそこにもあったってわけだな……」
悠斗は一呼吸置くと、俺たちの肩に手を置いた。
「変な気を遣う必要はない。それが亡き娘の願いだとしても、受け容れるかどうかは二人で決めろ。いいな? 愛菜やおれのためじゃなく、二人にとって最善の未来を選べ。それがおれの……オジイとオバアの願いだ」
「わかってる。さっき春日部神社に行ったら木乃香のお母さんに会ってね。奇遇にも同じことを言われたんだ。誰かの言葉で動くんじゃなく、自分で決めて行動しなさいって」
「そうか、あの人に……」
「ああ。心配いらないさ。何せ俺は悠斗と違って紳士なんでね。本能に任せて押し倒すような真似はしないし、家族計画はしっかり立ててるからな」
「ふんっ……」
いつもみたいに軽く受け流して欲しかったのに、疲れてるのか、今日は冗談が通じなかったようだ。怖い顔で迫られる。
「ならば紳士のお前には、獣のおれから寝技をプレゼントしてやろう。いつがいい? ……いや、お前の意見を聞くまでもないな。今すぐ始めようじゃないか」
「そ、そいつは嬉しいけど、出来ればお手柔らかに……」
「獣が手加減するとでも?」
「ひえっ……! めぐちゃん、ヘルプ!」
「えーっ? ……あ、そうだ。これ! 綺麗でしょ?」
俺が助けを求めると、めぐちゃんは手に持っていた桜の小枝を悠斗に差し出した。彼女は、花見に来た鳥たちが落としたそれをお土産に持ち帰ってきていたのだった。
「一つは悠くんに。こっちはおじいちゃんおばあちゃんに。最後の一つは仏壇に……」
「ふっ、仏壇か……」
強面だった悠斗は、呟くと同時に表情を和らげた。
「……めぐは優しすぎ。だから愛菜が早く会いたがるんだよ、きっと」
「……そうなのかな? でも、そうしたいんだからお供えさせてよね?」
「ああ、もちろん供えるさ。こっちのも花瓶に生けよう」
桜の花のついた小枝をしげしげと眺めながら廊下を歩き出そうした悠斗だが、急に足を止めて振り返る。
「……なぁ、めぐ。次の土曜日、今度は家族みんなで花見に行かないか? ニイニイに頼んでさ、車を出してもらおうぜ?」
ニイニイ、と聞いてぞわっとした。それが悠斗の、父の新しい呼び方だと知ってはいるがどうにも馴染めないのだ。だけど、そう呼ぶ悠斗はいつも嬉しそうにしている。俺にはさっぱり分からないけれど、野球部主将を任されたくらいだ、父には何かしら人を惹きつける力があるのだろう。
そんなことを考えているそばで、めぐちゃんと悠斗が週末の花見の話を続けている。
「パパとママも誘っていい?」
「ああ。あいつらも呼ぼう。弁当と酒も持ってさ。……って、ドライバーの横で飲んだら怒られっかなぁ? まぁ、いっか」
「それじゃあ俺はギター持ってくわー。酒飲みが騒ぐのが許されるんなら、歌ったっていいだろ?」
一人だけ仲間はずれにされるのも癪だったから無理やり話に加わった。めぐちゃんが飛び上がって喜ぶ。
「それ、賛成! わたしは酔っぱらいの話を聞くより、翼くんの歌声を聞く方が断然いいな!」
「何だよ、翼。格好つけやがって。お前だって飲むんだろうが」
「飲んで歌って……。最高じゃん?」
弾き語る真似をすると悠斗は苦笑し、めぐちゃんは嬉しそうに微笑んだ。
<悠斗>
雲一つない快晴。「いい花見日和になりそうだ」と青空に向かって伸びをしながら呟く。
今年の春はいつもと違う気がする。去年もその前も春はきちんと巡ってきてたし、桜の花が咲いているのだって見ているはずなのに、なぜだろう。
「あ、いたいた!」
声がして振り返ると、玄関の奥から翼が現れた。
「悠斗もいくつか荷物を持ってくれよ。まさか、手ぶらで場所取りに行くつもり?」
レジャーシートの入った袋を手渡される。おれたちが向かう先は花見会場。まずは二人で座る場所を確保しておき、後から家族が合流するという手筈になっている。
花見の場所取りで思い出すのは大学時代。水泳部の親睦会だ。それなりに楽しかったが、振り返ってみれば花見はただの口実で、酒を飲んだり騒いだりするのが主な目的だった。ひたすらに若くて自意識過剰で……。そんな年頃におれは子どもをもうけ、結婚したんだ。まさかその後、自分の不注意が一因で子どもを死なせ、離婚し、十年も後悔を引きずりながら生きることになるとは思ってもいなかった……。
苦い思い出が引っ張り出される、桜の花を見ながらの宴会。しかし今回、それを提案したのはおれ自身だ。
おれは変わった。いや、変えさせられた。めぐや翼、オジイやオバア、彰博や映璃たちと過ごす中で。今年の春は何かが違うと感じるのはきっとそのせいだ。
*
目的の花見会場に到着したおれたちは、満開の桜の木の下に大きなシートを広げた。まだ八時過ぎだというのに、気の早い人たちがどんどんやってきては場所取りをし、帰っていく。
「せわしねえな。静かなうちに花見を楽しんでいったっていいと思うんだけど……」

おれはレジャーシートの真ん中に寝転んだ。鳥の鳴き声、風の渡る音、花の隙間からこぼれ落ちる日の光……。
「ああ……。春って、こんなに美しい季節だったんだな……」
思わず呟くと、翼も隣に寝転んできた。そして「悠斗も、春が嫌いだった人?」と言った。
「うん、まぁ……。いろいろあったからな……。お前も?」
「まぁね……。だけど、今は違うよ。アキ兄の家でめぐちゃんや悠斗と暮らすようになってからは、春も悪くないなって思えるようになった。春に咲き出す庭の花々を一緒に愛でられる家族がいるってのは素晴らしいことだ。なんていうか……共に生きてるって思えるから」
庭の花がゆっくり生長するように、おれたちの愛もゆっくり育てていきたい――。
翼の言葉を聞いて、過去に自分がめぐに言ったことを思い出した。
結婚という形ではなかったが、その願いはたぶん、叶ってる。おれもめぐも家族として互いを思いやり、愛し合っている。それは年単位でゆっくり互いの気持ちを確かめ、育ててきたからこそ成し得たことだ。
めぐとのことに限らない。男と女。若者と年寄り。血縁のあり、なし……。加えて、考え方も好みも異なる彼らと同じ家に住み、同じ飯を食い、同じ景色を見、年を取っていきたいと思うのは、感動を分かち合いたいからだ。一人では決して味わうことの出来ない感情を、他でもない彼らと共有したいからだ。
奇しくも翼が同じ考えだと知り、だからやっぱり家族でいられるんだと思う。
「季節の移ろいとか、天候の変化に敏感な人は、今起きていることにちゃんと目を向けられる人だ。物事を冷静に見つめられる人だ。少なくとも、野上家の人はみんなそう。だから一緒に生きていきたいって思うんだよ」
「なるほど。だけど、悠斗だって同じだぜ?」
「サンキューな。まぁ、おれの方は最初からそうだったわけじゃなくて、今の穏やかな暮らしの中で、少しずつ感じられるようになったって言うのが正しいけどな」
「穏やかな暮らし、か……」
翼は起き上がると周囲を見回した。
「……せわしなく生きてると、人間も自然の一部だってことを忘れちゃうよな。せめて、こうやって自然の中に身を置いている間くらいは全身の感覚を研ぎ澄ましたいものだ。写真や動画では絶対に残せないからな」
「そうだな」
おれも起き上がって深呼吸をする。春の匂い――そこには土や新緑、花など、この季節に目覚めたあらゆる自然物が含まれる――が鼻腔を刺激し、満開の桜が目を楽しませてくれる。同時に様々な過去の記憶もよみがえるけれど、今日だけは胸の奥に押し戻そう。野上家の人たちと過ごす楽しい時間を存分に味わいたいから。
*
一度帰宅する予定だったが、話の流れからここで家族の到着を待つことに決めた。
よく考えてみれば、物心ついたときからこの地で暮らしてきたというのに、桜の名所でさえこうしてゆっくり散策したことはなかった。ときどき立ち止まりながら歩いてみると、今まで見えていなかった景色が見えてくる。
「こんなところにヒナゲシが咲いてらぁ。おっ、木の陰には地蔵さんもいる」
「本当だ。……よく見たらアキ兄にそっくりじゃん! 面白いから写真撮っとこーっと」
見たままを素直に伝えても、翼はちゃんと受け答えしてくれる。そういう家族がいるってだけでおれは幸せを感じ、今、生きてここにいられることに感謝するのだった。
*
昼頃になって映璃や彰博、翼の母親が飲食物を持ってやってきた。その後、オジイやオバアを連れためぐとニイニイも到着し、ようやく顔ぶれが揃う。
「んじゃ、とりあえずカンパーイ!」
待ちきれないと言った様子で乾杯の音頭を取ったのはニイニイだ。車で来たというのに、彼は誰よりも先に缶ビールに口をつけた。彰博がすかさず指摘する。
「待って、兄貴。それ、ビールじゃないの?」
「そうだけど? あ、もう飲んじゃったわー。ってことで、帰りはお前が運転な。今日はバスで来てるんだろ?」
「……聞いてないんだけど」
いきなり兄弟げんかが始まりそうな空気に包まれる。が、慣れているのか彰博はため息をついただけで、自分が飲むつもりで開けたアルコール飲料をおれによこし、そのままノンアルコールビールに手を伸ばした。二人を見て笑っているのはオジイとオバアだ。
「わっはっは! 喧嘩するほど仲がいいとは路教たちのことを言うんだろうな!」
「本当にねぇ。あなたたちを見てると飽きなくていいわ」
「……やれやれ。この親にしてこの兄あり、って気がしてきたよ」
彰博が再びため息をついたところで、ニイニイがおれたち隣に腰を下ろす。
「まぁ、いいじゃねえか。酒くらい、いつでも飲めるだろ?」
「それ、そっくりそのまま言い返してあげるよ」
「馬鹿言え。今日は、ユウユウと飲むって決めてんだ。先日の実家飲みではあんまりしゃべれなかったからな」
「は? ユウユウって、悠のこと? いつからそんなに親しい間柄になったのさ?」
「これからに決まってるじゃねえか。なぁ、ユウユウ?」
肩を組まれたおれは苦笑いする。こっちがニイニイと呼ぶのに合わせて、彼の方もおれを愛称で呼ぼうとしていたのだが、なかなかしっくりくる呼び名が思いつかず保留になっていたのだった。それにしても、ユウユウ、か……。ちょっと可愛すぎるような気もするけど、まぁ、いっか……。
*
彰博と翼、女性陣がオジイやオバアと穏やかに食事やおしゃべりを楽しんでいる横で、おれは管を巻くニイニイに付き合わされている。普段のおれは聞き役じゃあないけど、今日ばかりはその役に徹するしかなさそうだ。
しかし、聞けば聞くほどニイニイの人柄が分かってくる。彼は彰博や翼から聞いていたような分からず屋でもなければ、威張り散らすような人でもない。彼なりの信念に基づいての行動が端からはそう見えるだけなのだ。
酒の量が増えるにつれ、彼は真剣に自身の考えを訴える。
「おれは長男だから、親の面倒は絶対に見なきゃいけないと思っていたんだ。だけど実際そういう立場になってみると、親相手では衝突することも多くてな。親は親の、おれはおれの考えを譲らないせい。ああ、分かってるさ。それが『鈴宮家で面倒を見てもらう』って結果にも繋がってるわけだし。だけどさ、おれがこういう性格なのは親だって分かってるはずじゃん? 息子より、弟の友人と暮らす方がいいって言われるこっちの身にもなって欲しいもんだぜ」
「いいじゃないですか、衝突できるなんて。わかり合おうって気持ちがなければ、そもそもぶつかり合おうとさえしないと思います。おれなんて、親から逃げちゃいましたからね……。そうこうしてるうちに旅立っちゃったんで、当時は後悔してもしきれませんでしたよ」
「……苦労してきたんだなぁ、ユウユウは」
「まぁ、その時の後悔があるから、野上家の人たちと過ごす時間を大切にしたいと思ってますし、一緒にいたいと言ってもらえるのは本当に有り難いなぁと思ってます」
「そうだよなぁ……。いつか言おうと思ってることがあるなら、言えなくなる前に言った方が……、今、言った方がいいよなぁ」
そう言うとニイニイは缶ビールを片手に立ち上がり、オジイとオバアに歩み寄る。そして椅子に座る二人に目線を合わせた。
「親父、母さん。おれの親でいてくれてありがとう。おれは決していい息子じゃないけど、迷惑もいっぱいかけてきたけど、おれなりに親孝行しようと頑張ってきたつもりだ。あとどのくらい一緒にいられるか分からないけど、顔を合わせられるうちは何度でも喧嘩して、何度でも笑い合おう」
ニイニイがビールを差し出すと、オジイとオバアも手に持っていた飲み物を掲げた。
「路教は自慢の息子だよ。路教だけじゃない。ばあちゃんもそうだし、彰博や孫たち、野上家に関わる全員がじいちゃんの自慢だ。もちろん、悠斗さんもな」
「おいおい、褒めても何もでないぜ?」
「いいじゃないか、人生の最終盤くらい素直になったって。……ありがとう、路教。甲子園に連れて行ってもらったり、孫育てが出来るくらい近所に家を買ってくれたりと、たくさんいい思いをさせてもらった。こんなにも親孝行の息子が、悪い息子であるはずがない。本当にありがとう」
「よせよせ、そういうのは得意じゃねえんだ……」
ニイニイは缶ビールを飲み干すと、手近にあった缶チューハイを開けてあおった。
「だけどまぁ……親父がそう思ってくれたんなら良かった」
「わっはっは! 言いたいことは言わないと。お互い、後悔したくないだろう?」
「そうだな……」
「それじゃあ、気を取り直してもう一度乾杯と行こうか」
「おうっ!」
二人は笑顔で乾杯した。その乾杯がおれたちにも回ってきて一同が再び一つになる。そして笑顔の輪が桜並木の下で広がっていく……。

(この時間が永遠に続けばいいのにな……)
しかしそう思うのは、この瞬間が永遠には続かないと分かっているからだ。満開の桜の花が数日後には散ってしまうように、時は刻々と過ぎ去り、一秒たりとも止めることが出来ない……。そう思ったら、おれも黙っていられなくなった。
「オジイ、オバア。おれからもお礼を言わせて下さい。……野上家の一員として受け容れて下さってありがとうございます。自分の親に出来なかった親孝行をさせて下さってありがとうございます。……おれも今、最高に幸せです。生きてて、良かったです」
二人は何度も何度もうなずいた。
「じいちゃんも長生きできて良かったよ」
「わたしもよ。この年になってもう一人息子が増えただけでも嬉しいのに、毎日笑顔を分けてもらえるんだもの。こんなに素晴らしいことはないわ。ありがとうね」
年のせいか、酒のせいか、気づけば二人の言葉に涙していた。一瞬、隠そうとしたが、気づいためぐにそっとハンカチを差し出される。その顔を見て、おれが母親を亡くして肩を落としていたときに慰めてくれた、八歳のめぐを思い出した。奇しくも彼女はその時と同じようにおれをぎゅっと包み込んでくれた。
「悠くんは言ったよね? わたしたちと喜怒哀楽を感じたいって……。なら、うれし泣きしたっていいじゃん? 泣くほど笑ったっていいじゃん? そういう顔を見せられるのが家族、でしょ?」
「ああ、そうだ。その通りだ……」
呟いたおれの肩に翼が手を置く。
「もっと泣けばいいさ。声を上げたっていいぜ? 俺が歌って泣き声をかき消してやるから」
彼は肩からギターを提げると本当に弾き語り始めた。
#
胸いっぱい、深呼吸
新しい季節のにおい
柔らかな日差し
空は青く
からだの中に感じる春
色とりどりの花
草木の新緑が
目にまぶしくて
今日も 生きてる
ありがたさを知る
今年も家族と
春を過ごせますように
願いながら 今はただ
あなたといられる幸せを噛みしめる
#
彼の、透き通るような歌声に涙腺を刺激され、静かに涙した。そして歌詞にあるとおり、今家族といられる幸せを強く強く噛みしめたのだった。
◇◇◇
新緑が勢いよく伸びるのと真反対に、元気そうに見えていたオジイはゆっくりと衰え、花見から二ヶ月が経ったある日に旅立った。穏やかな最期だった。
梅雨の始まりを告げるかのように、朝から雨が降っていた。彰博やニイニイが慌ただしく死後の手続きをする様子を端で見守る。悲しみに暮れる暇もないまま、二人は淡々と手を動かしていた。
*
喪主であるオバアの負担を考えて通夜はせず、葬儀も家族だけで済ませることになった。
斎場につくと、長く暮らした野上家の庭を模した花に囲まれたオジイが額縁の中で嬉しそうに笑っていた。
そんな遺影を前に、彰博は立ち尽くしている。唇を噛み、涙を堪えているようだった。それを見たニイニイが背中を叩く。
「泣いてんのかよ? そんなことでどうする? 親父は涙じゃなくて笑顔で送り出してやらないと」
「父さん……! そんな言い方って……!」
そばで聞いていた翼が突っかかる。
「待て、ニイニイにはおれから話す」
「悠斗……」
「任せろ」
渋々引き下がる翼と入れ替わるように、ニイニイの前に立つ。そして不満げな彼に向かって言い放つ。
「彰博を、泣かせてやって下さい」
「ユウユウまで……」
「ニイニイの気持ちは分かります。でも、涙って身体の反応だから止めようがないじゃないですか。母親を亡くしたときのおれも、笑って送り出してくれと言われたのに涙が止まらなくて戸惑いました。そんなとき、彰博が言ったんです。泣き尽くせばいいって。涸れるまで泣いたらまた笑えるようになるって。その言葉がおれを救ってくれた……。だから今度はおれが彼を救いたいんです」
「……わかったよ。おれからはもう、何も言うまい」
そう言った彼の目が涙でにじんでいるのを、おれは見逃さなかった。
涙を見せないこと。悲しみに耐えること。それが男らしさ、強さであると教えられてきたおれたちは、いつしか声を上げて泣く方法を、悲しみの表現の仕方を忘れてしまった。しかしおれは思い出した。心の動くままに、全身を使って感情を表に出すのが自然な姿であり、それが人間らしく生きることなんだって。だから家族にも、感情を押し殺さずありのままの感情を出して欲しいと思う。
おれの隣で目を伏せる彰博の肩にそっと手を置く。
「泣けよ、彰博。今日だけは思い切り泣け。おれの前でも、だ。今日泣かないで、いつ泣くんだよ? 大丈夫、お前が泣いてたってオジイはきっと気にしないさ。むしろ、笑い飛ばしてくれるだろうよ」
「くぅっ……!」
それでも涙を堪えようとする彰博に、妻である映璃が寄り添う。
「アキ、悠の言うとおりだよ。ほら、お義父さんがいい笑顔でこっちを見てる。私には、泣くほどじいちゃんが好きだったのかって言いながら笑ってるように見えるよ」
彰博は写真を見つめた後で部屋の隅の椅子に座り、うつむいた。そして声を上げて泣いた。
*
葬儀はしめやかに行われた。おれたちは最後の別れを惜しむように何度も何度も礼を言った。しかし本当にその時がやってくると、一同はようやく覚悟を決めて口をつぐんだ。
数時間後、煙と共に旅立つオジイを見送るため、外に出る。その時、雨の止み間に日が差して大きな虹が架かった。オジイはきっとあの虹を渡って天国に向かっているのだろうとみんなで話しながら、七色の橋が消えるまで空を見上げていた。
*
「悠斗君、お疲れさま。今日はありがとうね」
すべてが終わり、タクシーを待っているとオバアに声をかけられた。その瞬間、肩の力が抜け、急に涙が溢れ出てきた。葬儀の間は一粒も落ちてこなかったというのに。オバアがおれの手を握った。
「おじいさんはいつでもそばにいてくれる。わたしには分かる。だから、ちっとも寂しくなんかないのよ?」
「……そうですね」
お骨は、納骨日まで鈴宮家で預かることになっている。オバアの近くに置いておくのが一番だというニイニイの発言を受け、皆で決めた。
骨壺を、孫である翼が自宅まで運んでくれる。
「じいちゃんがこの中に入っちゃったなんて、まだ信じられないな……」
タクシーで帰宅する最中に翼が呟く。
「家に帰ったらいたりして。……んなわけないか」
おれとめぐ、オバアは笑った。
程なくしてタクシーが家に到着した。オバアに肩を貸しながらゆっくりと室内に入る。オジイの骨壺が居間に安置されたのを見届け、その前にオバアを座らせる。オバアは「帰ってきましたよ」と言いながら手を合わせた。
「お疲れさん。悠斗はもう休んだ方がいいよ。後のことは俺とめぐちゃんでやっとくから」
早々に喪服から私服に着替えた翼に声をかけられた。少々のことでへたばるおれじゃないが、今日ばかりは疲れを感じている。
「それじゃ、お言葉に甘えようかな」
彼の優しさを素直に受け取り、まずは自室で楽な格好に着替える。一人きりになり、布団に寝転ぶと一気に身体が重くなった。
「あーっ、疲れたー! オジイ、肩でも揉んでくれよ……」
冗談めかして呟く。
――よし、分かった。言っとくが、じいちゃんの肩もみは痛いぞ?――
どこからともなくオジイの声が聞こえた気がしてハッとする。亡くなってすぐだからまだ生きているように錯覚しただけだろうか。それにしてははっきり聞こえた……。もしや、と思って誰もいない空間に問いかける。
「……オジイ? この部屋にいるんですか?」
すると案の定、身体の透けたオジイの姿が見えた。思わず起き上がって姿勢を正す。オジイは笑った。
――わっはっは。楽にしてていいよ。いや実は、ばあちゃんのことが心配でな。もうしばらくはこの家にいさせてもらうつもりで戻ってきたんだよ。構わないかな?――
「そ、それは構いませんが……。おれの前に現れたってことは、やっぱり見えるのはおれだけなんですか?」
――そのようだな。ま、じいちゃんがいる間は通訳を頼むよ――
「通訳って……」
「悠斗……? 誰としゃべってんの? 入っていい?」
ドアの向こうから翼の声がした。独り言を言うなんて、疲れすぎておかしくなったと思われたのかもしれない。おれは自分からドアを開けた。
「誰ってそりゃあ……オジイだよ、オジイ。魂になって帰ってきてるんだ」
「……は? マジで?」
「ほら、そこに……」
振り返って指し示したが、オジイの姿は見えなくなっていた。
<めぐ>
祖父は亡くなったはずなのに、まだ家の中のどこかにいるような気がする。そのせいか不思議とさみしさは感じないし、身近な人の命と引き換えにやってくるという赤ちゃんのことも今は深刻に受け止めていない。先日、木乃香のお母さんに言われ、わたしのことはわたしが決めると気持ちを新たにしたのも大きいだろう。
寝る支度をしていると、翼くんが寝室にやってきた。
「……悠斗、大丈夫かなぁ?」
彼は落ち着かない様子で呟いた。
「大丈夫って……。何かあったの?」
「……じいちゃんの姿が見えるって言うんだよ。ばあちゃんのことが心配で戻ってきたって言ってるらしくて……」
「ホントに?! ……どうりで気配を感じると思った!」
「えーっ? めぐちゃんまで……。だって、じいちゃんは死んじゃったんだよ? もうこの世にはいないんだよ?」
「そりゃあ分かってるけど、悠くんは亡くなった娘さんの姿を何度か見てるっていうし、霊感が強いならおじいちゃんの姿が見えたって不思議じゃないと思うけど」
翼くんは納得できない様子でため息をついた。
「……まぁ、今日はみんな疲れてるし、明日また聞いてみるか」
おやすみ……。翼くんは大あくびをしてわたしの隣に横たわった。
翼くんは、こういうときこそ現実を見なきゃダメだって、過去に引っ張られちゃダメだって言いたいのだろう。わたしもその通りだと思う。だけど、悠くんにとって霊が見えることが現実だとしたら、見えない側の人間がそれを否定することは出来ないはず……。現にわたしも愛菜ちゃんらしき声をはっきりと聞いている。あれは決して空耳なんかじゃなかった……。
◇◇◇
翌朝、目覚めてすぐ悠くんの部屋に向かう。夕べ翼くんから聞いた話を確かめるためだ。
彼は自室ではなく居間にいた。仏壇の前で静かに手を合わせている。その横に立ち、同じように手を合わせる。
「……今もおじいちゃんが見えるの?」
「翼から聞いたのか」
悠くんはわたしの言わんとすることをすぐに理解したようだ。
「今は見えない。……っていうか、あっちからの接触がなければ見えないんだ。まぁ、姿を見せてくれって頼んでその通りになったところで、見えない人には見えないんだろうけど。このうちで見えるのはおれだけみたいだし」
「そうなんだ……」
「めぐは信じる? オジイがまだこの家にいるってこと」
「もちろん。悠くんが嘘をつくはずないもん」
「そっか……。それを聞いてオジイも喜んでると思うよ。……ところで」
悠くんは声を低くして言う。
「その後、愛菜からコンタクトはあったか?」
「ううん。今のところはないかな」
「なら、いいんだ。身近な人……、つまりオジイは亡くなったけど、だからって愛菜の言葉を鵜呑みにする必要はないからな。それだけは言っときたくて」
「大丈夫。たとえわたしの心が揺れても、翼くんがしっかりしてるから」
「確かに……。言動はあれだけど、悔しいことに行動は紳士だからな。心配には及ばないか」
「言動だって紳士だけど?」
そこへ翼くんが現れた。
「おはよう、悠斗。疲れはとれた?」
「ああ、おれは大丈夫。それを聞くならオバアにしてくれ。夕べは遅くまで眠れなかったみたいだから」
「わたしならちゃんと寝たわよ」
振り返ると、寝ていたはずの祖母が起きていた。その表情は穏やかに見える。三人して心配げな顔を向けたにもかかわらず、祖母は微笑んだ。
「今の話は全部聞かせてもらったわ。やっぱり、おじいさんはそばで見守ってくれてるのね。悠斗君、また何かおじいさんからメッセージを受け取ったら教えてちょうだい」
「はい。……って言っても、おれからは語りかけることが出来ないので、いつお伝え出来るか分かりませんが」
「それでもいいわ。待ってるから。……それにしても、生きてる人間はお腹が空くわねえ。そろそろ朝ご飯にしようかしら?」
祖母の言葉を聞いて時計を見る。いつもならとうに食卓に着いている時間だ。今日は平日。翼くんもわたしも朝から仕事が待っている。
「やっべぇ、遅刻気味だ! 悠斗、食事の支度、頼める?」
「オーケー。……トーストと目玉焼きでいいか? スムージーを作るのは時間がかかるから、今日は無しでいい?」
「なんでもいいからとにかく頼む!」
「やれやれ。生きてくってのは大変だなぁ……」
悠くんのぼやきを端で聞きつつ、わたしも急いで身支度を調える。
*
「おはようございまーす!」
ワライバに出勤すると、双子のオーナーは同じ顔を同時に向けた。二人とも驚いた表情をしている。
「めぐっち、もういいの? まだ休んでていいのに」
「大丈夫です」
理人さんの言葉に即答する。
「家にいても余計なことばっかり考えちゃうので」
「そう? でも、無茶しないように! おれ自身、ばあちゃんが亡くなったときは立ち直るのにかなり時間がかかったからさ」
「はい、無茶はしません」
素直な返事を聞いて安心したのか、理人さんはいつもの表情に戻った。
開店の準備を一通り終え、「OPEN」の札に掛け替える。と、ぴったりのタイミングで車が駐車場に滑り込んできた。運転席から降りてきたのは、すっかり常連になったかおりさんだ。
「いらっしゃいませ。今日は早いんですね!」
「おはよう、めぐさん。今日は待ち合わせをしていてね」
「待ち合わせ?」
小首をかしげていると、すぐ後ろから見知った顔がやってきた。
「クミさん!」
「お久しぶりー」
彼女は赤ちゃんを抱っこしていた。人なつっこそうな赤ちゃんは、わたしたちを見るなりにっこりと笑った。
クミさんとの出会いはこのお店。出産を前に不安を抱えていた彼女に助言したのがきっかけで仲良くなった。近所に住んでいるらしく、出産の報告がてら一度お店に遊びに来たことはあるが、わたしが会うのはその時ぶりだ。
「赤ちゃん、大きくなったねぇ!」
「もうすぐ十ヶ月よ。最近はハイハイでどこにでも行っちゃうから目が離せなくて。でも、かわいいよ。……はい、かおりさん」
クミさんは赤ちゃんをかおりさんに抱かせた。かおりさんは満面の笑みを浮かべながら引き受ける。
「よしよし……。まぁ、わたしの髪の毛を口に入れちゃダメよぉ」
その様子はまるで母親そのものだった。二人のやりとりを見て察する。
「……もしかして、かおりさんに赤ちゃんを抱かせるためにここへ?」
「うん。……実は、初めて出会ったときに言われたことが――どんなに願っても愛する人との間に子どもを持てない人がいる、母親になる自信がないならわたしが赤ちゃんを育てるとお説教されたのが――ずーっと引っかかっててね。いろいろ考えた結果、ここで出会ったのも何かの縁かもしれないと思って、かおりさんに子育てを手伝ってもらえないかと相談したの。もちろん、一緒に暮らすことは出来ないからここに来たとき限定にはなってしまうけど、そういう形でもいいなら喜んでと引き受けてもらったってわけ」
「そうだったんだぁ」
訳を聞きながら、赤ちゃんがこちらに伸ばした手を握る。キャッキャと笑う顔を見たら自然と笑みがこぼれた。
「あれーっ、めぐさんも欲しくなったって顔してるよ? 子ども作っちゃいなよ」
「えーっ!」
クミさんに指摘され、慌てて赤ちゃんの手を離す。
「わ、わたしはまだまだここで修業するつもりだから……」
「そうなのー? 一緒に子育てしようよ」
「…………」
返事に困っていると、かおりさんが苦笑した。
「クミさん。人はその時々で役割が違うのよ。その役が巡ってくるタイミングも違うのよ。だから、めぐさんの子育ては、めぐさんにとって最適な時期にやってくる。望もうが望むまいがね」
「じゃあ、あたしが子どもを授かったのも今がその時だからってこと?」
「最近、確信したのよ。たとえ望んだ形ではなかったとしても、いつか必ず願いは実現するって。……わたしは純さんを愛したことで自分の子どもを持つことが難しかったけど、友人の子育てに関わることが出来たし、こうやってまた赤ちゃんを抱く機会を得ることが出来た。つまり彼との関係の延長線上には、ちゃんと子どもと接するチャンスがあって、ある意味では望みは叶ったとも言える。そのことに気づいたのよ。今は彼を愛したことを誇りに思っているし、ここまで一緒に歩んできて良かったと本気で思ってる。クミさんを羨む気持ちも今はないわ。むしろ、こういう機会を作ってくれたことに感謝しているくらい」
「あたしもかおりさんと出会えたのはラッキーだったなって思ってる。自分の親に子育てのことを聞いても親の経験からでしかアドバイスしてもらえないけど、かおりさんの場合は客観的な言葉をかけてくれるでしょ? だからすんなり受け容れられるんだよね」
「そう言ってもらえると嬉しいわ」
「めぐっち! カウンターのお客様にコーヒーをお出しして」
その時、オーナーの指示が耳に入った。
「は、はい! ……それじゃ、お二人ともごゆっくり」
一礼してきびすを返し、接客の仕事に戻る。ところが、カウンターにお客さんの姿はなかった。
(あれ? 今「カウンターのお客様」って言ってたような……? 聞き違いかな?)
しかし店内をくまなく見回しても、かおりさんとクミさんしかいない。
「あのー、理人さん。カウンターのお客様はどちらに……?」
「あー、めぐっちには見えないよね。だけど、ここに座ってるんだ。だから、出しておいて」
見えないよね、と言われてハッとする。
「そのお客様ってもしかして……?」
「うん、あっちの世界の人。今日は、かおりさんのお兄さんがくっ付いてきたみたい」
*
「ホットコーヒーでございます……」
誰もいないように見えるカウンター席にコーヒーを提供する。その後、他の仕事をしながら時折カップの中をのぞき込むが、コーヒーが減る気配はない。ないんだけど、そこにいると言われたらやっぱりいるような気がしてついつい気になってしまう。
モヤモヤした気持ちを引きずったまま仕事をするわけにもいかないと思い、正直に尋ねてみる。
「……さっきの口ぶりからすると、この店には頻繁にあっちの世界のお客様が来るってことですか?」
理人さんは窓際のカウンター席をちらりと見てから答える。
「たまにね。どうやらあっちの世界でもこの店はそれなりに知れてるらしくて。いろんな事情の幽霊たちが居場所や安らぎを求めてやってくるんだ。めぐっちが働き始めてからも何人か来てたんだけど、今日はかおりさんの連れ添いだから接客をお願いしたってわけ。……うわっ、その顔。信じてないっしょ」
「いえいえ! 実は亡くなったばかりの祖父の姿が見える家族がいまして、話を聞いているとやっぱりそういうことはあるんだろうなって思ってます!」
「ほんとにー?」
「オーナー、今日は兄が来てるの?」
わたしたちが掛け合いをしていると、かおりさんが話に加わった。
「うん、コーヒーが置いてあるところに座ってるよ。かおりさんが赤ちゃんを抱く姿を間近で見たかったのかもね」
「なら、こっちに来ればいいのに。相変わらず、人との距離感が分からないんだから」
「相変わらずってことは……。お兄さんがそばにいる期間って長いんですか?」
わたしが問うと、かおりさんはお兄さんが座っているであろう席に目を向けながら言う。
「そうね……。かれこれ三十年になるかしら。自分の身体では体験できなかった人生を霊魂の状態で味わおうとしているみたい。わたし自身、兄の姿を見ることは出来ないけれど、どういう因果か、身近に見える人や気配を感じる人がいてね。その都度存在を教えてもらいながら一緒に生きてきたというわけ」
「……そのー、どういう感じなんですか? お兄さんの魂がいつでもそばにいるっていうのは」
「そうね……。うまく表現できないけれど、同じ空間にいると言われたときには温かみを感じるというか、『あ、いるな』って分かるのよね。そういうときは、見守られてるんだと思えて優しい気持ちになるわ」
「そうなんですか……」
「今日ここに現れたってことは、かおりさんのお兄さんも子どもが欲しかったのかな?」
クミさんの言葉に、かおりさんは「まさか!」と応じた。
「兄はわたしの笑っている顔が見たいだけなのよ。それがあの世で生きる兄の、唯一の幸福なのだと思ってる。わたしも兄も、子どもの頃は勉強漬けであまり笑うことをしてこなかったから」
「……かおりさんのお兄さんは、生まれ変わりを望んだりはしないんでしょうか?」
再びわたしから問う。かおりさんは「どうかしら」と首をかしげた。
「本人に聞いたわけじゃないから分からないけど、透はわたしの兄で居続けたいんだと思う。生まれ変わったら関係も変わるでしょうからね。……わたし以外に信頼できる人がいないと思い込んでる、頭の固い人間なのよ」
そう言いながらも彼女の表情は穏やかだった。
(亡くなった人のことをこんなふうに語れるかおりさんって素敵だな……。)
そういえば、悠くんが亡き娘さんのことを話すときもこんな顔をしていた気がする。今朝の祖母も柔和な表情だった。
最愛の人を思い出すとき、人は優しくなれるのかもしれない。もしかしたら、生きてそばにいたときよりも……。かおりさんは続ける。
「兄はもう肉体を持っていない。どんなに感情を表現したくても表すことが出来ない。だからわたしは肉体を持ってる者として、生きてる者として、感情豊かでありたいと思うの。もう一緒に笑ったり怒ったりすることは出来ないけれど、わたしのそばにいることで疑似体験できるというなら、わたしは兄の代わりに笑ったり怒ったり泣いたりする。そうやって共に生きていくって決めてるの」
ザーッ……。
突然、店内で流しているテレビの画像が乱れた。オーナーたちが慌て出す。
「おい、どうしたどうした?」
二人はリモコンをいじったり配線を確認したりしているが、テレビはうんともすんとも言わない。わたしも手伝うつもりで動き出そうとしたとき、かおりさんがぽつりと呟く。
「まぁ……。透ったら、感激してるみたい。周囲を驚かせることでしか感情を伝えられないなんて、まるで子どもみたいよね」
呼応するようにテレビ画面が明滅する。直後、乱れていたテレビは何ごともなかったかのようにニュース番組を映し出したのだった。
*
一日の仕事を終えて帰宅すると、祖母が縁側に腰掛けて庭を眺めていた。夕方から仕事の悠くんとは入れ違いになったようで姿は見えない。
「ただいま」
「おかえり、めぐちゃん。今ね、お庭の紫陽花を見ていたところなの」
「うん」
わたしは祖母の隣に腰掛けた。
「このうちのお庭は素敵ね。悠斗君のご両親がしっかり手入れをされていたんだって分かる。……今でもお庭に目をかけているに違いないわね。ここに座っていると風もないのに葉が揺れたり、蝶がわたしの周りをひらひら舞ったりするのよ」
その話を聞いて、今朝ほどお店のテレビが乱れた出来事を思い出した。
「……亡くなった人はそうやって『自分がここにいるよ』って知らせてくれるものなの?」
「おばあちゃんも確かなことは分からないけど、そうだと信じた方が残された人間としては生きやすいじゃない?」
「……自分の存在を知らせようとするのは、この世に未練があるからなのかな?」
「肉体が滅びた人は住む場所を変えただけで、実はあっちの世界で生きてるんだとおばあちゃんは思うのよね。彼らは肉体を持たない分、こっち世界に気軽にやってきては自然現象という形で『元気にしてるか?』とか『いつでも見守っているからね』って伝えてくるような気がしていて。そういうのを信じられなかったり、怖がったりする人もいるけど、わたしたちが見ている世界が唯一じゃないと思うのよ」
「分かる気がする」
「なら、わたしが死んでもそう思ってちょうだい。例えばそうね……。今年は咲かなかったけど、毎年必ずここの梅の花を満開にすると約束するわ。めぐちゃんがこの約束を覚えている限り、少なくともめぐちゃんにだけは思い出してもらえるはずだから」
「おばあちゃん……」
「その日が来てすぐは泣いてもいい。だけど、ずっとは嫌。だって涙は梅の木の肥やしにはならないもの。おばあちゃんはあっちの世界でおじいさんと再会して楽しくやってるはずと思って、いつもと変わらずお庭の手入れをしてちょうだいな。それが残された者の務めなんだから」
「はい……」
「というわけで……。早速、お仕事。咲き終わった花がら摘みをしておいで。梅雨の時分に放っておくと、花が腐ってその株をダメにしてしまうから」
「えーっ……」
反射的に声が出てしまったが、この庭が維持されてきた背景にはそうした地味な作業があったのだろうと思い直し、重い腰を上げる。
「そうそう。立派なお庭は一日にしてならず、よ」
「はーい……」
咲き終わった花を丁寧に摘む。そうするうちに意識がそこだけに集中していき、やがて庭を整えることと自分を整えることは似ている、との思いに至る。
わたしたちは日々時間に追われ、身体のケアを疎かにしがちだ。しかし手入れを怠れば花を枯らせてしまうように、身体の不調も放置すれば健康を損なう。「目に見えないからこそ、心と真剣に向き合うことが必要だ」とは、心理カウンセラーのパパの台詞だ。
見えているものの更に奥で何が起きているかを知ろうとする。そういう姿勢ってけっこう大事じゃないか、と思う。例えばさっき祖母が言ったような世界もあると受け容れてみる。そうすることで感覚が研ぎ澄まされ、見える景色も変わるのではないか。
夕焼け色に染まる庭で胸いっぱいに息を吸い込む。そして自分に問うてみる。今一番大切にしたいことは何か、と。
答えは言葉ではなく感覚としてやってきた。それを丁寧に言語化してみる。
(今はまだ自分の時間を大切にしたい。こうやってお庭を眺めながらおばあちゃんと話したり、翼くんや悠くんと出かけたりする時間を作りたい……。それが、わたしの体が求めていること……。)
家族とはこれからも季節の変化を共に感じながら過ごしていこう。そして自然な形で母親になる日を迎えよう。すべての出来事は最適なタイミングで起きる……。人生の先輩たちがそういうのだ、わたしもそれを信じて生きていけばいい。
二 生と死の狭間で
<翼>
同居を始めて一年半もの間、鈴宮としか書かれていなかった玄関にとうとう野上の表札がついた。祖母が若い人のセンスに合わせるというのでローマ字表記だ。はじめは俺たちの分だけ追加する予定だったが、同じデザインで統一したいという悠斗の希望もあって鈴宮姓の表札も変えた。
「SUZUMIYA / NOGAMI」の表札は、すでに修繕済みの塀や門とも調和がとれている。外壁や内壁、水回りも現在進行形で改修中。それもこれも祖父母宅の跡地が無事に売れたおかげである。
建て直すわけじゃないから家の骨組みはそのままなのだが、工事が進めば進むほど悠斗の思い出の家は姿を消していく。祖父母の家の解体時には俺でさえ胸を締め付けられる経験をしたからちょっと心配だったけど、悠斗はむしろそれを望んでいるようだった。
「おれは今、ワクワクしてるよ。家が更新されるたびにおれ自身も若返ってく気がするし、今更だけど新生活が始まるみたいな感じがして。まぁ、日常は何も変わんないんだけどな」
その凜とした表情や堂々とした態度を見るにつけ、彼はもうまったく過去を振り返らなくなったのだ、と知る。そして実際、五十歳近い年齢であることを感じさせない容姿を見て、俺もこんなふうに年を重ねていきたいと思うのだった。
◇◇◇
それぞれがそれぞれの時間を過ごし、時間があえば食事を共にし、談笑し、時にめぐちゃんと愛し合い……。祖父亡き後の「我が家」での暮らしは、これまでよりもずっと穏やかに過ぎていく。おそらくは家族全員が、何気ない日常こそ有り難く、大切にしなければならないのだと改めて知ったからに違いない。
しかし穏やかなのは家の中だけ。一歩外に出てみれば園での仕事が待っている。入園シーズンを迎えれば年少児の対応に追われるし、それが落ち着いたかと思えば、家庭訪問などの行事が目白押し。おまけに今年は、結婚している同僚の先生の妊娠ラッシュ。そのせいでなぜか俺まで妙なプレッシャーをかけられる毎日だ。
「つばさっぴ先生のところはお子さん、まだでしたよね」
今日も、職員室で後輩の女性教諭と話していたらそんな質問が飛んできた。
「こういう仕事をしているし、私なら結婚したらすぐに子どもを作るけどなぁ。……って、これはもうすぐ三十で彼氏なしの人間のひがみですけど。奥さん、子どもが欲しいって言いません?」
「奥さんが、今は仕事が楽しいって言ってるからそれでいいかなって」
「あ、それ分かります。私がそうですもん。でも、そう言ってるうちに出産適齢期を逃して後悔する女子は多いらしいですよ。私も、このまま仕事を続けていたら子どもが産めなくなるんじゃないかって、今から焦ってます」
「ご心配なく。俺の奥さん、今年で二十歳だから」
「うっそ! 若いって聞いてはいたけど、そんなに若かったんですか! でも、そんなに年の差があったら、奥さんが子どもを欲しいと思ったときには、つばさっぴ先生のほうがいい年に……」
「余計なお世話!」
「あっ、すみませんっ……!」
そこへ俺たちの話を聞いていたらしい映璃先生がやってきて会話に加わる。
「カナ先生? 私の娘婿にちょっかい出すの、やめてもらえる?」
「……え? 娘婿?」
「つばさっぴは私の娘と結婚したのよ。知らなかった? それとね、世の中には子どもが産めない女性もいるってことをお忘れなく。……さぁ、おしゃべりはこの辺にして仕事に戻りましょう?」
「あ、はい……」
カナ先生はすごすごと自分の席に戻っていった。
「……エリ姉、サンキュー。ナイスフォロー」
「あの手の話にはトラウマがあるのよ。若い頃は私もずいぶん悩んでいたから……」
「そうだよね……」
「カナ先生の言っていたことを気にする必要はないわ。ご縁があれば子どもを迎えられる。その日がいつになるかは誰にも分からないけれど」
「……そういえば、エリ姉が養子を迎えようと決めたきっかけってあったの? 例えば誰かに言われてとか、年齢的なこととか」
エリ姉は思い出すように天を仰ぐ。
「……二人の気持ちが一致したのが三十歳の時だった、ってだけの話よ。でも、あの時はとりつかれたように足が動いたのを覚えてる。その結果、めぐと出会えた。私たちにとってめぐとの出会いは運命そのもの。もしあの時行動していなかったら、そしてちょっとでも時期がずれていたら翼くんもめぐと出会うことはなかったし、きっと別の人生を歩んでいたでしょうね」
「つまり、直感的に動いたのがよかったってこと?」
「そういうことになるかな……。まぁ、周りの言葉は気にせずに、自分たちの思うとおりに行動すればいいと思うわ。ただし、二人でしっかり話し合うこと! 私も、アキとは何度も話し合いを重ねた上で決断したから」
「そうするよ。ありがとう、エリ姉」
会話が一段落したところで目の前の電話が鳴った。一気に現実に引き戻される。電話を取った後はエリ姉との交わした話も忘れ、仕事に忙殺されたのだった。
◇◇◇
結婚生活が三年目を迎える前に、めぐちゃんが二十歳になった。以前から「三人で外飲みしたい」と話していたが、今日からは堂々とそれが出来る。俺と悠斗は行きつけの『バー・三日月』に予約を入れておき、そこで数日遅れのバースデーを祝うことにした。
「いらっしゃいませ。お誕生日おめでとうございます」
入店すると、店主のバーテンダーがわざわざカウンターの向こうから出てきてめぐちゃんを祝福した。
「いつものお席へどうぞ。本日は奥様がお誕生日と伺っておりますので、ささやかではございますが、カットフルーツをサービスさせて頂きます」
「あ、ありがとうございます……!」
めぐちゃんが緊張した様子で答えた。バーテンダーがカウンター内に戻ると、彼女はほっとした様子で椅子の背にもたれた。
「ふぅ……。この薄暗くて静かな店内にいるだけでドキドキしちゃうよ……。まず、どんな顔をしていればいいか分かんないもん。注文の仕方もさっぱりだし」
「もっと気楽にしてて大丈夫だよ。ここはそんなに肩肘張らずに過ごせるバーだから。なぁ、悠斗?」
「ああ。おれなんて大学生の頃からの常連だぜ? ここはどんな酔い方をしても許してくれるからホントに有り難いバーだよ。……で、最初の一杯はどれにしようか?」
「どれって言われてもなぁ……」
めぐちゃんはメニュー表を指で一通りなぞったが、俺もそうだったようにカクテル名を見ただけでは決められないようだ。彼女はしばらく悩んでいたが、突然「あっ!」と声を上げた。
「二人とも、それぞれ思い出のカクテル、あるよね? わたし、それにする!」
彼女の言葉を受け、悠斗に連れられてこの店で初めてカクテルを口にした日に思いを馳せる。
「俺はやっぱり、悠斗のことを深く知るきっかけになったウィスキーのロックかな……。あの晩の飲みがなければ、たぶん今の俺はない。そのくらい思い出に残ってるよ」
「奇遇だな。おれもその日を思い浮かべていたよ。家族についておれ自身も深く考えるきっかけをもらった日だ」
「へぇ。悠斗ならもっと若い頃の……それこそ、ここに通い始めた頃の方がいろいろと思い出もあるのかと思ってた」
「その頃のおれの延長線上に今のおれがいるのは確かだよ。だけどおれは、お前らと一緒に暮らし始めたときに一度、人生リセットしたつもりでいるから。家だって今はまるっと更新しちまって原型残ってないし。だから、おれの思い出のカクテルも翼と飲み交わしたカクテルだよ」
「本当に、過去とはすっかり決別したんだな……」
「やっと、って感じだけどなぁ。ま、今が一番楽しいよ」
ってことで、ウィスキーのロック三つ。悠斗は、カットフルーツの小皿を運んできたバーテンダーに飲み物を注文した。
「いきなりウィスキーかぁ。しかもロック……? なんか大人ーって感じ! わたしの知ってるカクテルのイメージとはだいぶ違うけど」
めぐちゃんが早速カットパインを口に放り込みながら言った。その様子を悠斗と二人で微笑みながら見つめる。
「ロックも水割りも立派なカクテルだからな。ま、めぐはそのうち好みのカクテルを見つけていけばいいさ。二十歳になったばっかりなんだから」
「うん」
程なくして三人分のグラスが運ばれてきた。それぞれにグラスを手に持って掲げる。
「めぐちゃん、二十歳のお誕生日おめでとう」
「四年越しの三人飲みに乾杯」

「ありがとう! かんぱーい! ……ゲホッ! 喉が焼けるっ!」
「ほら、水」
俺がチェイサーを差し出すと、彼女は一気に半分ほどを飲み下した。悠斗一押しのウィスキーは十二年ものだ。その熟成された酒を、氷を入れただけの状態で飲んだのだから当然の反応だ。
「二人とも、普段こんなに濃いお酒を飲んでるの? 信じられない!」
「なぁに、すぐに慣れるさ。翼なんて一回限界知ったら、次からおれと同じ量を飲めるようになったもんな?」
「……おかげさまで」
確かにその日は同量のアルコールを摂取したかもしれないが、以降、酒癖の悪い悠斗のペースで飲まないよう気をつけている。言われるがままに飲み続けたら最後、家に帰り着けなくなってしまう。しかし、当の悠斗に自覚はないのか、恐ろしい発言をする。
「めぐもいつか、自分の限界知ってみる? おれが付き合ってやるぜ?」
「おいおい、めぐちゃんを酔い潰すのだけはやめてくれよ。飲み相手が欲しいだけなら俺が付き合う」
思わず睨み付けると悠斗はたじろいだ。
「冗談だって。……そんなに怖い顔すんなよ」
「酒が入った悠斗は本音しか言わないんじゃなかった?」
「……そんなこと、言ったかな?」
悠斗ははぐらかすようにウィスキーのグラスを傾けた。
*
それからショートカクテルを一杯ずつ注文し、軽い食事を取りながら小一時間ほど他愛ない話をして過ごした。悠斗はもっと飲みたそうにしていたが、今日の主役はめぐちゃんだ。俺と彼女とで示し合わせて席を立ち、悠斗を店の入り口まで引っ張っていく。
「何だよぉ、付き合い悪いなぁ。めぐはもう二十歳なんだから、好きなだけ飲んでったっていいんだぜ? おれがおごるよ」
「あはは……。もう充分いい気分だよ。また今度ねぇ」
「今度って、いつだよぉ? すっぽかされる前に予約しとかなきゃ。いつなら空いてる?」
「鈴宮様。そのことでお話が」
レジの前で悪態をつく悠斗に、店主が申し訳なさそうに口を開いた。
「実は私、今月でバーテンダーを引退することに決めまして。ですから、こうしてお目にかかれるのはおそらく本日が最後になります。今までごひいきにして下さってありがとうございました」
「えっ……」
悠斗がさっと真顔になる。
「それって、店を閉めるってことですか?」
「いえ。店は私の一番弟子が引き継ぎますのでご安心を」
「だけどどうして急に……? 引退を決めた理由って何なんです?」
悠斗の問いに、店主は微笑みながら答える。
「今まではお客様の思い出を作るのが仕事でした。しかし最近になって気づいちゃったんです。ひょっとしたら、私は私個人の思い出を作ってこなかったんじゃないかって。……きっかけは、少し前に孫が生まれたことです。自分の子育て期には余裕がなくて気付きもしませんでしたが、赤ちゃんの微笑みの可愛いこと可愛いこと。それを見て、これからの人生は孫子と過ごしたいと思うようになったんですよ」
「孫、ですか……」
「すべては鈴宮様のおかげです」
「おれ……?」
「ええ。はじめは一人でいらしていた鈴宮様ですが、今ではこうしてご家族で飲みにいらして下さる。それも、終始笑顔でいらっしゃる。その変化を見て、次は私が変わる番だと思いましてね」
「……おれが変われたのは彼らのおかげです」
「ええ、存じております」
笑顔でうなずく店主を見て悠斗もうなずいた。
「……今月中はまだいらっしゃるんですよね? 近々、彰博を連れてまた来ます。あいつもマスターにはずいぶん世話になったし、最後に挨拶したいと思うんで」
「はい。またのご来店をお待ちしております」
店主は深々と頭を下げた。
*
真夏の夜道を歩きながら家路につく。この身体の熱さが酔いのせいか気候のせいかは分からないが、ちょっと風が吹くと汗が冷えて心地よい。
飲み控えたはずだが、ふらりふらりと左右に歩く悠斗が危なっかしくて見ていられず、めぐちゃんと二人で左右から手を取る。思いがけず、昔みたいに三人で手を繋ぐ格好になってちょっと気恥ずかしくなるが、悠斗は「ほろ酔いってのも悪くないなぁ」と言って嬉しそうにしている。
「それにしても、孫かぁ……。出会ったばっかりの頃は、マスターも三十そこそこだったのに。……それもそうかぁ。翼が三十過ぎちゃったんだもんなぁ」
「もしかして、愛菜ちゃんが生きていれば自分にも孫がいたかもしれないって思ってる?」
俺が問うと、悠斗は困ったような顔をした。
「……あんな話を聞かされたら昔の記憶もよみがえってくるよ。今が一番幸せなのに。酒のせいかな……」
「俺が思うに、悠斗はあのバーでそうとう負の感情をばらまいたんだろうな。だから酒を飲むと、あの場に行くと、そういう記憶が引っ張り出される。……本当は忘れたくなんかないんだと思うぜ。だって、若い頃の頑張りや苦しみがあったから今の悠斗がいるんだろ? 口には出さないけど、悠斗はそれを誇りに持ってるんじゃないの?」
「……翼のくせに、いいとこ突いてくるな」
「くせにって、何だよ?」
「そのまんまの意味」
悠斗はそう言うと、繋いでいた手を離して、俺とめぐちゃんの肩に腕を回した。
「他人から見ればおれの過去は失敗だらけで、若気の至りじゃとても片付けられないような人生だろう。三十前後のおれもそう思ってたし、自分には生きる価値がないとさえ思ってた時期もある。だけど頭の片隅では、頑張ってきたのにどうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだって思ってもいた。そりゃあそうさ。二十数年、がむしゃらに水泳に打ち込んできたおれは、こんな思いをするために生きてきた訳じゃない。華々しい、誰もが羨む成功者になるために頑張ってきたのに、何だよこの仕打ちは、ってな」
「うん……」
「……だけど彰博やお前たちが、その過去を価値あるものに変えてくれたんだ。こんなふうに穏やかに懐古できるようになったのはつい最近だよ。そういう意味では、年を取るのも悪くないって思ってる」
「語弊があるかもしれないけれど、わたしは悠くんがそういう人生を歩んでくれてよかったと思ってる。だって違う人生だったらこういう形で出会ってなかっただろうし、ましてや一緒になんて暮らしてないと思うの。結婚はしなかったけど、悠くんはわたしにとってなくてはならない人。家族以上に大切な人だから」
「ありがとな、めぐ。お前はホントにいい女だよ……」
俺の肩に回していた腕をほどいた悠斗は、その身体をめぐちゃんに預けた。酔っている彼女も彼女で抵抗せずにじゃれ合いを楽しんでいる。
「おい、悠斗。酔っ払ってるからって、そのくらいにしといてくれよ」
念のため釘を刺すが、二人の世界に浸っているのか返事はない。
「悠斗ってば!」
肩を掴んで振り向かせると、今度は俺に寄りかかってきた。
「なぁ……。そろそろ抱かせてくれないか。お前らの子どもを」
「は……? えっ……。何、言ってんの……?」
あまりにも突然のことに動揺を隠せない。悠斗は続ける。
「前から言おうとは思ってたんだ。でもこの際、言うよ。確かにおれはお前らの結婚を後押ししたし、こうして一緒に暮らしてもいる。だけど本音を言えば、お前らと一緒に子育てがしたいんだ。二人の夫婦生活に外野が口を出すもんじゃないのは分かってるよ。分かってるんだけど、おれたちの家に小さな子どもがいる生活も悪くないんじゃないかって最近強く思うんだ……」
「悠斗……」
「なぁ。お前らはどう思ってるの? 二人の考えを、今、ここで、聞かせてくれないか」
「…………」
俺は口をつぐんだ。が、めぐちゃんは悠斗の問いに答えるように口を開く。
「……実はわたし、最近になって子どもを持ってもいいかなって思ってるんだよね。というのも、仕事場で知り合ったお客さんの連れてくる赤ちゃんがかわいいんだ! 会うたびに成長を感じられるのも、他人ながら嬉しくって」
「めぐちゃん……?! それ、ほんと?!」
想定外の言葉に息が止まりそうになる。彼女は「うん」とうなずく。
「わたしも言おう言おうと思いながら、なかなかタイミングが合わなくて……。でも、さっきバーテンダーさんの話を聞いて、今夜家に帰ったらちゃんと話そうって思ってたとこだったんだよね」
「なら、話は早いじゃねえか。翼も子どもは欲しがってたし。なぁ?」
悠斗に笑顔を向けられる。が、ついにその時がやってきたのかと思ったらドキドキしてしまい、返事が出来なかった。
「どうした? ここは喜ぶところじゃないのか?」
「そうなんだけど……。子どもを作ろうかって意識したら、何だか緊張しちゃって……」
本音を漏らすと悠斗は立ち止まり、再びめぐちゃんに寄り添った。
「ほう、いざとなったら萎えたってわけか……。情けねえ野郎だ。なら、おれがめぐの相手をしよう。幸い、今日のめぐはご機嫌みたいだし、おれもおれで気分がいい。二人きりになりさえすれば、あっという間にいい雰囲気に持って行ける。……どうだ、めぐ?」
「わぉ! 今日の悠くんってば、大胆ー!」
見つめ合った二人は今にもキスしそうなほどに顔を近づけている。さすがに見ていられずに割って入る。
「あまりにも度が過ぎるだろ! めぐちゃんは俺の奥さんなんだ、手を出してもらっちゃ困る!」
「困る、だと? 甘いんだよ、お前は。おれだって男だ。仮にも一度愛した女と一つ屋根の下で暮らしていて何も感じないとでも思ってんのか? めぐさえその気になればこっちのもの。寝取ることなど造作もないんだよ。なにせ、おれには女を誘うテクニックがあるからな」
「……悠斗!」
「お前は頭で考えすぎてる。身体で感じろ、女の雰囲気を。流されろ、その場の空気に」
「簡単に言うなよ。俺がこれまでどれだけ計画的に子どもを作らないようにしてきたかも知らないくせに」
「じゃあ聞くが、これまでの人生で計算通りにいったことがどれだけあったってんだ? 少なくともおれは、二十二で子どもが出来て結婚する予定なんてなかったし、その子どもが五歳で水死して離婚するとも思ってなかった。ましてや三十八で母親を亡くすなんて夢にも思っていなかった。
……だけど同じ予定外でも、母親の病気がきっかけでこの地に戻った結果、彰博やめぐ、その後にはお前と出会えたのも事実だ。十年連絡を絶っていた親元に今更帰れるか、と意地を張っていたら、こうはなってなかったってわけだ。
……皮肉なことだが、思い通りの人生を送ってやろうともがき続けた前半生で待っていたのは不幸だった。ただ生きていればいいやと肩の力を抜いた後半生には幸せが待っていた。……この意味が分かるか?」
「本能の赴くままに生きろって言いたいのかよ……。めぐちゃんのこともそうやって抱けと……? 俺は悠斗とは違う。俺には、無理だ……」
「そうか……。なら、仕方がないな。めぐ。家に戻ってシャワーを浴びたらおれの部屋に来い。おれならお前の気持ちに応えられると約束しよう」
悠斗は言うなり、めぐちゃんにキスをした。以前にも見た、吸い付くようなキスだ。あろうことか、めぐちゃんがキスを拒む様子はない。誘惑に負けているのか、あるいは悠斗の術中にはまっているのだろうか。悔しい……。なのに、一ミリたりとも動かない俺の手足に嫌気が差す。
(俺は何をしている……? 目の前でパートナーの唇を奪われているってのに、何の行動も起こせないのかっ……!)
怒りにまかせて人を殴っちゃいけないとか、本能は抑えるべきだとか、そんな理由を並べ立てては俺を動けなくしている脳みその信号を無理やり断ち切り、非力な拳を突き出す。
「この野郎っ……!」
とっさに避けきれなかった悠斗は俺の拳を食らってよろけた。しかし彼は笑っている。
「いいよ、その顔。おれはお前のその顔が、女を奪われまいとする男の顔が見たかったんだよ」
「なら、もっと見せてやるっ!」
「二人とも、やめて!」
拳が悠斗の元に届く直前でめぐちゃんの待ったがかかった。
「悠くん、ありがとう。もう充分だよ」
「へ……?」
「……ったく。何でおれがこんな芝居をしなきゃいけないんだ。まぁ、久々にめぐとイチャイチャ出来て楽しかったからいいけど」
「し、芝居……?」
何が何やらさっぱり分からない。ぽかんとしているとめぐちゃんがおれの手を握った。
「実は、ママから話を聞いたんだ。最近、人手不足でお仕事が忙しいんだってね。頑張ってる話を聞いたら、とてもじゃないけど心境の変化を伝える気になれなくて……。でも、それじゃいけないと思って悠くんに相談したら、芝居を打ってみるかって話になってね……」
「…………」
「翼くんのお仕事に余裕があるうちに子どものことを考えられたらよかったんだろうけど、それが出来ずにごめんね。だけど、お待たせしました。ようやくわたしも前向きに考えられるようになりました。……だからって、焦るつもりは全然ないよ。二人の気持ちが一致したらその時に……ね?」
「めぐちゃん……」
彼女の優しさが身にしみる。じーんと感じていたところへ、悠斗が余計な言葉を継ぐ。
「本当は今日実行する予定じゃなかったんだけど、それもまぁ、臨機応変に対応したってやつだ。……おれたち、マジでベッドインしそうな雰囲気だっただろう?」
「……ああ、本当に嫌な気分を味わったよ。悠斗はともかく、めぐちゃんの演技力には参ったぜ。もう、これっきりにしてくれよなぁ」
「なら、仕事で忙しくったって、ちゃんと夫婦の会話を持つことだ。先生だって有給休暇を取る権利はあるんだろう? 平日に休みを取るのも手だと思うぜ」
「ただでさえ人手不足なのに?」
「んなこと言ってると、今日の芝居が現実のものになりかねないぞ?」
さっきの二人の会話を思い出して背筋が凍る。
「……ああ。前向きに検討してみるよ」
*
それから一週間ほどが経った。俺はめぐちゃんと休みを合わせ、一日ゆっくり過ごす日を作ることにした。家には悠斗も祖母もいない。本当に二人きりってのは、実は今までなかった。それもこれも悠斗が気を利かせてくれたおかげだ。
「ホントにどこにも行かなくていいの? バイク、出すよ?」
昼頃までは扇風機を回しただけの部屋でごろごろしていたが、さすがにじっとしていられなくなって家の中をうろつく。しかし、何度聞いてもめぐちゃんの返事はNOだった。
「今日は普段忙しくしている翼くんの身体を休めるのが一番の目的だもの。出かけちゃったら意味ないよ」
「だけど、せっかくの休みなのに」
「……ねぇ、こっちにきて」
めぐちゃんははにかみながら俺の手を引き、風呂場に導いた。
「せっかくの休みって言うなら、わたしは翼くんと二人きりのおうちタイムを満喫したいな」
「……二人きり」
呟いてみて、そうか、今日はこの家には俺とめぐちゃんしかいないんだと再認識する。同時に、今まではなんだかんだ言って同居人の目を気にしていた節があったと気づく。思えば一緒にシャワーを浴びたことさえなかった……。
結婚してもうすぐ二年。これまで何度となく肌を重ねてきたが、こう言うシチュエーションは初めてだ。
「……何だかドキドキするよ」
「わたしも……」
互いの気持ちを確かめ合い、自然な流れで汗ばんだ衣服を脱がせ合う。浴室に入ってシャワーを浴びながらどちらともなく身体を求め、息が乱れる。頭が痺れ、自分が何をしているのかも分からなくなる。そのうちに身体の感覚さえなくなって、気づけばめぐちゃんと一つになっていた。
俺たちを隔てるものは何もなかった。彼女の体内に俺のすべてを送り込んだのは初めてだったが、不思議と余計な考えは浮かんでこなかった。
自然な形で愛し合うとはこういうことか、と思い至ったのは、冷房の効いた部屋で昼寝した後だった。
「おはよう、よく眠れた? おやつにする?」
俺の目覚めに気づいためぐちゃんが傍らにやってきて座った。
「いや、大丈夫」
寝ぼけ眼で起き上がり、彼女の肩を抱く。
「……気のせいかな。今日のめぐちゃんはいつもよりずっと綺麗に見える」
「ふふ……。ありがとう。翼くんが愛してくれたおかげ、かな?」
寄せられた唇にキスをしようとしたとき「ただいまー」と玄関先から声がした。夕方になって悠斗と祖母が帰宅したのだ。まだ靴も脱いでいないうちから悠斗の暑がる声が聞こえる。
「あー、あちぃ。ちょっと外に出ただけで汗だくだぜ。シャワー浴びていいか?」
シャワーと聞いて、昼間の出来事が脳内再生される。めぐちゃんも同じことを想像したのか、頬を染めてうつむく。
「……今日のことは内緒ね」
「もちろん。でも……また機会があればしたいな」
「……だね」
「どうだ? ちゃんと仲良く過ごしたか?」
居間でささやき合っているところへ祖母と悠斗が入ってきた。俺たちが見つめ合うと、祖母が思いも寄らないことを口にする。
「あら。二人から石けんのいい匂いがするわ。もしかして二人で一緒にお風呂に入ったの?」
「…………!」
年のせいか、祖母には恥じらいのかけらもないようだ。
「オバア、ナイス!」
無遠慮に大爆笑する悠斗の脇で、俺たちは顔を真っ赤にしてうつむくしかなかった。
<悠斗>
季節は巡り、今年も残すところわずかとなった。
暖冬とは言え、日に日に寒さが厳しくなっている。庭の手入れのため部屋着のまま外に出たら思いのほか寒くて身震いする。
「めぐは職場で温かくしているんだろうか……」
秋に妊娠が分かってからと言うもの、おれは誰よりもめぐの身体を気にしている。まるで自分が父親になったかのような心持ちなのだ。そのせいで翼には「まさか俺のいない間に関係を持ってないよな?」と疑われているが、断じてそんなことはない。
めぐのお腹にいる赤子が愛菜の生まれ変わりなら、もうすぐ再会できる――。
そう思ったら、赤子の成長を気にしてしまうのは仕方がないことだ。めぐの妊娠を機に一度も愛菜の夢を見なくなったのも大きい。仮に赤子が愛菜の生まれ変わりじゃなかったとしても、おれはめぐの子どもを我が子のように愛し育てるつもりだ。それが、愛菜を死なせてしまったおれの責務だと思っている。
「悠斗君、そんな格好じゃ寒いわ。これを羽織りなさい」
開けたままの居間の窓から震えるおれが見えたのだろう、オバアはコタツから這い出して自分の着ている袢纏を差し出そうとした。が、その動作は危なっかしく、今にも転びそうだ。思わずこっちから部屋の中に飛び込む。
「おれなら大丈夫。ちゃんと自分の上着を着ますから、オバアはそのままで」
「でも……」
「オバアにはいつまでも元気でいてもらいたいんですよ。だから、無茶しないでください!」
ちょっと強めに言うと、オバアはしゅんとしてコタツに座り直した。申し訳なさを感じつつもまずは一安心する。
最近のオバアは毎週のように病院へ通っている。大抵はおれがタクシーで付き添っているのだが、以前より回数が増えたこともあって正直、休む暇はほとんどない。仕事を休めないニイニイからは「そろそろデイサービスの利用や老人ホームへの入所を検討しよう」と提案されているが、この家での暮らしが気に入っているオバアをこっちの都合で追い出すのは気が引けた。おれだけじゃない。めぐも翼もオバアとの暮らしが一日でも長く続くことを願ってる。ならばここは頑張らねばなるまい。日中手が空いているのはおれだけなのだから。
「ただいまー」
その時、明るい声が聞こえた。めぐが帰宅したようだ。慌てて玄関に赴く。
「歩いてきたのか? 帰るときは迎えに行くから連絡しろって言っただろ?」
「すぐ近くだもん、大丈夫だよ」
「だけど、お腹には大事な赤ちゃんが……」
「もう! 悠くんは心配しすぎ!」
めぐは腰に手を当ててハリセンボンみたいに頬を膨らませた。
「つわりもないし、わたしはお仕事もバリバリこなせるくらい元気だよ! 心配なのは悠くんの方。おばあちゃんの通院回数が増えてからお疲れに見えるよ? パパや伯父さんの言うように、そろそろ家族以外の人の手を借りてもいいんじゃないかってわたしも思うよ。職場のオーナーに聞いたら、認知症を患っていたおばあちゃんが最終的には介護施設のお世話になったって……」
「オバアは頭もしっかりしてるし、身の回りのことはまだ自分で出来るじゃないか! そんなオバアをどうして施設に預けられる?! それとも、おれじゃ頼りないっていうのか?!」
「そ、そういうわけじゃ……。わたしはただ無理をして欲しくなくて……」
「おれだってまだまだ動ける。老人扱いしてもらっちゃ困るな!」
「……ごめんなさい」
カッとなってまくし立てると、めぐはさっきのオバアのように頭を垂れ、自室に行ってしまった。
我に返って反省したおれもひとり、自分の部屋に引っ込む。
(参ったな……。いったい、どうしたってんだ……? まるで昔のおれに戻ったみたいじゃないか……)
ふぅと息を吐き、椅子に腰掛ける。冷静になったところで思考を巡らせる。
最近、家族と適切な距離をとれなくなっている。おれが変わったのか、めぐたちが変わったのかは分からない。いずれにしても話そうとするとギスギスしたり、イライラしたりしてしまうのは確かだ。
めぐの言うとおり、疲れているせいなのだろうか。いや、そんなはずはない。子どもの頃から今日に至るまで水泳をし続けていて体力は充分にある。病院の付き添いくらいで疲労が蓄積するとは思えない。
(とにかく泳いで気晴らししよう……)
大抵のことは泳げば解決する。そう言い聞かせてバイクのキーを持つ。なんとも表現しがたい胸の痛みを感じながら、今日も水泳コーチの仕事に向かう。
*
ところが、仕事を終えても胸のモヤモヤが晴れることはなかった。泳ぎが足りないのかもしれないと思い、スポーツクラブが閉館するまで泳いでみたがダメだった。こんなことは初めてだ。
九時を回ってから帰宅すると、オバアの就寝を手伝っていたらしい翼が出迎えてくれた。
「やけに遅かったじゃん。仕事が長引いたの?」
「いや、気晴らしに泳いできたんだ。……まぁ、気は晴れなかったんだけど、そういう日もあるよな」
「気晴らしはいいけど……。あんまり身体を酷使するなよ? 夜だってちゃんと寝てないみたいだし、休めるときに休まないと」
「翼までおれを年寄り扱いか?! 余計な心配するなよっ!」
乱暴に靴を脱ぎ散らかす。酷くイライラする。何かに怒りをぶつけたい衝動を感じながら部屋に上がろうとした、その時だ。
「うっ……!」
目の前の景色が歪み、胸に激痛が走った。胸を押さえて膝を折り、必死に呼吸をしようと努めるが、どうしても息を吸うことが出来ない。そのうちに起きていることも出来なくなって倒れ込む。
「悠斗、どうしたんだよっ……!? め、めぐちゃん! 救急車を呼んで! 悠斗が倒れたんだ!」
「えっ!? 悠くんが……?!」
遠ざかる意識の向こうでかろうじて二人の声が聞こえる。もしかしたらこのまま死ぬかもしれない……。そんな思いが脳裏をよぎる。
(めぐと翼の子ども、見たかったな……。ごめん、愛菜。どうやらこの世で再び会うのは難しそうだ……)
胸の内での呟きは二人の耳には届かない。死を意識したとき、たびたびおれの前に姿を現してきた亡き家族のことを思い出したが、おれがこんな状況だって言うのに彼らが迎えに来る気配はない。
(薄情な親たちだ……)
妙な孤独感に打ちひしがれながら一人、死を覚悟した。
◇◇◇
気がつくと真っ白な場所にいた。胸の痛みも息苦しさも今はない。
(おれは……死んだのか……?)
「おとーさんは死んでないよ」
心の中で呟いたのに、否定された。
「愛菜……?」
そこには、生前と同じ姿の愛菜がいた。これまでとは違い、声も姿もはっきりしている。まるで肉体がそこにあるかのようだ。
「……死んでないなら、どうしてはっきり見えるんだ?」
疑問をぶつけると愛菜が答える。
「……生と死の間にいるって言った方が正しいかな? だからこうして同じところに立っていられるんだよ」
「生と死の間……。やっぱりおれは死ぬのか……」
「死なせないよ。愛菜が、そうさせない」
そう言うと愛菜は勢いよく駆けてきた。無意識のうちに膝を折り、その身体を抱きしめる。
懐かしい抱き心地にもかかわらず、体温は一切感じられなかった。腕の中にいるのは血の通った人間ではない……。おれも愛菜も異次元にいるのだと思い知らされる。
「……そうさせないって、どういう意味だ?」
「……愛菜がおとーさんに命を渡すの。そうすればおとーさんはこの先も生きていける」
「それって、もしかして……」
嫌な予感がした。おれが最後まで言わずとも分かったのだろう、愛菜はうなずく。
「現世でおとーさんと再会するつもりだったけど、予定変更。おとーさんのいない現世に生まれても愛菜はあんまり嬉しくないからねー」
「そんなのはダメだ! めぐを、翼を悲しませるなんて……!」
「このままおとーさんが死んじゃっても二人は悲しむよ」
「…………」
オジイがなくなる前後の二人の様子を思い出して口を閉ざす。愛菜は続ける。
「おとーさんが苦しんでるのを知ったら、いてもたってもいられなくなったの。胎外に出るまではまだ魂のままでいられるし、自由に動き回ることも出来る。命を渡すことも……」
「……おれは愛菜に生き直して欲しいよ。おれはもう充分幸せに生きた。だから今度は愛菜の番だ。違うか?」
「ありがとう……。だけど、もう決めたことだから」
「愛菜っ……!」
「……また、会えるよ。おとーさんが生きていれば絶対に。だからその時まで自分の身体を大切にしてよね?」
「だけどっ……!」
「それじゃあ、元気でねー」
直後、抱きしめていた愛菜の身体が光り出した。目の前が再び真っ白になる。
(もうすぐ愛菜に会えるって、楽しみにしてたんだよ……。なのにどうしてまた遠ざかってしまうんだ……)
悔しさのあまり唇を噛む。しかしおれが死んでしまっても愛菜を抱くことは出来ないと気づく。現世で再会するにはやはりおれが生を繋ぐしかない……。
(生きて幸不幸を体験するのが、おれに課せられた使命だとでも言うのか……。それともおれは、早くに死んでいった愛菜や両親の分まで生きることを運命づけられているのか……。誰か教えてくれよ、なぁ……?)
◇◇◇
まぶたを開けると同時に胸の痛みを感じた。痛み……。それはおれが生きていることを意味する。
カーテンの隙間から太陽の光が差し込んでいる。周囲に時計はないから正確な時刻は分からないが、日差しの感じからして今は朝だろうか。
見覚えのある病室。どうやら、父親の死後に倒れたときと同じ総合病院に運ばれたようだ。
ボタンを押して看護師を呼ぶ。目が覚めたことを伝えると、看護師ではなく医師がやってきた。
「すぐに精密検査をしましょう」
聞けば丸三日寝込んでいたという。確かに身体が重い。三日の間に筋力が衰えてしまったに違いなかった。
早く体力を取り戻さなければ……。その一念から、診察室まで自分の足で歩くと主張したが取り合ってもらえなかった。
仕方なくわずかな距離を車椅子で移動する。看護師に押してもらわなければ行きたいところにもいけない……。酷くもどかしかったが、冷静に考えてみれば、三日も寝込んでいた人間が健常者のように動けるわけがない。もし家族がおれのように発言、行動しようものなら絶対に止めるだろう。
(おれはおれの身体を大事に扱っていなかったんだな……)
心身共に若いつもりでいた。それ故に身体の異変を見逃してしまったと、胸に手を当て反省する。
心臓が規則正しく動いている。この、どうしようもないおれを生かすために。
*
結果が出たのは午後も遅い時間になってからだった。結果を見た医師はまず眉をひそめ、それから口を開く。
「前回同様、過労が原因と思われますが、今回感じた胸の痛みは狭心症によるもので間違いないでしょう。幸いにして手術の必要はありませんが、ご家族の話では、寝る時間も満足にとれていない日々が続いていたそうですね。心筋梗塞を引き起こさなかったのが奇跡的なくらいです。健康を取り戻したいのであれば、これを機に生活を見直したり、仕事を辞めて休養することをおすすめします。身内に心疾患で亡くなった方もおられるようですし」
「……水泳コーチの仕事は生きがいです。簡単にはやめられません」
「同じ生活を続けていれば、次にお目にかかるときはこうしてお話しすることが出来ない状態かもしれません。それでもいいのですか?」
「…………」
「……ちょうどご家族がお見えになっていますから、私から容態と今後のことについてお話ししましょう」
医師は呆れたようにため息をつき、一度部屋を出て行った。おれはベッドの背に身を預け、点滴をしていない右腕を天井に伸ばした。
空を掴んでは離す、を繰り返す。意識したとおりに指が動き、力を込めれば拳を握ることも出来る。また呼吸に意識を向ければ、肺に空気が出入りするのも感じられる。
(これは、現実だ。おれは、生きている。いや、生かされてしまった……)
医師の診断が正しければ、おれも母親と同じ病で倒れていてもおかしくはなかった。それが一時的な胸の痛みで済んだのは、間違いなく愛菜のおかげだ。
しかしおれの意識下で起きた、およそ説明できない現象によって救われたと言ったところでどれほどの人間が信じるだろう? たとえ事実に反していても、医師が適切な処置し、投薬したから助かったと説明した方がよほど多くの人を納得させられるに違いない。
見えない世界に住む人々の存在を信じているめぐなら、あるいはおれの話を信じてくれるかもしれないが、懐疑的な翼にはどう話したらいいものか……。
思いを巡らせていると、医師と共に翼が姿を現した。その表情はいつになく険しい。
「……いろいろ、ごめん」
謝ってはみたものの、翼の表情は硬いままだ。重苦しい空気を断ち切るように、医師が淡々と症状や入院日程、投薬について説明するが、翼の耳には届いていないようだ。説明が終わり医師が部屋を出て行く際も、まるで金縛りにでも遭っているかのように動かなかった。
あまりにも無言が続くのでこっちから声を掛ける。
「久々に顔を合わせたんだ、もうちょっと喜んでもいいんじゃないのか?」
「……まだ信じられないんだ。こうして悠斗と生きて対面できてることが。……俺が夢を見てるわけじゃないんだよな? ちゃんと……生きてる……んだよな?」
「ああ、血は通ってるよ。ほら」
手を差し出す。翼は恐る恐る握り返したが、温もりを感じたのかほっと息を吐いた。
「そんなに心配だったのかよ?」
「ったり前じゃないか! 医者から、夕べが峠だって言われたら誰でも怖くなる。……あの先生、メッチャ驚いてたよ。一晩でこれほどの回復力を見せた患者は未だかつて見たことがないってね」
「そのことなんだが……」
翼が信じてくれるかどうかは分からない。それでも真実を言おうと決めて息を吸い込む。
「おれが生還したのは、めぐの胎内に宿っていた愛菜が自ら命を絶ったからだ……。おれがいないこの世に生まれても嬉しくないからと言って、その命をおれに……」
「…………!」
翼は目を見開いて再び黙り込んだ。
「……信じちゃくれないだろうな。だけど、本当のことだ」
沈黙に耐えかねて言葉を継ぐと、翼がようやく口を開く。
「……すべてが繋がったよ。めぐちゃんの急な流産も、悠斗の奇跡の生還も。もちろん、にわかには信じがたいけど、それが真実だってことにすれば全部納得できる」
「……やっぱり、流産したのか。……めぐはどうしてる?」
「ここに入院してる……。母体に問題はないらしいけど、赤ちゃんが亡くなったのは自分のせいだって酷く落ち込んでるんだ……」
「そうか……。心配だな……」
「死にかけた悠斗が言うと滑稽だぜ……」
翼がツッコミめいたことを言ったが、今日はまったく笑えなかった。
「仕事も休んでるんだろう? いろいろと迷惑をかけて済まない……。一日でも早くお前と漫才が出来るように、入院中はしっかり養生するよ」
「ああ、待ってる。……そうだ、動けそうならめぐちゃんにも顔を見せてやってよ。彼女も悠斗の安否を気にしてるから。会ったら生還するに至るまでの経緯を話してやって。そうすれば、赤ちゃんを亡くして落ち込む気持ちも少しは楽になるかもしれない」
「なら、今すぐめぐのいる部屋に連れて行ってくれ。医者が今日一日は自力で歩くなって言うんだ。車椅子に乗れば一応移動してもいいことになってる」
「オーケー。案内するよ」
*
翼に介助を頼み、車椅子で移動する。部屋は同じフロアだから、傷ついためぐに掛ける最適な言葉を思いつく間もなく着いてしまった。しかし、すぐに連れて行って欲しいと頼んだのはおれだ。たどたどしくてもいい、とにかく伝えようと意を決し、部屋に入る。
「悠くん……!? 本当に悠くんなの……? あぁ……無事でよかったぁ……」
おれの顔を見るなり、めぐはいつものように弾んだ声で言った。つかの間安堵するが、ベッドに横たわったままの姿をみて、彼女もまた安静にしなければならない身体なのだと悟る。
「めぐに言わなきゃいけないことがあるんだ。そのためなら這ってでも来る」
「……翼くんと一緒ってことは、流産の話は聞いてるってことだよね? 言わなきゃいけないことってもしかして……?」
「ああ……」
返事はしたものの、すぐに話し出すことが出来なかった。沈黙が続き、嫌な空気が場を支配する。長い間静かな時が流れたが、ようやっと覚悟を決めて口を開く。
「……めぐの言うとおりにすればよかったんだ。自分の体力を過信せず、ちゃんと休息をとるべきだった。おれが間違ってた。本当に済まない……」
やはりまずは謝るべきだと思った。こんなことをしてもめぐの赤子が戻ってくるわけではないが、そうせずにはいられなかった。おれは続けて言う。
「死の淵をさまよっていたとき、愛菜が現れたんだ。そしておれを助けるために命を差し出してくれた……。愛菜はおれに『生きろ』と言った。だけど正直、分からないんだよ。おれの命が、新しい命より重いのかどうかが……」
「そう……。愛菜ちゃんが……。わたしのお腹の中の命が悠くんを救ったんだね……」
ありがとうね。めぐは誰もいない自身のお腹を優しく撫でた。続いてその手が「こっちへおいで」と手招きする。翼に車椅子を押してもらいそばまで行くと、両腕でそっと抱かれた。
「やっぱり悠くんはあったかくなくちゃ。……生きててくれてありがとう」
「怒らないのか……? おれのせいでお腹の子が亡くなったかもしれないってのに」
「怒るわけないじゃん! ……悠くんの顔色がどんどん悪くなっていく様子を見て、このまま死んじゃうんじゃないかって本気で心配してたんだよ? どうか悠くんを助けて下さいって、ずっと神様に祈ってたんだから!
……だけど、わたしの願いを聞き届けてくれたのは神様じゃなくて愛菜ちゃんだったんだね。この腕で抱くことが叶わなかったのは残念だけど、愛菜ちゃんには感謝しないとね。悠くんに命を分けてくれてありがとうって」
「めぐ……」
潤んだ瞳を見て、今回のことはやっぱりおれの自信過剰が招いた災厄だ、と後悔する。しかしめぐはさっぱりとした口調で言う。
「……実は、お医者さんに言われたんだ。赤ちゃんがいるんだから、これまでと同じように力仕事をしたり、寒いのを我慢したりしちゃいけないって……。それを聞いて、悠くんが自分の体力を過信していたように、わたしも若さを過信してたんだって反省したよね。何気なく重たい荷物を運んでいたし、夜更かししてたし、寒いのにオシャレ重視の格好してたし……。そういう配慮のなさが残念な結果に繋がったんだと思ったら自分が許せなくって、さっきまで落ち込んでた。悠くんの話を聞いてもまだショックを引きずってるけど、うん、少しは落ち着いてきたよ」
「そうか……」
「悠くん、これからも元気でいてよね? これは、愛菜ちゃんを含めたみんなの願いでもあるんだから」
この命が自分ひとりのものではないことを知る。大した特技も稼ぎもないおれだけど、家族は、おれが生きてここにいる、それ自体に意味があることを改めて教えてくれた。
めぐは今度は翼を手招きし、抱きしめた。
「……次は翼くんが倒れないようにね? 夕べは寝てないんでしょう? わたしたちのことは大丈夫だから、今夜は家に帰ってしっかり休みなよ?」
「そうするよ。正直、今にも寝れそうなくらい眠いんだ……」
翼は言いながら大あくびをした。
「二人をいっぺんに失うんじゃないかと思ったら一睡も出来なくて……。めぐちゃんと結婚するときにも言ったけど、俺には二人が必要なんだ……。
人はいつか必ず死ぬ、それは充分理解してるつもり。だけど、日頃の行い一つで残りの人生が長くも短くもなるのだとしたら、身体の声には耳を傾けるべきだ。……見栄なんか張らなくていい。生きることに貪欲だっていいじゃん? みんなで細く長く生きていこうよ」
「生に貪欲なおれ、か……」
最近はめっきり声を聞かなくなってしまったが、おれの中の一人は生きることへのこだわりが人一倍強い。一時は恨んだこともあるが、翼が同じようなことを考えていると知り、「あいつ」の発言も間違ってはいないのだと今更ながらに思う。
「……そうだな。おれほどしぶとく生き残ってきた人間もそう多くはいるまい。だったらこの先はいっそ、徹底的に長生きすることを考えてみるのも悪くないかもしれない。どうやらおれは、いるだけで有り難がられる人間らしいから」
「そうそう、悠斗はそれでいいんだ」
「……ありがとう、翼。ありがとう、めぐ」
「いやいや、こっちこそ生き延びてくれてサンキューな。……愛菜ちゃん、ありがとう。悠斗を生かしてくれて」
翼が天井に向かって声を放った。
「愛菜の魂の存在を信じてなかったんじゃないのか……?」
「今回ばかりは信じざるを得ない……。俺の負けだ」
「目に見える世界がすべてじゃないんだよね……。わたしも彼らの姿は見えないけど、祈りはちゃんと届いたと思ってる。氏神様が翼くんを守護してくれるように、亡くなった人もわたしたちを見守ってくれている。そしていつでも助けてくれる。今はそう思えるんだ」
「うん、俺にもやっと分かってきたよ……。氏神様も、いつもありがとうございます……」
翼は今度は神に祈った。
換気のために開けられた窓からやさしい風が入り込む。真冬だというのにどこか暖かいその風に、おれは神を感じた。おれたちは見えない存在に見守られながら今日も生きている。
「ありがとうございます……。この命、大事にします……」
胸の鼓動を味わいながらおれも神に祈った。
~幕間『ワライバ』でのとある一日~

<前編・永江孝太郎>
――永江主将時代のK高野球部員を集めた飲み会を開催します。場所と日時は以下の通りです……。
「もちろん、永江さんも行きますよね?」
高校時代、そしてプロ入りしてからも長きにわたりバッテリーを組んできた相棒、本郷クンが見せてきたメールの文言を見てしばし思考する。
正直な話、プライベートに割ける時間はほとんどなかった。指定された日も球団関係者との仕事が入っている。だが、即答しない僕を見た彼は「仕事より大事なこともあるでしょう!」というなり電話をかけ、あっという間に仕事の予定の方を別日に変更してしまった。
「たまには肩の力も抜かないとダメっすよ。永江先輩」
笑ったその顔は高校時代の彼を思わせた。
二十三年間の現役生活を終えた僕は、その後の十年も解説者や指導者として野球に関わってきた。引退を決意した際、長年世話になった東京ブルースカイの一軍監督に……という話もあったが、純粋に野球と接したいとの思いから辞退した。時を同じくして現役を退いた本郷クンの方は数年間、同チームのコーチをし、現在は大学や高校野球の指導者として活躍する傍ら、なぜか僕のマネージャー的存在としてスケジュール管理をしてくれている。
◇◇◇
それから半月ほどが経ち、会合の日を迎えた。本郷クンはタクシーで自宅まで迎えに来てくれた。彼の妻でK高野球部員だった春山詩乃クンも一緒だ。
「迎えに来たのに、行かないなんて言いませんよね?」
お互いに五十代とはいえ、春山クンの笑顔は昔とちっとも変わっていなかった。彼女に微笑みかけられるとき、僕はつかの間、人間的な感情を取り戻すことが出来る。だけど、ほんのつかの間だ。勝つため、相手より抜きん出るため、がむしゃらに己を鍛え続けてきた僕は、人として持つべき心を再びどこかに置いてきてしまったようだ。気づいたときには自分が傷ついていることさえ分からないほど鈍感になっていた。
(彼女の言うことだけは聞いておけ……)
心の中で誰かが言った。僕が人として生き続けるなら絶対にそうするべきなのだろう。冷静に考えれば僕にだって分かる。
「ね、行きましょう?」
彼女はもう一度誘った。その顔で何度も微笑みかけられたら、さすがの僕も断れない。
「……春山クンには敵わないな。仕方がない、少しだけ君たちに付き合うことにしよう」
「……相変わらず素直じゃないなぁ」
本郷クンはそう言いながらも嬉しそうに笑った。
*
他愛ない会話をしているうちに目的の場所に着いた。店の看板にはカタカナで「ワライバ」と書いてある。道中で聞いた話によると、オーナーは僕が主将時代に素質を見抜いたキャッチャー、大津クンなのだという。
タクシーから降りて店のドアを開けると、中にいた大津クンと野上クンが駆け寄ってきた。
「本当に来てくれたんっすね! お忙しい中、ありがとうございます!」
「ご無沙汰してます。昨日の解説も面白く聞かせて頂きました。歯に衣着せぬ物言いはいつ聞いても痛快ですね」
少し離れたところで一礼した大津クンとは対照的に、野上クンは僕の手を両手で力強く握り、挨拶をしてきた。彼は僕が抜けた後のチームを託した人物で、紆余曲折はあったものの無事メンバーを統率し、甲子園出場に貢献した実績を持つ。
「健在で何より。……雰囲気は昔のままだな。懐かしいね。二人はたまに会ったりするのかい?」
尋ねると、大津クンが答える。
「いえ、会うのはホントに久しぶりで。あ、でもね、何の縁か知らないんですけど、野上センパイの姪っ子がうちで働いてるんっすよ。今回もそういう経緯でこの会を企画したってわけ」
「で、あそこにいるのがおれの姪っ子のめぐちゃん。実は、息子の嫁さんなんですよ。かわいいっしょ?」
野上クンが照れながら店の奥にいる女の子を指さした。
「……姪っ子で、息子の嫁さん? と言うことは、いとこ同士の結婚なのかい?」
「あはは……。最初は反対してたんですけど、おれに似たのか一度決めたら貫くタイプで。野球好きも似ればよかったのに、そっちのDNAは全部娘に行っちゃいました……」
そのとき、話題に上っていためぐさんがやってきた。
「いらっしゃいませ。永江さんのことは伯父から色々と伺ってます。東京ブルースカイでキャッチャーとして活躍していた永江さんと伯父が、高校時代に同じチームだったと聞いて驚きました。実際にお目にかかれるなんて光栄です。……サ、サインをもらっても?」
「今はもう引退しているけど?」
「構いません……! こ、ここへ……」
後ろ手に持っていた色紙とペンを見たとき、長年の経験から彼女が欲しているわけじゃないと直感する。
「……大津クン。店に飾るサインが欲しいならキミが色紙を持ってくるべきじゃないか?」
「あ、バレちゃいました? めぐっちが頼めば喜んで書いてくれると思ったんっすけど?」
「……ああ、書くさ。彼女のためならね」
いろいろな理由からサインを欲しがる人がいる。こういう事例も度々あったから今更驚くことはない。これも仕事のうちと割り切り、淡々と求めに応じる。プロ野球選手時代に身につけた術だ。
「ありがとうございます!」
彼女は両手で色紙を受け取ると、早速大津クンの元に向かった。
「ちゃんと仕事しましたからね! あー、緊張したー!」
「ありがとう、めぐっち。これがあれば少しは野球ファンのお客さんも増えるだろう。なにせ、うちの店は変わってるからね。使えるものは使わないと」
二人の会話が耳に入り、大津クンも昔と変わっていないなと思う。いや、彼に限らず、今日集まったメンバーは皆、あの頃の雰囲気を残したまま成熟している。
懐かしいと思う一方で、五十歳を超えてもなお子どもっぽい一面を見るとがっかりもする。僕が指導者だからそう感じるだけなのかもしれないが、もっとしっかりしろよと言いたくなるのをなんとか堪えている状態だ。
「永江さーん。顔が怖いですよー」
本郷クンの声で我に返る。目が合うと彼は呆れたように手のひらを天に向けた。
「今日はお仕事モードをオフにしましょう。ちょっとでも仕事っぽいこと考えるとそういう顔になっちゃうんだから。まぁ、ここにいるメンバーはそんな永江さんを知ってはいますけど、せっかくですし、今日くらいは日本一に輝いたときみたいな笑顔を見せて下さいよ」
「……球場以外で感情を表に出すのは苦手でね」
「嘘ばっかり。詩乃の前では笑えるくせに」
指摘されて苦笑いする。確かに彼女の前でだけは笑うことが出来る。だがそれは、彼女が僕の感情を揺さぶる存在だからに過ぎない。
チームメイトの前で見せる笑顔らしきものは仕事用に作り上げたもの。僕が笑っているように見えるとしたらそれは単に野球そのものが楽しいからだ。
「今日は鬼部長の顔をしていた方が、みんなにとっては懐かしいんじゃないのかい?」
そう言って、談笑している元メンバーの前に立つ。自然と視線が僕に集まり、一同が静まりかえる。この感じ。キャプテンをしていた頃を思い出す。
「変わらない君たちを見ていたら昔を思い出したよ。今日は飲み会と聞いていたが、予定変更だ。今からK高に行って野球をしよう。あの頃のように、投げて打って走ろうじゃないか」
『えぇーっ!!』
全員から予想通りの声が上がった。だけど僕は本気だ。むしろはじめからそのつもりでキャッチャーミットをカバンに忍ばせてある。
真っ先にぼやいたのは大津クンだ。
「せっかく店を貸し切りにしたのに……。飲み食いしてってもらわないと儲けが……」
「あれ、理人さん? 普段と言ってることが違いません? いつもは、お金は二の次だって……」
めぐさんが指摘すると、彼は開き直って持論を展開する。
「それは普段来るお客さんの話! 第一線で活躍した元プロ野球選手は別なの! 永江センパイには貧乏喫茶にお金を置いていってもらわないと困るんだよねぇ」
「ならば、僕が現役時代に着ていたユニフォームを一枚プレゼントしよう。僕にとってはもう袖を通すことのないただの仕事着だが、ファンの間では十万以上で取引されたこともある。お金に困っているというならそれを売ればいい。うまくやればかなりの金額になるはずだ」
「マ、マジっすか?! それ、欲しいっす!」
「帰宅したらすぐに送るよ。……交渉成立、かな?」
「はいっ! ランニングでも千本ノックでも、何でもします!」
おいおい、大津。勝手に返事するなよっ! 飲み会のつもりで来たから動ける服装じゃないぜ! 永江の言いなりになってんじゃねえよ! ……などなど、あちこちから不満の声が噴出し始める。このままでは飲み会がしたいメンバーが抜けかねない。ここへ来たのは彼らと野球をするためだと言っても過言ではないのに。
(やれやれ……。こうなったら、とっておきの一言を告げるしかないか……)
僕はもう一度皆を注目させた。そして渋々ながら顔を向けた彼らに言い放つ。
「みんな、なんだかんだ言って、仕事以外の時間はバットを振ったりボールを投げたり走ったりしてるんだろう? その体つきを見れば分かるよ。せっかくの機会だ、日頃の成果を見せてくれよ」
直後、全員の目が輝き始めた。そう。現在、どんな職業をしていようとも、元高校球児である彼らは、白球を追いかけなければ生きていけない人種であることを僕は知っている。ほかでもない、現役を退いたあとの僕がそうやって生きてきたのだから間違いない。
「みんなでわいわい飲めると思ってたんだけどなぁ。やっぱり永江さんが中心になったら野球が始まっちゃうんですね。ま、想定内ですけど」
本郷クンは野球で飯を食ってるから逆に離れたかったのだろう。しかし皆が乗り気になったからには、彼にもやる気を出してもらわなければならない。
「たまには勝ち負け無しの野球をしたっていいじゃないか。子どもの頃のように野球を楽しむ気持ちも大切だろう?」
「確かに……。その感覚、久しく忘れてましたよ」
彼は何かを思い出したようだ。にわかに目をキラキラさせ、エースらしく皆を鼓舞しはじめる。
「よっしゃあ! 久々にこのメンバーで楽しく野球やろうぜっ! 飲み会はその後だっ! 一汗かいてからのビールは絶対にうまいぞっ!」
「おーっ!」
僕は飲み会の代わりに野球を……と提案したつもりだったが、本郷クンの一声で野球プラス飲み会にすり替わってしまった。一番喜んでいるのは大津クンだ。
「やれやれ……。すべてが君達らしいな。幼稚なところまで懐かしいよ……」
小さく肩を落としている僕のそばにめぐさんが立つ。
「素晴らしい団結力ですね! 永江さんってやっぱりすごい方だなぁ! 理人さんや伯父が尊敬している理由が分かりました! ……個人的にサイン、もらっちゃおうかなぁ」
もじもじしている様子がかわいらしい、と思ってしまった。無意識のうちにテーブルの上のコースターを手に取り、彼女が持っているペンでサインを書く。
「君、野球は?」
「あー……。すみません、さっぱりで……。皆さんが野球をしに行っている間、もう一人のオーナーである隼人さんと飲み会の準備をしておきますね。帰りをお待ちしています」
「君は正直者だね。気に入ったよ。うん、必ず戻ってくる。その時はもう少しおしゃべりしよう」
「うっわ、永江さんが口説いてる! 珍しいこともあるもんだ。だけど、ダメっすよ? 人妻に手を出しちゃ」
端で聞いていた本郷クンが僕をからかった。
「野球がいかに面白いスポーツか、知ってもらいたいからね。野球人口を増やすのも僕の仕事だと思ってるから」
「……真面目すぎ。からかいがいがない」
「真面目で結構。……それじゃあ行こうか。なに、僕らが行けば顔パスさ」
「ですね。よーし、みんな、おれに続けっ!」
本郷クンが号令を掛け、一番に店を出る。かつてのエースの言葉に感化されたメンバーは喜々として彼の後に続く。
「永江さんの今の顔、まるで野球少年みたい。誘った甲斐がありました」
春山クンはそう言って僕の手を握った。
「いつでもその顔が見られると嬉しいな。……眉間にしわを寄せてばかりいると寿命が縮みますよ?」
「心配無用。この命、縮んでも微塵も惜しくはないから」
淡々と答えると、彼女はさっと目を伏せた。
僕の身を案じてくれているのは知っている。だが、僕の命は野球と共にある。これは生涯変わることのない信念だ。だから、いつかこの身体が思うように動かなくなったら、その時はこの命も終えるつもりでいる。白球を追いかけられない人生など、僕にとっては無意味も同然だから。
<中編・大津理人>
――コウをよろしくお願いします――
永江センパイに憑く霊の一人にそう頼まれた。誰にも気づかれないよう小さくうなずく。察するに彼の母親だろう。他にも何人かの霊が彼の周りを囲むように憑いている。これまで彼が最高のパフォーマンスを発揮し続けてこられた理由はここにあったのだと、ひとりで得心する。
がむしゃらに努力すれば誰でも成功者になれる、というのは嘘。幸運とは見えざる力が働いた結果得られるもの、と言うのがおれの持論だ。
おれと隼人が喫茶「ワライバ」を続けて来れたのもあっち側の人々のサポートがあればこそだ。
遡ること四十年前、ここには「シャイン」って名前の喫茶店が建っていて、同居していた祖母のお気に入りの場所だった。しかし店主の死去と共に店はなくなり、跡地には娘の手によって放課後児童預かり所が新設されたのだった。ただそこも経営者の体調不良により閉鎖が決まった。近々売りに出されるという話を聞いたのは、奇しくもおれたちが開業のための店舗探しをしているときだった。
祖母が大好きだった喫茶店の跡地で、今度は孫のおれたちが喫茶店を経営する……。運命を感じたおれたちは売りに出される前から交渉し、土地を買った。
その頃からだ。おれたちに亡き祖母の姿が見えるようになったのは。「シャイン」がよみがえったと大喜びの祖母は、今のワライバが完成し、開店するやすぐ常連客になった。ところが皮肉なことに「シャイン」での知り合いが多かった祖母の口コミにより「あっちの世界」の人ばかりが来店するという、嬉しくも悲しい状況が長く続いた。
肉体を持たない人に飲み物を提供する――。それは神社に賽銭を投じる行為に等しかった。当然、損失は増える一方。何度もやめようと主張したが、暢気な隼人は「誰もが好きなときに立ち寄れて、好きなことができる憩いの場。それがここ、ワライバだろう?」と言って聞かなかった。その結果、幾度となく経営難に陥った。
ところが不思議なことに、もう潰れそうだってとこまで行くと、必ず手を差し伸べてくれる人が現れた。最初の時は大手企業の社長。その次は引きこもりの息子を持つ資産家。どちらも病んだ心の持ち主もしくはその家族で、話を聞いてあげるとみるみる元気を取り戻し、お礼と称してかなりの額を寄付してくれたのだった。
そんなことが続いてからと言うもの、この仕事はおれたちの使命であり、生涯にわたって続けなさいという天からのメッセージだと思うようになった。
半分慈善事業みたいな格好で店を続けるうち、現実世界のお客さんも徐々にではあるが増えていった。安定収入が見込めるようになったはつい数年前のこと。めぐっちを紹介されたのはそんなタイミングだった。
まさか野上センパイの姪っ子と一緒に仕事をすることになるとは思ってもみなかったが、彼女を愛でるためだけに来店する客も現れ、ありがたいことに店の売り上げは右肩上がり。また彼女と野上センパイが「K高野球部OB会」を企画してくれたおかげで、野球ファンも増えそうな予感だ。これもまた一つの縁、天の計らいだと思っている。
*
K高にはタクシーで向かった。元気な連中は元プロ組と走って行ったようだが、今のおれにそこまでの体力はない。
「……もしかして、永江センパイとは『イイ感じ』なんです?」
春山センパイと同じタクシーに乗り込んだおれは、ここぞとばかりに質問する。
「さっき手を繋いでたっしょ? 旦那さんには黙っときますから、こっそり教えて下さいよ」
「えっ、見てたの? 残念だけど、想像しているようなことは一切ないよ。……放っておけないんだよね。永江さんって独身だし、野球のことしか頭にない人でしょ? 今日だって祐輔がスケジュール調整したから会合に出席してるけど、それがなかったら今ごろ仕事してたはずだもの」
「へぇ。そんなに心配なんっすか、あの人のこと。どうして? やっぱり特別な感情があるからじゃないんっすか?」
「んー……」
彼女はしばらくの間考えていたが、やがて観念したように話し出す。
「実は……頼まれたのよ。永江さんのお母さんが亡くなる前に、コウの面倒を見てほしいって。祐輔とはずっと同じチームで家族ぐるみの交流もあったから信頼されていたみたい。……永江さんなら何でもできそうなイメージあるでしょ? でも、家のことは全部お母さんがしてたらしくて、洗濯一つまともにできないと知ってびっくり。……一人じゃ生きていけないのよ、あの人は。だからお母さん亡き後は、私と祐輔とで身の回りの世話を引き受けてるってわけ」
話を聞いて再び納得する。どうりで死後も見守っているわけだ。それにしても、あの名捕手が家事の一つも出来ないとは面白いことを聞いた。
「……本人には言わないでよね?」
「言いませんよ。これでも店を持ってますからね。お客さんから聞いた話を許可なく言いふらすような真似はしません」
「へぇ。大津も大人になったんだ。お店、繁盛してるって聞いたよ? 今度、個人的に遊びに来ようと思ってるんだけど、いいかな?」
「もちろん。誰と一緒でも、いつでも歓迎しますよ」
幽霊でもね、と言おうとしたが、話が長くなりそうだったのでやめた。
*
K高についたおれたちは、先生の許可を得るなり現役高校生を退かせて野球を始めた。端からは、オジさんたちが遊びの野球をしに来たように見えたかもしれない。しかしその中には元プロが混ざってる。二人に刺激され、動けば動くほど昔の感覚がよみがえってくる。気づけばあの頃に返ったかのように身も心も軽くなっていた。
(やっぱ楽しいな、野球は。っていうか、この人たちと一緒にいるのが楽しい)
仲違いしたこともあった。横柄な態度をとったこともあった。それでも彼らはおれを許し、仲間と認め、共に戦おうと言ってくれた。そういう過去があるからこそ、今もなおわかり合えると信じたい。
隼人の言い分を聞き、善行を貫いてよかったと今ごろになって思う。店に戻ったらひと言だけ感謝の言葉を伝えよう。まぁ双子だから、おれがこう思った時点で何かしら感じ取っているだろうが……。
<後編・野上路教>
ずっと「鬼の永江」の印象を引きずっていただけに、めぐちゃんや春山と穏やかな表情で会話する姿には違和感を抱かざるを得なかった。ファン向けの顔なのかなとも思ったが、それにしてはあまりにも自然な笑顔に見えたのだ。
みんなで一汗かき、再び大津の店に戻る。すると、待ってましたとばかりに、めぐちゃんが笑顔で迎えてくれた。
「おかえりなさい! 準備万端です! すぐにでも始められますよ!」
「かわいい……」
おれをはじめ、いい年のオジさんたちは彼女の微笑みにメロメロだ。
(ひょっとしたら、相手がめぐちゃんだから永江先輩も……?)
その可能性は否定できなかった。この子は生まれながらに人を笑顔にする力が備わっている。事実、観察していると永江先輩が満面の笑みを浮かべて彼女に近づいていく。
「約束通り戻ってきたよ。……宴会が始まったらすぐにでも僕の野球論を語るとしよう」
今にも口説きそうだったのに、やっぱりこの人は野球のことしか頭にないようだ。しかし野球のことなどまったく知らないめぐちゃんが「はい、楽しみです」と言って自然に笑うのを見るにつけ、この子も人と話すのが好きなのだな、と思う。こういう子だから大津みたいな癖のある男の下でも働けるのだろう。世の中、実にうまくできてるものだ。
「ねぇ、見てよ野上。あんな顔の永江さん見たことない。あんたの姪っ子さんって何者? 私でもあそこまでの笑顔は引き出せないのに……」
同じく彼を見ていたらしい春山が、驚きを隠せない様子で言った。
「いや、フツーの女の子だけど?」
「そう……。まだあんなふうに笑えるなら大丈夫かな……」
「えっ?」
「ううん、なんでもない……。そんなことより、飲み会飲み会!」
彼女はそう言うなり自身も笑顔を作り、夫である祐輔のもとに向かった。
*
「んじゃ、皆さん。久方ぶりの再会を祝して、カンパーイ!」
ムードメーカーの祐輔が乾杯の音頭をとるや、宴会が始まる。一汗かいた後のビールは格別で、あっという間にビール瓶が空になっていく。
あまりにも久しぶりだから、当然「今なにしてる?」って話題になるかと思いきや、野球をしたせいか昔の話ばかりに花が咲く。
あの時の試合は誰それが打って点を取った、甲子園行きを決めたのはあいつのおかげだった、永江部長はやっぱりすごかった、などなど……。よみがえるのはおれたちが栄光を勝ち取った出来事ばかりだ。あの頃はよかったと言いたいわけじゃない。けれど、その感動を分かち合えるのはここにいる連中だけ。だから今だけは当時の興奮をもう一度味わわせてくれ……。ここにいる全員がそう思っているかのようだった。
*
「こんばんは……」
宴会が盛り上がってきた頃、貸し切りだといっていた店のドアが開いた。一同が一斉に顔を向ける。
そこにいたのは息子の翼だった。翼はおれと目が合うなり睨み付けてきたが、店の中に歩みを進めるごとにいつもの頼りなさげに見える顔に戻っていった。
「めぐちゃん、閉店の時間はとっくに過ぎてるんじゃないの? 電話にも出ないし、あんまり遅いから迎えに来たよ」
「あっ……」
彼女は慌てて店の時計を確認した。そして申し訳なさそうに肩をすぼめた。
「ごめんなさい……。あの、理人さん、隼人さん。後のことはお願いしても……?」
「ごめん、おれたちも気づかなかったよ。余分に働かせて悪かったね。体に障るといけないから、明日は休んでくれていいよ。お疲れさま」
「はい、ありがとうございます。それでは失礼します。皆さんはこの後も楽しんでいって下さいね」
彼女は深々と頭を下げると、翼と一緒に店を出て行った。
まるで過保護な父親だな、といってやりたい気持ちを我慢して見送った。ちょっと前に彼女が流産してしまったから神経質になっているんだろう。おれ自身、翼と舞の間に生まれるはずだった命を亡くしているからよく分かる。母親本人の悲しみは計り知れないが、父親の方も精神的なダメージは大きい。妻に無理をさせないよう気を配るのは当然のことだ。
「優しい息子さんだね」
いつまでも二人の出て行った方を見つめていると、永江先輩に声を掛けられた。
「君と同じにおいを感じたよ。正義感もありそうだ。野球は好きじゃないと聞いたが、他は君にそっくりだと思うよ」
「あはは……。そんなに似てますかね……?」
気恥ずかしくて笑うと、先輩は深くうなずいた。
「さっきめぐさんが色々と教えてくれたよ。先日彼女が入院した際、寝ずに付き添ってくれた翼くんのために伯父さんが車を出してくれたってね。無事に自宅まで送り届けてくれて感謝してると言っていたよ」
酒のせいか、はたまたおれの弱みを握ったせいか、先輩はほくそ笑んでいる。おれは「やれやれ」とため息をつく。
「……子どもを持つと心配なことばっかりですよ。だけど、放っておく訳にもいかないじゃないですか」
「……僕の母親も世話焼きでね。コウは野球以外なにも出来ないんだから、って愚痴をこぼしながらすべてやってくれた。もういい年の男だって言うのにね。……しかしその母も亡くなってしまった」
「…………」
「僕が言いたいのは、人は心配事があればこそ自分がしっかりしなければと、この先も頑張って生きていかねばと思うものなんだろう、ということだ。……僕にはそういうものが一つもない。だから正直、いつ死んでもいいつもりで今この瞬間も生きている。僕が死んでも、困ったり悲しんだりする人はいないだろうからね」
いつだったか聞いたことがある。彼が甲子園出場に人一倍情熱を傾けていたのは亡くなった父親との約束を果たすため。それだけが生きる目的であり、その後の人生には何の興味もなかったと……。
それでもプロの世界に飛び込んだのはおそらく、「甲子園」のその先を目指してみようと思うような出来事があったからだろう。実際、現役時代は三度のリーグ優勝と二度の日本一を経験、個人でも華々しい成績を残している。
彼はチームのお荷物になってもなおユニフォームを着続けた。どの球団からも必要とされなくなるまでプレイヤーで居続けた。本当は引退なんてしたくなかったに違いない。しかし生きていれば誰しも身体は衰える。生涯現役はどんなに願っても叶わぬ夢なのだ。そんな彼にとっての「今」とはおそらく、おまけみたいなものなのだろう。そうでもなけりゃ「いつ死んでもいい」なんて言えるはずがない。
無性に腹が立った。たとえ冗談であっても自分の命を軽んじるような発言をした彼に。
カッとなったおれは椅子から立ち上がると、手に持っていたビールを先輩の顔にぶっかけた。
「今の発言、取り消して下さい! 自分の命を何だと思ってんですかっ!」
拳を出しかけたところで周りの連中が慌てて止めに入る。ところが、止めただけで叱る者はいなかった。むしろ「よくぞ言った!」と賞賛の声が上がる。
(なんだ。みんなもそう思っていたのか……)
そういうことならと、おれは更にまくし立てる。
「先輩は誤解してます! 自分が一人きりで生きてるって。だけど、ぜんっぜん違います。先輩はたくさんの人に支えられて生きてるんです。この意味が分かりますか? 先輩が死んだらその人たちが悲しむってことです! 他でもない、おれたちの尊敬する永江孝太郎の死を受け容れられない人たちがいるってことです!
……先輩、おれに言ったでしょう? 自分の真似は誰にも出来ないって。それと一緒。誰もあなたの代わりにはなれないんですよ。だから……簡単に『いつ死んでもいい』なんて言わないで下さい!」
「……厳しい言葉だな」
彼はうつむいたまま言った。なおも静まりかえる店内でもうひと言だけ付け加える。
「もし、生きる目的を見失っているなら、おれのうちに来て下さい。っていうか、親戚に会ってください。会えば、いつ死んでもいいだなんて気持ち、絶対になくなりますから!」
なぜこんなにも熱くなっているのか、自分でもよく分からなかった。らしくないって思ってる奴もいるだろう。だけど、おれだって変わったんだ。いや、変えさせられたんだ。子どもの結婚話に始まり、翼と和解し、結婚を認め、ユウユウと家族になるその過程において、本当に大切にしなきゃいけないものが何であるかを知ったんだ。
大事なのは、思い出でもプライドでもない。今この瞬間に一緒にいる人と過ごす時間だ。それは過去にとらわれず、現実を見つめながら生き続けることでもある。
だまり続ける先輩を見てしびれを切らしたのか、祐輔が言う。
「路教、任せろ。おれが必ず引き合わせる」
「おれも手伝いますよ」
大津も話しに加わる。
「野上センパイのうちがダメでも『ここ』があります。ワライバはね、心が疲れてる人の集まる場なんですよ。自宅に帰ったら一人きりって人もたくさん来ます。そういう人の、もう一つの家がここ。つまり、ここに来ればみんな家族ってことです」
「家族……」
「ですです。だいたいね、いつ死んでもいいなんて言ってる人は寂しいだけなんですよ。そういう人こそ、うちに来た方がいい」
「……なぜそこまで僕に生きろというんだ? 僕の人生なんだから、いつ終わりにしようが勝手じゃないか」
そう言った目はうつろだった。本当に野球をする以外に生きがいがないんだと確信する。
(何か一つ、この人に生きる目的を与えなければ……)
しかしこの年になって今更……それも永江先輩の心を動かすようなものなどあるだろうか。心を……動かす……?
「あっ!」
おれは声を上げた。大津も春山も同時に気づいたのか、目が合うと深くうなずいた。大津が代表して言う。
「そーだ、センパイ。例のユニフォームですけど、直接ここへ持ってきてくださいよ。そうだなぁ、出来ればめぐっちがいるときに。タクシー代くらい出しますよ。どうです?」
「僕が直接……? しかしそんな時間は……」
「じゃあ言い直します。めぐっちに会うために来て下さい。それがセンパイのためです」
「なぜ……?」
「はぁっ……? はっきり言わなきゃ分かりませんか? じゃあ言いますよ? ……めぐっちに一目惚れしたんでしょ? 好きになっちゃったんでしょ? だったら、適当な理由をつけてでも会いに来るべきです。大丈夫、うちにはめぐっち目当てのお客さんが多いですからね。そこに永江センパイがひとり加わったところで店的には何も問題ありませんから。っていうかむしろ大歓迎ですよ」
「……参ったな」
永江先輩は本当に困ったように目をキョロキョロさせた。こんなに動揺するところは初めて見た。彼は戸惑いながら言う。
「彼女が素敵な女性だというのは認める。しかしそれだけだ。決して一目惚れなどと言うことは……」
その場にいた全員が苦笑した。あまりにも言い訳じみていたからだ。
たぶんこの人は本当にこの年まで恋愛感情を持ったことがないんだろう。これじゃまるで中学生だ。いや、今時小学生だって恋愛の「れ」の字くらいは知っているだろう。
まだ、救える――。そう思った。別に翼とめぐちゃんの夫婦仲を裂こうなどとは微塵も思っていないし、出来ないと確信している。が、永江先輩に人間らしい感情を取り戻してもらうためには、めぐちゃんの力が絶対に必要なのだ。
そこに春山がダメ押しのひと言を告げる。
「永江さん。ひとりで来られないなら私が同行する。それなら、いいでしょ?」
「……わかった。君の言うとおりにするよ」
抵抗しても無駄だと分かったのだろう、彼はようやく首を縦に振った。
どこからともなく風が吹き込み、おれたちの脇をすり抜けていった。
「おっ、センパイの決断を喜んでる人たちがいますよ。それでいいんです」
大津が店の中をぐるりと見回しながら言った。
「……そうかもしれない」
永江先輩も天井を見やりながらぽつりとつぶやいた。
三 生きるということ

<めぐ>
「ま、とにかく食べな。全部、木乃香ちゃん自慢の逸品だからね。おかわりもあるから遠慮はいらないよ」
「うん。ありがとう。……でも、こんなにたくさんは食べられないから、一種類ずつにしようかな」
洋菓子店「かみさまの樹」のカフェテーブルに十種類ほどの焼き菓子が数個ずつ並んでいる。わたしはその中のフルーツタルトに手を伸ばして頬張った。優しい甘さが口いっぱいに広がる。「かみさまの樹」の味を木乃香も再現できるようになったと知って嬉しくなる。
彼女は現在、料理学校の二年生。まだ学生とはいえ、これほどの出来映えの菓子が作れるのだから、本来ならば相応の代金を支払うのが筋というものだろう。けれども今日は全部タダ。二週間前に流産してしまったわたしを元気づけるため、冬休みを利用して彼女が焼いてくれたのだった。それもわたしの好きな菓子ばかりを。
本当は、次の妊娠を望むならきちんと体調管理をしなさいと言われている。上白糖を使ったお菓子も出来るだけ控えた方がいいそうだ。けれど「我慢もよくないよ!」と木乃香は言い「今日のお菓子はめぐ用にアレンジしてあるから大丈夫」と付け加えた。
「お菓子で出来ている私でもちゃんと妊娠できたんだもの、一日くらい余分に食べても大丈夫よ」
そばでそう言ったのは木乃香のお母さんだ。確か若い頃から、隣に住んでいた今の旦那さん(この店の主人で木乃香のお父さん)が焼いた菓子を食べて育ったと聞いたことがある。甘いものの食べ過ぎは病気の原因になる、と健康診断を受けるたびに言われたそうだが、妊活せずに木乃香を授かったし、大病もしたことがないという。
「だいたい、日夜新作の研究をしている主人は毎日甘いものを口にしてるけど健康そのもの。時々洋菓子店のケーキを食べる程度の人がそれで病気になる訳ないじゃない。悪者はケーキじゃなくて生活習慣の乱れの方。勘違いしている人のなんと多いことか……」
確かにそうかも……と内心で呟き、木乃香のお母さんは我慢せず好きなものを食べているから、五十代でも肌が綺麗で病気知らずなのかもしれない、などと考える。
「それにしても……」
と木乃香のお母さんが続ける。
「未だに信じられないんだけど、それが真実なんでしょうね。めぐちゃんのお腹に宿った赤ちゃんが、命の危機に瀕していた『元お父さん』を救ったという話……。あっちの人が現実世界の命を操れるはずがないと思っていたけど、生と死の狭間ではそういうことも可能なのね……。私もまだまだ勉強不足だと思い知ったわ。実は今度、鈴宮さんから直接お話を伺いたいと思ってるんだけど」
「そういうことなら悠くんに伝えておきます」
「ありがとう。会えるという話になったときにはこっちから出向くわね。病後の方に無理をさせるわけにはいかないもの」
「はい、そうして頂けると有り難いです」
わたしたちは互いにうなずき合った。
悠くんとわたしの入院が、各々の働き方や祖母の介護について考えるきっかけとなったのは言うまでもない。祖母についてはさっそくデイサービス通いが決定し、今日も施設の世話になっている。家族の負担が少なくて済むよう送迎も頼んでいるから、日中は仕事なり身体を休めるなりに時間を使える。もちろんお金はかかるけど、家族の命には替えられない。
悠くんは最後まで渋ったが、最終的には祖母自身が説得した。
「あなたがわたしに元気でいて欲しいと言ったように、悠斗君にも長生きして欲しいのよ。生きていれば毎日おしゃべり出来る。わたしはそのためにちょっとお出かけして帰ってくる。悪い話じゃないと思うんだけど?」
そう言われた悠くんは首を縦に振るしかなかった。
*
食べきれなかったお菓子は持ち帰り、家族にも食べてもらうことにした。焼き菓子だから日持ちするし、翼くんや悠くんにもぜひ味わってもらいたかった。
その前に祖母が帰宅する。送迎バスの停留所まで迎えに行ってくれたパパと祖母を玄関先で出迎える。
「おかえりなさい。あれ? おばあちゃん、お化粧してるの? いつもより顔色がいいね!」
ほんのりと香水らしき匂いもする。祖母は恥ずかしそうに笑う。
「今日は、地元の美容学校の生徒さんが訪ねてきてね。おばあちゃんたちにお化粧をしてくださったのよ。彼女たちは『見習いだから下手だけど』って謙遜してたけど、こっちの気持ちを若返らせてくれたんだもの。百点満点よね」
「ちょっと値は張るけど、思いきって通所を決めて正解だったよ。まだ通い始めて間もないのに、以前より元気になったように見えない? やっぱり同年代の話し相手がいるって言うのは大きいみたいだ。こんな笑顔が見られるなんて僕も嬉しい。仕事を早く終えて迎えに来た甲斐もあったというものだよ」
パパが祖母を居間のローチェアに腰掛けさせながら言った。
「……悠には、おばあちゃんが楽しく過ごしてきたことを話しておいて欲しい。一応承諾してくれたけど、完全に納得したわけじゃなさそうだからね」
「わかった」
「ただいまー」
その時、翼くんが帰ってきた。園は相変わらず人手不足だというが、わたしの体調を気遣う彼は最近定時で仕事を終え、どこにも寄らずに帰ってくる。
玄関の靴を見たのだろう、彼は「アキ兄、来てるの?」と言いながら居間に入ってきた。
「おばあちゃんを連れてきたところだよ。……翼くんが帰ってきてくれたなら僕は失礼しようかな。あとのことは任せてもいい?」
「うん、大丈夫」
「よろしく。……だけど、くれぐれも無理はしないように。ちょっとでも疲れを感じたら休んでいいから」
「分かってる。……っていうかその台詞、めぐちゃんにも悠斗にも毎日言われて耳にたこが出来てるよ」
「彼女らは入院したことで、健康がいかに大事か身をもって知ったばかりだからね。しばらくは聞き流したくもなるだろうけど、こうして元気な姿で戻ってきためぐたちの言葉をどうか受け容れて欲しい」
「そうそう!」
わたしは激しく同意し、翼くんの腕にしがみついた。彼は嬉しそうに微笑み、空いている方の手でわたしの頭を撫でた。
それじゃあ……と背を向けたパパが、長居は無用とばかりにすぐさま玄関に足を向けた。わたしは慌てて引き留める。
「木乃香にもらった焼き菓子があるの。せっかくだからパパもここで食べて行きなよ。ママはまだ帰ってこないでしょう? 家に帰ってもひとりなら、ね?」
わたしは袋を逆さまにし、コタツテーブルの上に焼き菓子を広げた。その数が想像以上だったのだろう。パパは「じゃあ、食べながらめぐのおしゃべりに付き合おうか」と言ってショルダーバッグを降ろし、コタツの前に腰を下ろしたのだった。
*
親子の団らんを終え、パパが帰宅した後はゆっくりと夕食の支度を始める。最近は健康のことを考えて和食が多い。この日のメニューも焼き魚や煮物中心だ。身体に気遣う前のわたしはハンバーグやピザなど洋食ばかりを好んでいたが、流産を経験後、身体を温める食材や食べ方があると知り、翼くんや祖母から積極的に和食の作り方を習っている。
食卓に料理が出そろった頃には悠くんも帰ってきた。彼も身体のことを第一に考えて勤務時間を短縮している。収入が減ることに不安や葛藤もあるようだが、また倒れるわけにもいかないというのは本人が一番分かっているので、今はそういう働き方を受け容れているらしかった。
皆が食卓に着き、「いただきます」をする。ご飯を口に頬張るより先にわたしは今日の出来事を話し始める。
「今日、『かみさまの樹』に行ったんだけど、木乃香のお母さんが悠くんと話したいって。どうやら臨死体験の詳細を聞きたいみたい。会いに行くから都合のいい日を教えてって言ってたよ」
「……つっても、大したことは話せないけど、まぁ、会いたいって言うなら了解。基本、昼間ならいつでも大丈夫って伝えておいてくれ」
「わかった」
わたしは悠くんの了解が取れるなりスマホを取り出した。と、思いがけず一通のメールが届いていることに気づく。時々お店に来るクミさんからだった。何の気なしに開く。
――めぐちゃん、お腹の赤ちゃんは順調? 実はあたしも二人目を妊娠したっぽいの! 同じ学年になるかもね、楽しみ♡ 近々、またお店に遊びに行くね――
血の気が引いた。彼女にはまだ流産したことを伝えていない。次にお店で会ったときに言おうと思っていたが、まさかこういう展開になるとは……。
この、言い知れぬ焦燥感は何だろう? この、胸のざわめきは何だろう? 呼吸が乱れる。
「めぐ……? 急にどうした?」
スマホを見たあと顔色を変えたわたしに気づいた悠くんが画面をのぞき込む。文面を見、押し黙る。そして何ごとかと不安げな翼くんにスマホを渡す。彼もまたメールを読み、言葉を失った。
「……みんな、どうしたの? 急にお通夜みたいな顔しちゃって」
ひとり事情を知らされていない祖母が言った。
「めぐちゃんの身体のことで、ちょっと……」
翼くんは曖昧に答えたあとでわたしの肩をそっと抱いた。
「もしかして、申し訳ないって思ってる? 赤ちゃんに対して。それから……俺に対して」
わたしは答えなかった。翼くんはため息をつく。
「そのことについては、ここにいる全員が残念に思ってる。だけど、誰にも罪がないことも全員が知ってる。……避けようがなかった。誰も介入できない、生と死の狭間でのやりとりだったなら尚更だ」
「分かってるよ、そんなこと……」
言いながらも、今感じていること、口にしたいのはそうじゃない、との思いが込み上げる。
「……違う。わたしはただ、妬んでるだけ。妊娠したら必ず元気な赤ちゃんが生まれると信じて疑わない彼女を。実際そうして生まれてくるであろう赤ちゃんのことを」
「…………」
「もう一度頑張ればいいって話じゃない。命が一つ失われたことに変わりはないんだもの。……だけど、悠くんが助かったのはその命が失われたおかげなのも事実。……分かってる。けど、未だに受け容れられないわたしがここにいるの……」
「めぐ……」
悠くんは何かを言いかけたが、唇を噛んで再び黙った。
「いま、わたしたちに出来ることは何だと思う?」
静まりかえった室内で、祖母がぽつりと言った。誰も返事をしないと分かると答えを言う。
「こうして生きている奇跡に感謝すること。それしかない。……そうでしょう、悠斗君?」
「そのとおりです。……おれたちは確かに生かされている。そこにどんな意味があるかは分からないけど、それを探しながら生きていくしかないし、それが人生だっておれは思います」
彼は力強くうなずき、今度ははっきりとわたしの顔を見て言う。
「オジイが亡くなったときも悲しかったと思うけど、自分の身体の一部を失った今はより深い悲しみがめぐを襲っていると思う。それでも、乗り越えなきゃいけない。前を見つめるなら、その悲しみを糧にしなきゃいけない。おれがそうしてきたように……」
ハッとする。そうだ。彼は娘を、母を、父を、そして家族だと言ってくれたわたしの祖父を看取った。そのたびに悲しみに暮れてきたはずだが、それでもこうして生きている。生まれ変わろうとしていた娘の命が再び失われてもなお、彼は生き続けている……。
本当はどう思っているかなんて分からない、それでも「生かされてしまった」彼がどんな気持ちでここにいるのか、その意味をわたしなりに考えなければならない。おそらくそれが、わたしにとって生きるヒントになるはずだから。
「すぐには難しいかもしれない。だけどわたし、やってみる。……そのための力を貸してください。お願いします……」
わたしは三人を見回して深々と頭を下げた。翼くんがわたしの冷え切った手を握る。
「俺はいつだってそばにいるよ。めぐちゃんの苦しみは俺が半分背負う。喜びは二倍……いや、悠斗と一緒に三倍、四倍にする。だからこの先も一緒に生きていこう」
「ありがとう、翼くん」
礼を言うと、悠くんと祖母も静かにうなずく。
気持ちが少し落ち着いたところで思う。わたしの人生とは何のためにあるのか。自分だけが幸せならいいのか。それ以前に、毎日笑って暮らすことが幸せなのか、と……。
年老いた者から順に死んでいくことは理解できるし、祖父の死に際しては最終的に受け容れることも出来た。しかし、胎内の命があっさりと消え去ったとき、自分が生きていることが実は特別な、奇跡的なことのように思えてならなかった。悠くんが「生かされた命」に感謝する様子をそばで見て、その思いは一層強くなった。
明日は今日の延長で平凡な一日。考えるまでもなく、そんな「明日」は必ずやってくると信じていたけれど、違った。普段は感じないだけで、本当は死とは常に隣り合わせなのだと今回のことで思い知った。
(もっと、生きている今に感謝しよう……)
それは自分のためであり、わたしを慕ってくれる人のためでもある……。
(そうだ。笑顔笑顔……!)
トレードマークであるそれを無理やり作る。わたしが元気であることを伝えるにはこれが一番だ。
「せっかくのご飯が冷めちゃう……! さ、食べよ食べよ!」
湯気の消えた白米を口に押し込む。冷めたそれは、ちょっぴり塩の味がした。
「……馬鹿だな、めぐは。泣き笑いしながら食うやつがあるか。無理すんな」
悠くんに言われて泣いていることに気づく。彼がそっと涙を拭ってくれる。
「大丈夫さ。愛菜にはまた会える。おれだって今度こそこの腕で抱くんだ。っていうか、抱かずに死ねるか。……ゆっくりでいい。その分おれも長生きすっから」
「……うん」
悠くんの穏やかな声が胸に染み入り、愛おしく感じられた。
◇◇◇
それから三ヶ月あまりが経った。一日一日を大切にする、と言っても日々はこれまで同様穏やかに過ぎていく。そんな中、ひょんなことからオーナーの理人さんと伯父の所属していた高校の野球部で集まりたいという話になり、伯父の声かけで急遽、ワライバを貸し切っての飲み会が行われることとなった。
幼少の頃から、甲子園に行ったことがあるという話は聞いていたものの、メンバーのことや当時の詳しいエピソードについては聞いたことがなかった。
「おれが二年の時に主将だった永江孝太郎って人はすごいんだ。十年くらい前まで東京ブルースカイのキャッチャーだった人。めぐちゃんもテレビで一度くらいは見たことがあるだろ?」
「うそ! あの人と知り合い?! っていうか、その人を呼ぶの?! 伯父さん、すっごーい!」
「だろ?」
「なら、理人さんに頼んでその日は仕事を入れてもらいます。ぜひ会ってみたいですもん」
「滅多にないことだもんな。それがいいよ」
*
四月某日。こうしてわたしは永江孝太郎さんとはじめて対面した。
彼は集まった誰よりも若かった。シワのない年齢不相応の顔。それはかつての悠くんを――過去にとらわれていた頃の彼を――彷彿とさせた。しかし、終始笑顔の永江さんを見る限り、暗い過去を持っているとは思えなかった。わたしが個別のサインを求めたときも嬉しそうにはにかんでいた。
(こんなに笑顔の素敵なおじさまが後ろ向きに生きてるわけ、ないよね……)
饒舌に野球のことを語る彼はむしろ活き活きとしてさえいた。まったく興味がなかったわたしに一瞬でも「野球って面白いな」と思わせたのだからすごい。どうやら彼には、野球への情熱もさることながら話術も備わっているようだ。熱い話に引き込まれる。少しも退屈しなかった。
話に夢中になっていたとき、貸し切りのはずの店のドアが開いた。
「こんばんは……」
翼くんだった。彼はずかずかとやってきて椅子に座るわたしを見下ろした。
「閉店時間はとっくに過ぎてるんじゃないの?」
ハッとして立ち上がり、店の時計を見る。退勤時間から一時間近くが経っている。あんまり帰りが遅いので迎えに来たのだと気づく。わたしは慌てて帰る支度をはじめた。彼らには申し訳ないが、体調を気遣う夫の気持ちを無碍には出来ない。
「それでは、失礼します……」
わたしは名残惜しさと申し訳なさを感じながら翼くんと共に店を出た。
「無理は厳禁! 分かってるよね?」
帰りのバイクに乗るや、真っ先に叱られた。
「ごめんなさい……。でも、オジさんたちの話が楽しかったんだもん。それでつい時間を忘れてしまって……」
「……まぁ、楽しかったんならいいけど」
言いながらも納得していない様子の彼に「足が出た代わりに、明日は一日休みをもらえることになったんだから許して!」と告げる。
「……そういうことなら、明日はしっかり休むこと!」
彼が念を押したところで我が家に着いた。
*
翌朝、目覚まし時計の音で目が覚めた。隣で寝ている翼くんを起こさないよう静かにベッドから降りる。
「待ってよぉ、めぐちゃーん」
ところが、起こしてしまったのか翼くんに引き留められた。
「もうちょっと寝てようよ」
言われて、今日休みをもらったことを思い出す。もう一度ベッドに横たわり、彼の腕に抱かれる。
「ごめん、習慣でつい……」
「まったく……。休みが重なった日の朝くらい、イチャイチャさせてよ……」
「もう、翼くんったら……」
ベッドの上でのんびりと夫婦の時間を過ごす。流産して間もないこともあり、互いに身体を求め合うことはしない。それでも温もりを感じるうち、彼の優しさが伝わってきて幸せな気持ちになる。
「大丈夫。また自然に愛し合えるようになるよ」
「うん……」
見つめ合い、キスを繰り返す。気分が高まってきたその時、階下で電話のベルが鳴った。
「めぐー。ニイニイから電話だ。……出れるか?」
ドアの向こうで、電話を受けてくれたらしい悠くんの声がした。
「え、伯父さんから? 何だろう?」
「無視しちゃえよ」
「でも……」
妙な胸騒ぎを覚えたわたしは翼くんの腕からするりと抜け出し、電話を受けにいく。
「もしもし……」
『ああ、めぐちゃん。単刀直入に言うよ。……永江先輩を助けてやってくれないか』
「えっ?!」
急な頼み事に動揺を隠せない。
「助けてって……。一体、どういうことですか……?」
詳しく話を聞いてみると、わたしが帰宅したあとで永江さんと一悶着あったらしい。その彼を説得するにはどうしてもわたしの力が必要なのだという。
電話を切ったわたしはすぐ翼くんと悠くんに事情を話した。
「……嫌な予感がする」
翼くんは眉をひそめた。
「まず、父さんの頼みってのがあり得ない。野球部でのもめ事は当人たちで解決すればいいものを、よりによってめぐちゃんを頼るなんて」
「うーん……。だけど永江さんを救えるのはわたししかいない、って言われたら一肌脱ぐしかないよね」
「脱ぐぅ……!?」
二人の時間を邪魔されて苛立っている翼くんはますます憤慨した。そんな彼をなだめるように悠くんが一つの案を提示する。
「めぐ。仕事の一環としてその人の相手をするのはいいだろう。だけど、ちょっとでも問題があったらおれに連絡すると約束してくれ。おれなら、平日だろうがいつだろうがすぐに迎えに行ける。……な? 翼の気持ちも分かってやってくれ」
二人からこうも心配されたのでは仕方がない。
「……わかった。万が一の時は必ず連絡して仕事を上がらせてもらうよ」
◇◇◇
永江さんと会う日はすぐに決まった。本人の意志、というよりは周囲が強引に推し進めたようだったが、飲み会の日から一週間と経たないうちにそれは実現した。
「……やぁ」
長年の友人だという詩乃さんに連れられてやってきた永江さんは緊張している様子だった。白のワイシャツに水色のジャケットを羽織った彼は、他のお客さんを気にしつつも、理人さんと対面する形でカウンター席に座った。詩乃さんは座らずに少し離れたところから彼を見守っている。
彼はまず、手持ちの袋をカウンターに置いた。
「大津クン、例のユニフォームだ。売るなり飾るなり、好きに扱ってくれて構わない」
「あざぁっす! ……ほら、めぐっち受け取って」
「え、わたしが?」
目の前の理人さんが受け取ればいいのに、と思っていたら小突かれる。
「今日は、永江センパイの相手はめぐっちに任せることにしてるの。だから、よろしく!」
少し背中を押され、カウンター越しに永江さんの前に立たされる。
(なんか、様子がおかしい。聞いてた話と違うんだけど……!)
喧嘩の仲裁役を任されたのだと勝手に思い込んでいたが、どうやら別の理由から呼ばれたらしいと分かる。
仕方なく、ユニフォームの入った袋に手を伸ばす。そのとき、ほんのちょっと指が触れた。永江さんはそれだけで驚いたように手を引っ込め、うつむいてしまった。
その様子を見て、さすがにピンときた。
「永江さん、もしかして今日はわたしに会いに……?」
思ったことをそのまま口にすると、彼は否定しようとして失敗し、口ごもった。一歩下がった理人さんが口元を抑えて笑いを堪えている。詩乃さんも呆れた様子で見ている。その詩乃さんを振り返りながら永江さんは立ち上がる。
「……野球以外に何を話せばいいと言うんだ? 僕にそんな引き出しがある訳ないじゃないか……! やはりこれ以上は間が持たない。帰ろう」
「ダメです! みんなに頼まれてるんですから。今日はひと言でも二言でも彼女と話して帰ってもらいます。……めぐさん、大丈夫よね?」
詩乃さんが「お願い!」というように顔の前で手を合わせる。
「もちろんですよ! えぇと……長くなりそうだから、窓際の二人席に行きましょう。そこでコーヒーでも飲みながらゆっくりお話ししませんか?」
わたしが提案すると、永江さんは「……で、出来れば食事を。慌てていたもので、朝食を取り損ねてしまって」と呟き、やはり恥ずかしそうにうつむいた。
*
ワライバで提供する料理は日によってバラバラだからメニュー表がない。ドリンクだけのお客さんが大多数であることに加え、理人さんと隼人さんが気まぐれだから料理を提供できない日もある。
幸い今日は、前日に隼人さんが買ってきてくれた食材が冷蔵庫内にあった。出されたものは何でも食べると言うので、冷蔵庫にある材料を使い、覚えたての生姜焼きを作る。すりおろし生姜をたっぷり利かせ、千切りキャベツもたっぷり添える。ご飯も山盛りサービスだ。
「お待たせしました。生姜焼き定食です。……味噌汁の具は余り物で申し訳ないですが、お口に合うと嬉しいです」
お盆を置くと、永江さんは出されたそれをじいっと見つめたまま動かなくなった。あまりにも長いことそうしているので心配になる。
「……あのぉ、お気に召しませんでしたか?」
「いや、逆だよ……。僕が一番好きな料理なんだ。それが出てきたもんだから驚いてしまって……。とてもおいしそうだ。いただきます……」
彼は丁寧に手を合わせ、真っ先に生姜焼きに箸をつけた。人の食事をまじまじと見るものではないと思いつつ、自然とこぼれたであろう笑みを見てほっとする。
彼は無言で食べ続け、気づけばあっという間に平らげてしまった。箸を置いたその顔は満足そうだった。
「ごちそうさまでした……」
再び手を合わせたのを見届けたところで、お盆を片付けようと立ち上がる。と、背後から理人さんがやってきて「今日はおれが片付けるから」と言うなりさっとお盆を持って行ってしまった。
仕事を一つ奪われた格好のわたしは、そのまま腰を下ろすしかなかった。
向かい合って座っているが、永江さんは目を合わせようとしない。困ったわたしは周囲を見回す。と、詩乃さんがカウンター席でのんびりコーヒーを飲みながら洗い物をする理人さんと談笑しているのが見えた。本当に永江さんのことはわたしに丸投げするつもりのようだ。
(全権を委ねられてもなぁ……)
父親ほども年の離れたおじさまの相手は比較的慣れている方だと思う。とはいえ、こうも黙りこくられては、こっちも困ってしまう。
しかし任されたからには、そして引き受けたからにはなんとかしなければ、と気合いを入れ直し、まずは料理の感想を聞くことにする。
「あの……。さっき生姜焼きがお好きだっておっしゃいましたが、何か特別な思い出が?」
「ああ、母がね、得意な料理だったんだ……。子どものときは生姜を避けながら食べていたけど、今では辛いくらいたっぷり利いてないとダメでね。……さっきいただいた生姜焼きはまさにその味だった……。懐かしかった……」
「お母さんのこと、お好きだったんですね?」
「……仲違いしていた時期もあったけれどね。仲間が、当時の監督が、僕を支え信頼してくれたおかげで母とは再び話せるようになって、それ以後はまぁ……どこにでもいる親子として一緒に暮らしていたよ。……僕が母を好きだったと言うより、母が僕を溺愛していた、と言った方が正しいだろうな。僕は母のすべてだった。母は最後の最後まで僕を気遣い、僕の名を呼びながら死んでいった」
「……もう一度会いたい?」
「……いや、たぶん、今もここにいる。僕には見えないけれど、分かるんだ。最後まで気にしていたからね。自分が死んだあと、僕が一人きりになってしまうことを。コウにもいい人がいればって……それがずっと口癖だった。……まるでその『いい人』が僕の世話をしてくれるみたいな言い方が嫌だった」
「それでずっと独身を貫いた、って訳ですか」
「まぁ、それは理由の一つで、僕が野球を愛しすぎたことが独り身でここまできてしまった原因だと自覚しているよ。僕を知る誰もが知っていることだ」
永江さんは一度もわたしの目を見ないまま語り、窓の外に視線を向けて、ふぅ……と息を吐いた。

ここに来る他のお客さんと同じだった。だから、分かってしまった。その目が自分だけを見つめてくれる眼差しを、寂しさを埋めてくれる誰かを探している、って。
「永江さん」
わたしは名前を呼び、思いきってテーブルの上に置かれていた手を握った。
予想通り、驚いた彼はこちらを向いた。一瞬、目が合う。わたしはそのタイミングで顔をのぞき込んだ。
「な、なにか……?」
目を逸らすことすら適わないほどの距離。緊張しているのが伝わってくる。もちろんわたしも緊張している。だけど勇気を出して言う。
「話している人の目を、わたしを見てください。恥ずかしいと思うときほど見てください。でないと、永江さんの本当の気持ちは伝わりませんよ?」
「えっ、だけど……」
彼はどうにかして視線をはずそうとする。思考を巡らせ、永江さんを説得できる言葉はないか、一生懸命に考える。その時、店で流しているテレビに海外の野球中継の様子が映し出された。わたしは「これだ!」と心の中で叫ぶ。
「ずっと野球されてたんですよね? ピッチャーがキャッチャーを見ずにボールを投げますか? キャッチャーがピッチャーを見ずに返球しますか? それとおんなじです」
彼は息を呑んだ。
「言葉というボールを投げ合うなら目を見ろ、と……。そう言いたいのかな?」
「そうです」
「……やはり君は面白い子だな」
僕の負けだ……。彼はようやく結んでいた口元を緩めた。そして正面からわたしの目を見た。
「なぜだろう。君と話していると未来を信じたくなる。明日を生きる活力が湧いてくる。こんな気持ちになったのは初めてかもしれない……。君はいったい何者なんだい……?」
「ごく普通の女の子です。出会った人を笑顔にする才能があること以外は」
とびきりの笑顔を向けると、永江さんは「……参ったな」と言って一度視線を逸らしたが、すぐに向き直った。
「一つだけ教えて欲しい。君の心の支えが何であるかを。僕がこれからも生きていこうとするならば参考になるかもしれない」
「それはもちろん……」
言いかけたとき、店のドアがガタンと開いた。振り向くと、悠くんが怖い顔でこっちを見ている。
「めぐ……。それが今のお前の仕事なのかっ……! この店がそういう場所なら、おれは今すぐオーナーに退職願を突きつけるぞっ!」
「ご、誤解だってば! っていうか、入ってくるなりそう言うってことは、どこかから見てたってこと……?」
「窓の外から丸見えだ、馬鹿っ!」
ずっと見られていたと思ったら急に恥ずかしくなった。しかし永江さんはこんなわたしを見て微笑んでいる。
「なるほど。君の心の支えの一人は彼なんだね?」
その目が悠くんに向けられた。悠くんは相変わらず眉をつり上げている。
「……あなたがニイニイに……野上路教さんにビールをぶっかけられた人ですか」
「いかにも」
「あなたの死を望まない人が近くにいたことに感謝すべきだ。ニイニイの思惑通り、めぐならあなたの、死への願望を取り除くことが出来るとおれも思う」
(ニイニイ……? 死への願望……?)
きっと悠くんは伯父から事の詳細を聞き出したに違いない。そしてやはり、わたしの直感は正しかったのだと分かる。二人の会話は続く。
「……だけど、これだけは言っておく。めぐの優しさに触れて惚れるのは勝手だが、あなたがめぐを振り向かせることは不可能だ。おれたちのように、小さな火を長く燃やし続けることの出来る胆力のない人には絶対に」
「……言葉を返すようだが、君にも僕が彼女を好きになったように見える、と? 馬鹿な。この年で恋をするなどあろうはずが……」
「人を好きになるのに年は関係ない。人はいつでも恋に落ちれる。そして、また会いたいと思える人がいる時ってのは生きる気力も湧いてくる。そういうもんだよ」
「なら、君も……?」
「……経験者だからそう言ってるんだ」
その目は真剣だった。
「そうか。君は今でもめぐさんを……」
永江さんはぽつりと言い、それからにやりと笑った。
「失礼だが、名前を伺っても?」
「鈴宮悠斗。……そっちは?」
「永江孝太郎だ。君とはまた近いうちに話がしたいものだ」
今日はこれで失礼する。永江さんはそう言うと、バッグから財布を取り出して一万円札をわたしに手渡した。
「ごちそうさま。この店も君もますます気に入った。また来るよ。次は一人で。……その時はちゃんと目を見て話すと約束しよう」
「はい。いつでもお待ちしています」
お辞儀をすると、永江さんは詩乃さんにタクシーを呼ぶよう告げた。タクシーを待っていると詩乃さんに耳打ちされる。
「……一緒に救いましょ、野球馬鹿なあの人を。あなたと私ならきっと出来る」
到着したタクシーが二人を乗せて走り出す。わたしは小さくなっていくそれが見えなくなるまでその場に立っていた。
<翼>
帰宅するなり、めぐちゃんからお叱りの言葉を受けた。本当は俺が行くべきだったのは分かってる。だけど私情を理由に仕事を休むわけにもいかず、身体が空いていた彼に頼むほかなかったのだ。
ちょっとばかり萎縮する俺の隣で悠斗が胸を張る。
「お前の予想通りだったけど心配すんな。永江って人にはおれからひと言、言ってやったから」
「予想通りって?」
めぐちゃんは首をかしげた。
「お前はオジさんキラーだからな。男ばかりの飲み会の席に若いお前がいれば、変な気を起こすオジさんのひとりや二人はいるだろうってのが翼の見立てだ」
「えー? 永江さんはそういう人じゃないと思うけど……?」
「……そりゃあ既婚者の余裕ってやつか? それとも単に鈍感なだけか?」
「悠斗。めぐちゃんは小さい頃からちやほやされるのに慣れているから、それが単なる優しさなのか好意なのか区別できない節があるんだ。おかげで俺も、最初は本気で愛してるって気づいてもらえなかったからな。仕方なくプロポーズって言う強硬手段に出たらようやく気づいてもらえたけど」
「あれは、そういうことだったのかよ……」
悠斗は言ってため息をついた。
「めぐ。あの男を助けてやりたい気持ちは分かるが、あまり親身になりすぎないことだ。伴侶がいる以上はな」
「そう言われても……」
「めぐちゃん!」
悠斗の説得も効果がないと分かった俺は苛立った。
「次に会うときは俺も行く。めぐちゃんを信じてないからじゃない。めぐちゃんの夫としてその人のことをよく知っておきたいんだ。来るなって言われてもいく。いいね?」
俺が意地を張るのには訳がある。悠斗が父さんに電話をかけ、教えてもらった情報が確かならば、永江という人物は根っからの野球人でこれまで一度も女性と交際したことがない。そんな人が初めて好意を持った女性がめぐちゃんだと言うことになれば当然、黙っているわけにはいかない。
しかし問題はその人に「めぐちゃんを好きになるな」と言い捨てられないことだ。俺は同意していないが、今回の「計画」の主目的は永江という人物が生きる希望を持てるようにすること。そのためにめぐちゃんへの恋愛感情を利用すると聞いている。
人を好きになる……。それは電気ショックみたいなもので、自分ではどうにも出来ない感情だってことは分かる。恋する気持ちが生きる原動力になり得ることも理解は出来る。それでも、だ。その人の命を長らえさせるために、よりによっておれの奥さんである彼女を利用するのは納得できないのだ。
これまでの常識観で語るなら、既婚女性を好きになるなどあり得ないと言い迫ることもできよう。しかし、いとこ関係にあたる俺と、三十歳も年上の悠斗とがめぐちゃんと恋愛してきた過去がある以上、その手は使いにくい。
先日の「野球部OB飲み会」に出勤させなければよかった、と後悔する。その人に会わなければこんなことにはならなかったはず……。
いろいろと考え込んでいたら、いつの間にか悠斗に顔を覗かれていた。
「お前、鏡見てみ? めっちゃ怖い顔してるぜ? おれにだってそんな表情見せたことないんじゃないか? よほどあの男が気に入らないんだな」
「そりゃあそうさ……」
迎えに行ったあの日、永江という人はめぐちゃんと熱心におしゃべりしていた。その時の嬉しそうな顔は今でもはっきり覚えている。その時すでに嫌な予感はしていた。それが当たっていたのだから、こういう顔にもなる。
「おれも行こうか。こっちもつい感情的になって余計なこと言った気ぃするし」
悠斗が頬をポリポリかきながら言った。
「気持ちは有り難いけど、次回は俺だけでいいよ。悠斗が来ちゃったら夫としての立場がなくなりそうで……」
「それもそうだな……。でも、何かあればおれもすぐに参戦するから。……なんつーか、あの人を見てたら昔のおれを思い出してな。放っておけないのも事実なんだ」
「ああ、分かるよ。だけど、それとこれとは別だから」
「おう……」
「っていうか……」
俺たちの話を聞いていためぐちゃんが会話に加わる。
「永江さんって普段はスケジュールがびっしり詰まってるって聞いたよ。だから事情はともあれ、二人が心配するほど頻繁に来るとは思えないんだよねぇ」
「そうだといいんだけど……」
本人の意志だけならば確かにそうだろう。が、この話、どうも本人以外が積極的に動き回っている感じがしてならない。
嫌な予感がする……。俺がそう感じるときは大抵当たる。そして案の定、数日後にその予感は的中することとなる。
◇◇◇
日曜の朝のことだった。めぐちゃんが仕事に出かけ、俺と悠斗、そして祖母の三人でのんびり春の庭を眺めていると、玄関前に一台の車が停まった。

見慣れない外車。それだけで胸がざわつく。そばにいた悠斗もまた落ち着かない様子で外を見ている。
「あら、大きな車ね。二人のお友達が訪ねてきたのかしら?」
祖母だけが暢気なことを言っている。突っかけを履いて庭から出向こうとしたとき車のドアが開く。中から出てきたのは先日「ワライバ」で見かけた、元プロ野球選手の本郷祐輔さんだった。彼は俺と目が合うなり気さくに話しかけてくる。
「あ、どーも。休みのとこ、悪い。ちょっとだけ邪魔するよ」
「あ、はい……」
「車、停めるとこある?」
「あー、バイクを寄せるんで待っててくれますか?」
「オーケー」
本郷さんはそう言うと一旦運転席に引っ込んだ。
実は彼とは、父を介して何度か会ったことがある。野球が好きになれない俺になんとか野球をやらせようとした父が、プロ野球選手に会えばその気になるのでは、と考えて引き合わせたのだった。しかしその気になったのは妹の方で、あいつはその後も頻繁に父を誘っては本郷さんや彼の子どもたちと共に野球をし、親睦を深めてきた経緯がある。
だから彼の訪問は、唐突ではあるがまったくあり得ない話ではなかった。しかし、俺が最後にちゃんと話をしたのはそれこそ小学生の時。先日「ワライバ」で会ったときはひと言たりとも話さなかった。そんな人が一体、何の用があってわざわざうちまで……?
悠斗にも声を掛け、二人してバイクを庭側へ寄せる。その最中に耳打ちされる。
「知り合い……?」
「んー、正確に言えば、父さんの知り合いの知り合い、かな」
「ってーことは……この前の会合がらみだな?」
「たぶん……」
外車が駐車場にきっちり収まると、車から降りてきた本郷さんは辺りをキョロキョロと見回した。
「路教は? 来てないの?」
「えっ、父と会う話になってるんですか? っていうか、父と会うなら家が違いますけど」
「家はここであってる。あいつの指示が間違ってなけりゃ。聞いてない?」
「ええ……」
困惑しているところへタイミングよく父が走ってきた。父は予定通りとばかりに手を挙げ、本郷さんとグータッチを交わした。
「ちゃんと連れてきたからな! ……っていうか、息子とはいえ、所帯持ってる人んちに上がるんだから連絡くらいしとけよ。訪ねてきていなかったらどうするつもりだったんだよ?」
「日曜は母さんが家にいる日だから出かけないことは分かってる。それに、下手に連絡して逃げられる方が面倒だったからな」
「……相変わらず、息子と不仲なのか? そんなんで大丈夫かよ?」
「大丈夫、大丈夫。今日一番会わせたいのはユウユウだから」
二人のやりとりを聞いてようやく理解する。直後、車の後部座席のドアが開き、長身の男性が降りてきた。
「永江孝太郎……」
悠斗が睨み付けながらその名を呟いた。
「……心配せずとも長居するつもりはない。僕は彼らの言う通りにここまで来ただけだ。あとは君たちと話せば任務完了。午後からは自分の仕事に戻るつもりだ」
「……めぐに会いたいなら生憎様だな。今日は仕事に行ってるぜ」
「……それも承知の上だ」
「まぁ、立ち話もなんだから、とりあえず家の中に……。おい、翼」
二人が火花を散らしていると、横から父に小突かれた。ただでさえ突然の訪問でイライラしているというのに、父から指図されて余計に腹が立つ。
「……家には上げたくない。どうしてもって言うなら、そこの縁側にしてもらう」
正直に告げる。父はあからさまに嫌そうな顔をし、何かを言いかけたが、永江さんに制される。
「僕が長居をしないと言ったんだ、庭先で充分だ。野上クンは中にいる母親が気がかりなのかな? それなら、僕のことは気にせずそばにいてやればいい」
「いや、そうじゃなくて……。先輩は仮にも元プロ野球選手なんですよ? そんな大物の話す場所が庭先……」
「悪いけど、我が家の人間は過去の肩書きなんて……過去に何をしてきたかなんて重要視しないから」
父の言葉を遮って言い放つと、永江さんが「面白い」と呟いた。
「どうやら彼らは、僕らにはない感覚を持っているようだ。野上クンが言ったように、彼らと話せば何かを得られるかもしれない……」
「えっ……?」
「言い争っている時間が惜しい。早速本題に入ろう」
永江さんはそう言って庭に足を踏み入れた。
*
二人とも「いらない」と言ったのに、結局父が飲み物を出した。これが野球部の上下関係ってやつか、などと勝手な想像したあとで、もしかしたらこのお茶は先日聞いたような――父が永江さんの言動を改めさせるため顔にビールをぶっかけたような――使い方をするために用意したものかもしれない、とも思う。
永江さんは縁側に腰掛け、黙ったまま庭を眺めている。彼を挟むように座った俺と悠斗はその彼を凝視する。
「……退屈しないのかい、こんな暮らしをしていて」
沈黙に耐えかねたかのように彼がまず口を開いた。
「しませんね。むしろ、こういう暮らし方をしていないと長生き出来ませんから」
悠斗がハキハキと答えた。永江さんはつまらなそうに言う。
「……長生きすることに何の意味がある? 人生で成すべき事を成し遂げたなら、それ以上生きていても時を空費するだけじゃないのか?」
「空費……。その発想は危険ですね。確かにあなたの人生はあなたのものでしょう。でも、あなたと関わり合った人の中には必ずあなたの影響を受けた人がいるはずです。あなたが自ら世を去れば、その人たちの心に穴が開く。……そんなふうに考えたこと、ありますか?」
「ない」
「じゃあ具体的な例を……。これは万に一つあってはならない例だけど、あなたの気に入りのめぐが何らかの理由でこの世からいなくなったらどんな気持ちになるか、想像してみて下さいよ」
「悠斗……! なんで、よりによってめぐちゃんなんだよ……!」
「だから、万に一つあってはならない例だって言ったろう……!」
この人のためだ。念を押されたら黙るしかない。
永江さんは長いこと考えているようだった。その間に本郷さんがようやくお茶に手を伸ばす。湯飲みがお盆に戻されたとき、永江さんが口を開く。
「……それは父を亡くしたときに感じた苦しみと同じだろうか。あのとき僕は、僕の知るどの言葉を持ってしても表現することの出来ない感情を抱いたんだ。喪失感。虚無感。しいて挙げるとすればそのような感情を」
「あなたがそう思うならきっとそうです。その時感じた苦しみを、あなたの仲間にも味わわせるつもりですか?」
「…………」
彼はぼんやりと空を見上げた。亡くなったお父さんに思いを馳せているのか、あるいはめぐちゃんのことを想っているのだろうか……。
静かな時間が過ぎていく。俺にとっては穏やかで気持ちのいい春の午前。いるだけで幸せなのだが、隣に座っているこの人は何も感じていないように見えた。俺はあえて尋ねてみる。
「永江さんはこの庭を見てどう思います?」
「……よく手入れの行き届いた庭だ、と思う」
「……それだけ? じゃあ、ずっとここに座ってて感じることは?」
「特にない」
予想通りだった。悲しくなってため息をつく。
「……ですよね。開口一番、ここでの暮らしは退屈しないのかって聞いたくらいですもんね」
「……何が言いたいんだい?」
突き放すような、無感情な物言いにイラッとした。思わず舌打ちし、それを皮切りに抑えていたものが噴き出す。
「これだけは言っておく。あんたが無価値に思うものほど大切にすべきだ。例えばこの庭に咲いている草花や木々。やってくる蝶や鳥たち。それから……目には見えないけど俺たちを見守ってくれてる神々や亡き人のことを。……そういう、日常に彩りを添えてくれるものをすべて自分の世界から排除するから、目標を失ったあんたは生きることがつまらないんだよ」
「……分からないな」
「分かるはずがないと思う。こう言うのって、日々感覚を研ぎ澄ましてないと感じられないからな」
「…………」
「……って、偉そうなこと言ったけど、俺だってこういうことは悠斗に教えてもらったんだ。だから、もし人としての感性を取り戻したいって思うなら悠斗を頼りな。こう見えてすっごく頼りになる」
「こう見えてってのは余計だろうが」
悠斗がすかさずツッコんだ。
「そう? じゃあ年の割に」
「それも違う!」
「じゃあなんて言って欲しいのさ?」
「……もういい」
悠斗は呆れたように天を仰いだ。
俺たちのやりとりを見ても永江さんは能面のように無表情だった。はじめは笑っていた本郷さんと父だが、微動だにしない永江さんを見て真顔になった。
「……あんたは笑い方も忘れちゃったの? それともめぐちゃんの前でしか笑わないって決めてるの?」
「…………」
ついに黙り込んだ彼を見てこれは重症だと思った。父がこの顔にビールをぶっかけたくなった気持ちも今なら分かる。
救いようがない……。そう思う一方で、完全に見捨てることが出来ないのはこの男にかつての自分と重なる部分があるからだろう。
いつしか俺の苛立ちはピークを過ぎ、次第に憐れみの情へと変化していった。
俺は悠斗と初めて交わした「あの言葉」や、その後一気に親しくなるきっかけとなった「あの出来事」に思いを馳せた。
(この人を救う方法があるとすれば、これしかない……)
悠斗を見る。すると「たぶん、お前と同じことを考えてると思う」と返された。
「だよな」
俺は力強くうなずいて立ち上がった。悠斗も立ち上がって言う。
「……もうこんな強硬手段に打って出ることはないと思ってたんだが、しゃーない。……ニイニイ、おれたちを頼ったんならおれたちのやり方を通させてもらいますよ」
「おれたちのやり方……?」
眉をひそめる父を余所に悠斗は永江さんの前に立った。そして冷たく言い放つ。
「……おれと翼とであなたを殺す。真にあなたを救う方法はこれしかない」
「なっ……! 何を……!」
父と本郷さんは慌てふためいた。しかし当の永江さんは表情を変えない。
「どうやら君たちは物わかりがいいようだ。そう。死を望む僕を生かそうとすること自体が間違っているんだ。二人の愛するめぐさんを好きになったかもしれない男を抹消する。実に理に適っている」
彼はそう言い、俺たちと目線を合わせた。
「僕は逃げない。殺すと言うなら今すぐ楽にしてくれ。さぁ、早く……!」
「……だってよ、悠斗」
「ああ……。それじゃ、やっちまうか」
俺たちは目配せし、それから二人して永江さんの腕をとった。
「強制連行! このまま銭湯に直行するっ!」
*
先日リニューアルオープンしたばかりの銭湯。そこは言わずもがな、悠斗と初めて裸の付き合いをした場所だ。
抵抗されるかと思ったが永江さんは大人しくついてきた。それも、心配する父と本郷さんの付き添いを拒んでまで。詳細は不明だが、ほぼ初対面の人間の面前で裸にさせられることは死に値すると考えたからかもしれない。仮にそうだとしたらこの人、どんだけ自分を追い詰めるのが好きなんだ、って話だけど。
新しくなった温泉施設の売りは露天風呂。ヒノキの香りを楽しみながら浸かっていると心身共にリラックス出来る。俺と悠斗は他の風呂には目もくれず、ヒノキ風呂に入ったり出たりを繰り返す。
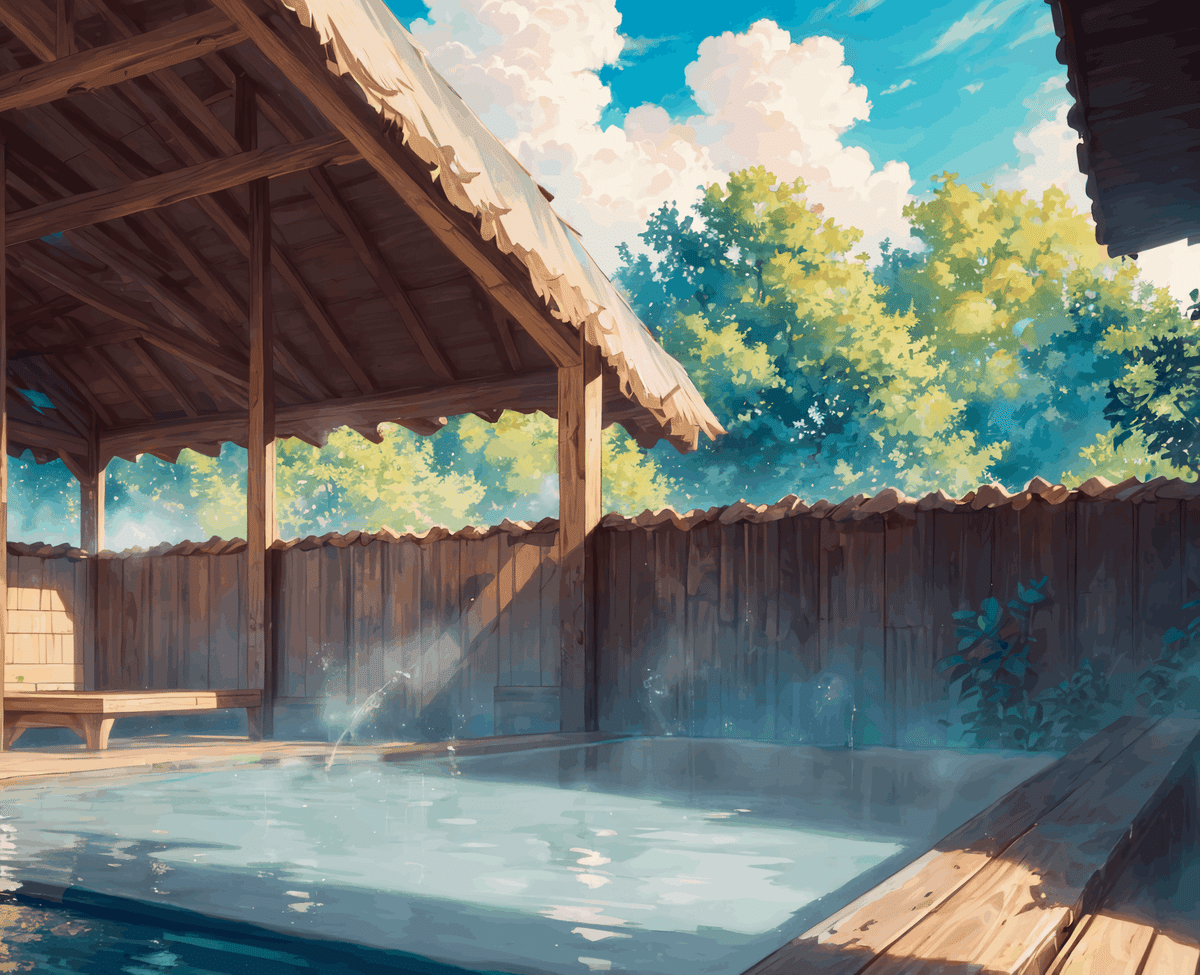
「……熱い湯に我慢して入るのが好きなの? 顔が真っ赤だけど?」
肩まで浸かったまま十分くらい微動だにしない永江さん。さすがに心配になって声を掛ける。
「……ほら。こうやってヒノキ風呂の縁に肘を掛けてさ、青い空を眺めてごらんよ。腰掛けたっていい。ほてった身体をなぜる風が気持ちいいぜ?」
しかし彼は俺ではなく、湯の中に目を向けた。
「……僕の心配より、何度も潜水している彼を気遣った方がいいんじゃないのかい?」
「ああ、前世が魚の悠斗は特別。熱かろうが冷たかろうが、水中にいるのが好きらしい」
「……なるほど。僕が野球で出来ているのと同じということか」
「……まぁ、似たようなもんかな」
直後、ザバーッと音を立てながら悠斗が顔を出した。こっちも真っ赤だ。しかし彼は満足そうに風呂の縁に腰掛け、全身に風を感じるように両腕を広げると「ふぅー、きっもちぃー!」と言った。
「……面白いな、君たちは」
ここでようやく永江さんが口元を緩めた。
「……聞かせてくれないか。二人が誰のために生きているのかを。なぜそんなにも活き活きとしていられるのか興味が湧いた」
「誰のためってそりゃあ……なぁ?」
「ああ。自分のためですよ」
予想と違う答えだったのだろう。躊躇うことなく答える俺たちを見た彼は目を丸くする。
「それならば僕だって同じだ。僕は僕自身のために生きている。しかし……僕と君たちとでは何かが違う。僕はその違いが知りたいんだ」
「寄りかかれる家族がいる。それが俺たちとあんたとの違いだろうな」
俺の言葉に悠斗はうなずく。
「おれたちは互いの弱さを知っています。それは克服すべきものじゃない。それが人間らしさであり、人として不可欠なものなんですよ。おれたちの家族は全員がそれを受容している。だから、おれも翼も家族の前では安心して素の自分をさらけ出させる。偽りのない自分でいられる。おれたちが活き活きしてるように見えるとしたら、理由はそこにあると思いますよ」
「家族……」
「一つ教えましょう。おれは翼と一つ屋根の下で暮らすことが決まった日の晩、ここに……風呂に誘いました。内に抱えていた秘密を教えてくれた翼と打ち解けたいって思ったからです。……もし、あなたを誘ったのも同じ理由だと言ったらどう思いますか?」
「……同じ理由? どういう意味だ……?」
表情を曇らせた永江さんの目が、早く答えを教えてくれと訴えていた。悠斗は一度空を仰ぎ、それからゆっくりと、焦らしながら答える。
「そうですね……。可能であれば引っ越しをおすすめします。今お一人で暮らしているならあなたの一存で決められますよね? 引っ越し先はまぁ、この辺りですかね……。正直、都内よりも遙かに安く住めるだろうし、空気もいいし、それにー……」
「早く結論を言ってくれ!」
「結論、ですか……」
悠斗は急かされてもなお、自分のペースを崩さない。そればかりか、俺に続きを言うよう促した。仕方なく彼の想いを引き継ぐ格好で「結論」を言う。
「要するに、だ。少なくともしばらくの間は俺たちの近くで暮らせって話さ。あんたに必要なのはあんたのすべてを理解してくれる人だ。そしてそれが出来るのは、元チームメイトじゃなくて俺たち。……さすがに一緒に暮らそうとは言えないけどさ、飯だけならいつでも食べに来いよ。幸いにして俺たち全員、料理はそれなりの腕前でね。事前に言っといてくれりゃ、あんたの好きなものくらいは振る舞ってやるよ」
「……どうして、そこまでしてくれるんだ……?」
「さぁ……。どうしてかなぁ……?」
うまく言語化できそうもない俺は悠斗に助けを求めた。彼はちょっと悩むフリをしてから答える。
「何者でもない、ただの永江孝太郎って人がどんなふうに笑うのか見てみたいんですよ。生きる意味を失ったと言ったあなたがこの先、どんな生き方を選択するか見てみたいんです。あなたならきっと出来る。だって……ホント、さっきから笑いそうなんだけど、そんな『ゆでだこ』みたいな顔になるまで湯船に浸かっていられる我慢強さがあれば、人生リセットしてここから生き直すのなんて楽勝だろうから……」
言い切った悠斗はついに笑い出した。目が合い、俺もつられて笑う。
「……失礼な人たちだ。風呂に入りに来たんだろう? だったら出たり入ったりせず、肩までゆっくり浸かるべきじゃないのかい?」
「んなこと言ってたら、一生上がれないっしょ!」
思わずツッコむと「それもそうだな……」と呟き、ようやく立ち上がった。
「……確かに、風が気持ちいいな。……いま、思い出したよ。自然に身を置いたときの心地よさを。この地の風の匂いを」
永江さんは深呼吸をした。
「戻ろう、君たちの家に。残してきた二人に伝えなきゃいけない用向きが出来た」
*
「は……? 今住んでるマンションを引き払ってこの辺りに引っ越す……? 一体どういう心境の変化っすか?」
「彼らに興味が湧いてね。腰を据えて話したいと思ったんだ。ああ、それから夜の解説の仕事も減らそうと思う。空いたその時間を彼らと過ごす時間に充てたいんだ」
「そりゃあ、好きにしたらいいとは思うんですけど……」
話を聞いた本郷さんは、ぽかんとしたまま俺たちに視線を移した。
「おれと詩乃が二十数年かけても変えられなかったのに、ほんの一時間少々でこの人の考えを変えちゃうなんて……。一体どんなマジック使ったの?」
「特別なことは何も。ただ一緒に風呂に浸かって雑談してただけ。……ですよね、永江さん?」
俺の問いかけに彼は深くうなずいた。そして、そばにいた父をまっすぐに見つめる。
「野上クンは恵まれているな。こんなに面白い家族がいて。君の言ったとおり、彼らの考えに触れた僕は今、この先を生きることを考え始めているよ……」
「先輩……」
「近所に移り住んだ際にはまた杯を交わそう。次に君から注いでもらう酒はこぼさずに飲むつもりだ」
「なんか根に持たれてるような……。まぁ、でも、そういうことならいつでも誘ってください。おれ、待ってますから」
二人は固い握手を交わした。
永江さんが車に乗り込むと、本郷さんは「やれやれ」と言いながら運転席に座り、エンジンをかけた。後部座席の窓が開く。
「また会おう。翼クン、悠斗クン」
「えっ」
唐突に名前で呼ばれた俺たちは顔を見合わせた。すぐあとで車内の永江さんに視線を移す。が、車はすでに走り去っていた。
四 新しい命
<悠斗>
また夏がやってきた。めぐの二十歳の誕生日祝いにバーで飲んでからもう一年が経とうとしている。店主は代わってしまったが、今年も「バー・三日月」で誕生日を祝おうと計画していた矢先、めぐから再び妊娠したとの知らせを受けた。
それなりの期間、流産のショックを引きずっていためぐだが、翼の支えもあってか、ちゃんと立ち直ることが出来たようだ。
前回の妊娠では「赤子は愛菜の生まれ変わりだ」と信じ、その誕生を切望していた。だがそのことがめぐにプレッシャーを与え、流産しやすい身体状態にしてしまった可能性も否定は出来なかった。反省したおれは、今回は「めぐと翼の子」という、ごく当たり前の意識を持つよう心がけている。そのせいか、そわそわしたり、日がな一日めぐのことを考えたりはしない。めぐが母親になっていく様子を、普段通りの生活をしながら見守るだけだ。
めぐもめぐで、今回こそは赤子と対面したいと願い、身体優先の生活を心がけている。仕事の日数や勤務時間を減らし、オバアから身体を冷やさないコツや体操を教わっては毎日実践しているようだ。
◇◇◇
そんな我が家に最近、あの人が頻繁に出入りするようになった。言わずもがな、永江孝太郎氏である。
彼はひと月ほど前、本当に都内からこの街の一等地に建つマンションの一室に移った。車の運転免許を持たない彼はロードバイクでやってくる。一週間から十日に一回、何の連絡も無しに、だ。
この日も夕食を終えた頃にふらりと現れた。料理は残っていないと言っても「構わないよ」と返事をし、「少し話せるかな?」と玄関に足を踏み入れる。
「やぁ、めぐさん。こんばんは。お腹の赤ちゃんは元気に育っているかい?」
「はい。順調みたいです。っていっても、つわりがあんまりないから実感はないんですけどね」
「しかし、君の胎内には確かに命が宿っているんだろう? 赤ちゃんのためにも君には元気でいてもらいたいものだ。……もし食欲が減衰していないならこれを。僕の気持ちと思って受け取って欲しい」
永江氏は手に持っていた紙袋をめぐに渡した。中には枝付きのメロンが入っていた。
「わぁ! おいしそうー! ありがとうございます! あ、そうだ。翼くんお手製のフルーツポンチが食べたい! メロンを器にしたやつ。わたし、あれ好きなんだよねぇ」
「オーケー。めぐちゃんのためなら、いくらでも作るよ」
翼はめぐに顔を寄せて微笑み、キスをした。永江氏の前でも翼は遠慮などしない。むしろ、これが我が家の作法とばかりに見せつけてさえいるようだった。
ちらりと盗み見た永江氏は無表情で二人を見ていた。こんなとき、どんな顔をすればいいか分からない様子だった。さすがに、端から見ていて可哀想になる。
「あの……。ちょっと外に出ませんか? イチャつくこいつらのことは放っておいて」
「……ああ、付き合おう」
彼は二つ返事で了承した。
*
家を出ると、どこからか火薬のにおいがした。ちょっと歩くと家の前で花火に興じる親子の姿を見つけた。
めぐが無事に出産し、その子が少し大きくなったらおれもあんなふうに花火がしたい、と思う。結局、愛菜とは一度もすることが出来なかったせいか、こんな光景を見ると胸が痛む。
永江氏はしかし、親子には目もくれず、黙ったまま歩く方向を見つめている。無言なのも適当に歩くのもどうかと思って提案してみる。
「腹が減ってたら、どこかに食いに行きます? まだ開いてる店、知ってますけど」
「お気遣いなく。長年プロ野球選手として夜に仕事をしていたから、一般の人の夕食時には空腹を感じないんだ」
「あー……」
会話が途切れる。それなりにおしゃべりだという自覚があるおれでも、こういう空気感を放つ人との会話は苦手だ。
(どうしたもんかな……)
空を見上げる。そこには夏の大三角があった。さすがにこんな街中じゃ天の川は見えないが、こと座のベガとわし座のアルタイルの間には無数の星々があるのだと思うと宇宙の広大さや神秘を感じずにはいられない。
おれの行動を不審に思ったのか、声をかけられる。
「……何を見ている?」
「夜空を……星々を見ています」
「なぜそんなことを? 昔の旅人のように方角が知りたいわけでもあるまい?」
「ただ美しいから見ています」
「ただ美しいから……」
永江氏はおれの言葉を反復し、立ち止まって空を見上げた。
そこはちょうど公園脇で開けていた。星を遮るものは限りなく少なく、月影もない。LEDの外灯が煌々としているのは残念だが、それにも負けず大三角を形成する三つの一等星は頭上で力強く輝いている。
「……夜空なんて久しく見上げていなかったな。最後に見たのはそれこそ、小学校の理科で星空観察の宿題が出たときかもしれない」
「そりゃまたずいぶんと昔ですね」
おれが言うと、彼は一つうなずいて当時を思い出すように語り始める。
「あの頃はまだ父も元気で、その宿題も確か一緒にやったと記憶している。……あれは台風が去った日の夜のこと。少し風があったけど、流れる雲間から覗く星々を一生懸命探しては記録したものだ。……なぜだろう。長い間忘れていたはずなのにその時の父の顔が目に浮かんでくるよ」
「記憶は心が動いたときに残る……。きっとその時のあなたは、お父さんと一緒に星空の観察が出来て嬉しかったんだと思います」
「……確かにそうかもしれない」
彼はそう言うと、公園のフェンスに両肘をかけて身体を反らせ、上半身ごと空を仰いだ。
「目が慣れてきたのかな。さっきよりもたくさんの星が見える。まるで……僕が天に降り立ったかのようだ」
「あなたがそう感じるのは生きているからだ、ってことを忘れないでください。死んだら二度と味わえないんですから」
「……君がこういう時間を大事にしている理由が少しだけ分かったような気がする」
「そりゃあよかった」
「……あっ、流れ星」

「えっ」
言われてすぐに見上げたが捉えることが出来なかった。少しばかり悔しい……。
「今って何かの流星群が見える時期だった気がする……。よーし、流れ星を見るまでは帰らねえぞっ!」
「……まるで子どものようだな」
彼は呆れているようだ。
「年甲斐もない行動をして、恥ずかしくないのかい……?」
「おれはいくつになってもやりたいことをやる。馬鹿だと言われてもやる。それがおれらしい生き方だと思ってるんで、何も恥ずかしいとは思いません」
躊躇わずに言ったら笑われた。
「……そういう生き方を選択できる君にますます興味が湧いてきた」
「なら、流れ星を探すのに付き合ってくださいよ。十五分……いや、十分でいいんで!」
「……ここは少し明るい。公園の真ん中へ行こう。その方が見つけやすいはずだ」
彼は「イエス」の代わりにそう言って歩き出した。
*
「おかえりー! じゃーん! 見て見て! おいしそうでしょう! ……って作ってくれたのは翼くんなんだけどねぇ」
帰宅すると、待ってましたとばかりにめぐが玄関先に顔を出した。手には輪切りメロンの器に盛られたフルーツポンチを持っている。
「ちょうどフルーツ缶が家にあってね。作るなら今しかない! ってことで二人の帰りを待ってたの。ね、早く食べよー? 永江さんも上がって上がって!」
「……この短時間で作れるものなのか」
永江氏は翼の料理テクニックに驚いているようだ。
「幼稚園教諭をしているなんてもったいない……」
「あー、それって褒めてるつもり……? 俺は何でも一通り出来ちゃうタイプなだけだよ。子どもの世話はもちろん、料理も出来るしピアノやギターも弾けるんだぜ? ……スポーツはからっきしダメだけどな。ま、俺に出来ないことは悠斗やめぐちゃんが補ってくれるから、俺たちは家族としてうまくやってけるってわけよ」
「そうやって君たちは得意を活かし、支え合っているのか……」
「そーゆーことー」
居間はオバアが寝ていて使えない。手洗いを済ませたおれたちは、ダイニングテーブルを囲んでフルーツポンチを食べることにした。
「うまいな……」
永江氏はメロンを頬張りながら呟いた。翼が即座にツッコむ。
「そりゃ、高級メロンだもん。うまいに決まってらぁ」
「いや、たぶん君たちと一緒だからそう感じるんだ。一人で食べても味気ないに違いない」
彼は食べる手を休めたかと思うと、おれたちを見回した。
「めぐさん、悠斗クン、翼クン……。恥を忍んで頼む。どうか僕のことは名前で……孝太郎と呼んでほしい。君たちともっと親しい関係になりたいんだ」
その顔は真剣だった。そんな彼の言葉を翼が優しく受け止める。
「オーケー、コータローさん。俺も悠斗もめぐちゃんも、あんたのことをもっと知りたいと思ってるよ。だからまたいつでも遊びに来いよな。食材を持ってきてくれればこんなふうに、何かしら食べられる形にすることも出来るし」
「ならば次回は君たちの食事時に顔を出すようにしよう。こっちに越してきてからは尚更、家庭の味が恋しくてね……」
そう言った顔は、初めて会ったときよりずいぶん柔和になっていた。頑なだった心は、おれたちとの交流の中で少しずつだが確実に開かれていると感じる。
いつかこの人を心の底から笑わせてやる。そして、生きててよかったと言わせるんだ。それが、しぶとく生き残ったおれに課せられた使命だと今は思っている。
◇◇◇
翼の勤める園の夏休みが終わり、新学期が始まると聞いてぞっとした。忙しくしているつもりはないのに、いつの間にか夏が終わろうとしていたからだ。
暦の上ではもう秋。しかし照る太陽はいまだ真夏を思わせる。子どもの頃、九月にもなれば涼しさを感じたものだが、この頃は秋らしい空気を感じる日も少なくなってしまった。
「こう……秋を感じるイベントとか、ないもんかなぁ?」
呟きながらポストを覗く。と、綺麗な花柄の往復ハガキが一枚届いていた。めぐ宛てかな、と思って手に取る。が、宛名はおれになっていた。
「同期会のお知らせ……? 城南高校の……?」
卒業アルバムを見ながら作成したのだろうか。わざわざ郵便で知らせるとは今時珍しい。このやり方では、卒業時と同じ家に住んでいる連中の元にしか届かないじゃないか。
一体どんな人間が主催したのかと思って詳細を見てみる。すると驚いたことに企画者は生徒ではなく、数学担当の先生だった。奇しくも自身が初めて赴任した高校で教師生活を終える記念に、初めて受け持った学年の生徒を集めようということらしい。なんとも妙な形ではあるが、どうせ暇だし、たまにはそういった会合に出てみるのも悪くないだろう。
彰博と映璃に同期会のことを話す。やはり二人の元にハガキは届いていなかったが、その日程なら行ってみたいという返事だった。
映璃がおれ宛てのハガキを見ながら言う。
「別に会いたい人がいるわけじゃないけど、こういうのってなぜか行きたくなるんだよね」
「それはエリーが今の人生に満足しているからだよ。もし、いまでも高校生の頃のエリーを引きずっていたら? 恥ずかしくて同級生の前に顔をさらせないでしょ?」
「んー、確かに」
二人の会話を聞いて納得する。いくら暇だからって、話せるネタがない状態で同級生の輪に飛び込むのはあまりにも愚かだ。つまり、ちらっとでも「行ってみようか」と思ったおれもまた自分の生き方に満足しているんだろう。
「だけどおれたち、高三の時はずいぶんやらかしてるから、三人で一緒にいたらそれこそ話題にされるだろうな」
先に好きだったおれと後から好きになった彰博とで映璃を奪い合った。はじめから勝負は決まっていたようなものだが、おれが暴れたせいで学年中の噂になったから、違うクラスだったやつでも話題にすれば「あのことか」と思い出すだろう。
今考えてみても、当時のおれは呆れるほどに水泳馬鹿だったな、と思う。もっと映璃のことを大事にしてやればよかった。そうすりゃ、おれの人生も変わっていたかもしれない……。過ぎたことを悔やんでも仕方がないのは分かっているが、こうして三人で昔話をしていると決まってそういう気持ちになるのだった。
彰博は勝者らしく余裕の笑みを浮かべている。
「あの出来事は今の僕たちの原点だ。何を言われても僕は堂々としているつもりだよ」
「原点、ねぇ……」
「悠だって胸を張っていればいいさ。……あのときの出来事があったから今がある、そうじゃなかった?」
「……ああ、そうだな」
しかし同級生の前でもそう思える自信がなかった。
◇◇◇
九月某日。同期会は市内のホテルの一室で行われた。中に入らずとも入り口の前でうろついている人の多くが同期会の出席者だと分かる。ただ、顔を見てもパッと名前が出てこない。皆、三十数年の人生を重ねてきてすっかり容貌が変わってしまっているせいだ。若作りだったおれでさえ今では年相応。おかげで誰からも声がかからない。それはそれでほんのちょっぴり寂しいと感じてしまうおれである。
*
会が始まると、すぐに主催の先生の挨拶が始まった。こういう場で話すのに慣れているのか、はじめからテンションが高い。しかし少し緊張していた一同は先生のジョークで徐々に笑いはじめ、話が終わる頃にはずいぶん和んでいた。
立食パーティーが始まり、集まった百人以上が一斉に動き出す。会場が笑い声と食器類のぶつかり合う音で満たされる。
「おっ、鈴宮か。生きてたんだな。久しぶりー」
料理を皿に取り分けていると声をかけられた。同じ水泳部だった佐々木だ。その手にはワイングラスが握られており、半分ほど飲んだ形跡があった。
「よぉ。……ずいぶんと肉付きがよくなったな。さては水泳してねえな?」
「んな暇あるかよ。こちとら忙しいサラリーマンやってんだぜ? ……そっちは当時と変わらない体型してんな」
「おかげさまで、水泳やってる暇があるんでね」
「へぇ……。風の噂では、泳げなくなったって……。十数年前には死んだって情報も流れてきてたけど?」
確かにおれは一度水泳をやめ、この街を離れている。が、そのことを知っている人間はほとんどいないはずだ。一体どこから漏れ伝わったのか。人の噂とは恐ろしいものだ。
「……昔のことは忘れたな」
適当にはぐらかす。佐々木は大して興味がなかったのか、それ以上は聞いてこなかった。代わりにもっと前の話を引っ張り出してくる。
「ああ、昔っていえば、高三の時、野上と吉川の取り合いバトルしてたよな。ありゃあホント、見てて面白かったなぁ。鈴宮が負けるところまで含めて。その恋敵の野上と同じ大学に進んだって聞いたときにはびっくりしたけど。なぁ、あのあとも野上とは親しくしてたの? 結局あの二人、どうなった?」
吉川というのは映璃の旧姓だ。予想していたとおりの話題になったので、こっちも用意していた返しをする。
「あのあと? ま、いろいろあったよ」
嘘はつかない、けど真実も告げない。こういうのは曖昧にしておくのが一番だ。
そこへ運悪く話題の二人が現れた。おれが「いろいろ」としか言わなかったからだろう。佐々木は大喜びで二人に話しかける。
「今ちょうど、高三の時の話をしていたところだ。……待てよ? 一緒に現れたってことは二人ってもしかして結婚したの?」
「そうだけど、何か?」
彰博が堂々と答えた。佐々木は一瞬面食らったが、ひるまずに返す。
「へぇ! 野上、やるじゃん。……ベッドに誘うときもチェスを使ったりするわけ?」
「…………! お酒の席でも言っていいことと悪いことがあるわよっ……!」
映璃が顔を真っ赤にして怒りをぶつけた。
「わりいわりい。吉川は相変わらず威勢がいいな……。鈴宮。こいつと別れてよかったかもしれないぜ?」
「……悪いが、こいつらはおれの家族なんだ。そういう言い方はよしてくれ」
「……は?」
ヘラヘラしていた佐々木は目を丸くした。
「聞いて驚きなさい。悠は私たちの娘と一緒に暮らしてるのよ!」
「えーっ!!」
映璃が言い放つと、佐々木は大げさに両手を広げた。
「……ってことは、鈴宮は野上と吉川の子どもと結婚したってこと……? いくつか知らないけど、犯罪だろ、それ……」
思わず舌打ちをする。この男はどうしてこんなふうにしか言えないんだろう。否定するのも面倒くさくなってきた。しかしこのままでは誤った情報をリークされかねない。どうしたものか……。
「佐々木、誤解しているようだから一から説明するよ」
そう言ったのは彰博だった。やつはおれと違って過ちを正すことを嫌がらず、懇切丁寧に事実を伝えた。途中、おれに関するいらぬ情報も漏れ出たが、かえってそれがよかったようだ。すべてを聞き終えた佐々木は、最後にはおれに同情の眼差しを向けた。
「鈴宮も大変な人生を送ってきたんだな。……実はおれも嫁さんに逃げられて今、別居中でさ。家に帰っても一人なんだよ。……なぁ、フリーなんだったらこのあと一緒に女の子、探しに行かねえ? 鈴宮と一緒ならおれにも勝算があるかもしれない」
「やめとく」
即答すると、佐々木はさっと表情を変えた。
「……そういうキャラじゃなかっただろ。もっとこう……軟派な男ってイメージあったのに」
「悪いな……。ナンパがしたけりゃ他を当たってくれ」
「…………」
佐々木は黙り込み、逃げるように群衆の中に消えた。その背中に向かって映璃が毒づく。
「最低なやつ! 昔から思ってたけど。だから奥さんにも逃げられるのよ。悠もそう思うでしょ?」
同意を求められたが、おれは首を横に振る。
「いや……。おれも一歩間違えばあいつと同じ道をたどってたと思うよ」
「悠……!」
「確かに佐々木はどうしようもない野郎だ。だけどおれだって、ああなってた可能性があると思ったらそこまで悪くは言えないよ。……実はおれ、あの頃の自分が結構好きだったんだ。今よりずっと陽気で垢抜けていた頃の自分が。だから時々考えちまう。もし、あの頃のおれで居続けてたらどうなってたのかなって。もちろんやり直すことなんて出来ないし、戻りたいわけでもないんだけど」
「…………」
「大事なのは、自分の打った『この一手』が最善だったと信じられるかどうかだと僕は思うよ」
彰博が静かに告げた。
「人は惑う生き物だ。だけど、悩み、苦しみ、考え抜いて決めた一手はいつだってそのときの最善だ。……失ったものや切り捨てたものを取り戻したい気持ちは分かる。だけど今の君は、それらを失ったからこそ最高に輝いているってことを忘れないでほしいな」
それを聞いて、やはり彼と映璃を奪い合わなかったら、そしておそらく負けを喫していなければ、今の幸せを手にすることはなかったのだと痛感する。
「よーし。それじゃあ最高に輝いてる今を祝して乾杯といこうぜ。そうだな、今日の目玉はワインっぽいからそれにしよう」
「いいね」
意見が一致し、酒が並ぶテーブルまで移動しようと足を向ける。
「ワインなら私も飲みたーい! 仲間はずれにしないでよー」
映璃が年甲斐もなくかわいらしい声を出してすり寄ってきた。
「わかったわかった、一緒に行こうぜ」
映璃の肩を抱く。そのとき、正面から数人の女が押し寄せてきた。彼女らはおれたちを見るなりキャーキャー騒ぎ始める。
「あ、鈴宮君、みっけ! あれ? 吉川さん、肩なんか抱かれちゃってぇ、ああ、羨ましいー」
明らかにさげすんだ言い方と目つき。おれと映璃が付き合っていた頃から嫉妬心を抱いていた女の発言に違いないと思ったら案の定、散々おれに告白してきた山田のぞみだった。タイプじゃなくて無視し続けたんだけど、結局、卒業間際までつきまとわれた。
山田は刺々しい口調で言う。
「今し方、佐々木君から聞いたよ。鈴宮君、今は吉川さんの娘さんと同居してるんだって? 高三の時、そこにいる野上君に愛する吉川さんを奪われて悔しがってたのは有名な話だけど、まさか三十年経っても思いを断ち切れず、彼女のお尻を追いかけ回してるとはね……。吉川さん、迷惑してない? 女の気持ちをこれっぽっちも理解できないやつなんて、さっさと見限っちゃえばいいのに」
「山田さん……!」
「待て……!」
手を出しかけた映璃を制する。
「なんで止めるの?! 悠、馬鹿にされてるんだよ?!」
「だけど……本当のことだ」
「えっ……」
「だっておれは……」
その時、会場のスピーカーからビンゴ大会のアナウンスが流れた。どこからともなくカードも回ってきて手渡される。そのどさくさに紛れ、三人揃って部屋の隅に移動する。
「……さっきの話の続きだけど、なんて言おうとしたのよ?」
映璃は気になって仕方がない様子でおれに言い迫った。
「何って……。おれが、女の気持ちをこれっぽっちも理解できない男なのは事実だろ? だから映璃だっておれじゃなく彰博を選んだ。違うか?」
「……嘘。悠は別のことを言おうとしてた。私には分かる。ね、アキもそう思うでしょ?」
「そうだね。あまり喜ばしい内容じゃなさそうだけど」
「何だよ、お前ら……。いつからそんなにおれのことに詳しくなったんだ?」
「そりゃあもう……。長い付き合いだからね」
彰博はため息交じりに言って、手元のカードに目を落とした。
「……こういうのはどう? どちらが先にビンゴするか競い合うって言うのは。もし僕が勝ったら、君の秘密を洗いざらいしゃべってもらう」
彰博からこの手の提案をされて勝ったためしがない。だけど、端から勝負しないのはさすがに格好悪い。
「オーケー、その勝負、受けて立つよ。一応確認だけど、逆におれが勝ったときはちゃんと言うことを聞いてくれるんだろうな?」
「もちろん。犯罪行為以外なら何でも」
「ちっ、相変わらず言ってくれる」
気合いを入れるため、飲み損ねていたワインを二杯引っかける。クワッとしてきたところで最初の数字がアナウンスされる。
「一番目はラッキーセブン! 七番です」
「七、あった」
「私も!」
「…………」
幸先の悪いスタート。むしゃくしゃしたおれは、ワインをもう一杯飲みながらサンドイッチを頬張った。
*
「……まさかこんなにあっさり勝負が決まるとは」
「くそっ……!」
予想通り、惨敗だった。開始からわずか五分の出来事。しかも一番に上がったので、景品は某テーマパークのペアチケットだ。彼はそれを手に、満面の笑みを浮かべながらおれの隣に舞い戻ったのだった。
「ビンゴ、続ける? それとも僕の言うことを聞く?」
「……約束は約束だ。お前の言うとおりにする」
「なら、食事も済んだし、とりあえずここを出ようか。これだけの人がいる中で罰ゲームをさせるのはさすがに心苦しい」
「お前に良心が残ってたことに感謝するよ……」
苦々しい思いを胸に会場を後にする。このあとさらに恥を掻かされることになるのかと思うと気が重い。
駅のロータリーを過ぎると、行きつけのバー『三日月』が見えた。彰博は「ここで飲み直そう」と言って店の中に入っていく。
*
「いらっしゃいませ」
声をかけてきたのは三十歳前後の女性バーテンダー。数人いる店員の中で、先代のマスターから店を任されたのは彼女だった。
彼女が店主になってから女性客が一気に増えた。特に早い時間が人気で、今日も店内はほぼ満席に近い。
マスターがにこやかに話しかけてくる。
「野上様。今日は奥様とご一緒ですか? 鈴宮様と三人でいらっしゃるのは珍しいですね」
「高校の同期会があったもので。まぁ、三人で二次会ってやつです」
「……申し訳ありません。いつものお席はあいにくと空いておりませんで。ご予約頂いていればよかったのですが……」
「三人で座れるならどこでも構いません」
「でしたら、カウンター席へ。ちょうど三席空いてますので」
隣の客に詰めてもらい、映璃を真ん中に、おれが左側、彰博が右側にそれぞれ腰掛ける。
「……あのさぁ、早いとこ済ませてくんねえ? 焦らされるのは好きじゃねえんだ」
「まぁまぁ。まずは一杯ずつ頼んでからにしよう。……エリー、何を飲む? 君が選んだものを僕らも注文しよう」
「ほんと? それじゃあ……」
映璃は少し考えてから「XYZにする」と言った。
「だって、思い出のカクテルだもの」
「いいチョイスだ」
彰博はうなずき、それを三つ頼んだ。
程なくしてカクテルが提供される。二人がグラスを交わす隣でひとり、一気に飲み干す。
「さぁ、約束だ。罰ゲームとやらを受けてやろうじゃないか!」
指を差し、彰博にいい迫る。
「わかった」
彰博はおれの言葉を聞いて酒をあおり、グラスを空にした。映璃はそんなおれたちを黙ってみている。彰博が目を細め、にやりと笑う。
「……君の本音を聞かせてくれないか。エリーのことを本当はどう思っているのか。そして本当はどういう関係でいたいのかを。遠慮はいらない。はっきり言って欲しい」
予想外の言葉に戸惑う。
「……それが、罰ゲームの内容か。……聞いてどうするつもりだ? おれの返事次第では、お前だってただじゃ済まないはずだろう?」
「……僕だって覚悟の上だよ。だけど、このまま年をとっていくのはお互いに気持ちが悪いじゃないか」
彰博はそう言い、二杯目のカクテルを注文すべく手を挙げた。
「ブルーマンデーを」
「おれにも同じものを」
「かしこまりました」
空いたグラスが回収され、次の酒が出てくるまで手持ち無沙汰になる。かと言って、本題を口にするにはもう少し酒の力が必要だ。二人も同じなのだろう、黙ったままカウンターの向こう側を見つめている。
こんなとき黙っていられないのがおれの性分。酒が回り出して口が軽くなったのをいいことに、思いつくまましゃべる。
「……まさか、本気にしてるのか? 山田のぞみが言ってたこと。おれが未だに映璃を好きでいて、あわよくば振り向かせようと家族のフリをしてつきまとってるって……。そりゃあ映璃は年齢より若く見えるし、話してて楽しいし、作る飯もうまいし、優しくしてくれるし、いい女なのは確かだけど……。だいたい、めぐのことが好きで結婚も考えてたおれが、どうして映璃に気があるって話になるんだよ? おれがいつ、映璃を口説いたって? 証拠があるなら提示して欲しいぜ」
そこまで言ったところでカクテルが差し出された。綺麗な青色の液体が逆三角形のグラスに注がれている。おれと彰博は同時にグラスに手を伸ばし、同時に飲み干した。
「……それが君の本心なんだね」
彰博がぽつりと呟いた。慌てて否定する。
「お、おれは決して家族のフリなんか……」
「僕が指摘してるのは、君がエリーを好きでいるってところだよ。……もしかしたらこれは僕の思い込みが過ぎるだけなのかもしれない。だけど、少なくとも君はエリーへの思いを断ち切れてはいない。無意識なんだろうけど、君は彼女の肩を抱くことがあるだろ? それが君なりの家族としての接し方なのだとしても、夫としてはいささか不快でね。それをエリーが拒まないのも問題なんだけど」
「待て待て。だったらまずは映璃を問いただすべきじゃないのか? 妻なんだし」
「エリーの気持ちはすでに聞いている。君への想いは『友だち以上恋人未満イコール家族』だそうだ。だけどそれは一定じゃなく、グラデーションになっているという。つまり、君を受け容れたくなる日もあれば、おしゃべりだけがしたいような日もあるということらしい。……納得できずにかなり詰問した。だけどそれが答えだと押し切られては、それ以上問いようがない。僕はその言葉を信じることにした」
「映璃の態度に余裕があると思ったら、そういうことかよ……」
少しは映璃に罪をなすりつけられると思ったのに、すでに解決済みだと言われてしまったら、矛先は必然的におれに向けられることになる。
完全にお手上げだ。そしてこれは罰ゲームだ。幸か不幸か酒も回っている。
「酔った勢いで言わせたことを後悔するなよ……」
宣言し、一気に告げる。
「ああ、そうだよ。彰博の言う通り、おれは今でも映璃が好きだ。だけど、勘違いしないでくれ。今更若い頃のように愛し合いたいとは微塵も思ってない。めぐへの想いとはまったく違う。これだけは信じてくれ。……そう、映璃が感じているようにおれの情もグラデーションになってる。友情、恋愛、性愛、家族愛、博愛……。その間を行ったり来たり……だ。想いは、気持ちは、線引き出来ない。そうだろう? おれが映璃の肩を抱くのも決して下心からじゃない。なんつーかそうだな……。握手みたいなもんだよ」
「握手……? 肩を抱くのが握手……?」
「わりい。おれ、語彙力ねえんだ」
「知ってる。だけど、あまりにも表現の幅がなさ過ぎる……」
「なら、お前の知ってる言葉で補ってくれ」
「やれやれ……」
さっきまで強面だった彰博は、おれの馬鹿な発言を受けて少しだけ表情を和らげた。
「君はもともと情熱的な男だ。だから想いが行動に表れてしまう、と。そういうことかな?」
「それだよ、それ! な? 映璃」
いい気分のまま抱き寄せる。映璃は嫌がることなくおれに凭れた。
「私、悠に肩を抱かれるの、好きだよ。すごくあったかくて守られてる感じがして……。大事にされてるって思えるの」
「おれも同じだよ。映璃のそばにいると落ち着くし、心がぽかぽかする。それは家族だからじゃなくて、映璃が映璃だからだと思ってる。……高校生の頃のおれはそんなふうに思えなかったから選んでもらえなかったんだろうけど、今のおれなら……」
「そうだね。今の悠は人として、とても魅力的よ。……だけど、ごめんね。悠が言ったように、私も悠を恋愛対象としてみることが出来ないわ。残酷なことを言うようだけど、それはアキに対しても同じ。愛の形が変わってきたって言うのかな……。そう、私たちはもう成熟しきったのよ。そして次のステージに進まなければいけなくなったのよ。
……どんなふうにこの先の人生を歩めばいいのか、私にはまだ見えてこない。だけど私はひとりじゃない。アキがいて、悠がいて、子どもたちがいる。だからきっと立ち止まらずに歩いていける。……もうあの頃のようにいつまでも迷ったりはしないわ」
「ああ、そうだな」
「さすがエリー。語彙の少ない僕らの思いを見事に言語化してくれたね。エリーのそういうところが好きだ。ホント、尊敬するよ」
「えっへん! 留年しかけた二人とは違うのよ!」
映璃は腰に手を当て胸を反らした。
「そういう仕草、かわいくて好きだぜ!」
調子に乗ってぎゅっと抱きしめる。すかさず彰博が怒りを押し殺したような声でマスターに注文する。
「すみません、鈴宮悠斗にジンベースの方のアースクエイクを。一気に潰したいんで」
「潰すって……。おれを殺す気か……?」
「死にたくなかったらエリーから離れてくれる?」
「……だってよ、映璃。どうする?」
「んー……」
映璃はあごに人差し指を当ててじっくり考え始めた。そのうちにカクテルが出来上がり、おれの前に提供される。
「じゃあ、こうしよ?」
何かよからぬことを思いついたのか、映璃がカクテルグラスを持ち上げた。
「……これは私が飲む。これ以上、私を巡って争わないように。……ね?」
言うが早いか、映璃は四十度近いカクテルをぐいっと飲んだ。おれたちのように一気に飲み干すことは出来なかったが、その心意気に胸を打たれたおれたちは顔を見合わせ、反省した。
「……やれやれ、エリーには敵わないよ」
「全くだ。……残りはおれたちで片付けるか」
「そうしよう」
おれを潰すために作らせたカクテルを半分ずつ飲む。半分だって充分酔えるものを飲ませようとした彰博の怒りを思い知る。
「……お前、本当に映璃のことを愛してるんだな」
おれが呟くと、彰博はチェイサーを飲み、ふっと息を吐いた。
「……もちろん愛してるよ。だけど時々不安にもなるんだ。エリーがさっきみたいに、悠に喜んでその身を預けているようなとき、エリーの心は一体どこにあるんだろうって。愛していると口では言っていても、その心はとっくに僕以外の誰かに向けられてるんじゃないかって」
「アキ……」
「エリーの心がその時々で揺れるのは聞いた。悠が魅力的な男だというのも分かってる。中年になった僕らが次のステージに進まなきゃいけないってことも……。僕も模索しなきゃいけないな。これから進んでいく道を。君とのこれからを」
「うん。私も一緒に探すわ。アキとはこれからも同じ景色を見ていたいから。……だけど、その道には他の人もいていいと思う。例えば悠とか。二人より三人の方が楽しいじゃない?」
「……そうだね。きっと、そうだ」
「ありがとな、映璃。二人の人生におれを加えてくれて」
「こっちこそ。好きでいてくれてありがとう。これからもよろしくね」
昔と変わらない顔で微笑みかけられ、嬉しくなってつい頭を撫でる。それを見てムッとした彰博に宣言する。
「映璃とはこれからもこんなふうに関わっていく。これが、罰ゲームの問いに対する答えだ。……おれ、自分は変わっちまったんだと思ってた。今を幸せに生きるためにはそれも仕方がなかったんだって、思い込もうとさえしてた。でも、違った。変わったんじゃなくて、使い分けが出来るようになっただけなんだ、きっと。だからおれは映璃の前では昔と変わらずに甘えるし、映璃にもそうしてもらいたい。そして彰博にはこんなおれたちを……可能であれば受け容れて欲しい」
「……君の想いは確かに聞いたよ。エリーとの関わり方も了解した。ただし、エリーと会うときは必ず僕も同席させてもらう」
「さては、信用してねえな?」
「そうじゃない。……いい雰囲気に見える二人の仲を引き裂く。そして優越感に浸る。それが、二人といるときの僕の新しい関わり方だ」
「…………! ひでえ性格してんな! お前、いつからそういうキャラだよ?!」
「たぶん、君を名前で呼ぶようになってからじゃないかな。あの日以来、僕は君に遠慮しなくなって本当に楽になったんだ。感謝してるよ」
「感謝されても嬉しくねぇし!」
馬鹿な会話をしていたら、映璃に笑われた。
「あっはは! いいね! 昔より楽しいよ! これからはこんな感じでやってきましょ!」
「了解。……ってことで悠、もう一杯、どう?」
「……オーケー、オーケー。ただし、お前のおごりなー」
もうずいぶん酔ってはいるが、この二人とこんなにも腹を割って話せたのだ。こうなったらとことん思いの丈をぶつけようと決める。そんなおれの心中を察したのか、彰博が言う。
「僕の本性を知っても変わらずに付き合ってくれる友人は君だけだ。ありがとう」
「あぁ、まぁ……、お互い様ってやつよ」
深く知ることは深く傷つけ合うことでもある。だがおれたちは今、そこを乗り越えた。新しく切り開いた道の先に何が待っているのかは分からない。それでもおれたち三人は、少なくともしばらくは同じ景色を見ながら歩いて行くと誓った。一人では決して見ることの出来ない世界。それが見られると思うと今からワクワクするのだった。
<めぐ>
最近、両親が妙に仲良しだ。今日も、二人してテーマパークにクリスマスデート中らしい。ママから送られてきたツーショット写真を悠くんに見せると、彼は酷く腹を立てた。
「くそっ……。ちょっと前までおれが映璃といい雰囲気だったのに。やっぱり同期会がきっかけなのか……」
「あー、それ、俺のせいかも。アキ兄から、妻への甘え方を教えてくれって言われてさ。仕草やら口調やらを伝授してあげたんだよ。その後からじゃないかな、あの二人が以前より仲良くなったのは」
「はぁ……? 何だよ、それ……。絶対、映璃のやつが何か言ったな? あいつが急にそんなことを言い出す訳がない」
憤慨する悠くんに恐る恐る質問する。
「えーと……。一応確認なんだけど悠くんは、ママとは『友だち兼家族』……なんだよね?」
「もちろん。映璃だってそう言ってる。だけどな……。いい女ってのは、夫がいても、いくつになっても男を惹きつけるもんなんだよ。……言っとくけど、映璃とはあくまでもプラトニックな関係だから」
「……んー。何だか複雑な気持ちだけど、まだまだわたしの知らないオトナの世界があるってことなのかな」
「はぁ……。これだから恋に生きる男は困る。めぐちゃん、気をつけてよ? エリ姉に気があるようなことを言ってるけど、悠斗の本命は今でもめぐちゃんなんだから」
「分かってるじゃねえか。だったらおれにつけいる隙を与えないよう、お前が男を磨いておくんだな。そうすりゃおれが口説いても、めぐがなびくことはないだろうさ」
「けっ、言ってくれるぜ……。でもま、さすがの悠斗でも、これから生まれてくる赤ちゃんのことが気になってるうちは心配しなくていいだろう」
「まぁな」
そう言うと、悠くんはわたしのお腹に手を置いた。
「女の子だってことは分かってるんだし、もう名前は考えてあるんだろう? そろそろ教えてくれよ。いいだろ?」
「ダメダメ、生まれてからのお楽しみ!」
「ケチケチすんなよ。意地悪だなぁ、めぐは」
そう言いながらも悠くんは穏やかな表情をしている。彼は赤ちゃんの誕生を本当に楽しみにしているようだ。たぶん、わたしよりも熱心に予定日までのカウントダウンをしているんじゃないだろうか。
妊娠二十五週目。もうずいぶん大きくなって、日々胎動も感じている。毎回三人で赤ちゃんの様子を見に行くから、看護師さんたちの間で悠くんは「心配性のお父さん」だと思われているが、出産まではそれで通すことになっている。
居心地がいいのか、赤ちゃんは逆子のまま動く気配がなく、担当の先生には帝王切開での出産になる可能性が高いと言われている。手術かぁ……って思うけど、出産日が決められるので、翼くんは「前もって休みを申請できるならむしろ有り難い」と言う。三月の園は忙しいみたいだけど、我が子との対面の方が大事だからと、何が何でも休みを取るそうだ。
今ではわたしも悠くんも「あの子」のことは口にしない。前回の流産以後、悠くんでさえ一度も「会って」いないと言うし、話題にすればどうしても流産のことを思い出すからだ。
悠くんは尚もお腹に向かって呼びかける。
「ちゃんと無事に出てこいよ。……って、手術になったら安全に出てこれるのか。早く会いたいな」
「……ったく。前回の時もそうだったけど、これじゃあどっちが父親か分かりゃしないぜ」
「今のうちからこのくらいの愛情を注いでおかないと新生児の世話なんて出来ないよ。他人の子だと思ったら、とてもじゃないが一晩だって一緒にはいられないだろうさ。とにかく全力で泣くからな、赤ちゃんってのは」
「泣く子どもに耐性はある方だけど、そんなに大変なの?」
「……まぁ、その時が来てみたら分かる」
悠くんの話を聞いていたら段々心配になってきた。こんなとき、ママに相談できたらいいんだろうけど、ママは新生児のわたしを育てていないから体験談を聞くことが出来ない(養子のわたしがママたちと出会ったのは生後四ヶ月頃だと聞いている)。パパを産み育てた祖母も、新生児の頃の記憶はほとんど残っていないと言うし、身近な先輩ママであるクミさんに至っては「大丈夫、なんとかなる!」としか言わないから参考にならないのだ。
「わたし、ちゃんとお母さんになれるのかなぁ……?」
無事に生まれて欲しいけど、このままお腹にいて欲しい気持ちもある。妊娠中のクミさんが鬱っぽくなってたのも今なら分かる。
「大丈夫さ」
不安げなわたしを見て翼くんが言う。
「なんてったって、この子には父親が二人もいるんだぜ? それだけじゃない。ばあちゃんもいるし、近所には俺たちの両親も住んでる。今時、こんなに手助けしてくれる大人がいるなんて珍しいし、恵まれてると俺は思うよ。だからめぐちゃんは、なーんも心配しなくていいんだよ」
「……だね!」
直前では、どっちが父親か分からないと言っていたのに、ちゃんと「二人の父親」と言い切るのが翼くんらしい。なんだかんだ言って、悠くんのことを「父親」だと認めているし、頼りにしているのだろう。
そのとき、赤ちゃんがお腹の内側を蹴った。私も早く会いたいよって主張しているみたいだった。
◇◇◇
年が明けてしばらくの後、産休に入った。ワライバに産休制度なんてないけれど、オーナーたちが、わたしのお腹がいよいよ大きくなってきたのを見て「出勤停止命令」を出したのだった。確かに、出産予定日まではひと月以上あるのに、自分でも驚くほどお腹が膨れ上がっている。祖母なんて「今日にも生まれそうね」と、このお腹をみるたびに言ってくるほどだ。
さて、仕事が完全に休みになってしまうと案外手持ち無沙汰なことに気づく。赤ちゃんグッズは悠くんが先んじて用意してくれているから、あとは赤ちゃんの誕生を待つだけ、である。
祖母がデイサービスに行っている平日は基本、家には悠くんと二人きり。互いにおしゃべりだから話題があれば長時間話すことも可能ではあるが、さすがに一日中は無理。かと言って、ごろごろしていられる性分でもない。あれこれ考えた末に思いついたのが「お手製弁当を幼稚園まで届ける」というものだった。
これまでもお弁当は時々作ってあげていたが、わたしが仕事の日はどうしてもバタバタしがちで、前日の残り物や手軽に作れるおかずを詰めておしまい、という日も多かった。時間のある今なら少し手の込んだものが作れる。
中途半端な時間にお弁当の支度をしていると悠くんに不思議がられた。わけを話すと、「園に行くんならバイクで送ろうか?」と提案された。しかし妊娠中、それも臨月を迎える頃のお腹で二人乗りはまず無理だろう。
「気持ちは嬉しいけど、電車で行くよ」
自宅から園までは電車を利用しても二、三十分かかるが、妊娠中でも適度な運動は必要だ。それに、歩きながら今まで認知していなかったお店を見つけるのが最近の楽しみだったりする。とにかく、身体を動かしたかった。
「暇だし、おれもついてくよ」
もちろん、病気ではないので付き添いは不要である。しかし悠くんが気遣ってくれているのも充分承知しているので、ここは彼の厚意を有り難く受け容れることにした。
*
クリスマスにプレゼントしてもらった厚手のダウンコートと裏起毛のスラックス、それから発熱するタイプの靴下を穿いて出かける。正直、これだけ着込んで動いたら汗も出てくるのだが、ちょっとでも薄着をしていると怒られるので、この冬はこの格好で乗り切るしかない。
電車で二駅。中心街にあるその駅からバスで十分ほど揺られたところに幼稚園はある。翼くんとはいわゆる、待ち合わせデートをしたことがないので、どこかで落ち合う時の気持ちってこういうものなんだろうな、と思いながらバスの車窓を眺める。
お弁当はおいしく食べてもらえるかな?
どんな顔で受け取ってくれるかな?
明日も楽しみって言ってもらえたら嬉しいな……。
妄想を膨らませていると、あっという間に降りる駅に着いてしまった。バスを降りて二、三分歩くとすぐに園が見えてくる。
水曜日の園は昼で終わりだ。ちょうどお迎えの時間に当たったらしく、周辺は車や迎えに来た親御さんでごった返している。
「あ、めぐちゃん」
悠くんを園外に待たせ、保護者に紛れて園庭をうろうろしていたら、翼くんから声を掛けられた。わたしは一瞬、ここが幼稚園だと言うことも忘れ、浮かれ気分で彼の元に駆け寄った。
「はい、例のお弁当。中身は開けてのお楽しみ」
「わぁ、ありがとう。……これだけのためにわざわざ来てもらっちゃって、やっぱり悪いなぁ。せっかくだし、一緒に食べる? 水曜の今日なら大丈夫だよ」
「あー……。実は、ここまで悠くんと一緒に来てるんだよね。お昼は外で食べる約束で」
「悠斗と一緒なの? ったく、どんだけ心配性なんだか……。まさか、バイクで?」
「ううん。電車」
「なら、安心だな」
――あの人もしかして、つばさっぴ先生の奥さん?
――今、お弁当渡してたよね? 健気ー!
――つばさっぴも、奥さんの前だとあんな顔するんだねぇ……。
保護者なのか、先生たちなのか、あちらこちらからうわさ話が聞こえてきた。翼くんは園でも人気の男性教諭だから、わたしが来れば話題にされるのは覚悟してたけど、陰でこそこそ言われるのはあまりいい気分じゃない。居心地が悪くなって辺りをキョロキョロ見回す。
「あ、ママ……じゃない。映璃先生だ」
見知った顔を見つけてほっとしたわたしは友だち感覚で手を振った。ママはわたしに気づくなり大股でやってきた。その顔は穏やかではない。
「つばさっぴは今、仕事中よ。用が済んだなら早めに帰りなさい」
いきなり説教されて興ざめする。
「そんなに怖い顔をしなくても……。映璃先生はお仕事となると途端に厳しいんだから。まさか、子どもたちの前でも同じような顔で接してる……わけないよね?」
「言っておくけど、私の特技は相手によってつける仮面をさっと変えられるところよ」
「ふーん……」
わたしは園の外で待っている悠くんの姿を探した。ちょうど、所在なさげな彼と目があったので、手招きしてこちらに呼ぶ。彼はニヤニヤしながらやってきた。
「えっ、悠……?! なんでここに……?」
案の定、翼くんとの会話を聞き逃していたママは、悠くんがここに来ていることを知らなかった。酷く動揺し、「映璃先生」の仮面は一瞬にして外れた。
「よぉ。ここで会うのは久しぶりだな、映璃先生?」
実は悠くんは五年ほど前に一度、臨時でサンタクロースの仕事を引き受けたことがある。呼びかけられたママはしかし、「映璃先生」の仮面をすぐに付けることが出来ず、ただの「野上映璃」の顔でうつむいていた。
「何しに来たのよ……?」
「何って……。映璃の顔を見に来たんじゃないか」
「嘘。だったらどうして園の外にいたの?」
「迎えの親でごった返してたからな。タイミングを見計らってたんだよ。……ほら。今ならこうして一対一で話す余裕がある。見つめ合うことだって……」
悠くんはママの顔をのぞき込もうとしたが、そっぽを向かれた。
「揶揄うのはやめて……! 私を困らせるつもりなら、このまま園で一仕事していってもらうわよ、鈴宮先生」
かろうじて先生の仮面を付け直したママが言った。
悠くんは少し考えるような仕草を見せ、「それも悪くないが、今日はめぐとランチデートする約束なんだ。おれと一緒にいたいなら、勤務時間外かつ彰博の許可が取れたときにしてくれ。会いにきてくれりゃいつでも対応する」と言った。
「腹減ったな。帰るぞ、めぐ」
悠くんは、反論は聞かないとでも言うかのようにわたしの手を取り、彼らに背を向けた。
「ま、待ちなさいよ、悠!」
ママの声に、悠くんは振り返りもせず片手だけ上げて歩き続けた。
*
バスで駅前まで戻り、以前から気になっていたスパイスカレーのお店に入った。少し待ったが、待ち時間に注文をしておいたので、席に着くとすぐに料理が提供された。
「いただきます!」
お腹が空いていたので早速食べる。辛さは控えめにしてもらったが、お腹の赤ちゃんもびっくりして暴れ出すほど辛い。しかしこの辛さは癖になる。なるほど、人気の理由はここにありそうだ。
店内には、園服姿の子どもを連れた親子が二組ほどいた。この店はお子様カレーが充実しているようで、赤ちゃんと来店するお客さんもちらほら見えた。
「そういえば……」
すでに半分ほどを平らげた悠くんが口を開く。
「さっき園に行ったとき、父親らしき人もそこそこいたな。お陰でおれがうろついててもあんまり目立たなかったぜ」
「わたしもそれ、思った! 夫婦で協力して子育てするのが定着してきたのかもね」
「ああ。めぐはいい選択をしたと思うよ。おれは翼のこと、尊敬してんだ。自分の子どもを育てるのでさえ大変なのに、あれだけの幼児の世話を何年もやってるんだからな。おれには出来ねえよ」
スプーンを振りかざしながら話すのを見て、愛菜ちゃんと過ごした日々にはいいことばかりではなく、苦労も多かったのだろうと推察する。いよいよ赤ちゃんが生まれる段になって、乳幼児期の子育てが大変だったことを思い出し、またあの日々がやってくるから心の準備を……と自らに言い聞かせているのかもしれない。
「悠くんの子育てにも期待してるよ?」
ちょっと意地悪く言うと、彼は困ったような顔をした。
「……一応、子育て経験者として役に立とうとは思ってるけど、あんまり期待しすぎるなよ? 愛菜とは五歳までしか一緒に暮らさなかった上に、おれは割とお気楽な父親だったからな」
「それ、分かる気がする。わたし、八歳から悠くんのことを見てきたけど、結構甘やかしてくれたもんね。あ、今でもそうか」
「……ま、厳しくすりゃあいいってもんでもない。むしろ、子どものことを理解するにはこっちも子ども目線で話さないと」
「つまり、悠くんは今でも童心を忘れてないってこと?」
「よくいえばそうなる。まぁ、悪く言えば幼稚ってことなんだけど」
だから三十歳離れていても、わたしたちは友人としてうまくやってこれたのだなと改めて思う。しかし、そんなわたしも二十一歳。そしていよいよ母親になろうとしている。不安は尽きない。が、どんなに経験が乏しくても、赤ちゃんを産み落とした瞬間からその子の人生を背負わなければならない。現実を直視できる大人にならなければならない。それは、父親になりたいと言った悠くんだって同じはずだ……。
*
昼食を終えて帰宅し、夕方まではのんびり過ごした。悠くんが仕事に出かけたあとからは、入れ違うように外に出ていた翼くんと祖母が帰ってくる。今日先に戻ったのは翼くんだ。
「ただいまー。めぐちゃん、お弁当マジ最高だったよ。明日もよろしくー」
彼はそう言って空の弁当箱をわたしに預けた。
「ほんと? よかったぁ。届けた甲斐があったよー」
「あー、そのことなんだけどさー」
翼くんは珍しく愚痴をこぼし始める。
「あの後、俺がエリ姉に怒られたんだけど! 勘弁して欲しいよなぁ。だいたい、エリ姉自身が悠斗に気があるそぶりを見せるから揶揄われるんだよ。自業自得だっつーの」
「あはは。とばっちりを食っちゃったんだ? じゃあ明日のお弁当は届けずに、朝作ったものを翼くんが自分で持ってく?」
「いや、俺はどっちでも構わないよ。めぐちゃんの好きにしてくれればそれで。むしろ、エリ姉のあんな顔が見られるなら、悠斗と一緒に毎日来てくれてもいいくらい」
「そうなの? でも、毎日行ったら次はわたしが怒られそう。それに、陰で『つばさっぴの奥さんって……』みたいな話されてるのも気になったし」
「勝手に言わせとけばいいじゃん。みんな、嫉妬してるだけさ。気にするだけ時間の無駄」
「わぉ! 翼くん、言うねぇ! 格好いい!」
「だろ? ……さあて、晩ご飯の支度しなきゃ」
翼くんは手洗いを済ませると、エプロンを身につけて台所に立った。
*
それからしばらくして、パパと一緒に祖母が帰ってきた。
「おばあちゃん、おかえりー! パパ、お迎えお疲れさま」
「やー、ホントに疲れた……。今日はいつも通りの時間に送迎バスが来ないからずいぶん待たされて参ったよ……」
「どうりで遅いと思ったら……。それは大変だったね。少し休んでいきなよ」
「ありがとう。お言葉に甘えて、そうさせてもらおうかな」
パパは祖母を定位置に座らせると、自身も畳に腰を下ろした。
「あ、そうだ! パパ、久しぶりに肩たたきしてあげるよ。その代わり、話を聞いてくれる?」
わたしは勝手にパパの肩を叩きながら今日、園で起きたことを話して聞かせた。最初はうんうんと頷いていたパパだったが、次第にうなり声を上げはじめた。
「なるほど。そういうことなら再度、説得しなきゃいけないね。……まったく、懲りない男だ」
「ねぇ、パパ? 聞きづらい内容ではあるけれど、パパは悠くんが今でもママを好きでいることについてどう思ってるの?」
「そりゃあいい気分はしないさ。だけどそれについては三人で話し合ったし、結論はとうに出ているから心配はしていないよ。ただ、悠にはもうちょっと大人になってもらわないと」
「だよねぇ……」
「ほらほら、夕食が出来上がったよー。アキ兄も食べてく?」
話し込んでいる間に料理が完成し、食卓に並び始める。今日の晩ご飯は筑前煮だ。
「ごめんごめん、わたしも作るつもりだったのに。配膳を手伝うよ」
テーブルに両手をついて重たい身体を支え、立ち上がる。そのとき、インターフォンが鳴った。一瞬、悠くんかと思ったが、彼なら自分で鍵を開けて入ってくるはずだ。カメラと通話をオンにする。
「はい……」
『悠を出して。話があるの』
モニターに映っていたのはママだった。一気にテンションが下がる。
「……悠くんなら、まだ仕事から帰ってないけど」
『じゃあ、帰ってくるまで待たせてもらうわ』
「えー?」
面倒なことになった。やりとりを聞いていた翼くんも同じことを思ったようだ。
「きっと昼間のこと、まだ怒ってるんだよ。俺に言ったんじゃ埒があかないから、直接文句を言いに来たに違いない。……悠斗ならもうすぐ帰るだろ。任せときゃいいさ」
「うん……」
こちら側でやりとりしていると、モニターの向こうのママが思い出したように言う。
『そういえば、パパとは合流した? おばあちゃんのお迎えに行ってるはずなんだけど』
「……もう帰ったって言って」
わたしが返事をするより早くパパが小声で耳打ちした。パパの言葉をそのまま伝えると、ママは『道中では会わなかったけど、寄り道してるのかな……』と言いながら通りに目をやった。
『あ、帰ってきた』
折しもそんなタイミングで悠くんが帰宅した。一体どんな会話が成されるのだろうか。わたしと翼くん、そしてパパは玄関ドアに近づき、こっそり盗み聞きすることにした。
バイクから降りた悠くんはママの姿をみても驚くどころか、はじめから約束していたかのように手を挙げた。
「映璃か。早速会いにきてくれたってわけ?」
「そうよ。こっちから出向けば対応してくれるんでしょう?」
「もちろん。……だけどその様子じゃ、これからデートに行こうって感じじゃないな? 文句があるなら受け付けるが、外は寒い。とりあえず中に入ろう」
「玄関を入ってすぐのところで充分よ」
「了解」
二人が入って来そうだったので、慌てて居間に引っ込む。そして今度は襖の隙間から二人の様子を窺う。ピリピリとした空気の中、二人の会話が始まる。
「……ああいう嘘を平気で言うなんて。見損なったわ」
「おっと、いきなりそう来たか。……嘘はついてない。めぐが翼に弁当を届けるって言うから付き添った。そこに映璃がいるなら会って行こうってだけの話じゃねえか」
「なら、もうちょっとマシな声かけは出来なかったの? こっちは仕事中だって言うのに!」
「おれがああいう発言をするのは知ってるだろう? 今に始まったことじゃない。それを咎められても困るな。……狼狽える映璃も可愛かったけど?」
「そういうのはもうおしまいにしてっ!」
突然、ママが大声を出した。
「いい加減、私とめぐの間を行ったり来たりするのはやめなさい!」
「…………」
悠くんはうつむいた。ママはまるで子どもを叱るように指を振りかざして責め立てる。
「確かに、好きでいてくれて嬉しいとは言った。だけど、私にもめぐにも夫がいるの。いつでも悠のお遊びに付き合えるわけじゃないの。……言ってる意味、分かる?」
「…………」
「分からないならちゃんと教えてあげる。……悠はもう一度父親になるんでしょう? めぐと翼くんの子どもを彼らと一緒に育てるつもりなんでしょう? だったらもう、女を弄ぶようなことはやめなさい。真面目に、小さな命に意識を集中しなさい」
「おれは別に弄んでるつもりは……」
「じゃあこう言えば分かる? ……もう無責任な行動は慎みなさいって言ってるの。悠は長い間、独身で通してきた。それはとても楽な生き方だと思うし、悠には合ってるとも思うよ。だけど、子どもの世話をすると決めたらそうはいかないわ。女にうつつを抜かしている暇なんて一秒もない。目の前で泣き叫ぶ赤ちゃんの世話を最優先しなきゃいけなくなるの」
「分かってるよ、そのくらい。おれだって心の準備はしてるつもりだ」
「そう……。なら当分の間、私の前に顔を出しても口説くような発言や行動はしないと誓って」
「当分の間ってどのくらいだよ?」
「めぐたちの子どもがそこそこ大きくなった頃かな? もっとも、その頃には私もおばあちゃんが板についてて口説こうなどとは思えなくなってるでしょうけど」
「……今日は冷てえなぁ。三人で飲んだときとは大違いだぜ」
「酔ってる時としらふの時とを一緒にする方が間違ってる!」
「正論で返すなよ……。何も言えねえじゃねえか……」
昼は悠くんが優勢だったが、今は完全に立場が逆転している。ママでもあんなふうにすごむんだと知って驚きを隠せない。隣でみている翼くんでさえ「過去最高に怖いエリ姉をみた」と恐れおののいている。パパだけは二人の様子を静観している。
二人の会話は続く。
「……それは彰博の入れ知恵か? それとも映璃自身の考え?」
「多少はアキの思いも込めたわ。だけどほぼ、私の考えと言っていい」
「……多少なりともあいつの考えを含んだ発言だと思うとうんざりするな……。やっぱりおれは一生あいつには勝てないのか……」
「アキを上回りたいと思うなら、十年でも二十年でも父親をやってみることね。……アキも私も子どもから……めぐから様々なことを学んだわ。悠だって、短かったとしても子育てから学んだことはあるでしょう?」
「まぁな……」
「今からでも遅くはないわ。悠自身がやる気に満ちあふれているんだもの。子育てを通じて悠はきっと変われる。今よりもっと魅力的な人になれる。私はそう信じてる」
「可能性を信じてくれるのは有り難いことだ。じゃあ、もしおれが今よりイイ男になった暁には……ランチデートくらいはしてくれるか?」
「そうね、ランチくらいなら。……アキも一緒に行くって言うでしょうけど」
「……それ、デートって言えるか? まぁ、いっか。……あいつのことだ、どうせこの話もそこら辺で聞いてるんだろ?」
「まさか。アキなら家に帰って……」
ママがそこまで言うとパパは襖を開けた。
「……なんでここにいるのよ? 帰ったんじゃなかったの?」
「言ったはずだよ。悠と会うときは、か・な・ら・ず同席する、と」
「んもう……! じゃあ、私たちの会話は全部聞いてたってこと?」
「そういうことになるね」
「信じられない!」
「仕方がないじゃないか。めぐから昼間の出来事を聞かされた以上、悠には忠告しておかなければと思ってたところなんだから。でも、僕が言いたかったことは全部君が言ってくれた。補足することはほとんどないよ」
「……ったく、二人してよぉ。電車で園まで行き、ちょっぴり映璃をからかって、めぐとランチして帰った。それだけのことじゃねえか」
悠くんが言い訳じみたことを言うと、パパは彼の前にすっと歩み寄った。
「めぐの父親として、また祖父になる者として、娘のお腹から生まれてくる赤ん坊の養育を任せる男には覚悟を決めてもらいたいんだよ。中途半端な気持ちでは、同じ失敗を繰り返すだけだからね」
「…………」
「君は翼くんを見習うべきだ。彼は一途に妻を愛し、めぐの気持ちを確かめた上で子をもうけた。これこそがエリーの言った『責任ある行動』ってやつだ。ところが悠はどう? 現実を見つめるのは赤ん坊が生まれてからだ、と言われればその通りだけれど、少なくとも女性陣は君の行動に不安や不満を感じている。僕自身もそうだ。様々な人生経験を積んできた今の君が、若い頃と同じように、その場の気分で恋愛と子育てのいいとこ取りをするのだとしたらあまりにも『無責任』じゃない?」
「くっ……」
「エリーが言ったように、もう一人の父親になるつもりがあるなら今ここで宣言して欲しい。エリーやめぐに向けていた愛情を赤ん坊に向けると。それが出来ないというのであれば、君自身が赤ん坊だと言わざるを得ない」
「言ってくれるじゃねえか……。そんなにおれは信用ならない男かよ?」
二人はにらみ合った。
「違う。信じているからこそ言うんだ」
パパは悠くんの両肩に手を置いた。
「……五年前、君に頼んだことを覚えてる? 僕は君に、めぐと結婚して欲しいと頼んだんだ。そうすれば本当の家族になれるから、って」
「ああ。だけどあれはお前の偽善だった。それも含めて覚えているよ」
「……あのときの僕が、優越感を得たいという個人的な理由から結婚話を提案したのは確かだ。でも今は違う。僕はね、君がめぐの子のもう一人の父親になりたいと言うのを聞いて心の底から喜んでるんだよ。これでいよいよライバルを卒業できる。真の意味で家族になれると思ったら嬉しくて仕方がないんだよ」
「え……」
「繊細でやんちゃで自由奔放で放っておけない。君は……同い年ではあるけれど、僕とエリーにとっては息子みたいな存在なんだ。だから今度のことを機に僕は君の義父になるつもりでいる。しっかりして欲しいと頼んでいるのはそういう理由からだよ」
「…………」
「どうだろう? 何か不満があるかな?」
「えーと……。わりぃ、混乱してる……」
悠くんはうつむいたり頭を掻いたりと、落ち着かない様子だった。
「……そうだね。少し一度に話しすぎたかもしれない。赤ん坊が生まれるまでまだ時間がありそうだから、何日か真剣に考えてみて欲しい」
「…………」
悠くんは押し黙った。重たい空気が場を支配する。
「彰博? まだ話は済まないの? 晩ご飯が冷めちゃうわ。とりあえず食事にしましょうよ」
背後から祖母の声がした。料理が出来上がったタイミングでママが訪ねてきて長い話が始まったことを思い出す。
「せっかくだから二人も食べて行きなよ。普段から多めに作ってるし、足りなきゃあり合わせの材料でもう一品、適当に作るから」
翼くんはそう言って、ママとパパの背中を押した。
「……実はさっきから早く食事にありつきたいと思ってたんだ。目の前に料理が出てきた直後、お預けを食ってたようなもんだからね。エリー、ここは翼くんの厚意に甘えよう」
パパはさっさと食卓に着いた。それに習ってママたちも居間に向かう。わたしは翼くんと一緒に配膳をし、ようやっと席に着いた。
「お待たせしました。いただきます!」
手を合わせ、料理に箸をのばす。筑前煮はもう熱々ではなかったが時間が経った分、味がしみていた。
「んー! おいしい! やっぱ翼くんの料理はサイコーだよねー!」
なんとか場の空気を変えようと努めて笑顔で食事をしてみるものの、悠くんは相変わらず黙したまま茶碗の中に目を落としている。わたしはふっと息を吐いた。
「……パパとママの言ったこと、気にしすぎなくてもいいと思うよ。わたしは別に、これまで通りの悠くんでも……」
「めぐ」
「……はい」
「あとでおれの部屋に来てくれないか。二人だけで話がしたい」
特別な話がある、と直感した。わたしはひとこと「……わかった」とだけ答えた。
「翼、ほんの少しだけ……一時間だけめぐを貸してくれ」
「オーケー。だけど、異変を感じたらすぐ部屋に飛び込むからそのつもりで」
悠くんは黙ったまま小さく頷いた。
*
食事を終えて一息ついたあと、わたしはちょっとドキドキしながら悠くんの部屋を訪れた。
四畳半の小さな部屋。しきっぱなしの布団と出しっぱなしの衣類のせいでさらに狭く見える。わたしがやってきたのが分かると、彼は「ちょっと待ってろ」と言って布団をたたみ、空いたスペースに座布団を二つ出した。
「……まぁ、座れよ」
悠くんは先に座布団に腰を下ろした。その隣にわたしも座る。と、いきなり抱きしめられた。戸惑いを口にする間もなく、彼は話し始める。
「めぐのことが好きだからこそ翼と幸せになって欲しいと願い、結婚を後押しした。そして、二人の子どもをこの腕で抱きたいと懇願した結果、いよいよその時がやって来ようとしている……。すべてはおれが望んだことだ。だけど翼や映璃の言ったとおり、おれはまだめぐと恋愛したいらしい」
「悠くん……」
「めぐは優しいから、今のまま赤子の世話をしてくれればいいと思ってくれてるんだろう。だけど、それじゃダメなんだってさ……。それじゃあ覚悟が足りないんだと」
「…………」
「もう、これっきりにしなきゃいけない。おれを信じてくれる家族のためにも……。だから最後に……」
その唇が頬を伝い、わたしの唇に重なった。何度も何度も求められる。わたしは拒まなかった。なのに悠くんは戸惑いの眼差しを向けた。
「……こんなふうにしか接することの出来ないおれを叱ってくれよ。大嫌いだと突き飛ばしてくれよ。そうでもされなきゃ、おれはめぐを嫌いになれない。赤子の父親として堂々とすることも出来ない……」
「嫌いになれるわけないじゃん……。わたしだって悠くんのことは今でも好きなのに……」
「それじゃあダメなんだっ……!」
まるで自分に怒っているみたいだった。悠くんは「わりぃ……」と言って続ける。
「映璃の方はあっちから拒んでくれたし、彰博がちゃんとしてるから諦めもつく。でもめぐは、おれがこんなことを言ってもなお好きだと言ってくれるだろ? 翼もそこまでキツく言わないし。 ……おれは意志が弱いから、自分の力だけじゃめぐを遠ざけられないんだよ。甘やかされたら甘やかされただけ依存しちまう。だからめぐの方から、こんなおれを突き放してほしいんだよ……」
「悠くん……!」
わたしは彼の手を取り、その目をじっと見つめた。
「弱い自分から目を逸らしちゃダメ! そんなことをしたら悠くんじゃなくなっちゃうよ!」
「えっ……」
「……意志が弱かったり、依存しないと生きられなかったりするのは悠くんの特徴だとわたしは思う。だから、それをなくそうとしたり見なかったことにしたら、本来の悠くんが台無しになっちゃうよ。……いいんだよ、そのままで。パパやママに言われたから何よ。そんなの、言わせておけばいいじゃん!」
『それ、俺の台詞!』
会話に割り込むように、戸の向こうから声がした。翼くんだった。彼は「入るよ」と言って狭い部屋に足を踏み入れる。
「……立ち聞きとは、趣味が悪いな」
「妻を貸してくれって言われて、黙って一時間も自室にこもっていられるかよ」
翼くんは立ったまま腕を組む。
「確かに俺たちはあんたを甘やかしすぎてるかもしれない。だけど残念ながら俺たちは、アキ兄たちと違って何年経っても三人で一人前なんだよ。だから悠斗の弱さは俺たちが補うし、俺やめぐちゃんの至らなさは悠斗が補ってくれればそれでいいんだよ」
その言葉にハッとする。そうか。親になることに不安を感じていたけれど、わたしたちはそもそも未熟者。いきなり完璧を目指すことはないのだ。そう思ったら急に楽になった。
「悠くん」
わたしは再び彼の名を呼び、今度はしっかりとその手を握った。
「三人で新米パパ、ママになろう? それでいいじゃん。ね?」
「そうだよ。アキ兄やエリ姉は自分たちが親歴二十年だからあんなことを言うけど、こちとらこれから入学して一年生になるところなんだ。知らなくて当然。出来なくて当たり前。だからこそ頑張ろうって気にもなってるし、失敗しながら学んでいくしかないんだよ」
「おまえら……」
「前に別の形で言ったけど、我が家には我が家のルールや考え方がある。たとえ身内であっても俺たちのやり方に文句は言わせない。……もちろん、何かあったときは自分たちでなんとかしなきゃいけないんだけど、それも承知の上だ」
「うんうん。これまでだって三人でなんとかしてきたんだもん。この先もきっと大丈夫だよ!」
「……本当にそれでいいのか? 正直おれは自信がない……」
これだけ励ましても彼の元気はなかなか戻ってこなかった。よほどママやパパに言われたのが堪えているのだろう。
わたしが翼くんを見上げると彼は隣に腰を下ろし、わたしの大きなお腹に手をやった。赤ちゃんが動く。まるで赤ちゃんも悠くんを励まそうとしているかのようだ。
「……ねぇ、教えちゃおうか」
「教えるって……名前を?」
「うん」
「……そうだな。悠斗にやる気を出してもらうにはそれしかないかもな」
わたしたちはうなずき合い、悠くんを正視した。
「本当は生まれてから言うつもりだったけど、前倒しだ」
「……で、名前は?」
恐る恐る問うた彼に告げる。
「まな」
悠くんは目を見開いた。
「……今、なんて?」
「まな。それがこの子につける名前だよ」
「待て待て。だってお前らの子どもだろうが。たとえ生まれ変わるのだとしても、おれの死んだ娘と同じ名前をつけるなんて……」
戸惑う悠くんに翼くんが説明する。
「もちろん、はじめはそのつもりはなかったよ。だけど、前回の流産を経験して考えが変わったんだ。……悠斗の命を救ってくれた恩人の名を我が子につけようってな」
「本気……なのか……?」
「本気も本気さ。ただし、めぐちゃんに合わせて表記は平仮名にしようと思ってる。野上まな。いい名前だろ?」
「…………」
「流産のあとで悠くんが言ってたでしょう? もう一度、愛菜ちゃんと会うんだって。その願いをどうしても叶えてあげたいっていうのもあってね」
「…………!」
悠くんは目に手を当て、天井を仰いだ。喜ばせるどころか、泣かせてしまったことにわたし自身ショックを受ける。しかし翼くんは、「大丈夫」と呟いてわたしの手を握った。
「馬鹿だよ、お前らは……」
しばらくして、悠くんは天を仰いだまま呟いた。
「ああ、そうだ。俺たちは悠斗と同じで馬鹿なんだ。だから一緒に家族やってんだ」
「そうそう! わたしね、思うんだ。この子は絶対に愛菜ちゃんの生まれ変わりだって。そう思ったら、やる気になってこない?」
「……そうだな。俄然、やる気になるな」
悠くんは翼くんと一緒にわたしのお腹に手を置いた。
「……まな。お父さんは待ってるよ。今度こそこの世で一緒に暮らそうな」
その言葉に反応するようにお腹がぐるぐるっと動いた。もうすぐ会える。赤ちゃんもその日を待ちわびているように思えた。
<翼>
奇しくも今日、三月二十六日は関東で桜が満開になるという。年々、春の訪れが早まっているのは温暖化のせいに違いないが、今の俺はその現象をいいものとして受け止めている。満開の桜が、今まさにこの世に生まれ出てくるまなを祝福しているように感じられるからだ。
産科の入った病院近くの公園で春を感じながら、めぐちゃんと初めて出会った日に思いを馳せる。二十一年前、アキ兄とエリ姉が赤ちゃんと一緒に自宅へやってきた日のことは今でもはっきりと覚えている。これまで友だちのような夫婦だった二人が、その日を境に父親と母親の顔になったのを見て、こんなにも一瞬にして顔つきが変わるのかと驚いたものである。その二人に、妹のように可愛がってあげてと言われた俺は実際その通りに関わってきた。
そのとき実の妹は五歳くらいで、すでに父と一緒に野球を始めており、一緒に遊ぶことはほとんどなくなっていた。父に似て性格も言葉遣いもキツく、生まれながらに俺とは相性が悪かった。だからというわけではないが、ハイハイでもよちよち歩きでも俺を慕ってくれるめぐちゃんが可愛くて仕方がなかった。
めぐちゃんが小学生になったばかりの頃、高校で同じ演劇部員だった子とほんのちょっと付き合ってみたこともあったが、本当の俺を出すことが出来ずに苦しくなりすぐ別れてしまった。それ以後めぐちゃん一筋なのは他でもない。彼女がいつも俺の居場所を用意してくれていたからだ。
そんな彼女と紆余曲折を経て結婚し、愛し合うことが出来ただけでも夢みたいなのに、このあと俺は、二十一年前のめぐちゃんと同じような顔をした赤ちゃんをこの腕で抱くことになる。あのときの感動を思い出すのか、それともまったく別の気持ちになるのか……。帝王切開での手術の時間が来るまで落ち着かず、さっきからずっと同じ場所を行ったり来たりしている俺である。
「あー……。お前をみてると、愛菜の誕生を待っていた三十数年前を思い出すよ」
同じ場所で出産を待つ悠斗。こちらはベンチの背にもたれ、初めて父親になる俺を落ち着き払った様子で見ている。
「そういえば、悠斗の娘さんの誕生時の話は聞いたことがなかったな」
歩きながら緊張と不安を取り除くため悠斗に話しかけた。彼は渋い顔をしてからポツポツと語り出す。
「……嫁さんは普通分娩だった。陣痛が始まって病院連れてって最初のうちはそばにいたんだけど、こっちはなにも出来なくてな。オロオロしてたら迷惑だって叱られて愕然としたもんだ」
「へぇ……」
「女ってのは不思議な生き物で、出産が始まった瞬間からすでに母親の顔してんだよ。で、赤子を産み落としたらもう夫のことは二の次、三の次だ。……ま、そこに至るまでにおれと嫁さんの関係がすでに冷えてたせいもあるだろうけど」
悠斗と元奥さんの恋愛感情の波は、線香花火が散り落ちるようなスピード感で冷めていったそうだ。性格が合わず、喧嘩もしょっちゅう。子どもの存在が唯一二人を繋いでいたが、その子が亡くなってしまったので即刻、離婚届を突きつけられたと聞いている。
「お前はその時のおれとはまったく違う。女の気持ち、母親の気持ちにより添えるお前ならちゃんと立派な父親になれるだろうさ」
そう言った悠斗の表情がにわかに緊張感を帯びた。もうその時のおれではない、今度こそはうまく父親をやるぞと意識しているみたいだった。
「そう言うんなら肩の力を抜けよなぁ」
肩を揉んでやると「その言葉、そっくりそのまま返してやるよ」と言われ、立ち上がった悠斗に肩を力強く揉まれた。
「いってぇ……! そんな力で赤ちゃんをあやすなよ?」
「なに、ふにゃふにゃの赤子が目の前にいればおのずと繊細に扱うさ。愛菜の生まれ変わりだと思えば尚更な」
いよいよ、会えるんだな……。悠斗はそう言って遠くの空を見やった。俺も同じ方を見ると風がぶわっと吹いた。桜の花びらが舞う。それはまるで、父親になる俺たちを祝う紙吹雪のようだった。

*
早めの昼食を済ませた俺たちは、午後一番で病院入りした。程なくして案内があり、手術室の前で二人揃って待たされる。
「あのー、手術って安全なんですよね……?」
緊張しすぎてしょうもないことを質問したが、看護師は笑顔で「名医が執刀しますからご心配なく」と答えてくれた。
「お・ち・つ・け!」
そのとき、悠斗に両肩をぐっと押さえつけられた。
「……立ったり座ったりして、せわしねえな。さっき俺に、肩の力を抜けって言ったのはどこのどいつだよ?」
「……実は俺、演劇でも練習は自信満々で出来るのに、本番となると途端に緊張しちゃうタイプで」
正直に告げると悠斗は鼻で笑った。
「意外だな。俺を殺すって言ってきたときは迫真の演技だったのに」
「あのときは緊張よりも怒りが勝ってたから……」
「なら、瞑想でもしてろ。無の境地でいれば緊張も不安も感じなくなるって聞くぜ?」
「瞑想ね……」
深呼吸をした俺の隣で、悠斗も一つ息を吐く。
「……分かるよ、お前の気持ち。おれだって初めての子育てのときは、冬の荒波に放り出されたような不安と緊張でいっぱいだった。だけど、冷たい海で身体の感覚を鈍らせながらも泳ぎ続けるしかなかった。そうするうちに気づけば空は晴れ、陸地が見え、地に足がついていた……。そういうものだよ。ま、おれの場合は楽園に思えた陸地が再び嵐に見舞われて溺れかかった訳なんだけど」
「……でも悠斗は何度も助かってきた。それはきっと泳ぎ方を知ってるからに違いないよ」
「……もう、溺れるような悲惨な目には遭いたくないけどなぁ」
「大丈夫さ。いま悠斗が立っている場所には俺もめぐちゃんも、それからこれから生まれてくる赤ちゃんもいる。つまり悠斗に何かあってもすぐに助けてやれるんだ」
「それは頼もしいな。……おっ、少しは自信が戻ってきたか? お前はこうでなくちゃ」
そのとき「野上さん」と声がかかった。
「お子様が無事に生まれましたよ。かわいらしい女の子です」
落ち着いたはずの身体が再び緊張し、天井からつり上げられたかのように立ち上がる。
看護師が運んできた新生児用のベビーベッドには本当に小さな赤ちゃんが、生まれたままの姿にタオルだけを掛けられた状態で寝かされていた。いや、寝かされているという表現は正しくない。赤ちゃんは何かを訴えるように全力で泣いている。
思わず腕を伸ばすと「もうちょっと待ってて下さいね」と笑顔で返された。赤ちゃんは身体を綺麗にしたり、服を着せたりするために一旦ベビールームに連れて行くのだと言う。
あっさりと退場する我が子を目で追いかけていたら悠斗に小突かれた。
「そんな顔をするなよ。待ちわびた赤子を早く抱きたい気持ちは分かるが、あとで嫌と言うほど抱くことになるんだぜ?」
「そうだけど。……ああ、めぐちゃんのことも気がかりだし、じれったいなぁ!」
これが悠斗の言っていた男の無力さってやつなのか。俺に出来るのは唯一待つことだけ。自覚していた以上に忍耐力がない自分に嫌気が差す。
「めぐとの結婚は何年も待てたのに、どうして十分、二十分が待てない?」
今日だけは、冷静な悠斗のツッコミが俺の心にグサリと突き刺さった。
*
程なくして再び声がかかり、俺たちはようやく出産を終えためぐちゃんの待つ処置室に通された。悠斗の言ったように、出産を果たしためぐちゃんの顔はいつもより大人びて見え、それはやはり母親の顔としか言いようがなかった。
顔色が良さそうな彼女を見て安心した俺はねぎらいの言葉をかける。
「手術、お疲れさま。赤ちゃんとの対面はどんな気分だった?」
「ちっちゃーいって思った! でもまだ実感が湧かないよ。翼くんたちも対面したんだよね?」
「うん。俺もまだ実感は湧かないや……」
そこへ執刀医と看護師が身ぎれいにした赤ちゃんを連れてやってきた。さっき全力で泣いていた赤ちゃんは、今は看護師の腕の中で大人しく目を瞑っている。
「ご出産、おめでとうございます」
執刀医は俺たちに向かってそう言うと、手術が成功したことや術後のことなどを淡々と説明した。それが済むと看護師からめぐちゃんに赤ちゃんが手渡される。彼女はぎこちなくその腕で赤ちゃんを抱いた。

「わぁ、本当に産んだんだねぇ……。翼くんと悠くんも抱いてごらんよ。あったかいよ」
言われて赤ちゃんを引き受ける。普段、園で抱っこする幼児とはまったく違う重量感。それは、かつて抱いた赤ちゃん時代のめぐちゃんの重さとも違った。これが本当の、新しい命の重さ……。ぽかんと開けた口が可愛くて思わず頬ずりしたくなる。
「うん、目元がめぐそっくりだ。鼻の形は翼かな……」
のぞき込む悠斗に我が子を抱かせる。
「ほら。ついに願いが叶うときが来たよ」
彼は目を細めながら「……おかえり、まな。やっと会えたな」と語りかけた。
赤ちゃんはもちろん何も答えない。しかし悠斗は何かを感じ取ったのか、その目にうっすらと涙を浮かべていた。
「カメラがあれば、お写真撮りますよ」
看護師がニコニコしながら言った。俺は手持ちのスマホを手渡し、めぐちゃんが横たわるベッドの脇に立った。
「めぐが抱けよ」
悠斗が赤ちゃんを渡そうとしたが、彼女は「悠くんに抱いててほしいな」と言った。
「えっ……。だけどこういうのは母親の方が……」
「俺もめぐちゃんに賛成! ほら、待たせるのも悪いから早く撮ってもらおうぜ」
「……ったく、お前らはどこまでも馬鹿なんだから」
悠斗は愚痴りながらも赤ちゃんを抱いたままカメラの方を向いた。
「わぁ! お父さん思いのいいお子さんたちですね!」
悠斗のことを俺たちの父親と勘違いしている看護師は明るい声で「撮りますよー」と言い、スマホの画面をタップした。写真を見せてもらうと、それぞれがちょっぴり成長した顔つきで写っていた。
「俺たちの新しい生活が始まるんだな」
思っていたより早く、自分の中に父親としての実感が湧いてきていることに気づく。
「まな。俺がパパだよ。よろしくね」
語りかけると、いちごくらいの小さな手が俺の人差し指を握った。新しいパパ、よろしくね。そう言っているように思えた。
◇◇◇
運よく出産日が園の春休みに重なったこともあり、割合堂々と育休をとることが出来ている。帝王切開で出産した場合の入院期間は一週間。個室で一人のめぐちゃんが寂しくないよう、俺と悠斗は毎日のように病院を訪れては彼女の話し相手になり、まなを愛でている。
*
入院生活も三日が過ぎたころ「一緒に病院のご飯を食べない?」と提案された。幸いにも俺だけは健康体を維持しているため、病院で提供される食事というものを食べたことがなかった。事前に頼めば用意してもらえるというので、これも経験だと思い、その日は悠斗と一緒に昼飯を食べていくことにした。運ばれてきたのは、いかにも病人食って感じの和食だった。
「うーん。身体には良さそうだけど、これを毎食一人で食べていたら侘びしくなりそうだ……」
俺がぼそっと呟くとめぐちゃんは大きく頷いた。
「でしょう? もうちょっと、新米ママが喜びそうな洋食にして欲しいよねぇ」
「えっ、出産するまであんなに和食にこだわっていたのに?」
「そうなの! あぁ、ピザが食べたーい!」
そんな会話をしていると、部屋のドアをノックする音が聞こえた。
「おれが出るよ」
悠斗がドアを開けると、そこには巨大な花束が立っていた。彼は恐る恐る花束の向こう側をのぞき込む。
「……孝太郎さん?」
「その声は悠斗クンか。めぐさんの出産祝いに駆けつけたんだけど、入っても構わないかな?」
「いいですけど、めちゃくちゃデカい花束ですね……」
「特別に作らせたんだ。大切な人を喜ばせたいからとにかく大きなものを、とね」
「……いくら何でも限度ってものが。まぁ、いいか」
悠斗はドアを全開にし、コータローさんを部屋に通した。めぐちゃんが立ち上がる。
「……あのー、顔は見えませんが孝太郎さん、わざわざお見舞いに来て下さってありがとうございます!」
「……とりあえず、これを受け取ってもらおうか。話はそれからにしよう」
「はい。……って、抱えきれないんですけど!」
「俺が預かるよ。昼飯食い終わったら持って帰るから、一旦ベッドの上に置かせてもらうぜ」
半ば奪い取るように受け取り、ベッドに置く。途端に花の香りが部屋中に広がった。
「……ってよく見たら、バラばっかりじゃん! あんたは愛の告白をしに来たのかよっ! さては目的を伝えなかったな? ったく、野球しか知らない人はこれだから困るぜ」
「……高価な花の方が喜ばれると店の人が言うからその通りにしたんだが。場違いだったなら申し訳ない。責任を持って持ち帰ろう」
「分かってないなぁ、ったく……。あんたは気持ちを伝えるためにこれを用意したんだろ? 持って帰っちゃったら何の意味もないじゃん。これはちゃんと自宅に飾っておくよ」
「済まないね。そうしてもらえると有り難い」
彼はほっとしたような、照れくさそうな顔で俺たちを見、それからベビーベッドで眠るまなに視線を向けた。
「……めぐさんの中にいたときは頼りなさげに思えた命だが、こうして外に出てきた彼女は、こんなに小さいのに、ここで眠っているだけなのに、とてつもない存在感を放っている。新生児の生命力には恐れ入るよ」
「孝太郎さんも抱っこしてみますか?」
「いや……。めぐさんの顔を見に来ただけの僕が、興味本位で抱いていい存在ではないだろう。生まれたばかりの赤ちゃんを抱いていいのはやはり責任ある立場の人間、母や父、それに準ずる者でなければならない」
「もっともらしいことを言っちゃって。本当は新生児をどう扱っていいか分からないだけじゃないの?」
俺がツッコむと、コータローさんは窓の外に目をやって「……そうかもしれないな」と素直に認めた。
「君たちのことを尊敬するよ。自ら親になりたいと手を挙げ、ひとりの人間を育て上げようというのだから。僕には到底真似できない偉業だ」
「ゼロから育てるのは確かに大変だろうさ。だけど、その気さえあればコータローさんにだって……」
「野球に人生を捧げてきた僕にそんなことが出来ると思うかい……? やはり君たちは人類の未来に貢献している。誇りを持って子育てに当たってほしいものだ」
「大袈裟!」
とっさに返したものの、内心では「そうか、これは誇りに思っていいことなんだ」と胸を張った。まさかコータローさんに俺の自信を取り戻してもらうことになるとは思ってもみなかった。
*
この日はめぐちゃんを見舞うため、親や彼女の職場のオーナーらが続々やってきた。笑いの絶えない室内で、やはり彼女は俺たちの太陽だ、と改めて思う。時には雲が太陽を隠すこともあるだろう。雨を降らせ日もあるだろう。そんなときは寄り添うことしか出来ないが、それが夫としての役目だと思うし、彼女の精神を安定させられるのはやはり俺だけだとも思っている。
賑やかな彼らを見ていたとき、悠斗が急に背筋を伸ばして独り言を言い始めた。時を同じくしてワライバのオーナーも悠斗と同じ場所――誰もいない空間――に目を移す。
「……悠斗?」
そっと声を掛けると、彼も同じ声のトーンで返事をする。
「……オジイがひ孫の顔を見に来てる。父親になった気分はどうだ? って言ってるよ」
「……マジ? どこどこ?」
「まなのすぐそばに……。っていってもお前には見えないんだよな? ちゃんとそこにいるんだけど」
「ちぇっ。遊びに来てるんなら孫の俺の前にも姿を見せて欲しいもんだぜ」
俺はわざとらしく言う。
「じいちゃん。天国から見に来てくれてありがとな。ほら、見たがってたひ孫だよ。俺たちの子ども、可愛いだろ? これからもあっちの世界から見守ってくれよな」
「えっ、おじいちゃん、来てるの?」
めぐちゃんが辺りをキョロキョロと見回すと、ワライバのオーナーのひとりが「さっきから赤ちゃんの頭を撫でてるよ」と言って笑った。どうやら彼にも幽霊が見えるらしい。
「あの世の人もお祝いに駆けつけてくれるなんて、めぐっちは本当に愛されてるんだなぁ」
「きっと、わたしがまだまだ未熟者だから放っておけないんでしょう。実際、その通りです。皆さんにも、子育て中はこれまで以上に力を貸して頂けたら嬉しいです」
「……オジイが、めぐのためならあの世から何人でも助っ人を連れてくるってさ」
悠斗の通訳を聞いた一同がどっと笑う。それが現実になったらさすがにちょっと怖いけど、いつでもサポートされてると思ったら何だか心強くもある。
「野上さん、そろそろ授乳の時間ですよ。赤ちゃんと一緒に授乳室に来て下さいね」
そのとき、看護師が張りのある声でめぐちゃんを呼んだ。
めぐちゃんがまなを抱き上げるのを見て、男性陣が揃って荷物を持つ。と、看護師が俺たちの通行を妨げた。
「授乳室は男子禁制です! お父さん方はご遠慮下さい!」
そんな気は全くなかったが、こうもビシッと釘を刺されては萎縮もする。俺だけではなく、その場にいた男たちもみんな小さくなっている。
「それじゃ、授乳に行ってきまーす!」
そんな俺たちに笑顔を向けためぐちゃんは、まなと共に部屋の外へ消えていった。
「めぐのやつ、すっかりママだな……」
彼女を見送りながら悠斗が呟いた。
「……おれたちも負けてられねえ。な、翼?」
「ああ。だけど焦らず、ちょっとずつ、な。なんてったって子育て期は長いんだから」
「……今度は長いといいな」
「大丈夫。きっと長いさ」
俺は悠斗に手を差し出した。
「よろしく頼むよ。一緒に、まなの父親やってこう」
「こっちこそ、よろしく」
悠斗は言って、俺の手を両手で包み込むように握りしめた。
―― あっとほーむ~幸せに続く道~ 第三部 完 ――
第四部に続く
💖本日も最後まで読んでくださり、ありがとうございます(^-^)💖
あなたの「スキ」やコメント、フォローが励みになります。
ぜひよろしくお願いします(^-^)
感想お待ちしてます!
「あっとほーむ~幸せに続く道~」第一部・第二部本編はこちら
いつも最後まで読んでくださって感謝です💖私の気づきや考え方に共感したという方は他の方へどんどんシェア&拡散してください💕たくさんの方に読んでもらうのが何よりのサポートです🥰スキ&コメント&フォローもぜひ💖内気な性格ですが、あなたの突撃は大歓迎😆よろしくお願いします💖
