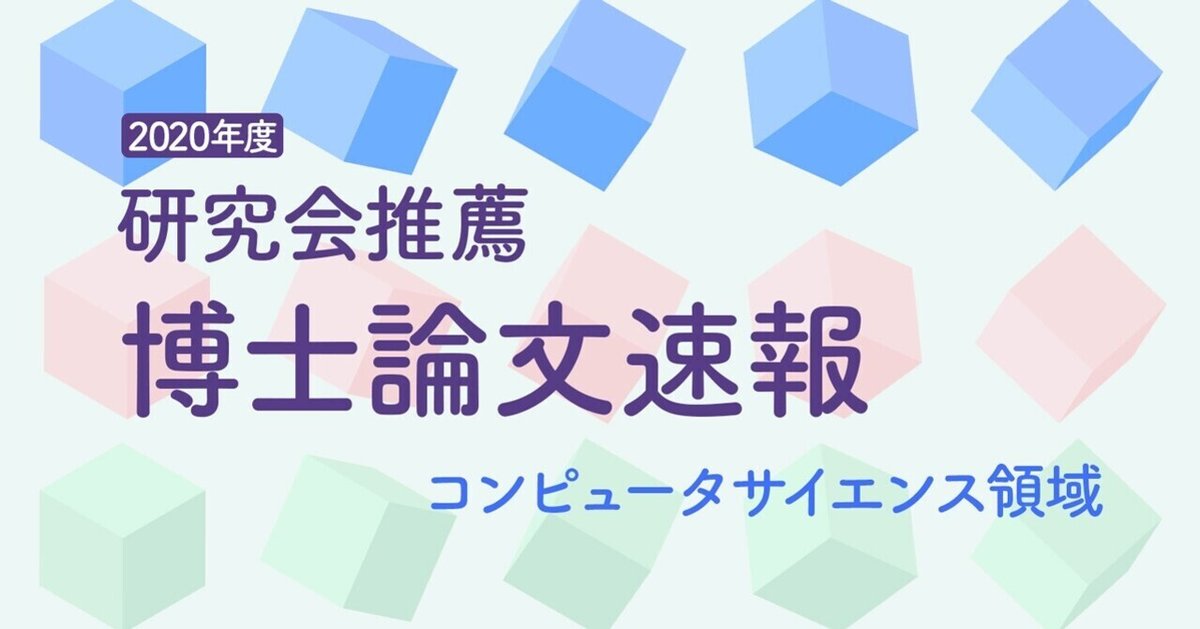
プロダクトライン開発における可変性モデル化手法とシステム構成導出への応用の研究
新原敦介
((株)日立製作所 研究開発グループ 主任研究員)

------------------ keyword ------------------
複合システム
可変性分析
システムテスト
----------------------------------------------
【背景】複合システムにおいて,個別に派生開発されるサブシステムの組合せ数は膨大
【問題】膨大なシステム構成の全テスト実施は工数的に不可能
【貢献】テストを実施すべきシステム構成を体系的に導出
本研究では,単独の機器で機能を提供するのではなく,複数のサブシステムが接続され連携して機能を提供する複合システムを対象とする.サブシステムはそれぞれに派生開発(既製品をベースに改造・拡張開発)されており,廉価機・普及機・高級機などのバリエーションによって機能に細かい差が生じたり,容量が異なったりする.そして,これらのサブシステムが組み合わさった複合システムには,どのサブシステムが何台つながっているのかというバリエーションが生じる.さらに,サブシステムの組合せ方によって,複合システム全体で提供する機能にもバリエーションが生じる.
このような複合システムを出荷する際,理想的には生じ得るすべてのサブシステムの組合せで動作を確認するテストを行いたい.しかし,実際にはサブシステムの組合せ数は膨大となり,すべての組合せのテストは現実的には実施困難である.そこで,テストの確認項目ごとに,サブシステムの組合せを限定してテストを実施する必要がある.長期にわたる派生開発によって蓄積されたテスト項目を実施するためには,テスト項目ごとにどのサブシステムの組合せでテストすべきかを導出することが困難という課題がある.そして,テストを実行する際に,サブシステムの組み換えは,機器の移動や接続の切り替えや初期設定のやり直しなどによって,非常に工数が高い.そのため,複数のテストを実施する際に,サブシステムの組み換え回数を極力少なくしたいという要求がある.
既存の方法には,複合システム向けのバリエーションを管理しやすい形で記述する方法がなかったため,本研究では,まず,バリエーションを分析し表現するための可変性モデル(製品の機能や特徴の共通箇所や差異を整理・記述するもの)を用いて,複合システム全体とサブシステムの組合せ方やシステム全体の機能を表現するための,複合システム向け可変性モデルを提案した.そして,その複合システム向けの可変性モデルを用いて,テスト項目ごとに実行可能なシステム構成(サブシステムの組合せ)を導出し,テスト項目すべてを網羅する少ない数のシステム構成の組を導出する手法を提案した.
提案した可変性モデリング手法に関して,多くのサブシステムで構成される業務用空調機やPOSレジシステムを例に,被験者実験を行い,提案手法の効果を確認した.その結果,提案手法を用いない方法では,テスト項目を網羅するシステム構成を導出できなかったのに対し,提案手法を用いればテストケースを網羅する少ない数のシステム構成が導出できることを確認できた.

(2021年5月27日受付)
(2021年8月15日note公開)
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
取得年月日:2021年3月
学位種別:博士(工学)
大学:東京工業大学
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
推薦文:(ソフトウェア工学研究会)
本論文の主要な貢献に 1)新しい可変性モデリング手法の提案と 2)テストケース生成への応用があり,これらは産業界の需要を色濃く反映している.事例分析にとどまらず,最終的に一般性のある手法としてまとめ複数の論文誌に掲載されている点でも優れている.プロダクトライン開発研究の未来につながる博士論文として推薦する.
新原敦介(正会員)
研究生活:本研究は,2008年に企業の開発現場で発生していた課題を一般化して取り組みを始めました.それから,トップエスイーの修了制作とノルウェー留学で発展させ,社会人博士として5年半を費やし,博士論文にまとめさせていただきました.足掛け13年と時間はかかりましたが,心が折れても継続することの重要性を感じております.
本研究の推進ならび博士論文をまとめるにあたり,多大なご指導をいただきました佐伯元司教授,林晋平准教授,鷲崎弘宣教授,オイステン ホウゲン教授に,心よりお礼申し上げるとともに,企業における研究開発を指導していただいた職場の皆様に感謝いたします.
