
18-3.参加してみよう!オンライン事例検討会
(特集 今こそオンラインで技を磨こう!)
高山由貴(東京認知行動療法センター)
interviewed by 下山晴彦(東京大学教授/臨床心理iNEXT代表)
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.18
〈参加者募集中〉平木典子先生オンライン事例検討会
平木典子先生をコメンテーターにお迎えして,若手心理職対象のオンライン事例検討会を実施します。事例発表をしないオブザーバー参加もできます。貴重な機会ですので,若手の皆様には,ぜひ積極的にご参加いただければと思っています。
【目的】どのような分野や職場でも必要となる心理職の基本技能向上をテーマとします。若手の皆様が安心して技能学習ができる場を提供します。
【日程】2021年6月6日,6月27日,7月11日(いずれも日曜)
13時〜17時です。
【詳細】参加条件や申込み方法などは,下記の臨床心理マガジンをご参照ください。
https://note.com/inext/n/nced56120d0d5
1.オンライン事例検討会を活用する
今回は,オンライン事例検討会(ケース・カンファレンス)を上手に活用するコツをお伝えする。“上手に活用する”というのには,次の2つの意味がある。
①「参加者として,自身の技能向上のためにオンライン事例検討会を利用する」
②「主催者として,参加者の技能向上に役立つオンライン事例検討会を運営する」
これまでの日本の事例検討会では,同じ学派内や職場内での事例検討会が中心だった。例外として学会などで,さまざまな立場のメンバーで参加しての事例検討会が開催された。そのような場では,各参加者が自分の立場から意見を主張したり,発表者を批判したりすることがみられ,生産的な議論にならないことが散見された。逆にスーパーバイザーのご意見拝聴になったり,参加者が発表者をやたら褒めて議論が深まらないといったこともあった。
そこで,臨床心理iNEXTでは,PCAGIP法※を参考にして,事例の理解を深めるために参加者とコメンテーターが協力して建設的な議論を深めるための事例検討会の方法を開発した。そして,さまざまな立場のメンバーをオンラインで募集し,今年の1月から5月にかけて臨床心理iNEXTオンライン事例検討会を実施した。
※ 『新しい事例検討法 PCAGIP入門──パーソン・センタード・アプローチの視点から』(村山正治・中田行重(編著)2012,創元社)
⇒https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=3618
今回は,この臨床心理iNEXTオンライン事例検討会にメンバーとして参加し,事例発表もされた高山由貴さんにインタビューをし,技能向上のための事例検討会活用について体験的に語っていただいた。以下に,高山さんとのインタビュー記録を掲載する。
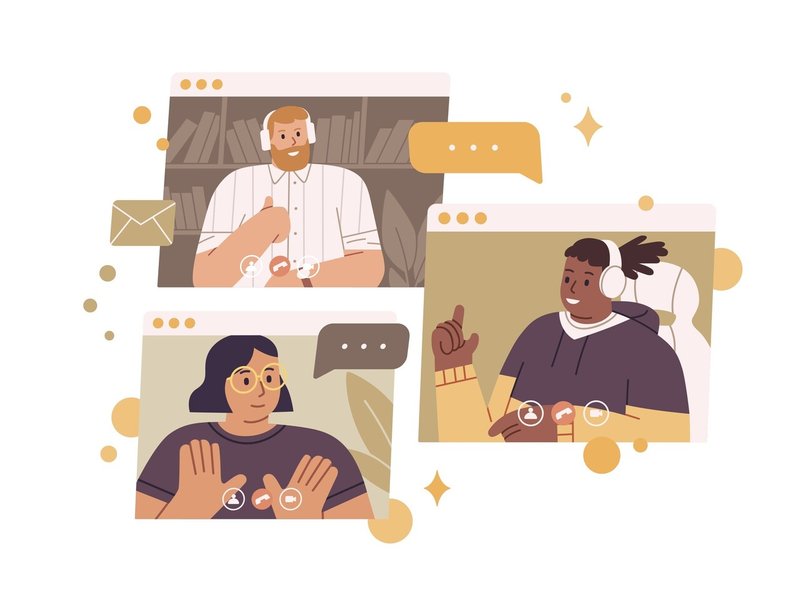
2.事例検討会は,心理職の必須事項!
──オンラインに限らず,対面の場合も含めて事例検討会に参加する目的はどのようなものか。どのようなことを期待して事例検討会に参加されたのか。
学生の時は,多くの事例に触れたいと考えて参加していた。他の心理職の発表事例を聴いて,いろいろな問題や方法を知ることができた。現場で心理職として働くようになると,事例検討会の意味が変わってきた。心理療法を個別に担当する職場に勤めたので,他の心理職の意見を聴くことが難しかった。「これでよいのだろうか」と迷いながら仕事をしていた。そのため,事例検討会で他の心理職から意見をもらい,自分のやり方を確認したり,修正したりする必要があった。
現場での経験が長くなると,臨床に慣れてきて,手前味噌になって自己満足する傾向が出てきた。実際には,同じことを繰り返しているだけなのに,「これでよいだろう」と思う傾向が出てきた。しかし,同時に「同じことをやっているのに,最近はクライエントさんの反応があまり良くない」ということが気になるようになってきた。そのことに気がついて,自分では意識できていない問題点を事例検討会でオープンにみてもらいたいと思うようになった。このような点で事例検討会への参加は,心理職にとっては必須業務と考えている。
──学生時代だけでなく,初心の頃は,事例検討会に出てみると,確かに「こんなケースがあるんだ!」という驚きや発見がある。心理職として仕事をするようになると,常に技能向上をして有効な心理支援を提供する責任が出てくる。しかし,チームで活動する職場ではなく,個別に心理療法や心理支援を担当する職場では,秘密保持のこともあり同僚であっても,安易に担当ケースの相談をしにくい。そのような場合,固定化やマンネリ化が生じ,「こんなものでいいだろう」という慣れもでてきてしまう。だからこそ,心理職にとっては,事例検討会は必須となる。

3.オンライン事例検討会の特徴
──コロナ禍によって“オンライン”での事例検討会が広まってきている。対面での事例検討会とオンライン事例検討会の違いをどのように感じたか?
オンラインになることで,事例検討会に参加する敷居が下がっている。事例検討会の会場まで移動しなくて済むので時間という点で効率的。最近は,オンライン研修も増えてきて,気楽に参加するようになった。事例検討会もそれと同じで物理的には参加しやすい。
ただ,事例検討会は,研修会と違って,参加者との関係性が大きく影響する。対面の場合は,事例検討会の会場に行って,初対面の人とは挨拶したり雑談をしたりして関係作りができる。オンライン事例検討会では,知り合いでない人が参加する場合には,その関係づくりの経験ができない。そのようなメンバーの関係のあり方が事例検討の場に影響を及ぼすかと思う。
──すでに知り合いの仲間で事例検討会をするのと,知り合いでないメンバーで事例検討会をするのでは検討会のあり方は大きく違ってくる。
そこは大きく違う。今回の臨床心理iNEXTのオンライン事例検討会のメンバーは,全国からオンラインで参加してきた心理職で,お互いに全く知らない人だった。それにもかかわらずに事例検討会の雰囲気が良く,自由に議論ができたのは運営側の工夫があったからだと思う。
iNEXTのオンライン事例検討会では,事前に主催者側から事例検討の進め方のルールの提示と説明があり,メンバーの役割も決められており,上手に構造化されていた。最初にメンバーの自己紹介をした。コメンテーターの大谷彰先生は,米国のご自宅からのご参加で愛犬のワンちゃんの写真を出していただいたりして,和気あいあいとした雰囲気でメンバーの人となりを知っていくことができた。

4.安心できる場作りが必須
──知らない心理職が集まるオンライ事例検討会では,グループ作りというか,チーム作りがどれだけうまくできるかがとても重要となる。私が参加していた事例検討会も,コロナ禍になりオンラインで実施することになった。メンバーはお互いによく知っている関係であったが,オンラインになることで発言のタイミングがつかめずに沈黙が多くなった。発表者もどのくらいわかってもらえるか不安で事例発表の情報量が多くなり,ほとんどの時間を事例経過の説明で終わってしまったしまった。知り合いのメンバーでも発言するのに勇気がいるので,お互いに知らないメンバーによるオンライン事例検討会では,参加者がどれだけ安心できる場を作ることができるかが重要となる。
その点で参加メンバーの安心できる場作りを重視するPCAGIP方式を取り入れたのは良かった。本方式では,必ず一人一回は質問しなければならないということで発言の機会が確保されていた。それで発言の敷居が下がった。しかも,それが事例発表に対する意見を言うのではなく,事例発表の内容に関して質問をするというルールにしたのがとてもよかった。意見だと,批判になりかねない。質問することで一緒に問題理解を深めるという体制ができる。
──臨床心理iNEXTオンライン事例検討会では,グループ作りをかなり意図的に行った。大谷先生と私は,長い付き合いなのでエンカウンターグループの共同ファシリテーターのように安心できる場作りを第一に重視した。PCAGIP方式の「批判しない」という原則はとても重要であると思う。
メンバーは,まず質問をすることをルールにしたのがよかった。質問は,正しい質問と間違っている質問という区別がない。そのため発言しやすい。しかも,質問する内容には,その心理職個人の臨床観やバックグラウンドが現れている。それと自分の質問を比較することで,自分の癖や他者の視点に気づくことができる。メンバーが質問を重ねていくことで,事例理解を深めていける点が,今回のオンライン事例検討会の肝(キモ)だと思う。

5.多様性を活かす質問タイム
──今回のiNEXTオンライン事例検討会には,本当に多様なバックグラウンドの心理職が集まった。分野も学派も専門領域も職場もほぼ全員が異なるメンバーだった。その多様性がどのように討論に影響するかが心配であり,課題であった。今のお話から,場を作ることも大切だが,“質問をする”ことが皆で協力して問題理解を進めることがとても重要であるとわかった。多様なメンバーだけに,意見の言い合いになって「それは違うだろ」となると,事例検討の場がバトルになる。そうでなくて,質問は「事例についてもっと知りたい」ということで共通しており,皆で協力して事例情報を集めていく仕組みが出来上がっていく。
本当にそう。認知行動療法では,同じものでも見方によって理解が違ってくることを強調する。それにも関わらず,臨床現場で仕事をしていると,一方通行の見方になってしまうことがある。多様な質問を通していろんな視点で事例を見ることができるようになる。もう1つ良かったのは,最後に結論をひとつに決めつけないで余地を作り,発表者に委ねている。多様性が生かされている感じがあった。
──コメンテーターの大谷先生も権威的に決めつけることはない。皆で情報を探って理解を深めながら,「こんなところかなぁ」というところに落ち着いていく。
そうですね,ふわっとした感じで。
──質問をするというプロセスの中で疑問点も出てきて,いろんな分野の人がいるから知識も出してくれる。私にとっては,障害年金や地域のネットワークなど,福祉分野のメンバーからの情報はとても勉強になったし,役立った。
そこが職場での事例検討会と一番違うところ。多様なメンバーだからこそ,新しい視点や知識を学ぶことができる。
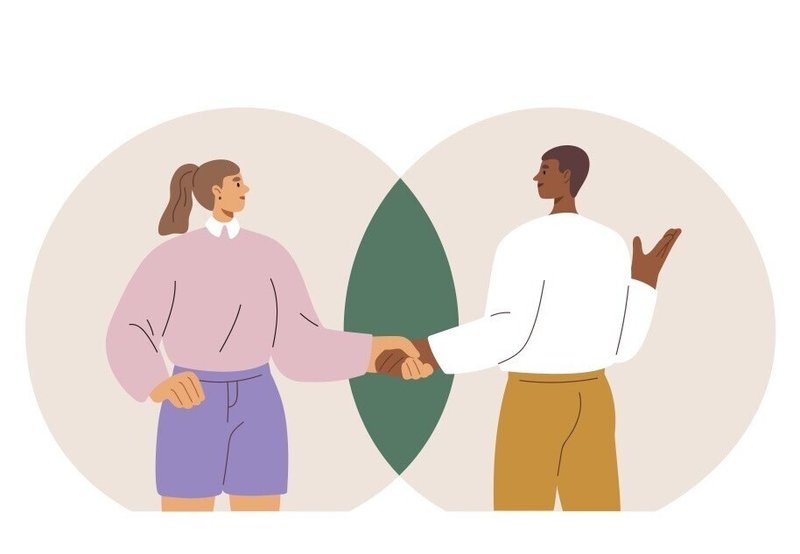
6.リスクをチャンスにする
多様なメンバーの事例検討会にはリスクもある。学会の事例発表などでは,特定の参加者が自分の意見を延々と話して終わってしまということもあった。多様性はリスクにもなる。混乱したり批判されたり危険性をどう回避するかが課題だと思う。
──リスクをチャンスにしたい。多様性の中から心理職の共通の専門性を探っていきたい。今の日本の心理職は,安心できる派閥や仲間の中で引きこもって自分を保とうとしている。そのため派閥争いが生じてバラバラになっている。さらに,臨床心理マガジン17-4でも指摘したように公認心理師制度の導入で分野別の縦割りが進み,心理職の専門性とは何かといった議論ができない危機的な状況になっている。
臨床心理マガジン17-4⇒https://note.com/inext/n/n6f40d652adb2
──分野や派閥が違っても,お互い切磋琢磨して専門技能を磨ことができれば心理職の専門性が高まる。だからこそ心理職の発展に向けて,多様な心理職が同じ土俵で議論するためのルールと場作りどうするかが緊急の課題になっている。江戸時代は,江戸の三道場に代表される各道場が,各流派の剣術の流儀に従い,それぞれ腕を磨いていた。しかし,道場間での手合わせは,真剣や木刀での勝負では殺傷沙汰(いわゆる道場破り)となり遺恨が残るために他流試合は禁止されていた。そこに竹刀打ち込み剣術(つまり今の剣道)が提案された。その結果,安全に試合ができるようになり剣術が興隆したという歴史がある。
⇒参照ウェブサイト:武道ワールド「新流の台頭と江戸三大道場」
──それと同様に安全な事例検討の場があれば異なる学派や分野の間で議論をすることができ,その経験によって心理職の専門性は高くなっていく。逆に現在のように狭い派閥や職場に内に留まっていると,心理職の発展がないように思うが,どうだろうか。
私が参加した臨床心理iNEXTのオンライン事例検討会は良かった。参加したメンバーには「知らないことを学びたい」,「自分の技能を向上させたい」という貪欲な姿勢があった。しかし,そのようなメンバーが集まらない可能性もあると思う。

7.グループとして成長する
──ご自身が担当する事例を発表してみて,どのような経験となりましたか。
いろんな視点が得られたというのも大きい。それ以上に検討してくださった皆さんが応援してくださっている感じがあった。その後にその事例のクライエントさんにお会いした際に,落ち着いて臨めた。事例自体は,クライエントさんと家族が大喧嘩をして大変な状況になる展開だった。でも,事例検討を通して,その家族との対立自体の意味がわかっていたので,安心して対応できた。他の人だったらどう見るかと考えながら対応できた。事例検討会での皆さんの視点が内在化できた。
──事例への理解も深まったということなのか?
深まったこともあるが,一人でやっているけど何となく一人じゃない感じがあった。事例検討会のメンバーがついている感じがあった。
──PCAGIP方式は,エンカウンターグループの理念や方法を組み込んでいる。グループで成長していくことを重視している。グループでメンバーの成長を支えるということが目標。知識や視点が増えることもあるが,メンバーが一緒にケースに取り組む経験をグループですることに意義がある。
今回のオンライン事例検討会は,5回だけだったが,仲間意識が生まれた。そのようなグループ体験をしたことが,事例の関わり方にも良い影響を与えた。
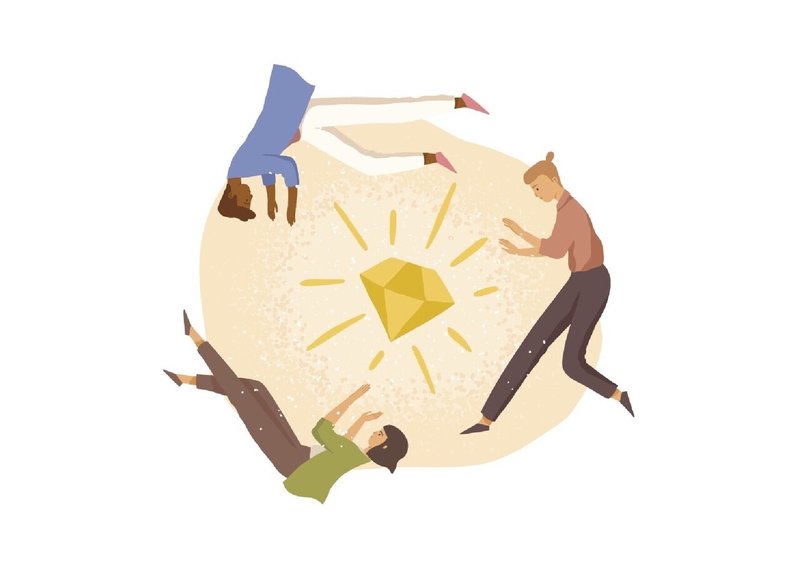
8.心理職にとって大切なこと
──派閥や分野,専門領域を越えたオンライン事例検討会に参加して,心理職に共通して大切なものは何かについて気づいたことがあれば教えてください。
参加に皆さんに共通していたのが,クライエントさんの良さに目を向けるということだったと思う。メンバーの皆さんは,クライエントさんの味方に立って検討している感じだった。たまたまそういう方が集まったからかもしれないが,参加者同士だけでなく,クライエントさんを批判しない感じがあった。そうすると,事例検討の場が,前向きで良いものになっていく。それは共通していたと思う。
──なるほど。クライエントさんの資源や可能性をみていく視点の重要性ですね。私としては,それに加えて生物的な情報をみておく視点も大切と思った。発達障害の傾向や,複雑性PTSDも含めてトラウマ経験などは,問題の素因として存在している場合がある。それが,表面には見えにくい。しかし,問題の根底に素因が有る場合には,症状や診断にとらわれず,その影響を把握しておくことの重要性を感じた。
症状や問題行動といった表面的な問題の根底にある素因をみておくことですね。そのような素因ゆえの“生きにくさ”を確認することで「ああ,そうだったのか」ということでクライエントさんの苦しさが理解できる。クライエントさんをもっと応援したくなる。
──「このような素因を抱えてよく頑張ってきたな」となる。今回のオンライン事例検討会では,そのような議論が多かった。あと,地域のネットワークを大事にする視点も広がった。

9.地域の資源を活用する
メンバーの中には地方の地域に根ざした支援をしている心理職が比較的多かった。面接室にこもらずに,気軽に地域に出ていく支援の方法を学んだ。クライエントさんに同行して病院や職業紹介所に行くこともしている事例もあった。ちょっと羨ましくなった(笑)。特定の職場で働いていると,いつの間にか「自分の仕事はここまで」という枠を作ってしまう。他の心理職の話を聞くと,自分で勝手に作った枠や限定を問い直すチャンスにもなった。そこがすごく良かった。
──私が所属する大学では個人心理療法の発想や訓練がベースになっている。そこでは,現場の中での人々のダイナミックな動き,ネットワーク,さまざまな資源がたくさんあることをどのように活用するかが重要となる。そのことを学んで自分の狭さが見えてきた。
社会に直と繋がっている臨床活動がある。社会に根差した心理支援がみえてきて勉強になった。改めて,いろんな研修会や事例検討会に参加する機会が必要と感じた。似たような仲間や先生に教えてもらっていると,狭い枠から出られない。枠から出たいとすると,そこから一歩出て,異業種交流のような機会をあえて作っていったほうが良いかと思う。それは,誰が来るか分からない事例検討会に出る意義でもある。

10.若手心理職に期待する
──平木典子先生をコメンテーターにお招きしての,若手心理職のための事例検討会を企画した。その中で若手は,力付けたいという気持ちがある一方で,自信がなくて自分の知らない人が参加する場に参加するのが怖いという気持ちがあるのではないかと思う。結果として,若手心理職のほうが内向きになり,チャレンジをしなくなっている傾向があるのではと心配になっている。
若い人のなかには,関心がある情報はネットで得られるからそれでよいと閉じてしまっている人もいるかもしれない。だからこそ,普段付き合わない人と敢えて付き合ってみることを勧める。それができるのは,もしかしたらオンラインの場なのかもしれない。自分の体験も踏まえて言うならば,若手心理職には,敢えて知らない,自分になじみのない心理職の人と話してみてほしい。私は,今後も異業種交流や安全な他流試合を今後もやってみたい(笑)。それによって,個人で勉強しているのでは得られない経験ができるのではないかと期待している。
──オンラインには多様性がぶつかり合うリスクもあるので,若い人がチャレンジできるような安全な場を提供することがまず必要ですね。
安全な場であるとともに多様な意見を許容する場であることが重要だと思う。

11.オンライン事例検討会について
今回のインタビューで話題となった臨床心理iNEXTオンライン事例検討会については,下記オンラインセミナーで詳しく解説する。関心のある方は,ぜひご参加ください。
対話集会型オンラインセミナー
======================================
なるほど活用術!オンライン事例検討会
─ケース・フォーミュレーションを学ぶために─
======================================
[日時]2021年5月30日 9時~12時
[主催]臨床心理iNEXT+遠見書房
第1部 オンライン事例検討会の活用術
1.海外におけるオンライン事例検討の現状と課題
2.オンライン事例検討会の上手な進め方
3. コメント:事例検討会とケースフォーミュレーション
第2部 オンライン事例検討会の発展に向けて
4.オンライン事例検討会を経験してみて
5.鼎談:オンライン事例検討会の発展に向けて
[参加費]
・臨床心理iNEXT会員(フロンティア会員含む):無料
・臨床心理iNEXT会員以外:1,000円
[申込み]
・iNEXT会員⇒https://select-type.com/ev/?ev=i_fXOg12y-o
・iNEXT会員以外⇒https://select-type.com/ev/?ev=_JPVyd1MeAc
なお,オンライン事例検討会については,臨床心理マガジン18-1号で解説している。
⇒https://note.com/inext/n/na1edbec35ceb
■デザイン by 原田 優(東京大学 特任研究員)

(電子マガジン「臨床心理iNEXT」18号目次に戻る)
====
〈iNEXTは,臨床心理支援にたずわるすべての人を応援しています〉
Copyright(C)臨床心理iNEXT (https://cpnext.pro/)
電子マガジン「臨床心理iNEXT」は,臨床心理職のための新しいサービス臨床心理iNEXTの広報誌です。
ご購読いただける方は,ぜひ会員になっていただけると嬉しいです。
会員の方にはメールマガジンをお送りします。
臨床心理マガジン iNEXT 第18号
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.18
◇編集長・発行人:下山晴彦
◇編集サポート:株式会社 遠見書房
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
