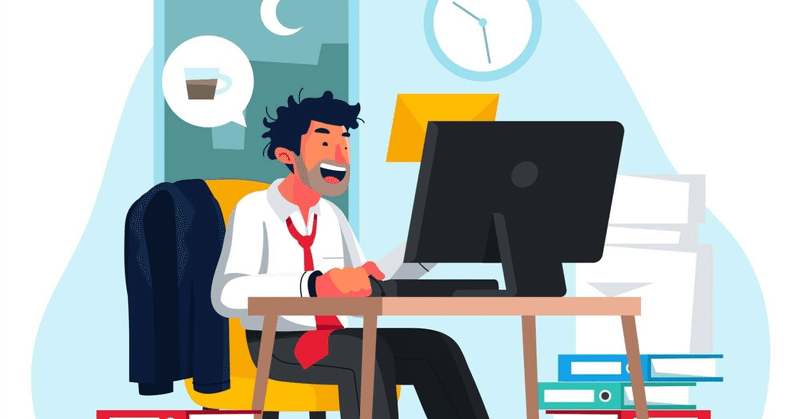
能力給・出来高制で、残業は自由選択へ。
なぜ、「ノー残業デー」はあるのか? 残業が常態化しているので、働き過ぎを防いだり、仕事の効率を高めるためである。とは言うものの、強制力はなく、多くの会社で形骸化している。その原因はどこにあるのか。
決算期・繁忙期の残業は仕方のないことだとしても、日常的に残業をしなければならないのはなぜか。
理由はさまざま。
・仕事量が膨大で、定時内では処理できない。
・上司が残っていると、自分だけ帰ることはできない。
・残業が当たり前になっていて、定時帰宅の雰囲気ではない。
・基本給が安いので、残業で稼がないと生活できない。
・仕事が遅いので、仕方なく。
人それぞれに違った理由があるにも関わらず、みんなが同じように残業をしている。実に不思議である。
そもそも「ノー残業デー」を作ること自体が間違っている。9時〜5時という、決まった就労時間があるのなら、できる限り守るべきである。
仕事量が多過ぎるなら、それは会社運営のシステムに不備がある。自分だけが帰ることができない雰囲気は、職場環境の不備。基本給が少ないのも会社の問題。仕事が遅いのは、本人の問題だが。
これらはすべて、根本的な改善策を講じるべきものであって、「ノー残業デー」で誤摩化すものではない。
残業せずに会社と従業員が儲かるようにすることが理想ではあるが、それは現実的ではない。競争の激しい社会では、残業をしてでも、より多くの収益を上げなければならない。ならば、残業に正当な理由があれば良いのではないか。従業員が納得して、居残りを選択するような理由が。
それは、『能力給・出来高制』ではないか。
働いた質と量に合わせて、給料を支払う。レベルの高い仕事をした者は、高給優遇。質が眼に見えにくい職種の場合は、仕事量で判断する。やったことに対する正当な報酬が貰えるなら、不平等感もなく、残業も苦にはならないだろう。
もし、自分は仕事が遅いと思うのなら、残業をしてカバーすれば良い。能力給・出来高で給料が決まるのなら、「残業で稼いでいる」と言われる心配もない。
みんなが仕事内容に対する正当な報酬を貰えるようにすれば、やる気も出て、仕事の効率も高まるのではないか。みんなの能力が上がれば、会社の業績も上がり、残業も少なくなる。「ノー残業デー」など、必要無い。
よろしければサポートをお願いします!頂いたサポートは、取材活動に使わせていただきます。
