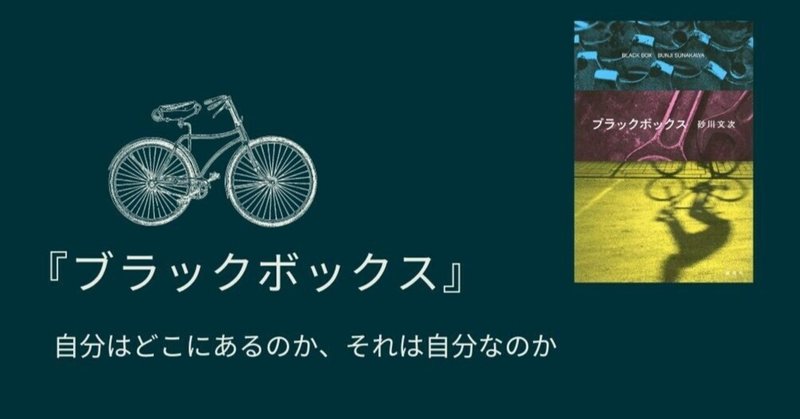
『ブラックボックス』自分はどこにあるのか、それは自分なのか vol.510
現代の若者を描いた本。

第166回芥川賞受賞作。
ずっと遠くに行きたかった。
今も行きたいと思っている。
自分の中の怒りの暴発を、なぜ止められないのだろう。
自衛隊を辞め、いまは自転車メッセンジャーの仕事に就いているサクマは、都内を今日もひた走る。
昼間走る街並みやそこかしこにあるであろう倉庫やオフィス、夜の生活の営み、どれもこれもが明け透けに見えているようで見えない。張りぼての向こう側に広がっているかもしれない実相に触れることはできない。(本書より)
気鋭の実力派作家、新境地の傑作。
一見、なんでもないただの青年の毎日を描いているような本ですが、なぜかその内容は我々読者を物語の世界へと引き込み、どこか悲哀と共感、焦燥感を駆り立てる。
そんな不思議な本です。
このブラックボックスを読んで感じたことをまとめます。
自分は自分なのか

自分は本当に自分なのか。
自分でもよくわからないそんな問いかけ。
でも、そんな瞬間は誰にでもあるのではないでしょうか。
カッとなってしまった時、自分ではコントロールしきれない感情が発生した時、本書ではそんな場面が頻繁に出てきます。
そしてそんな時、たいてい主人公の立場は変わってしまいます。
おそらく、いわゆる何かを持っている人物なのでしょう。
カッとなった時に理性が抑えきれずに本能が無意識下で顔を出してします。
これはもう、自分ではどうにもできない。
そんな特性なのだから、そんな自分を理解して生きていかないことにはどうしようもできない。
それが分かるからこそ、一概にこの主人公に対して嫌悪感を抱けずに読み切ってしまいました。
自分が本当に自分なのかわからなくなってしまうのです。
変えたくても変えることを拒む世の中

そしてそんな自分を治そうと誰でもそう思うはずです。
でも、世の中はそれを望んでいない、というより全くもって興味がないのです。
だからこそ、不意にそれを治そうとする本人の邪魔をしてしまう。
いや、邪魔をしていないのかもしれないけれども、世の中が邪魔をしているように見えてしまう。
しかしそれは、変わりたくないという自分の安全領域に縛り続ける何かの心の甘えの部分でもあるのかもしれません。
そんな葛藤に溢れた世の中、いずれ主人公は全てを投げ出したくもなってしまいます。
そして最後には自分の感情ととことん向き合い、その感情の言うことを聞くと言う所作に移る。
そんな人間的な有り様を書いた本なのかもしれません。
どこでもいい、何も聞こえないその場所まで

だからこそ、
ずっと遠くに行きたかった。
今も行きたいと思っている。
なのでしょう。
自分の意思が邪魔をしない、ただ言われた与えられた生物的な指令を受け入れ続ければ住む場所へ。
もしかしたら、この本ではそんな人間の本来あるべき特有の欲求にとことん向き合った視点を表していたのかもしれません。
何を描きたいのかがいまいちパッとしない、物語として大きな転機がところどころ現れるわけでもない。
それでもなぜか読み進めてしまう。
ここには何かしらの引き付ける魔力があるのでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
