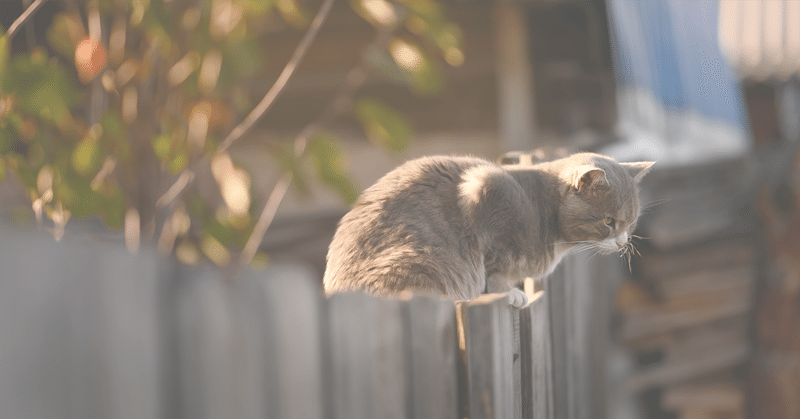
「ガッタン、ガッタン」と「ヨッコラショ」の境目と、ビジョン・組織文化の役割
ここしばらく、マンションの外に置かれた吸水ポンプの騒音に悩まされていたけど、その原因が分かってみると、それまでとは「騒音」の聞こえ方が違って感じられた。
何が原因なのか? どんなプロセスから違いが生まれたのか?
そんなことを考えていたら、チームや組織におけるビジョンや組織文化って、こうした変化を生み出す役割を果たしているんじゃないかと思えてきた。
ポイントは、「象徴的な意味」が生まれるメカニズムとプロセスだ。
「ガッタン、ガッタン」と「ヨッコラショ」の境目
ちょっと前からマンションの外に置かれた吸水ポンプの調子がおかしい。
しょっちゅう「ガッタン、ガッタン」と、けっこうな音がする。昼間はそうでもないけど、夜、寝るころにこの音を耳にするとなかなか眠れない。イラッとする。
というわけで、業者に点検してもらったところ、原因はどうやらポンプ内の水圧の低下にあるらしい。
低下した水圧を上げようと、機械が起動するときに『ガッタン、ガッタン』の音が出ているんだと思います
そう聞いて、それまではつねにイライラを引き起こしていた「ガッタン、ガッタン」の音がちょっと違って響くようになった。
「うわっ、水圧、低下してんじゃん! ポンプ動かさなきゃ、ヨッコラショ!」
血相を変えてポンプを動かそうとする給水ポンプのつぶやきが、ほんの少しだけ聞こえるような気になったのだ。
もちろん、ぜんぜん気にならなくなった、ということじゃない。
でも、「何だコイツ、誰だ?」な音が、「素性は知っていて、ちゃんと会ってはいないけど何度か見かけたことがある人」くらいに自分に近づいたようで、気になる度合いがだいぶ減ったような気がする。
耳にする音に何を聞くのか
「ガッタン、ガッタン」の受け止め方が変化したことを面白がっていたら、たくさんの町工場が集まる街の市役所に勤める人から、こんな話を聞いたことを思い出した。
工場が騒音対策にしっかり取り組むようになって騒音の苦情が減ったかというと、じつはそうでもないんですよ。
その人がいうには、通りに面した工場が騒音対策なんてぜんぜん気にしないで、開け放しで作業をしているころは、近所の人も、どんなおっちゃんが何をしているのか分かっていた。
だから、うるさいのはうるさいんだけど
こんな暑い日に、板金のトンカチをカンカン叩いたり、ウィーンと旋盤を回したりするのもタイヘンだよな
みたいに感じていたから、すぐにそれが騒音に対するクレームにならなかったのではないか。
逆に、騒音対策がしっかりと行われ、「カンカン」や「ウィーン」が閉ざされたシャッターの向こうから聞こえるようになると、それが「何だコイツ、誰だ?」な音として響くようになる。
匿名の誰かが立てる音が一定のデジベル値を超えると、すべてが「騒音」として感じられて、イラッとする人が多くなる。
ビジョン・組織文化の役割
「ガッタン、ガッタン」が「ヨッコラショ」に変わったり、板金の「カンカン」や旋盤の「ウィーン」が単なる騒音になったりする境目はどこにあるのか?
それは、音=空気の振動に、それ以上の意味を読み取るかどうかだと思う。むずかしい言葉でいえば、音が象徴的な意味を持つかどうかだ。象徴的な意味とは、目に見えるもの、耳に聞こえるものから、単なる映像や音以上の意味が生まれてくるということ。
それって、チームや組織においてビジョンや組織文化が担っている役割と重なり合っている。
いま職場で起きていることが、これから向かおうとしている将来とどんな点でつながっているのか? これまでに歩んできた道のりとどう重なっているのか? そしていま仕事に取り組んでいる他のメンバーの働きと、どのように絡み合っているのか?
ビジョンや組織文化というのは、具体的に何なのかが語られるにしても、それをつくるために何をすべきかが語られるにしても、何かとボンヤリしがち。
しかし、大事なことは、チームや組織が単に「ガッタン、ガッタン」音を立てているのではなく、その一員である自分も含めて「ヨッコラショ」とがんばっている姿を思い起こせる形でつくること。
そして、メンバーの内側にそのつぶやきがつねに響きわたるように、単なる映像や音以上の仕事の意味を伝えていくことが大事なんだよな、と思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
