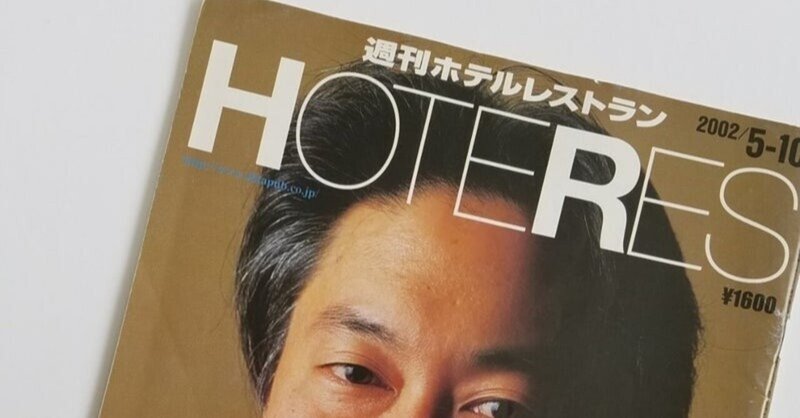
移転・新規開業。地方都市ホテルの挑戦。2001
「ホテル産業経営塾」卒塾論文・優秀賞
<週刊ホテルレストラン2002/5-10発行号掲載>
金原 榮

Ⅰ 序章・・・夢をカタチに
1983年10月に開業した茨城県水戸市のホテルは、市内を流れる一級河川・那珂川の河川敷に居を構え、白亜の11階建ての美しい姿を川面に映していた。この川は、ホテルにとっては格好の借景であり、そのむかしは献上鮭が遡上する川として、さらには水浴の場として周辺住民に愛される川であった。
しかし反面、頻繁に暴れ川へと変容する側面を持ち、かいわいに幾度と無く被害をもたらした。国と県は、これを解消すべく改修工事に着手し、ホテルはその18年間の役割を終えて、新天地へと移転することとなった。
閉館は2001年3月。その約5年前となる1996年には既に第一班のプロジェクトが編成された。並行して移転の候補地を絞り込む作業が行われていた。こうして18年間培われた実績とお客様の信頼をもとに、スタッフたちが夢に描いた理想のホテル実現への采は投げられた。

Ⅱ マーケットの素顔
県都水戸市の人口は約25万人。徳川御三家の一つ水府35万石の城下町として栄え、勤皇論と王政復古の先駆けとなった水戸学を生んだ。水戸を中心に、観光資源としての史跡も豊富にある。
水戸地域におけるホテル事業者は地場業者と大手のチェーンとが混在し、事業者数は約30、総客室数は約2,000室ある。特徴としてはJR水戸駅周辺に立地する中小規模のビジネスホテルが多いこと。
水戸市は日立製作所の関連企業や県庁所在地として大手企業の茨城支社・出張所が多いこともあり、宿泊者は地域外のビジネス客が大部分を占めている。反対に観光客や地域住民の縁故客が少ないといわれている。
県の観光・レジャーの実態を動向調査資料で見ると、年間の観光客数約2,300万人、うち宿泊者は17%の約400万人。このうち水戸市の宿泊者は約30万人となっている。利用交通機関別では鉄道が7%、貸切りバスが9%、自家用車が84%で、車による来県が圧倒的だ。
地方ホテルにとって一番の財源となるのはやはり婚礼である。その動向だが、まず、県人口が昨年300万人の大台に到達した。全国47県の中で最近5年間の伸び率が茨城県を超えているのは10県しかない。年齢別構成比でも相対的にバランスのとれた人口構成となっている。
つぎに96年の全国婚姻数は775,662件、人口千対の婚姻率は6.2である。茨城県はこれが17,553件、5.9となり全国の婚姻率をやや下回る。
この地域の結婚披露宴利用者の特徴を一言で表現するならば「一定規模の参加人数と豪華さやセンスの良さを求める比較的富裕で保守的な層」ということができる。
そして今後の傾向としては、都市型ホテルを利用する富裕層と、廉価な結婚式場を利用するエコノミー層との分離がますます拡大していくものと考えられ、事実そうなっている。
さて、98年の常陽地域研究センターの「茨城県民の生活行動圏調査」によると、「芸術・文化活動」では、定住人口25万人弱の水戸市が74万3千人の吸引人口を、また「紳士服・婦人服」などの買い物行動では78万9千人と、約80万人近くの交流吸引人口を持つという結果である。
ちなみに、水戸市民自身がどのような意識でこの都市を見ているかということに関しては、菅原信男 著「水戸発都市再生の実践的研究」の表現を借りたい。
快適さや余裕はないが、おしなべて衣食住が充足され、地方都市の良さと恵まれた自然環境がある。しかし活力、魅力がない。・・・都市の魅力とは、都市に哲学、信念、主張、ドラマ、感性、輝き、香り、温もりがあること、働く場、交流の場、眺める場、遊びの場、ショッピングの場、休める場、飲食の場があること、そして、市民にとって、ときめきや感動があり、快適かつ、楽しく面白いことである。
このように、ドラマ、感性、輝き、交流、ときめき、感動など、この書のさししめす数々の言葉のキーワードは、その後のわれわれの開発にとって重要な指針となった。

Ⅲ 私たちのお客様はいったい誰
土地の選定が終了するとともに、99年になるとプロジェクト要員も補充された。また並行して商圏設定とターゲット選定のための根拠の検証作業が開始された。いよいよわれわれの顧客探しがスタートしたのだ。
なによりもまず、合わせて総売上の70%以上を占める婚礼と宴会の売上に関しては、慎重な検証がなされた。婚礼の商圏ボリュームを予測する時にその根拠づくりの始めにあるのは人口である。
開業時の県人口をわれわれは309万人と予測した。これに先にあげた人口千対の婚姻率5.9を掛けて、予測婚姻数を1万8千件弱とする。さらに過去のホテルのシェアを掛け、まず一次の予測婚礼獲得組数を割り出した。
当然これだけでは根拠不足は否めない。次に商圏人口からの組数割り出しと市場の売上予測を試みた。これも先の「生活行動圏調査」から水戸の商圏人口を80万人と想定するところから始まった。
80万人の人口に対しては約4,700件の婚姻届出数があると考えられる。この数はわれわれのホテルの地理的商圏30km、ベスト10・実績地域5市4町1村の届出婚姻数5,400件強の約9割近くにあたる。充分な根拠である。
しかし、当然この全ての人たちが披露宴をするワケではない。披露宴をしない率は首都圏では30%、われわれの土地では20%と仮定して、80万水戸商圏では約3,700組強の披露宴がおこなわれていると想定した。
ところで平成9年度の国民一人当たりの宴会会合支出額は4万5千円。これに80万人を掛け、さらに0.295(宴会市場指数0.995の内の婚礼指数)を掛けると約106億円という水戸商圏の披露宴売上げが出てきた。
前記の組数とこの数字から商圏の平均的な一組の想定披露宴料金約290万円が算定された。しかし当然のことながらこの料金は、われわれが開発しようとするホテルの一組料金を下回った。
さて、旧ホテルのターゲット属性の中で特に際だっていたのが挙式者の年齢と、挙式者、列席者の居住地県外比率だった。新郎年齢は、全国平均28.5才に対して30才、新婦が26.6才に対して27才といずれも高く、挙式者の居住地の13%が、そして列席者の37%が茨城県外の方々だ。
われわれはこれらの資料から、新ホテルの挙式者像をつぎのように定義した。「ホテルの新郎新婦はグループの中でも年齢と学歴の高い二人で、東京に近い地域で生活し、または生活していた経験を持ち、友人・知人もその地域の方々がかなり多い。二人はモノ・コトに対するこだわりが強く、自分の主張をはっきりと持つ。さらに、嗜好や志向もハイセンスであることが多い。このような二人に提供する“婚礼”という商品は、夢を叶える自由度の高いセンスあふれるものである必要がある」。
そしてつぎに宴会市場の規模予測があった。都市の吸引人口の平均66万人と、同じく前出の宴会市場指数から婚礼指数を除いた0.7を相関指数とし、国民支出額4万5千円をそれぞれ掛け合わせて208億円/年という水戸商圏の宴会市場規模が算出された。
一般に新規の参入規模(マーケットシェア)は3%といわれ、ここから当該計画の宴会市場参入規模、つまり新ホテルの年間の宴会売上げは6億2,400万円とはじき出した。以上から発生して客単価、会場回転率等を加味しながら、適正と考えられる宴会場の収容規模を予測した。
いずれにしてもこと宴会に限らず、バブル経済崩壊後の景気後退と民間需要の低下、財政の悪化による公共部門の支出削減により、今後の売上げ予測は楽観されるものではなかった。
こうした検証に基づき婚礼同様宴会についても、その商品をつぎのように定義づけた。「宴会は一種の動機付け商品である。今後のマーケットの柱となる個人客に対応する小規模で機能性の高い宴会場を確保し、ソフトを合わせて開発することで、その受け皿を作る。また、法人利用に関しては、主客であるVIP対応の万全性をハードとソフトの両面から訴求し、幹事の歓心をあおる」。

Ⅳ 開発コンセプトを探して・・・1枚のハガキが伝えたもの
宿泊、およびレストラン等の料飲施設についても同様の検証作業が繰り返され、とくにレストランに関しては例外無く幾つもの難題が待ち受けていた。
しかし、われわれがそれ以上に悩んだのは、旧ホテルがその偉容を映し、借景として頂いていた「一級河川・那珂川」に代わるモノを、新ホテルの「何に求めるか」ということであった。
移転地として決定したのは、既に新県庁が移転するなどして今後発展が期待されている市の南部地区、郊外のありふれたバイパス沿いである。そして敷地には、保存が義務づけられた自然林が残っていた。
初期計画ではこの林は伐採され駐車場とする計画であった。規制の範囲の中で、どれだけの駐車台数を確保出来るのか。まさに一家に2台以上の車両を保有する車社会の地方都市における営業にとって、駐車場の収容台数は成功のための大きなファクターだ。
そんなある日、開発担当者のもとに一枚のハガキが舞い込んだ。移転地に近い町内に住むという退職教員からのものだった。
御社が経営するホテルが、この町の近くに移転するという話を新聞報道で知りました。あの場所は私が子供の頃よく父親に連れられて、夏はクワガタ取り、秋は栗拾いにと行った思い出の場所です。新緑のまぶしい春、秋の紅葉と四季折々に美しく姿を変えて私たちを楽しませてくれました。どうかそんな思い出の木々を伐採しないでください・・・
わたしたちは動かされた。そしてわたしたちが求めていたものがそこにあったことを同時に知ることとなった。
・・・林を残す・・・
プロジェクト会議の中で決議されるまでに、そう多くの時間はかからなかった。こうして、林は「森」という表現に衣替えされ、出発点である「森の中の迎賓館」というコンセプトが導き出された。
Ⅴ オペレーションストーリーの実現に向けて
コンセプトが確定すると、ハードの計画は堰を切ったように動きだした。
建物の高さを低く抑え、アトリウムを含めて外気に接する面を多く確保した配置計画。入れ子構造状に空間の中に別の空間をつくる構成。内と外の自然を一体化させたデザイン。その全てが「森の中の迎賓館」をスタートとした。
このハードにどんなソフトをという時に、なかなかそのイメージを全員に伝えるのは至難の技であった。そこでわれわれはオペレーションストーリーというものを作成し、それを経営会議とスタッフにプレゼンテーションした。
以下それを抜粋する・・・。
・・・緩いS字カーブの森を抜けると、風格のあるエントランスホールが待ち受けていた。
キチッとした制服を身につけたドアマンの白手袋に誘導されて、車をホテルの正面玄関に横付けする。ベルボーイの先導でロビーに歩をすすめると、そこはもう外界とは隔絶された『ヨーロピアンクラシック』の世界。
フロントレセプションに向かいながら、視線を左右に振り向けると、右手には陽光が燦々と降り注ぐアトリウムガーデンパーク。午後の時間をティーとスコーンで楽しむ上品なご婦人たちの小さな笑い声が聞こえる。
左手のロビーとバンケットを仕切るドアのずっと奥、ホワイエとおぼしき場所では、今まさに結婚披露宴が開いたばかりのようで、新郎新婦が大勢の友人達の祝福を受けていた。この玄関からのアプローチは、なんともエレガントでスプレンディッドな感覚のスペース。
フロントレセプションはアイランドスタイル。パーソナル対応のサービスコンセプトがうかがわれる。もちろんクイックチェックイン。ベルボーイに伴って歩くコートヤードが望める窓のある客室通路には、コーディネートされているのかわずかな香りが漂い、それが彼の動きにつれて攪拌され、彼自身が身につけたコロンとして流れ出したかのような錯覚を与える。・・・
こんなふうにオペレーションストーリーは全部門分作成された。開業したいま、あらためてこれを読み返してみるときに、大きくその物語とずれたのはレストランであった。
今回のホテルプロジェクトにおいてレストラン部門の刷新は、成功の鍵を握る大きな課題であり、それは衆目の一致する所だった。
われわれプロジェクトが提示したのは「ショーキッチンレストラン」。これは、レストランのマーケット環境分析から①時代がフードコートであること。②レストランがそのホテルの印象を決定づけてしまう事があること。③3~5年程度でのリノベーション、リニューアルが必要であること。
という前提をもとに、レストランコンセプトを「エキサイティング&エンターテイメント(雰囲気やサービスが一体となって商品として成立する)」とし、運営委託も選択肢に入れながら、導き出した方向性だ。
しかし、この考え方は、数々の協議の中で開業までに、そのハード、ソフトを含めて大きく転換することを余儀なくされた。誤解を恐れずに言うならば、わたしは個人的には、当初のコンセプト通りに各店舗が開店する姿を見てみたかったと今でも思っているひとりだ。

Ⅵ そして2001年11月開業
竣工レセプションのその日は、文字通りの晴天の一日となった。県内各地は言うにおよばず、全国からの総数2,000名におよぶ招待客で、新ホテルの館内は沸き立った。そして誰もがそのハードに驚嘆の声をあげた「ここは水戸じやない」と。
これを迎えるスタッフはそれこそその前後数日間、文字通り不眠不休で準備に明け暮れた。しかし、それを感じさせないほど若いスタッフ達は輝いていた。わたしは感動していた。言葉が見つからなかった。
その3日後には、われわれマーケテイング部門が仕掛けたプレスへのプレビューによって、新ホテルの開業はテレビ電波や各新聞・雑誌に乗り全国の注目を集めることとなった。
わたしも部門の責任者として何度かそうした媒体の取材を受ける機会に恵まれた。そしてその席では必ずこう答えた。
「私どもは地域の人々にとっての第二の邸宅として、機能していかなければなりません。自分の家ではできないけれど、このホテルに行けば、満足の行くおもてなしができるというようなホテルです。しっかりとした非日常感を打ち立て、それに沿ったサービスに力を入れていきたいと思っています。また、ホテルにはストーリー性とコロニアル性が必要だと言われます。ラッフルズホテルにサマセット・モームが長期滞在したように、当ホテルにも文豪が滞在する、などということになれば・・・これは私の夢ですね」。
鼻がツンと上を向いていた。


Ⅶ 最後に
こうして「ホテル産業経営塾」の卒業レポートのかたちをとって、地方都市ホテルの開業の顛末を、一部とはいえ残す機会が与えられたことを無上の喜びとします。しかし、真実はこんなモノではなく、もっとドロドロした毎日の連続でした。
それはわたしだけで無く、この開業に携わった多くの人間の偽らざる感想でしょう。だが開業というこのエキサイティングな経験は、それらの全てを払拭してあまりあるほどの達成感と感動を、わたしたちに与えました。
そして、この地方都市ホテルの開業は業界内でも一つの成功例として評価されたのです。もしきわめて個人的な話を許していただけるのであれば、最後に申し述べたいことがあります。
最初に準備室のスタッフはわたくしを入れて3名で構成されました。その中の一番若いスタッフの「妥協を許さないこだわり」がなければ、恐らくこのホテルのハードは、こんなに洗練されたものにはならなかったであろう。ということです。
わたしは意見の食い違いから彼と2ケ月間も口をきかなかったほど対立したこともありましたが、この一点において彼に負けました。
大きな組織やプロジェクトの中では、ともすると個人の意志や希望は簡単にねじ伏せられてしまうものです。しかし、その大組織を動かしているのも実は一人一人の個人なのです。
担当する人間に「夢」と「希望」と「こだわり」と、そしてそれを推進する屈強な精神力があれば、その願いは必ず叶えられる。今回のホテルの開業が、そうわたしに教えてくれました。

〔参考文献および資料〕
コミュニケーション科学研究所「全国縦断マーケット調査」
第一勧業銀行総合研究所「調査報告書」
常陽地域研究センター「茨城県民の生活行動圏調査」
月刊ホテル旅館・連載、前澤秀治「中級コマーシャルホテルの開発と経営
菅原信男「水戸発都市再生の実践的研究」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
