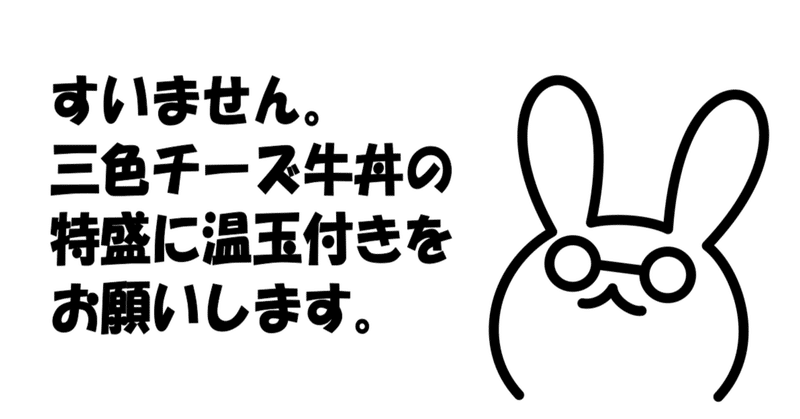
なぜ、陰キャは他人と自分を比べてしまうのか?——ルサンチマンの社会的生産条件
例えば、絵、歌、演劇、小説など、文化的な領域における言語を獲得しておらず、あるいは友人、恋人など親密な関係性によって生成される固有の言語を獲得していない、文化社会圏(コミュニティやネットワーク)に積極的に参加できない人間を、理念型として「陰キャ」と設定しよう。
さて、この陰キャにとって日常的に意味をなし続ける領域とは一体、どのようなものになるのか?言い換えると、彼が抱える社会的世界とは、いかなるものになるのか?
それは、強固に資本主義だと思われる。
正確にいうと、それは商品社会に内在する論理によって、人格-人格の関係から転倒した物-物という自己-他者関係、つまり、物象化した人間の相互関係により絶えず構成される社会的世界だけが、彼らの内面に強制されて、彼らの思考のフレームワーク自体を規定しているのではないか。
現代社会では、人間が生きる手段は資本主義的生産様式と一体化してしまっている。
したがって、大部分の人間の生活様式は「労働力商品を売って貨幣を得て、貨幣を介して商品を買う」という形態(w-g-w)となっている。すると、人は恋心を抱いていようと、いなかろうと、常に貨幣のことを想っていなくてはならない。
人は資本主義から逃げられない。
ここで資本主義に内包する世界観を確認しておきたい。
一万円札。
たかだか紙切れと分かっていても、現代人はこの紙切れに大いなる価値があると夢想して、人生の大部分を労働に費やす。
マルクスの理屈で言えば、貨幣とは、単に商品価値の等価物として表示する特殊な商品形態にすぎない。しかし、この物質に絶対的に価値が実在すると確信してしまう “”物神的””な幻想性が商品形態の内的論理によって与えられる。
だから、人は貨幣を崇拝する。
商品社会では、人間よりも貨幣が価値あるものとして現象する。市場では人間は単なる労働力商品にすぎないのだ。商品の王に勝てるはずもない。
ゆえに、金は命より重い。
この冷酷な「商品語」は下部構造の基本論理として確実に社会の根底を貫いている。
とはいえ現実では労働環境上の人間関係が内包する稀な温かさ(例えばバイト先の優しいお姉さんのフォロー)によって資本制の冷酷性がわずかに緩和されることがあるけれども… しかし、その人間的な試みの大部分は資本の再生産を死守しようとする防衛を何も超越しない。
結局のところ、それは資本と人間の折り合いであり、気休めにすぎず、何なら人間の疎外は誰しも受け入れなくてはならない。
言ってしまえば、資本から押し付けられる不平等条約にすぎない。
ところで、前近代で社会的分業を支えていた生産関係は、身分や地位を媒介にした人間相互の親密な人格的関係であった。つまり、ヒト と ヒトの関係、ゲマインシャフトである。
しかし、ここに商品交換が媒介することによって、近代的な社会的分業は非人格的な人間関係、否、モノとモノの関係へと転倒してしまった。ゲゼルシャフトである。
それゆえに、交換関係における諸商品と同じ具合に人間と人間は容易に比べられてしまう。
その際に、資本が気に召さない具体的な人間要素は使用価値と同じように捨象されて、抽象化された簡単な社会的価値だけが労働市場の価値尺度によって計られる。 それはもちろん、貨幣だけではない。年収だけではなく、学歴、容姿、人脈(文化資本/社会関係資本である)などは、その人間の価値をはかるモノサシとして中々に有用であろう。(一時期、象徴資本たるブランド品がモノサシとして機能していたのは示唆に富んでいる)
このような文化資本をモノサシとして、人間の価値を比べるという発想は、実は人間と人間を比較しているのではない。究極的に単純化して例えるなら、東京大学卒業と京都大学卒業の資格を、””俯瞰的かつ客観的に “” 比べているのである。
つまり、資本主義の社会的世界が許容する人間関係とは、人間が疎外された モノ-モノの物象関係である。(逆に商品-商品の関係は人格化する)
現代社会に生きる人間は、まさに「現代社会に生きるがゆえに」この冷たい社会関係に、好むと好まざるとにかかわらず組み込まれる。
そうなると、ありとあらゆる文化圏が内包する豊かな意味を喪失した末に、力強く顕現してくるのは、まさに、この冷酷な資本主義の世界である。人間が文化的意味を喪失すれば、物象の次元にまで降格させられてしまうのだ。
ここに陰キャが、人間比較という病から抜け出せない理由がある。
豊かで多様な文化的言語を持ち合わせず、したがって、資本主義が認める思考だけが残された陰キャの内面世界は、まずもって自分に社会的に表示されている「市場価値」と 周囲の人間に社会的に表示されている「市場価値」の比較により規定されるのだ。比較の際に用いられるのは先に述べた学歴や容姿 等である。つまり、人間疎外されたモノ と モノ を比べるという俯瞰的な思考が粛々と行われる。
言ってしまえば、陰キャの俯瞰的視点とは、市場の目線と緊密に一体化している。そのため、自分という商品と他人という商品をオートメーションの如く比べざるをえないのである。比べたいとか、比べたくないとか、そんな人間の恣意性が通用するような世界ではないのである。
ここから、さらに話は深刻になる。ルサンチマンの社会的な生産条件について触れておこう。
人間の価値の商品的比較は、 彼らから自信を搾取して、挙句の果てに「存在価値・存在理由」を剥奪してしまう。売れない商品は廃棄されるように彼らの社会的存在は廃棄される。
まさに資本主義の呪いと言えるだろう。
この資本主義がもたらす呪いこそ、彼の中にニヒリズムと無気力と憂鬱を生み出す契機として作用して、やがて、彼は資本主義的勝者あるいは文化的勝者に対してルサンチマンを抱く。
さて、「存在理由」を喪失しているルサンチマンが「存在証明」を行うには?
他者に対する無差別な攻撃が手取り早い。
資本主義には、ルサンチマンの社会的な生産条件が十分に整っていると言えるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
