
【自由民主主義の擁護】カール・ポパー著『開かれた社会とその敵』【オープンソサエティ財団の起源】
こんにちは。いつもお越しくださる方も、初めての方もご訪問ありがとうございます。
今回は『開かれた社会とその敵』の英語版Wikipediaの翻訳をします。
翻訳のプロではありませんので、誤訳などがあるかもしれません。正確さよりも一般の日本語ネイティブがあまり知られていない海外情報などの全体の流れを掴めるようになること、これを第一の優先課題としていますのでこの点ご理解いただけますと幸いです。翻訳はDeepLやGoogle翻訳などを活用しています。
翻訳において、思想や宗教について扱っている場合がありますが、私自身の思想信条とは全く関係がないということは予め述べておきます。あくまで資料としての価値を優先して翻訳しているだけです。
『開かれた社会とその敵』
『開かれた社会とその敵』は、哲学者カール・ポパーによる政治哲学の著作で、「開かれた社会をその敵から守る」ことを提示し、歴史が普遍的な法則に従って不可避的に展開するとする「目的論的歴史主義」の理論に対する批判を展開している。ポパーは、プラトン、ヘーゲル、マルクスが歴史主義に依拠して政治哲学を支えていることを非難している。
※歴史主義は、英語のHistoricism、ドイツ語のHistorizismusの訳語として用いられている。
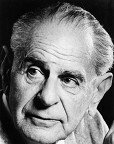
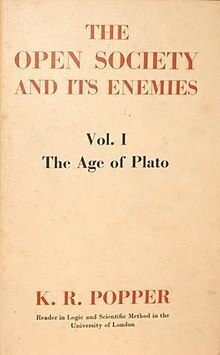
第二次世界大戦中に書かれた『開かれた社会とその敵』は、1945年にロンドンでラウトレッジ社から「プラトンの呪縛」と「予言の大潮――ヘーゲル、マルクスとその余波」の2巻が出版された。2013年には、アラン・ライアンによる新しい序文とE・H・ゴンブリッチによるエッセイを加えた1冊版がプリンストン大学出版局から刊行された。この作品は、モダン・ライブラリー・ボードが選ぶ20世紀のベスト・ノンフィクション100冊に選ばれている。
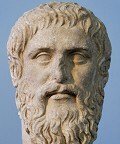


本書は歴史主義を批判し、開かれた社会と自由民主主義を擁護するものである。ポパーは、プラトンの政治哲学には、多くの解釈者によって描かれた良質の牧歌とは異なり、全体主義に向かう危険な傾向があると主張する。プラトンの社会変化の分析は賞賛するが、その解決策は、民主主義国家の台頭によってもたらされる変化への恐怖に駆られ、ソクラテスやアテナイの「偉大な世代」の他の思想家たちの人道的・民主的見解に反すると見て、否定している。また、ポパーはヘーゲルを批判し、その思想をアリストテレスにまで遡り、20世紀の全体主義の根源にあると主張している。彼は、ヘーゲルが「平頭で、無味乾燥で、吐き気がする、文盲のペテン師であり、最も狂った神秘的なナンセンスを走り書きしてばらまくという大胆さの頂点に達した」というショーペンハウエルの見解に同意している。ポパーはマルクスの歴史主義を徹底的に批判し、それが彼の主張を誇張させたと考え、彼の急進的で革命的な見通しを否定している。ポパーは、暴力や流血を伴わずに制度の改善を可能にする唯一の政治形態として、直接自由民主主義を提唱している。
概要
ポパーの本は2巻に分かれており、最近の版では1巻としてのみ出版されていた。第1巻「プラトンの呪縛」はプラトンに、第2巻「予言の大潮」はカール・マルクスに焦点をあてている。
第1巻:「プラトンの呪縛」
第1部「起源と運命の神話」には、第1章から第3章までが収録されている。第2部「プラトンの記述社会学」には、第4章と第5章が収められている。第3部「プラトンの政治綱領」には第6章から第9章までが収められている。第1巻の最後となる第4節「プラトン攻撃の背景」には、第10章のみが収録されている。巻末には、番号のない「補遺」のセクションがある。
起源と運命の神話
第1章「歴史主義と運命の神話」では、ポパーが欠陥のある方法と考える社会科学への歴史主義的アプローチについて述べている。歴史主義とは、「歴史は特定の歴史的法則や進化的法則によって支配されており、その発見によって人間の運命を予言することができるという教義」である。ポパーは、歴史主義的なアプローチは良くない結果をもたらすと主張し、より良い結果をもたらすと考える方法を概説している。また、歴史主義がどのように生まれ、私たちの文化に定着していったかについても述べている。ポパーは歴史主義の例として「選ばれし民の教義」を挙げている。この教義では、神がある民族を選び、神の意志の道具として選び、歴史的発展の法則は、神の意志によって定められ、この民族が地を受け継ぐと仮定している。ポパーは、「選ばれた民の教義」は社会生活の部族的形態から発展したものであり、他の形態の歴史主義理論にはまだ集団主義の要素が残っている可能性があると指摘している。ポパーは、歴史主義の最も重要な現代版として、右派の人種主義やファシズムの歴史哲学と左派のマルクス歴史哲学の2つを挙げている。どちらの理論も、歴史発展の法則を発見することにつながる歴史の解釈に基づいて、その歴史的予測を行う。
第2章「ヘラクレイトス」では、古代ギリシアにおける歴史主義の出現、特にヘラクレイトスの哲学を通しての歴史主義の出現に焦点を当てる。ヘラクレイトスは、普遍的な変化と罰によって強制される隠された運命の考えを信じ、争いや戦争がすべての変化、特に社会生活のダイナミックで創造的な原理であると考えた。彼の哲学は、社会的・政治的騒乱の個人的な体験に触発されたものであり、社会力学の重要性を強調する彼の姿勢はこれを反映している。
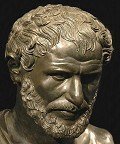
「万物は流転している」と考え、自然界は絶えず変化しているとした
第3章「プラトンの形相ないしイデア説」では、その同名の理論について論じている。最初の2章よりも長く、ポパーによって6つのパートに分けられている。ポパーによれば、プラトンの哲学は、彼が経験した政治の混乱や不安定さに大きな影響を受けており、道徳的な退化が政治の退化につながると考えていた。彼は、退化や変化のない国家を確立することで、この政治的変化を阻止しようと努め、それを黄金時代の完璧な状態と見なした。プラトンは、変化しない理想的な国家を信じることによって歴史主義の信条から逸脱した一方で、歴史主義の最後の結末から後退する傾向をヘラクレイトスと共有した。
本章では、ポパーが社会エンジニアと歴史主義者を区別し、前者に好意的であることを紹介する。社会エンジニアは、人間が歴史をコントロールして目的を達成できると考え、政治を社会制度を構築・修正するための道具としてとらえ、制度の設計や効率など現実的な要素に基づいて評価する(ポパーは、社会工学に断片的なものとユートピア的なものの2つのタイプがあるとし、第9章でさらに論じる)。これに対して、歴史主義者は、制度の過去、現在、未来の意義を理解することに関心を持つ。彼らは、制度が神の意志によるものか、重要な歴史的傾向に奉仕しているかなど、その歴史的役割に基づいて評価する。ポパーは、制度は単なる機械ではなく、その実用的な目的を超えたユニークな特性を持ちうることを認めている。
また、本章では、ポパーが物事を理解する方法として、方法論的本質主義と方法論的名辞主義という二つの異なる方法を区別し、後者を好んでいることを紹介する。方法論的本質主義とは、科学は知的直感によって物事の隠れた現実や本質を明らかにし、それを定義によって言葉で記述することを目指すべきという考え方である。これに対し、方法論的名辞論は、物事がさまざまな状況でどのように振る舞うか、特にその振る舞いに規則性があるかどうかを記述することの重要性を強調するものである。ポパーによれば、自然科学はほとんどが方法論的名辞主義を採用しているが、社会科学はいまだに本質主義的手法に頼っており、それが後進性の原因の一つになっているという。ポパーは、自然科学と社会科学の方法の違いは、両分野の本質的な違いを反映していると主張する人がいるが、この見解には反対であることを指摘している。
プラトンの記述社会学
第4章「静止と変化」は、形相論と普遍的な流動と崩壊に基づくプラトンの社会学について述べたものである。長文で、5つのパートに分かれている。ポパーによれば、プラトンは、変化は不完全と悪に向かうものでしかなく、それは退化の過程であると考えた。彼は歴史を病気とみなし、進化の法則に支配された歴史時代の体系を打ち立てた。プラトンの理想国家は、進歩的なユートピア的未来像ではなく、むしろ歴史的、あるいは前史的なものであり、階級戦争を避けるために古代の部族貴族制を再構築しようとした。プラトンの最良の国家における支配階級は、挑戦しがたい優越感と教養を備えている。支配階級の繁殖と訓練は安定を確保するために必要であり、プラトンは犬や馬や鳥の繁殖と同じ原則を適用することを要求した。ポパーは、変化する社会世界を理解し解釈しようとしたプラトンの体系的歴史主義社会学をまとめている。
第5章「自然と協定」は、ポパーの自然法と規範法の区別を紹介する。ポパーは、この区別が歴史を通じて発展する段階を分け、さらにプラトンの分析に応用している。ポパーによれば、自然法は運動法則や重力法則のような自然界の厳密で不変の規則性を表すものであり、規範法は十戒のような特定の行動様式を禁じたり要求する規則である。規範法は人が強制することができ、変更可能であるのに対し、自然法は人の手に負えず、変更不可能である。
ポパーは、この区別は歴史を通じて発展してきたと考え、自然法と規範法の区別がなく、不快な経験は人が環境に適応することを学ぶための手段であるというナイーブなあるいは魔術的一元論から出発した。この段階には、ナイーブな自然主義とナイーブな慣習主義という2つの可能性がある。後者の可能性では、自然と規範的な規則性の両方が、人間のような神や悪魔の決定による表現であり、それに依存するものとして経験される。魔術的部族主義の崩壊は、タブーが部族によって異なること、タブーは人間が課し、強制するものであること、仲間による制裁から逃れさえすれば、不快な反響なしに破ることができることを認識することと結びついている。この展開は、ポパーが批判的二元論と呼ぶもので、規範や規範的法則は人間によって作られたり変えられたりするものであり、必ずしも恣意的ではないものの、自然の規則性や法則から導き出すことはできないとする考え方に行き着く。この立場は、ソフィストであるプロタゴラスが最初に到達したものである。人間は規範に対して道徳的な責任を負っており、それが好ましくないものであれば改善するように努めるべきであるということを強調する。また、事実と決定の二元論と表現されることもあり、決定は自然法則に適合していなければ実行されないが、その法則から導き出されることはない、という意味である。決定は、行われたある決定を指す場合と、決定する行為そのものを指す場合がある。
ポパーによれば、ナイーブな一元論から批判的二元論への発展には、生物学的自然主義、倫理的または法学的実証主義、心理的または精神的自然主義という、魔術的一元論と批判的二元論の要素を併せ持つ三つの中間ポジションがある。生物学的自然主義とは、「道徳法則や国家の法則が恣意的であるにもかかわらず、そこからそのような規範を導き出すことができる永遠不変の自然法則が存在するという理論である」。 ポパーは、生物学的自然主義を倫理的教義の支持に用いることはできないと主張する。なぜなら、事実に規範を基礎づけることは不可能だからである。一方、倫理的実証主義は、既存の法律が善の唯一の可能な基準であり、規範は慣習的なものであると考える。しかし、倫理的実証主義はしばしば保守的あるいは権威主義的であり、神の権威を持ち出してきた。ポパーは、権威主義や保守主義が倫理的ニヒリズムの表現であり、極端な道徳的懐疑と人間やその可能性への不信であると主張している。心理的または精神的自然主義は、前の2つの見解を組み合わせたもので、規範は人間と人間社会の産物であり、したがって、「人間の心理的または精神的性質、および人間社会の性質の表現である」と主張する。ポパーは、この見解はプラトンが最初に定式化したものであり、「もっともらしい」ものの、「あまりにも広く、あまりにも曖昧なので、何でも擁護するために使われるかもしれない」と述べている。
このように区別した上で、ポパーは第5章の最後の部分で、さらにプラトンを分析する。ポパーは、プラトンの「自然」という言葉の使い方と、歴史主義との関係を分析する。また、プラトンの国家を超組織体としてとらえ、国家を統一された全体としてとらえ、個々の市民を国家の不完全なコピーとしてとらえることについて論じている。プラトンの一体感や全体性の強調は、部族的な集団主義と関係があり、彼は個人を全体に奉仕するための手段として捉えたのである。ポパーはまた、プラトンの国家における退化論についても論じている。退化とは、生成されたものすべてに腐敗をもたらす自然進化の法則のことである。プラトンは、品種改良の知識とプラトン数によって人種の退化を防ぐことができるが、純粋に合理的な方法を欠いているため、いずれは退化が起こると示唆している。プラトンの歴史主義社会学の基本は人種的退化であり、それは「支配階級の不和の起源を説明し、それとともに、すべての歴史的発展の起源を説明する」。
プラトンの政治綱領
第6章「全体主義における正義」は、ポパーがプラトンの政治哲学の全体主義的性質とするものを、歴史主義に基づき、プラトンの「階級支配の安定条件に関する社会学的教義」と、哲学者の考える正義と哲人王に基づいて分析するものである。ポパーは、プラトンが「共和国において、正義は不平等と階級階層を意味するが、彼の時代の「一般的な用法では」平等を意味する」と主張し、意図的に混乱をもたらしたと論じている。ポパーは、平等主義、個人主義、集団主義を論じ、それらがプラトンの自然な指導者に対する自然な特権への反対とどのように関係しているかを論じ、プラトンの反個人主義が彼の哲学の基本的二元論に深く根ざし、反人間主義、反キリスト教であると結論付けている。第6章では、ポパーの国家論を紹介し、国家の第一の目的は「市民の自由の保護」であるべきだという特別な意味での保護主義と呼んでいる。自由主義の理論であるとしながらも、「自由の保護」はかなり広義にとらえることができ、「自由を守れなくなるような怠慢から」若者を守るために、教育における国家統制の手段を含むことができると考えているからである。しかし、彼は「教育問題において国家がコントロールしすぎることは、自由にとって致命的な危険であり、それは教化につながるからだ」と認めている。「自由の限界という重要で難しい問題は、切りのいい公式では解決できない」と彼は考えている。
第7章「指導者の原則」では、プラトンの「自然の支配者が支配し、自然の奴隷が奴隷であるべきだ」という考えを批判している。彼は、政治権力は歯止めがかからないと主張し、この議論を用いて、「誰が支配すべきか?」というプラトンの根本的な問いを、「悪い支配者や無能な支配者が大きな損害を与えることを防ぐことができるように政治制度を組織するにはどうすればよいか?」と置き換えている。彼は、政治における個人主義と制度主義の区別について論じている。彼は、今日の問題は大部分が個人的なものであり、一方、未来を築くことは必然的に制度的でなければならないと考えている。また、ポパーはソクラテスの道徳的知識主義とその民主的・反民主的側面、プラトンの最高の教育形態に関する制度的要求についても論じている。そして、「将来の指導者を選抜したり教育したりするという考え方は、まさに自己矛盾である」とし、「知的卓越性の秘密は批判の精神である」と論じている。
第8章「哲人王」は、プラトンの哲人王という考え方と、それが全体主義とどのように関連しているかを分析している。プラトンの哲人王は、必ずしも真理の探求者ではなく、国家の利益のために嘘と欺瞞を用いなければならない支配者である。ポパーは、プラトンが、王権と支配を運命づけられた神のような男女の種族を作り出すために品種改良を重視したのは、支配者層が支配する完璧な社会を作ろうとする試みであると主張する。さらに、プラトンの哲学は理論的な論説ではなく、実践的な政治的マニフェストであり、彼の考える哲人王は理想的な支配者であり、単なる理論的な構成ではない。ポパーは、プラトンが哲人王のポストにふさわしい真の哲学者と考えたのは、自分と友人の何人かを含む少数の人物だけであったと指摘する。
第9章「唯美主義、完全主義、ユートピア主義」では、ポパーが社会工学のアプローチとしてユートピア工学とピースミール工学の二つを区別し、そのうち後者を好んでいることに着目している。ユートピア工学は、理想社会の設計図を少なくとも大まかには必要とし、究極の政治的目的を実現するための最善の手段を検討することで実践的行動を決定する。これに対して、ピースミール工学は、「社会の最大の究極の善を探し、そのために戦うのではなく、社会の最大かつ最も緊急な悪を探し、そのために戦う方法」を採用している。ピースミール工学は、苦しみや不正、戦争など、その存在が比較的容易に立証できる社会悪と少しずつ戦いながら、社会の現状を改善することを目指す。これに対して、ユートピア工学は、壮大なスケールの社会工学の青写真を判断することが難しいため、多くの人々の賛同や合意によって支持される可能性は低くなる。実際、ポパーによれば、ユートピア工学は、「理想とは何か、その実現のための最善の手段は何かを「一度きりで決定する合理的な方法が存在すること」」を否定する傾向があるので、「ユートピア工学間の意見の相違は、したがって、理性の代わりに力を使うこと、すなわち暴力に至るに違いない」ということになる。ポパーは、「社会全体の再建、すなわち、我々の限られた経験のために、その現実的な結果を計算することが困難な非常に大きな変化」を試みる傾向が強いユートピア的アプローチよりも、小規模な社会実験を伴うピースミール的アプローチの方が効果的かつ現実的だと論じている。ポパーは、試行錯誤を通じて経験を積むことの重要性を強調し、社会工学を機械工学に例えている。プラトン的な理想主義への批判とマルクスのユートピア主義への批判を対比させ、行動しながら学び、見方を変えていく断片的なアプローチを提唱している。
プラトンの攻撃の背景
第10章は、本書と同じく「開かれた社会とその敵」と題され、プラトンが政治プログラムの一環として幸福を信じたことを検証し、プラトンの幸福の扱いは「正義の扱いと類似」しており、同様に概念を階級階層に結びつけることによって一般的な用法を歪めていると論じている。ポパーは、プラトンの使命は、社会の変化や社会の不和と戦うことであったと考えている。閉鎖的な部族社会の崩壊は、主に海洋通信と商業の発達によって引き起こされ、古い生活様式の部分的解消、政治革命と反動、魔術的な強迫観念から解放された批判的議論の発明を招いた。アテナイ帝国主義は、この2つを主要な特徴として発展させた。ポパーは、トゥキディデスの民主主義とアテナイ帝国に対する態度を論じ、トゥキディデスはアテナイ帝国を専制政治の一形態とみなす反民主主義者であったと主張する。ポパーは、部族主義的な排他性と自給自足は、ある種の帝国主義にしか取って代わられないと主張してアテナイの帝国拡大を擁護し、最も思慮深く才能あるアテナイ人が開放社会の魅力に抵抗した理由を説明し、人類史の転換点とされるペロポネソス戦争の直前と最中にアテナイに住んでいた世代「偉大な世代」を紹介している。最後に、ソクラテスがアテナイの民主主義を批判し、個人主義を信奉していたこと、また、プラトンがソクラテスを「逮捕社会論の構築という壮大な試み」に巻き込み、裏切ったと考えることについて述べている。プラトンの民主主義に対する主張は、ポパーの解釈では、悪の根源は「『人間の堕落』、閉鎖社会の崩壊」であるという信念に基づいている。ポパーによれば、プラトンは「個人の自発性を憎み、すべての変化を阻止したいという願いを、正義と節制への愛、誰もが満足し幸福で、金目当ての粗野さが寛大さと友情の法則に取って代わる天国の状態へ変身させた」のである。
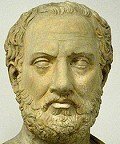
ペロポネソス戦争を実証的立場から著した『戦史』で知られる
補遺
1957年の補遺「プラトンと幾何学」では、プラトンの幾何学観に関するポパーの扱いについて論じている。1961年の補遺では、「テアエテトスの年代」と題し、プラトンの対話の年代を論じている。1961年の2番目の補遺は、「批評家への返答」と題され、ロナルド・B・レヴィンソンの著書『プラトンの擁護』における様々な主張に対して、広範囲に渡って返答している。1965年に追加された最後の補遺は無題で(番号は「IV」)、ダイアナ・スピアマン著『現代の独裁』、特に「独裁の理論」と題する章を推奨している。
第2巻 予言の大潮
第1部「信託的哲学の勃興」は、第11章と第12章を収録している。第2部「マルクスの方法」には、第13章から第17章までが含まれている。第3部「マルクスの予言」には、第18章から第21章までが含まれている。第4部「マルクスの倫理」は、第22章のみ。第五部「余波」は、23章と24章を含む。「結論」のセクションには第25章のみが含まれ、その後に「補遺」の番号のないセクションが続く。
信託的哲学の勃興
第11章「ヘーゲル主義のアリストテレス的根源」では、歴史主義のアリストテレス的根源と全体主義との関連について論じている。ポパーは、アリストテレスの哲学と、プラトンの自然主義的な隷属論を支持したこと、またベスト・ステートの理論について検証している。また、ポパーは、定義の問題や、アリストテレスが用いた定義の本質主義的な方法についても説明している。彼は、現代科学は定義と科学の進歩に対して根本的に異なるアプローチを持っていると主張している。また、ポパーは、プラトン=アリストテレス哲学と偉大な世代との対立、キリスト教が当初プラトン化する観念論や知識主義に反対していたが、ローマ帝国で力を持つようになると大きく変化したことを論じている。
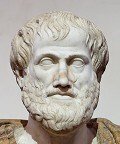
第12章「ヘーゲルと新しい部族主義」は、ポパーが「現代のあらゆる歴史主義の源」と呼ぶヘーゲル哲学に対する長い批判である。この章は、この本の中で最も長い一章であり、平均的な章や中央値の章の2倍以上の長さである。ポパーは、ヘーゲルの哲学は理解不能であり、欺瞞的であったと主張する。ヘーゲルのプラトン化する国家への崇拝」に焦点を当て、ポパーは、ヘーゲルの哲学が真理の純粋な追求ではなく、むしろ下心に触発されたものであることを示唆している。第2章では、ヘーゲルの哲学をプラトンの哲学と対比しながら分析し、「ヘーゲル主義の2つの柱」である弁証法的三段論法と同一性の哲学について述べている。そしてポパーは、この章の残りは、ヘーゲルがこれらの抽象的な理論を実際に政治的に応用することに限定され、彼のすべての労作の弁明的な目的を示すことになると述べている。
ポパーは、ドイツのナショナリズムの台頭が、理性や開かれた社会に対する反乱と強い親和性を持っていると主張し、「国民国家の原理、すなわち、すべての国家の領土が一つの国民が住む領土と一致するべきだという政治的要求」は、自然主義や部族集団主義の非理性的でユートピア風の夢であり、神話だと考えている。そして、ドイツ・ナショナリズムの創始者の一人であるフィヒテの意見の展開を簡単に論じた後、再び「ヘーゲルのヒステリックな歴史主義」を批判し、「現代の全体主義が急速に成長するための肥やし」と見なします。第5節では、「現代の全体主義のより重要な考え方は、ほとんどすべてヘーゲルから直接受け継いだものである」と主張する。ポパーは、ファシズム思想の中心である「現代の血と土の神話」は、「プラトンの生誕神話にその正確な対応関係がある」と述べている。
マルクスの方法
第13章「マルクスの社会学的決定論」は、ポパーのマルクスに関する最初の章である。ポパーは、マルクスの歴史的予言は当たらず、マルクスは「数多くの知的な人々を、歴史的予言が社会問題にアプローチする科学的方法であると誤解させた」と論じている。ポパーは、マルクス主義理論の基礎となっている史的唯物論の考え方を批判し、第1章で述べたように「発見できる特定の歴史的法則があり、それに基づいて人類の未来に関する予測ができる」と仮定した欠陥のある歴史観であると主張している。また、歴史的な変化はあらかじめ決まっているわけではなく、社会は自ら道を選ぶことができると主張している。最後にポパーは、社会世界は自然科学と同じ手法で研究するにはあまりに複雑であり、社会科学者は人間の行動や社会制度の複雑さを考慮した別の方法を用いなければならないと主張している。
第14章「社会学の自律」では、すべての社会法則を心理法則に還元できるとする考え方である心理主義に対するマルクスの批判を展開している。ポパーは、ミルのこの思想のバージョンに対して、拡大した議論の形でこれを行い、章の終わりに、ミルをマルクスの真の標的であった「ヘーゲルよりも価値のある相手」と考えたからだと説明している。彼は、社会現象を説明する上で、社会環境とその制度が重要であることを強調している。ポパーは、彼が社会の陰謀論と呼ぶものを批判している。「社会現象の説明は、この現象の発生に関心を持ち(時には、最初に明らかにされなければならない隠れた関心である)、それをもたらすために計画し共謀した人物や集団を発見することにあるとする見解である」。彼は、社会科学の主な仕事は、人間の意図的な行動がもたらす意図しない社会的な反響を分析することであると主張する。そして、心理学的分析は、特定の状況において何が合理的な行動とみなされるかという基準を開発するために用いるべきではなく、社会の問題は人間の本質の問題とは還元不可能であると結論付けている。
第15章「経済学的歴史主義」では、ヘーゲルの心理主義を唯物論に置き換えたマルクスの「史的唯物論」哲学を論じている。ポパーは、マルクスの哲学を、マルクスの言葉「低俗経済学者」になぞらえて、「低俗マルクス主義者」と呼ぶ人たちが持つ信念と区別している。マルクス主義者は、マルクスの哲学は「経済的動機、特に階級的利害が歴史の原動力である」という考えを中心としており、マルクス主義の目的は、利益への欲求を満たすために社会の不幸を作り出す権力者の隠れた動機を明らかにすることであると考えている。ポパーは、この解釈はマルクスの哲学の誤読であると主張する。彼は、経済的動機は「社会システムの腐敗の影響による症状」であり、「歴史の原動力」ではないと考えたのである。彼は、社会的な「戦争、恐慌、失業、豊穣の中の飢餓などの現象」を、権力者の「狡猾な陰謀の結果」ではなく、「異なる結果に向けられた」「行動の望まれない社会的結果」とみなした。マルクスは、権力者を含む人間の行為者を、「経済的なワイヤーによって、自分ではコントロールできない歴史的な力に抗しがたく引っ張られる操り人形」と見なしたのである。
マルクスは、社会科学を社会の物質的条件に焦点を当てた科学的歴史とみなしていたが、ポパーは彼の歴史主義を批判する一方で、経済主義を支持している。「すなわち、社会の経済的組織、つまり自然と物質の交換の組織は、すべての社会制度、特にその歴史的発展にとって基本であるという主張である」。ポパーは、マルクスの経済主義は、すべての社会制度と歴史的発展における経済組織の基本的な役割を強調しているので価値があると考えるが、還元主義的・本質主義的な見方には警告を発している。
第16章「階級」では、「これまで存在したすべての社会の歴史は階級闘争の歴史である」というマルクスの発言と、歴史が国家ではなく階級の戦争によって決定されるというその意味について論じている。ポパーは、マルクスの階級論を、人間の心に影響を与え、それに従って行動させる制度的あるいは客観的な社会状況として説明している。ポパーは、政治的対立を搾取する側と搾取される側の闘争として単純化しすぎることの危険性を指摘し、マルクスの広範な歴史主義的一般化に内在する危険性を警告している。ポパーは、このような批判にもかかわらず、「階級状況の論理」を使って産業システムにおける制度の働きを説明しようとしたマルクスの試みを賞賛している。
第17章「法体系と社会体制」では、マルクスの国家論と政治行動への影響について論じている。マルクスは、法体系と政治体制は、経済システムの実際の生産力の上に成り立つ上部構造であり、国家は階級支配のための機関であると考えた。ポパーは、マルクスの理論は洞察に富んでいたが、それは一握りの真実しか含んでおらず、その後の経験によって反論されてきたと論じている。ポパーは、自由を守るためには経済的介入主義が必要であり、政治権力は基本的なもので、経済権力をコントロールすることができると提案している。また、民主的な経済政策には形式的な自由が不可欠であり、経済的な悪魔を飼いならすには社会工学が必要であると主張している。ポパーは、権力の制御に関するマルクス主義のアプローチを批判し、民主主義が国家の制御を実現する唯一の手段であると主張している。
マルクスの予言
第18章「社会主義の到来」では、マルクスの経済史主義について論じている。ポパーは、マルクスが資本主義の経済力を分析し、3つのステップからなる社会主義の到来を予言したことを説明する。彼は、無階級社会というマルクスの結論が前提から導かれないと主張する。また、現代の民主主義国家の経済システムは、マルクスの描いた資本主義とは異なっており、マルクスの共産主義革命のための10項目のプログラムのほとんどは、現代の民主主義国家で実践されていることを指摘している。ポパーは、マルクスの予言的な議論の前提を強化することで、有効な結論を導くことができるが、道徳的・思想的要因に関する仮定は、経済的要因に還元する能力を超えていると主張している。ポパーは、マルクスの歴史的予言が近年のヨーロッパ史に与えた影響を検証し、マルクス主義の指導者たちは「各国の労働者よ、団結せよ!」以上の実践的プログラムを持たず、約束された資本主義の自殺を待っていたが、手遅れで、その機会は失われたことを指摘している。
第19章「社会革命」は、マルクス主義のさらなる批判であり、その欠点と暴力の可能性について論じている。ポパーは、マルクス主義は社会で起こりうる多くの展開を説明しておらず、潜在的な暴力革命の予言は有害であると論じている。また、ポパーは、マルクス主義政党における暴力の問題に対する曖昧な態度と、それが民主主義の戦いに勝利する可能性にどのような影響を与えるかについて考察している。最終的にポパーは、すべての政治的問題は制度的問題であり、より平等への進歩は、権力の制度的コントロールによってのみ守られるものであると主張する。
第20章「資本主義とその運命」では、マルクスの資本主義論について述べています。マルクスは、資本の蓄積が、「(a)生産性の向上、富の増大、富の少数の手への集中(b)貧困と悲惨の増大、労働者は、主に「産業予備軍」と呼ばれる労働者の剰余が賃金を最低水準に維持することによって、生業賃金や飢餓賃金に抑えられる」と考えた。ポパーはマルクスの価値論を批判しているが、余剰人口が賃金に及ぼす圧力についての分析には同意している。しかし、不幸増大の法則というマルクスの予言的な議論には異を唱え、労働組合、団体交渉、ストライキによって、資本家が産業予備軍を使って賃金を低く抑えることを防ぐことができると提言している。ポパーはまた、マルクスの貿易循環と余剰人口に関する理論や、利潤率が低下する傾向にあり、資本主義の必然的な崩壊につながるという彼の主張についても論じている。
第21章「予言の評価」では、現代の経済傾向の観察から導き出されたマルクスの予言的結論が、認識論としての歴史主義の貧困を主因として、無効であることが説明されている。マルクスの現代社会に対する社会学的・経済学的分析は、一方的ではあるが説明的であり、彼の自由奔放な資本主義体制は、長くは続かないだろう。国家の影響力の低下に対するマルクスの希望は称賛に値するものである。「マルクスが発見したと主張する歴史的傾向の一つ」で、「他のものに比べてより持続的な性格をもつと思われるもの」は、「生産手段の蓄積、特に労働の生産性の向上への傾向」である。マルクスは、生産力の発展と信用制度との関連を強調し、それが貿易循環をもたらしたとし、彼の貿易循環論は、完全雇用への接近が「発明家や投資家を刺激して新しい労働節約機械を作り、導入し、それによって(まず短いブームを起こし、その後)新しい失業と恐慌の波を生じさせる」としている。生産性が上がると、投資が増え、消費が増え、労働時間が減少し、生産されたが消費されない財の量が増える。「マルクスは多くのことを正しい視点で見ていた」が、「その先に何が待ち受けているかは全くわかっていなかった」ので、その予測は間違っていた。
マルクスの倫理学
第22章「歴史主義の道徳論」は、マルクスの『資本論』に含意された倫理論を論じたものである。マルクスは資本主義をその本質的な不正と寡頭制のために非難し、社会制度の道徳的側面を強調した。ポパーは、社会の変化や政治革命はすべて当該時代の経済に起因するという歴史主義的な道徳論に疑問を呈し、人間とその目的はある程度社会の産物であるが、社会もまた人間とその目的の産物であると主張する。ポパーは、人間の見方や行動は、遺伝、教育、社会的影響だけで決まるわけではないと結論づけ、ベートーヴェンを例に挙げ、その作品の社会学的側面を説明している。

その余波
第23章「知識社会学」では、変化する社会環境の中で変化を予測し制御しようとするヘーゲルやマルクスの歴史主義哲学を論じている。ポパーは、このような態度が「道徳的・科学的意見を含め、我々の意見は階級的利害によって、より一般的には我々の時代の社会的・歴史的状況によって決定されるというマルクス主義の教義」と密接に関係していると論じている。ポパーは知識社会学を紹介し、科学的客観性は「多くの科学者の友好的・敵対的協力」と「批判や意見の公的表現」によって達成されると主張する。また、知識社会学が科学的手法の社会的側面を理解していないことを批判し、社会科学には断片的な社会工学によって検証できる社会技術が必要であると提言している。ポパーは、社会科学者は「知識」と「意志」の絡み合いを忘れ、他の科学と同じ理論的手法で現代の現実的問題に焦点を当てるべきだと考えている。
第24章「神託的哲学と理性への反逆」では、「合理主義と非合理主義の対立」を探り、「現代において最も重要な知的、そしておそらく道徳的な問題になっている」という。この章では、合理主義とは「感情や情緒に訴えるのではなく、理性、すなわち明確な思考と経験に訴えることによって、できるだけ多くの問題を解決しようとする態度」であり、「経験主義」と対立するものではなく、むしろ「理性ではなく、感情や情緒が人間の行動の源泉であると主張する」態度である非合理主義に対抗するものである、と語っている。ポパーは、個人主義や社会における合理的思考の必要性を主張する一方で、今日流行していると思われる非合理主義的な立場を批判している。
ポパーは、「基本的な合理主義的態度は、(少なくとも暫定的な)信仰行為(理性への信仰)から生じるという事実を認識する」批判的合理主義を提案している。これは、「『議論や経験によって擁護できないものは受け入れる用意がない』と言う人の態度として表現することができる」といった無批判的または包括的合理主義とは対照的であり、合理主義そのものを含め、ポパーは自滅的であると考える。非合理主義と批判的合理主義のどちらを採用するかは、単なる知的判断ではなく、道徳的判断であり、「他の人間に対する態度、社会生活の問題に対する態度全体に深く影響する」ものである。
ポパーは、非合理主義が「絶望的に非現実的な」態度につながると主張している。また、「政治生活において、すなわち、人間が人間に対して持つ力に関係する問題の分野において、反平等主義的な態度をとる」ことになり、ポパーはこれを「犯罪的」だと考えている。ポパーは、議論と経験を重視し、公平性を示唆する批判的合理主義が、非合理主義よりも優れたアプローチであることを強く求めている。また、ポパーはA・N・ホワイトヘッドやルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインなど、20世紀の有力な非合理主義哲学者たちを批判している。


結論
第25章「歴史に意味はあるか」では、自然科学における理論の役割、歴史理論の限界、権力への崇拝、有神論的歴史主義の考え方が論じられている。ポパーは、教育においてより高い価値を課すことの難しさを強調し、歴史には意味も目的もないが、目的を押し付けることによって意味を与えることができると論じている。最後に、彼は再び自然と慣習の問題を論じ、倫理的な問題は社会的な状況においてのみ発生すると述べている。
補遺
1961年の第2巻の補遺「事実、基準、真理:相対主義のさらなる批判」は、客観的な真理は存在せず、競合する理論間の選択は恣意的であるとする考え方である相対主義を批判している。ポパーは、ある発言が事実に即しているかどうかを客観的に判断する方法があり、また道徳や政治の分野でも基準を設けることで、相対主義に対抗することを提案している。ポパーは、人間の知識には誤りがあり、確実性の追求は誤りであることを認め、可謬主義を主張する。また、ポパーは、知識の成長の基本である真理に近づくという考え方を説明し、この考え方が非合法であるという考え方に反論している。ポパーは、権威主義的な宗教の衰退が、相対主義やニヒリズムの蔓延につながる結果を強調している。さらに、ポパーは事実と基準の二元論を説明し、基準は事実からは決して導き出せず、創造し、批判し、改善しなければならず、知識の成長には終わりがないことを説いている。
1965年の補遺に「シュヴァルツシルトのマルクスに関する本に関するノート」と題し、ポパーがレオポルド・シュヴァルツシルトの『赤いプロシア人』という本に書かれているマルクスの性格に関する証拠に以前接していたならば、マルクスをこのように同情的に扱うことはなかっただろうと記している。ポパーは、この証拠、特にマルクスとエンゲルスの書簡から、「マルクスは、『開かれた社会とその敵』の中で見かけられるよりも、人道主義者でもなく、自由を愛する者でもなかったことを示す」と考えている。
巻末資料
『開かれた社会とその敵』には豊富な注釈があり、それを合わせると、本書の第1巻とほぼ同じ長さになる。その多くは、プラトンやマルクスからの引用で、本文の主張を裏付ける参考文献的なものである。
第7章の注4は、「無制限の寛容は寛容の消滅をもたらす。もし、不寛容な人にまで無制限の寛容を広げるなら、もし、不寛容な人の猛攻撃から寛容な社会を守る準備がないなら、寛容な人は破壊され、寛容も一緒に破壊されるだろう」という寛容のパラドックスを定義したもので、非常に人気のある注である。この考え方は、本書の本文ではまったく取り上げられておらず、それよりも関連する自由のパラドックス、「いかなる抑制的統制もないという意味での自由は、いじめっ子を自由にし、おとなしい人を奴隷にするので、非常に大きな抑制につながるはずだという議論」に関心が集まっている。ポパーによれば、自由のパラドックスは「プラトンが最初に使い、成功させた」が、「無階級社会では国家権力はその機能を失い、『枯れる』だろうというナイーブな見方」をしていたマルクスには「全く理解されなかった」のである。ポパーは、第7章の注4を自由のパラドックスの定義から始め、さらに余談として、寛容のパラドックスと、民主主義のパラドックス、「より正確には多数決の支配、すなわち、暴君が支配すべきことを多数が決定する可能性」と呼ばれる別のパラドックスを定義している。
出版の履歴
ポパーは、第二次世界大戦中のニュージーランドで、学問的には無名のまま執筆を続けていたが、哲学や社会科学分野の数人の同僚が、この本の出版への道を支援してくれた。友人のE・H・ゴンブリッチに出版社探しを任せ、ライオネル・ロビンスとハロルド・ラスキが原稿をチェックし、J・N・フィンドレーが3つの候補から外した本のタイトルを提案した。(「すべての人のための社会哲学」が原稿の原題であり、「三人の偽預言者:プラトン、ヘーゲル、マルクス」「政治哲学批判」なども検討されたが却下された。)フリードリヒ・ハイエクは、ポパーをロンドン大学経済学部に引き入れたいと考え、彼の社会哲学への転向に熱狂した。
ゴンブリッチが語る出版までの歴史
ゴンブリッチ氏は、本書の出版に際して「個人的な回想」を書き残し、2013年のプリンストン版1巻に本書とともに掲載された。原稿は第二次世界大戦のさなかにニュージーランドからイギリスに送られ、出版までに2年半を要したという。ポパーは本書を「緊急の」新しい政治・歴史哲学として捉え、文明に対する全体主義の反乱の理解に貢献しようとしていたことが、ゴンブリッチの手元にあった手紙の数々から明らかになった。ポパーは、開かれた社会に対する根強い敵意は、文明のひずみと、過去の閉鎖的な部族社会から紀元前5世紀のアテネに端を発する個人主義文明への移行に伴う漂流感によるものだと考えた。ゴンブリッチは原稿を受け取り、ポパーがイギリスの様々な出版社に送るのを手伝った。
1943年8月19日、ゴンブリッチはカール・ポパーから長い手紙を受け取り、その中にはポパーの著書『開かれた社会とその敵』に対する前者の批判的な指摘に対する返信が含まれていた。 ポパーはショーペンハウアーとヘーゲルの誠実さを論じ、西洋の民主主義の信条がキリスト教に基づくという事実から偏見がないことを主張した。さらに、ポパーは、友人のハイエクの協力により、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の読者資格を得ることができたことに興奮を覚えたことを話している。ゴンブリッチは、ポパーから応募方法とポパーの履歴書、参考文献を受け取った。また、ポパーは自著の長さと複雑さを擁護し、「1ページごとに思考がひしめいている」にもかかわらず、稀に見る明晰さと簡素さを達成していると主張した。
1944年10月、ポパーは「私的価値と公的価値」と「決定論の反論」という2つの重要な論文を書き終えたと報告し、「自由の論理」という別の論文を書き上げた後、実践的方法論と音楽に戻るつもりだった。ポパーはまだラウトレッジ社からの出版日を待っており、ニュージーランドやオーストラリアの大学からのオファーも検討していた。また、ゴンブリッチは、カンタベリーのポパーの学科長がポパーを軽蔑するような発言をしたことを明らかにし、ポパーは退職を望んでいた。ポパーは4月中に体調を崩したが、山で休暇を過ごしている間に健康状態が回復した。5月21日、ニュージーランドのバスの中で、ケンブリッジから「ロンドン赴任おめでとう」「素晴らしい論文をありがとう」という電報を受け取る。
第二次世界大戦中のニュージーランドからイギリスへの移動は、新しい人々との出会いや、イギリスへの入国許可が下りないのではないかという不安など、カール・ポパー夫妻にとって困難と心配の連続だったが、ようやくイギリスに到着した二人を迎えたのは、ゴンブリッチとその家族たちだった。ゴンブリッチはポッパーに自著『開かれた社会とその敵』の初版を渡し、ポッパーはゴンブリッチの家に向かう途中で熱心に目を通した。ゴンブリッチの「回想」は、その後数十年間、ポパーが知的言説に与えた多大な貢献について考察し、反省の弁で終わっている。
出版後の経緯
本書は1992年までロシアで出版されなかった。2019年、本書は初めてオーディオブック形式で発売され、リアム・ジェラードがナレーションを担当した。このオーディオブックは、クラーゲンフルト大学/カール・ポパー図書館との取り決めにより、録音図書の一部門であるタンター・メディアによって制作された。
受容と影響
ポパーの著書は、第二次世界大戦後、西洋のリベラルな価値観を擁護する最も人気のある本の1つである。ギルバート・ライルは、ポパーの本を出版からわずか2年後にレビューし、彼に同意して、プラトンは「ソクラテスのユダだった」と書いている。『開かれた社会とその敵』は、哲学者のバートランド・ラッセルから「第一級の重要性を持つ作品」「民主主義の精力的で深い擁護」と賞賛され、シドニー・フックからは「自由の愛(と開かれた社会の存在)を脅かす歴史主義的思想」に対する「繊細に論じられ、情熱的に書かれた」批判と称された。フックは、歴史主義の主要な信念に対するポパーの批判を「間違いなく健全」とし、歴史主義が「歴史における真の代替案の存在、歴史的パターンにおける複数の因果過程の作動、未来を再決定する際の人間の理想の役割を見落としている」と指摘する。それにもかかわらず、フックは、ポパーが「自分の目的にかなうときにはプラトンを文字通り読みすぎ、テキストがあいまいなときにはプラトンの『本当の』意味が何であるかについてあまりにかしこまりすぎる」と主張し、ポパーのヘーゲルに対する扱いを「まさに乱暴」で「明らかに誤り」と呼び、ポパーもヒトラーには言及していないが「アドルフ・ヒトラーの『我が闘争』には一度もヘーゲルに対する参照がない」ことに言及している。



他の哲学者の中には批判的な人もいた。ウォルター・カウフマンは、ポパーの著作には、全体主義に対する攻撃や多くの示唆に富むアイデアなど、多くの美点があると考えた。しかし、彼は、ポパーのプラトンに対する解釈には欠陥があり、ポパーはヘーゲルに関する古い神話を「包括的に述べた」と書いており、重大な欠陥があることも認めている。カウフマンは、ポパーが全体主義を憎んでいるにもかかわらず、ポパーの方法は「残念ながら全体主義の『学者』のそれと似ている」とコメントしている。

ポパーの批判に対して、マルクス主義の作家モーリス・コーンフォースは
『開かれた哲学と開かれた社会:カール・ポパー博士のマルクス主義に対する反駁への返答』(1968年)において、マルクス主義を擁護した。コーンフォースは、ポパーに異論を唱えながらも、ポパーを「おそらく最も著名な」マルクス主義批判者と呼んでいる。哲学者のロバート・C・ソロモンは、ポパーがヘーゲルに対して「ほとんど完全に不当な極論」を展開し、ヘーゲルに「道徳的・政治的反動者」という評価を与える一助となったと書いている。マルクス主義経済学者のエルネスト・マンデルは、『開かれた社会とその敵』を、ドイツの社会民主主義者エドゥアルド・ベルンシュタインに始まる、マルクスがヘーゲルから借りた弁証法が「役に立たない」「形而上学」「神秘主義」だと批判する文献の一部と位置づけている。彼は、ポパーや他の批判者たちを「実証主義的な狭量さ」を非難している。

政治理論家のラジーヴ・バルガヴァは、ポパーが「ヘーゲルとマルクスの誤読で有名」であり、ポパーが自由主義的政治価値を守るために展開した定式化は「最も抽象的な形而上学の前提に不思議なことに根ざした党派的イデオロギー的考察に動機づけられる」と論じている。ジョン・スチュワートのアンソロジー『ヘーゲル神話と伝説』(1996年)では、『開かれた社会とその敵』がヘーゲルに関する「神話」を広めた著作として挙げられている。ヘーゲルが弁証法を用いて他人を欺こうとしたというポパーの非難は有名だが、それは無知でもある。ポパーが『哲学科学事典』における音と熱に関するヘーゲルの説明を「失言」であると非難したのと同様、彼はヘーゲルが具体的に何を意味していたのかそれ以上詳しく述べてはいない」とスティーヴン・ホウルゲイトは書いている。
投資家のジョージ・ソロスが創設したオープン・ソサエティ財団は、名実ともにポパーの著書に触発されたものである。

「イングランド銀行を潰した男」の異名を持つ
哲学者のジョセフ・アガシは、歴史主義がファシズムとボルシェビズムの両方に共通する要素であることをポパーが示したと評価している。
関連記事
最後に
最後までお付き合いいただきありがとうございました。もし記事を読んで面白かったなと思った方はスキをクリックしていただけますと励みになります。
今度も引き続き読んでみたいなと感じましたらフォローも是非お願いします。何かご感想・ご要望などありましたら気軽にコメントお願いいたします。
Twitterの方も興味がありましたら覗いてみてください。
今回はここまでになります。それではまたのご訪問をお待ちしております。
今後の活動のためにご支援いただけますと助かります。 もし一連の活動にご関心がありましたらサポートのご協力お願いします。
