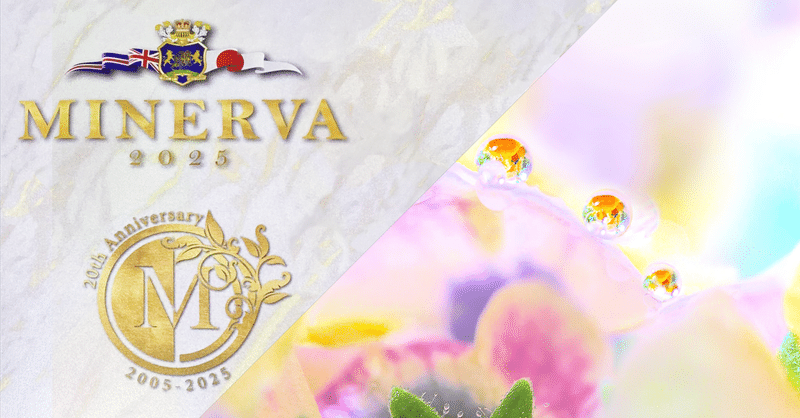最近の記事
- 固定された記事

続報 森永卓郎さんの「告発」政府とやり取りした結果の疑問。何故、墜落した日航123便の機長らは、酸素マスクをつけていなかったのか?横田空域、横田ラプコンとの関係は? 2024/07/22
20204年 令和6年 7月22 月曜日 朝の6時57分を回りました。原口一博です。 えっと、JAL123便の墜落事故の調査 の 続報です。 え‥その前に、亡くなられた方々に心から哀悼の誠を捧げ、ご遺族にお悔みを申し上げたいと思います。 え‥政府とやり取りをしたんですね。というのは‥もう今頃なんでそういうことやるかと言うとですね。これが、この事故によって日本がそのさらに続行化を進めたんじゃないかっていう人が、このところすごく増えてきてるんですね 今僕は『日本独立』っていう
- 固定された記事
マガジン
記事

救国内閣をどうやって創るか。鮫島浩さんとの対談。民主党政権の誤りを正しく総括するところから始まる。(その一) 2024/01/11
皆さんおはようございます。2024年1月11日。今日はですね、私の講演の第八回発足記念日でもあります。みなさんから沢山のご支援賜りまして、お礼を申し上げます。また、被災地に対しましてですね、いま後方支援してるわけですけれども、多くのみなさんからご協力を頂き、被災地で一生懸命救命救援、そして救援活動してくださってるみなさんに、あらためてお礼を申し上げたいと思います。 ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈✄ また、私の活動についてもですね、ほんとに拡がってきました。龍を探せ、と言うことを、
-
-