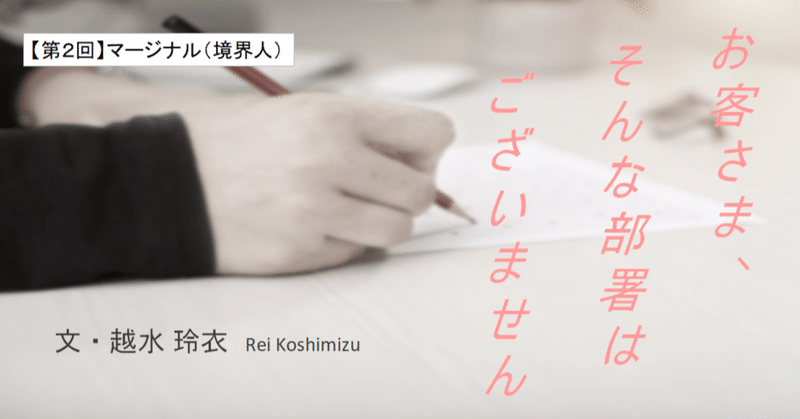
市役所小説『お客さま、そんな部署はございません』【第2回】「マージナル(境界人)」
注)これは少し前のこと。私が働いていた場所での出来事と雑感を「セミ・フィクション(ゆるやかな事実)」的にまとめたお仕事小説。
毎週日曜・夜9時頃に更新予定です!
「あの家の親父さんお役所だよな。出世してんのかな」
「友達の息子さん、市役所受かったって。いいわねえ、安定していて」
おそらく誰しも人生のどこかで、こういう言葉を家族や知り合いと交わしたことがあるだろう。しかし実際にその人が働いているところを目撃したことがあるという人は、意外に少ないのではないだろうか。
それもそのはずで、多少大きい市や区であれば職員なんてほとんど他人同然の集合体なのである。ましてや市内や区内に住んでいなくて、他市町村から通勤している職員となればもう「あんたどこの誰」状態だ。しかし間違いなく役人とは、ほとんどの人にとって憎むべき一属性のひとつになっているのだろうと思う。
それどころか、普通の人間だとすら思われていないフシも、ないでもない。それだから、時々こんな身も蓋もない投書が届いたりする。
「昼休みにカップ麺を食べてる職員がいたが公務員としていかがなものか」
(イカガナモノカ、といわれましても・・・)
「仕事中に飲んでるペットボトルの商品ラベル、見えてますよ?」
(市役所はNHKではないんですが・・・)
「〇〇課の奥の男の人、あれ絶対カツラだよな」
(それ知って、何になるんですか)
役所に設置しているご意見箱には、知らない誰かの入れた、こういう類の投書がけっこう来る。(()内は私の所感(ツッコミ)です)
そしてやっぱり私たちへも、来るわ来るわ。
一番目立つ位置にいる私たちへの「ご意見・ご感想」が、まるでヤフコメのようにやって来るのだ。
「総合受付の人たちの雰囲気が何かキツそうです」
「拝見した限りでは、期待外れの人選でした」
「最悪20代後半までで。受付って普通は若い女性でしょ」
「手続きのことを聞いたけど、よくわからなそうだった」
毎日業務を終えると、コンシェルジュデスクの右わきに置いてあるポストを覗く。そして郵便屋さんのように裏から取り出して総務課に持ち帰る。投書は例外なく、総務課の課内で回覧されることになっているからだ。
指摘のあったご意見には素直に耳を傾け、カイゼンに努めるべき。
それが女性部長のポリシーだからだ。
知らず知らずのうちに観察されている。
何にせよ、ご意見をポストから出して「これ私(たち)のことだよね」と思いながら総務課の担当に手渡し、課内でそれを回覧され、それが自分のところにも回ってきて、自分のことが書かれた「晒し物」を再び自分が見て、その上「見ました」のハンコを押して次の人に回すという一連のルーティンが、精神的にキツかった。
上司からは特に注意もない。総務課とコンシェルジュデスクは遠く離れているから、何が起きているのか誰も把握できていない。ゆえに、誰も何も言えないのだ。しかし私にとって、この回覧文書は十分に「恥」の意識を煽られる。そしてそれは、エンヤマさんも同じだった。
こういうことが起こるたびに「前任者といえる職員が誰も存在しない」ということが、私たちを途方に暮れさせた。
何を誰から習えばいいのだろう。
だったら誰を手本にしたらいいのだろう。
何をどこまでやったらいいのだろう。
どういうふうに、そこに存在していたらいいのだろう。
この「晒し物」のなかで本当の苦情といえるものは、ハッキリ言って4番目のものだけだ。
これだけは、移築オープンしてまだ1か月とたたない私たちの経験のなさから来ているものだ。それは申し訳なく思える。結局は、尋ねた人の力になれなかったのだから。
自分が本来負けず嫌いだったということは、前回自覚したとおりだ。だからこそ早く、何を聞かれてもいい状態になりたかった。まだまだ知らないことがあるというストレスから、一日も早く解放されたかっただけかもしれない。あまりにも「底が見えない」ものだから。
この市役所業務というのもは、知れば知るほどはまっていく沼のようなものなのだ。多岐に渡る手続きは複雑かつ相互に関連し合い、とんでもなく奥が深いことがわかってくる。知れば知るほど、知らない何かがその奥に見えてくる毎日。蟻地獄のようだった。
こわい。怖すぎる。
毎日、毎瞬が「抜き打ちテスト」。
よくある手続きならいいが、そこからちょっと踏み込んだ領域に入ると、とたんにワタワタしてしまう。
「中のひと」になったあの日のこと
これより5年前。
今住んでいるところに引っ越す前のこと。
生まれ育った街で、私ははじめて市役所の「中のひと」になった。
一時的に繁忙することのある市役所窓口だが、そういう時は決まって「臨時職員」の募集が出る。しかしその年は、なぜかいつもより人の集まりが悪く、本格的に人手不足に困っていたらしい。
雇用契約最長5年のフルタイム臨時職員を、ハローワークで募集していた。
例のデザイン部を辞めて「次は何しようかなあ」と決めかねていた私に、ハローワークの窓口の人が「デスクワークだったら、これどうですか。急募なんですよ。行ってやってくださいよ」と、まるで学生アルバイトみたいなノリで勧めてくれた。
午前中に応募が決まると、面接は今日の5時でと言われた。慌てて帰宅し履歴書を整え、夕方には市役所ロビーにいた。そしてひとり静かにキョドっていた。
これまで市役所というものにほとんど出向いたことがなかったと、我ながらようやく気がついた。何をする場所なのかすら想像できないほど、私の人生においてノーマークだった場所だった。私は何故ここを受けたのか、自分でもさっぱりわからない。ノリとしか、言いようがない。
その日は週末で、夕方のちょっとしたピーク(金曜日の夕方は少しだけ混む)だったらしく、まずまずの人出があった。それだけで圧倒された。
人波が四方八方にいり乱れる1階フロアの奥に、やっとのことでエレベーターを見つけ、恐る恐る乗り込んだ。
幸い、ほかに誰も乗ってこなかった。
ひとりになり、やっと深いため息をついた。
やっぱ気後れするなあ・・・
変な汗をかいているようだ。
エレベーターが上昇し、最上階に着いた。
扉が開いたとき視界いっぱいに見えたのは、広い赤絨毯の床だった。
真っ赤なフロアのつきあたりに宴会場・・・じゃなかった「大会議室」と書いた扉がある。
電話によると、ここが面接会場として指定されているはずだ。
存在を消して(とにかく目立ちたくない)歩きながら、ふと横を見ると「秘書課」と書いてある部屋が見えた。半開きになっていたドアから、黙々とパソコンに向かっている職員たちの横顔が見える。
ここに望んで入った人々だ!!!
ヒエーーー
とんでもなく場違いなのではないか。
怖気づいた悲鳴しか出ない。
すると、大会議室の扉の前に人影がふっと現れた。細身の眼鏡の男性が私を迎え、にこやかに声をかけてきた。
「ネコミズさんですか。わたくし、人事課のマキノといいます」
そう言って胸元のIDを私に持ち上げて見せる。
「あっ、本日はよろしくお願いします」
「こちらこそ急ですいません。今ちょっとこの・・・大会議室のカギ、開けますね」
マキノさんはズボンのポケットから、土蔵用なのかと思うほどの古風なカギを取り出し、扉に差し込んでガチャガチャッとやった。
あれ、意外と穏やかな口調。
少し動悸が収まってきた。
古い市役所特有の、威圧感漂う会議室。
足を踏み入れた瞬間、静寂がツーンと耳にきた。
手前の隅に会議用の机が1つ、向かい合わせにイスが2つ置いてある。大会議室は予想以上に広く、ゆうに300人は入るのではと思うほどだった。
そこに、たった2人ということか。
かくして私たちは、大会議室の20分の1以下のスペースを使って面接をしている。著しいスペースの無駄が生じていた。
ほかに空いてる部屋なかったのかよ・・・
大きすぎる部屋に気が散った私に気づいたのか、マキノさんは話を中断して少し笑った。
「すいません、今日はここしか空いてなくて」
察してくれた・・・じゃなくて。バレてるぞ?!
意外にあなどれない職員かもしれない。
さすが人事課だ。
話のあいまにIDに目をやる。
主査・・・
この肩書きがどのくらい偉いのか、当時の私では全然わからなかった。(実は中堅どころで管理職ではい。それくらい急募だということだ)
物腰は柔らかで、人当たりは良さそうだ。
しかし声が異常に小さい。
大広間に2人だったおかけでなんとか聞き取れたが、ざわつく窓口なら致命的である。完全に「大丈夫か?」というレベルだ。
異動がある職員でも、いずれこうして「畑」が決まっていくのだろうか。
それから私は、すぐに「中のひと」になった。
それでも最初は、不思議な気持ちにとらわれていた。
トイレに行った後、鏡に顔を近づけて
「どうしてここにいるんだっけ?」
と思ったものだ。
首には赤いストラップのID。
念願のIDである。
不思議なものだ。
ほんの数日前まで、私はカウンターの外で不安げにあっちにこっちにと歩く人だったのだ。まして公務員試験を受け、将来の職業として希望して入ったわけではない。これは努力の結果でもなく、念願の場所でもないのだ。
だからこそ、私はけっして外のことは忘れてはいけないと最初は強く思ったものだ。
「外の人」だった時の、あの不安な気持ち。
これが市民の当たり前の気持ちなのだ。
ここに染まりきってはいけない!と。
そうは言っても、少し働くと見えてくるのだが、本当にいろいろなタイプの人がやって来るのだ。そもそも見た目が怖い人に、わからず屋。やたらイチャモンをつけてくる人。悲しいことに、そういう場面を重ねていくうち、非正規雇用ですら次第に、外にいた頃の自分を忘れていくのだ。
慣れた、馴染んだ、ともいう。
けれど今度は、市民に「現実味」を感じられなくなっていくのだ。外の人たちが、いつのまにか「匿名の、めんどうくさいだけの人たち」に思えてくるのである。
実際、そういうふうに完全に市民を下に見ることが定着してしまった職員もいる。残念なことに、念願叶って入った新人さんですら多分に洩れず、毎日こんな雰囲気にマリネのように浸かっていると、ものの数ヶ月で同じようなタイプの職員に仕立て上がってしまうのだ。
まるで「最初からそうなりたくて入った」かのように。
市民には市民の言い分がある。
「複雑・横柄・理屈っぽい」
この3点セットを1つでも経験している人は多い。ゆえに役人とは「税金泥棒」「怠け者」ーーそう思うのは、ごく当たり前なのだと思う。そして間違ってもカップ麺など食わない生き物だと思っている、ほどの人もいる。
お互いがお互いを「仮想敵」だと思っている。
その両者の境界は窓口に設置されたカウンターだ。そこに配備されるのは、非正規雇用の私たちなのである。
私はマージナル(境界人)
ある混み合う月曜日のことだ。
「ねえ、あんたたち・・・」
コンシェルジュのカンターにいる私とエンヤマさんに、用事を済ませた中高年の男性が、笑顔で声をかけてきた。
定年するかしないか、くらいの中高年だ。
来ていた黒いTシャツには「Pizza of Death」と描かれている。
手にはたった今交付された何かの証明書がある。
用事が済んで、これから帰るところらしい。
「ありがとうございました・・・」
2人でそう頭を下げかけたその時だ。
おじさんにピシャっと言葉を遮られたのである。
「ボーナスの時期だねえ!」
意味ありげに笑った。
「・・・?」
私たちがキョトンとしていると、おじさんの目が急に険悪になったのがわかった。怖い。
そしてカウンターに肘を乗せて、身を乗り出してきた。近い。
「いくら貰うの?」
「・・・?」
その言い方に、驚いて固まってしまった。
声をひそめ「これから裏金をもらうことを、俺は知っているんだぞ」そんなシーンで使う時のような声色だったからだ。私たちがさも悪いことをしていることを知らしめ、だから辱めて当然だ、そんな下心が声の端々に埋め込まれていたのだ。
おじさんの目がマジなことに、恐怖が走った。
結局、何も言えなかった。
おじさんは私たちの言葉を待たず、早足で外に出て行った。
しばらく呆気にとられた。
息を止めていたらしい。
我に返ると、腕にものすごい緊張が残っていた。
この高圧的な言葉こそ「攻撃」だ。
やっとのことで言葉を振り絞る。
去っていくおじさんの背中に、私たちは呟いた。
「ないよね、ボーナスなんて」
その後も何故か、ボーナスおじさんはわらわらと沸き出て来た。
そうかm職員はボーナスの時期なのか。今さら気づいた。
「ボーナスがあっていいねえ!」
「いっぱい貰うんでショ?」
「へーそこに座ってるだけでボーナス出るんだ?」
私たちは申し訳なさそうに、小さく会釈するのが精一杯だった。
そういうことを言う人たちは、言い終わると決まってすぐに立ち去る。その素早さはピンポンダッシュ並みだ。
まさか。
まさかおじさんたちは、本当に知らないのだろうか。
私たちは中でも外でもない、その中間に立つマージナル(境界人)だということを。
5年後は、私たちだって外に戻るのだ。
今日「いいねえ」と言ったあなたと同じところに、どうせ戻るんだよ?
「わたし役所キライだから。働くのも無理」
幼馴染みの友達は、私が臨時として働き始めた時、そう私に言った。その言い方には僅かながら「嫉妬」と「敵対心」が含まれていた。
でも、それが普通じゃないかと思う。
結局、人様のオフィスに出向くなんてことは、誰だって苦手なのだし、特に役所となればなおさらだ。だから多少マゴついたり、書類を書き損じたり、普段ならわかりそうなことも一瞬わからなくもなるし、どこから話したらいいかわからなくなる。役所は私を緊張させるーーー
逆に「そこだけ」を切り取った役人は、市民を「無知」だと決めつけてしまう。
嗤わないでほしいのだ。
迷っているところを見て、間違ってしまったところを見て「普通の人って、こんなこともわからないのね」「市民って、書類一枚書けないんだよな」と冷笑しないでほしいのだ。私だって、今もし裁判所や法務局へ行けば、まず絶対にキョドるだろうし、そもそも他人のオフィスに出向いて、悠々としていられる人なんてほとんどいない。
人格者であろうと思うからじゃない。
無駄に争いたくないからだ。
しかし、だよ。
ああいうピンポンダッシュな輩に対して私は(ご存じのとおり)、いやエンヤマさんも、いつまでも黙っていられるようなタイプ・・・ではなかった。
ある日。
またしても別のおじさんが笑顔でやって来た。
「いいねえ、職員は」
ほーら始まった。
どうせ次には「ボーナス云々」「給料云々」「税金云々」と言うのだろう。
だから私とエンヤマさんは、笑顔でこう言うことにしたのだ。
「いえ!私たち、職員じゃないんですよ~」
一瞬、止まるボーナスおじさん。
「え?」
「違うの?」
私たちは手を前でひらひらさせて、こう返した。
「私たち非正規なんで、ボーナスなんて無いですよ~」
おじさんはポカンとして、目と口を小さく丸くすぼめた。
まさか。
いや、やはり?
予想外だったようだ。
おじさんの顔が、3つの点の集まりみたいになっている。
「あ、そう・・・」
おじさんはそそくさと、正面玄関を出て行った。
女2人に言い返されて、悔しいでもない。
かといって憐れんでいるかというと、そうでもない。
確実に戦意喪失した、萎えた、という顔。
これはこれで、何か「気持ち悪い」反応だった。
私たちはマージナルだ。
だからこそわかるもの、見えるものがある。
職員になると見えなくなるもの、市民には見えないもの。
それをいつまでも私は抱いていたい。
そうでないと、腐る。と思う。でも、
「不毛なことも、したくないよね」
2人で小さく笑った。
毎日の労働から早く解放されて専業ライターでやっていけますように、是非サポートをお願いします。
