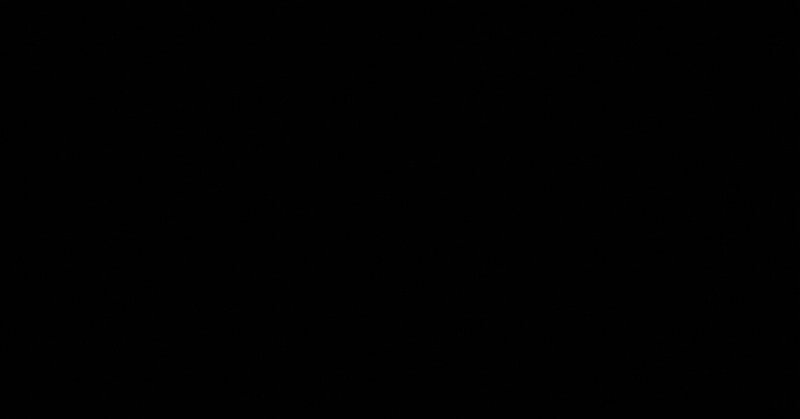
闇を思え
私がまだ小さかったころ、深い夜の街を両親と弟といっしょに歩いたときのことを、なぜだか忘れられずにいる。深夜23時くらいだったろうか。子どもの私にとって見覚えのある街はいつも昼の格好をしていたから、「真夜中の街」という新しい側面を発見し、そのなかを探検することに、何らかの高揚を覚えたのは確かだろう。
それから夜の街――ここで「街」というのは、家の外にある人工的な環境と考えてもらって構わない――は、特別な感慨をもたらすものとして常に私の心の中にあったと思う。たまに通り過ぎる車が引き裂く風の音。暗闇をじっと照らし続ける街灯。静けさを規則的に攪乱する私の足音と呼吸音。そのどれもが、夜の街の闇に対する、高揚感を伴ったイメージの形成に一役買っていたとは思うが、とりわけそういった想念を育てたのは、やはりあの心地よい冷やかさではなかったろうか。それは必ずしも風によって運ばれる一過性の冷たさではない。それは、常に闇を満たし続け、私がいま夜の街を徘徊していることを不断に証明してくれる冷やかさである。私はその冷やかさに誘われて、闇の世界に沈潜する。その闇の中では、どうあがいてもその冷やかさから逃れることはできない。たぶん、うだるような暑さの夜に外に出歩いたとしても、たいしてテンションは上がらないだろう。
そう考えると、夜の街は夜の街でも、私がより好んでいるのは「冬の」夜の街なのだ。深夜に冬の街を歩いていると、たとえそこが活気あふれる繁華街ではなかったとしても、あるいは、とりどりのイルミネーションによって美しく装飾された一面の花畑でなかったとしても、ワクワクした気持ちを抑えることができない。静寂のなかで、昼には聞こえようもない遠くの踏切の音が聞こえてくると、夜の街をじゅうぶんに堪能している感じがして、とてもうれしくなる。斎藤茂吉のあの有名な短歌の舞台は、ここにもあるような気さえしてくる。
〇
闇について考えることはたまにある。それは心の闇であることもあるが、物理的な闇であることのほうが多い。それは街の闇にとどまらず、闇一般を相手取った思索である。『陰翳礼讃』で谷崎潤一郎がくりかえし述べているように、電燈の急速な普及によって都市は過剰なまでに明るくなり、「陰翳」と呼べるようなものは絶滅しつつある。私は都市(都会とはいわないでおく)に住む一介の現代人であるので、かつて日本全土を覆いつくしていた暗闇がその姿を消してゆく過程をこの目で目撃したわけではもちろんないのだが、いまも残されている暗闇――都市ならどこにでも転がっているような暗闇ではない――と対峙した経験から、日常私たちの暮らしている都市空間のいびつな眩しさを、それこそ逆照射されるような形で理解しているつもりではいる。
私の祖父の生家は三重にあって、二年前までは毎年そこに住んでいる祖父の兄を訪ねていた。大阪の実家から車で結構な時間がかかるので、車酔いのひどい私はもどしてしまうのがいやで、その帰省のようなものを毎年やってくる悪夢のように感じでいなかったわけでもない。そのうえ、家に着いたら着いたで真っ黒な袈裟を着た住職がひたすら唱える念仏を正座しながらじっと聴きつづけるというのも、年頃の子どもにとっては責め苦以外の何物でもなかった。それでも、都市的な「べんりな」暮らしに慣れ切っていた私にとっては、そうした田舎の雰囲気や風景はとても新鮮に感じられ、たとえば、築何十年かもわからないような木造の家の床が、その上を通るたびにギシギシと軋むのがなんだか心地よくもあった。ぼっとん便所のあのいやな臭いや、技術革新に取り残された旧式のテレビはさることながら、やはり「木造」という要素が私の田舎の家にたいする心象形成にもっとも大きな影響を与えているような気がする。石膏ボードからは感じられるはずもない、木特有のにおいが、あの家には充満していた。「夜の街」についての感慨と同じように、どうやら私は、私を取り囲んで離してくれないもの、私をどっぷりとその中に浸しこんでくれるものに惹かれるらしい。それが冷たさという知覚的なものであれ、匂いという物質的なものであれ、なにかそれ特有の世界観を常に提示してくれるものに身をゆだねるのが好きなのだ。
関係のないことを長々と書いてしまったが、「闇」についての話だった。祖父の実家に毎年赴くのは曾祖父母(祖父の両親)の墓参りのためである。曾祖母は私が物心つく前に他界し、思い出と呼べるものはない。(こう書いていてふと思い出した。この前昔の写真を漁っていたら、二歳くらいのまだかわいかったころの私とそれを囲む家族のうしろのほうにあった棚に、ぽつんと曾祖母の遺影が置かれていたことを。)曾祖父とは何回か会って話した記憶がある。長命な人で、95歳まで生きた。最初はひとり、途中からはふたりの墓参りのため、春先にわざわざ三重まで足を運んできたのだった。祖父の家系の墓は、家の近くの山にあって、そこへ行くには急な坂道をのぼったのち、これまた急な階段(もちろん木製の)をのぼらなければならなかった。その頃は活発ながきんちょだったから疲れなど知らなかったが、自分の身長の十何倍もあろうかという木々がひしめき合う暗々とした空間に足を踏み入れると、まるで異世界へ迷い込んだような感じがして、自分の存在のおぼつかなさを思い知らされているようだった。墓参りが終わると、家に戻り、そこで寝泊まりするわけだが、ここからが闇の本領である。田舎には街灯が少ない。まだ生活の大部分を親に依存している小さな子どもだったから、夜に外を出歩くなどという真似はとうていできなかったが、家の中から見た「田舎の闇」はまさしく闇であった。それは大阪の実家の居間で過ごす夜をふちどるあの闇とはわけが違う。そこに広がっていた闇は、照らされ、明るさに駆逐されることが目指されているような闇ではなかった。むしろ、なにか「闇」という実体をもったものがそこに横たわっていて、あんぐりと口を大きく開けているかのように思えた。まわりにあるものすべてを丸のみにして、永久に閉じ込めてしまいそうなほど凄みのある闇だった。家の前にある闇でさえそのような観念を惹起するのだから、あの墓があるところに巣食う闇はいったいどれだけ凄まじいのだろうか。それをいったん目撃してしまったら、もう二度と戻ってこられないのではないか。
こういった形で私が(間接的ながらも)体験した一連の闇に対する恐怖や凄絶さは、ところが、こんにち私たちが「ふつうに」暮らしを営んでいる都市空間には存在しないのではないだろうか。もちろん都市にだって闇はあるし、それが何らかの恐怖を感じさせるのは確かだ。でも、その闇、その恐怖は、やはりあのとき私が受け取った田舎的闇のそれとは性質を異にしているように思われる。都市における闇は、「明るくない」状態――光の欠如態――であるといった方が正確ではないだろうか。そこでは明らかに、闇から遠ざかり、光へと無限に近づいていくような志向性が展開している。その展開の結果、夜になってもいろいろな話し声が響き渡り、そこから蒸発した興奮や熱気が人の流れによって攪拌され空間全体を染め上げていく、暴力的なまでに眩しい世界があちこちにみられるようになった。人間の活動範囲を規定するものとしての光、すなわち《非》闇は、その性格からしてあらゆる大地をくまなく照らして、それまで闇の領分だったところをたちまち人間様の通り道へと変えてしまう。「人あるところに光あり、光あるところに人あり」という文句が空気のように私たちのからだに自然に浸透している限り、光の拡大は止まらないし、闇の絶滅も止まらない。光一強の時代で、闇は迫害されるしかなかったのだ。
私たちはあまりにも光に目が慣れすぎている。大正から昭和にかけての時代を生きた谷崎でさえそのような警鐘を鳴らすくらいなのだから、現代の人間がどれほど明るさを当然のものとして気にも留めないかは、推して知るべしだろう。不気味なもの、危険なもの、恐ろしいものとして闇を排斥し、光で置き換えていく精神性は、「安楽」を求めて不快の源を徹底的に除去しようとするがあまり、その「安楽」を喪失することに対するいら立った不安に絶え間なく駆られるようになる逆説が発生するという藤田省三の指摘を思い出させる。彼の言葉を拝借すれば、このような状況は「光への隷属」とでも呼べようか。私は、そういった形で世界を光一色でべったりと塗ってしまうことで、なにかたいそう恐ろしいことが起きてしまうような気がしてならない。光という一元論でもなく、光対闇という二元論でもなく、光と闇のあいだの連続性としての「陰翳」を大切にすること。大げさな言い方ではあるが、こういった意識を持つことがなければ、現在繁栄の真っただ中にある人間の王国は、いつか自分の手で自分の首を絞めることになるだろう。光を人間のメタファーとして、闇をありのままの自然のメタファーとして理解するならば、ここでの主張は文明批判にも重なる。ただしここで主張されているのは、文明一辺倒でも、自然一辺倒でもない。光も闇も、人間と自然も、そもそも、はっきりとは区別できないスペクトルの中に抽象的に存在しているに過ぎない。言葉の弁別性によって虚構として組み上げられたその対立構造を、自明性の檻から解放するときだ。そして、人間は自らが作り上げた世界に閉じこもってその外側から目を背け続けるのをやめ、それらとの関係をいちから考え直すべきだ。
照らされるものとしてではなく、こういった言い方をしてよければ、闇色の光を放つものとして闇を捉えかえすことは、私たちの生活における《光》や《闇》の存在の仕方、認識の仕方、果てには世界へのかかわり方に、何らかの変容をもたらしうるものであると思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
