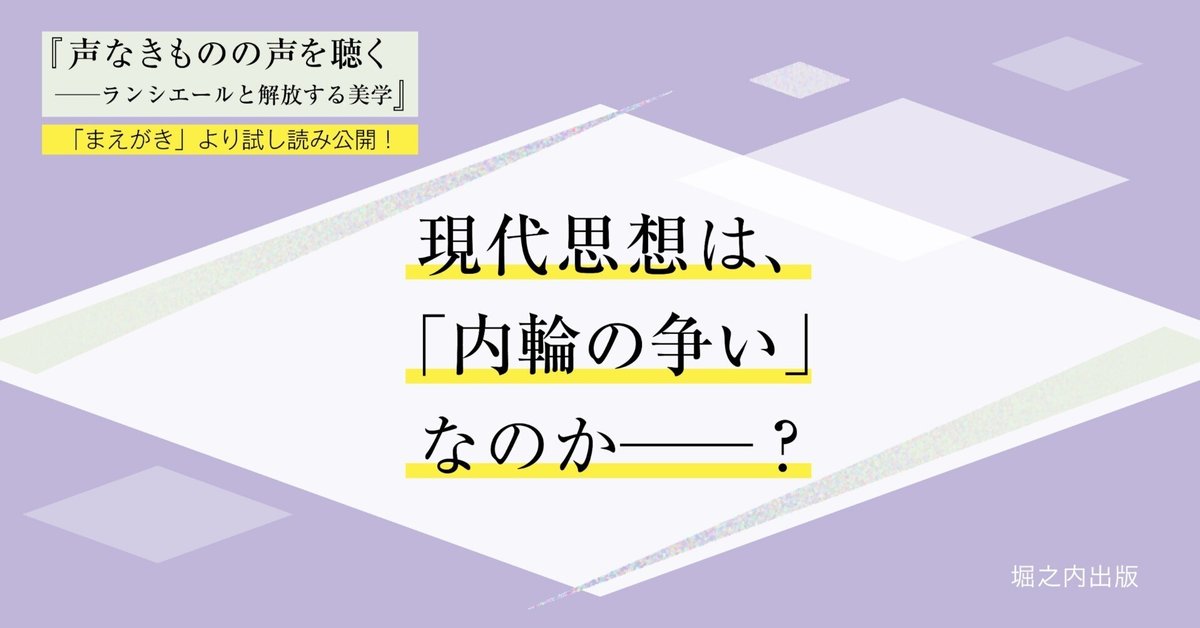
『声なきものの声を聴く──ランシエールと解放する美学』 試し読み公開!
弊社既刊、『声なきものの声を聴く──ランシエールと解放する美学』のまえがきを公開します。本書は、フランス現代思想の重鎮、ジャック・ランシエールの美学思想をテーマとし、ランシエールの思想を通じて、下記のような疑問に迫る一冊です。
現代思想は、内輪で各々の思想を卓越化し合うだけで、実際的な力を持っていないのではないか?
現代思想は机上の空論で、今なお続く世界の悲惨を変えてはくれないのではないか?
テクストを読むこと、思想を練り上げることは、社会においてどのような力を持つのか?
試し読み(書籍「まえがき」より)
本書はジャック・ランシエール(Jacques Rancière 一九四〇─)の美学・芸術思想に関する研究である。
ランシエールは世代的にも活動地域的にも、構造主義以降のいわゆる「(フランス)現代思想」の潮流に身を置く哲学者である。「現代思想」に関わる人々の営為はしばしば、他の思想に対する自らの思想のポジショニングによって特徴づけられてきた。つまり、自らの思想が他の思想とどのように違い、どのように優れているのかを、絶えず追求し強調する姿勢である。「現代思想」のこのようなあり方を指摘した文献として、まずフランソワ・キュセの『フレンチ・セオリー』を挙げることができる。
ミシェル・フーコーやジル・ドゥルーズ、ジャック・デリダ、ジャック・ラカンら二〇世紀後半のフランス人思想家の──典型的に現代思想的な──議論が、いかにして「フレンチ・セオリー」としてアメリカの知的業界に輸入され、誤読や単純化を含めアメリカナイズされたかを論じたこの著作において、キュセは、アメリカの大学人は討論や政治活動といった公共空間での社会的貢献ではなく、テニュアトラックの獲得やより多くの業績の積み上げといったもっぱら専門分野内部での卓越化の戦いに汲々としていると詰った上で、こう続ける。
こうした戦いに勝つためのただひとつの基本原則は、絶えず知を刷新し、内部の基準では測れないような(新しい思想がその新しさを認められることは難しい)独創性を獲得することである。そのための基準となるのは、ライバルとなる研究者を払いのけ、有名な同僚の主張を時代遅れのものにする能力、今ある研究分野のあり方から逸脱し、その分野においてこれまでほとんど使われてこなかったがゆえに最も効果的な概念を最小限の努力で見つけ出し、それを突きつける能力だけである[注1]。
そしてアメリカの学者たち──ここではジュディス・バトラーやフレドリック・ジェイムソンらが挙げられている──は、こうした独創性の獲得のために、フランス現代思想の理論をいわば降霊術のように召喚し、それによって名声を獲得してきたという。
アメリカで英雄とされる理論家たちの名声は、その大部分を偉大な著者たちからの独自の影響のされ方に負っており、それが彼らのトレードマークだと言える。彼らはそうした偉大な著者たちの名を引き合いに出して、そこに自分の姿を重ね合わせ、彼らの論を引用して自論の展開に巧みに活用するのである[注2]。
このようにキュセは、現代思想の独創性・新規性の獲得ゲームが、得てして象牙の塔での内輪の争いに終始し、真理探求や社会正義の実現から遠ざかりがちであることを、いくぶん戯画的にではあるが批判的に描き出している。
キュセが槍玉に挙げるのはアメリカでの「フレンチ・セオリー」の身元引受人たちである。ただしこうした事態はフランス本国での、現代思想の担い手本人たちにおいても同様だろう。哲学者の千葉雅也は『現代思想入門』において、「フランス現代思想的」な言説が生産され評価されるための(非明示的な)原則を、以下の四点に要約している(多少アイロニカルに言いかえれば、現代思想にありがちな四つの論法のまとめである)。第一に、先行議論がその体系・構造を安定化させるために意図的にせよ非意図的にせよ排除しているもの=他者的なものを指摘し、前景化させる「他者性の原則」、第二に、先行議論それ自体の成立条件を問題化し、より根本的な次元を提示する「超越論性の原則」、第三に、先行議論に対して自らの立場を際だたせるため特定の論点を誇張法的に極端化する「極端化の原則」、そして第四に、それら三点の追求によって現れる一般には受け入れがたい反常識的な帰結にこそ、人々の常識的世界観の超越論的前提があるとみる、「反常識の原則」である。具体的に言えば、マルティン・ハイデガーの存在論には他者が排除されていると糾弾しつつ、その他者を絶対的に到達不可能なものとして極端化するエマニュエル・レヴィナスの倫理学や、あるテクストの細部に着目することでそのテクストの(一見したところの)首尾一貫性を支える条件をあぶり出し、そこから純粋な真理の不在という反常識的な帰結を引き出すデリダの脱構築などが挙げられる。千葉いわく、フランス現代思想的な議論の特徴とは、例えば先行研究の論理的不備を指摘し補うとか、曖昧な概念を整理し明晰化するといったことよりも、むしろ以上四つのような手続きを通し、自らの新規性や独自性をいわば「逆張り」的に打ち出すところにある[注3]。
本書の全体がこれから描いてゆくように、ランシエールもまた先行議論に対する強い批判を通じ、自らの立場を差異化させてきた。本書の方法は、こうしたランシエール自身のテクスト的戦略によっても根拠づけられている。
ドゥルーズ研究者でもある千葉は、若干の距離を取りつつも、こうした現代思想のスタイルを是認する──「新規性とか差別化といった言い方はビジネスライクであまりよくないかもしれませんが、とはいえ、自分には他の人とは違う独自性があると主張しなければ学者だってやっていけないわけで、そこにはビジネス的な部分が実際あるわけです[注4]」。さらに言えばそもそも、こうした傾向は現代思想の領域に限ったものなのだろうか。
美学者の佐々木健一は『フランスを中心とする一八世紀美学史の研究』において、《月の皇帝アルルカン》の作者認定をめぐる問題──アントワーヌ・ウァトーの単独作なのか、師であるクロード・ジローとの共作なのか──を取り上げながら、興味深い観点を提示している。佐々木は、ウァトーの単独制作とみる「通説」に反対して共作説を採るアイデルバーグの研究に依拠してこの論争を取り上げつつ、最終的にウァトー説を支持するのだが、その際に、決定的証拠を挙げられないままに共作説を押し通そうとするアイデルバーグの態度に対して次のような想定を書きつけている。
「通説を覆すことは学者の勲章と見られるところがあり、美術史学者の仕事にはこれを「ジロー作」と見なそうとする動機が潜んでいるのではないか。探求の動機としては相当に強いものがありながら、それは同時に探求の方向を予め大きく規定する要因となる[注5] 」。
佐々木はここでキュセと同様の論点を美術史家に関して提出している。すなわち先行の通説に異を唱えて追いやること、それが学者に(独創的で新規的だとする)名声をもたらすのであって、その獲得に強く動機づけられたとき、厳密な論理性や実証性はしばしば後回しになりがちである、という論点である。
佐々木は美術史家を取り上げつつ学者一般が陥りがちな視野狭窄を戒めているかに見えるが、その原因となる学者特有のパトスについては、必ずしも批判的な立場をとっていないように思われる。というのも佐々木はこのに注を付し、解釈を「権威簒奪usurp」のためのものとする、アメリカの文学研究者ハロルド・ブルームの『アゴーン』に言及しているからである[注6]。ブルームの議論を見ておこう。「われわれ批評家が書くのは権威簒奪するためであり、それは詩人が書くのが権威簒奪のためであるのと同じである。何を簒奪するのか? 一つの場所、立場、一つの充実、そして自己同一化あるいは所有という幻想、すなわち何か自分自身のもの、ないし自分自身と呼べるものを奪うことである[注7]」。
ブルームによれば、偉大な先行詩人や先行論者に対し、後続する者──ブルームを含めた私たちはこちらの立場に置かれている──は常に、それらからの圧倒的な影響から逃れられていないという「遅来性belatedness[注8]」の不安にさらされている。先行者からの抑圧と不安を克服するために、後続者は「強い誤読」ないし「創造的誤読[注9]」を行うことによって、解釈行為において自分自身のアイデンティティを確立し、独創性を獲得しなければならないという。それがブルームの言う権威簒奪の解釈、すなわちいわば父権的に後世の詩人や批評家を抑圧する先行者に対する、後続者の闘争としての解釈である。
ブルームによる以上の立論は精神分析的なエディプス・コンプレックスのモデルに基づくものであるが、ここには明らかな政治的ニュアンスをも読み取ることができる。事実ブルームはこう言っている。「人間精神は王というものを抜きにして解釈における権威を想定することができない。解釈は暗々裡にヒエラルキー的含意を持っており、権威の簒奪なしに進展することができない[注10]」。解釈は旧来の権威と抑圧を打破し、新たに覇権を奪取する、ひとつの政治的実践の側面を持つのである。
かくして、本書が行う研究は次のように特徴づけられる。すなわちそれは、ランシエールが学者として有する、アイロニーでも「あえて」でもないパトスをあぶり出す作業であり、また彼が行う先行論者への批判や再解釈を、テクストにおける政治的実践として描き出す試みである。一言で言えば、ランシエールの美学・芸術思想が有する独自性と意義とを浮き彫りにすることを目指すものである。
だがここで、次のような疑問が提起されるかもしれない。すなわち、こうした「権威簒奪」の政治性は、単なる象牙の塔での内輪の争いを越えて、実際的な効力を有しているのか、というものである。それは机上の話であって、今なお続く世界の悲惨を変えてはくれないのではないか。テクストを読むこと、思想を練り上げることは、社会にとってどのような力を持つのか……。本書はこうした疑問に対し、次節以降で、ランシエールの「政治」概念をふまえることから出発して回答を与えるだろう。総じて示されるのは、読解と解釈、あるいは読み直しと再解釈が、感性の枠組みを変容させ、無名なものの声を聞こえるようにさせ、見えなかったものを見えるようにさせるということ、そしてそれを通じ、現実を変革させる可能性を開くということである。
本書の旅はそこから始まる。
【続きは書籍でお楽しみください。】
【注】
[注1] François Cusset, French theory : Foucault, Derrida, Deleuze et cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-Unis, Découverte, 2003, p. 208.〔フランソワ・キュセ『フレンチ・セオリ—──アメリカにおけるフランス現代思想』桑田光平・鈴木哲平・畠山達・本田貴久訳、NTT出版、二〇一〇年、一八六頁〕
[注2] Ibid., p. 209.〔同書、一八七頁〕
[注3] 千葉雅也『現代思想入門』講談社、二〇二二年、一七六─一九二頁。西洋近代の思想的特徴を共有可能な合理的体系の追求であるとすれば、フランス現代思想はそれについての自己批判と位置づけられる。コギト批判、啓蒙主義への懐疑と言い換えてもいいだろう(以下を参照。José Guilherme Merquior, From Prague to Paris: A Critique of Structuralist and Post-structuralist Thought, Verso, 1986〔J・G・メルキオール『現代フランス思想とは何か──レヴィ=ストロース、バルト、デリダへの批判的アプローチ』財津理・荻原真訳、河出書房新社、二〇〇二年〕; 岡本裕一朗『フランス現代思想史──構造主義からデリダ以後へ』中央公論新社、二〇一五年)。その体系に還元不可能なものの誇張的設定や非合理的狂気の導入といった千葉の論点は、それぞれ西洋近代批判の具体的側面であると見ることができる。
[注4] 千葉雅也『現代思想入門』、前掲書、一七七頁。
[注5] 佐々木健一『フランスを中心とする一八世紀美学史の研究──ウァトーからモーツァルトへ』岩波書店、一九九九年、一三頁。
[注6] 同書、三八八頁。
[注7] Harold Bloom, Agon: Towards a Theory of Revisionism, Oxford University Press, 1982, p. 17.〔ハロルド・ブルーム『アゴーン─《逆構築批評》の超克』高市順一郎訳、晶文社、一九八六年、三六頁〕
[注8] Ibid., p. 29.〔同書、三九頁〕
[注9] Ibid., pp. 6-7.〔同書、二一頁〕
[注10] Ibid., p. 43.〔同書、六七頁〕

著者プロフィール
1991年生まれ。現在、東京大学大学総合教育研究センター特任助教。専門は美学。主な論文に、「ランシエールの政治的テクスト読解の諸相──フロベール論に基づいて」(『表象』第15号、2021年)、「ランシエール美学におけるマラルメの地位変化──『マラルメ』から『アイステーシス』まで 」(『美学』第256号、2020年)。他に、「おしゃべりな小三治──柳家の美学について 」(『ユリイカ』2022年1月号、特集:柳家小三治)など。訳書に、ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『受肉した絵画』(水声社、2021年、共訳)など。
Twitter:@s_waterloo
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
