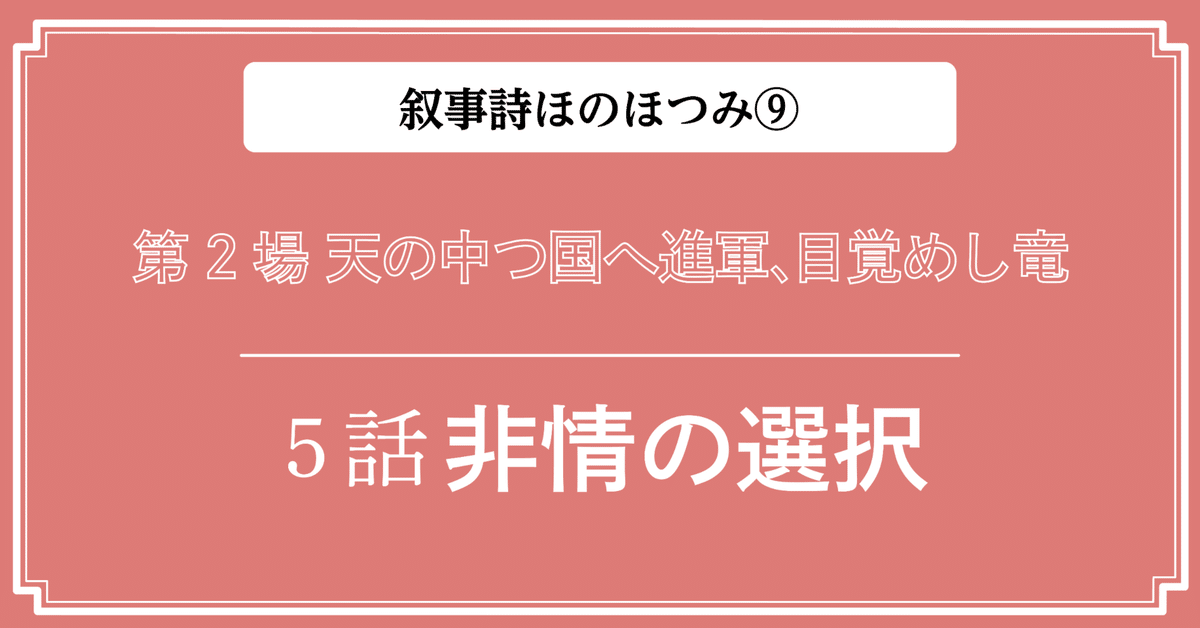
ゆけどもゆけどもぬかるみぞ

喜平が妻からの手紙を受け取り、その便りを読み、哀しんだ。が、喜平ひとりの哀しみとは無縁にあしかび国軍の作戦は、その日からさらに1年以上続いた。
思えば、大陸の東の大国、天の中つ国の南の都市に上陸して2か年が過ぎていた。
春、海と見まごうばかりの幅をもつ川面に、柳の穂絮が風にながされて舞っていた。その乱舞を楽しむかのように、ことのはを風に伝える神、ほのほつみが柳絮のひとつをまるで傘でもひらくようにつかみ、舞っていた。そして、ほのほつみは、部隊について回り、喜平を見守っていた。あるときは蟾蜍の背に乗って、また、あるときは蝶の脚をつかみながら飛んで。
いつ竜の災いが喜平に訪れるかもしれない。その災いを受けても喜平がこころ折れぬようにと。
齢40を過ぎて、兵が務まるかという喜平の不安は、天の中つ国への上陸後実戦を重ねるなかで、杞憂となり、むしろ喜平は若い兵たちひとりひとりの性格を知りつくし、束ねるまでになっていた。
火砲隊の実戦は、火砲を指定の配所に並べ、指令を受けて目標に向かっ砲撃を始める。
そのために喜平のなすことといえば、火砲をいかに運ぶか、その準備に日々明け暮れた。神出鬼没に敵の目をあざむき、思いもしなかった場所から火砲を撃つには、部品をいくつかに分け、そっと運び、それを素早く組み立てるという一連の動きを、着実に行うことが肝要だ。喜平の与る火砲は、山砲と呼ばれ、部品を解体できる。その部品を運ぶ役目を担うのが馬だ。
軽いもの、たとえば火砲の弾を打ち出す筒、砲身で20~30㎏はある。それを「重い」といって馬は文句ひとついわぬ。無論、そのためには馬の機嫌をとり、ときに手綱で励ます、馭者がいたればこそ、ではあったが。

喜平と同じ郷から戦のために徴用された馬、天竜号は、馬体が少し華奢だった。それゆえ、火砲を運ぶ輓馬でなく、兵や馬などの食料を運ぶ駄馬として役目を与えられた。その馭者が、|兼松(かねまつ)という20歳をわずかに超えた兵だった。兼松は、若いながら馬の性格をよく知り、馬の扱いになれ、我がこと以上に馬の面倒を見ていた。
喜平は、天竜号が我と同郷であることはその馬の名から知れた。栗毛の天竜号は、天竜の川の流れを想わせるように鼻に一筋の白い線が入り、くりくりした瞳は深い紺を帯びていた。喜平が軍の仕事の合間、折を見て、天竜号に近づくと、人なつこい性格からか鼻先を差し出してくる。そんなときは、喜平もよしよしといって天竜の鼻筋をなでてやりながら、馭者の兼松とひとことふたことことばを交わす。
「天竜号の調子はどうだ?」
「はい、上々です」
兼松がうれしそうに顔を上気させて応えた。
こうして、喜平は兼松との距離は少しずつ縮まっていった。
だからといって喜平は、天竜号を特別扱いにするわけにいかぬ。
喜平には部隊に必要なすべてのものを過不足なく整える役目だったから。たえず何が何個あり、何個足らなくなったということに広く目を光らせていなければならない。
が、喜平も人の子。こころの根っこで、天竜号は「いずこぞ」と目で探していた。
喜平は、行軍の小休止の際、天竜号に水を飲ませ、ほほをなでている兼松を見つけた。いつもの、馭者のあるべき微笑ましい姿だった。
しかし、それときの行軍は何日も雨が続き、兵も馬もさんざに濡れていた。しかも行軍は敵に見つからぬように、田や森の細い道なき道を進んだ。そんな行軍が何日も続く。
このとき、あしかび国は物資が足りなくなっていた。軍馬の鞍は革ではなく、ズックと呼ばれる粗い布で作られていた。布製ゆえに、荷を載せたときに皺がよりやすい。
荷を運ぶときに皺となったところに荷の力が加わると、すれて馬の背に「たこ」ができ、ともすると皮がむけて血がでる。
目配りのきく馭者は、荷を載せるときはまず鞍のしわをのばす。そして、休憩ともなると、一度荷を下ろし、馬を休ませる。が、そのつど、馬の背を優しくもんだり、わがことよりも馬の面倒に明け暮れるのが馭者の務めだった。
農民の出として馬がどんなに大切か、喜平はそのことを身に沁みていた。それだけに、自分より年下の兼松を弟のように想い、「かわいいやつよ」とこころの奥で思った。
その日、さんざんな雨に降られ兵も馬もすっぽり濡れ、ほとほと疲れはてていたが、兼松は、唯一身の周りで濡れていない己の褌を取り外し、それで天竜号の背を拭き、もんでやったのだ。
兼松の天竜号に寄せる思いのなみなみならぬ強さを喜平は知った。そればかりでなかった。田の畦を進むとき、兼松は自身は田のなかにに足を付け、馬には濡れないあぜを譲っていたのだ。
馬のひづめに履かせた蹄鉄が緩まぬようにという兼松の配慮を喜平は悟った。
田の泥水に足を浸して歩けば、当然、靴のなかは濡れる。濡れても足を渇かすいとまもない。そんな兼松は、足をひきづって歩いていた。それに気づいても、心配する者はいない。だれもが自分のことで精一杯なのだ。

行軍が一段落したある日。天の中つ国は、ようやく酷暑の夏が過ぎ、秋に入った。
秋といっても昼の暑さはやや薄らぎ、朝夕にわずかに涼しい風が吹く。それでも兵や馬にはありがたかった。
軍事物資の一覧を調べていた喜平は、火砲を運ぶ輓馬の数が思った以上に足らぬのを知った。足らぬのは馬だけでなく、弾薬も食料も十分といえなかった。幸い若い兵士の多い喜平の部隊は、足りぬなかでも若さゆえに兵たちはまだなんとか乗り切っていた。
物資を手配するときは、まず喜平が部隊の本部に無線でその旨を知らせ、本部からさらにあしかび国の本国に依頼する手はずになっていた。その要望通りに物資が届くとは限らぬし、「いつ届く」とも知れぬ。
表向き、あしかび国の戦は、あちこちで連戦連勝といわれ、そのように報じられていた。妻のつねからの手紙も、食べることにまだこと欠いていないので心配しないようにと記してあった。ただ、砂糖などが家の人数により割り当てる「配給」になった、「頭分甘いものはがまんね」と付け足されていた。
では、異国の地で戦をするとき、物資が足りないと分かったときどうするか? それは全体の塩梅を見、足りているところから足らぬところへ回す。臨機応変が戦場の常だ。
馬でいえば、火砲を運ぶ輓馬の不足が大きい。それに比べ、荷を運ぶ駄馬は、まだ輓馬ほどでなかった。
「駄馬から輓馬へ、何頭か役割を変える必要があります」
喜平が隊長に報告した。
「あしかび国本部へは打診したのか?」
「はい、しかし、早くて半年後……。あるいはそれ以上待ってほしいと」
「よし分かった。そのように手配してくれ」
喜平は迷った。
駄馬のどれを輓馬に回すか? 一番先に候補に挙げたのが、状態が良い天竜号だった。しかし、天竜号の状態が良いのは馭者、兼松の献身故である。そして、兼松にとって天竜号がこの戦地においていかに心の支えになっているか。そのことも喜平はよく判った。
尾長鳥が尾を引くように夜の帳が落ち、雛が自ら殻を割るように朝の幕が上がった。秋の終わりに近い、よく晴れた日だった。
その日、ことのはを風に伝える神、ほのほつみは、常にない喜平の表情を見た。辛いけど、ひきしまった顔。そこに「我は鬼になる」といういつに見せぬ喜平の決意を見た。
「兼松上等兵、話がある」
「野木曹長、なんでありますか?」
「火砲を運ぶのに天竜号を使いたいのだが、承知しれくれぬか」
「……? それは命令でありますか?」
「そうだ」
「……いや、であります」
「お前が辛いのは、天竜号を自分ごと以上にのように世話を焼くお前ゆえ、よく分かる。儂もよくよく考えた、考えたすえだ。どうか隊全体のためだ、頼む」
「……。野木曹長、どうか頭を上げてください。承知、しました」
「すまぬ。
で、もうひとつ。これはおぬしへの命令だ」
喜平は、兼松の靴を脱がした。兼松の足裏はまるでよくふやけたまんじゅうのようだった。が、まんじゅうと違うのは、そこから異様な匂いが発せられていることだった。
「これでは行軍は無理だ。すぐ部隊を離れ、治療を受けるように、良いな」
兼松は歯をくいしばった、そして、声が洩れぬように息をのみこんだ。
「ここまで天竜号の面倒をよく見てくれたな、感謝する」
喜平の手がそっと兼松の肩に乗せられた瞬間、兼松の身体は大粒の涙とともに崩れおちた。
ことのはを風に伝える神、ほのほつみが蒲の穂綿を兵の背中にいっぱい、いっぱい振らせた。
【馬子唄-道行き】
かわいいわが子にゃ着せられないが
めんこい馬っ子のためならば
金襴緞子を着せましょう
しゃなりしゃんなり やれやれなんしょ
手だれの馬子でも通りゃあせぬが
めんこい馬っ子のともならば
険しい岨道通りましょう
しゃなりしゃんなり やれやれなんしょ
遠くのあの娘に聴かせたい
めんこい馬っ子の神の鈴
峰の代掻き馬にまで はるかに響けよ 神の鈴
しゃなりしゃんなり やれやれなんしょ
・叙事詩ほのほつみ の物語のあらましは、こちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
