
【広告表現規制】広告担当者は"医療広告ガイドライン"を読んでほしい
【注意】筆者の樋爪康之(@yasuyuki_ad)は、法律にたずさわる職業経験がありません。あくまで広告代理店の一担当者が書いた記事である点をご了承頂ければ幸いです(気になる点等ありましたらご指摘頂ければと存じます)
■本記事の想定読者とは?
医療広告ガイドラインを紹介することで「病院」「クリニック」の広告規制の理解促進を目的としています。
特に近年話題となっている美容医療(ダイエット注射、発毛、アンチエイジング、リフトアップ)、歯科医療(インプラント、審美、矯正)の広告に携わる可能性のある広告担当者様に読んで頂ければ幸いです。
■医療広告の経験者はどのくらい?アンケート結果
Twitterでこのようなアンケートを取らせて頂きました。ご協力ありがとうございました。


以下は医療広告ガイドラインの引用になります。
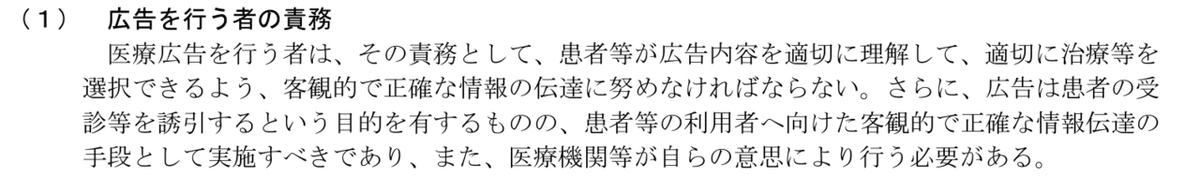
医療広告を行う者の責務として、患者が適切に治療を選択できるように努める必要があると明記されています。しっかりと責務を全うするように医療広告ガイドラインの中身を把握しておく必要はあるでしょう。
■実態としてどのような行政指導が行われているのか
医政局が実施する「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」のレポートをみると、具体的な取り組み内容の経過報告が公開されています。
厚生労働省委任事業「医療機関ネットパトロール」が機能しており、監視体制と是正に向けた改善指導の取り組みが相当数行われている印象を受けます。参考までに、平成30年度は通報受付件数8,358サイト、そのうち医療広告通報件数6,726サイトにも及んでいます。定期的に更新されるため、時間のある時に目を通すと面白いかもしれません。

■そもそもガイドラインと法令は何が違うのか
医療広告ガイドラインとは、日本の医療法等に基づいて医療広告が適正に行われるよう解釈、補完を目的とした技術的助言に該当します。
厚生労働省が作成した医療広告ガイドラインの役割は「医療広告を行う者が広告を行う際に自主的に遵守することが推奨される指針」として地方自治体の行政指導をサポートすることにあります。
医療広告ガイドラインは、医療法、景品表示法、薬機法、健康増進法、不正競争防止法などの法令に基づいて作成されています。ガイドライン自体に法的拘束力がなくても、悪質な場合は行政指導に留まらず罰則が課されます。以下参考資料のQ&Aによると広告代理店や、サイト運営会社も罰則対象に含まれると記載があります。
■医療広告ガイドラインをスムーズに理解する為に
「とはいっても法令は長くて読む気が起きないよ」という方向けに、医療広告ガイドラインを読む前に押さえておくべき5つのポイントを簡単に紹介します。以下、ガイドラインの目次と本記事で触れるポイントの対照表を作成しました。

【公開】厚生労働省
【通称】医療広告ガイドライン
【正式名称】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
【point⓵.規制目的】
医療行為は人の健康や命に関わります。医療機関で不適当なサービスを受けた際の被害が他の分野と比べて甚大です。そのため、患者や利用者を手厚く保護することが大切だと考えられています。近年、美容医療の相談が増加した背景から、これまでは明言されていなかった医療機関のウェブサイトまで明確に是正命令や罰則等の対象とする経緯が記されています。
【point②.規制業種】
「病院」「クリニック(診療所、医院)」の全てが対象です。
特に近年被害が増加している美容医療(ダイエット注射、発毛、アンチエイジング、リフトアップ)も含まれます。歯科医療(インプラント、審美、矯正)が含まれます。
【point③.規制対象】
「誘因性」「特定性」の性質が認められるもの。具体例は以下の通り。
「ウェブサイト」「インターネット上の広告」「ブログ」「メルマガ」「チラシ」「パンフレット」「ダイレクトメール」「ポスター」「看板」「新聞※」「雑誌※」「記事風広告※」
※利益を期待して費用負担して誘因するものは原則規制対象です
【point④.規制対象外】
「誘引性」「特定性」が認められないもの。具体例は以下の通り。
「学術論文・学術発表」「院内掲示」「院内配布パンフレット」「新聞・雑誌等での記事※」
※費用負担していないものは原則規制対象外です
【point⑤.禁止表現】
代表的な禁止表現 を6パターンに分類しました。
(すべて網羅しているわけではない点をご留意ください)
■5-1.虚偽広告
■5-2.比較優良広告
■5-3.誇大広告
■5-4.患者の体験談
■5-5.患者等を誤認させる治療前、後の写真
■5-6.費用を強調した広告
■禁止表現の具体例について
【point⑤.禁止表現】で紹介した6パターンの事例を見てみましょう。
■5-1.虚偽広告
患者等に事実に相違する情報、誇張した表現によって誤認を与える表現は禁止されています。
例「絶対安全な手術です!」
例 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
例「 厚生労働省の認可した○○専門医」
例「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
■5-2.比較優良広告
他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告は禁止されています。
例「肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。」
例「当院は県内一の医師数を誇ります。」
例「芸能プロダクションと提携しています」
例「著名人も○○医師を推薦しています」
例「著名人も当院で治療を受けております。」
■5-3.誇大広告
事実を不当に誇張して表現することで人を誤認させる広告は禁止されています。
例「比較的安全な手術です。」
例「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
例 「知事の許可を取得した病院です!」
例「手術や処置等の効果又は有効性を強調するもの 」
例「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります。」
■5-4.患者の体験談
患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、誘引を目的として紹介する広告は禁止されています。(補足として広告とみなされない例として、個人のウェブサイト、個人のSNS、個人の口コミサイトの投稿が挙げられます。広告か、広告ではないか、の一つの目安として、広告費用の負担が挙げられます。)
■5-5.患者等を誤認させる治療前、後の写真
誤認させるおそれがあるビフォーアフター写真等を利用することは禁止されています。
例「 術前又は術後の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの」
■5-6.費用を強調した広告
医療広告として適切ではなく品位を損ねる内容の広告は禁止されています。
例「今なら○円でキャンペーン実施中!」
例「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」
例「○○%オフ。100,000円→50,000円」
例「○○治療し放題プラン」
■おわりに 医療広告ガイドラインを読んでほしい
例えば、ビフォーアフター写真はいかなる場合でもNGとまでは書かれていません。なぜビフォーアフター写真がNGなのか?ガイドラインをよく読んでみると、例外的に許可される記載方法関しても以下のように言及されています。
「また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらない。」
今回紹介しきれなかった付随する条件なども数多くあります。一律NGというほど単純明快なものではありません。やはり、しっかりと医療広告ガイドラインに目を通す重要性は高いでしょう。
本記事がきっかけで、医療広告担当者が医療広告ガイドラインに目を通す後押しになること、更には自身に広告倫理の土台を作るきっかけとなれたら幸いです。医療広告ガイドラインのリンクはこちら。
また以下URLは厚生労働省のHPです。こちらを定期的に確認すると良いでしょう。医療法に関連した広告をとりまく法規制の最新の動きを把握することが可能です。
■Tips広告媒体社ごとに審査の厳しさが異なる理由
医療法や、医療広告ガイドラインなどを満たしていれば、どのような広告表現を行ってもよいのでしょうか?
医療広告ガイドラインの目的を踏まえて、より安全に余裕を持って審査基準を設定している、いわゆる自主規制を設ける広告媒体があります。それがYahoo!広告です。「Yahoo! JAPAN広告掲載基準」として審査基準を公開しながら広告主と共に法令を遵守する姿勢を示しています。
法令上、厳密にNGではないケースであっても、ユーザーを保護する目的にそぐわない広告表現であると判断された場合は、Yahoo!審査部門の自主規制により非承認となるケースもありえます。広告媒体の中でもYahoo!は審査が厳しいと言われているのはこのような背景があるからです。
広告媒体各社、完全に足並みが揃っているわけではありません。そのため「A社では審査に通るのに、B社では審査に通らない」ことが珍しくありません。広告媒体の審査結果に一喜一憂していると、本来のガイドラインや医療法により定められたルールに対して、誤解が生まれてしまう、媒体審査の特徴を理解する前に、しっかりと原則を理解しておきたいですね。

■参考文献
■シリーズ記事紹介(広告担当者向け)
「病院」「クリニック」等の広告担当者の方に
「医薬品」「化粧品」「健康食品」等の広告担当者の方に
あらゆる商品やサービスの広告担当者の方に
「健康食品」等の広告担当者の方に


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
