
「となりがイスラム」だったころ 「となりのイスラム」を読んで
「積読」になっていた内藤正典さんの「となりのイスラム」を読んだ。
帯の「たぶんこれまででもっともわかりやすく、実践的で、役に立つイスラムの入門書だと思う」という、控えめなのか、ノリノリなのか判然としない文句に、偽りはない。拙著「おカネの教室」と同じ編集者アライさんが担当しているという贔屓目を抜きにして、日本のメディアでなかなか描かれない視点からイスラム教とのお付き合いのあり様が平易に書かれている。特にムスリム(イスラム教信者)と西欧人(および日本人)の内的論理の違いを、繰り返し、明確に述べているのが良い。万人にオススメできる良書です。
あえて言えば、後半のカリフ制復活が必要という見立てを理解するのは、ハードルが高いかもしれない。いかにこの100年の欧米の中東政策および中東諸国のガバナンスがクソかという予備知識がないと、腹に落ちないだろう。
「それぐらいドラスティックな手を取らないと、国民国家システムとイスラムは和解できない」という冷徹な分析には、個人的には同意する。
ただ、現実には、エルドアンのトルコやムスリム同胞団が政権を握ったときのエジプトの例のように、暴力装置を独占する国民国家システムと宗教・思想(イスラムに限らない)が結託すると、急進的・抑圧的・強権的な監獄国家が出来上がってしまうリスクが高そうな気がするが。
詳細は本書に譲るとして、「となりのイスラム」という書名は秀逸だ。世界の3人に1人がイスラム教徒になる時代が待っているのだから、日本人にとっても無縁の人々ではないですよ、というニュアンスがうまく出ている。
現実には、日本に住んでいる限り、隣人がムスリム、となる確率はとても低い。
そう、日本に住んでいる限りは。
実は、私は、「となりがイスラム」という状態で、2年暮らしたことがある。しかも「両隣がイスラム」だった。2016年から2年駐在したロンドンでのことだ。近所の女子校は、おそらく生徒の半分以上がムスリムで、髪や顔を覆うブルカやヒジャブを身に着けた女の子たちがゾロゾロ歩いていた。小学生の三女の送り迎えでも、ヒジャブ姿のお母さんたちがたくさんいた。
人間というのは何にでもあっという間に慣れるもので、初めは「あ、イスラームな人だ」と目が行ったヒジャブ姿も、ほんの数週間で何とも思わなくなる。シーク教徒のターバン(タイガー・ジェット・シンみたいなやつね)も然り。東京の地下鉄で和服姿を見るのより驚かない。
どれくらい「日常」にイスラームな人々が溶け込んでいたかと言うと、帰国してしばらくは、娘たちは「日本はヒジャブの人がほとんどいなくて変な感じ!」とよく漏らしていたものだった。
良いお隣さん
「おとなりがイスラム」な日々で、とりとめもなく思い出すのは、こんなことだ。
両隣さんとは別にこれと言った交流はなかったが、とても感じの良い人たちだった。
イギリスのAmazonは、不在だとお隣に荷物を預けるという技をフツーに使う。帰ると不在票がドアに挟まってて、「お前の荷物は隣の112番地の人に預けたよ」と書いてある。日本では考えられないブン投げだ。
そうすると、ピンポーン、ともらいに行くことになる。お互い様で、こちらが預かることもあった。
たったそれだけの荷物のやり取りだけど、お隣のムスリムさんは、とても感じが良く、面倒くさそうにしたり、ぞんざいだったりと言ったことは皆無で、非常に気持ち良い付き合いができた。
私がロンドンにいた頃はラマダンが夏に当たっていた。これはムスリムにはキツい。イギリスの夏は9時過ぎまで日が暮れないのに、日の出から日没まで断食しなきゃいけないからだ。厳格な人は、水が飲めないどころか、唾も飲み込めない。
だから、夜になると、解放感のあるお食事の時間がはじまる。お隣からも、ご家族が庭で食事する声が聞こえてきたものだ。でも、ラマダン明けのお祝いでさえ控えめで、近所迷惑ということは全くなかった。
三女の送り迎えで思い出すのは、「ヒジャブハンズフリー」お母さん。タイトに巻いたスカーフと耳の間にスマホを突っ込んで固定し、通話しながら空いた両手で子供2人と手をつないで歩いている。ヒジャブ、便利やんけ!と感心した。
大西洋を越えるインスタ一目惚れ婚
娘の友達にも「ヒジャブっ子」はたくさんいた。特に印象に残っているのは、長女のアルジェリア人の友達、タコアちゃんだ。この子はかなりの美人さんで、趣味は美容。ものすごくメイクが上手い。
詳しくはないのだが、中東・アフリカ系の一部の人たちのお化粧は、独特の質感がある。毛穴が完全に消えるような厚塗り(と思われる)なのだが、濃いめの肌にそれが映えて、彫刻のような光沢がとても美しい。あまりジロジロ見るのは失礼なのだが、地下鉄で近くにいると、思わず目を凝らして毛穴を探したくなる(笑)
タコアちゃんもその系統で、一度、長女も同じテクニックでお化粧してもらったら、妖怪人間ベムのベラのような顔つきになって、爆笑してしまった。
タコアちゃんは、髪の色もしょっちゅう変える。ヒジャブで隠している髪の毛を、だ。自分が楽しいのはもちろんだろうが、旦那さんも見てくれるからオシャレするのだと思う。
そう、タコアちゃんは20歳ちょい過ぎで既婚者だった。それを聞いて、私は先入観から「親同士が決めた小さい頃からの婚約者とかかね、相手は」と長女に聞いた。
これが、全くの見当違い。
実際は、イギリスに住んでるタコアちゃんがインスタにバッチメイクの自撮りをアップしまくってたら、そのころアメリカに住んでた旦那さんが一目惚れして、SNSでお友達になり、最終的にはタコアちゃんを追って旦那さんが渡英してきた、という。
この話を聞いたときは、「ムスリムもフツーの若者やん」というありがちな多文化主義的な感想を突き抜けて、「今どきの若者は理解不能だ!」と驚いた。
「イスラム国家としてのイギリス」
身近にムスリムがいて、一方で、そう頻繁ではないが、欧州ではイスラム過激派によるテロがちょいちょい起きる。自然と「欧州でムスリムとして生きる」とはどんな人生なのか、興味がわく。
そんなときにロンドン中心街の書店で偶然出会ったのが「AL-BRITANNIA, MY COUNTRY」だった。タイトルは、無理に訳せば「アラビア的わが祖国イギリス」とでもなるのだろうか。非ムスリムのイギリス人ジャーナリストが、自国内のムスリムコニュニティーを丹念に回ったルポで、最後には著者のラマダン体験記まで入っている。タイトルと装丁、写真の充実度がツボにはまり、「ジャケ買い」した。
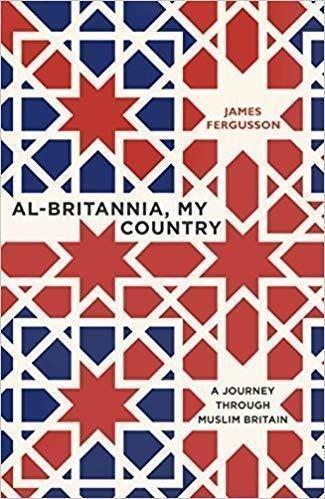
私の「ジャケ買い」の打率は高く、これも「当たり」だった。邦訳されることはないだろうから詳しく中身を紹介したいところではあるが、再読するのはしんどいので割愛する。
要は、「ムスリムはもうイギリス社会の一部だし、一部の過激派だけに目を向けて排外主義に陥るのは愚の骨頂だ」という主張が一貫して流れている。足で稼いだファクトを積み上げているので、とても説得力がある。
ムスリムは、いろいろな要因から、出生率が高い。イギリスはEUからの離脱、いわゆるBREXITという愚かな選択をしたが、国境を閉ざしても、すでに「内側」にいるムスリムだけでも、これから社会の在り様を変えていく勢力になるのは確実だ。「共生」以外の選択肢はなく、これは「となりのイスラム」でも繰り返し説かれている論点だ。
溝は深いようで、深くない
「コーラン」という神の言葉を絶対視するムスリムと、啓蒙主義を経て科学的合理思考と宗教の分離を曲がりなりにも成し遂げた西欧人(とそれを模倣した日本人)の間には、確かに溝がある。
でも、イギリスにいる間に私が接したムスリムに関する知見は、「そんな溝は、実はたいしたことじゃない」とも思わせてくれた。
一例は、イギリスでは今なお大きな社会問題として尾を引く、グレンフェルタワーの火災だ。
わずか数百メートル先には「超」が付く高級住宅街があるこの高層アパートは、貧困層がスシ詰めで暮らす、有り体に言えばスラムのような場所だ。杜撰な改装工事が原因でビル全体が想定外のスピードで大炎上し、多数の死者が出た。このニュース自体は日本でも割と大きく扱われたので、覚えている人もいるかもしれない。
日本ではほとんど報じられなかったのは、この火災の犠牲者を大きく減らしたのが、ムスリムの若者たちだったという事実だ。
火災があったのはラマダンの時期の夜で、火災発生時はちょうど、モスクで礼拝を終えたムスリムたちが帰宅する時分だった。この時、グレンフェルタワーに住む若者たちは、火の手が回り始めた危険な状況を顧みず、すでに眠りについていた非ムスリムの家庭のドアやベルを乱打して回り、避難を呼びかけた。このおかげで助かった住人は少なくなかった。
もう一つ、忘れられないのが、ムスリムを狙ったテロに対するある聖職者の行動だ。
これもラマダンの時期のことだった。イスラム排斥主義者が、夜の礼拝を終えたムスリムの人波に車で突っ込み、死者も出た。犯行後、逃走しようとした犯人は、その場にいた信者たちにつかまり、怒りに燃えるムスリムたちによるリンチが始まりそうな気配だった。報道によると、犯人の男は、この間も「イギリスにイスラム教徒の居場所はない」といったヘイトスピーチを続けていたという。
一触即発のそんな現場に、モスクに勤める一人の聖職者が割って入った。
「手を出してはいけない。この男は司直の手に渡して、法の裁きを受けなければいけない」
その聖職者はこう言って民衆をなだめ、警察が到着するまで秩序を守ったという。
自らの信仰は守りつつ、その土地ごとの秩序を尊重し、無用な争いごとを避け、社会と調和する。「となりのイスラム」でも繰り返し述べられてるイスラム教の本来もつ柔軟性と強靭さを、まだ二十代というその聖職者は体現していた。
こんな乏しい体験から、安易に「だからイスラムと我々は共生できる」という結論を誰かに強いるつもりはない。
でも、私の実感は、こうだ。
「他者に共感できる人間力の有無は、ムスリムか、非ムスリムかという軸とは別物としてある」
そして、個人主義や自己責任論に偏りがちな西欧の価値観は、共感力という点で、イスラムより「劣るとも勝らない」。
海外に出れば、ムスリムと接触する機会は増える。日本国内でも、もうしばらくすれば、インドネシアやマレーシアから来るムスリムが「おとなり」になることは増えるかもしれない。
でも、大丈夫。
彼らは、我々と同じ、ただの人間だ。
悪い人も、良い人も、変な人も、普通の人も、おそらく我々日本人と同じくらいの割合で混じっている。
日本人は「外人」が苦手だけど、「イスラム教徒だから」と二重の偏見が生まれるようなことは、絶対避けるべきだし、意味もない。
「となりのイスラム」は、そんな当たり前のことを、とても丁寧に解説してくれている。
−−−−−−−−−−
ツイッターもやってます。アカウントはこちら。@hiro_takai
異色の経済青春小説「おカネの教室」もよろしくお願いします。
いいなと思ったら応援しよう!

