
メディアでメッセージを打ち出す「こわさ」をどう克服したか。
2019年、2020年あたりはアクセラや投資家などに接触するたびに、「競合がいない=マーケットが存在しない」ということだと言われ続け、官民共創の領域のビジネスを理解してくれる人が本当にいなかった。一番モヤモヤしていた時期だ。その1年後に新型コロナが猛威をふるい、時を経て振り返ってみると、新型コロナが時計の針を進めたと感じる。当時はそんなことは知るよしもなかったけれど。というわけで、僕が官民共創への社会的な理解が得られずにもがいていたころの話をもう少し続けよう。
2018年夏、日経BPと何を議論していたか
「官民共創のマーケットなんて存在しない」とほぼ同義と言ってもいい、フィードバックを各方面からもらっていたころ、一冊の本を送り出した。それが日経BPから出版された「日本の未来2019-2028 都市再生/地方創生編」だ。
33万円もする高額書籍で、店頭で並ぶような本ではない。企業の経営企画や大学などの研究機関、民間シンクタンクなどを狙った本。僕はこの書籍の総合監修および執筆を行なった。
執筆の分量は全体の7割ほど。全300ページに及ぶ、この書籍は弁護士、教授、起業家など各分野の専門家の協力を得て作り上げたもので、僕としても力作だった。
で、この本が2019年春に出版されていることは、企画そのものはもっと前に始まっているわけで。
それが2018年夏。僕がmillion dotsを創業して半年が経ったころだ。この頃は、会社の売上も順調に伸びていて、少ない月でも150万くらいの売上があって、精神的にも落ち着いていた。
会社立ち上げて、ゼロから始めて半年後に、この数字だったので、「あぁ、このまま個人としてはこれから先も生きていけそうだな」という安心感が芽生えていた頃だ。

地方創生ビジネスだったら異なるメッセージになっていたかも
そんな時にかつて日経エレクトロニクスの編集部でご一緒していた先輩から、一つの企画の提案があった。
当時のメールを振り返ると、最初に連絡があったのは2018年5月のことだ。神谷町にある日経BPにお邪魔した。
当初の議論はまだ、茫漠としていて「地方創生ビジネスの未来」、そんなタイトルで書籍を出せないか、という議論からスタートしている。
同年8月下旬には早稲田大学の北川正恭先生(元三重県知事)に総合監修でご一緒頂けないか、企画書を送っているので、5月からの3ヶ月で企画を練り上げたことになる。
当初は「地方創生ビジネスの未来」で検討が始まった書籍企画が「日本の未来 都市再生/地方創生編」に変わった経緯としては、政府が発表している数字、僕が市議時代に見聞していたこと、それらを総合的に分析すると、大きな地殻変動が起きていると感じたからだ。
それで「地方創生ビジネス」という表現にして矮小化してしまうのではなく、「日本の未来」とちょっと大仰なタイトルになった。

書籍という形に残る「こわさ」
ただ、その際に葛藤したことがある。
それはこの書籍で打ち出すメッセージについて、だ。数字からも、政府の発表資料からも、そして僕自身の肌感覚からも、「自治体がすべての公共サービスをフルパッケージで提供する時代は終わった」のは明らかだった。
しかし、それを明言するのには勇気がある。特に書籍は後々まで形に残るがゆえに、記者を経験した者としては人一倍、こわさがあった。
「本当にそうなのか?」
「そんなこと、はっきり言い切って大丈夫なのか?」
という内なる声と葛藤した。しかも出版元は日経BPだ。
自分がそこの出版社出身だからいうわけではないが、しかし、日本におけるビジネス書籍、雑誌の分野では業界トップであることは間違いない。
変な著者の、変な主張を出版するわけにはいかないし、そんな書籍を出してしまって、会社の評判を傷つけてもいけない。そんな悩みもあった。
この数ヶ月の議論で導き出した、「フルパッケージの時代が終わる」というメッセージは本当に正しいのだろうか。
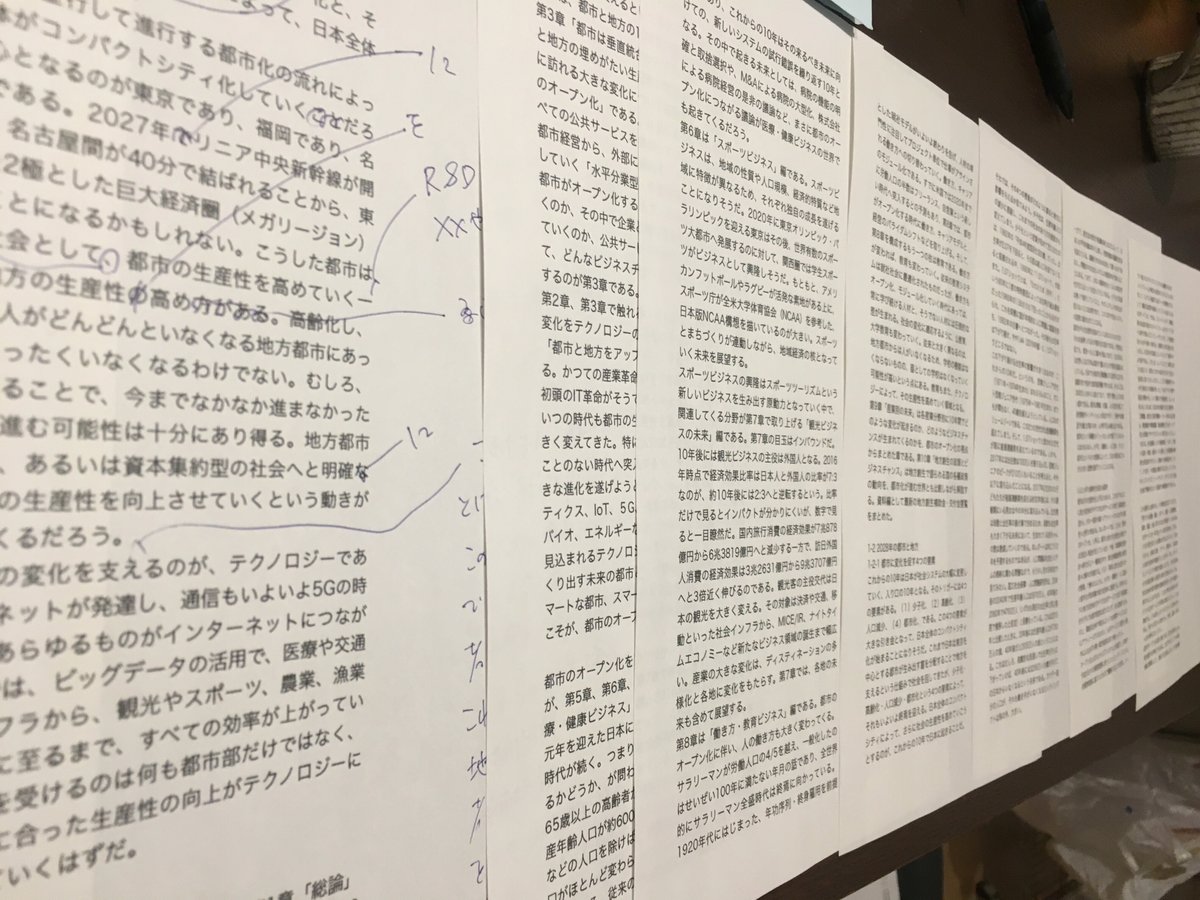
早いと感じるくらいがいいタイミングという意外
そんな悩みを書籍担当の仲森さんと高橋さんに伝えた時の言葉が今でも忘れられない。
「伊藤さんが、ちょっと早いと思うくらいのタイミングこそ、メディアとしては出すべきタイミングだ」。
僕が社会人駆け出しのころに、ヒット記事を次々と飛ばしていた先輩が、そう言ってくれるのであれば、このメッセージで本を書いてもいいのかも、と思えた瞬間だった。背中を押してくれたのと思う。
公民連携という領域は、2000年代初頭、横浜市は明らかにトップランナーだった。そして、先頭を走るからこそ、行政内部も議会も、市民もメディアも、なかなか理解されず、当時、このセクションにいた職員は苦労していた。
僕も最初は理解できずに激しい議論をふっかけた側にいた。
ただ、議論を重ねていくうちに、見えてきた景色と共有できた問題意識があって、僕自身はいつしか、この分野で数少ない応援者になっていった。
当時、横浜市の市長は中田さんで、元々僕の選挙区の国会議員とは政敵でもあった。だから、議会の中で僕は中田さんと対立する市議というレッテルも貼られていたが、こと、公民連携については、議会の中では僕は数少ない賛成派で、不思議に思っていた人も少なくなっただろう。

メディアの慧眼、そしてベストタイミングだった
ま、それはさておき。
その公民連携の黎明期の混沌とする様をつぶさに見ていた、かつ観察するだけでなくその渦中に身を投じていたからこそ、「行政がフルパッケージで公共サービスを提供するのは難しい」というのは実感でもあった。
この感覚を持ち得たのは、あの時代、あの横浜で、議員をしていたから。そして、知りすぎているからこそ、その真実を出版という形でメッセージを出すことが、僕はこわかったのだ。
改めてメディアの力はすごいなと思う。
あの時、紛れもなく、「ちょっと早いと思うくらいで出すのがいい」という後押しがなかったら、日本の未来は出版していなかった。
この企画の議論が2018年夏。
そして出版が2019年春。
2019年春でもまだ、「官民共創はビジネスにならない」と投資家やアクセラなどに言われていたことを思うと、この本の出版の決断が、いかに早かったか、日経BPの慧眼というより他はないだろう。
今ではそこかしこで、行政ですら、「すべての公共サービスを維持するのは難しい」と言うような、あるいは言える時代になった。

新型コロナが時計の針を進めた
時計の針を2019年に戻そう。
この時点ではまだ、官民共創に関わるビジネスの未来像は、社会的には全然見えてなかった。
では、そんな官民共創が今日の状態にいたったのは、なぜだろうか?それは結果論でしかないが、新型コロナだった。
正確に言えば、小さな、小さな種はそこかしかに蒔かれていたし、その芽は出ていた。社会の大きな経済活動から見れば、目にも止まらないほどの小さな規模で。
でも、そんな小さな芽が大きく成長していったのは、まぎれもなく、新型コロナだっただろう。
あの時期は僕も人生の中で最も苦しい時期だった。もう2度と戻りたくない。
一方で、社会としても未来が見通せない、絶望の中にあって、新しい萌芽が生まれていたのも事実で、それがどのように今日につながっているのか、それはまた、改めて。

この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
