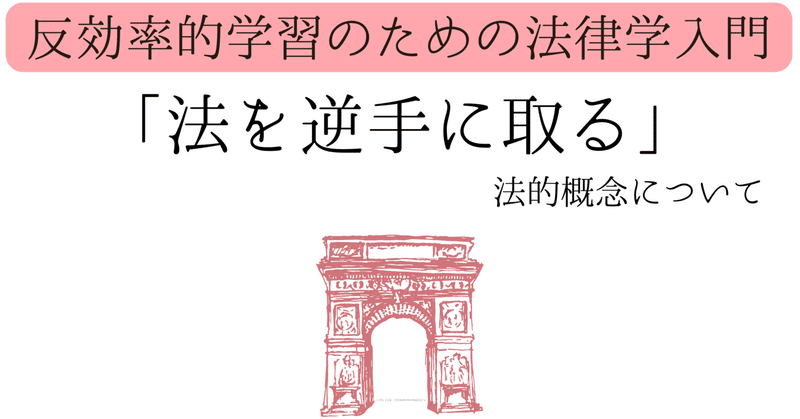
反効率的学習のための法律学入門 「法を逆手に取る」 法的概念について③ #6
1 はじめに
前回に引き続き今回もすこし抽象的ですが、法律学、とりわけ実務を踏まえた法の実態を学ぶうえではクリティカルな部分に位置します。
*前回の記事
以前、下記の図を示しました。

この図が示しているのは次のことでした。
物語「大学生Aの憂鬱」や物語「農家Xにおける費用果実連関」で例示されるように、個人の自由は危機に瀕する。このような事態は、「人間社会の所与(各個人間の諸力の差、人の心の闇,集団形成力,時間・資源・エネルギーの希少性と余剰性・過剰性及びこれらの偏在,信用供与の不可欠性,病気や災害などの非人為的リスク等)」が生み出すものであり、現実世界は、不定形主体間の不定性・不定量な互酬関係になろうする力学がどうしようもなく働く。つまり、社会の例外事象ではなく、通常運転の常態事象です。そこで、これに対処するのが法でした。つまり、かかる互酬関係を、「個人の自由」を基底理念として、二当事者間の定性的かつ定量的な権利・義務関係に編成するということです。そのために、転々流動してやまない現実を「法的概念」という法の世界の語彙で捉え直し、抽象的な法の世界に移転し、法ルールを駆動させていくことで現実世界を動かしていく。これにより、互酬性のカオスを権利・義務のコスモス化された新しい現実へと作り直す、そのことにより個人の自由を守る。
では、これで安心でしょうか。
2 法を逆手に取る-優位者の戦略
(1)法の盾を乗り越えようとする優位者
「現代には法律が整備され、社会生活は権利・義務関係で整序されているのだから何も心配いらない」、とはならないのが現実です。上記のとおり、そもそも互酬性のカオスを生み出したのは、「人間社会の所与」です。これは、根絶することも消滅させることもできません。人間存在そのものが生み出す問題群だからです。この巨大で奥深い「人間社会の所与」が生み出す力は、屹立する法の前に恐れをなして委縮するようなヤワなものではありません。むしろ、より一層巧妙に法の盾を攻略しようとしてきます。ここに、歴史性ある法律学展開の一つの理由もあるはずです。
では、一体、どうやって攻略しようとしてくるのでしょうか。
互酬関係において個人を圧迫するのは、集団など「優位な状況にある者」です。優位者は、劣位者に対し、力(経済力、集団力、情報力、心理的圧迫力などの諸力)を使うことができる。そうした優位者にとっては、曖昧不透明な互酬関係の方が好ましい。気ままに振舞うことができ、相手に防御されることなく、自己の意思を貫徹できるからです。それゆえ法の盾は、優位者にとっては障害物に他ならない。上記の優位性が毀損されかねないのです。しかし、法のない世界に逆転させることまでは不可能である以上、法が存在する状態を前提にせざるを得ない。そこで、優位者は、法の盾を攻略するために、法を逆手にとることにします。手段は大きく3つあります。
(2)法を逆手に取る「①法を使って優位者のための部分カオスを作る」
法においては、権利・義務関係を設定することが要求されます。優位者は、例えば契約において、カオスを潜ませます。契約主体を複数関与させて曖昧性を作ったり、契約条項の中に曖昧な規定を作るのです。「条項が曖昧だから双方にとって曖昧であり、不十分といえる条項だけれども一方だけに不利にはならないのではないか」と観念的思考に陥ったら優位者の思うツボです。当該契約の性質上、その曖昧さは一方当事者に不利に働くようになっています。
法治である以上、現代において法を全面的に排除したり、権利・義務に形式化していくことを避けることはできません。そうであれば、むしろ法を使って一部にカオスを生じさせればよい。そこを突破口に優位者が劣位者の自由を奪っていくことができるからです。複数の契約主体が関与する契約(不定形主体の部分形成)、不明瞭な契約条項(不定性・不定量の部分形成)に起因して、大いに民事紛争が発生していきます。
(3)法を逆手に取る「②法の形式で劣位者を縛り上げる」
当事者間を法で規律すれば、そこには定性的かつ定量的な権利・義務の関係が支配するのであるから、明解かつ透明な関係が樹立されるように思えます。しかし、形成された関係が、一方当事者へ何重もの義務を課して、意思と行動を制限する法律関係として「明解かつ透明」であることもあるのです。定性的かつ定量的に、個人を縛り上げるわけです。
消費者トラブルに見られる一度契約したら抜けられない、解約できないという系統の問題や、フランチャイズ紛争に見られる諸問題で表面化したりします。
(4)法を逆手に取る「③法自体を優位者有利に改変する」
優位者には力がある。優位者の連合体がその力を法制定の過程に及ぼし、法律自体を自己に有利に改変するという方法があります。あまりにオーソドックス過ぎて実例の枚挙に暇がないことは、皆さまご存じのとおりです。
ただ、法的概念の体系は、法律学の歴史を踏まえて営々と形成されてきたもので、完全な閉鎖系ではもちろんありませんが、自律性ある世界を形作っています。それゆえ、いかに優位者の連合体が法律を変え、法的概念さえ変容させようと挑戦してきても、また、一見それが成功したかに見えても、法的概念体系のコアは変えられない、変えたと思っても実は変えられてはいない、という視点が重要であると思います。
以上、法を逆手にとる優位者の戦略を簡易に図解すれば、次のようになるでしょう。

3 おわりに
以上のように、優位者は法を逆手にとる。劣位者はまたしても、その自由を失う危機にある。
法解釈を学び、判例を学ぶ際は、上記のような優位者の戦略の諸相を見抜くという態度でいなければ、結局、平板な「利益調整のための紛争解決」図式に取り込まれてしまうでしょう。取り込まれるとは、その視点からでしか事象を見ることができなくなるということです。
他方で、当該具体的な事象における優位者の戦略の諸相を見抜ければ、むしろ本来の法を発揮させ、「逆手を取ろうとする相手を逆手に取る」という転回の可能性が開けてきます。法律家の目がここに試されます。
*以下の記事につづく
【参考リンク】
(独)国民生活センター 身近な消費者トラブルQ&A
中小企業庁 「フランチャイズ事業を始めるにあたって」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
