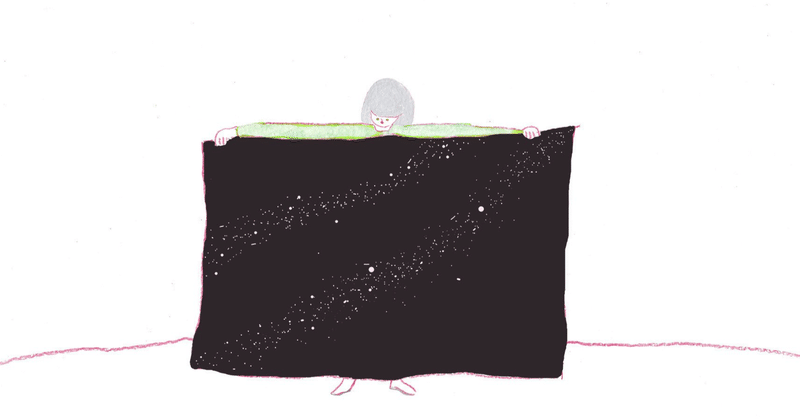
自分の「テーマ」を手にいれる
テーマを変えた方がいいと言われてしまった
作品を発表したところ、「文章はほとんど直すところがない。でもテーマは変えた方がいい。あるいはテーマを押し付け過ぎだ」と評価を受けた。テーマは振りかざさず、読了後にじんわりと感じられる程度におさえ、読者が安心して、物語の世界に没入できるのが、小説の目指すところだということだ。
実力だけで見れば何年かで作家になれる(かもしれない)けど、私が選んだテーマでは、ものにするのに10年かかるか、あるいは何年費やしたところで、認められないかもしれない……と解釈できる。
純文学かエンターテイメントか、の葛藤にも通じてくるかもしれない。
評価の前提に、商業で通用するかどうかがある
商業的な作品とはなにか。人によって意見はさまざまで、定義する意味があるかどうかもわからないが、わたしは「ポストモダン的な価値観」も含まれると感じている。なんとなくそうかな、くらいの感覚でしかないけれど。
いっぽう、私の作品は多様性を全肯定するものではない。モノカルチャー的だし思想文学に近いかもしれない。それしか書きたくない、と言い切ることはできないけど、限られた人生の時間の中で、できるだけエネルギーを費やしたいと思っている。
私が持っているテーマは、大量に刷られても、飛ぶように捌ける商品になりうるか? そうではないと、今まさにわかった、ということだ。
その上で……まずはいい面を見よう。
①テーマが伝わった
なんせ言いたかったことは伝わった。評価者は、テーマを感じ取ったうえで、同意できなかっただけかもしれない。あるいは「テーマの感じ方・読後感」の好みによるところかもしれない。
②自分はテーマを持っている
たいていの人はテーマに悩んだりブレたりする。その心配は私にはない。
③はやばやとテーマの人気度が判明した
「私にはこのテーマしかない。面白いと思うのに、なんで伝わらないんだァァァっっっ!?」と世を恨み、何年も執着するよりも、ばっさり「このテーマは難しい」とわかってよかった。
腹に一物抱えたまま活動し続けるより、誠意を持って勝負を仕掛けたから、一足早く結果が出た。戦うポイントが切り替えられるというものだ。議論の俎上に載せられるだけの作品を出せた、そこにまず価値があるはずだ。
テーマを変えられるか?
私には次の選択肢がある。
テーマを完全に捨てる・変える
テーマを一旦捨て、実力とニーズがかち合うところを目指す
さらに研鑽を積んでテーマ性を深め、表現力を高めつつ、マーケットを模索する
テーマを初心者にもわかりやすく平易にできるまで、さらに研鑽を積む(池上彰方式)
テーマを捨てられるかどうかの判断
1.テーマを完全に捨てる・変える
テーマを完全に変えられるかは、テーマへの確信とか覚悟とか、テーマを見つけるまでにした苦労で変わると思う。
「作品を作るためにテーマを設定する」のと、「テーマを表現したくて作品を作る」では、テーマに対しての思い入れは違ってくる。
とりあえずうけ狙いをするのは、読者に対して誠実だろうか?
2.テーマを一旦捨て、実力とニーズがかち合うところを目指す
いったんデビューして認められてから、書きたいもの書けばいいじゃん、という意見がある。まっとうな意見に思える。ただ物事はそう単純じゃない。
第一に、器用さがあるならばそうすればいい。しかし器用に生きられないから、物語の世界を作り上げている場合もある。
第二に、自分にとっての2番手のテーマで売れ続けるとは限らない。のちのちテーマを切り替えられるところまで作家生命が続く保証はない。何を書いてもついてきてくれる熱烈なファンがどれだけつくかはわからない。熱烈なファンがついたとして、そのとき、本当に方向転換できるんだろうか。
考えられるのは、デビューした直後から、担当編集なりに「ゆくゆくはこういう方向性の作家になっていきたい」と話しておくことか。そうすればうまいこと導いてもらえるんだろうか? あくまで全て仮定の話だ。
そもそも、私が物語を作る意味はなんだっただろうか
大きくは以下に3つある。
「自分の物語」と思える作品が少ない
自分の居場所がないから作りたい
自分にできることで人を楽しませたい
これらを叶えるにあたって、物語を作るしか自分にできることがないから、小説を書いている。紙とインクとイマジネーションで生計を立てたい、というのは主要な動機に含まれない。
いまのところは、まだテーマを追いかけていたい。当面は「3と4」の道を進もうと思う。生計は別のところで立てる。私の道は決まった。
自分の道を進む根拠
まがりなりにアラフォーなので、周りに忖度した結果どうなるかを、ある程度はわかっている。
「合わせてやった結果がこれかよ」というのが、私の社会生活の総括だ。
成功法則まで大袈裟ではないけれど、世の中には「こうすればフォロワー10000人」とか「〇〇になれる」とか「人から好かれる」とかいうメソッドであふれている。メソッドでうまくいく人も一定数いる。そういう方々はそのままいけばいい。
問題は、メソッドでかえって物事を複雑にする人もいる、ということだ。狙いを定めるほど的が外れていくタイプが、この世には確かにいる。あくまでも優しさから周りに合わせているのに、どんどん歪になっていくのだ。これでは、自分もまわりも不幸になってしまう。
アドバイスはありがたい。ある意味素直には受け止める。しかし忠告についての解釈は自由に考える。瑣末なことは喜んで改善するけれど、中心は変えてなるものか。
自分が不幸になった結果、周りさえ幸せにできないなら、せめて自分の幸せは確保した上で、周りもほのかに温まる程度、そういうものを目指している。
出版がマーケティングだというのなら
私に戦略がないわけではない。一流のマーケターにはなれなかったけれど、勉強はした。
楠木建氏の『ストーリーとしての競争戦略』において、「スターバックスなどのヒットしたブランドは、ライバルにとって非合理と思われる要素を戦略の肝に据える」とあった。いわゆる「クリティカル・コア」だ。
「そのテーマは難しい」と言われたことから、手応えを感じてもいる。私のテーマは「クリティカル・コア」だと思っている。考えもなしに奇を衒ったのではない。となるともはや問題は、戦略を支えるだけの胆力とか持久力があるかないかだ。
加えて、まだ自分のテーマを扱いきれている気もしていない。今後は以下のように活動していこうと思っている。
テーマは変えない。書きたいことが尽きるまで書き、勉強する。
公募にこだわらない。(商業デビューにこだわらない)
発表はWeb上、自分なりに作品の編集や見せ方の試行錯誤をする。ワードプレスで世界観を演出してもいいかもしれない。
ターゲットを明確にし、そこに向かって丁寧な情報提供をする。
生計は別で立てるが、制作中心の生活になるよう調整する。
10年だとさすがに長期的すぎるので、5年くらいを設定し、私財を投入し、やりたいことをやり尽くす期間にしようと思う。
何者でもないアラフォー女性が、作品を作り続けるための全努力をマガジンにまとめています。少しでも面白いと思っていただけたら、スキ&フォローを頂けますと嬉しいです。
▼導入記事
▼人気記事
▼文体について考え始めた記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
