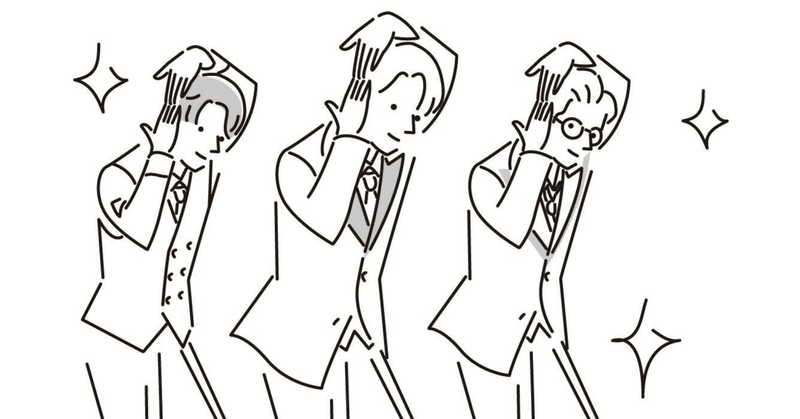
包丁×ダンス=高橋由伸
大学二年の春、私はダンスに明け暮れていた。だがそこにはキラキラした夢溢れる青春物語など全く持って無い。やらされていたからだ。
私が通っていた大学は所謂『芸術系』で、そこは音楽やら絵画やらを志望する若者たちが行きつく、ルール無用のディストピアである。
当時私は同期たちと学生劇団を立ち上げ、楽して名声を得ようとヤイヤイしていた。
ある日メンバーの一人が突然「一年間各々で力を溜めよう」と言い出した。どうせその週のジャンプの漫画が修行パートに突入したのだろうが、惰眠を貪りロクに冒険もしていない我々が力を溜めたところで、悪性の屁くらいしか出なかろう。
だが私の考えは他所に、屁溜まり劇団の面々の反応は良く、各々が能力を発揮できる環境で名を上げてくることが決まった。そこで私が向かった先はダンスサークルであった。
断っておくが、私はダンスが苦手である……というか正直嫌いまである。身体能力弱者として恥ずかしくも生き永らえてきた私のコンプレックスに四つ打ちの刺激を与えてくるからだ。
勿論イチTVっ子として人並みの憧れを抱いたこともあり、ブレイクダンスを鏡の前でやってみたこともあったが、映っていたのは玄関前の死にかけのセミだった。
そんな私は「せめて一人は勘弁してくれ」と拝みこみ、屁溜まりメンバーの茶沢に付いてきてもらった。ちなみにこの茶沢も私と同じセミ一族である。頼んでおいて何なのだが何故彼は付いてきたのだろう。
サークルの稽古は毎日4時間、休憩無しでみっちり踊り続けると言うものだった。「これでも他所より軽めだから」と同期の女がキラリと笑う。
私は丁寧にお辞儀を返し、“コイツぁてんでド素人だが悪い奴じゃないから強く当たるのは可哀そうだ”という雰囲気を演出した。
何故同い年の学生に下手に出なければならないのか、そもそもダンサーたちと仲良くなることがどう劇団の価値に繋がるのであろうか……、数々の疑問を胸に、二匹のセミは太陽のお膝元、ダンスサークルに飛び込んだ。
しかし、心とはうらはらに私たちはダンスに熱中していた。同期や後輩たちも皆、晴れ舞台に向け青春の一時をかけている。
フリが甘い!
もっと音楽を聴いて!
皆で合わせるんだよ!
もう少しだけ、頑張ってみよう!
……あの瞬間、確かに我々は『TEAM』だった。
倒れこむ私に駆け寄り、同期が「やれば出来るじゃん、ひこにゃん!」と爽やかな笑顔を向けてくれる。100人中98人が付けるであろうクソみたいなあだ名も、この時の私には『キムタク』と同じに思えた。私は汗をぴしゃりと払い、親指を立ててみせた。
二十二時。稽古が終わり各々が帰路に就く。「この後飲みに行こうか!」などと如何にも学生らしい提案をしてくれる同期たち。どうやら我々を“益虫”だと認識してくれたようだ。だがこの誘いは断らなければならなかった。残念そうな同期たちを尻目に私は着信履歴を見た……彼女である。
幸運にも当時の私には、お付き合いをさせて頂いていた女性が居た。男子高出身だったというのもあり、女性に対する知識が皆無だったため、彼女が当時の流行り言葉で言うところの『メンヘラ』であると言う事を知ったのはもう少し先の話である。
彼女は自分の中の“漠然とした不安感“を消化することが苦手で、私の返答次第で気分の矛先を変えたがる悪癖があった。「どこ行くの?」「誰と行くの?」「何で教えてくれないの?」は彼女の常套句であり、近頃は「何で私の嫌な事ばっかりするの?」がトレンドである。そしてその彼女の嫌な事が「ダンスサークル」になってしまったため、私は飲み会からの撤退を余儀なくされている。
日々を穏やかに過ごす方法はただ一つ『報告・連絡・相談』である。私はダンサーたちの軽快な足音が聞こえなくなると同時にLINE無料通話をかける。そして彼女が出るまでのわずかな間に、200件近く送信されているメッセージをひたすら頭に叩き込んだ。『既読』というカンニング殺しの機能により、“既に見ているはずなのに電話を寄越さないとは何事か”という不慮の事故を避けるためである。ここまでで3秒ほどであり、到底追える分量ではない。
「……何?」第一声は必ずコレである。こちらから要件が無ければ射殺すると言わんばかりの鋭い疑問形が私の鼓膜に刺さるが、私は怯まない。
「いや、○○が○○でさァ」この程度の打球ならNOルックで打ち返せる程に私の返答技術も高まっている。ペテンやハッタリで、彼女の矛先を薄皮一枚で躱していく。この間にも残り180程の“未見メッセージ”に目を通していく。ちなみに今回の要件は“妹にゲームで負けた”だった。
「ねェ、ちゃんと聞いてよ!」彼女の咆哮が電話を通じて街に反響する。全人類の中で一番聞いていると自負していた己の欺瞞を呪い、未だに認められないとは、“傾聴道“とはどれだけ険しい道なのだろうと目を瞑った。こうなってしまってはもう私は、スカッシュの壁である。
彼女の怒号が耳をつんざく中、全く同じ状況に陥っている隣の茶沢だけが心の救いだった。年齢も出身も趣味も異なる私たちは、『同タイプの女性と付き合っている』というただ一点のみで、互いに絶大なる信頼を置いていた。ちらりと見える茶沢の横顔は、携帯の画面に照らされ青白く光っていた。
家が近所であった私たちは、どちらから提案するともなく、『どちらかの家まで送る』という流れが出来ていた。“一人じゃない、君が希望(ゆめ)に変わってゆく”と信じ込みたかったのだろう。
この日は私の家の前まで付いてきてくれた。彼はこの後、暗闇の中に響く女の叫び声を頼りに帰路に就くと思うと“明日は俺が守るぞ”と私の中の闘志が燃える。
茶沢の背中を見送るとともに、戦いは激化していく。電話越しの彼女も『もう一人の僕』が居なくなったことを察知し、本腰を入れる。ここからはスピード勝負だ。
稽古着から着替えることもなく、ささっと晩飯を作る。本当は汗だくのジャージなんぞ一刻も早く脱ぎ去りたいところだが、戦場にそのような甘えは禁物である。向こうが必殺『何で私の嫌な事ばっかりするの?』の構えをしているときに焼きそばでも啜ろうものなら、それは文字通りの“必殺”になってしまうからだ。
電話で封じられた左腕を捨て置き、利き腕を残した私は流星の速さでマルちゃん焼そば麺とハムをシバき上げ、有無も言わさず平らげる。
“生まれた瞬間に刈り取られる命……正に諸行無常なり”と心中でつぶやく私を尻目に、彼女の話題は『どうせめんどくさいって思ってるんでしょ』に突入した。白い巨塔に匹敵する頻度の再放送である。こうなってしまえば最終回までの垂れ流しが確定してしまい、調子を合わせているだけで朝になってしまう。
ちなみに『調子を合わせる』というのは一見して軽薄な印象を醸し出しているが、やってる本人としては死に物狂いであり、一挙手一投足を常に見張られながら、時に絶望、時に涙し、それでもなるべく相手に傷が付かないように、出来る限りの配慮を欠かさずに、最後には平和にこの戦争を終わらせなければならない。『たとえそれが自分に全く関係のない話だとしても』である。
気付けば大概、深夜から早朝に変わっている。戦争を吹っ掛けた張本人の体力の限界によって、休戦の狼煙が上がるのだ。
LINE無料電話というシステムに憤りを覚えているのは昨今、私だけであろう。平均して毎日6時間以上稼働させられ、灼熱を孕んだ我が携帯も、この不条理にダウン寸前である。
瞬速でシャワーを浴び、TVを付けると、フジテレビが明朗快活に朝を告げている。水商売のバイトでもない私が『これからおやすみになられる方』になるとは夢にも思わなかった。
そして私は8時ごろ、私はカトパンにではなく、電話が繋がりっぱなしの彼女に叩き起こされるのである。
これが大学二年時の私の生活である。窓を開けると桜が舞い、道行く小学生は『誰が誰と同じクラスになった』と心躍らせている中、私はダンスに身体をイジメられ、彼女に心のカツアゲをされていた。ここからこの生活は一ヶ月半休みなしで進み、満身創痍の私にいよいよダンスの本番が迫る。
そして本題はここからである。
本番前日、私は彼女と共に授業に向かっていた。『サボりの愉悦』をまだ知らなかった当時の私は、この地獄巡りをしながらも授業は欠かさずに受けていた。つまりこの時の私は、演劇、ダンス、彼女、そして学生という四足の草鞋を履き、這いつくばってあべこべに歩く珍獣であった。
当然のことながら私に授業の選択肢は無く、私の履修表はすべて彼女によるオーダーメイドだった。断っておくが、彼女に対する愛情が無かったわけではない。むしろ若輩ながらもかなり大切に想っていただろう。故に授業に対して不満は一切なければ、同じ時間を過ごせて幸福だとも思っていた。
こんな書き方をしているが、彼女は常時キリング・マシーンなどでは無く、共に過ごしているときの時間のうち3割程は笑顔で過ごしていた。
なので、この登校時間は、日々の戦いを一瞬でも忘れることのできる至福の一時であった……いつもならば。
彼女の様子がおかしい。いつもであればこの時間は、彼女の日々の愚痴や友達が居ない等の専門外の相談を受ける場面であったが、待ち合わせてから10分の間に、こちらの呼びかけに彼女は「あー」とか、「うー」とかしか返さない。神妙な面持ちの彼女はまさにカオナシのようであった。
彼女が千を探そうと暴れる前に、私は先手を打つべく何か怒っているのではないかと疑問を投げかける。
明らかに機嫌の悪い相手に対してこの手の愚問は悪手だとは思うが、そのような判断や、起爆させずに信管を無力化する術なぞ、当時の私は持ち合わせていなかった。
「ダンス辞めてよ」私の予想通り、彼女は怒っていた。それどころか、普段の戦争がレクリエーションだったとすら感じさせるほどの激昂っぷりであった。
彼女から直接発せられる言葉の徹甲弾は、爽やかな通学路をことごとく破壊し、近隣住民に『ここは戦場になった』ということをまざまざと知らしめていた。
銃弾をすり抜け、決死に集めた情報によると、どうやら男女で踊ることがこの上なく嫌であると言う事であった。
ダンスサークルの同期は、所謂『パレードダンサー』志望であり、今回の企画もそのような形で行う。そこには同期の、パレードに対する憧れそのものが詰まっており、その憧れの中には『姫と王子様が手を取り合い舞踏会に行く』的な要素も含まれていた。
さらに今回の企画は、大学キャンパスの大広場でゲリラ的にダンスを披露する、『フラッシュモブ』のようなものであり、私の王子様スタイルが大衆の面前に曝されるという二段構えが、どうしても承服しかねるという話である。
私の王子様スタイルなんぞ、良くて出来損ないのインド映画だろうと高を括っていたが、彼女はそれを『浮気』という驚きの解をはじき出し今日に至ったという。
事前に何度も説明しているはずだと返しても知らぬ存ぜぬで、挙句「アナタの為に納得したフリをしてあげた」と言うしまつ。こんな後出しじゃんけんがあっていいのだろうか。この女のイカサマを支配人に密告してやろうか!? 私の心は完全にディーラーだった。
いつもであれば早々に私が先に折れ、わがままな性格がなおさら愛しくさせたと自分自身を騙すのだが、この件は引けなかった。毎日4時間の熱い青春を過ごし抜いた私の心は、既に一端の陽キャであった。
あれだけ苦手だったダンスも、今では軽やかにボックスステップを踏み、後輩を捕まえては「リズムが合ってないんだよねェリズムが」などと息巻く程に熱中していた。
何よりも、自分の将来とやりたいことを重ね努力し、観客に喜んでもらおうと一生懸命準備していた同期。自分の劇団に向かう私たちよりも遥かに崇高なその姿勢に、私はリスペクトを抱いていたのだ。
幾つもの物語が重なったこの企画を、己の主観だけで否定し、自分の気持ちを落ち着けるために『浮気』の烙印を無理やり作ろうとする彼女に、私は反旗を翻した。
「そんなに信じられないなら、この関係は続かないと思う」そう言い放ち、私は授業へ向かった。今思えば、この選択が大きな間違いであった。
彼女は教室に現れなかった。言い過ぎたかもしれない……幾許かの後悔を噛みしめながら、私は自分史上最も真面目に授業に臨んだ。
90分間の授業で分かったことは、自分は生粋の現代人であると言う事だけだった。彼女からの連絡を恐れ携帯の電源を切った私は、暇と疲れに脳を侵食されていた。
今まで授業中と言えば、友達の写真に奇妙な加工を施し、グループLINEに投下するという、『クソコラ職人』と成る他に過ごし方を知らなかった私は、コラ職人の仕事道具を失い、只のクソと化していた。
更に連日続くダンスと戦争によってイジメ抜かれた身体はもはや誤魔化しが利かないほどに疲弊していた。
5月も中旬に差し掛かり、教授の授業が本格化していることを肌で理解しながらも、私は睡魔への降服を選んだ。ここまでで約10分。コレが大学二年の私の真面目であった。
80分の休息を経た私は、すっかり睡魔と打ち解け、今度俺んちでプレステやろうぜ! と、マブダチとも言える間柄になっていた。
音もなく出席カードを提出し、一度帰って仮眠を取ろうと自宅へ向かう。
今頃ダンサーたちは稽古場に早入りし、明日のための最終確認をしているだろうが、この一ヶ月の平均睡眠時間が3時間程度である私が今すべきことは、振り付けではなく体調のチェックだろう。
大丈夫! 稽古開始には間に合わせるぜ! と自分の中の陽キャの正当性を主張しながら自宅のドアを開けた。
ドアが開いたのだ。
仮眠とのランデヴーに想いを馳せていた私は、無意識的にドアノブを引いていた。そしてそれがロックに引っかかることなく、あまりにもスムーズに引けてしまったことに、遅れて気が付いた。
「……あれ? 鍵閉めたよな?」日頃から家を出る前は何度もドアノブをガチャガチャやり、ロックを確認した後も鍵の心配をする“鍵閉めたっけ症候群”に苛まれている私が、鍵を閉め忘れたなどあり得ない。
ポケットの鍵を確認すると、外出時に必ず入れている定期入れの中に、さも当たり前のように収まっている。つまり、私は鍵を『閉めた』のだ。
“泥棒かもしれない”。眠気眼の思考回路が一瞬で覚醒し、「えッ」だか「あッ」だかの情けない声を発すると、「おかえり」と聞き慣れた声が返ってきた。女の声だった。
私は泥棒の正体が物取りではないと瞬時に理解した。目線を靴のたまり場にやると、これまた見慣れた赤い靴が丁寧に並んでいる。リビングのドアの曇りガラスには、先程まで徹甲弾を撒き散らしていた女らしき人物が、背を向け座っているのが見える。彼女だ。
「……ただいま」意を決し話しかけると、「遅かったね」と、まるで日常のような返答が聞こえてきた。
奇妙の連続で私の頭はショートした。ただ本能的に、ドアの向こうで何かが行われていると感じ、会話を引き延ばしながらもリビングの前で立ちすくんでいた。
彼女は「どうしたの?」と私に笑いかける。こっちの台詞だったのだがツッコミを入れるゆとりはなかった。
だがその穏やかな声色からは害意は感じられず、“あァ、きっと鍵を閉め忘れたんだ”と、さっきまでの自分のアリバイをひっくり返し、今度はゆっくりとドアを開けた。
部屋には西日が差していた。ぺたんと座り太陽を見つめている彼女には後光が差しており、まるで菩薩のようだった。
他愛ない話を続けるか、或いは先程の喧嘩を詫びるかするべきであったが、気が動転している私は彼女に、「……鍵、開いてた?」と聞いてしまった。
一瞬の沈黙の後、彼女はゆっくりと振り向いた。ニコリと笑っていたようだが、私の眼には、両手に握られた包丁しか入らなかった。
私の全身を死の予感が包んだ。格闘系漫画愛好家の私は反射的に、相手の攻撃などを払う目的の『死に手』として左手を前に差し出した。
同時に利き腕の右手は何時でも閉められるよう、ドアノブをしっかり握り、その構えは非常口マークの白いアイツの様であった。
彼女がゆらりと立ち上がる。右手の包丁は、連日焼そば用のハムをシバき上げていた我が家のものであり、ロクに洗っていない甲斐あってか、西日が反射し妖刀の如く怪しい光を放っていた。
小さいころから妄想少年だった私の頭の中では、よく学校にテロリストが襲来し、当時好きだった女の子が人質に取られていた。当然私はスマート且つ合理的に犯人と交渉したり、隙を付いて武装解除したりするのである。
つまり脳内ではこの手の事件は頻繁に起きており、対策も万全であった。
そんな私の第一声は「ま、待て、話し合おう」だった。スマートのスの字も無かった。
「何を話し合うの?」という彼女の素朴な問いに、確かに話すことなど何もないと一瞬我に返った私には、確かな隙があったのだろう。
一瞬の出来事だった。
彼女の右手の妖刀が、その禍々しい邪気を孕んだが如く、揺らめいて見えた。そして気づいたときには、私の左手首に横一文字が赤く刻まれていた。
音も無く斬り裂かれた私は、痛みを覚えるまでに数秒かかり、その後に「ひェ」とまたもや情けない声が出た。ここまで声が遅れるのは私といっこく堂くらいなものだろう。
華の女子大学生から一瞬で人斬りになってしまった彼女は激しく動転し、今度は自らをその妖刀に捧げようとしていた。
ついさっき斬られたのも相まって、開き直った私の対応は我ながら迅速だった。妖刀と彼女の間に身体を入れ、その手を離させようとする。
だが彼女の握力は思いのほか強く、一向に手を放す気配が無い。本当に呪われてしまったのか、その力は衰えるどころか、私に押し勝つまでに至っていた。
私は彼女に手を放すよう説得を試みた。だが私も気が動転しているため、「それ洗ってないよ! 油いっぱい付いてるよ!」などと衛生面の指摘しか出来なく、合理的のゴの字も無かった。
だが内容とは裏腹に、彼女の力は抜けていった。それはあまりにも素っ頓狂だったからか、或いは本当に汚いと思ったのか、「それはイヤだァ!」と泣き叫んでいた。泣きたいのはこっちである。
妖刀を手放し、徐々に落ち着きを取り戻した彼女は、事の重大さに気づき、泣きながら謝り続けた。
精神的に不安定な状態だったとはいえ、危うく一刀に斬り伏せられるところ。平常であれば、恋人という点を加味しても落とし所に頭を悩ませる様な大事件である。
だが当時の私は、粗雑な出来とはいえ妄想通りに彼女を救い出せたことに妙な達成感を抱き、あっさりと許していたのだ。
それどころか、全ては妖刀のせいだと本気で思い込み、「形はどうであれ、君がどれだけ俺を想ってくれているかわかったよ!」と謎の納得をしていた。
果ては理性を取り戻した彼女と共に、汚ッたない包丁を『封』と刻んだ段ボールに入れ、ゴミ捨て場に葬るという珍業まで成した。
気付けば日は落ち、稽古開始時間はとっくに過ぎていた。
私は彼女に今一度ダンス公演の説明をし、出演する許諾を得た。誤解が解けた彼女は「最初から言ってよね」と言っていた。
言われなくとも始めからそう伝えていたのだが、既に思考停止している私は「ごめんね!」とカラ返事をしていた。
『家の鍵どうやって開けたの問題』なんぞ、もう聞く気力が無かった。
彼女を駅まで送り届けたその足で、隣町の稽古場へ走る。幸い傷自体は薄皮を擦る程度に浅く、大した痛みも無かった。ウチの包丁がなまくらで良かったし、彼女が鬼殺隊じゃなくて本当に良かった。
だが彼女と包丁を取り合っている間に、どうやら事故的に『2撃目』が入れられていたようで、私の左腕にはさらにもう一本、手首の筋に沿う形で赤いラインが入っていた。
これにより私の手首には、色白の肌に赤十字の、『逆ヘルプマーク』が刻まれてしまった。
神妙な面持ちで稽古場の扉を開けると、そこもまた異様な空間にデザインされていた。何やら困り顔の陽キャたちが、我が盟友、茶沢を囲んでいる。
茶沢は両手を地に着け何やら交渉をしているようで、相対するパレード志望の女が深く考え込んでいる。おかげで私の遅刻は大した話題にもならずに済んだのだが……
茶沢の話を要約すると、「彼女が怖いから男女ペアは辞めさせてくれ」との事。はて、どこかで聞いた話である。
本番前日の急な出番変更など、企画側からしてみたらいい迷惑であり、「今更変更は出来ない」と突っぱねることも出来たはずだが、痣だらけの茶沢の顔がその判断を曇らせていた。
聞けば、茶沢の王子様スタイルが許せない茶沢の彼女が、革靴のかかと部分で顔面を30発近く殴打したようだ。隣の芝も真っ赤とは、この世は“蟹工船”より残酷である。
血豆やら青タンやらで、ルービックキューブと化してしまった茶沢の眼は真剣そのものであり、窮鼠猫を噛むと言わんばかりの迫力を醸していた。そして後の同期の話によると、私も同じ眼をしていたようだ。
気付けば私は茶沢の隣で、同様に手を付いていた。言葉を交わしたわけではないが、阿吽の呼吸で同時に頭を下げた私と茶沢は、強い気持ち・強い愛によって心をギュッとつないでいた。
勿論企画自体から降りたいわけでは断じてない。ダンスをしたいのは我々である。
だが、たかがダンスの配役一つで失われる命もあると言う事を、皆には知ってほしかったのだ。
そしてその想いが功を成し、本番当日は『私と茶沢で組む』こととなった。
最終稽古の残りの時間は、『私たちの傷をどの様に隠すか』に充てられ、皆でなんとかしようという、本家陽キャパワーを目の当たりにすることになった。
彼ら彼女らを、“どうせバーベキューとクラブしか能のない頭の軽さだけが取り柄の痴れ者”と内心蔑んでいた自分を恥じ、明日だけはこのダンス公演に、己の命を懸けて挑もうと固く決意した……
翌日、私は寝坊した。
言い訳をさせてもらえば、昨日仮眠を取ろうとした時間で“命のやり取り”をした私の活力は枯渇をとうに超えていたのだ。
本来であれば私は早入りし、件の十字傷を、同期の女たちのファンデやらコンシーラーやらで消し去る手筈であったが、私が起きた時間は、走ってギリギリ間に合うくらいの絶妙なものであった。
このままではキラキラパレードに流浪人が紛れ込んでしまうと焦った私は、家の靴下と同化していたリストバンドを左手にはめ、現場へ駆けた。
本番をトバすという大惨事は何とか免れた私だったが、相方の茶沢の姿が無い。
正確に言えば、顔面をトイレットペーパーでぐるぐる巻きにされた謎の男が、茶沢の声で喋っていた。
どうやら茶沢の痣は一日置いたことにより、エグ味が増してしまい、もはや化粧ではどうしようも無いほどに仕上がってしまったようだ。
残酷にも本番時刻が迫る中、苦肉の策で生まれたのがこのダブルロール・ミイラスタイルであったという。
かくいう私も、衣装の事などとうに忘れており、テキトーに選んだTシャツにリストバンドという、夏真っ盛りの風貌である。
さらにこのリストバンドは読売新聞の付録の物であり、黒にオレンジ色の刺繍で、高橋由伸の背番号『24』が刻まれた、ジャイアンツ仕様の一品であった。
かくして、四月から必死に準備したキラキラパレードの本番に、『ミイラ男とジャイアンツファン』という狂気のコンビが爆誕したのであった。
本番自体は必死でロクに憶えていないが、私たちは誰よりも可愛かったと自負している。情けを乞うてまで繋いだ命は、さぞ煌めいていたことであろう。
唯一印象に残っていることと言えば、私のリストバンドが否応なく目立ち、観客から「よッ! 24番!」と暖かい応援をもらい、ボディビルコンテストみたいだなァと思ったことくらいである。
ダンスの評判は概ね好評で、前日の一大事件からの逆転劇、という雰囲気も相まって、私たちのパレードは大団円を迎えた。
「また一緒にやろうね!」と涙ぐむ面々。コレが今生の別れであるかのように各々は日常へ戻る。公演というのもまた、諸行無常なのだ。
濃密な一ヶ月半を過ごした私。この子の公演がもたらしてくれたものは、十字の傷と“やっぱりダンスが嫌い”という確固たる意志だった。
ちなみに、この日の夜、「茶沢くんが羨ましい」という理由でまたもや命のやり取りをすることになるのだが、それはまた別の話である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
